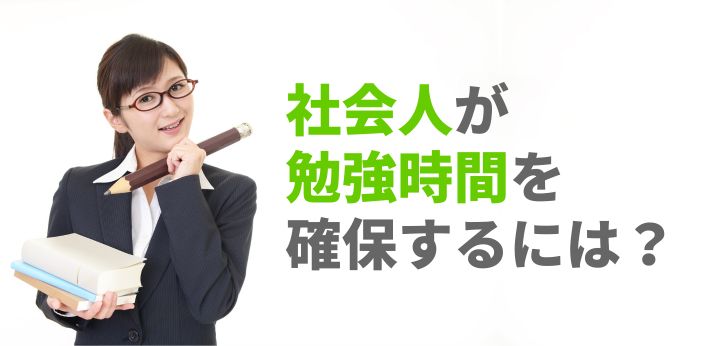高卒で弁護士になるには?試験の種類や合格率・年収を詳しく解説高卒で弁護士になるには?試験の種類や合格率・年収を詳しく解説
更新日
公開日
予備試験は学歴に関係なく受験できるものの、合格率はおよそ3.57%で難易度は高い
「高卒から弁護士になれるの?」「どうやって弁護士を目指せばいいのか分からない」と悩んでいる方もいるでしょう。高卒から弁護士を目指すことは可能です。弁護士を目指すには「法科大学院ルート」と「予備試験ルート」があります。予備試験ルートは学歴を問わず受験できるものの、合格率はおよそ3.57%と低く、高卒で司法試験に最終合格する人の割合は全体のわずか0.05%にとどまることも理解しておく必要があります。
このコラムでは、高卒から弁護士を目指す方法や試験の合格率、仕事内容を解説します。弁護士を目指す高卒の方はぜひ参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
高卒で弁護士になれる?
高卒で弁護士になることは可能です。ただし、弁護士になるためには司法試験に合格する必要があります。高卒で弁護士になるための主なルートは、法科大学院に入学して目指すか、予備試験に合格して目指すかの2つです。以下で弁護士を目指す方法について解説しています。
法科大学院に入学して目指す方法
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
高卒から法科大学院ルートで弁護士を目指す場合、まず大学の学部を卒業する必要があります。法科大学院は大学院であるため、学部卒業が入学の前提条件となるからです。学部は法学部でなくても構いませんが、法学部で基礎知識を身につけておくと法科大学院での学習がスムーズになるでしょう。
大学入学にあたっては、一般入試のほか、AO入試や推薦入試など、さまざまな入試制度を活用できます。社会人の場合は、働きながら通信制大学や夜間大学で学士号を取得する方法も選択肢の1つです。法科大学院には「未修者コース」と「既修者コース」があり、法律の学習経験がない方は未修者コースからスタートします。
なお、大学や法科大学院に掛かる費用は決して安くありません。たとえば、国立大学の法科大学院でも年間約80万円程度、私立大学では年間100万円以上掛かることも一般的です。しかし、奨学金制度や授業料免除制度なども存在するため、経済的な理由で諦める前に、このような支援制度について調べてみることをおすすめします。
予備試験に合格して目指す方法
高卒から弁護士を目指すもう一つのルートとして、予備試験に合格する方法があります。予備試験とは、法科大学院を経由せずに司法試験の受験資格を得るための試験で、年齢や学歴の制限がありません。
予備試験には「短答式、論文式、口述試験」の3つがあります。試験の難易度は高く「憲法、民法、刑法、行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法」などの科目が出題されるため、深い法律の知識が必要です。
予備試験に合格すれば、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格を得られます。そのため、法科大学院ルートで掛かるぶんの学費を節約でき、時間的にも短縮できる可能性があるでしょう。社会人が働きながら弁護士を目指す場合も、予備試験ルートが現実的な選択肢といえます。
独学で合格を目指す方もいますが、法律の学習経験がない場合は、予備校の講座などを活用して体系的に学ぶことも1つの方法です。法律の学習は決して簡単ではありませんが、粘り強く取り組めば、努力次第で高卒から弁護士になる夢を叶えられるでしょう。
弁護士になるにはどんなに早くても3年以上は掛かる
高卒から弁護士を目指す場合、どのルートを選んでも、弁護士になるまでに一定の期間が必要になります。たとえば、法科大学院に進む場合は、大学で4年間、法科大学院で2年または3年間学ぶことになるでしょう。
予備試験ルートを選択した場合、最短で司法試験の受験資格を得られますが、それでも試験対策に要する期間や、司法試験合格後の司法修習期間を考慮すると、一般的には3年以上の期間を要すると考えられます。弁護士になるには、法律の専門知識を習得し、実務に必要な能力を身につけなければなりません。自分に合ったルートを選択し、合格に向けて着実にステップを踏んでいくことが大切です。
ハタラクティブキャリアアドバイザー
後藤祐介からのアドバイス
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
高卒で弁護士になった人の割合や年収
高卒から弁護士を目指すことは可能で、実際に高卒から弁護士になった人も存在します。しかし、その割合は全体としてはかなり少数なのが実情です。高卒で予備試験を経由して司法試験を受験する場合、法律の深い専門知識を独学で習得する必要があるため、難易度は高いといえるでしょう。
ここでは、高卒で弁護士になった人の割合や年収について詳しく解説します。弁護士を目指そうと考えている方は、参考としてご覧ください。
高卒の司法試験合格率
| 試験の種類 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率
(四捨五入) |
|---|
| 短答式試験 | 12,569人 | 2,747人 | 21.86% |
|---|
| 論文式試験 | 2,647人 | 462人 | 17.45% |
|---|
| 口述試験 | 461人 | 449人 | 97.4% |
|---|
| 予備試験全体 | 12,569人 | 449人 | 3.57% |
|---|
| 司法試験 | 3779人
(予備試験合格者は475人、うち高卒2人を含む) | 1592人
(予備試験合格者は441人、うち高卒2人を含む) | 42.13%
(高卒の割合は0.05%) |
|---|
表のとおり、予備試験の最終合格率はおよそ3.57%で、非常に難易度が高いと分かります。予備試験合格後に司法試験を受験した人数は、5年以内に合格した人を含めて475人で、そのうち高卒者は2人でした。司法試験の最終合格率はおよそ42.13%ですが、全体でみると高卒で合格した人の割合は0.05%になっています。
高卒で予備試験ルートから弁護士を目指す場合、まずは予備試験に合格しなければなりません。合格率がおよそ3.57%と低いため、予備試験を突破するには、基礎的な法律知識から効率的に学習を進める必要があります。合格後も司法試験があるので、弁護士試験に合格する難易度は高いといえるでしょう。
高卒弁護士の年収
高卒弁護士の年収は、学歴ではなく実績や経験、専門分野、勤務形態などによって大きく変わります。一般的に弁護士の収入は、経験年数や実績に応じて上昇する傾向にあり、学歴が理由で年収に差が出ることは基本的にありません。
| 弁護士になった年数 | 平成25年分の年収 | 平成26年分の年収 | 平成27年分の年収 |
|---|
| 1年目 | 621万円 | 577万円 | 568万円 |
|---|
| 2年目 | 851万円 | 786万円 | 762万円 |
|---|
| 3年目 | 1,055万円 | 1,011万円 | 904万円 |
|---|
表のとおり、弁護士1年目の平均年収は600万円前後でした。また、1年目以降はどの年においても年収が上がっていると分かります。弁護士としての実力と実績を積み重ねることで、さらなる収入アップを目指せるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
弁護士の仕事内容や活躍場所
弁護士は法律の専門家として、さまざまな法律問題の解決をサポートする役割を担っています。依頼者の権利を守り、法的トラブルから解決までを導くプロフェッショナルです。高卒から弁護士を目指す場合、まずはどのような仕事をするのか、どこで活躍できるのかを知ることが第一歩となるでしょう。
ここでは、厚生労働省の職業情報提供サイト 「job tag」を参考に、弁護士の主な仕事内容や活動場所について解説します。
主な仕事内容
弁護士の仕事内容は多岐にわたりますが、大きく分けて「民事事件」と「刑事事件」の二つが挙げられます。
民事事件における弁護士の役割は、個人や企業間のトラブルを解決に導くことです。たとえば、金銭の貸し借りに関する問題や不動産の賃貸借トラブル、交通事故の示談交渉、離婚・相続といった家族間の問題などが含まれます。弁護士は依頼人の代理人として、交渉や調停、訴訟を通じて、法的な観点から最適な解決策を追求していくのが仕事です。
一方、刑事事件では、犯罪の容疑をかけられた人の弁護を担当します。被疑者・被告人の権利を守り、公正な裁判が受けられるよう尽力するのが弁護士の役目。具体的には、警察の取り調べへの立ち会いや勾留の阻止、保釈請求、公判での弁護活動などがあります。
このほかにも、企業法務として契約書の作成やリーガルチェックを行ったり、行政事件で行政処分に対する不服申し立てをサポートしたりすることも。弁護士は、法律の専門家として、困っている人々を法的に支援し、社会の公正を守る重要な役割を担っています。
主な活躍の場
弁護士の活躍の場は、従来の法律事務所だけでなく、さまざまな領域に広がっています。それぞれの場所によって求められる能力や専門性が異なるため、自分の強みや志向に合わせた進路選択が可能です。
最も一般的なのは法律事務所です。大きく分けると、総合法律事務所と特定の分野を専門にした事務所があります。総合法律事務所では幅広い法律分野を取り扱い経験を積めるのに対し、特定の分野を専門にした事務所では、知的財産権や労働問題などに特化したサービスを提供しているのが特徴です。
ほかには、国や地方公共団体の公務員弁護士として行政機関の法務部門で働いたり、企業内弁護士として活躍したりする選択肢もあります。弁護士としてのキャリアをスタートする際には、どのような分野で経験を積みたいかを考えて事務所を選ぶことが重要でしょう。
高卒で弁護士を目指すメリット
高卒から弁護士を目指すことには、「年収が平均より高い」「予備試験ルートの場合は学費が発生しない」といったメリットがあります。高卒から弁護士になる道は決して容易ではないものの、成功した際の報酬は大きいといえるでしょう。以下では、高卒で弁護士を目指す主なメリットについて紹介します。
年収が高卒の平均を上回る
高卒で弁護士を目指すメリットの1つ目は、年収が高卒者の平均を大きく上回る可能性があることです。一般的に、高卒で就職した場合の平均年収は、大卒者や大学院卒者と比較して低い傾向にあります。
高卒で合格した実績ができる
高卒で弁護士を目指すメリットの2つ目は、高卒で合格した実績ができることです。司法試験は難関とされる国家試験の一つ。学歴に関わらず誰もが受験できる予備試験ルートがあるとはいえ、合格率は非常に低く、難易度は高いといえます。
そのような難関を、大学を経ずに突破した実績は、弁護士としてキャリアをスタートさせたあとも、能力と努力を証明する強力なアピールポイントになるでしょう。
高卒で予備試験と司法試験に合格するためには、徹底した自己管理能力や学習能力、目標に向かって突き進む強い精神力が必要です。学歴ではなく、実力と努力で弁護士になったバックグラウンドは、中小企業経営者や自営業者など、自分の力で道を切り開いてきたクライアントからの共感を得やすいでしょう。また、学歴に関係なく自らの力で道を切り拓いた経験は、弁護士として働くうえで直面する困難を乗り越える自信にもつながります。
学費の負担が発生しない
高卒で弁護士を目指すメリットの3つ目は、学費の負担が発生しないことです。予備試験ルートで弁護士を目指す場合、大学や法科大学院に通うルートと比較して、学費の負担が大幅に軽減されるでしょう。
大学によるものの、都内の私立大学に4年間通った場合、およそ400万円から650万円程度の学費が必要です。さらに、法科大学院では「既修者コース」が2年間でおよそ200万円から400万円、「未修者コース」は3年間でおよそ370万円から600万円の学費が掛かります。合計すると数百万円から1,000万円以上の学費が必要になるケースもあり、経済的な負担は大きいといえるでしょう。
一方、予備試験ルートでは大学や法科大学院に掛かる学費の負担はありません。予備校に通う場合、およそ80万円から150万円程度の費用が発生するものの、参考書や問題集、受験料などとあわせても、数十万円から数百万円程度に抑えることが可能です。予備校に通わず、独学で予備試験に挑戦する場合は、さらに費用を抑えられるでしょう。
高卒で弁護士を目指すデメリット
高卒から弁護士を目指せるものの、なるためにはいくつかの壁が存在します。予備試験に合格すれば、大学や法科大学院を卒業していなくても司法試験の受験資格を得られますが、決して簡単な道のりではありません。司法試験では法律の知識だけでなく、論理的思考力や文章力など総合的な能力が試されるので、高卒者にとってはハードルが高いと感じる側面もあるでしょう。
ここでは、高卒で弁護士を目指す際に直面する主なデメリットについて詳しく解説します。
高卒で司法試験に合格している人の割合は少ない
高卒で弁護士を目指すにあたって認識しておくべきデメリットの1つに、司法試験に合格している高卒者の割合が少ない現状があります。コラム内の「高卒の司法試験合格率」でお伝えしたように、予備試験全体の合格率はおよそ3.57%で、司法試験に合格した高卒の割合は全体の0.05%でした。これは、ほとんどの合格者が法科大学院を卒業した人たちであるとを意味します。
高卒で弁護士を目指す場合は、この実情を理解して、より一層の計画性と強い意志をもって学習に取り組む必要があるでしょう。
弁護士になるまでの道のりが厳しい
高卒から弁護士を目指す道のりは、決して簡単ではないと認識しておく必要があります。大学や法科大学院を経由する一般的なルートと異なり、予備試験ルートを選択する高卒者は、自力で法律の専門知識をゼロから体系的に習得しなければなりません。
予備試験自体が難関であり、合格するには法律の広範な知識と高度な論文作成能力が求められます。この試験に合格した後も、さらに司法試験を受験しなければなりません。学習期間は長期にわたり、数年間を学習に費やすことになります。人によって異なるものの、予備試験ルートの場合、一般的には合格までに 3000時間から10000時間程度掛かるといわれているようです。多くの時間と労力を勉強に集中させる必要があり、精神的にも肉体的にも負担が大きくなるでしょう。
経済的な面では、学費は発生しなくとも、生活費や教材費の捻出、長期間にわたる学習で収入がないことへの対策も考える必要があります。このような厳しい道のりを乗り越えるためには、強い覚悟と継続的な努力が欠かせません。
学習のモチベーションを保つのが難しい
高卒で弁護士を目指す際に直面するデメリットの1つとして、学習のモチベーションを維持することの難しさが挙げられます。大学や法科大学院に進学する場合、周囲に同じ目標をもつ仲間がいたり、講義や定期的な試験があったりするため、学習を継続しやすい環境が整っているのが特徴です。しかし、予備試験ルートで高卒から弁護士を目指す場合、独学を選ぶ人も多く、学習が孤独になりがちといえます。
長期にわたる法律学習は、ときに挫折しそうになるほど地道で困難な道のりです。周りに相談できる人がおらず、学習の進捗が思わしくないと、モチベーションが低下し学習が停滞してしまうことも。そのため、自分で学習計画を立て、それを実行し続ける強い意志と自己管理能力が求められます。予備校の活用や学習仲間を見つけるなど、モチベーションを維持するための工夫も重要になるでしょう。
高卒から弁護士になる方法
高卒から弁護士になるには、司法試験に合格するだけでなく、法曹資格を取得して正式に弁護士として働くための登録が必要です。厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」を参考に、弁護士になるまでの流れを以下にまとめました。
高卒から弁護士になる方法と流れ
- 法科大学院修了または予備試験に合格する
- 司法試験に合格する
- 司法修習を修了して法曹資格を取得する
- 日弁連の弁護士登録に関する審査を受ける
- 名簿に登録されると弁護士として活動できる
司法修習とは、司法試験に合格した人が、法曹(弁護士や裁判官、検察官)になるために必要な実務研修のことです。司法試験に合格しただけでは、法曹資格は得られません。司法修習を修了し、「司法修習生考試」に合格すると法曹としての資格が与えられます。その後、日弁連に弁護士登録をすれば、弁護士として活動できるようになるのです。
【まとめ】難易度は高いが高卒から弁護士は目指せる
高卒で弁護士を目指す道のりは簡単ではないものの、目指すことは十分に可能です。大学や法科大学院を経由するルートと予備試験のルートがあるため、それぞれの特徴を把握しつつ、自分に合った方法を選択して合格を目指しましょう。
高卒で弁護士試験に合格すれば大きな実績となり、その後のキャリアにおいて有利に働く可能性があります。学習のモチベーション維持や長期にわたる努力は必要ですが、強い意志と計画性をもって取り組めれば、弁護士になる夢の実現に近づけるでしょう。
ハタラクティブは、高卒を含む若年層の就活に特化した就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングして、あなたの適性に合った求人情報を厳選してご紹介します。応募書類の添削や面接対策など、就活に向けた選考対策も充実しているので、不安を解消しながらスムーズに取り組めるでしょう。ハタラクティブのサービスはすべて無料でご利用いただけます。就職や転職に悩みを抱えている方は、お気軽にお問い合わせください。
高卒で弁護士を目指す場合によくあるQ&A
ここでは、高卒で弁護士を目指す場合によくある疑問をQ&A形式で回答しています。弁護士になりたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
法務省の情報では、令和6年に司法試験に合格した高卒の方は2人いると発表されました。この年の司法試験全体の合格者は1592人で、高卒者の割合は0.05%と低く、難易度の高さがうかがえます。しかし、実際に高卒で試験に合格している方がいるため、徹底した自己管理をしつつ覚悟をもって学習を継続できれば、高卒から弁護士を目指すことは十分に可能です。コラム内の「高卒の司法試験合格率」も参考としてご覧ください。
社会人から弁護士を目指すことは、十分に可能です。社会人から目指す場合、主に二つのルートがあります。一つは、予備試験ルートです。この試験は学歴を問わず受験できるため、働きながら学習を進め、合格すれば司法試験の受験資格が得られます。もう一つは、法科大学院ルートです。大卒ではない場合、大学に入学してから法科大学院に進むため、時間と費用が掛かるでしょう。
どちらのルートも学習期間は長期にわたるため、強い意志と計画的な時間管理が求められます。自分に合った方法を選択し、弁護士を目指すことが大切です。
高卒で弁護士に就職したいのでなり方を教えてください
高卒から弁護士になるには、「予備試験ルート」を選ぶのが一般的な方法です。弁護士になるには、まず予備試験に合格し、そのあとに司法試験に合格する必要があります。予備試験と司法試験のどちらも難易度が高いので、学習に多くの時間を費やさなければなりません。
司法試験の合格後は、司法修習を受け、司法修習生考試に合格して法曹資格を取得したうえで弁護士登録をする流れになります。コラム内の「高卒から弁護士になる方法」でも解説しているので、参考にしてみてください。
就職・転職エージェントのハタラクティブでは、キャリアアドバイザーがあなたの悩みや希望に寄り添い、就活をサポートしています。就活に悩みがある方は、ぜひご相談ください。