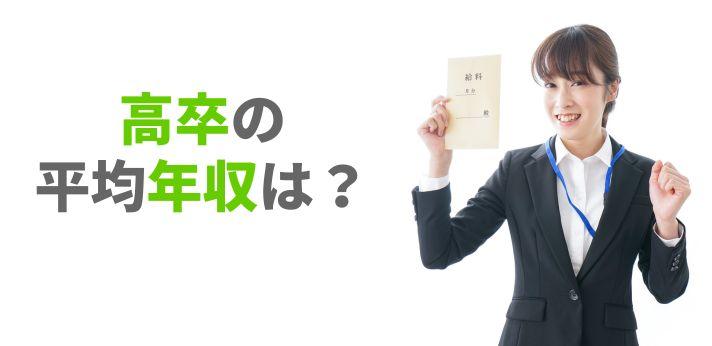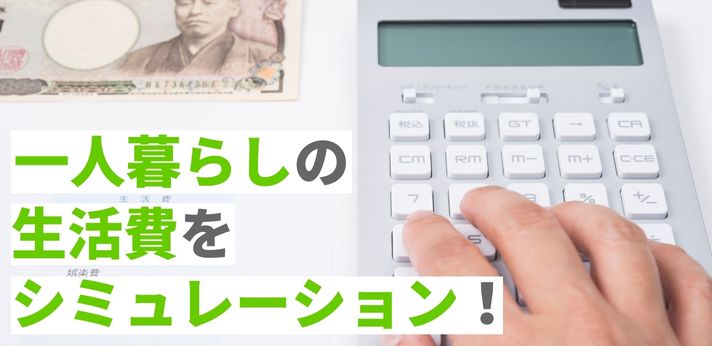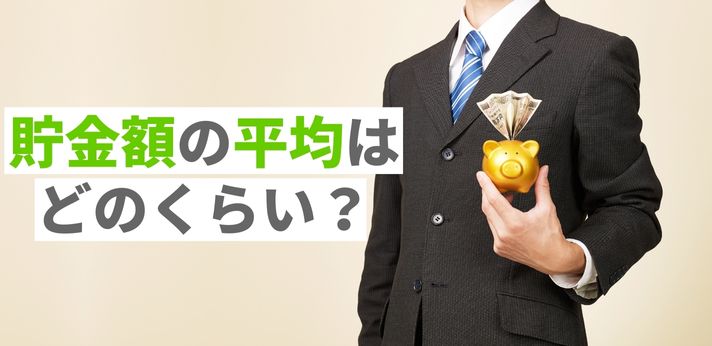高卒で一人暮らしをするのはきつい?実現するために必要な費用や流れとは高卒で一人暮らしをするのはきつい?実現するために必要な費用や流れとは
高卒で一人暮らしをするなら、就職して生活リズムや収入が安定してから始めよう
「高卒の給料で一人暮らしをするのは難しい?」「どれくらいの貯金があれば安心なのか」と生活に必要な収入に対してお悩みの方もいるでしょう。高卒者も引越しや生活に必要なお金を貯蓄できていれば、一人暮らしをスムーズに始められます。
このコラムでは、高卒で一人暮らしをするのに必要な費用や準備の流れを解説。新生活を始めるうえでのポイントも紹介するので、高卒で一人暮らしができるか不安な方は、ご一読ください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
高卒者はいつから一人暮らしができる?
引越しや生活に必要な費用が貯まったら、高卒者も一人暮らしを始められます。また、就職と同時に一人暮らしを始めるよりは、生活リズムや収入が安定してからのほうが精神的な負担は抑えられるでしょう。
ここでは、高卒者が一人暮らしを始めるのに適したタイミングを紹介します。「一人暮らしを始めるならいつのタイミングを選ぶべきか」と悩んでいる高卒の方は、参考にしてみてください。
引越し費用と1ヶ月分の生活費が貯まったとき
家事に不慣れな状態だと生活費が増えやすいため、家計管理に影響しないように知識やスキルを習得しておきましょう。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
引越し費用と1ヶ月分の生活費が貯まってから一人暮らしを始めると、金銭的な負担を抑えられます。もし、必要な費用をまかなう貯金がないと、毎月の給料から捻出することになり、生活を圧迫してしまうおそれがあるからです。
一人暮らしを始めてからも、急な出費でお金が必要になる場合も考えられるため、計画的に貯金しておくことをおすすめします。
就職後の生活リズムや収入が安定したとき
就職後、生活リズムや収入が安定してからのタイミングも一人暮らしを始めるのに適しています。たとえば、社会人未経験の状態から正社員として働き始めた場合、労働による心身の疲労を感じやすいでしょう。その状況で、一人暮らしでの家事を両立させるのは負担がかかります。
一方、正社員としての労働に慣れた状態であれば、一人暮らしに伴う引越しや生活に関する準備にも余裕をもって対応できるでしょう。毎月の収入が安定してからのほうが、収支のバランスを考えやすいので、就職して状況が落ち着いてからのタイミングで一人暮らしを始めるのをおすすめします。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
高卒で一人暮らしをするのが難しいのはなぜか
高卒者の場合、大卒者よりも貯金をする余裕が生まれにくく、一人暮らしを始めるのにハードルを感じやすいでしょう。特に、一人暮らしを始めるのに賃貸契約を結ぶ際、フリーターは有期雇用で収入が突然途絶えるおそれもあることから、支払い能力を認められずに審査に通りにくい場合があります。
以下に、高卒で一人暮らしをするのが難しい理由をまとめました。どのような点に気をつけるべきかを知ったうえで、一人暮らしを始めるようにしましょう。
貯金をする余裕が生まれにくいため
高卒は大卒に比べて収入が低い傾向があるため、そのぶん貯金をする余裕が生まれにくく、一人暮らしを実現するのが難しい場合があります。すべての企業が学歴を給与を設定する基準としているわけではありませんが、収入の一部を貯金にまわせる余裕のある仕事でなければ、一人暮らしで生活するのに金銭的な負担を感じやすいでしょう。
高卒者の平均賃金
一人暮らしを始めるうえでは、高卒者と大卒者の平均賃金を比較し、学歴により貯蓄にまわせる金額がどれくらい異なるのかを確認しておくことが大切です。ここでは、一人暮らしを始める年齢を20代前半と仮定して、高卒・大卒の平均賃金や貯蓄にまわせる金額を比較して紹介します。
| 学歴 | 平均賃金 | 平均消費支出額 | 貯蓄にまわせる金額
(平均賃金-平均消費支出額) |
|---|
| 高卒 | 24万5,900円 | 16万6,480円 | 7万9,420円 |
|---|
| 大卒 | 27万2,200円 | 16万6,480円 | 10万5,720円 |
|---|
※記載している平均賃金は20~24歳の常用労働者(正社員・非正規雇用社員)の金額です
※平均消費支出額は単身世帯34歳以下の金額です
一般的な消費支出額をもとに、20~24歳の貯蓄にまわせる金額の目安を計算すると、高卒・大卒では、2万6,300円の差があることがわかりました。
一人暮らしで金銭的な負担を軽減するためにも、より多くの収入を得られる仕事を選ぶほうが望ましいでしょう。
賃貸契約の審査が通りにくい場合があるため
賃貸契約の審査が通りにくい場合があることも、高卒者が一人暮らしを始めるのが難しい理由の一つです。18歳以上である高卒者は、親の同意がなくても賃貸契約を結ぶことが可能ですが、無職やフリーターの状態だと家賃の支払い能力を認められにくい場合があります。
賃貸契約の審査に通るためには、正社員として働いて支払い能力を証明するか、あるいは収入が安定している家族に連帯保証人もしくは契約者になってもらうのが望ましいでしょう。
社員寮のある企業へ就職する方法もある
高卒で一人暮らしを検討している場合は、社員寮のある企業へ就職するのも方法の一つです。社員寮の場合、一般的な賃貸物件よりも家賃相場が安い傾向があるため、金銭面の負担を軽減できるでしょう。
ただし、社員寮の場合、会社が指定する場所に住まなければならないため、自分で住む家を自由に選びたい方には向いていません。
希望のライフスタイルに合わせて、社員寮のある企業へ就職するか検討してみてください。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
高卒での一人暮らしにかかる費用とは
一人暮らしをする際には、物件契約時の初期費用や引越し費用、生活費用などのお金が必要です。以下に、高卒での一人暮らしをするのにかかる費用をまとめました。「一人暮らしをするにはどれくらいお金がかかるのか」と疑問に感じる方は、ご一読ください。
物件を契約するための初期費用
家賃や初期費用は物件により異なりますが、賃貸情報に関するWebサイトや不動産会社の見積もり内容を通して確認できるでしょう。一人暮らしのための貯蓄計画を立てるためにも、おおよその初期費用の金額や内訳を把握しておくことが大切です。
| 項目 | 概要 | 金額の目安 |
|---|
| 敷金 | 退去時の原状回復費用などに充てられ、退去時に返還される費用 | 家賃1~2ヶ月分 |
|---|
| 礼金 | 管理人に支払う返還されない費用 | 家賃0~2ヶ月分 |
|---|
| 前家賃 | 入居する翌月分の家賃を事前に支払う費用 | 家賃1ヶ月分 |
|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う費用 | 家賃0.5~1ヶ月分 |
|---|
| 火災保険料 | 火災や災害に備える保険料 | 1.5万~2万円 |
|---|
| 保証料 | 家賃保証会社を利用する場合の費用 | 家賃0.5~1ヶ月分 |
|---|
| 鍵の交換費用 | 防犯のため鍵を交換する費用 | 1.5万~2.5万円 |
|---|
引越しをするための費用
一人暮らしを始める際には、引越しに関する費用もかかります。引越し業者を利用するかどうかで金額は大きく異なるので、以下でそれぞれにかかるおおよその金額を確認しておきましょう。
引越し業者を利用する場合
引越し業者を利用する場合にかかるお金は、荷物を運んでもらう距離や時期により異なります。引越し業者の種類や運んでもらう荷物の量によっても利用料金に違いがあるため、複数の業者へ見積もりを依頼して比較しましょう。
以下は、一人暮らしの場合で引越し業者を利用する場合の利用料金の目安です。
| 距離 | 通常期(5月~1月) | 繁忙期(2月~4月) |
|---|
近距離
(50km未満) | 3~6万円前後 | 4~8万円前後 |
|---|
中距離
(200km未満) | 4~8万円前後 | 6~10万円前後 |
|---|
遠距離
(200km以上) | 6~10万円以上 | 8~15万円以上 |
|---|
引越し業者の費用は、利用する地域によっても異なる場合があるでしょう。特に、都市部は地方に比べて引越しに対する需要があり、人件費も高くなる傾向があります。
引越しをする地域による料金の違いも考慮したうえで、おおよその金額をシミュレーションしてみてください。
2月~4月は引越し費用の相場が通常よりも高い
2月~4月は引越しの繁忙期にあたるため、費用相場が通常よりも高くなる傾向があるでしょう。特に3月下旬から4月上旬にかけては、進学や就職、転勤などによる引越しの需要が集中します。それにより、引越し業者の対応が追いつかなくなるため、通常期の1.5~2倍の料金まで高騰することもめずらしくありません。
希望の日程で予約が取りにくくなる可能性もあるため、繁忙期を避けて引越しを検討するのも一つの手です。
引越し業者を利用しない場合
引越し業者を利用せずに荷物を運ぶ方法もあります。レンタカーを借りたり、家族や友人に手伝ってもらったりすることで、業者に頼む分の費用を浮かせられるでしょう。
ただし、生活家電は破損を防ぐためにも、安全な運び方を調べておく必要があります。運搬に必要な梱包資材や段ボールなどを確認して、計画的に準備を進めましょう。
生活家電の購入費用
生活家電の購入費用も一人暮らしを始めるうえでは、確認しておくことが大切です。高卒での収入の範囲内でできる貯蓄計画を立てるうえでも参考になります。
以下は、一人暮らしをする際に購入が必要になる代表的な生活家電の金額の目安です。
| 洗濯機 | 3~7万円程度 |
|---|
| 冷蔵庫 | 3~8万円程度 |
|---|
| 電子レンジ | 1~3万円程度 |
|---|
| 炊飯器 | 0.5~2万円程度 |
|---|
| 掃除機 | 1~3万円程度 |
|---|
生活家電は、3月ごろに一人暮らし向けのキャンペーンを実施しているメーカーを見つけやすいでしょう。
また、物件によっては、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジ、エアコン、照明器具などの家具が備え付けられている場合があります。賃貸情報サイトで「家電付き」といった条件で検索することで見つけられるでしょう。
1ヶ月あたりの生活費
| 項目 | 概要 | 金額の平均 |
|---|
| 食費 | 食料品の購入費、外食費など | 4万2,954円 |
|---|
| 水道・光熱費 | 電気、ガス、水道の合計 | 8,759円 |
|---|
| 家具・家事用品 | 家具、寝具、家電、家事用消耗品など | 4,241円 |
|---|
| 被服及び履物 | 衣服、靴などの購入費 | 5,829円 |
|---|
| 保健医療 | 医療費、医薬品、健康保持用具など | 4,999円 |
|---|
| 通信費 | 携帯電話料金、インターネット回線費用など | 6,049円 |
|---|
| 交通費 | 通勤・通学費、ガソリン代、公共交通機関利用料 | 7,386円 |
|---|
| 教養娯楽 | 趣味、レジャーに関するものの購入費、書籍、スポーツ用品など | 2万2,230円 |
|---|
| その他の消費支出 | 理美容サービス、交際費などの上記の項目に当てはまらない支出額 | 2万9,704円 |
|---|
上記の消費支出はあくまで平均的な金額であるため、自身の生活費を見直して、何にどれくらいのお金がかかっているかを確認してみてください。
地域による平均消費支出額の違い
平均消費支出額は、住む地域によっても違いがあります。同資料による、地域ごとの平均消費支出額は、以下のとおりです。
| 地域 | 平均消費支出額 |
|---|
| 北海道・東北地方 | 19万3,194円 |
|---|
| 関東地方 | 17万9,539円 |
|---|
| 近畿地方 | 18万322円 |
|---|
| 北陸・東海地方 | 15万9,687円 |
|---|
| 中国・四国地方 | 14万6,171円 |
|---|
| 九州・沖縄地方 | 14万7,452円 |
|---|
上表のとおり、地域によって消費支出の金額に差があることがわかります。これは、その地域の物価や交通の利便性、気候による光熱費などが異なるためです。
一人暮らしを始めるにあたり、住む地域が変わる場合は生活費が大きく変動する可能性があることを念頭に置きましょう。事前に、引越し先の生活費をシミュレーションしておくことをおすすめします。
総務省統計局
家計調査(家計収支編) 調査結果
高卒で一人暮らしを始めるメリット・デメリット
一人暮らしの魅力には、自分のペースで家計管理スキルを磨きながら生活できる点は魅力ですが、仕事との両立や予期せぬトラブルが発生した際に、一人で対応しなければならない部分に負担を感じる場合もあるでしょう。
ここでは、高卒で一人暮らしを始めるメリット・デメリットをそれぞれ紹介します。一人暮らしを始めるかお悩みの方は、生活を始めたらどのようなことが起こり得るかを確認しておきましょう。
メリット
高卒で一人暮らしを始めるメリットは、以下のとおりです。
自分のペースで生活ができる
一人暮らしは自分のペースで生活ができる点が魅力といえます。自分の好きなタイミングで食事や入浴などを済ませられるため、自由に過ごしたいという方におすすめです。時間にしばられずにプライベートな時間を満喫できるでしょう。
家計管理スキルを習得できる
一人暮らしをすることで、家計管理スキルを習得できます。高卒者の方のなかには、「今まで家計管理は家族が行っていたため経験がない」という方もいるでしょう。
日々の家計管理を自分で行うことで、お金の流れを把握できるようになり、貯蓄の計画や将来設計を考えやすくなります。
デメリット
高卒で一人暮らしを始めるうえでは、デメリットも把握しておくことが大切です。
仕事と家事の両立に負担を感じる場合がある
高卒で一人暮らしをする際に、仕事と家事の両立に負担を感じる場合があります。一人暮らしの場合、仕事で疲れていたとしても、料理や洗濯、掃除などを自分で行わなければいけません。
特に、実家暮らしで今まで家事をした経験が浅いと、不慣れで時間がかかってしまうことがあるでしょう。
さらに、家計管理の経験が浅いと、思うように収支のバランスを保てず、ストレスが蓄積してしまうおそれがあります。
仕事と家事の両立に伴う負担を軽減するためにも、一人暮らしを始める前に練習をして経験を積んでおくことが大切です。
トラブルがあっても自分で解決する必要がある
一人暮らしの場合、基本的にはトラブルがあっても自分で解決する必要があります。一人暮らしをしていると、水回りや防犯、近隣住民の対応などで予期せぬトラブルが発生する可能性もあるためです。
家族や友人、管理人などに相談するのも手ですが、最初の対応は自分で行う必要があるでしょう。
高卒で社会経験が浅いと、トラブルの対応に対する不安を感じることもあります。トラブル対応の経験は、問題解決能力を磨けるチャンスです。いざというときに慌てずに対応できるよう、事前に、一人暮らしで起こりやすいトラブルの対応方法や連絡先を確認しておきましょう。
高卒で一人暮らしを始めるために必要なステップ
一人暮らしをする際には、物件選びから引越しをして生活を始めるまでに、どのような準備が必要かを把握しておくことが大切です。
ここでは、高卒で一人暮らしを始めるために必要なステップを解説します。「一人暮らしをしたいものの、何から始めたら良いかわからない」と感じる方は、ぜひご一読ください。
高卒で一人暮らしを始めるために必要なステップ
- 物件の内見をして引越し先を決める
- 賃貸契約を結ぶ
- 引越し準備をする
- 引越しに必要な役所やライフラインの手続きをする
- 引越し作業をする
- 一人暮らしを始める
1.物件の内見をして引越し先を決める
まずは、物件の内見をして引越し先を決める必要があります。事前に、物件と職場の距離感や周囲の環境、家賃額などに関して希望することをリストアップしておくと、スムーズに引越し先を決めやすくなるでしょう。
実際に複数の物件を内見して比べることで、より自分に合う引越し先を見つけられます。現地に向かうのが難しい場合には、オンラインツールを活用した内見を実施している不動産会社の物件を選ぶのも方法の一つです。
2.賃貸契約を結ぶ
希望に合う物件が見つかったら、賃貸契約を結びます。高卒者の場合、18歳以上であるため、不動産会社を通して賃貸契約を結ぶことが可能です。
契約内容を丁寧に確認し、初期費用や生活におけるルールの有無などを把握しておきましょう。
賃貸契約に必要なもの
- 本人確認書類
- 住民票
- 収入証明書
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明書
- 銀行通帳・銀行印
- 連帯保証人関連書類
収入を証明する書類は、源泉徴収票や給与明細書、納税証明書などがあります。
賃貸契約に必要なものは、事前に不動産会社から明示されるのが基本ですが、疑問点があれば早めに質問しておくようにしましょう。
3.引越し準備をする
賃貸契約を終えたら、引越し準備を進めます。引越し先に運ぶ荷物を梱包したり、不要な物を処分したり、計画的に進めるように、引越しまでにしなければならないことをリスト化しておくのがおすすめです。
引越し業者の利用の有無によっても準備が異なるので、早めに依頼をするか決めておきましょう。
引越し準備に必要なこと
一人暮らしの引越しでは、以下のような準備をしておく必要があります。
- 引越し業者の選定・予約
- 荷造りの準備
- 不用品の処分
- 転居先で使用する家具や家電の購入
- 転居先の家具の配置の確認
引越し業者を依頼しない場合は、上記の内容に加えて、家族や友人への協力の依頼も行わなければいけません。いつまでに何を終わらせるか、具体的に期限を決めて準備を進めると、計画的に進められるでしょう。
4.引越しに必要な役所やライフラインの手続きをする
引越しに必要な役所やライフラインの手続きも漏れがないように進める必要があります。
- 旧居・新居の電気、ガス、水道に関する手続き
- インターネット回線の契約・開通の手配
- 郵便物の転送届の提出
- 住民票の転出届の提出
- 国民健康保険・国民年金の住所変更
いずれの手続きも引越し当日までに行うことが基本です。転出届のように、引越しの約2週間前から手続きを行える場合もあるため、計画的に進めましょう。
5.引越し作業をする
当日になったら、引越し作業をします。引越し業者を利用する場合には、指示に従って進めましょう。自分で荷物を運ぶ場合は、家具や家電製品が破損しないよう注意が必要です。
荷物を運び出したら、旧居の掃除も忘れないようにしましょう。
6.一人暮らしを始める
引越しが完了すれば、一人暮らしの生活が始まります。住み始めるうえで必要な手続きを行うのを忘れないようにしましょう。
一人暮らしを始めたあとに必要な手続き
以下に、一人暮らしを始めたあとに必要な手続きの代表例をまとめました。
| 手続きの種類 | 手続きの概要 | 期限の目安 | 手続きの場所 | 必要なもの |
|---|
| 転出届・転入届 | 引越し先の地域の役所に住民登録を行う | 引越しから14日以内 | 引越し先の市区町村役所 | 転出証明書、本人確認書類、印鑑など |
|---|
| 印鑑登録の変更 | 引越し先の市区町村で印鑑登録を行う | 登録が必要な場合 | 引越し先の市区町村役所 | 登録する印鑑、本人確認書類など |
|---|
| 各種保険の住所変更 | 国民健康保険、生命保険、自動車保険などの住所変更を行う | 住所変更後速やかに | 各保険会社や役所 | 保険証、本人確認書類、新住所を証明するものなど |
|---|
| マイナンバーカードの住所変更 | マイナンバーカードに記載されている住所の変更を行う | 引越しから90日以内 | 引越し先の市区町村役所 | マイナンバーカードやパスワードなど |
|---|
自治体により、必要な手続きや提出書類が異なる場合があります。手続きの漏れがないよう、疑問点はその都度自治体の役所の窓口で相談するのが大切です。
高卒で一人暮らしを始めるためには
高卒で一人暮らしをスムーズに始めるためには、家事に関する知識やスキルを習得したり、必要なお金を貯金したりしておく必要があります。生活し始めてからの金銭面の不安を回避するためにも、収入を安定させておくことも重要です。
ここでは、高卒で一人暮らしを始めるために必要なポイントを紹介します。「一人暮らしを始めるうえで何を準備しておけば安心なのか」と気になる方は、参考にしてみてください。
家事に関する知識やスキルを習得しておく
一人暮らしを始めるまでに、家事に関する知識やスキルを習得しておくことがおすすめです。料理や洗濯、掃除などをスムーズにこなせるようになっていれば、家事に伴う負担も軽減できるでしょう。
以下のような、節約術に関する知識も習得できていれば、家計管理にも役立ちます。
一人暮らしに役立つ節約術
- なるべく自炊を心がける
- 食材や日用品をまとめ買いする
- 電気や水道の無駄遣いを避ける
一人暮らしにかかるお金を貯金する
一人暮らしにかかるお金を貯金しておくことも大切です。事前に引越しや生活にかかる費用を貯蓄できていると、暮らし始めてからの家計管理にも気持ちの余裕が生まれます。予期せぬ事情でお金が必要になることも考えられるため、一人暮らしにかかる費用はできる限り事前に貯蓄しておくほうが望ましいでしょう。
就職をして収入を安定させる
就職をして収入を安定させておくと、一人暮らしの支出管理の負担も減らせます。また、賃貸契約を結ぶうえでも、正社員として決まった収入を確保できていれば、支払い能力を認められて審査に通りやすくなるでしょう。
一人暮らしができる収入を得られる企業を選ぶ
高卒で正社員として働く企業を選ぶ際は、一人暮らしができる収入を得られるかどうかを確認することがポイントです。企業のなかには、学歴に関係なく個人のスキルや実力を評価し、給与を設定する場合もあります。スキルを磨いて成果を出すことで収入アップができれば、一人暮らしの家計管理にも金銭的な余裕が生まれるでしょう。
また、家賃補助制度を設けている企業を選べば、住まいに関する費用の負担を軽減できます。
企業により、暮らしをサポートする福利厚生があるかどうかは異なるため、一人暮らしにどれくらいのお金がかかるのかを計算したうえで、支出をまかなえる収入を得られるかどうかを基準に求人選びをしてみてください。
自分に合う仕事を就職エージェントに相談するのも手
一人暮らしをしながら働き続けられるか不安がある場合は、自分に合う仕事を就職エージェントに相談するのも手ですよ。就職エージェントでは、あなたの仕事に対する希望条件や学歴・経歴、スキルなどをヒアリングしたうえで、マッチする求人を厳選して紹介します。
「高卒であっても希望の収入を得られる仕事に就けるか」と不安を感じる場合にも、学歴に関係なく活躍して収入アップできる働き方をアドバイスするので、ご安心ください。
また、希望の収入を叶えられる仕事が自分に合っているのかを判断するのに、適職診断を利用することが可能です。このコラムの上部にもある適職診断であれば、約1分程度で簡単に仕事の適性をチェックできるので、ぜひご活用ください。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
高卒の一人暮らしに関するまとめ
高卒で一人暮らしをする際は、必要な費用や準備の流れを確認したうえで、計画的に進めることで、スムーズに生活を始められるでしょう。一人暮らしを始めてから金銭に関する負担を軽減するためにも、支出を無理なくまかなえる収入を得られる仕事を選ぶことが重要です。
高卒で一人暮らしを実現するための仕事選びにお悩みの場合は、就職・転職エージェントのハタラクティブの利用をおすすめします。高卒者の就職支援の実績のあるキャリアアドバイザーが、仕事に対する希望を丁寧にヒアリングしたうえで、仕事探しや選考対策をマンツーマンでサポートするので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
高卒で一人暮らしをする際によくある疑問のFAQ
以下に、高卒で一人暮らしをする際によくある質問の回答をまとめました。
高卒で貯金がない場合に仕送りなしで一人暮らしをするのはきつい?
貯金がない場合に仕送りなしで一人暮らしをするのには、金銭的な負担が大きいでしょう。
一人暮らしを始めるのに必要な初期費用は、家賃の4~6ヶ月分かかります。さらに、毎月の生活費に関する支出もあるため、貯蓄や金銭的な支援がなければ、支払うのは難しいでしょう。
金銭的な負担を回避するためにも、引越し費用や生活費1ヶ月のお金が貯まってから一人暮らしを始めることをおすすめします。
このコラムの「高卒での一人暮らしにかかる費用とは」では、一人暮らしにかかる費用を紹介しているので、ご覧ください。
高卒で上京して一人暮らしをするにはいつから準備するべき?
高卒で上京し一人暮らしを始めるなら、引越しや生活に必要なお金を貯蓄するのにかかる期間を確認することで、適切な時期が明らかになるでしょう。まずは、上京するのに必要な引越し費用や物件を借りるのにかかる初期費用、生活費などがいくらかかるかを計算してみてください。そのうえでその目標金額を達成するのに、月々いくらなら貯められるのかを考え、計画を立てましょう。
上京する場合、地元で就職するより物件や仕事探しにも時間がかかりやすいため、余裕をもったスケジュールで考えることが大切です。
高卒で車を所有している場合の一人暮らしに必要なお金は?
車を所有している場合、仮に、生活費が16万円、家賃が5万円だった場合、車に関する費用として、ガソリン代・保険代・駐車場代などで毎月2万円〜5万円程度加わることを想定しておく必要があります。これらを合計すると、月々の出費は23万円〜26万円程度になることが考えられるでしょう。
ただし、都市部では駐車場代が高額になる傾向があります。車を維持しながら一人暮らしをするには、家賃を抑えるか、より高い収入を得られる仕事を選ぶかを検討することが必要です。
高卒で就職せずにバイトをしながら一人暮らしはできる?
不可能ではありませんが、アルバイトの場合突然収入が途絶えるおそれもあるため、収支のバランスを保つのが難しいでしょう。また、アルバイトの場合、賃貸契約を結ぶうえで「安定した収入がある」と認められずに審査に通りにくくなることもあります。
スムーズに一人暮らしの生活を始めるうえでは、安定した収入を得られる正社員として就職するのがおすすめです。高卒者であっても、学歴よりも実力を重視する仕事を選べば、金銭的に余裕のある収入を得られる場合があるでしょう。
高卒で一人暮らしを始めた後に生活が苦しくならないか心配です
高卒で一人暮らしを始めたあとの生活に不安がある場合は、事前に収支のシミュレーションをして、無理のない生活をするために必要な収入を確認してみることが大切です。仕事と家事の両立に関する負担を軽減するためにも、料理や洗濯・掃除・家計管理の練習や知識の習得をしておくこともポイントといえます。
一人暮らしと両立できる仕事選びでお悩みの方は、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。仕事の希望条件や適性に合う仕事に就くための求人選びや選考対策をサポートします。