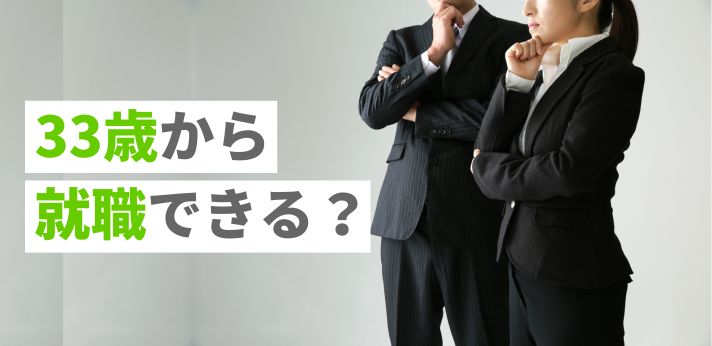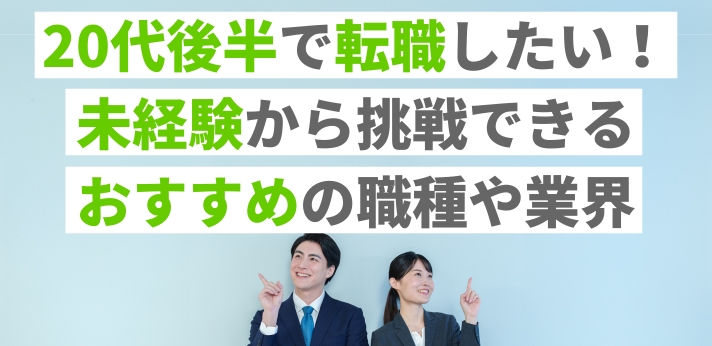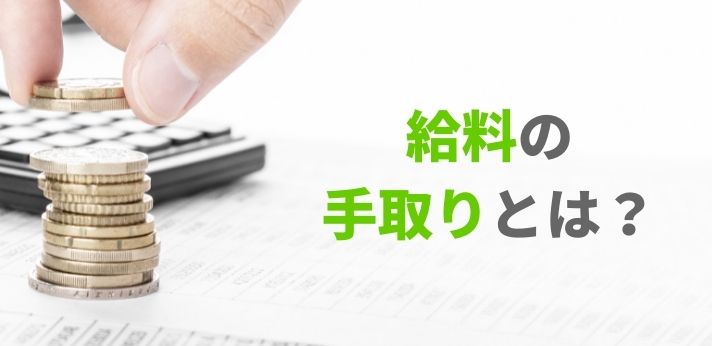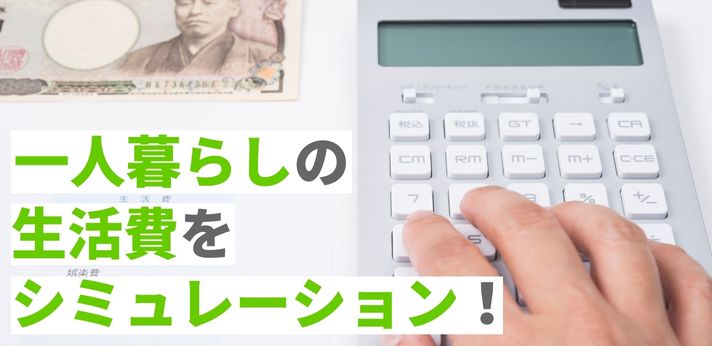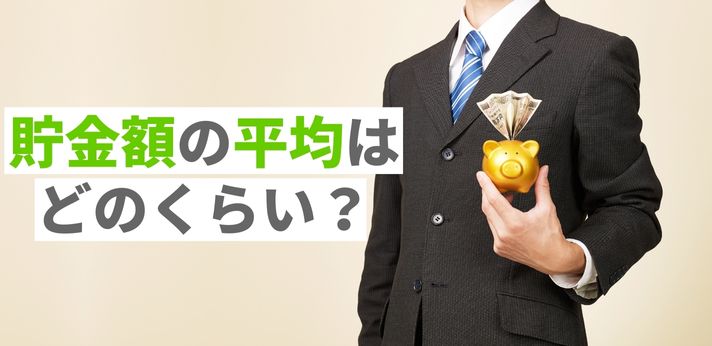23歳の平均年収と手取りはいくら?平均貯金額や年収アップの方法も解説23歳の平均年収と手取りはいくら?平均貯金額や年収アップの方法も解説
更新日
公開日
23歳の平均年収は約279万円、月収にすると約23万円
「もしかしたら自分の年収は23歳の平均より少ないかも…」「今の給与が低くて満足できないから年収アップしたい」という方もいるでしょう。23歳の平均年収は約279万円ほどです。
このコラムでは、性別や学歴別といった分類ごとの平均年収をご紹介します。今の年収に満足できない場合は就職・転職を検討してみるのも選択肢の一つです。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
23歳の平均年収は約279万円
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によると、23歳を含む「20~24歳」の平均賃金は23万2,500円でした。これを12ヶ月分で換算すると、23歳の平均年収は279万円と推定されます。
ただし、この金額はあくまで平均であり、地域や業種、働き方によって異なります。ボーナスが含まれていない点も考慮する必要があるでしょう。
【男女別】23歳の平均年収
男女別にみた23歳の平均賃金と平均年収は以下のとおりです。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
| 性別 | 20~24歳の平均賃金 | 20~24歳の平均年収 |
|---|
| 男女計 | 23万2,500円 | 279万円 |
| 男性 | 23万4,200円 | 281万400円 |
| 女性 | 23万600円 | 276万7,200円 |
※平均年収は20〜24歳の平均賃金×12ヶ月分で算出しています。
男女別で23歳の平均賃金を比較すると男性が23万4,200円、女性が23万600円となっており、約3,600円の差があります。23歳の平均賃金に12ヶ月分を掛けて年収を換算すると男性が281万400円、女性が276万7,200円です。
【学歴別】23歳の平均年収
以下に学歴別にみた23歳の平均賃金と平均年収をまとめました。
| 学歴 | 23歳の平均賃金 | 23歳の平均年収 |
|---|
| 高校 | 21万7,300円 | 260万7,600円 |
| 専門学校 | 23万1,000円 | 277万2,000円 |
| 高専・短大 | 23万400円 | 276万4,800円 |
| 大学 | 25万800円 | 300万9,600円 |
| 大学院 | 28万6,200円 | 343万4,400円 |
※平均年収は20〜24歳の平均賃金×12ヶ月分で算出しています。
このデータから、学歴によって平均賃金や平均年収に差があることが読み取れるでしょう。ただし、個人の能力や経験、就職先の業種や職種、働き方によって収入は異なる可能性があるため、あくまでも統計上の平均値であることを理解しておきましょう。
【企業規模別】23歳の平均年収
企業規模によっても平均賃金や平均年収には差が生じるようです。同資料では、企業の従業員数によって企業規模は以下のように分類されています。
- ・大企業:常用労働者1,000人以上
- ・中企業:常用労働者100~999人
- ・小企業:常用労働者10~99人
上記の基準に基づいて、23歳の平均賃金と平均年収を以下にまとめました。
| 企業規模 | 20~24歳の平均賃金 | 20~24歳の平均年収 |
|---|
| 大企業 | 24万4,700円 | 293万6,400円 |
| 中企業 | 22万7,300円 | 272万7,600円 |
| 小企業 | 22万1,800円 | 266万1,600円 |
※平均年収は20〜24歳の平均賃金×12ヶ月分で算出しています。
上記のデータから、企業規模が大きいほど平均賃金と平均年収は高くなる傾向が分かるでしょう。
【産業別】23歳の平均年収
ここでは、産業別にみた23歳の平均賃金と平均年収を表にまとめました。
| 産業 | 20~24歳の平均賃金 | 20~24歳の平均年収 |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 26万7,400円 | 320万8,800円 |
| 建設業 | 23万8,900円 | 286万6,800円 |
| 製造業 | 21万6,800円 | 260万1,600円 |
| 電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 24万4,400円 | 293万2,800円 |
| 情報通信業 | 24万9,100円 | 298万9,200円 |
| 運輸業、郵便業 | 23万4,900円 | 281万8,800円 |
| 卸売業、小売業 | 23万600円 | 276万7,200円 |
| 金融業、保険業 | 25万500円 | 300万6,000円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 25万9,600円 | 311万5,200円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 24万5,300円 | 294万3,600円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 22万1,000円 | 265万2,000円 |
| 生活関連サービス業、 娯楽業 | 22万4,500円 | 269万4,000円 |
| 教育、学習支援業 | 23万2,500円 | 279万円 |
| 医療、福祉 | 24万4,000円 | 292万8,000円 |
| 複合サービス事業 | 21万3,500円 | 256万2,000円 |
| サービス業(ほかに分類されないもの) | 22万2,100円 | 266万5,200円 |
※平均年収は20〜24歳の平均賃金×12ヶ月分で算出しています。
上記の表から、産業によって平均賃金や平均年収に差があることが分かるでしょう。23歳を含む「20~24歳」において最も平均賃金と平均年収が高いのが「鉱業、採石業、砂利採取業」、次いで「不動産業、物品賃貸業」「金融業、保険業」となっています。
一方、23歳を含む「20〜24歳」において最も平均賃金と平均年収が低かったのが「複合サービス事業」、次いで「製造業」「宿泊業、飲食サービス業」でした。
【雇用形態別】23歳の平均年収
以下では、雇用形態別にみた23歳を含む「20〜24歳」の平均賃金と平均年収をまとめました。
| 雇用形態 | 20~24歳の平均賃金 | 20~24歳の平均年収 |
|---|
| 正社員・正職員 | 23万7,000円 | 284万4,000円 |
| 正社員・正職員以外 | 19万7,300円 | 236万7,600円 |
※平均年収は20〜24歳の平均賃金×12ヶ月分で算出しています。
上記によると、23歳を含む「20〜24歳」の平均年収は、正社員が284万4,000円、非正規社員が236万7,600円でした。正社員は非正規社員に比べて平均賃金・平均年収ともに高い傾向があります。これは、仕事内容や勤務時間の違い、賞与制度の有無などが影響していると考えられるでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
23歳における平均年収の手取り額は約223万円
前述のとおり、23歳の平均年収は約279万円ですが、実際に手元に残る「手取り額」はこの金額より少なくなります。一般的には、年収(額面)の約8割が手取りの目安とされているようです。そのため、279万円×0.8=223万2,000円ほどが、手取り額の目安となります。
ただし、手取り額は月収や住んでいる地域などによって異なるため、より正確に知りたい場合は源泉徴収票を確認しましょう。特に次の3つの項目をチェックするのがポイントです。
- ・支払金額
- ・源泉徴収税額
- ・社会保険料などの金額
上記の3項目をチェックすることで、年収から何が差し引かれているかを把握できます。「支払金額」はいわゆる年収(額面)にあたり、ここから「源泉徴収税額(所得税)」や「社会保険料」などが差し引かれ、実際に受け取る金額(手取り額)が決まります。
また、住民税は源泉徴収票には記載されておらず、交通費は非課税扱いになるため、過去の手取り額を調べる際は、以下の計算式に当てはめてみましょう。
「手取り額 = 支払金額 − (源泉徴収税額 + 社会保険料等 + 1年間の住民税 + 1年間の交通費)」
手取り額については、以下のコラムで解説しているので、ぜひご一読ください。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
23歳ではどのくらいの年収が必要?
生活に必要な年収は、ライフスタイルや家族構成によって異なります。ここでは一例として、「23歳独身で一人暮らしの場合」と「23歳で配偶者と2人暮らしの場合」のそれぞれで、毎月の生活費の概要を表にまとめてみました。
23歳で独身の場合に必要な年収
一人暮らしをしている23歳の独身の場合、収入の多くを生活費に充てることが考えられます。実家暮らしに比べて支出は増える可能性がありますが、自炊を増やしたり家賃や交際費を抑えたりして生活することはできるでしょう。ここでは、自炊を基本とした比較的シンプルな生活を想定し、毎月の生活費の目安をまとめてみました。
| 項目 | 月額の目安 | 備考 |
|---|
| 家賃 | 6万円 | ワンルーム、首都圏外想定 |
| 食費 | 3万円 | 自炊中心の場合 |
| 水道光熱費 | 1万円 | 季節により変動あり |
| 通信費 | 8,000円 | スマートフォン・ネット含む |
| 交通費 | 5,000円 | 通勤定期代など |
| 日用品・雑貨 | 8,000円 | 洗剤・ティッシュなど |
| 娯楽・交際費 | 1万5,000円 | 飲み会・趣味など |
| 貯金 | 1万円 | ー |
| 合計 | 14万6,000円 | ー |
この場合、手取りで毎月15万円ほどが必要になり、年間では180万円が目安です。手取りが年収の約8割と仮定すると、年収225万円程度が必要になります。生活に余裕をもたせるなら、もう少し多めの収入が必要です。
23歳で結婚している場合に必要な年収
配偶者が専業主婦(主夫)である場合、生活費は2人分かかるため、独身の場合よりも必要な年収は高くなることが予想されます。ここでは、夫婦2人で暮らしている場合の生活費の一例をまとめてみました。住居は1LDK〜2DK程度、生活は自炊中心で節約している設定です。
| 項目 | 月額の目安 | 備考 |
|---|
| 家賃 | 8万円 | 1LDK~2DK程度 |
| 食費 | 4万5,000円 | 2人分、自炊中心 |
| 水道光熱費 | 1万5,000円 | 2人分 |
| 通信費 | 1万2,000円 | スマートフォン2台、ネットなど |
| 交通費 | 7,000円 | 通勤定期代など |
| 日用品・雑貨 | 1万円 | 2人分 |
| 娯楽・交際費 | 2万円 | 外食など |
| 貯金 | 1万5,000円 | ー |
| 合計 | 20万4,000円 | ー |
このケースでは、手取りで月21万円ほど、年間では約252万円が必要になります。これを年収に換算すると、315万円程度が目安となります。今後、子どもをもつといったライフステージが変化すれば必要な収入も増えるため、将来を見据えた資金計画も大切です。
23歳の平均貯金額は約245万円
| 世帯主の年齢(10歳階級) | 1世帯当たり平均貯蓄額 |
|---|
| 総数 | 1,368万3,000円 |
| 29歳以下 | 245万1,000円 |
| 30~39歳 | 717万8,000円 |
| 40~49歳 | 925万8,000円 |
| 50~59歳 | 1,248万4,000円 |
| 60~69歳 | 1,738万8,000円 |
| 70歳以上 | 1,594万7,000円 |
※「1世帯当たり平均貯蓄額」には、貯蓄の有無が不詳の場合は含まない
※貯蓄の有無が「あり」で貯蓄額不詳の世帯は含まない
※年齢階級の「総数」には、年齢不詳を含む
上記から23歳を含む「29歳以下」の平均貯金額は、245万1,000円であることが分かります。また、年齢が上がるにつれて平均貯金額は増加傾向にあることも読み取れるでしょう。
23歳で年収を上げる方法
「このまま働き続けて年収は上がるのかな?」「今より良い働き方はないかな?」と考える23歳の方もいるでしょう。ここでは、年収アップのための方法をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
資格を取得して手当をもらう
企業によっては、特定の資格をもっていることで「資格手当」が支給される場合もあるでしょう。たとえば、事務職であれば簿記やMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)、販売職であれば登録販売者など、業務に役立つ資格が挙げられます。
また、資格をもっていると任される仕事の幅が広がり、昇給や昇進のチャンスにつながることもあるでしょう。資格によっては通信講座や独学で取得できるものもあるため、「少しでも収入を増やしたい」と考えている人にとって、取り組みやすい選択肢のひとつといえます。
非正規社員の場合は正社員就職をする
非正規社員から正社員になることで、年収アップにつながる可能性があります。ハタラクティブの「若者しごと白書2025」では、雇用形態ごとの手取り月収の分布が示されており、そこから推定される年収にも差がみられるようです。以下は手取り月収をもとに算出した年収の比較表です。
| 手取り月収 | 推定される手取り年収 | フリーター | 正社員 |
|---|
| 10万円未満 | 120万円未満 | 38.8% | 2.2% |
| 10~15万円未満 | 120~180万円未満 | 21.1% | 6.1% |
| 15~20万円未満 | 180~240万円未満 | 14.8% | 31.3% |
| 20~23万円未満 | 240~276万円未満 | 4.7% | 23.5% |
| 23~26万円未満 | 276~312万円未満 | 1.5% | 11.2% |
| 26万円以上 | 312万円以上 | 1.7% | 14.2% |
| 答えたくない | ー | 17.4% | 11.5% |
この表から、フリーターで最も多い層は、全体の38.8%を占めている推定手取り年収120万円未満。次いで、推定手取り年収120〜180万円未満が21.1%、180〜240万円未満が14.8%となっていることが分かります。
一方、正社員で最も多い層は推定手取り年収180〜240万円未満で31.3%を占めており、次いで年収240〜276万円未満の層が23.5%となっています。正社員はフリーターに比べて、より高い年収帯に分布していることが読み取れるでしょう。
就職支援機関に相談する
正社員を目指したいけれど、どこから始めれば良いか分からない方には、就職支援機関を活用するのがおすすめです。就職支援機関には、ハローワークや就職エージェントなどがあります。これらの機関では、求人紹介だけでなく、自己分析のやり方や履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接、企業とのやりとり代行まで幅広く対応しています。無料で利用できるサービスもあるので、何から始めれば良いか分からない場合は、相談してみるのも手です。
紹介予定派遣として働いたのちに正社員を目指す
正社員就職を目指す場合、一旦紹介予定派遣として働く選択肢もあります。紹介予定派遣とは、派遣社員として企業で働き、そのあとに正社員や契約社員として採用されることを前提とした制度です。実際に働いてみてから職場との相性や仕事内容を見極められるため、「入社してから後悔する」といったミスマッチを避けやすいのがメリットといえるでしょう。
紹介予定派遣は、人材派遣会社に登録することで求人を紹介してもらえます。「いきなり正社員はハードルが高い」と感じている方にとって、ステップを踏みながら正社員を目指せる選択肢のひとつです。
アルバイト先に正社員登用制度があれば活用する
今働いているアルバイト先に正社員登用制度があれば、活用するのも手です。新しい職場に応募するのとは違い、すでに人間関係や業務内容を理解しているため、環境の変化に戸惑うことなく、スムーズに正社員として働き始められるというメリットがあります。
正社員登用制度があるかどうかは、求人票や就業規則、上司への確認などで把握できるでしょう。また、制度があるだけでなく、実際に登用実績があるかどうかも確認しておくと安心です。登用にあたっては、勤務態度や出勤日数、スキル面などが重視される可能性があるため、日ごろから責任感をもって仕事に取り組む姿勢が大切です。
職場を変えずに正社員を目指したい人や、今の職場にやりがいを感じている人にとっては、正社員登用制度を活用することを検討してみると良いでしょう。
実績を積んで昇給や昇進を目指す
今の職場で年収を上げたいと考えるなら、着実に実績を積み上げることが重要です。企業によって昇給の時期や基準は異なりますが、一般的には「評価制度に基づいた昇給」や「昇進による給与アップ」などがあります。与えられた業務を正確にこなすのはもちろん、自ら工夫して仕事の効率を高めたり、周囲と積極的にコミュニケーションを取ってチームに貢献したりする姿勢も評価されやすくなるでしょう。
評価面談や人事考課のタイミングでは、自分の成果をしっかり言語化して伝えることもポイントです。努力が正しく評価されれば、昇給や役職の昇格につながり、結果として年収アップを目指せるでしょう。
現職よりも年収が高い企業への転職を検討するのも手
今の職場で昇給の見込みが少ない、評価制度が曖昧で年収が上がりにくいと感じている場合は、より年収の高い企業への転職を検討するのも選択肢の一つです。職種や仕事内容は同じであっても、業界や企業の規模、地域、福利厚生などによって年収には差があります。特に、成長業界や利益率の高い企業では、初任給や昇給ペースが比較的高い傾向があるようです。たとえば、同じ営業職でも、商材やターゲットとする市場が異なることで基本給やインセンティブ制度が異なることもあるでしょう。
転職活動を始める際は、自分の経験やスキルがどういった業界や職種で評価されやすいかを把握することが大切です。そのうえで、求人サイトやハローワーク、転職エージェントなどを活用して、自分に合った条件の企業を探してみましょう。
現職よりも年収アップを狙える企業へ転職する方法
現職での昇給が見込めない場合や、今の働き方に不満がある場合は、思い切って現職よりも年収が高い企業への転職を検討するのも一つの方法です。ここでは、転職活動を始める際に活用できる3つの方法をご紹介します。自分に合った方法を見つけ、前向きな一歩を踏み出してみましょう。
ハローワークを活用する
ハローワークは、国が運営する公共職業安定所で、無料でさまざまな求人情報を提供している機関です。求職者の職歴や希望条件に合わせた求人紹介に加えて、職業相談や面接対策、履歴書の添削など、転職活動全般をサポートしてくれるのが特長です。
特に「わかものハローワーク」といった若年層向けの就職支援窓口もあるため、年齢に合ったサポートが受けられる点も魅力といえるでしょう。
求人サイトで今よりも年収が高い仕事を探す
転職サイトでは、希望条件に応じて年収や職種、勤務地を絞り込んで検索できるため、年収アップを狙ううえで効率的です。サイトによっては、「年収△万円以上」「昇給制度あり」「賞与年2回以上」といった検索フィルターがあり、自分に合った条件の求人を見つけやすいでしょう。
また、企業ごとの平均年収や口コミ、実際に働いている人の声などもチェックできる求人サイトもあるため、入社後のギャップを減らせることも。求人サイトは自分のペースで情報収集ができるのがメリットですが、非公開求人や個別のアドバイスは得られにくいため、ほかのサービスと併用するのもおすすめです。
転職エージェントに相談する
転職エージェントは、求職者一人ひとりに専任のキャリアアドバイザーがつき、求人紹介から応募書類の添削、面接対策までを無料でサポートしてくれるサービスです。エージェントが保有する求人のなかには、一般には公開されていない「非公開求人」もあり、年収が高い好条件の案件に出会える可能性もあるでしょう。
加えて、企業との交渉も代行してくれるため、給与や待遇の相談がしやすく、現職よりも年収が高い仕事への転職が実現しやすいのもメリットです。初めての転職や、年収アップを軸にした仕事探しに不安がある人にとって、キャリアアドバイザーは心強い存在となるでしょう。