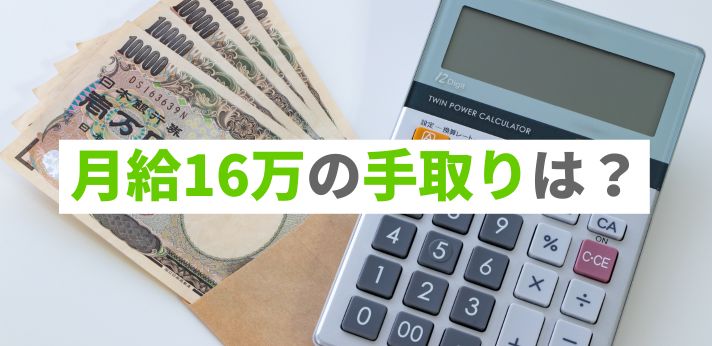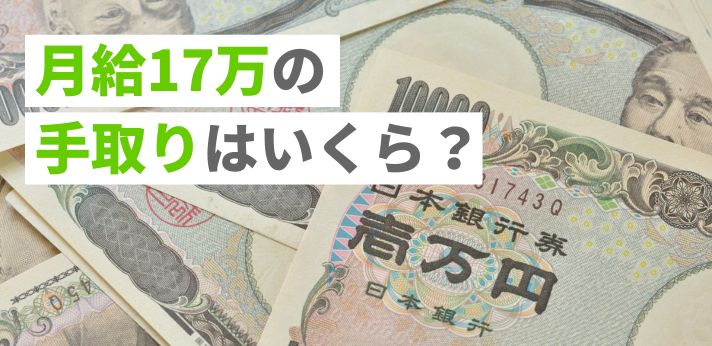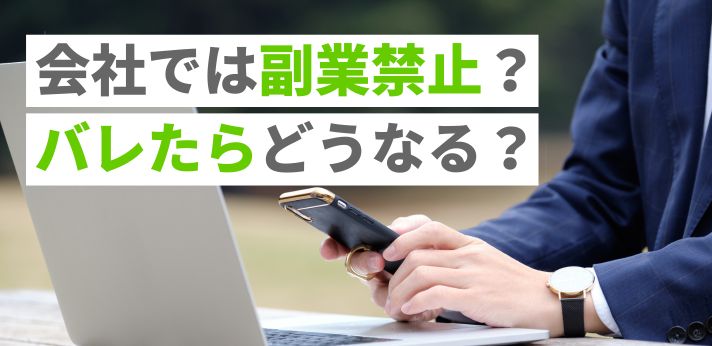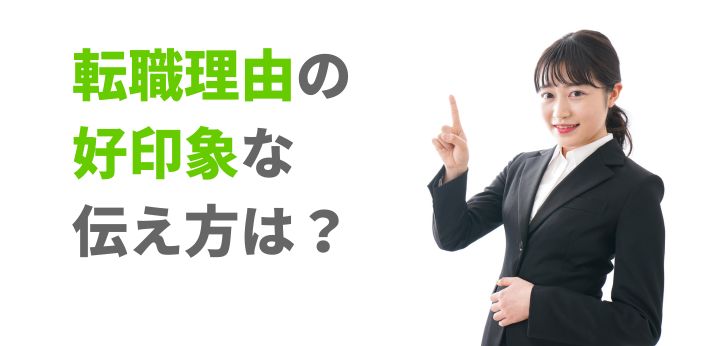高卒公務員は生活できない?大卒との給料差や生活が苦しいと感じる理由を紹介高卒公務員は生活できない?大卒との給料差や生活が苦しいと感じる理由を紹介
更新日
公開日
高卒公務員で経験年数が浅いうちは給料が安いため、生活できないと感じる場合もあるのが現実
「高卒で公務員になったけれど、生活が苦しい…」「公務員でも高卒だと給料が低いの?」と感じる人もいるでしょう。大卒より初任給が低く、昇給ペースもゆるやかなため、手取りが想像より少なく感じる場合があります。また、副業を行うにも制限があり、収入を増やしにくいのが実情です。
このコラムでは、高卒公務員の給料や大卒公務員との比較、「生活できない」と感じる理由について解説します。高卒公務員のメリットや働きながら生活していくコツなどもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
高卒公務員は生活できないほど給料が安い?
公務員の仕事に対して「安定している」「就職できれば勝ち組」というイメージをもつ高校生や高卒の方もいるでしょう。しかし、就職して間もないうちは「生活するのがやっと」と感じるほど手取りが少ないと感じる人もいるようです。特に、一人暮らしをしている場合や都市部で勤務している場合は、収入に対して出費がかさみやすくなるため、生活に不安を覚えることも。ある程度の勤続年数を重ねて給料が上がるまでは、節約や家族からの仕送りが必要になる時期もあるでしょう。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
高卒公務員として働きながら生活していくコツ
高卒公務員として安定した職に就いても、収入面で不安を感じる人は少なくありません。生活を安定させるには、家計管理や節約をしたり、福利厚生を活用したりすることなども必要になるでしょう。ここでは、高卒公務員の方が無理なく暮らすためのコツを紹介します。
高卒公務員として働きながら生活していくコツ
- 家計簿をつけながら節約する
- 住居手当や地域手当などの福利厚生を活用する
1.家計簿をつけながら節約する
経済的に「生活できない」と感じる高卒公務員の方は、家計簿をつけて日々の支出を把握し、可能な範囲で節約を心掛けましょう。家計簿をつけずにお金を使っていると、無意識のうちに出費がかさんでしまうリスクが考えられます。リスクを減らすためには、「何にいくら使っているのか」を目に見える形で管理することが重要です。昨今はスマートフォン向けの家計簿アプリもあり、簡単に入力できるだけでなくグラフや集計も自動で行ってくれます。「コンビニでの無駄遣いが多い」「外食費が増えがち」といった支出のクセに気づくことができ、何を節約するべきかが明確になるでしょう。
2.住居手当や地域手当などの福利厚生を活用する
高卒公務員として働きながら安定した生活をしていくためには、自分が受けられる福利厚生を利用することも大切です。特に、住居手当や地域手当などは生活費の軽減に役立つので、積極的に活用しましょう。
住居手当とは、社員や職員が賃貸住宅などに住んでいる場合、その家賃の一部を企業や団体が補助する制度。従業員の生活を安定させるための福利厚生の一つで、民間企業だけで働く人だけでなく公務員も利用可能です。支給額は居住地域や家賃額によって異なりますが、生活費の負担を軽くできるでしょう。
地域手当は、勤務地の地域によって異なる生活費や物価の差を補うために支給される手当のことです。物価が高い都市部で働く人には、地方で働く人と比べて基本給に上乗せされる形で支給されます。住む場所による経済的な不公平を軽減する目的があり、支給金額は地域ごとに異なります。
このほかにも受けられる制度を活用することで、限られた収入のなかでも生活を維持し、貯金や自己投資に回す余裕を創りやすくなるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
高卒・大卒公務員の給料
公務員の給料は、高卒か大卒かで金額が異なります。また、国家公務員か地方公務員かによっても、給料に差があるようです。ここでは、高卒公務員と大卒公務員の給料を経験年数別にそれぞれご紹介するので、高卒と大卒の公務員でどれくらい給料の差があるか知りたい方は、参考にしてみてください。
国家公務員の場合
| 経験年数/学歴別平均俸給額 | 高卒の国家公務員 | 大卒公務員の国家公務員 |
|---|
| 1年未満 | 17万712円 | 20万2,364円 |
|---|
| 1年以上~2年未満 | 17万5,512円 | 20万7,885円 |
|---|
| 2年以上~3年未満 | 18万347円 | 21万4,011円 |
|---|
| 3年以上~5年未満 | 19万1,126円 | 22万4,921円 |
|---|
高卒公務員と大卒公務員のデータを比較すると、両者の平均俸給額には約3万円程度の差があることがわかります。金額だけを見ると、「高卒公務員の給料だと若いうちは生活できないかも」と感じるかもしれません。ただし、経験年数による昇給のペースは、高卒と大卒に大きな差はないようです。
地方公務員の場合
総務省の「令和6年 地方公務員給与の実態」では、経験年数別に地方公務員の平均給料月額が公開されています。地方公務員の場合の高卒・大卒者の平均給料は以下のとおりでした。
| 経験年数/学歴別平均給料月額(一般行政職) | 高卒の地方公務員 | 大卒の地方公務員 |
|---|
| 1年未満 | 16万9,762円 | 20万048円 |
|---|
| 1年以上~2年未満 | 17万4,059円 | 20万5,456円 |
|---|
| 2年以上~3年未満 | 17万9,328円 | 21万1,382円 |
|---|
| 3年以上~5年未満 | 18万9,004円 | 22万1,390円 |
|---|
地方公務員の場合も、大卒者より高卒者のほうが平均給料が低い傾向にあります。また、高卒・大卒どちらの場合も、地方公務員の給料は国家公務員より若干低いようです。
高卒者の場合、国家公務員であっても地方公務員であっても、1年目の給料は16~17万円程度になるでしょう。
民間企業に勤める高卒者・大卒者の給与
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 (3) 学歴別にみた賃金」によると、民間企業に勤める19歳未満の高卒者の平均賃金は19万9,800円でした。公務員の場合、経験年数1~2年の公務員が同年代に該当しますが、民間企業に勤める高卒者とは約2~3万円の賃金差があるといえるでしょう。
高卒公務員が「生活できない」と感じる3つの理由
高卒公務員が「生活できない」と感じるのは、「大卒公務員より給料が低いから」「給料が上がるペースが遅いから」などの理由が挙げられるでしょう。それぞれ詳しく解説します。
1.大卒公務員より給料が低いから
高卒公務員が「生活できない」と感じるのは、大卒公務員よりも給料が低いからという理由が挙げられます。先述したように、高卒公務員の給料は大卒公務員よりも低いのが実情です。また、4年制大学卒の新卒者が公務員として就職した場合、同年齢の高卒公務員の経験年数は5年目になりますが、1年目の大卒者と給料に大きな差はありません。「同じ歳で自分の方が経験を積んでいるのに、1年目の大卒と給料が変わらない…」という不満が、生活が苦しいと感じる原因になることも考えられるでしょう。
2.給料が上がるペースが遅いから
給料が上がるペースが遅いことも、高卒公務員が「生活できない」と感じる理由の一つです。公務員の給与体系は基本的に年功序列で構成されており、長く勤めることで少しずつ昇給していく傾向にあります。そのため、経験年数が少ないうちは経済的な余裕を感じにくく、生活に苦しさを覚えることがあるでしょう。
3.原則的に副業ができないから
高卒公務員が「生活できない」と感じるのは、副業が原則禁止されているからという理由もあります。公務員は国家公務員法や地方公務員法によって副業が制限されており、足りない分の収入を別の仕事で補えないため、経済的な不安につながりやすいでしょう。
しかし、公務員でも一定の条件下で許可される副業は存在します。たとえば、人事院の「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」によると、不動産投資や太陽光発電事業、アフィリエイト収入などにより収入を得ることは可能です。ただし、承認・許可が必要なものも多いので、所属組織の確認をしましょう。
生活できないわけではない!高卒公務員の4つのメリット
「経験を積むまで給料は低そうだし、高卒公務員にメリットはない?」と思った方もいるかもしれません。しかし、高卒か大卒かにかかわらず、公務員ならではのメリットもあります。以下で詳しくご紹介するので、ぜひご一読ください。
高卒公務員のメリット
- 雇用が安定している
- 福利厚生が充実している
- 大卒公務員より早く経験を積める
- 大学や専門学校に通う費用がかからない
1.雇用が安定している
公務員として働くメリットの一つは、雇用が非常に安定していることです。公務員は、民間企業ではなく国や地方自治体といった公的機関に雇われている立場。民間企業は業績悪化による人員整理や倒産などによる解雇のリスクがありますが、公務員は重大な規律違反を犯さない限り、職を失うことはありません。そのため、長期的な人生設計の準備をしやすい環境で働けるでしょう。
2.福利厚生が充実している
福利厚生が充実しているのも公務員のメリットです。公務員は法律や制度に基づいた待遇が整えられており、民間企業と遜色のない支援を受けられます。健康保険や年金制度はもちろん、有給休暇や育児休業、介護休暇といった各種休暇制度も整備されているので、将来的にライフイベントとも両立しやすいでしょう。また、家賃補助や通勤手当といった生活支援制度も充実しており、生活費の負担を軽減できるのも魅力です。
3.大卒公務員より早く経験を積める
高卒公務員は、大卒公務員よりも早い段階で実務経験を積める点もメリットといえます。高校卒業後すぐに就職することで、同年代の人が大学生活を送っている間に多くの実務経験を積めるでしょう。同じ職種に従事する公務員の場合、基本的に仕事内容は高卒も大卒も同じです。そのため、経験があるぶん同年代の大卒公務員よりも、現場で積み重ねた信頼や対応力などが評価されやすいでしょう。
4.大学や専門学校に通う費用がかからない
大学や専門学校に通う費用がかからないのも、高卒公務員のメリットです。専門学校や大学などに進学するには、入学費用や授業料などの高額な学費を捻出する必要があります。奨学金で通うこともできますが、その場合は卒業後に返済しなければなりません。進学せずに就職すれば学費はかからず、いち早く社会人として自立した生活を送れるでしょう。
高卒公務員になって後悔した場合の選択肢
高卒で公務員になったものの、「自分に合っていない」「もっと違う道があったかも」と後悔する場合もあるでしょう。そのようなときは我慢し続けるだけでなく、新たな選択肢を考えることも大切です。ここでは、高卒公務員になって後悔した場合の選択肢について詳しく解説します。
大学や専門学校に入学し直す
高卒で公務員になった後に別の道を考えたくなったとき、選択肢の一つとして大学や専門学校に入り直すという道があります。「ほかにやりたい仕事が見つかった」「もっと専門的な知識や資格を身につけたい」と感じた場合、退職して進学を目指すことは可能です。
また、退職せずに夜間大学や通信制の専門学校に通ったり休日にオンライン授業を受けたりと、自分のペースで学ぶこともできます。もちろん学費や時間はかかりますが、それでもやりたいことを見つけた場合は、改めて学び直すことも選択肢の一つになるでしょう。
民間企業に転職する
高卒で公務員になったことに後悔を覚えた場合、民間企業へ転職するという選択肢も考えられるでしょう。たとえ一度公務員として就職したとしても、自分の適性に合った環境を求めて新しい仕事を探す人もいます。転職によって公務員では経験できなかった分野に挑戦できるため、自分の可能性を広げられる点は大きな魅力です。
民間企業へ転職する際の選考では、公務員時代に培ったスキルや経験が評価されることもあります。ただし、面接では「なぜ公務員を辞めたのですか?」と質問される可能性が高いため、面接官を納得させる明確な転職理由が必要です。自己分析や企業研究などを綿密に行ってから選考に臨みましょう。
第三者に相談する
公務員を辞めて別の道を選択するか迷ったときは、焦って決断する前に第三者へ相談してみましょう。相談相手は家族や友人のほか、転職エージェントのキャリアアドバイザーもおすすめです。
家族や友人
家族や親しい友人は、自分の性格をよく知っている存在です。身近な人に自分の気持ちや悩みを話すことで、自分でも気づかなかった考え方や本音が見えてくることがあります。第三者の視点から客観的な意見をもらうことで、公務員として働き続けるべきか別の道に進むべきか判断する材料になるでしょう。
転職エージェント
高卒で公務員になったことに後悔を感じたとき、選択肢の一つとして転職エージェントに相談するのもおすすめです。転職エージェントは、希望や適性に基づいて求人を紹介してくれるサービス。より専門的な視点でキャリアの選択肢を広げたい場合は、転職のプロからアドバイスをもらうのが有効です。高卒公務員としての職務経験は「安定した組織での事務経験」「社会人としての基本マナー」「住民対応などの対人スキル」などを強みとして認められることも多く、エージェントを通すことでアピールポイントを整理してもらうことができます。
また、転職市場の動きや業界の情報に詳しいエージェントであれば、自分では思いつかなかった選択肢や未経験から挑戦できる仕事を提案してくれることも。履歴書の書き方や面接の練習などのサポートも受けられるため、転職が初めてでも安心して準備を進められるのがメリットです。
「後悔のない就職・転職をしたい」「就職した仕事のミスマッチに気付いて後悔している」という高卒の方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは高卒の方はもちろん、フリーターや既卒といった若年層向けの支援サービスです。キャリアアドバイザーが求人紹介から内定獲得後のアフターフォローまで、マンツーマンのサポートを提供します。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
高卒公務員に関するQ&A
ここでは、高卒公務員に関する質問やお悩みをQ&A形式でご紹介します。
給与面において劇的な変化は期待できませんが、毎年の定期昇給とボーナス額の増加によって楽になる可能性は十分あります。初年度は自炊や固定費削減などの工夫をする姿勢が重要です。
ただし、2年目に入って住民税の支払いが始まることで、「給与が全然変わらなくて辛い」「より生活が厳しくなった」と感じてしまう恐れも。1年目は手取りが少ない上に住民税のの支払いが基本的にはありませんが、2年目からは天引きされるため、一時的に手取りが減る「2年目の罠」に注意しましょう。
都会と地方で高卒公務員の生活のしやすさは変わりますか?
都会の方が物価が高い傾向にあるため、地方の方が生活水準を維持しやすいといえます。都会は「地域手当」で基本給が上乗せされるのが一般的ですが、それ以上に家賃や物価が高いためです。
一方、地方は車が必須な場合もあり維持費がかさみますが、公務員宿舎や安価な賃貸物件を活用することで、支出を抑えつつ安定した生活を送ることが可能といえるでしょう。
高卒公務員ですが、パートナーと結婚するのに適した時期はありますか?
明確な決まりがあるわけではありませんが、基本的に「自分たちの関係性が安定していて、仕事や生活の土台が整ってきたと感じられるとき」が結婚に適した時期であることが多いでしょう。高卒公務員の場合は18歳から働き始めるため、20代前半のうちはまだ仕事に慣れる時期であり、収入もそれほど高くないことが一般的です。この段階では仕事と生活の両立に慣れていないこともあり、結婚に踏み切るには少し早いかもしれません。20代後半になると仕事にも慣れ、一定の安定感や責任あるポジションを任されるようになる時期です。給料やボーナスも少しずつ増え始め、生活の基盤が整いやすくなるため、結婚を現実的に考えられるタイミングといえるでしょう。
公務員は「扶養手当」や「住居手当」などの手当が手厚く、共働きでなくても生活の設計が立てやすいため、結婚後に家族を養うことは可能といえます。育休などの福利厚生が充実しているため、共働きを継続すればさらに余裕のある家計を築けるでしょう。年功序列で将来の年収予測が立てやすいため、教育資金や住宅ローンも戦略的に組みやすいようです。
高卒公務員が勝ち組かどうかは、個人の価値観や人生観によって変わる部分も大きいため、一概に断言はできません。しかし、公務員は景気に左右されにくく雇用が安定しており、若いうちから経済的な基盤をもち将来設計もしやすいことから「すごい」「勝ち組」と評価されることはあるでしょう。特に、安定した生活や堅実な人生を求める人にとっては、勝ち組であると映りやすい仕事といえます。
就職・転職エージェントのハタラクティブでは、自分に合っている仕事をキャリアアドバイザーがご紹介します。ぜひお気軽にお問い合わせください。