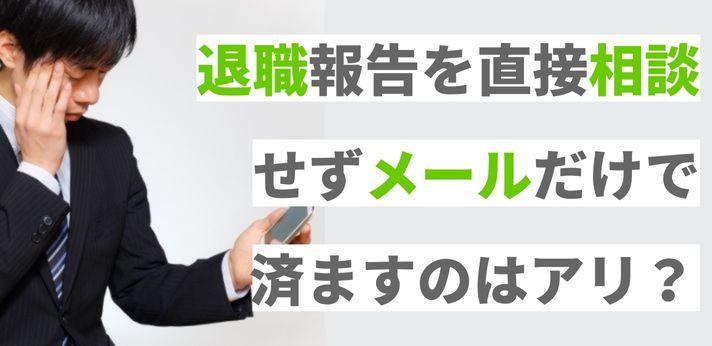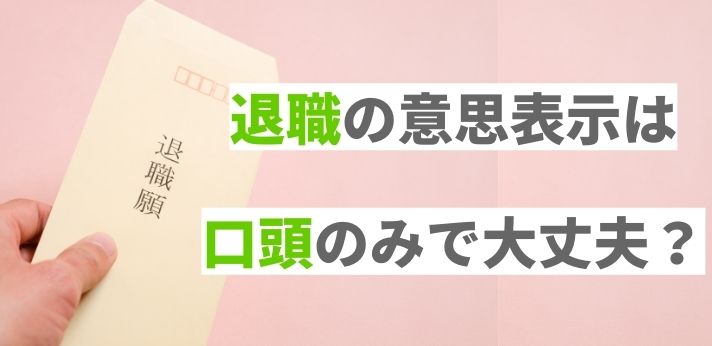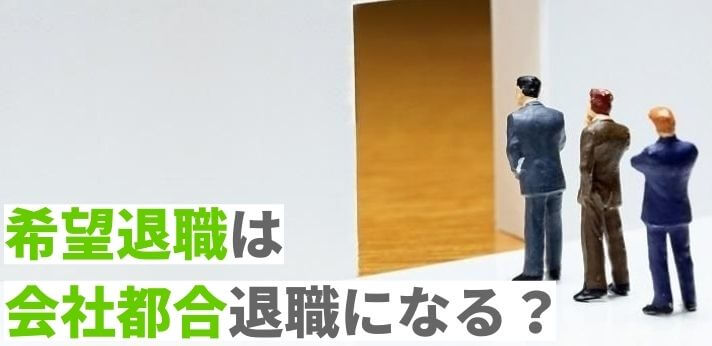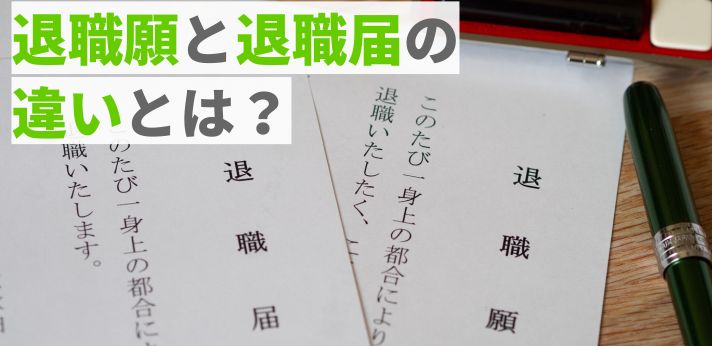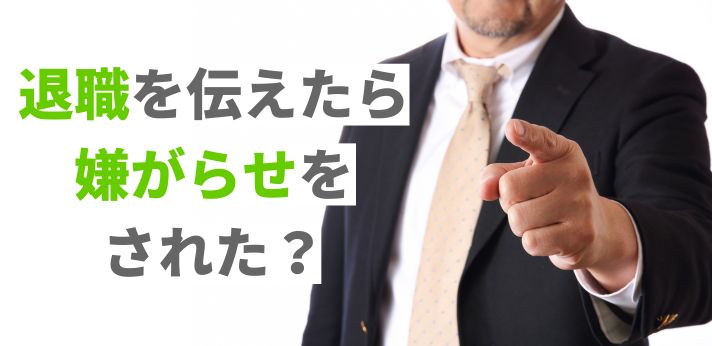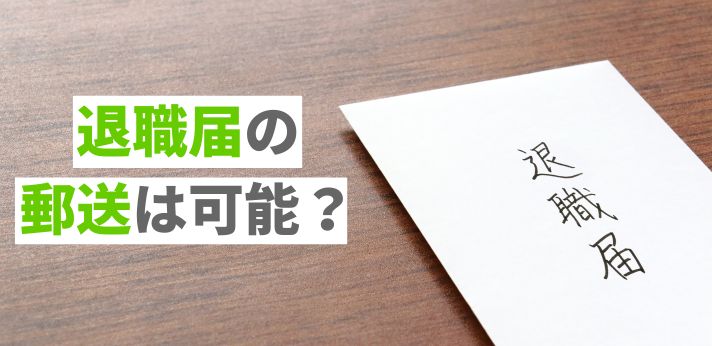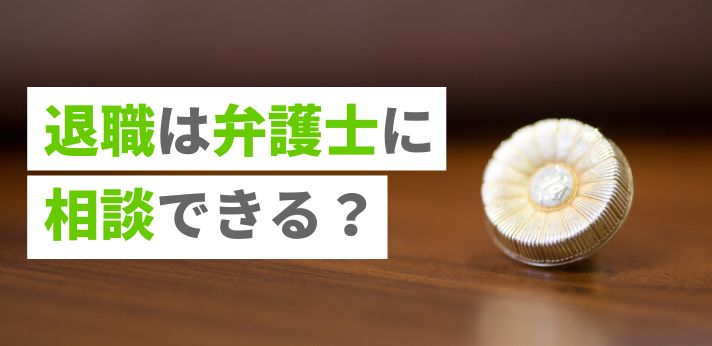退職届を受け取ってもらえない時はどうする?知っておきたい法律と対処法退職届を受け取ってもらえない時はどうする?知っておきたい法律と対処法
更新日
公開日
退職届は憲法による保障と民法の定めにより、会社側は受け取りを拒否できない
「退職届を受け取ってもらえない」あるいは「退職届を受理してもらえなかったらどうしよう」と悩む方は多いでしょう。憲法や民法の観点から、会社は退職届の受理を拒否できません。このコラムでは、事前に知っておきたい法律や、退職届と退職願の違い、退職の拒否がパワハラにあたるケースなどもまとめています。トラブルを避けスムーズに退職するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
退職届や退職願を受け取ってもらえないことはある?
退職届を提出しても、「人手が足りないから厳しい」「後任者が見つかるまで待ってほしい」などと言われ、受け取ってもらえない場合があります。しかし、
会社側の理由があっても、労働者が法律や就業規則に則り、ルールを守って提出した退職届であれば受け取りを拒否できません。日本国民は、日本国憲法第22条1項において「職業選択の自由」が保障されているためです。
就業規則と民法のどちらのほうが効力がある?
一般的に、労働者を保護する目的で定められた法律である民法の規定が優先されるため、会社側が一方的に労働者に不利な条件は押し付けられません。しかし、退職に関するルールは、会社ごとに定められた就業規則と、民法に基づく法律の両方が関係します。
民法では退職の2週間前に意思を伝えれば退職できるとされていますが、就業規則で「1カ月前に申し出ること」と定められている企業もあるでしょう。このような場合、1カ月前の申し出が合理的と認められる可能性もあるため、円満に退職するためには会社の規則を確認し、適切なタイミングで話し合うことが大切です。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職願を受け取ってもらえないときは退職届の提出を検討する
「退職願」は「退職したい旨を願い出る」書類で、「退職届」は「退職することを届け出る」断定的な書類です。
円満退職する方法として一般的なのは、退職願を提出し内諾を得られたあと、退職届を提出するという流れです。しかし、退職を有耶無耶にされる、退職願を受け取ってもらえないなどの場合は、強い退職の意思を伝えるためにも退職届の提出を検討しましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職届を拒否されたら?雇用形態別に知っておきたい法律
退職届を受け取ってもらえない、拒否されたという状況は、原則として違法とみなされる可能性が高いです。ここでは、労働者が「有期労働契約」の場合と「無期労働契約」の場合で発生する違いについて、法律をもとに解説します。
「無期雇用労働者」の場合
「無期雇用労働者」とは、雇用期間の定めを設けない契約をしている労働者のことです。正社員や無期雇用のパート、派遣などが該当します。
この契約においては、「民法第627条」に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」とあります。
つまり、「無期雇用労働者」の場合、法的には退職日の2週間前までに退職を申し出れば、退職届を拒否されても退職できることになっています。
ただし、会社の就業規則として「退職日の1ヶ月前までに退職届を提出」などの規定を設けている場合が多いので、そちらもきちんと確認しましょう。
「有期雇用労働者」の場合
派遣社員や契約社員など契約の際にあらかじめ雇用期間が決まっている場合は、基本的に契約を全うしなければなりません。そのため、この契約期間中は会社側も労働者側も一方的に契約を解約することはできず、仮に退職届を提出したとしても、上司や会社が拒否権を発揮すれば契約終了までは勤務することになります。
ただし、「民法第628条」において「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」とされています。本人の病気や家族の介護など、やむを得ない事情がある場合は理解が得られることが多い傾向です。
退職の意思を伝えても労働契約が続く間は無断欠勤しない
退職の意思を伝えた後も条件を満たせず労働契約が継続する場合は、無断欠勤をしないよう注意が必要です。退職の意思を伝えた後も、退職までは労働契約が続いているため、会社の指示に従う義務が残ります。
この状態で無断欠勤をすると、企業側から懲戒処分を受ける可能性があり、最悪の場合、諭旨解雇や懲戒解雇となるケースも。懲戒解雇となると、退職金の減額や不支給といったリスクもあるため、会社との交渉が難航しても一方的に出社をやめるのは避けましょう。トラブルを防ぐためにも、退職の手続きを慎重に進めることが重要です。
退職届の拒否がパワハラの可能性がある3つのケース
退職の意思を伝えたあとに、会社側の態度に変化があったり明らかな嫌がらせ行為があったりすれば、パワハラに該当するかもしれません。以下で3つのケースを紹介するので、対処法とあわせて把握しておきましょう。
理不尽な損害賠償などを請求された
正当な理由もなしに「退職するなら損害賠償を請求をする」といった脅迫をしてくる場合は、聞き入れないようにすることが重要です。会社側が労働者に対して賠償金の請求を行うには、労働者による横領や情報漏洩などで会社が多大な損失を被っている必要があります。
1人で対応しきれないと感じる場合は、「賠償請求する」と言われた音声を録音したり、メールやチャットなどの文書を保存したりしておくと、第三者へ相談する際に役立つでしょう。
給与の支払い拒否を示唆された
労働者がいつ辞めるとしても、会社には働いた分の給与を支払う義務があります。しかし、「辞めるなら残りの給与を支払わない」と言われて引き止められるケースもあるようです。
そのようなことを言われた場合は、会社が本当に給与を支払わなかったときに備えて、シフト表やタイムカード、業務日報などの証拠を集めておきましょう。労働者は、退職後も未払い賃金の請求を行える権利を持っているため、退職してからでも請求できます。
退職届提出後に有給休暇の消化を拒否された
有給休暇の取得は「労働基準法第39条」で定められているとおり、労働者に認められた権利です。会社が労働者の有給休暇申請を拒んだり、申請したのに欠勤扱いにしたりすることは、違法行為に該当します。
万一に備えて、有給休暇の取得条件・取得状況が把握できる資料を手元に集めておくと安心です。
退職届を受け取ってもらえない場合の対応
退職届を提出しても会社に受理されない場合、対処法はいくつかあります。下記で解説するので、自分に合った方法で退職の手続きを進めていきましょう。
さらに上の上司もしくは人事に相談する
退職届を上司に拒否された場合は、直属の上司より上の上司へ相談するのが適切な対処法のひとつです。「退職届が受理されず困っている。今後どう対応すればよいか教えてほしい」と冷静に相談してみましょう。
それでも解決しない場合、人事や労務担当に話すのも有効です。人事は社内ルールや労働法に詳しく、公正な対応をしてくれる可能性が高いでしょう。相談時は、感情的にならず、事実を簡潔に伝えます。事前に話す内容を準備し、最後に感謝の言葉を添えることで、良好な印象を残せるでしょう。
上司の上司や人事への相談は、円滑に退職を進めるための大切なステップです。対応が得られない場合は、次の手段に進む判断材料にもなります。
内容証明郵便で退職届を郵送する
「どうしても手渡しでは退職届を受け取ってもらえない」「渡しても受け取っていないと言われてしまう」といった場合は、客観的な証拠を残すためにも、内容証明郵便を使って退職届を郵送する方法が可能です。
内容証明とは、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が送られたのかを公的に証明してくれる郵便のこと。通常の郵便より料金は高くなりますが、郵便局またはインターネットで手続きができます。郵便局から相手に直接手渡しで配達されるため、「受け取っていない」「投函されていなかった」などの言い訳ができないところが利点です。
退職届が受理されたかわからない!とならないために
「郵送したけど、受理されたかわからない」という事態を避けるには、「配達証明」というサービスをあわせて利用するのがおすすめです。配達証明を利用することで、相手に郵便物を配達したという事実を証明してもらえます。
後日、相手が郵便物を受け取った日時が記載された「郵便物等配達証明書」というはがきが届くので、大切に保管しておきましょう。
労働基準監督署などの公的機関へ相談する
退職届を受け取ってもらえない場合、労働基準監督署や労働局へ相談しましょう。労働基準監督署には、職場でのトラブルに関する相談を受け付ける「総合労働相談コーナー」が設置されています。
退職届の受け取り拒否をはじめ、解雇や賃金の引き下げ、嫌がらせ、パワハラなどさまざまな分野の労働問題について、専門の相談員に面談もしくは電話で対応してもらえます。
相談のなかで労働基準法などの法律違反の疑いがあると判断された場合は、会社へ助言・指導してくれるケースもあるので、迷ったら一度相談してみましょう。
弁護士に相談してみる
退職届を拒否されても、「これ以上は嫌がらせされるかもしれない」「退職後に必要な書類をもらえないかもしれない」といった不安からなかなか行動に移せない方もいるのではないでしょうか。そのような場合は、労働問題に特化した弁護士に相談するのも一つの手です。
労働者の代理人として、弁護士が法的観点から企業を説得するほか、未払いの給与や退職金などの請求、退職届を受理されないといった嫌がらせやパワハラといった不法行為に対する賠償請求にも対応してくれるでしょう。
まとめ
退職届を上司が受け取ってくれないときは、まずはその上の上司に相談しましょう。それでも解決しなければ、人事や総務といった部署に問い合わせます。
会社として受け取らない姿勢であれば、内容証明による郵送や弁護士の介入も検討してください。
ただし、「雇用期間の定めがある契約の途中で退職を希望している」など、退職を希望する側の法律やルールが守れているかも確認する必要があるでしょう。
「なんとか退職できたけど転職活動をスタートしていない」「次はトラブルのない企業で働きたい」という希望があるなら、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブは、求人紹介をする企業すべてをしっかりと調査しているエージェント。企業風土もしっかりと把握しているので、ご相談者にぴったりの企業を紹介できます。ミスマッチのない転職を希望するなら、ぜひご利用ください。
退職届に関するお悩みQ&A
ここでは、退職届に関する疑問をQ&A方式で解決します。退職届について疑問がある方は参考にしてみてください。
退職理由がどのようなものであっても、労働者が法律や就業規則に則って提出していれば、会社側の都合で退職願や退職届の拒否はできません。なるべく円満に退職するためにも、退職を願い出る前に、一度就業規則や雇用契約書などを確認しておくとスムーズです。
退職届を提出後撤回したいです…会社に拒否されることはある?
「民法第540条」によると、会社側は退職届の撤回要求に応じる必要はないとされています。
これは、片方の意思だけで契約を解約できるとき、その意向が二転三転してもう片方に不利益をもたらすことを避けるためです。退職願・退職届はどちらも一度提出すると退職の意思があると判断されるため、よく考えてから提出しましょう。
参照元
e-Gov法令検索
民法
内容証明で退職届を送るのは、証拠を残したいときには有効ですが、通常の退職には不向きです。費用がかかるうえ、文面に制限があり作成も複雑。また、強い意思表示と受け取られやすいため、会社との関係が悪化する恐れもあるでしょう。送っても退職が確実になるとは限らず、拒否された場合は労基署や弁護士の対応が必要になることもあります。トラブル時の手段としては有効ですが、円満退職を望むなら、通常の提出方法を選びましょう。
「人手が足りないから」と引き止められたり、「自分が辞めたら周りの人に迷惑がかかる」と考えて退職をためらったりするケースもあるようです。しかし、人手不足によって退職拒否をする行為は会社の問題であり、引き止められても退職可能です。「転職したいけど、会社が人手不足でなかなか転職活動ができない」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブをぜひご利用ください。専任のキャリアアドバイザーが就職・転職活動をバックアップいたします。