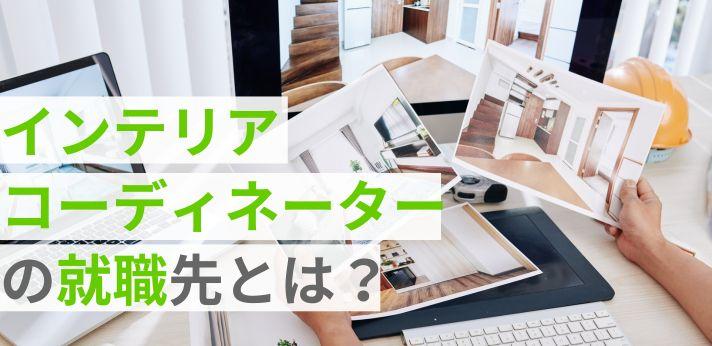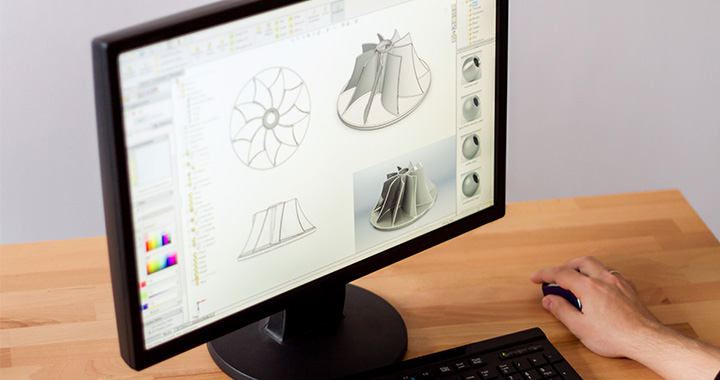検品の仕事内容を解説!向いている人の特徴や正社員としての就職事情も紹介
更新日
公開日
検品の仕事内容は、商品の品質確認や数量や種類に間違いがないかのチェックなど
検品の仕事内容が分からないため、「きついって本当?」と疑問を感じる方もいるでしょう。検品の主な仕事内容は商品の品質チェックや数量に間違いがないかを確認することです。立ちっぱなしの作業や倉庫内の荷物の運搬といった力仕事もあるため、人によっては「きつい」と感じることもあるようです。このコラムでは、検品の仕事内容や向いている人の特徴などを解説するので、理解を深めて就職や転職を叶えましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
検品の仕事内容とは
検品の仕事内容は、商品の品質の確認や数量、重さ、種類に間違いがないかのチェックです。扱う製品は飲食物から衣料品、電化製品、玩具までさまざま。飲食物の場合は、異物が混入しているものや傷んでいるもの、製品なら破損や汚れのあるものを除いてパッケージやダンボールに詰めていきます。
ショップ店員やコンビニ店員などが店舗に商品を入荷した際に、数や種類に間違いがないか確認する作業も検品と呼ばれます。
製造業の検品の仕事内容
製造業における検品には、「入荷検品」「工程間検品」「出荷検品」があります。
| 入荷検品 | 工場に納品される原材料のチェック。数量や品番が発注書と合っているかを確認します。 |
|---|
| 工程間検品 | 製造の工程で行われる中間チェック。完成前に一度チェックすることで、大きなミスを防止します。 |
|---|
| 出荷検品 | 完成した商品にキズや異物混入、動作不良がないかをチェック。目視のほか、電源を入れて動作確認も行います。 |
|---|
製造業の検品作業は工場のライン作業が多く、ベルトコンベアで流れてくる商品を確認して不良品を取り除きます。異物混入のチェックでは、機械が使われる場合もあるようです。
物流業の検品の仕事内容
物流業における検品の仕事内容を大きく分けると、「入荷検品」と「出荷検品」になります。
| 入荷検品 | 倉庫に届いた物の数量・規格・品質をチェック。発注書に照らし合わせて、型番が合っているかも確認します。 |
|---|
| 出荷検品 | 出荷前に破損や汚れ、数量などをチェック。注文書どおりに商品がセットされているか確認して梱包します。 |
|---|
物流業では、取引する企業数も扱う物の種類も多く、さらに出荷先も多岐に渡ります。入荷・出荷がミスなく行われるためには、検品をしっかりと行うことが重要です。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
検品の種類とそれぞれの仕事内容
検品の仕事内容を細分化すると、いくつかの種類に分かれます。製造業でも物流業でも扱う商品によって検品の仕事内容は異なりますが、おおむね以下のいずれかに該当するでしょう。
この項では、6種類の検品作業を紹介するので、実際にどのような仕事をするのか把握するための参考にしてみてください。
不良検品
不良検品の仕事内容は、商品にキズや汚れ、形状不良などがないかを確認して仕分ける作業です。塗装ムラや異物の付着、印字ミスなどについても確認します。
検品方法は目視のほか、触って異常がないか確認したり、拡大鏡で細かい部分を見たりする場合もあるようです。
作動検品
製品が仕様どおりに正常に動作するかを確認します。主に機械や電気製品、電子機器などが対象です。電源を入れて正常に動くか、異音がしないかといった点をチェックします。
また、デバックと呼ばれる新開発のアプリやゲームの不具合チェックなども作動検品の一つです。
混入検品
商品やパッケージのなかに異物が入っていないかを確認するのが混入検品です。特に、食料品や医薬品、化粧品で重視されます。これらの商品にゴミや金属片などが混入し、ユーザーの手に届いてしまうと、健康被害などにつながるリスクがあるため、目視だけでなく機械を用いて詳細にチェックされることが多いです。
計量検品
製品の重さが規定値と一致しているかを確認します。食料品や医薬品などでは、「個包装ごとの数量が合っているか」「既定の量を超えていないか」といったチェックを行うのが計量検品の仕事内容です。
数量検品
注文数と入出荷数が合っているかを確認するのが数量検品です。発注書と納品伝票を照合し、そのうえで実際の数が合っているかを確認します。数を間違えると帳簿と実在庫にズレが生じ、決算時に処理しなければなりません。
また、営業担当者が顧客から注文を受け、実は在庫が足りなかったとなると大事です。数量検品は単純作業ではあるものの、重要や役割を担っているといえます。
出荷検品
商品を出荷する前に、数量や梱包に問題がないかを最終確認するのも検品の仕事内容の一つ。ここで見落としがあると、誤った商品が顧客に届いてしまうため重要な工程です。
「ここまでに数々の検品を通過しているのだから大丈夫」と甘く考えると重大な過失につながる可能性があるため、最後まで気を引きしめて確認する必要があります。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
検品作業の1日の流れ
この項では、検品作業の1日の流れを紹介します。検品の作業現場は工場や倉庫なので、駅から離れていることが多いです。そのため、通勤用のバスが出ている職場もあります。
| 9:00 業務開始 | 制服に着替えてクリーンルームで滅菌する |
|---|
| 9: 30 | 検品を開始
集中力が必要な ため、適宜休憩を取りながら作業を進める。連携が必要な作業の場合、グループで一斉に休憩を取る。 |
|---|
| 12:00 | 休憩 |
|---|
| 13:00 | 検品を再開 |
|---|
| 17: 30 | 検品現場の清掃・整理整頓を行い、作業を終了 |
|---|
食料品や医薬品を扱う場合は、マスクや手袋も着用します。また、1日の検品数にノルマがある場合もあるようです。ただし、検品の仕事は見落としなくチェックすることが大事なので、過度なノルマは課せられないのが一般的でしょう。
検品の仕事の効率性を上げるコツ
検品の仕事で効率性を上げるには、まずは時間をかけて丁寧に仕事を覚えることが重要です。最初にしっかりと手順を覚えれば、自然とスピードが上がっていきます。マニュアルに沿って基本的な作業ができるようになってから、自分なりの工夫を加えてください。
1.最初は丁寧に仕事を覚える
まずは一つ一つの作業を丁寧に覚えましょう。検品の仕事はスピードも大事ではありますが、それよりも「ミスをしない」「確実にチェックする」ことが重要です。作業のスピードを上げても、ミスがあると検品をやり直さなければならず、結果的に時間がかかってしまいます。
慣れるまではしっかりと時間をかけることが、効率アップにつながるでしょう。
2.マニュアルを守る
検品作業の効率性を上げるためには、マニュアルを守ることも大切です。マニュアルを確認せずに、自己判断で作業を進めると余計な手間がかかったり、ミスが増えたりする原因になります。マニュアルは、誰もが一定の成果を出せるようにするための手順書であると理解しましょう。
3.自分の苦手ポイントを把握する
自分の苦手なポイントを把握しておくと、ミスを防止でき効率的に検品作業を進めやすくなります。たとえば、上司から注意されたことや、危うく見落とすところだったことなどを覚えておき、自分の担当作業の最後に必ず確認することを組み込んでおきましょう。
4.自分なりのやり方を掴む
検品作業の効率が上がる、自分なりのやり方を見つけるのもおすすめです。たとえば、道具の配置や、時間単位のノルマを自分で設定するなど、オリジナルの工夫をしてみましょう。
5.違和感があったらすぐに声をかける
作業中に少しでも違和感があったら、周りの人に声をかけて確認しましょう。「何か変だな」と思った段階で対処すれば、問題が小さいうちに解消できるのでさほど時間もかかりません。
一方、違和感を放置してしまい、事態が大きくなってからリカバリーしようとすると、検品作業が止まってしまうことも。何事もなければそれで良いので、気づいたことは報告するのが大切です。
検品の仕事でありがちなミスと対策
検品の仕事では、慣れないうちに起こる失敗と、慣れたために起きやすい失敗があります。慣れないうちの失敗は、仕事のコツを掴むことで少しずつ減らせる可能性が高いです。一方、慣れたために起きやすい失敗は、改善のために工夫が必要といえます。
検品作業はルーティンワークが中心のため、気を抜くと失敗しやすい側面も。ありがちな失敗を把握しておくことで、対策を打ちやすくなるでしょう。
1.よく似た品物を間違える
検品の仕事では、形や品番がよく似た商品を扱うことも多いです。慣れないうちは見分けがつかず、数量検品でミスしてしまうこともあるでしょう。
このような失敗を減らすには、先輩社員にコツを教えてもらったり、慣れるまではダブルチェックをしてもらったりするのがおすすめです。見分け方が分かれば失敗しなくなるので、それまでは周囲に協力をお願いしましょう。また、教えてもらったことをリストにして、検品の際に一つ一つ確認するなどの工夫も必要です。
2.不良品を見落とす
仕事に慣れてくると流れ作業になり、不良品を見落としてしまうこともあります。また、疲れが溜まると小さな異物やキズに気づきにくくなることも。
こういった失敗を防ぐためには、「ミスは起きるもの」という前提で自分に厳しい目を向ける姿勢が必要です。また、集中力が切れる前に小休憩を取るなどの対策も行いましょう。
3.作業の順番を間違える
作業の順番を間違えてしまったことが、大きな失敗につながる場合もあります。「マニュアルは頭に入っているから大丈夫」と過信した結果、手順の確認をおろそかにしてしまうことで起こる失敗といえるでしょう。
作業の手順を間違えないためには、始業前に毎回マニュアルを確認したり、定期的に見直したりすることが大切です。
検品の仕事を選ぶメリット
検品の仕事を選ぶメリットとして、未経験歓迎の求人が多く挑戦しやすいことや、仕事を覚えやすいことが挙げられます。そのため、就職に不安があり「まずは働くことに慣れたい」と考えている方にはおすすめの仕事の一つ。また、現在仕事がある方は、まずは副業として始めることも可能といったメリットもあります。
未経験歓迎の求人が多い
検品の職に就くために特別な資格やスキル、経験は必要ありません。また、検品の仕事は常に需要があり、未経験でも募集している場合があるので、比較的挑戦しやすい職種といえます。
働いた経験がない方や、長期間のブランクがある方など、仕事を始めることに不安がある方は正社員へのステップとして選択するのもおすすめです。
仕事を覚えやすい
前述のとおり、検品の仕事にはマニュアルが用意されていることが多いので、仕事を覚えやすいのもメリットの一つです。経験年数が増えれば難しい作業を任される可能性もありますが、最初は簡単な作業から始めることが多いでしょう。
仕事に慣れていない方も挫折するリスクが少なく、できることが徐々に増えていくのでモチベーションが上がりやすいといえます。
私生活と両立しやすい
検品の仕事は残業が少ない傾向にあり、私生活との両立がしやすいでしょう。また、正社員のほかに派遣社員やアルバイトとしての採用も多いので、育児などでフルタイム勤務は難しいという方は自分の都合に合わせた働き方を選ぶのも一つの方法です。
副業としてもやりやすい
検品の仕事は覚えやすく、負荷がそれほど重くないため副業としてもやりやすいでしょう。夜間勤務のある工場や倉庫なら、本業の仕事が終わったあとに働けます。
「本業の収入だけでは少し足りない」「ボーナスのつもりで副収入を得たい」という方におすすめです。
検品作業がきついって本当?仕事の大変さ
「検品作業はきつい」と聞いて不安に思う人もいるでしょう。検品作業は、製品の品質を守り、クレームやリスクを未然に防ぐための「最後の砦」として責任を背負う側面も。常に正確さと注意力が求められるので、プレッシャーを感じる可能性もあります。
この項では、検品の仕事の大変さを紹介するので、あらかじめ把握したうえでそれでも挑戦してみたいか考えてみてください。また、検品作業の実態を把握したい方は、口コミサイトを確認したり、就職・転職エージェントに相談したりする方法もあります。
集中力と正確性が求められる
検品の仕事は同じ作業の繰り返しでありながら、集中力と正確性が求められるのが大変なところです。前述のとおり、ミスをしないことが重要なので、小さなキズ、微妙な色の違い、混入物などを見逃さない集中力が常に求められます。
疲れて集中力が切れそうになったとき、気持ちを切り替えて作業を続けなければならないことに苦労する人もいるようです。
立ち仕事が多い
検品作業の多くは、立ったままの作業になります。ベルトコンベアや検査台の前に立ち続けるため、身体への負担が大きいでしょう。
体力に不安がある方は、休憩の取り方や作業用の椅子が使えるかどうかを確認するのがおすすめ。作業員の負担軽減に力を入れている職場であれば、それほど心配しなくても良い可能性があります。
検品の仕事に向いている人の3つの特徴
検品作業はラインでの単純作業を長時間続けることが多い傾向にあるので、特に集中力や注意力のある方に向いていると考えられます。この項では、検品の仕事に向いている人の特徴を紹介するので、自分に適性があるか確認してみましょう。
1.ルーティンワークを楽しめる人
先述したように、検品作業は同じ作業を繰り返すルーティンワークが中心です。毎日似たような工程をこなすため単調に感じることもありますが、自分なりにやりがいや楽しさを見つけられる人は検品の仕事に向いています。
たとえば、自分なりの目標を立ててタイムトライアルのように取り組むといった工夫ができる人は、ルーティンをポジティブに捉える力があるでしょう。
2.黙々と行う作業でも集中力が切れない人
長時間にわたり静かに作業を続けても集中力が切れない人は、検品の仕事に向いています。検品の仕事は周囲との会話が少なく、1日のなかで緩急がつきにくい側面も。そのため、集中力のオンオフで仕事のリズムを作る人にとってはやりにくい環境です。
反対に、一定のリズムを保ったほうが集中力が切れにくい人は、検品作業で重宝されます。
3.細かいところに気がつく人
検品の仕事では、ちょっとした違いを見逃さない能力が必要です。日常生活でもほかの人が気づかないような微妙な変化にすぐ気がつく人や、異変に対して先回りして対処できる人は検品の仕事に向いているでしょう。
検品の仕事に就くには
検品の仕事はアルバイトや派遣社員といった非正規雇用での募集が多く、正社員の場合は入出庫や在庫管理なども含めて行うのが一般的です。したがって、軽作業全般や製造ライン全体に関わる職種を探すことで、選べる求人の幅が広がるでしょう。
また、場合によっては自動車やフォークリフトなどの免許があると、仕事の幅が広がる可能性もあります。
検品の求人の探し方
検品を含めた倉庫作業員や事務職の求人は、転職サイトやハローワーク、就職・転職エージェントなどで探せます。また、アルバイトから正社員へ登用を目指せる場合もあるようです。
応募先を選ぶ際は、基本給のほか資格手当や役職手当の有無などを確認しましょう。また、工場や倉庫は土日休みのところもあれば、24時間稼働している場合もあるので、その点も確認が必要です。
求人情報で確認すべきポイントは?
まずは雇用形態を確認しましょう。「求人情報の見方とは?理想の職場へ就職するために見るべきポイントを解説!」で紹介しているように、求人情報に書かれている雇用形態には、「正社員」「契約社員」「派遣社員」「アルバイト・パート」などがあります。正社員以外は雇用契約に期限があるため、定年まで働けるわけではありません。アルバイトから正社員を目指したい方は、「正社員登用あり」と記載があるかをチェックしましょう。
そのほか、給与形態にも「基本給」「固定給」「年俸制」といったさまざまな記載があり、理解していないと「思ったより手取りが少ない」といった事態に陥ることも。ミスマッチを防ぐためにも、転職に慣れていない方は就職・転職エージェントを活用することを検討してみてください。
求人探しについて疑問があれば、ハタラクティブへお気軽にご相談くださいね。
ハタラクティブキャリアアドバイザー
後藤祐介 出荷・荷受けの事務職の年収
ここでは、検品作業を含む仕事の例として、「出荷・荷受事務」を紹介します。
厚生労働省が運営する職業情報提供サイト(job tag)によると、検品作業を含む「出荷・受荷事務」の平均年収は約520万円です。
「出荷・荷受事務」の就業先は倉庫や工場のほか、運送会社が物流センターも含まれます。検品以外に担当する業務としては、物流/在庫管理でデータ入力を行ったり、送り状や納品書の発行をしたりすることが多いため、PCスキルがあると望ましいでしょう。
検品の仕事の志望動機を作成するポイント
1人で考えるのが難しい場合は、就職・転職エージェントに相談してみるのもおすすめ。キャリアアドバイザーが応募先に合った効果的な書き方、伝え方を教えてくれるでしょう。
経験者の場合
経験者の場合は、前職での経験や培った技術などを採用担当者にアピールしましょう。また、その現場の業務内容をよく確認し、どのように経験を活かしていけるかも伝えるよう意識するのが大切だといえます。
未経験者の場合
検品の仕事は特別な資格やスキル、経験などは問われない傾向にある職種です。責任感や集中力がある点などを、自分のエピソードを交えて具体的にアピールしましょう。
また、扱っている製品などについて興味や知識がある場合は、明確な志望動機になります。
「検品の仕事をやってみたい」「物流業界に興味がある」という方は、ハタラクティブに相談してみませんか。
就職・転職エージェントのハタラクティブは、既卒やフリーターなどの若年層に向けた就職・転職支援サービスを行っています。経験豊富なキャリアアドバイザーが、求職者一人ひとりに丁寧なヒアリングを行い、希望や適性に合った求人をご紹介。そのため、「思っていた仕事内容とは違う」と感じるリスクを減らせるメリットがあります。応募書類の作成や面接対策などのサポートを無料で受けられるので、ぜひお気軽にご相談ください。