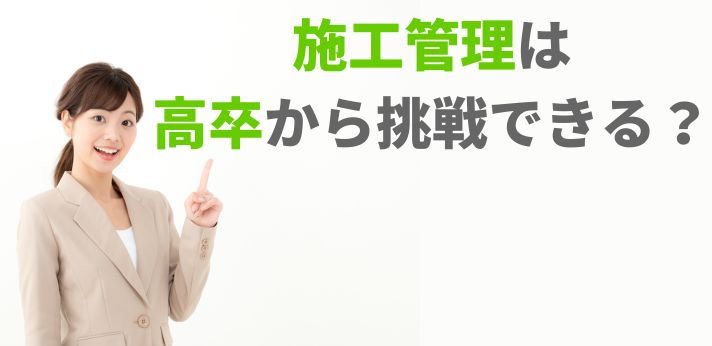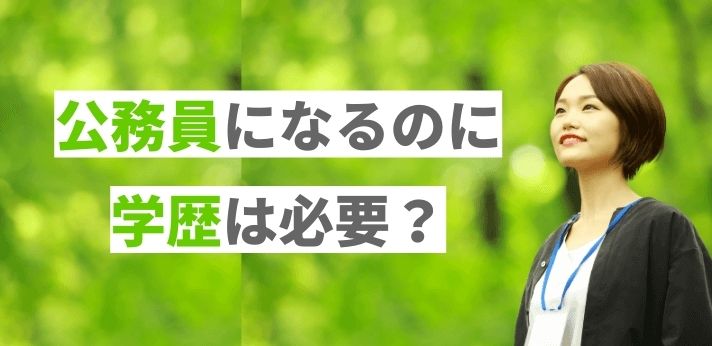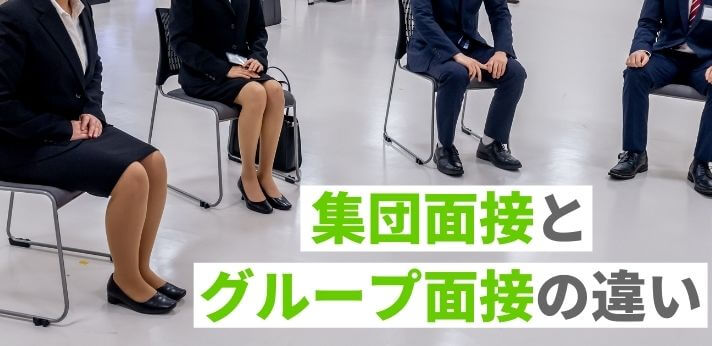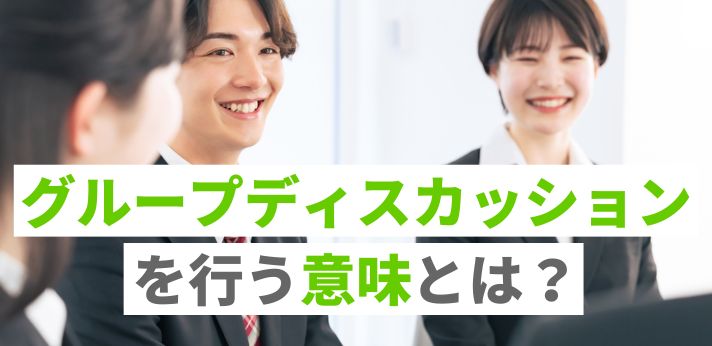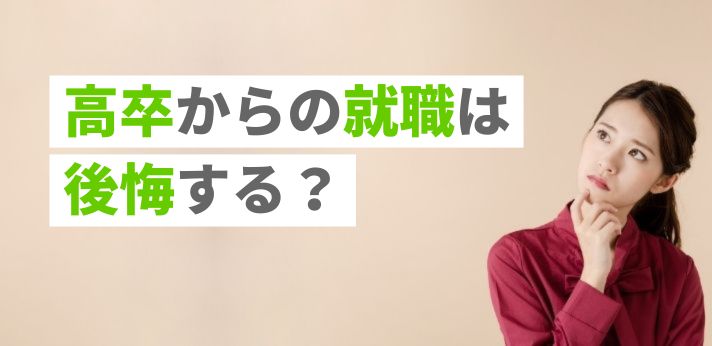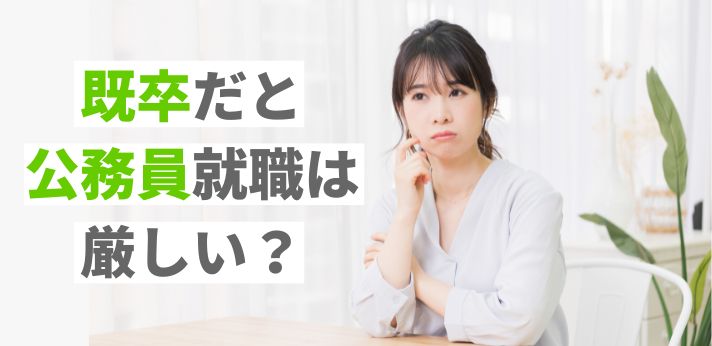高卒者が公務員になるには?年収や試験内容・対策方法を解説高卒者が公務員になるには?年収や試験内容・対策方法を解説
更新日
公開日
高卒者も受験可能な試験があるため、合格すれば公務員になれる
高卒から公務員になりたいと思い、試験内容や日程を調べている方もいるのではないでしょうか。高卒の方も、試験に合格すれば公務員になることは可能です。 勉強の計画をきちんと立てて、過去問を繰り返し解き、準備を万全にして臨みましょう。
このコラムでは、高卒から公務員になる方法や目指せる種類、試験内容などをご紹介します。また、初任給や年収など気になる給与の話もまとめました。公務員の仕事が自分に向いているか確認したい方は、ぜひご一読ください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
高卒者は公務員になれる?
公務員は「大卒以上の学歴が必要」というイメージをもつ方もいるでしょう。しかし、高卒者が受験可能な公務員試験に合格すれば、高卒から公務員になることは可能です。
高卒も受験可能な試験がある
高卒者も受験可能な公務員試験は存在します。公務員試験の受験資格に学歴は定められていないため、「高卒程度区分」の試験はもちろん、「大卒程度区分」の試験も場合によっては受験が可能です。
しかし、「大卒程度区分」は「高卒程度区分」と比べて試験内容が難しく、大卒者も受験することを踏まえれば合格を目指すのは簡単ではないでしょう。
大卒よりも高卒の試験のほうが難易度が低め
「高卒程度区分」の試験は「大卒程度区分」の試験よりも難易度が低めです。高卒程度区分の筆記試験は教養試験のみのケースが多い一方、大卒程度区分では教養試験に加えて専門試験が課されるケースもあります。
出題範囲が狭く対策しやすいのは、高卒程度区分の試験のメリットといえるでしょう。
年齢制限に注意する
公務員試験には年齢制限があるので、高校を卒業して時間が経っている場合は注意しましょう。自治体では、高卒程度試験の年齢制限を「17~21歳まで」のように低めに設定していることがあります。上限の年齢を超えてしまうと試験は受けられません。
一方、大卒程度の年齢の上限は「30歳」と定めている自治体が多く、高卒程度よりも年齢制限の幅が広いのが特徴です。上限を超えていなければ、高卒者も大卒程度試験を受験できます。
しかし先述のとおり、大卒程度の試験は難易度が高めです。できるだけ若いうちに高卒程度試験の合格を目指すのが賢明といえます。
試験対策をしっかりする
高卒程度試験は大卒程度試験よりも難易度が低めなぶん合格倍率が高くなりやすいため、試験対策が必須です。公務員試験では、数学や社会などの科目である一般知識だけでなく、数的処理や文章理解といった一般知能が判断される問題も出題されます。問題に慣れていないとスムーズに解けない可能性があるため、参考書や過去問などを使って対策をしておきましょう。
また、公務員試験の実施は通常年に1回なので、勉強を始める時期によっては時間が足りなくなってしまう可能性があります。試験日までの日数を考慮して、試験対策のスケジュールを立てることが重要です。
高卒の国家公務員(一般職)採用数は大卒者より少ない
人事院の「図 1-3令和 5 年度における職員の採用状況(p.102)」によると、国家公務員の「一般職」の採用人数は大卒が3,509人、高卒が1,511人でした。大卒は全体の15.1%、高卒は全体の6.5%を占めています。
なお、国家公務員の「専門職」の採用人数は大卒が1,957人、高卒が2,161人です。専門職の場合は、大卒よりも高卒のほうが採用人数が多くなっています。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
高卒から公務員になる方法
ここでは、高卒から公務員になる方法を詳しく解説します。
受験資格を満たしている公務員試験を受験する
高卒から公務員になるためには、公務員試験を受験して合格する必要があります。高卒者が受験可能な公務員試験は、「高卒程度区分」「大卒程度区分」「社会人経験者採用」の3つです。
それぞれの特徴や違いについて理解しておきましょう。
高卒程度区分と大卒程度区分
高卒程度区分と大卒程度区分は、「受験できる年齢」「試験内容」「給与」といった点に違いがあります。
| | 高卒程度区分 | 大卒程度区分 |
|---|
| 受験できる年齢 | 17~21歳のように低めに設定されている場合が多い | 30歳までとされている場合が多い |
|---|
| 試験内容 | 高校で学ぶ範囲
※高卒者も大卒程度区分の試験を受験できるが、経済や法律といった専門試験が出題されるため、高卒程度区分よりも広い範囲の知識が必要 | 大学で学ぶ範囲 |
|---|
| 給与 | 高卒よりも高く設定されている |
|---|
社会人経験者採用
高卒・大卒程度区分のほかに社会人経験者採用を実施している自治体もあり、受験要件によっては高卒者も受験可能です。受験要件は「民間企業での職務経験が5年以上」といった職務経験を求められるのが一般的であり、年齢制限は「59歳未満の者」「満28歳以上59歳未満の者」など自治体によって異なります。
高校を卒業して間もない場合は、社会人経験者採用は受験できない可能性が高いものの、将来的な選択肢として視野に入れておくのもおすすめです。
地方公務員の試験には「専門・短大卒程度」もある
地方公務員の試験では、高卒・大卒程度のほかに「専門・短大卒程度」も存在します。「専門・短大卒程度」の試験も、自治体が定める受験要件を満たしていれば高卒者も受験可能です。
ただし、自治体によっては「専門・短大卒程度」の試験を行っていない場合も多いので、受験を考えている際はよく確認しましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
高卒が目指せる公務員の種類
高卒が目指せる公務員の種類は、「国家公務員」「地方公務員」の2つです。どちらの公務員を目指すかは、希望する職種を見据えて検討してみましょう。
以下で、「国家公務員」「地方公務員」の種類と職種についてご紹介します。
国家公務員
国家公務員は中央省庁や地方機関などに勤務し、国の政策に関わる仕事を担います。国家公務員の職種は、「一般職」と「特別職」の2種類です。一般職は行政に関わる事務の仕事をメインに担当し、特別職は政治に直接関わる業務を行います。
- ・内閣総理大臣
- ・大臣
- ・国会議員
- ・日本学士院会員
- ・防衛省の職員
- ・裁判官
国家公務員の特別職では、大卒レベルの知識が求められることが多いので、希望する場合は事前によく確認しましょう。
地方公務員
地方公務員の仕事は、地方自治体などに勤務し、地域住民の暮らしを支えること。職種は、大きく分けると「一般職」と「特別職」の2種類で、それぞれ以下のような職種が挙げられます。
| 一般職 | 特別職 |
・県庁職員
・市区町村の役所職員
・警察官
・消防士
・教師 | ・都道府県知事
・地方議員 |
地方公務員・高卒程度区分の試験日程
高卒程度区分の地方公務員の一次試験は、毎年9月の下旬に実施されます。早い自治体では5月ごろから受験案内の配布を始めるため、時期が近づいたら自治体のWebサイトをチェックしましょう。
高卒で受験できる公務員試験の概要
国家公務員と地方公務員の役割や試験の種類は異なります。違いを知りたい方は、以下でそれぞれの仕事内容や試験の詳細を確認しましょう。
国家公務員と地方公務員の試験の種類
国家公務員の試験は、「総合職」「一般職」「専門職」「その他」の4つに分類されます。国家一般職では高卒者試験が行われますが、国家総合職では院卒者試験と大卒程度試験のみ実施。高卒者が大卒程度の試験を受けることは可能ですが、受験者が多いため合格倍率が高いのが特徴です。
一方、地方公務員の試験は、「大卒程度」「専門・短大卒程度」「高卒程度」の3種類に分けられます。ただし先述したように、自治体によっては「専門・短大卒程度」は設けていない場合もあります。自治体ごとに受験要件も異なるため、事前に確認が必要です。
年齢制限以外の要件
公務員試験には、年齢制限のほかにも、「共通要件」「学歴要件」「資格要件」「身体要件」といった要件があります。年齢制限をクリアしていても、ほかの要件を満たしていない場合は公務員試験を受験できない可能性が高いため、内容をチェックしておきましょう。
試験内容
高卒者が受験できる公務員試験の内容は職種や自治体によって異なりますが、多くの場合は一次試験と二次試験があります。公務員試験の一次試験では筆記テスト、二次試験では面接試験が行われるのが一般的です。
| 一般教養試験 | 一次試験 |
|---|
| 適性試験 | 一次試験 |
|---|
| 作文試験 | 一次試験 |
|---|
| 面接試験 | 二次試験 |
|---|
1.一般教養試験
英語・国語・数学・理科・社会の教養を問う問題と、職種ごとの専門的な問題が出題されます。出題形式は、記述式と選択式の両方です。
2.適性試験
性格を判断するものや、単純計算などの事務処理能力を問う問題が出題されます。
3.作文試験
「コミュニケーションのなかで心掛けていること」「挑戦した結果、得られたもの」といったさまざまなテーマが与えられます。
4.面接試験
一次試験に合格したら、二次試験に進み面接試験を受けます。面接の形式は、個人面接、集団面接、グループディスカッションなどが一般的です。
個人面接は、受験者1人に対して複数人の面接官が対応する形式。強みや志望動機、就職してやりたいことなどを質問される傾向にあるようです。
集団面接は、受験者と面接官がそれぞれ複数人いる面接形式。受験者は面接官の質問に対して、挙手制や指名制で回答します。
グループディスカッションは、5〜10名ほどのグループに分かれて討論を行うのが一般的です。与えられた課題に対して意見を出し合ったり、面接官に考えを発表したりします。
高卒公務員の給与
「高卒公務員の給与はどのくらい?」と気になる方に向けて、初任給と年収を紹介します。
高卒公務員の初任給
人によって金額は異なりますが、高卒の国家公務員は18万円前後、地方公務員は16~17万円ほどが初任給の目安となるでしょう。
高卒・大卒の国家公務員の年収
| 経験年数階層 | 高校卒 平均給与額 | 大学卒 平均給与額 |
|---|
| 1年未満 | 18万3,769円 | 21万492円 |
| 35年以上 | 40万8,039円 | 44万6,437円 |
平均初任給額は高卒者で約18万、大卒者で約21万円です。上記の平均給与額に12を掛けて年収に換算すると、国家公務員歴が1年未満の場合、高卒者の年収は約220万円、大卒者の年収は約252万円となります。
また、35年以上勤めたときの高卒公務員の平均給与は約40万円で、大卒者の場合は約44万円。先ほどと同じように年収に換算すると、35年以上勤めた場合の高卒者の年収は約490万円、大卒者の年収は約535万円です。
以上から、高卒で国家公務員になった方の年収は、勤続年数に関わらず大卒者よりも低いことが分かります。
なお、給与は人によって差があるほか、公務員の場合はこの数値に賞与が加算されるのが一般的なため、実際の年収は計算した金額と異なる場合があります。
高卒・大卒の地方公務員の年収
| 経験年数 | 高卒 | 大卒 |
|---|
| 1年未満 | 16万9,762円 | 20万48円 |
|---|
| 35年以上 | 38万5,329円 | 39万6,993円 |
|---|
勤続年数が1年未満の平均給与額は、高卒の場合は約16万円、大卒の場合は約20万円です。平均給与額に12を掛けて年収に換算すると、地方公務員歴が1年未満の場合、高卒者の年収は約202万円、大卒者の年収は約250万円となります。
また、高卒で35年以上勤めた場合の平均給与は約39万円、大卒の場合は約43万円です。先ほどと同じように12を掛けて年収を計算すると、高卒で35年以上勤めた場合、高卒者の年収は約474万円、大卒者の年収は約522万円。
実際に支給される給与額や賞与によっては計算した年収と異なる場合がありますが、地方公務員の場合も高卒者の年収は大卒者と比べると低いといえるでしょう。
高卒公務員の昇給と賞与(ボーナス)
公務員の昇給には「定期昇給」と「昇格による昇給」の2つがあります。
「定期昇給」は1年に一度昇給するのが一般的で、多くの場合1月もしくは4月に昇給します。いくら昇給するかは評価によって異なるでしょう。
「昇格による昇給」とは、能力が評価されて給料が上がる制度です。昇給の時期は職種によって異なります。法令や規則によって厳密に決まっているため、気になる方は調べてみましょう。
また、公務員は賞与(ボーナス)も受け取ることができます。時期にもよりますが、月給の2~4ヵ月分が賞与として支給されることが多いようです。
高卒で公務員として就職するメリット・デメリット
高卒で公務員になりたいなら、メリット・デメリットの両面を把握しておきましょう。公務員には手厚い待遇や雇用の安定性がメリットとして挙げられますが、キャリアアップや転職が難しいといったデメリットもあります。それぞれを理解したうえで公務員を目指すかどうかを検討しましょう。
高卒で公務員として就職するメリット
高卒で公務員に就職するメリットには、「大学の費用がかからない」「手厚い待遇が受けられる」「雇用が安定している」などが挙げられます。それぞれのメリットについては、以下をチェックしてみてください。
大学の費用がかからない
専門学校や大学などに進学するには、受験費や学費、生活費など高額な費用を捻出する必要があります。費用を奨学金から工面する場合は卒業後に返済しなければなりません。
しかし、進学せずに高卒で公務員になれば進学に必要な費用がかからず、いち早く自立した生活を送れる点がメリットといえるでしょう。
手厚い待遇が受けられる
高卒で公務員になると、手厚い待遇が受けられるのもメリットです。国や自治体は民間企業の手本となる必要があることから、率先して各種制度を整えている傾向にあり、公務員の福利厚生は充実しているといえます。
たとえば、女性公務員の場合は、出産すると育児休暇を最長で3年取得できます。男性公務員も、育児参加休暇や配偶者出産休暇の利用が可能です。女性・男性ともに、公務員になると仕事と子育てが両立しやすくなると考えられるでしょう。
さらに、住居手当や賞与、退職金の支給などもあるため、経済的に安定した生活を送れる可能性が高まります。
雇用が安定している
公務員の給与は納税された税金で賄われており、民間企業の給与は会社の売上から捻出されているのが一般的です。そのため、景気の悪化や情勢の影響によってリストラになる可能性がある民間企業と比べると、公務員は雇用が安定しているといえるでしょう。
また、公務員は勤続年数に伴い昇給するため、将来的に安定して生活できる点もメリットといえます。
高卒で公務員として就職するデメリット
高卒で公務員として就職するデメリットには、「キャリアアップや昇給がしにくい可能性がある」「転職や独立が難しいことがある」などが挙げられます。「若いうちから高収入を目指したい」「いつか自分の店を出したい」といった考えがある場合は、以下を参考に公務員になるかを検討してみましょう。
キャリアアップや昇給がしにくい可能性がある
公務員は、昇格の条件として在籍期間が定められている場合が多く、年功序列のため、キャリアアップや収入アップを目指しにくいといえます。「早期からキャリアを築いていきたい」と考えている方にとっては、すぐにキャリアアップを目指せない点はデメリットと感じるでしょう。
また、就職後すぐに給与アップを目指すのも難しいといえます。どれだけ仕事を頑張ってもすぐに給与には反映されず、支給額は段階的にしか上がっていきません。そのため、若いうちから高収入を得たい方にとっては向いていない可能性があります。
転職や独立が難しいことがある
公務員以外の仕事経験がない場合、転職や独立が難しいことがあります。公務員は、その職場で役立つスキルを習得することは可能ですが、民間企業で求められる知識や技術は身に付きにくいようです。そのため、公務員から民間企業への転職や独立を考えた際、スキル不足を懸念される可能性があります。
公務員に向いている人の特徴
公務員への就職を考えているものの、「自分に向いているか分からない」という人もなかにはいるでしょう。ここでは、公務員を目指すのに向いている人の特徴をご紹介するので、自分に当てはまるかどうか確認してみてください。
公務員に向いている人の特徴
- 国や地域のために働きたい気持ちがある
- 安定した仕事に就きたいと考えている
- コミュニケーションに自信がある
- 学ぶことが好き
国や地域のために働きたい気持ちがある
就職をするにあたって、「国や地域のために働きたい」という気持ちがある方は、公務員に向いている可能性が高いといえます。仕事を通して国や地域に貢献できるので、モチベーションを保ちながら働けるでしょう。
安定した仕事に就きたいと考えている
職先に求める条件として「安定」を求める場合、公務員への就職は向いていると考えられます。このコラムの「雇用が安定している」でご紹介したように、公務員は景気や情勢に左右されにくい仕事のため、雇用が安定しているのがメリットです。
また、年功序列で昇給することから収入が下がることは少ないため、生活も安定しやすいといえます。
コミュニケーションに自信がある
公務員は、同じ部署の職員はもちろん、ほかの部署の職員などと連携しながら業務を進めます。そのため、コミュニケーションに苦手意識がない方に向いているでしょう。
また、さまざまな人や企業を対象に仕事を行うため、自分とは異なる価値観をもつ人と接する機会が多いです。偏見をもたずに対応するスキルも求められるでしょう。
学ぶことが好き
公務員は3~4年に一度異動があるため、そのたびに異なる仕事を覚える必要があります。また、法の改正や社会情勢によって業務の進め方などが変わる場合もあるので、学び続ける姿勢が必要です。
「公務員はルーティンワークだから一度仕事を覚えれば大丈夫」というイメージをもつ方もいるかもしれませんが、そのような考えで公務員を目指すと「自分には合わない」と後悔する可能性があります。
公務員試験で後悔しないための対策方法
公務員試験は合格倍率が高い場合がある・試験範囲が広いなどの理由から、簡単には合格できないでしょう。公務員試験は基本的に年に一度のみの実施なので、合格を逃すと来年また公務員試験に挑戦するか、民間企業に就職するかを決めなければなりません。そのため、公務員を目指す場合は効率的に試験対策を行う必要があります。
以下で、公務員試験で後悔しないための対策方法をご紹介します。
公務員試験で後悔しないための対策方法
- 試験の日程を確認する
- 勉強の計画を立てる
- 過去問演習を繰り返し行う
試験の日程を確認する
公務員になると決めたら、まずは試験の日程を確認しましょう。試験の日程が分からない状態で試験勉強を始めると、「試験当日までに勉強が間に合わなかった」といった事態に陥る可能性も考えられます。
地方公務員を目指す際は、どの自治体の試験を受けるかをおおよそ決めておくと安心です。また、公務員試験の日程は高卒程度と大卒程度で異なります。
「どのレベルの試験を受けるか」「国家公務員と地方公務員のどちらになりたいのか」「どの自治体で働きたいのか」など、自分の希望を明確にしたうえで試験の日程を確認することが重要です。
勉強の計画を立てる
勉強を開始する日から試験日まで何日あるかを確認し、勉強の計画を立てましょう。一般的に、筆記試験で教養のみを問われる自治体を受験する場合、300〜800時間の学習が必要といわれています。
しかし、実際に必要となる時間や確保できる時間は人によって異なるため、自分の苦手な科目や得点の割合が多い分野を集中的に勉強するのもコツです。公務員試験の教養試験の場合、6〜7割程度の点数で突破できるといわれている点も踏まえ、勉強の戦略を立てるのがおすすめです。
過去問演習を繰り返し行う
試験勉強をする際、過去問演習を繰り返し行うのが効果的です。公務員試験では論点が同じ問題が出題される傾向にあるため、過去問演習を取り入れることで効率的に勉強を進められます。
現職で働きながら公務員を目指す場合は、過去問演習ができるスマホアプリを使うのもおすすめです。スマホアプリなら、通勤時間や仕事の休憩時間に勉強できるので、「平日は仕事が忙しくてなかなか勉強時間が取れない」という方も効率的に試験対策を行えるでしょう。
予備校や通信講座を利用するのもおすすめ
公務員試験対策として、予備校や通信講座を利用するのもおすすめです。公務員試験に特化した予備校や通信講座であれば、必要な知識や答え方のコツをスムーズに学べるでしょう。
ただし、予備校の場合は費用が高かかったり通学が必要だったりすることがデメリットとして挙げられます。通信講座も、テキストに沿って勉強を進めなければならず向き不向きが分かれる可能性もあるので、利用する際は多角的な視点から検討することが大切です。
高卒の就職時に公務員と民間企業で迷ったら考えたいこと
高卒で公務員と民間企業のどちらを目指すか迷っている方は、以下で紹介する3点を確認してみましょう。公務員になることで叶えられること、民間企業でないと難しいことなどを把握し、どちらが自分に合っているのか検討してみてください。
経済的な安定を求めるかどうか
就職して「安定した収入を手にしたい」と考えているなら、公務員はおすすめの仕事といえます。先述のとおり、民間企業では倒産やリストラが起きる可能性がありますが、公務員の場合は国の機関や地方自治体に所属するので、そのような心配がありません。
また、民間企業で受け取れる給与や賞与は、業績によって決まることがほとんどです。一方、公務員は一定の給与や賞与、退職金を受給でき、福利厚生も充実しています。年齢が上がるごとに給与額も上がっていくため、経済面で将来の不安を感じることは少ないでしょう。
副業したいかどうか
「副業をしたい」と考えている高卒者の方には、民間企業への就職がおすすめです。民間企業では副業が可能な会社も多く、本業と両立できれば所得を増やせます。
一方、国家公務員の副業は、私企業からの隔離が明記された「国家公務員法第百三条」により、固く禁じられています。地方公務員も「地方公務員法第三十八条」に営利企業への従事等の制限が明記されており、厳しく制限されているのが現状です。
公務員の副業が禁止されているのは、「公務員の信用を失う行為につながる」「守秘義務が守れなくなる」「本業に専念できなくなる」といった理由が背景にあります。
もし公務員が副業をすれば、免職や停職などの罰則が課されることも。副業の内容によっては一部認められることもありますが、制限されたくない方は民間企業への就職も考えてみましょう。
将来的に転職や独立をしたいかどうか
転職や独立を視野に入れているのであれば、民間企業に就職することをおすすめします。民間企業では、専門分野に特化して仕事を進めることが多いでしょう。専門スキルが身に付けば、職場を変えても同じ業界や職種で応用できるので、転職や独立がしやすくなります。
公務員の場合は、専門職や技術職に就かない限り、主に事務の仕事を担います。事務の仕事は、窓口対応や書類作成などのルーティンワークが多いのが特徴です。そのため、公務員から民間企業への転職を目指す場合、就きたい仕事によっては経験・スキル不足と判断される可能性が考えられるでしょう。
高卒で就職しても、定年まで同じ職場で働き続けるとは限りません。将来どのようなキャリアを築いていきたいかをイメージして、就職先を考えることが大切です。
視野を広げて仕事探しをしよう
就職活動では、最終的に「絶対にこの企業に入りたい」と決めることも大事ですが、まずはいろいろな業種・職種に目を向けてみましょう。世の中には自分が知らない仕事が数多くあり、今知っている仕事の中から選ぶだけではもったいないといえます。求人サイトや就職エージェント、ハローワークなどを活用し、興味をもてる仕事をいくつか探してみましょう。
高卒の公務員に関するまとめ
高卒から公務員を目指す方は、自分が受ける試験の日程を確認し、計画を立てて勉強を進めていくことが大切です。ただし、最初から公務員だけに絞らず、さまざまな仕事に目を向けるのも忘れないようにしましょう。
「公務員のように安定して働ける民間企業で働きたい」という方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、若年層の求職活動をサポートする就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの希望や適性に合わせて求人をご紹介します。さまざまな業種・職種の求人を扱っているので、年齢や学歴が気になるという方もご安心ください。
求人の紹介だけでなく、応募書類の添削や面接対策、就職の悩み相談なども実施しているので、スムーズに就職・転職活動を進められます。ハタラクティブがご用意している適職診断を行えば、自分に合う仕事を簡単に調べることも可能です。
サービスの利用はすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
高卒の公務員に関するFAQ
どちらにもメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合わせて選ぶのが賢明です。
【高卒のメリット・デメリット】
・試験の難易度が低め
・大卒よりも早く社会人経験を積める
・大卒と比べると給与が低い
・昇格が遅い可能性がある
【大卒のメリット・デメリット】
・高卒よりも給与が高い
・昇格が有利になりやすい
・試験対策の幅が広い
・高卒公務員よりは経験が劣る
たとえば、とにかく早く自立したいという方は高卒公務員・試験が難しくても年収を多く得たい方は大卒公務員、のように選ぶ方法があります。