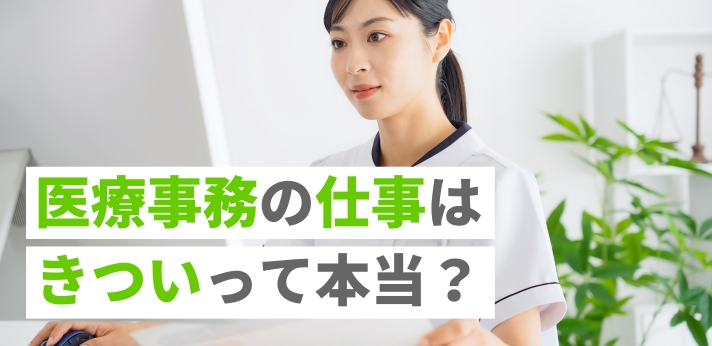飲食店がきついといわれる理由とは?おすすめの仕事や転職成功の方法を解説
飲食店の仕事がきついのか気になる方もいるでしょう。飲食店の仕事はやりがいがある一方で人手不足や労働環境の厳しさから「きつい」と感じることもあるようです。
このコラムでは、飲食店の仕事がきついといわれる主な理由やどのような瞬間に楽しさを感じるのかをまとめました。また、退職時のポイントや転職を成功させるための方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断

就職でお困りではありませんか?
当てはまるお悩みを1つ選んでください
飲食店の正社員がきついといわれる主な6つの理由
飲食業界は、多くの人と接する機会があり、やりがいを感じる反面、労働環境や業務内容において「きつい」と感じることもあるでしょう。ここでは、飲食店の正社員が「きつい」といわれる主な6つの理由について詳しく紹介するので、職場環境の改善や転職時の参考にしてみてください。
飲食店の正社員がきついといわれる主な理由
- 人手不足により負担が増えている
- 休日が不規則で少ない
- 給料が低い
- 体力が必要
- 職場の人間関係にストレスを感じる
- お客さまからクレームを受けることもある
1.人手不足により負担が増えている
飲食業界では、スタッフの不足が長年続く問題です。厚生労働省の「労働経済動向調査(令和6年11月)の概況」を参考にして、2024年11月における「未充足求人がある事業所の割合」を以下にまとめました。
| 産業 | 未充足求人あり | 未充足求人なし | 欠員率 |
|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 60% | 40% | 3.2% |
| 建設業 | 53% | 47% | 3.7% |
| 製造業 | 55% | 45% | 1.9% |
| 情報通信業 | 51% | 49% | 2.6% |
| 運輸業、郵便業 | 63% | 37% | 5.9% |
| 卸売業、小売業 | 51% | 49% | 2.3% |
| 金融業、保険業 | 21% | 79% | 0.7% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 56% | 44% | 2.5% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 53% | 47% | 2.5% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 60% | 40% | 4.5% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 50% | 50% | 3.2% |
| 医療、福祉 | 74% | 26% | 3.5% |
| サービス業(ほかに分類されないもの) | 76% | 24% | 5.3% |
参照:厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年11月)の概況 表5 産業、未充足求人の有無別事業所割合及び欠員率(p.9)」
※「未充足求人」の割合は無回答を除く数値で、「欠員率」は未充足求人がない事業所も含めています。
上記によると、2024年11月における「未充足求人あり」の割合が最も高いのは76%の「サービス業(ほかに分類されないもの)」、次いで74%の「医療、福祉」、63%の「運輸業、郵便業」、60%の「宿泊業、飲食サービス業」でした。
また、企業が求める労働者数と実際に雇用できている労働者数との差を示す欠員率は「運輸業、郵便業」が5.9%、「サービス業(ほかに分類されないもの)」が5.3%、「宿泊業、飲食サービス業」が4.5%となっています。このことから、飲食店の仕事は比較的人手不足の状況であると分かるでしょう。
特に繁忙期は、必要なスタッフ数を確保するのが難しく、一人ひとりの負担が増大することが考えられます。シフトの調整や急な欠勤への対応が必要になり、現場のスタッフが複数の業務を掛け持ちしなければならないこともあるでしょう。この人手不足が原因で、業務の質が低下したり、忙しい時間帯に十分なサポートが得られなかったりして、働き手にとってのストレスとなり得るようです。
参照元
厚生労働省
労働経済動向調査(令和6年11月)の概況
2.休日が不規則で少ない
飲食店の正社員が「きつい」といわれる要因の一つに、休日が不規則で少ないことが挙げられます。飲食業界では、土日や祝日、年末年始が繁忙期となり、平日に休暇を取ることが一般的です。そのため、家族や友人との時間が取りづらくなることがあります。
さらに、急なシフト変更やほかのスタッフの欠勤に対応することになり、予定していた休みが急遽キャンセルされるケースもあるでしょう。従業員数が少ない店舗では、一人が休むことで業務に支障が出てしまい、有給休暇の取得が難しくなるケースも考えられます。
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」によると、産業別に見た年次有給休暇の取得率は以下のとおりです。
| 産業 | 労働者1人平均付与日数 | 労働者1人平均取得日数 | 労働者1人平均取得率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年調査計 | 16.9日 | 11日 | 65.3% |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 17.8日 | 12.7日 | 71.5% |
| 建設業 | 17.8日 | 10.8日 | 60.7% |
| 製造業 | 18.3日 | 12.9 日 | 70.4% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.7日 | 13.2日 | 70.7% |
| 情報通信業 | 18.7日 | 12.5日 | 67.1% |
| 運輸業、郵便業 | 17.8 日 | 11.1日 | 62.2% |
| 卸売業、小売業 | 16.7日 | 10.1日 | 60.6% |
| 金融業、保険業 | 15.1日 | 9.9日 | 65.4% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 16.9日 | 10.6日 | 62.4% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 18.6日 | 12.2日 | 65.7% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 11.6日 | 5.9日 | 51% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 13.9日 | 8.8日 | 63.2% |
| 教育、学習支援業 | 17.7日 | 10.1日 | 56.9% |
参照:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況 第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況(p.8)」
上記によると、全産業の年次有給休暇の取得率は65.3%、「宿泊業・飲食サービス業」は51%でした。飲食店を含む「宿泊業・飲食サービス業」の有給休暇取得率は、全産業平均を下回っていることが分かります。
「休みが少ない仕事の目安は?きつい場合の対処法や転職先の探し方を解説」のコラムでは、何日からが休みが少ないのかについてまとめているので、あわせてご参照ください。
参照元
厚生労働省
令和6年就労条件総合調査 結果の概況
3.給料が低い
飲食店の正社員が「きつい」と感じる要因の一つに、給与水準の低さが挙げられるでしょう。
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」によると、産業別に見た平均賃金は以下のとおりです。
| 産業 | 賃金 |
|---|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 36万6,700円 |
| 建設業 | 34万9,400円 |
| 製造業 | 30万6,000円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 41万200円 |
| 情報通信業 | 38万1,200円 |
| 運輸業、郵便業 | 29万4,300円 |
| 卸売業、小売業 | 31万9,600円 |
| 金融業、保険業 | 39万3,400円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 34万800円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 39万6,600円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 25万9,500円 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 27万8,700円 |
| 教育、学習支援業 | 37万7,200円 |
| 医療,福祉 | 29万8,000円 |
| 複合サービス事業 | 30万2,000円 |
| サービス業(ほかに分類されないもの) | 28万5,700円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況 第5-1表 産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率(p.10)」
上記によると、2023年における飲食業界の平均賃金は 25万9,500円でした。この数字は、一般労働者の平均給与と比較すると低い水準にあるようです。同資料では、一般労働者の平均賃金は31万8,300円と報告されています。この差が、飲食業界の正社員が給与面での不満を感じる一因となっているようです。
参照元
厚生労働省
令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況
4.体力が必要
飲食店の正社員が「きつい」といわれる理由の一つに、体力が必要であることが考えられます。接客業務では立ち仕事が基本であり、長時間の立ちっぱなしや歩き回ることが求められがちです。
また、調理業務では、重い食材の運搬や高温の厨房環境での作業が負担になることも。繁忙期やピークタイムには休憩が取りにくく、体力の消耗が激しくなる傾向があるでしょう。こうした身体的な負担が、飲食業界の正社員が「きつい」と感じる要因の一つとなっています。
5.職場の人間関係にストレスを感じる
飲食店の正社員が「きつい」といわれる理由の一つは、職場の人間関係によるストレスです。飲食業はチームワークが重要であり、ホールとキッチンの連携やスタッフ同士のコミュニケーションが欠かせません。
しかし、忙しい時間帯には業務が立て込み指示がきつくなったり、感情的なやり取りが発生しやすくなったりすることも考えられます。また、上司や先輩からの厳しい指導、アルバイトとの関わり方、クレーム対応など、対人関係がストレスになり得る環境です。複数人のスタッフで回す飲食店の場合は、密接なコミュニケーションが求められるため、意見の食い違いや些細な誤解が摩擦につながることも考えられます。
さらに、急なシフト変更や繁忙期の業務集中により、ほかのスタッフとの連携や調整が難しくなり、トラブルやプレッシャーの原因になることも少なくありません。経験の浅いスタッフが多い職場では、上司からの指導方法や評価の仕方によって職場全体の緊張感が高まり、人間関係が悪化するケースもあるでしょう。こうした要因が重なり、飲食店の仕事は「きつい」と感じることもあるようです。
6.お客さまからクレームを受けることもある
お客さまからのクレーム対応があることも、飲食店の正社員が「きつい」といわれる理由の一つです。飲食業界では、お客さまの少しの不満がクレームにつながる場合があります。特に忙しい時間帯や繁忙期では、混雑による待機時間やサービスの遅延が原因でお客さまの不満が高まりやすいもの。正社員は、こうしたクレームに対して冷静に対応し、問題を解決する責任を担いますが、その対応にはストレスが伴うでしょう。
さらに、クレーム対応後の報告や反省会などが行われることもあり、精神的な負担が積み重なることも考えられます。クレームを解決しても再発防止策を考える必要があり、常に改善策を求められるため、プレッシャーを感じる場面もあるでしょう。
個人経営の飲食店とチェーン店はどちらがきついの?
個人経営の飲食店とチェーン店のどちらがきついかは、業態や規模、スタッフの数などによって異なります。
個人経営の飲食店では少人数で業務をこなすため、一人一人の役割が広範囲になり、仕事量が比較的多いのが特徴です。経営者との距離が近いため、プレッシャーや負担が大きく、スタッフ間での連携が重要になるでしょう。
チェーン店では、業務がシステム化されており効率的に働ける一方で、マニュアルや規則に従う必要があり、自由度が制限される可能性があります。規模が大きいため、店舗間の調整や責任者との連携がより求められるでしょう。経営者とのつながりは薄いものの、組織内での人間関係がストレスになることもあるようです。
どちらも異なる形での負担やストレスが考えられるため、それぞれの環境に適した働き方が求められます。「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
飲食店で正社員として働く場合の楽しい瞬間
飲食店の正社員として働くのはきついことばかりではなく、楽しい瞬間もあるようです。忙しい時間帯や大変なシフトのなかでも、お客さまとの交流やスタッフとの協力を通じてやりがいや充実感を得られる場面はあります。もちろん、すべての瞬間が楽しいわけではありませんが、こうした瞬間が積み重なることで、仕事に対するモチベーションや満足感を得られるでしょう。
ここでは、飲食店で正社員として働く場合、どのような瞬間に楽しさややりがいを感じられるかをまとめました。
お客さまから感謝の言葉を直接聞ける
飲食店で正社員として働く場合の楽しい瞬間の一つは、お客さまから直接感謝の言葉をもらえることです。料理を提供したりサービスを行ったあとに、お客さまから「美味しかった」「ありがとう」と言われると、その言葉が励みになることがあるでしょう。
チームで協力して達成感を味わえる
飲食店で働くうえで、チームワークは欠かせません。特に、忙しい時間帯や繁忙期には、スタッフ全員が協力して業務をこなすことが求められる場合もあるでしょう。お互いに助け合い、声を掛け合って仕事を進めることで、ピークを乗り越えたあとの達成感に楽しさを感じるようです。
スタッフ同士で連携がうまくいった瞬間に「チームとして一つの目標を達成できた」という実感が得られ、仕事に対する充実感が生まれることも。共に働く仲間との信頼関係や協力が、職場の雰囲気を明るくし、より良いチーム作りにつながるでしょう。仕事を終えたあとの達成感が次の仕事へのモチベーションとなり、日々の業務を楽しく感じさせてくれるはずです。
食の知識やスキルを身につけられる
飲食店で働くなかで、食材や料理に関する知識を深められることも楽しい瞬間の一つです。たとえば、食材の産地や特徴、調理法、料理の盛り付け方法などを学べるため、料理の世界についての理解が深まります。
また、ドリンクのペアリングやワインの選び方など、食に関連するさまざまなスキルを身につけられる機会もあるようです。お客さまに料理や飲み物について説明する際に自信をもって答えられると自分自身の成長を実感でき、楽しさを感じられるでしょう。
「楽しい仕事がしたい」「仕事をするなら楽しいほうが良い」などと考えている方は、「楽しい仕事とは?おすすめの職種や楽しく働ける求人を探すコツを紹介」のコラムもぜひチェックしてみてください。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
飲食店の仕事がどうしてもきついなら転職するのも選択肢の一つ
どうしても飲食店の仕事が「きつい」と感じるなら、転職を考えるのも一つの選択肢です。飲食業界は、体力的な負担が大きかったり勤務時間が不規則になりやすかったりすることがあり、「働き続けるのが難しい」と感じる人もいるでしょう。また、人間関係やクレーム対応、長時間労働などのストレスが積み重なることも考えられます。
仕事の負担が大き過ぎる・給与に見合っていないと感じる場合は、「同じ飲食業界の労働環境が整った職場を探す」「ほかの業界や職種に目を向けてみる」というのも手です。転職をすることで、自分に合った働き方が見つかり、仕事への満足度が向上する可能性があります。無理を続けることが必ずしも改善につながるとは限らないため、自分の将来や健康を考えながら慎重に判断することが大切です。
飲食店の仕事から転職を考えている場合は、「飲食業から転職したい!経験やスキルが活かせる仕事や自己PRのコツ」のコラムもぜひ参考にしてみてください。
きついと感じる飲食店を退職する際に起こり得ること
飲食店を退職する際には、思いがけない問題が発生する可能性もあります。職場の人手不足や業務の引き継ぎの関係で、スムーズに辞められないケースもあるでしょう。退職を決意したらできるだけ円満に手続きを進められるように、起こり得る事例を理解して事前に準備をしておくことが大切です。
自分が辞めたことで上司が怒られる
飲食店は人員が最小限で回っている場合があり、一人が辞めると職場の負担が増える可能性があります。そのため、退職の意思を伝えると、店長や直属の上司がさらに上の立場の人から責任を問われることもあるようです。特に、急な退職や繁忙期の退職では、「なぜ引き止めなかったのか」「人員管理が甘いのではないか」と上司が詰められる恐れもあり、それが原因で退職の際に気まずい雰囲気になることも考えられます。
引き止めに遭い、退職手続きをスムーズに進められない
飲食店では、退職の申し出をしても「もう少し頑張ってみないか」「人が足りないからあと△ヶ月だけいてほしい」と引き止められることもあるようです。辞めることで店舗の運営に支障が出る場合は、強い引き止めに遭う可能性もあるでしょう。
場合によっては、退職届を受理してもらえなかったり、退職日を延ばされそうになったりすることもあるため、事前に退職の流れを確認し、会社の規則に従って手続きを進めることが大切です。
退職時の引き止めについては「退職を引き止められたときの効果的な対策をご紹介!」のコラムもあわせてチェックしてみてください。
飲食店がきつい…退職する際のポイント
飲食店を退職する際は、スムーズに手続きを進めるためのポイントを押さえておくのがポイントです。人手不足の店舗では引き止めに遭う可能性もあるため、計画的に準備を進めることでトラブルを避けやすくなるでしょう。以下で退職する際のポイントを解説するので、ぜひご一読ください。
退職の意思は早めに伝える
飲食店では少人数でシフトを回している場合もあり、急な退職は職場に大きな負担を掛ける可能性があります。そのため、退職を決めたら早めに店長や上司に伝えることが重要です。1〜2ヶ月前に申し出るのが一般的とされていますが、何ヶ月後に辞められるかは企業によって異なるため、就業規則を事前に確認しておきましょう。
店長や上司に退職する旨を伝える際は、口頭だけでなく書面で提出することで、正式な手続きとして認識されやすくなります。なお、繁忙期の直前に伝えると引き止められる可能性が高まるため、タイミングには注意しましょう。
繁忙期を避けて円満退職を心掛ける
飲食店では、年末年始やゴールデンウィーク、夏休みなどの繁忙期にスタッフが不足すると、職場全体の負担が増える可能性があります。そのため、繁忙期に退職すると、上司や同僚から強く引き止められてスムーズに退職できないこともあるようです。退職の意思を伝えるタイミングを考慮し、できるだけ業務が落ち着いている時期を選ぶことで、円満に退職しやすくなるでしょう。
円満退職を目指す場合の上司への切り出し方を「円満退職するための伝え方は?上司への切り出し方や注意点もご紹介」のコラムにまとめているので、ぜひご一読ください。
転職先を決めてから退職する
収入の不安を避けるためにも、次の仕事を決めてから退職するのがおすすめです。特に、異業種への転職を考えている場合は必要なスキルや経験について事前に調べ、準備を進めるようにしましょう。飲食業からの転職では、接客経験やチームワークのスキルが活かせる場合もあるため、自分の強みを整理しておくと転職活動がスムーズに進めやすくなります。
また、転職先が決まっていれば、引き止めに対しても「すでに次の職場が決まっています」と伝えやすくなり、退職交渉がスムーズに進むこともあるようです。
飲食店から転職する際におすすめの仕事
飲食店での仕事が「きつい」と感じて転職を考える場合、どの職種に進むべきか悩むこともあるでしょう。飲食店で培ったスキルや経験は、ほかの仕事でも活かせる可能性があります。転職先としては、販売職や食品メーカーの営業職、事務職などが挙げられるでしょう。以下で詳しく解説するので、ぜひチェックしてみてください。
販売職
アパレルや家電量販店、スーパーなどの販売職は、飲食業で培った接客スキルを活かせる仕事の一つです。お客さまとのコミュニケーションやニーズに応じた提案が求められるため、飲食店での接客経験を役立てられるでしょう。
また、飲食業と比べて労働時間が安定しやすく、休日を確保しやすい点が魅力です。ただし、店舗によっては立ち仕事が多かったり、繁忙期にシフトが増えたりすることもあるため、勤務条件をよく確認するようにしましょう。
「接客の仕事」のコラムでは接客の仕事についてまとめているので、「飲食店で身につけた接客スキルを活かしたい」といった場合はあわせてご参照ください。
食品メーカーの営業職
食に関する知識を活かしたい場合、食品メーカーの営業職も選択肢の一つです。飲食店での経験があると、飲食業界の仕組みや現場のニーズを理解しやすく、提案営業の際に強みとなり得ます。
また、飲食店のオーナーや仕入れ担当者と関わる機会もあるため、これまでの人脈や現場での経験を活かしやすい点もメリットです。営業職は個人の成果が評価されやすい仕事ですが、ノルマがある場合もあるため、自分に合った働き方かどうかを考えて選ぶことが重要といえるでしょう。
事務職
体力的な負担を減らしたい場合は、事務職への転職もおすすめです。事務職はデータ入力や書類作成、電話対応などが主な業務で、接客業務は少ない傾向にあります。飲食業で培ったマルチタスク能力やコミュニケーション能力は、事務職の仕事で活かせるでしょう。
ただし、基本的なPCスキルやビジネスマナーが求められる可能性があるため、事前に学んでおくと採用されやすくなります。
参照元
厚生労働省
職業情報提供サイトjob tag(日本版O-NET)
飲食店がきつい…転職を成功させる方法
飲食店の仕事は、体力的な負担や人間関係のストレスなどがあるため、「きつい」と感じることもあるでしょう。転職を考える際には、経験を活かせる仕事に注目し、労働条件をしっかり確認することが大切です。また、転職活動をスムーズに進めるためには、応募書類や面接の準備を徹底することが成功の鍵となります。
ここでは、飲食店から転職を成功させるための方法を詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
「未経験可」「飲食の経験を活かせる」仕事に注目する
飲食店の経験を活かして転職する場合、「未経験可」の仕事や、自身の経験が役立つ職種を選ぶことが大切。飲食業界で積んだ経験がそのまま別の業界で「経験」として評価されるとは限らないためです。未経験可の求人は、経験を問わず業務に必要なスキルを研修で学べる可能性があるため、新たな分野でキャリアを築くための足掛かりとなるでしょう。
また、接客スキルやチームワーク、問題解決能力などの飲食業で培ったスキルは、別の業界でも評価される可能性があります。未経験者として応募する場合も、これらのスキルをアピールすることで即戦力として評価してもらえる可能性があるでしょう。そのため、未経験可の求人や飲食店での経験を活かせる仕事に注目することが、転職を成功させるための鍵となり得ます。
労働条件を確認する
転職の際は、給与や休日、労働時間などの条件をしっかり確認することが重要です。労働時間の長さや休日が取りにくいことが原因で飲食店を辞めた場合は、次の職場で改善できるかを見極める必要があります。
年間休日数や残業の有無、福利厚生、シフトの柔軟性などを事前にチェックすることで、転職後のミスマッチを防げます。また、キャリアアップの制度が整っているかも確認しておくと、将来のキャリアプランを考えやすくなるでしょう。
応募書類の作成や面接対策を徹底する
転職を成功させるためには、履歴書や職務経歴書の作成、面接対策を丁寧に行うことも大切です。飲食業の経験をアピールする際は、「コミュニケーション能力」「チームワーク」「臨機応変な対応力」など、他業種で活かせるスキルを具体的に伝えると評価されやすくなるでしょう。
また、面接では「なぜ飲食業から転職するのか」「次の職場でどのように貢献できるか」を明確に伝えられるように準備しておくことが大切です。転職エージェントを活用すると、書類の添削や面接のアドバイスを受けられるため、効率的に転職活動を進めやすくなります。
「転職のコツとは?面接に受かる方法や企業研究のやり方などを伝授」のコラムでは転職のコツをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
一人での転職活動が不安ならエージェントを活用するのも手
一人での転職活動が不安なら、転職エージェントを活用するのも一つの方法です。転職エージェントは求人紹介だけでなく、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、企業との交渉などもサポートしてくれるため、転職活動をスムーズに進めやすくなります。特に未経験の業界へ挑戦する場合は、キャリアアドバイザーのアドバイスが役立つでしょう。
ただし、エージェントによって得意な業界やサポート内容が異なるため、複数を比較して自分に合うサービスを選ぶのが大切です。
「飲食店の仕事から転職したい」「自分に合う仕事が分からない」という方は、ぜひ就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブは、若年層の既卒や第二新卒、フリーター、ニートの方へ求人紹介を行っています。専任のキャリアアドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを行い、働くうえでの希望条件に合う仕事を提案。1分間の適職診断を通して適性に合う職種を知ることも可能です。
応募することが決まったら、書類作成や面接対策もサポートします。企業とのやり取りはキャリアアドバイザーが代行するため、効率的かつ安心して選考を進められるはずです。
ぜひハタラクティブにお問い合わせください。
飲食店の仕事に関するよくある質問
めてのアルバイトや、店長としてのキャリアを考えている人のなかには、「飲食店の仕事はきついの?」と不安に感じる方もいるでしょう。ここでは、飲食店の仕事に関するよくある疑問をQ&A形式で回答していきます。
飲食店の店長はきついから就職するのはやめとけって本当?
人によって感じ方が異なるため、飲食店の店長が一概に「きつい」とはいえません。
ただし、店長は業務内容が多岐にわたり、労働時間が長くなることもあるため、「きつい」と感じる人もいるようです。「マネジメント経験を積みたい」「成長次第でキャリアアップのチャンスがある仕事がしたい」などの場合は、飲食店の店長の仕事に挑戦してみるのもおすすめです。
初バイトで飲食店はきつい?
仕事の流れを覚えるまでは「きつい」と感じることもあるかもしれませんが、初めてのアルバイトとして選ぶのも選択肢の一つです。不安な気持ちが強い場合は、マニュアルが整っている店を選んでみましょう。
飲食店のアルバイトでは、幅広い仕事で活かせる接客技術やチームワークスキルが身につけられます。
飲食店のキッチンとホールはどちらがきつい?
人によって感じ方が異なるため、どちらがきついとはいえません。キッチンは高温の環境での作業や体力的な負担が大きく、調理スキルが求められるでしょう。一方、ホールは接客対応が中心で、クレーム対応や臨機応変な対応が必要になります。自分の得意なことや適性を考えて選ぶようにしましょう。
「一人での転職は不安」「応募書類をプロ目線で見てほしい」などの場合は、若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?
マーケティングアシスタント
東京都
年収 315万円~360万円
正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!
ライター・取材担当
東京都
年収 315万円~360万円
未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?
営業
東京都
年収 328万円~374万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆
ルート営業
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…
年収 228万円~365万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「仕事選び」についての記事一覧
- 「職種図鑑」についての記事一覧
- 飲食店がきついといわれる理由とは?おすすめの仕事や転職成功の方法を解説