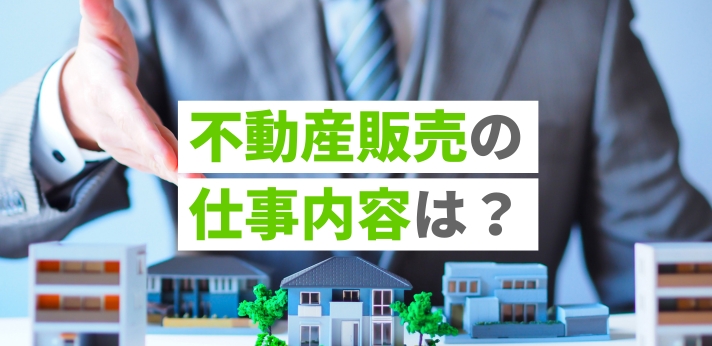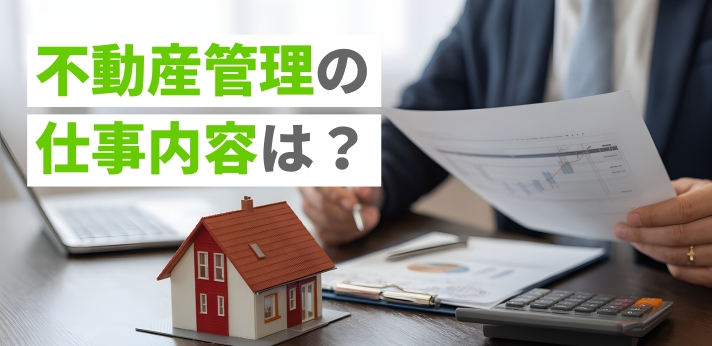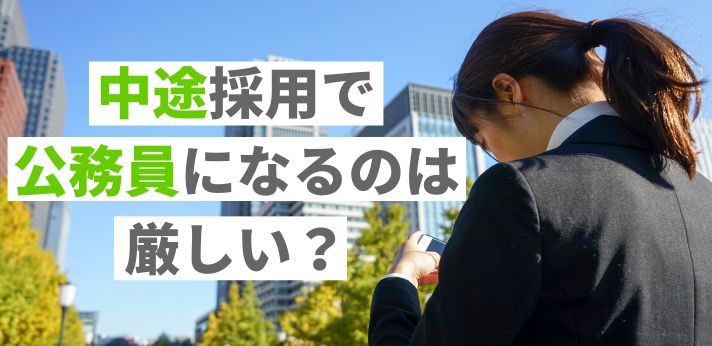地方公務員の仕事内容をわかりやすく解説!必要な資格とやりがいも紹介地方公務員の仕事内容をわかりやすく解説!必要な資格とやりがいも紹介
更新日
公開日
地方公務員の仕事内容は窓口対応や、インフラに関わる業務など
地方公務員の仕事内容が気になる方もいるでしょう。地方公務員のうち行政事務の仕事は、地方自治体で行政施策の企画立案や、住民サービスに関する事務処理などを行うことです。
このコラムでは、地方公務員の平均年収や必要な資格を紹介。また、やりがいや働くメリットも解説するので、ぜひ仕事選びの参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
地方公務員の仕事内容とは
地方公務員とは、都道府県や市区町村といった地方自治体で働く公務員のことです。その主な役割は、地域住民の生活を支え、地域社会の発展に貢献すること。国家公務員が国全体のために働くのに対し、地方公務員は特定の地域に根ざした業務を行います。
地方公務員の仕事内容は多岐にわたり、市役所の窓口での対応や地域のインフラ整備、教育、福祉など、私たちの日常生活に密接に関わる業務を担当。たとえば、県庁や市役所の窓口での各種証明書発行、道路や公園の整備計画、地域の防災対策など、住民の生活に直接影響する仕事が中心となっているのが特徴です。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
地方公務員には、上記のような行政職だけでなく、保健師や保育士、消防士など、さまざまな専門職も含まれています。では、地方公務員のうち行政事務の仕事の概要を見ていきましょう。
| 仕事内容 | 地方自治体で行政施策の企画立案や予算編成、住民へのサービスに関する事務処理を行う |
|---|
| 平均年収 | 481.4万円 |
|---|
| 向いている人 | ・幅広い行政分野に関心がある人
・責任感、奉仕の精神を持つ人
・公正かつ中立な判断ができる人 |
|---|
| ポイント | ・試験の内容は地方自治体によって異なるが、多くの場合、3つの区分(大学卒業程度、短大卒業程度、高校卒業程度)に分けられる
・行政内部での異動が多い
・政令指定都市は、都道府県と同等の役割と機能を担う |
|---|
採用後は、行政内部で数年ごとに部署を移動するのが一般的です。さまざまな分野の業務に携わることで、地方自治に関する幅広い知識やスキルを得られるでしょう。
※ここで紹介した情報は2025年5月時点のものです。最新の情報と異なる可能性があります。
やりがい
地方公務員のやりがいは、業務を通じて住民の暮らしに貢献できることです。住民からの「ありがとう」の言葉を直接聞ける機会もあり、人の役に立っていることを実感できる職業です。
また、長期的な視点で地域づくりに関われることも大きなやりがいとなります。たとえば、自分が関わった都市計画によって数年後に街並みが整備されたり、福祉政策によって地域の高齢者が暮らしやすくなったりといった成果が出ることも。利益を追いかけるのではなく、社会貢献に集中して取り組めるのは、地方公務員ならではのやりがいといえるでしょう。
働くメリット
地方公務員として働くメリットは、安定した雇用と収入が保証されている点です。民間企業に比べて業績によって給与が大幅に変動したり急に解雇されたりするリスクが低く、長期的なライフプランを立てやすいでしょう。また、福利厚生が充実しており、住宅手当や家族手当などのさまざまな手当制度があることも魅力の一つです。
さらに、ワークライフバランスが取りやすい点もメリットといえます。基本的に残業が少なく、有給休暇も取得しやすい傾向にあるため、家庭と仕事の両立がしやすいでしょう。地域に密着した仕事のため、転勤が少ないか、あっても同じ自治体内であることが多く、生活環境を維持しやすいこともおすすめポイントです。
地方公務員と国家公務員の違い
地方公務員と国家公務員の主な違いは、勤務地と業務のスケールにあります。地方公務員は都道府県や市町村に勤務し、地域住民に密着した行政サービスを提供する仕事です。一方、国家公務員は中央省庁で国の政策立案や法律の整備に携わり、業務のスケールは全国レベル、ときには海外におよびます。また、両者は採用試験や給与体系も異なります。
参照元: 職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag トップページ
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
地方公務員の勤め先と特徴
地方公務員の勤務先は大きく分けて、都道府県・市町村・政令指定都市・東京特別区の4つがあります。ここでは、それぞれの業務の範囲や規模といった特徴を紹介するので、自分に合った勤め先を考える際の参考にしてみてください。
都道府県
都道府県は、複数の市町村にまたがる広域的な行政サービスを担う機関です。道路・河川・公共施設といったインフラの建築や教育施設の運営、産業振興など、市町村よりも大規模な事業を手がけます。
市町村よりスケールの大きな地域づくりに関わることができ、専門性の高い業務も多いため、特定の分野でスペシャリストを目指すことも可能です。
市町村
市町村は、地域住民にとって身近な行政機関。住民票の発行や国民健康保険の運営、ごみ収集、小中学校の管理など、日々の暮らしに欠かせないサービスを提供しています。
市町村で働く魅力は、自分の仕事が地域住民の生活に直接貢献していることを実感しやすい点です。窓口業務などで住民と直接対話する機会が多く、「顔の見える関係」のなかで働けます。
政令指定都市
政令指定都市は、人口50万人以上の市のうち、政令で指定された都市のことです。「指定都市」「政令市」などと呼ばれることも。政令指定都市は、一般の市では都道府県が行っている児童福祉・生活保護・食品衛生などに関する事務を担っています。そのため、これらの政令指定都市の地方公務員は、一般の都市に比べて業務の幅が広いのが特徴です。
なお、総務省の「指定都市一覧」によると、現在、政令指定都市は大阪市や名古屋市、京都市など20の市があります。
東京特別区
東京特別区とは、東京23区のことです。特別区は、それぞれ住民が選んだ区長や議会、条例制定権、課税権といった特別な権限をもっているのが特徴。また、市役所と同じく、住民の生活や地域の福祉に関する行政サービスも行います。
東京特別区の地方公務員になるためには、特別区職員採用試験に合格したあと、各区が行う面接を受けて採用内定を得なければなりません。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
地方公務員の平均収入
平均年収
地方公務員の平均年収は地方自治体や職種によって異なりますが、ここでは県庁や市役所などで働く行政事務の年収・月収・賞与の平均値を紹介します。地方公務員の仕事に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
平均年収
| 年齢 | 平均年収 |
|---|
| 20~24歳 | 310万5,200円 |
|---|
| 25~29歳 | 390万5,900円 |
|---|
| 30~34歳 | 444万5,900円 |
|---|
| 35~39歳 | 476万3,500円 |
|---|
| 40~44歳 | 500万4,300円 |
|---|
| 45~49歳 | 523万6,300円 |
|---|
| 50~54歳 | 552万100円 |
|---|
| 55~59歳 | 588万8,100円 |
|---|
平均年収は20代前半の約310万円から年齢とともにアップし、50代後半には約588万円とピークを迎えます。一般的に、大都市圏の自治体は、地方よりも給与水準が高い傾向にあるでしょう。
平均月収
| 年齢 | 平均月収 |
|---|
| 20~24歳 | 19万4,075円 |
|---|
| 25~29歳 | 24万4,119円 |
|---|
| 30~34歳 | 27万7,869円 |
|---|
| 35~39歳 | 29万7,719円 |
|---|
| 40~44歳 | 31万2,769円 |
|---|
| 45~49歳 | 32万7,269円 |
|---|
| 50~54歳 | 34万5,006円 |
|---|
| 55~59歳 | 36万8,006円 |
|---|
平均月収も、年齢と経験に比例して増加。民間企業と比べると、基本給は若干低めに設定されている場合がありますが、安定性と扶養手当・住宅手当といった手当の充実度を考えると、総合的には好条件といえる水準です。
平均賞与
| 年齢 | 平均賞与 |
|---|
| 20~24歳 | 38万8,150円 |
|---|
| 25~29歳 | 48万8,238円 |
|---|
| 30~34歳 | 55万5,738円 |
|---|
| 35~39歳 | 59万5,438円 |
|---|
| 40~44歳 | 62万5,538円 |
|---|
| 45~49歳 | 65万4,538円 |
|---|
| 50~54歳 | 69万13円 |
|---|
| 55~59歳 | 73万6,013円 |
|---|
賞与額は、基本的には勤務成績や勤続年数によって変動します。また、地域の財政状況によって支給率が調整されることもあるため、必ずしも毎年同じとは限りません。とはいえ、民間企業のような「業績不振で大幅カット」といった極端な変動は少なく、比較的安定しているといえるでしょう。
参照元: 職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag トップページ
地方公務員のスケジュール
地方公務員の仕事スケジュールは職種によって異なりますが、基本的には勤務時間は一定しています。ここでは、年間休日数と1日の一般的な流れについて見ていきましょう。
年間休日数
地方公務員の年間休日は、一般的に120日前後です。これには土日、祝日、年末年始休暇が含まれます。さらに、年間に20日程度の有給休暇が付与されるため、実際の休日数はさらに多くなります。
多くの自治体では、夏季休暇や結婚・忌引きなどの特別休暇制度も充実しているため、ワークライフバランスを重視する方に適しているといえるでしょう。
1日の流れ
地方公務員のうち、県庁や市役所で働く行政事務の勤務時間は、原則として1日7時間45分です。窓口業務がある部署では定時での業務終了が基本ですが、地方自治体によっては夜間や休日に窓口を開けている場合もあり、部署によって勤務体制が異なるでしょう。
行政事務の一般的な1日のスケジュールは以下のとおりです。
| 時間 | 主な業務内容 |
|---|
| 8:30〜9:00 | 出勤・朝礼・メール確認 |
|---|
| 9:00〜12:00 | 窓口対応、書類作成、会議など |
|---|
| 12:00〜13:00 | 昼休み |
|---|
| 13:00〜15:00 | 午後の窓口対応、事業計画の立案など |
|---|
| 15:00〜17:00 | 関係機関との打ち合わせ、翌日の準備 |
|---|
| 17:00〜17:15 | 業務終了の準備、デスク整理 |
|---|
部署によって業務内容は異なりますが、多くの場合、定時での退庁が可能で、家庭との両立がしやすい環境といえます。ただし、繁忙期には残業が発生することもあります。
地方公務員に向いている人
地方公務員に向いている人には、以下のような特徴があります。ここでは、これらの特徴について解説するので、自分に当てはまるものがあるかチェックしてみてください。
地方公務員に向いている人
- 雇用や収入が安定している仕事をしたい人
- プライベートと仕事の両立を目指している人
- 仕事を通じて地域に貢献したい人
雇用や収入が安定している仕事をしたい人
雇用や収入が安定している仕事をしたい人は、地方公務員に向いています。地方公務員は法律で身分が保障されているため、民間企業のような倒産やリストラのリスクが極めて低いのが特徴です。
また、給与やボーナスといった収入も、景気の変動に左右されにくいため、将来のマイホーム購入や子育てなど、長期的な人生設計を立てやすいでしょう。
「将来への不安がない状態で仕事に集中したい」という方にとって、地方公務員は理想的な仕事といえます。
プライベートと仕事の両立を目指している人
地方公務員に向いている人の特徴として、プライベートと仕事の両立を目指していることも挙げられます。地方公務員は、残業が少ない傾向があり、ワークライフバランスを重視できる働き方が可能だからです。
部署によっては定時退庁が基本とされており、仕事とプライベートの時間を両立しやすい環境が整っています。育児休業や介護休暇などの制度も充実しているため、結婚や出産といったライフステージの変化にも対応しやすいでしょう。
また、引っ越しを伴う転勤が少なく、同じ地域に長く住み続けられる点も、家族との将来設計を立てやすくします。
したがって、家庭や趣味といったプライベートと仕事を両立したい人は、地方公務員に向いているといえるでしょう。
仕事を通じて地域に貢献したい人
仕事を通じて地域の役に立ちたいと考えている人も、地方公務員に向いています。地方公務員は、道路や公園の整備、福祉サービス、防災対策など、さまざまな分野で地域や住民の生活に貢献できるからです。
また、長期的な視点で地域の課題解決に取り組めるため、持続可能なまちづくりといった、社会的意義のある仕事に携わることができます。
「公共サービスを通じて地域に貢献したい」という方は、このような地方公務員の仕事に意欲的に取り組めるでしょう。
地方公務員になるために必要な資格
地方公務員になるには、特別な資格は必須ではありません。一般行政職(事務職)を志望する場合、公務員試験に合格することが主な条件となります。
ただし、薬剤師や保育士といった専門職に応募する際は、それぞれの資格が必要です。
また、希望する職種や部署に関連する資格を事前に取得しておくのも手。たとえば、一般事務職ならPCスキルを示すMOS資格、財政部門なら日商簿記検定などが挙げられます。これらの資格は、採用試験でのアピールポイントになるだけでなく、就職後の業務をスムーズに進めるうえでも役立つでしょう。
地方公務員になるには
地方公務員になるには、各地方自治体の採用試験に合格しなければいけません。試験や選考の内容は、自治体によって異なりますが、多くの場合、「大学卒業程度」「短大卒業程度」「高校卒業程度」という3つの区分に分けられています。
なお、「○○卒業程度」と区分されていますが、基本的には受験において学歴は問われません。
また、地方自治体や区分によって受験できる年齢の上限が異なりますので、詳しくは各自治体のWebサイトなどでご確認ください。
地方公務員の試験は教養試験のほか、作文、面接、適性検査などがあります。試験の勉強方法には、「独学でテキストや過去問をこなす」「予備校やオンライン講座を活用して効率的に学ぶ」といったものが挙げられます。
また、面接対策として、時事問題のチェックや志望動機、自己PRの整理も大切です。志望する自治体の特色や課題について深く理解していることをアピールすると、好印象を与えられる可能性があるでしょう。
地方公務員のキャリア形成
地方公務員として働き始めたあとのキャリアには、勤務先や職種によってさまざまな道があります。ここでは、行政事務の一般的なステップアップの流れやキャリアチェンジの例をまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
就職後のステップアップ図
行政事務の一般的なステップアップの流れは以下のとおりです。
- 就職1年目~3年目:主事
- 4~10年目:係長・主任
- 10~20年目:課長補佐
- 20年目以降:課長
- 25~30年目:部長
- 30年以上:局長・副市長など
地方公務員は、採用後、まず主事として基本的な業務からスタートし、数年ごとに部署を異動して幅広い行政経験を積みます。
その後、係長、課長とキャリアを重ね、チームのリーダーや管理職として政策立案や組織運営に携わるようになり、専門知識やマネジメント能力が身につくでしょう。最終的には部長、局長といった自治体の重要政策に関わるポジションまで昇進する道が開かれています。
昇進のスピードは自治体や個人によって異なりますが、年齢や勤続年数だけでなく、能力が評価される場合もあるでしょう。地方公務員は、キャリアや実績を積み重ねることで、段階的に責任のある仕事へとステップアップしていくことが可能です。
異業種・異職種へのキャリアチェンジ例
地方公務員としての経験を活かして、民間企業や公的機関への転職だけでなく、起業や政治の世界へ転身する例もあります。
たとえば、コンサルティング会社や社会福祉法人、商工会議所などでは、行政手続きや公共政策に関する知識や実務経験が専門性として評価される可能性があるでしょう。また、行政書士として独立したり、地方議員や国会議員の秘書になる道もあります。
このほか、副業規制の緩和が進む自治体では、在職中に副業によって専門スキルを磨いたり人脈を築いたりして、将来のセカンドキャリアに備えることも可能です。
まとめ
地方公務員は、行政サービスを通じて地域社会の発展と住民の生活に直接貢献できる仕事です。安定した雇用と収入、充実した福利厚生、ワークライフバランスの取りやすさなど、さまざまなメリットがあります。勤め先や職種によって業務内容が異なるため、自分の志向に合った働き方を選ぶことができるでしょう。
「収入が安定した職業に就きたい」「仕事で人の役に立ちたい」という方は、就職・転職エージェントに相談してみるのも手です。プロのアドバイザーが、一人ひとりの希望や適性に合う求人を紹介してくれるので、仕事探しをスムーズに進められます。
ただし、エージェントによって扱う求人やサービスの対象が異なるため、自分に合うエージェントを選びましょう。
若年層に特化した就職・転職エージェントであるハタラクティブでは、未経験OKの大手企業の求人を豊富に取りそろえています。求人の職種は幅広いので、「やりたい仕事がまだわからない」という方も安心です。専任のキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングしたり一緒に自己分析をしたりして、適性や希望条件を聞いたうえで、あなたに合う求人をご紹介します。
自己PR作成のアドバイスや企業ごとの面接対策なども行い、就職・転職活動を手厚くサポート。サービスはすべて無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。