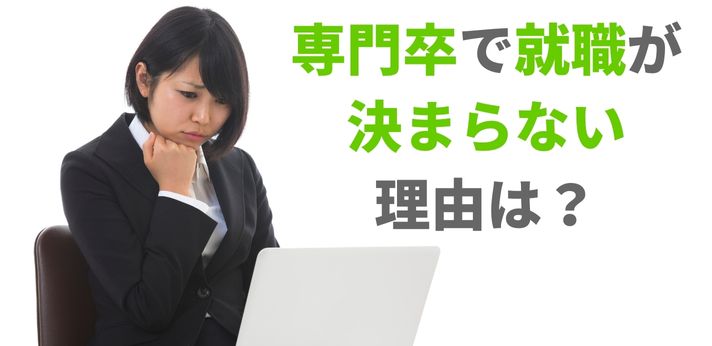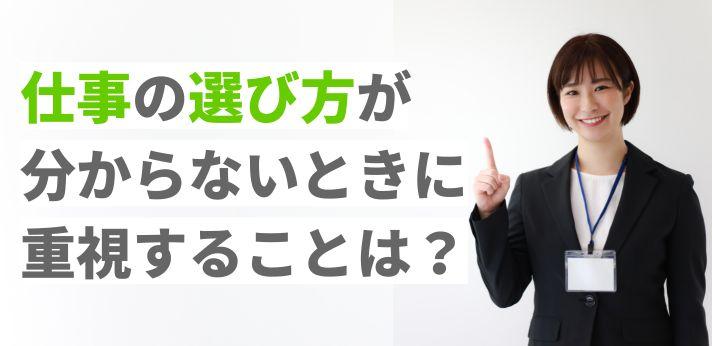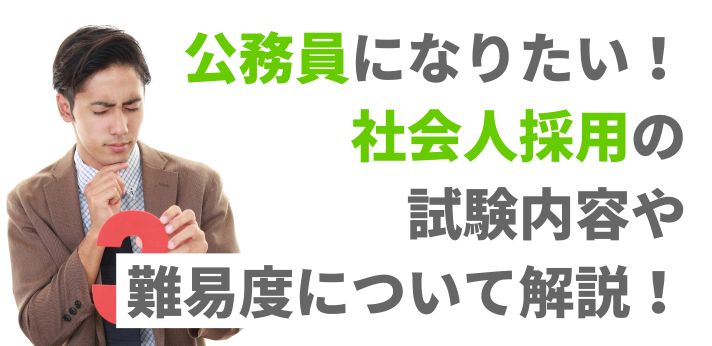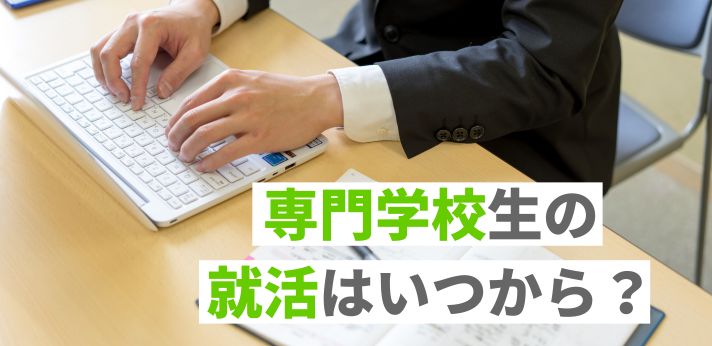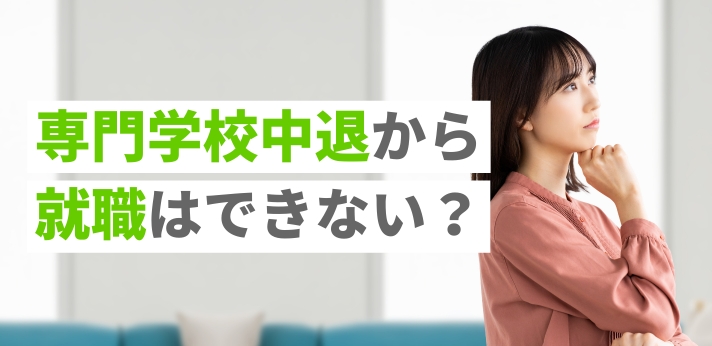専門学校生の就職は厳しい?就活事情や不安を感じたときの対処法を解説専門学校生の就職は厳しい?就活事情や不安を感じたときの対処法を解説
更新日
公開日
専門学校生の就職率は99.2%と高く、企業から即戦力として期待されやすい
専門学校生や専門学校に通うことを検討している方のなかには、「専門学校生は就職に強い?」と気になっている方もいるでしょう。専門学校生の就職率は90%以上と高く、学んだ専門分野への就職に強い傾向があります。
そこでこのコラムでは、専門学校生の就職事情や入学するメリット・デメリットをまとめました。専門学校生が就職活動を成功させるためのコツや、不安を感じた際の対処法も紹介しています。専門学校生の就職事情について知り、理解を深めていきましょう。エージェントの活用方法もお伝えしているので、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
専門学校生の就職事情
専門的かつ実践的なスキルを身につけた専門学校生は、企業から「入社後の早い段階で戦力になる」と評価されやすく、特定の専門分野への就職は強い傾向にあります。以下で解説する就職率や傾向をもとに、専門学校生の就職事情を確認してみてください。
専門学校生の就職率は99.2%
専門的かつ実践的なスキルを身につけた専門学校生は「入社後の早い段階で戦力になる」と評価されるため、特定の専門分野への就職は有利といえるでしょう。一方、特定の専門分野以外への就職は、一般教養を身につける大学生と比べて不利に働きやすいのが実情です。
就職率の推移は10年以上90%を超えている
厚生労働省の同資料「就職(内定)率の推移 (専修学校専門課程)(P.7)」では、専門学校生の就職率の推移を公表しています。専門学校生の就職率は、過去10年以上にわたって90%を超える高い水準を維持しており、専門分野でキャリアを築きたいと考える学生にとって、専門学校を選ぶ大きな理由の1つとなるでしょう。
この安定した就職率の背景には、専門学校が業界のニーズを反映した実践的なカリキュラムを提供していることや、企業との強固なネットワークを築いていることが挙げられます。ただし、就職率のデータだけでなく、「どのような企業に就職しているか」「卒業生の満足度は高いか」など、より詳しい情報もあわせて確認することが大切です。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
就職活動が厳しいと感じる理由とは
お伝えしているように、専門学校生の就職率は高く、10年以上において推移は90%を超えています。一方で、別の分野への就職を目指すのが難しい、就活に充てられる時間が少ないといった理由から、就職活動が難しいと感じる場合もあるようです。以下で解説しているので、どのようなときに厳しいと感じるのか確認してみてください。
別の分野への就職が難しい
専門学校は、特定の分野の知識とスキルの習得に特化しています。そのため、それ以外の分野で就職を目指す際に、厳しいと感じる場合があるようです。専門学校での学びは、特定の分野の専門性を高めることに重点が置かれているので、習得した知識やスキルが志望する分野と直接関連しない場合、企業に自分の強みをアピールすることが難しいと感じる可能性があります。
専門分野以外に就職を考えるなら、「なぜ専門分野ではない企業に就職したいのか」「入社してどのようなキャリアを築いていきたいか」などを明確にし、採用担当者に入社意欲やポテンシャルをアピールしましょう。
就活に充てられる時間が限られている
専門学校のカリキュラムは、実習や課題が多く、多忙な日々を送る学生が少なくありません。そのため、就職活動に充てられる時間は限られてしまうでしょう。自己分析や企業研究、エントリーシートの作成、面接対策など、就職活動には多くの準備と時間が必要です。しかし、授業や実習に追われるなかで、これらの対策を十分にこなすことが難しいと感じる学生もいます。
就職活動のスケジュールを立てて、限られた時間のなかでしっかりと準備や対策を行いましょう。スケジュールの立て方は後述するので、参考としてお役立てください。
大卒以上の求人には応募できない
就職活動において、専門学校生は、大卒以上を応募条件とする求人には応募できません。応募できる求人や企業が限られてしまうため、就職活動の選択肢が狭まると感じることも。たとえば、大手企業や特定の職種では、大卒以上を応募条件としているケースが見受けられます。
専門学校生の就職活動では、自分が学んだ専門分野に特化した求人や、学歴不問の求人を中心に探す必要があるでしょう。
在籍中に専門スキルを習得できない場合がある
専門学校に入学したものの、カリキュラムや教育内容が期待と異なり、卒業までに十分な専門スキルを習得できないと感じる場合があります。たとえば、入学前にイメージしていた授業内容と異なっていたり、実習環境が不十分だったりすると、卒業後のキャリアプランがあいまいになり、就職活動で自分の強みをアピールしにくくなる可能性があるでしょう。特に、技術職や専門職では、在学中にどれだけスキルを磨けたかが就職の成功を左右するため、希望する職種への就職が厳しくなることもあります。
専門学校のパンフレットやオープンキャンパスで得られる情報だけでなく、在校生や卒業生の声を参考に、入学前に十分な情報収集を行いましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
専門学校生が就職活動を成功させるコツ
専門学校生が就職活動を成功させるためには、具体的なスケジュールを立てて、習得した知識やスキルを棚卸しすることが大切です。
ここでは、専門学校生が就職活動を成功させるコツについて解説します。これから就職活動を始める方や、専門学校生への入学を考えている方は参考にしてみてください。
具体的なスケジュールを立てる
就職活動の成功に向けて、具体的なスケジュールを立てましょう。以下で、専門学校生の就活スケジュールの流れをまとめました。
専門学校生の就活スケジュール
- 【1年制は4月、2年制は9月】就職ガイダンス
- 【3月】会社説明会
- 【6月】選考
- 【10月】内定
専門学校が2年制の場合、大学と同様に卒業年度の1年前から就職ガイダンスが始まります。なお、1年制の場合は入学した4月に行われるのが一般的です。就職ガイダンスの時期に自己分析や企業研究を始め、会社説明会への参加やエントリーシートの作成に取り組みます。
本格的な選考が始まるのは、大手企業を中心に6月からです。中小企業の選考は、7月中旬ころから始まります。選考の合否が決まり、内定が出始めるのは一般的に10月ごろです。12月になると、内定を貰い就職先を決めた人が多い傾向にあります。
就職活動の流れを押さえたうえで、いつまでに何をすべきか具体的なスケジュールを立て、内定獲得に向けて準備と対策を進めましょう。
学んだことや身につけたスキルを棚卸しする
専門学校での学びを就職活動に活かすためには、授業や実習を通して学んだことや身につけたスキルを棚卸し、整理することが大切です。たとえば、授業で制作した作品や実習で得た知識、資格取得に向けた努力など、専門学校での経験をすべて書き出してみましょう。そうすると、自分の強みや得意なことを客観的に把握でき、自己PRや志望動機を作成する際に役立ちます。
ポートフォリオを作成する場合は、何のスキルを使い、どのようなプロセスで作品を完成させたのかを具体的に示せれば、企業側に自分の能力を明確に伝えられるでしょう。
専攻分野を活かして就職活動をする
専門学校で培った知識やスキルを最大限に活かすことが、就職活動を成功させる方法の1つです。専門学校は、特定の分野のプロフェッショナルを育成することを目的としているため、即戦力として期待されます。
就職活動では、学んできた分野に関連する企業や職種を中心に探してみましょう。たとえば、医療系の専門学校生であれば病院やクリニック、デザイン系であればデザイン事務所や広告代理店など、自分の専門性が活かせる職場を見つけることで、内定獲得の可能性が高まります。また、面接では「なぜその分野を志望したのか」「どのように貢献したいのか」を採用担当者に伝えることが大切です。
専門学校に通ってから就職する4つのメリット
専門学校に通ってから就職するメリットには、「授業や実習を通し、即戦力につながる知識とスキルの習得や経験が得られる」「同じ目標をもった仲間と切磋琢磨しながら学べる」などが挙げられます。以下でメリットを紹介するので、専門学校に通うか迷っている方はデメリットとあわせて目を通してみてください。
1.即戦力につながる知識や経験が得られる
専門学校は特定の分野に特化し、働くうえで必要な知識や技術を学べるのが特徴です。専門学校では知識の習得だけでなく、実習や演習が設けられているので、より実践的な技術が身につきます。そのため、卒業するころには企業が求めるスキルを身につけている場合が多く、即戦力として期待されるでしょう。
専門学校のなかには、卒業と同時に国家資格を取得できたり、試験の受験資格を得られたりする学校もあります。業界や職種によっては、資格がないと仕事ができない場合もあるため、在学中に取得した資格や専門知識は就活で強い武器となるでしょう。
2.業界とのコネクションを得やすい
専門学校は特定の業界との連携が強く、それが就職活動に有利に働くことがあります。学校によっては、つながりのある業界の企業から直接求人情報が寄せられたり、学校独自の企業説明会が開催されたりして、多くの企業と接点を持つ機会を得られるでしょう。
講師が業界の現役プロである場合、授業で学んだ内容がそのまま仕事に直結するだけでなく、講師を通じて業界の最新情報を得たり、人脈を広げたりすることも可能です。
3.充実した就職指導を受けられる
多くの専門学校は、入学直後から就職ガイダンスが始まり、定期的に就職セミナーや相談会などを実施しています。就職の専任スタッフを置いて、学生の就職相談やサポートを行っている学校もあるようです。
このように、専門学校生は就職の情報を得やすい環境に置かれており、就職へのモチベーションが維持されやすくなっています。学生が安心して就職活動に取り組めるよう、手厚いサポートを提供しているため、就職活動で何から手をつければいいか分からない場合でも、専任スタッフに相談できる安心感があるでしょう。
サポート内容や充実度は学校によって異なる
専門学校の就職支援は、学校によって内容や手厚さが大きく異なります。専門学校生のなかには、就職サポートが手厚いと聞いて入学したものの、実際には「就職に関する有益な情報が得られにくい」とギャップを感じている人もいるようです。
専門学校を検討している方は、入学後に後悔することのないよう「就職率のチェック」のほか、「オープンキャンパスや学校説明会のイベントに参加する」「先輩に実情を聞いてみる」などして、就職のサポート内容や充実度をきちんと調べましょう。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
4.同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる
専門学校には、特定の分野に興味や関心を持つ学生が集まります。そのため、同じ目標を持つ仲間と出会い、ともに学べるのは専門学校に入学するメリットです。授業や実習などを通して、互いに刺激し合い、高め合う関係を築けるでしょう。
たとえば、作品制作でアイデアを共有したり、技術的な課題を一緒に解決したりして、1人では成し得なかった成果を出せることも。就職活動では、情報交換をしつつ、お互いを励ましながら支え合うこともあるでしょう。同じ目標を持つ仲間とともに成長できる環境は、専門学校ならではの魅力といえます。
専門学校に通ってから就職する3つのデメリット
専門学校に通ってから就職するのは、メリットだけでなく「就職先の選択肢が限られる」「大卒と比べて給与が低い傾向にある」といったデメリットもあります。通ってから後悔することのないよう、ここでデメリットも把握しておきましょう。
1.就職先の選択肢が狭まる
専門学校は、特定の分野の知識やスキルを専門的に学ぶため、就職先の選択肢が限定されることがあります。たとえば、途中で興味が変わったり、別の分野に挑戦したくなったりした場合、専門学校で培ったスキルが直接活かせないため、就職活動が難しくなる可能性があるでしょう。
また、企業によっては、応募条件を「大卒以上」と定めている場合があります。専門学校生は「専門卒」となるので、大卒以上の求人には応募ができません。進路が明確でない場合は、専門学校に通うことで「就職先の選択肢が狭くなる」「応募できない企業が発生する」といったリスクが生じるでしょう。
2.大卒よりも給与が低い傾向にある
専門学校卒は、大卒と比べて給与が低い傾向にあります。これは、専門学校が特定のスキル習得に特化している一方、大学がより幅広い教養やビジネススキルを身につける場と見なされているためです。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」をもとに、専門卒と大卒の給与平均を表にまとめました。
| 学歴 | 初任給 | 平均給与 |
|---|
| 専門卒 | 22万2,800円 | 30万6,900円 |
|---|
| 大卒 | 24万8,300円 | 38万5,800円 |
|---|
専門卒と大卒の初任給は2万円以上の差があり、専門卒と大卒の全年齢を含めた全体平均では、8万円近くの差があると分かります。ただし、頑張りや成果が認められ昇給・昇進をすることで、給料の差を埋められる可能性があるでしょう。
3.年齢がネックにになる場合がある
既卒やフリーターから専門学校へ通おうと考えている方は、就職時の年齢が上がってしまうと就職で不利になる場合があります。就職において年齢制限はありませんが、新卒採用では卒業年次や年齢が重視されることもあるため、一定の年齢を超えてしまうと、未経験から採用される可能性が低くなるのが現状です。就職を目的に専門学校への進学を考えている方は、就職時の年齢も考慮する必要があるでしょう。
専門学校卒業後に就職できない場合の進路
専門学校卒業後に就職できない場合、就活を継続するほかに、「大学に進学して学ぶ」「アルバイトや契約社員などの非正規雇用で働く」といった選択肢があります。ここでは、専門学校を卒業した後に就職できない場合の進路を紹介するので、どのような選択肢があるのか確認しましょう。
就活を継続する
専門学校を卒業しても就職先が決まらない場合、まずは就職活動を継続する選択肢があります。専門学校卒業後も新卒枠で応募できる企業があるかを確認し、応募先を広げてみましょう。厚生労働省の「卒業後3年以内の既卒者は、『新卒枠』での応募受付を!」により、多くの企業では、新卒の採用活動を卒業後数年間は継続している場合があります。
専門学校によるものの、卒業後も在学中と同じように就職活動をサポートしてくれる場合があるので、相談してみましょう。
エージェントにサポートしてもらう方法がおすすめ
就職・転職エージェントは、個人のスキルや希望に合った求人紹介のほか、応募書類の添削や面接対策など、就職活動全般をサポートしてくれます。また、非公開の求人情報を持っていることもあり、自分1人では見つけられなかった企業と出会える可能性が高まるでしょう。自分に合ったエージェントを見つけて、効率的に就職活動を進める方法がおすすめです。
大学に編入して学ぶ
専門学校で学んだことを活かしつつ、さらに専門性を深めたい場合や、将来の選択肢を広げたい場合は、大学への編入を検討するのも1つの方法です。専門学校の卒業生は、大学の3年次に編入できる場合があります。文部科学省の「大学への編入学について」によると、「専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(法第132条)」の条件に当てはまる場合、大学への編入が認められるようです。
大学では、専門分野をより深く研究できるだけでなく、幅広い教養を身につけられます。これにより、就職活動では専門性と教養の両方をアピールできるでしょう。ただし、大学によっては編入制度がない場合もあるため、事前に志望校の情報を調べておくことが大切です。
非正規雇用で働く
就職先がすぐに見つからない場合、アルバイトや契約社員、派遣社員などの非正規雇用で働く選択肢もあります。非正規雇用でも、専門学校で学んだ知識やスキルを活かせる仕事を選べば、実務経験を積むことが可能です。その経験は、その後の就職活動において大きな強みになる可能性があります。
また、非正規雇用で働きながら転職活動を継続できるので、焦って希望しない仕事に就くよりも、働きながら自分に合った仕事を探す時間を持つことも大切です。
公務員を目指して採用試験を受ける
安定した働き方を望む場合、公務員を目指して採用試験を受ける方法も選択肢の1つです。公務員には、国家公務員と地方公務員があり、さまざまな職種が存在します。専門学校卒から公務員になるためには、公務員採用試験への合格が必要です。
公務員試験には筆記試験と人物試験があり、合格に向けた勉強と対策が欠かせません。受験する区分によって、試験の難易度や倍率も変わるでしょう。自分でスケジュールを立てて勉強したり、予備校や通信講座を利用したりして、計画的に学習を進めることが大切です。
フリーランスとして独立・起業する
専門学校で学んだ専門的なスキルを活かして、フリーランスとして独立したり、起業したりする道もあります。たとえば、IT系の専門学校でプログラミングスキルを身につけたのであれば、Webサイト制作やアプリ開発の仕事を受注できるでしょう。また、デザイン系の専門学校であれば、デザイン制作の仕事を引き受けることも可能です。
独立や企業をした場合、自分で仕事を見つけてくる営業力や管理能力が求められるものの、スキルを最大限に活かして働き方を自由に決められるでしょう。ただし、安定して仕事を受注できるまでの間は収入が不安定になりやすいため、資金計画や事業計画をしっかりと立ててから取り組む必要があります。
専門学校生が就職活動に不安を感じたときの対処法
就職活動を進めていると、思うように選考が進まず「ちゃんと就職先が決まるか心配」「もし就職できなかったらどうしよう」など、不安を感じることもあるでしょう。ここでは、専門学校生が就職活動に不安を感じたときの対処法を6つ紹介します。
専門学校生が就職活動に不安を感じたときの対処法
- 就活の軸を明確にする
- 業界・企業に幅を持たせる
- 専門学校卒業生の就職先を確認してみる
- インターンに参加してみる
- スキルや知識を身につける
- 就職支援サービスを利用する
就活の軸を明確にする
専門学校生が就職活動に不安を感じた際は、まず「就活の軸」を明確にすることが大切です。どのような仕事に就きたいのか、仕事を通じて何を成し遂げたいのかなど、自分にとっての優先順位を整理しましょう。
目的が不明確なまま就職活動をしていると、モチベーションが上がらなかったり面接での受け答えに一貫性がなかったりと、うまく進まない傾向があります。就職活動への目的意識を深めるためにも、就活の軸は事前に定めておくのが成功に近づくためのポイントです。
業界・企業に幅を持たせる
特定の業界や企業にこだわって就職活動を進めており、なかなか内定が出ないと、「本当に就職できるだろうか」と不安が大きくなることがあります。そのようなときは視野を広げて、これまで考えていなかった業界や企業にも目を向けてみましょう。
専門学校で学んだ知識や身につけたスキルは、一見関係なさそうな業界でも活かせる場合があります。たとえば、デザイン系のスキルは、ITや広告、製造業などの業界で求められるため、学んだことを活かして活躍できる可能性があるでしょう。
また、知名度や企業規模を問わずに求人を探してみるのもおすすめです。就職の選択肢を増やすことで、自分に合った企業と出会える可能性が広がります。
専門学校卒業生の就職先を確認してみる
同じ専門学校の卒業生が、どのような企業に就職しているのかを知ることで、就職活動の不安が和らぐ場合があります。まずは、専門学校のパンフレットやWebサイトに掲載されている、過去の卒業生の就職先を確認してみる方法がおすすめです。
実際に就職した卒業生の声を聞く機会があれば、仕事内容や就職活動の経験談を質問してみましょう。学校に相談すれば、OB・OGの情報を得られる場合もあります。卒業生の就職先や成功事例を知ることで、就職活動のモチベーションを高められるでしょう。
インターンに参加してみる
専門学校生が就職活動に不安を感じる理由の1つに、「実際の仕事内容が想像できない」ことが挙げられます。この不安を解消するためには、インターンシップに参加して実際に企業で働き、仕事内容や職場の雰囲気を体験してみるのがおすすめです。インターンシップの参加により、自分の適性や興味を確かめられるだけでなく、面接で話せる具体的な経験を得られます。
また、インターンシップを通じて、企業の人事担当者と直接コミュニケーションをとり、就職への意欲をアピールすることも可能です。
スキルや知識を身につける
専門学校の就職活動では、実践的なスキルや学んだ分野の深い知識が大きな強みになります。もし、就職活動に不安を感じたり、学んでいる内容とは別のスキルが必要な企業を志望したりする場合は、改めて自分のスキルを見直し、足りない部分を補う努力をしてみましょう。
たとえば、資格取得を目指して勉強する、関連分野のアルバイトを始めるなど、実際に行動を起こすことは自分の自信につながります。企業側も、学生が自主的にスキルアップに取り組む姿勢を高く評価するため、就職活動では積極的にアピールしましょう。スキルを磨くことは、就職活動を有利に進めるだけでなく、入社後の業務でも役立ちます。
就職支援サービスを利用する
専門学校生は、就職先の選択肢や可能性を広げるために、外部の就職支援サービスを併用して、学校外からの情報を集める方法がおすすめです。就職支援サービスの主な種類に、「就職・転職エージェント」と「ハローワーク」があります。
就職・転職エージェントは、求人紹介や履歴書・職務経歴書の添削、面接対策といった就職活動全般をサポートしてくれる支援機関です。面接の日程調整や就職後のフォローも手厚いので、安心して相談できます。エージェントに相談すると、キャリアアドバイザーが丁寧にサポートしてくれるため、スムーズに就職活動を進められるでしょう。
一方、ハローワークは、厚生労働省が運営している就職支援機関です。全国の各地域に拠点があり、地元の求人を多く取り扱っています。ハローワークでも就職相談や求人紹介を受けられるので、悩みや不安を解消しながら就職活動を進められるでしょう。
専門学校生の就職事情に関するまとめ
専門学校生の就職率は高く、10年以上にわたり90%を超えています。就職活動の際は、まず就活の流れを知り、具体的なスケジュールを立てたうえで取り組むことが大切です。学校で学んだ知識や身につけたスキルを棚卸しして、就職活動に向けた準備や対策を進めていきましょう。
また、就職活動に不安があったり、学んだ内容とは別の分野に挑戦したりする場合は、就職支援サービスの利用がおすすめです。プロのサポートを受けながら、自分に合った就職先を見つけましょう。
「専門学校で学んだ内容とは別の分野に挑戦したい」「自分に合った仕事を見つけたい」と考える方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、第二新卒や既卒を含む若年層の就活に特化したエージェントです。
専任のキャリアアドバイザーが丁寧に希望をヒアリングし、あなたの適性や価値観に合った求人を厳選してご紹介します。また、応募書類の書き方や面接対策のほか、面接日程の調整などもサポートしているので、スムーズに就活を進められるでしょう。分からないことがあれば、キャリアアドバイザーにすぐ相談できるため、就活に自信がない方や不安を抱える方も安心です。ハタラクティブのサービスはすべて無料でご利用いただけるので、まずはお気軽にご相談ください。
専門学校生が就職に感じるお悩みQ&A
ここでは、専門学校生の就職事情でよくある疑問に対し、Q&A形式で回答します。専門学校生の就職事情が気になる方は、参考としてご覧ください。
厚生労働省の「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」によると、専門学校生の就職率は99.2%と公表されています。
専門学校は特定の職業に必要な知識やスキルを習得できるため、その分野においては就職で有利に働くでしょう。大学とは異なり、専門的なスキル習得に特化したカリキュラムが組まれているため、企業側も即戦力として期待します。また、学校によっては業界とのつながりが強く、独自の求人情報を得られることも。在学中に学べる知識や習得できるスキルは、就職活動において武器となるでしょう。
専門学校が2年制の場合、大学生と同じように卒業年度の1年前から始めます。1年制の場合は、入学月の4月から始めるのが一般的です。
就職活動はガイダンスから始まり、会社説明会、選考、内定の流れで進みます。本格的な選考は6月から始まるので、内定獲得に向けて十分な準備と対策を行うことが大切です。コラム内では、就活スケジュールについて詳しく解説しているので、そちらもあわせてご確認ください。
就職先が決まらない場合は、なぜ内定が出ないのか原因を分析してみましょう。面接での受け答えや自己PRが不十分だったのか、応募書類に改善点があるのかなど、客観的に振り返ることが重要です。
また、視野を広げて、当初考えていた業界や職種以外に目を向けてみるのも選択肢の1つといえます。ハローワークやエージェントなど、学校以外の就職支援サービスを利用して、サポートを受けながら新たな求人情報を探す方法もおすすめです。
専門学校生が就職活動を成功させるためには、学んできた専門スキルや知識を具体的にアピールしましょう。また、インターンシップやアルバイトを通じて、実務経験を積んでおくこともプラスになります。面接では、なぜその企業で働きたいのか、入社後にどのように貢献できるのかを明確に伝えることが大切です。
専門学校を中退したことに対して自信をなくす必要はありません。就活では中退した理由を正直に説明し、その経験から何を学び、今後にどのように活かしたいかを前向きに伝えます。たとえば、「自分の学びたいことが明確になり、新しい道に進むために中退を決意しました」といったように、ポジティブな言葉を意識して説明しましょう。
また、専門学校中退から就職を目指すなら、エージェントに相談してサポートを受ける方法がおすすめです。就職に向けた幅広いサポートを受けられるので、不安を解消しながら就活に取り組めるでしょう。
就職・転職エージェントのハタラクティブでは、中退者を含む若年層の就活をサポートしています。キャリアアドバイザーがあなたの就活を全面的にサポートするので、就職を考えている方はお気軽にご相談ください。