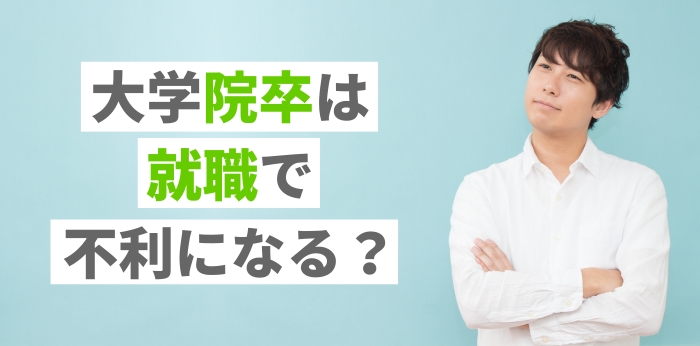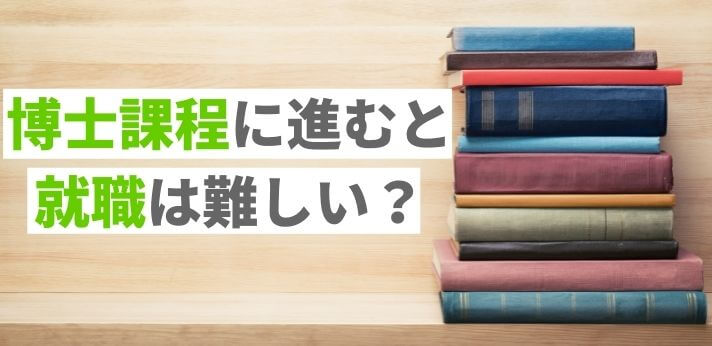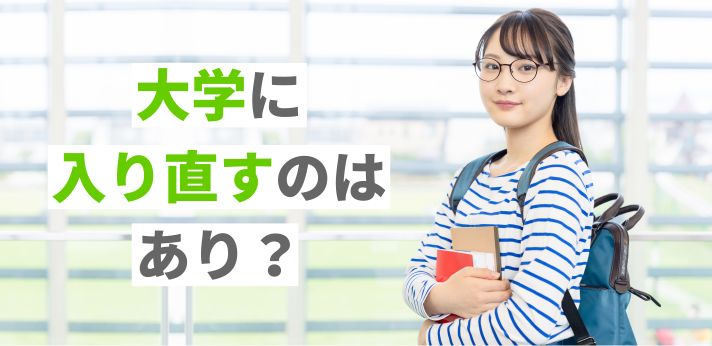学士とは?大学の学位の違いと就活に与える影響を解説学士とは?大学の学位の違いと就活に与える影響を解説
更新日
公開日
学士とは何か、正しい定義が分からない方もいるでしょう。大学や大学院で無事学業を修めると「学位」が授与されます。学位のなかでも、大学を卒業すると得られるのが「学士」です。
このコラムでは、学士・修士・博士の学位の違いや、社会的な評価についてまとめました。また、「短大卒は準学士?」「専門学校卒の称号は?」といった疑問についても解説するので、それぞれの違いを知って学位に合った就活時の参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
学士とは
学士とは、大学を卒業した人に与えられる学位です。卒業に必要な単位を履修したうえで卒業論文や試験に合格すると、卒業時に学士の学位が得られます。したがって、在学中の大学生は学士とは呼びません。
学士を得るための卒業要件
学士となるために必要な大学卒業の条件は、124単位以上を取得することです。
なお、詳細は大学によって異なり、130単位以上を要件としている場合もあるようです。
そのほか、大学卒業の条件には、以下のような違いがあります。
- ・大学によって必修科目、専門科目、自由科目ごとに必要な単位が異なる
- ・同じ大学でも、学部/学科によって必要な単位数や卒業論文の有無などが異なる
- ・医学や薬学といった一部の学部については、卒業要件が異なる
単位を取得するには、授業に出席するほか、課題やテストの点数などが影響する場合もあるため、事前によく確認しておくことが重要といえます。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
学位とは
学位とは、大学や大学院で学業を修めると授与されるものです。学位は、「修士」や「博士」などの総称で、「学士」も含まれます。
「学位授与等」によると、文部科学省は学位を以下のように定義しているようです。
- ・学術の中心である大学が与えるもの
- ・一定水準の教育を受け、知識/能力をもつと認められる者に与えられるもの
- ・授与された学位は国際的にも通用
学位には法的な定めがある
学位は、大学や大学院において、以下の項目を修めた人に授与されます。
- ・規定の教育課程を履修
- ・試験や卒業論文に合格
- ・研究および論文を発表
学位ごとに授与の要件が決められている
たとえば、修士の場合は「大学院設置基準 第十六条(修士課程の修了要件)」で学位授与の条件が定められています。これによると、「大学院に二年<中略>以上在学し、三十単位以上を修得し、<中略>修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする」が要件です。
前述のとおり、学士の卒業単位は124単位以上であり、修士と異なることが分かります。同様に、博士についても個別の定めがあるようです。
学位には専攻分野も併記するのが原則
学位を記載する際は、専攻分野も表記するのが原則です。同省の「学位規則 第十条(専攻分野の名称)」には、「学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。」と明記されています。
たとえば、「学士(教育学)」「修士(生物学)」といった書き方が正式です。
学位をもっていると、専門的な知識や技術を習得している証拠になるので、就活の際にスキルの証明になります。
自分が学んだ専門分野に関連した就職先を目指す場合は、スキルの証明ができるので就活で有利になりやすい傾向にあるでしょう。
学位と称号の違い
学位と称号は、その国際的な通用度に違いがあります。
「称号」は、特定の学校を卒業したことについて本人が称することができるもので、公に一定の価値・栄誉がありますが、国際的には、どのような知識・能力を持つか理解され難いことがあります。
学位として認められていない称号は、日本国内では一定の知識の証明になりますが、国際的には通用しない可能性があるようです。
高卒と学位の違い
「学校教育法 第五十一条」によると、高等学校における教育は、「義務教育として行われる普通教育の成果をさらに発展拡充させ」ることが目的とされています。
一方、大学は「学校教育法 第八十三条」にて、「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」と記載されているようです。
高校と大学では目的が異なるため、それぞれで学べる専門性の高さも異なるといえるでしょう。また、学位は選考した専門分野によって称号が異なり、教育学部は「教育学士」、文学部は「文学士」というように専門的な学問を修めたことを証明する学位を得られます。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
学位・称号の種類を一覧で紹介
学士以外の学位には、「修士」や「博士」「短期大学士」などが挙げられます。そのほかにも、国が認めた専門学校を卒業した人に与えられる「専門士」という称号も。以下の一覧で学位・称号の全体像を確認してみてください。
主な学位・称号の種類
| 学位・称号 | 学歴 |
|---|
| 博士 | 大学院(標準5年) |
|---|
| 修士 | 大学院(標準2年) |
|---|
| 学士 | 大学(4年)※特別の学部では4年以上 |
|---|
| 短期大学士 | 短期大学(2年または3年) |
|---|
| 高度専門士 | 文部科学省で認めた専修学校(4年以上) |
|---|
| 専門士 | 文部科学省で認めた専修学校(2年以上) |
|---|
上記のうち、博士の大学院の在籍期間は、修士課程も含めて5年です。いずれの学位も、必要に応じて在籍期間は前後する場合があります。
学士以外の学位・称号の特徴
この項では、前項で紹介した主な学位・称号について、詳しい内容を説明します。
博士とは
博士とは、大学院の博士課程を修了、または博士論文が認められた人に授与される学位です。「ドクター」とも呼ばれ、博士と称されるもののなかには「課程博士」と「論文博士」があります。この2つの違いは、以下のとおりです。
- ・課程博士…大学院の博士課程へ進学後、研究をして博士の認定をされたもの
- ・論文博士…博士課程を経ずに博士論文を提出し、博士と認定されたもの
論文博士として称号を得るには、たとえば「修士修了後に企業へ研究職として就職し、仕事で研究論文を発表して認定を得る」といった方法があるでしょう。
自身の研究テーマに打ち込み、論文でその成果を発表するなどの研鑽を積むことで、将来的には大学教授への道も拓けます。
修士とは
修士とは、大学院の修士課程を修めた後に授与される学位です。「マスター」とも称され、基本的には4年制学部で学士を得たあとに、2年間の大学院修士課程を修了することで取得できます。しかし、以下の学部学科の場合は異なる場合もあるので確認しておきましょう。
- ・医学部医学科
- ・歯学部歯学科
- ・農学部獣医学科
- ・薬学部薬学科
これら6年制学部で学士を得た場合は、2年間の修士課程を経ずに博士課程へ直接進学するので、学士から博士を取得することになります。
修士と博士の目的の違い
| 修士課程 | 幅広く深い学識を養い、
研究能力に加えて高度な専門的職業を担うための卓越した能力を培う。 |
|---|
| 博士課程 | 研究者として自立して研究活動が行える、
あるいは社会の多様な方面で活躍できるほどの研究能力を身につけられるように、
その基礎となる学識を養う。 |
|---|
修士は「高度専門職業人の養成」「高度で知的な素養のある人材の養成」が目的とも示されており、卒業後は社会的なニーズに応えることが重視されています。一方、博士は「多様な研究・教育機関の中核を担う研究者」「大学教員の養成」を目的としており、修士よりも研究者養成に重点を置いているといえるでしょう。
博士はドクター、修士はマスター、学士は?
修士課程や博士課程の呼称としてよくあるのが、「M1」「D1」「B1」などです。
- ・M…修士課程「Master’s course」
- ・D…博士課程「Doctor’s course」
- ・B…学士課程「Bachelor」
これは大学や大学院でどの程度の過程を習得しているかによって異なり、たとえば修士課程で1年の場合は「M1」と呼びます。
短期大学士とは
短期大学士とは、短期大学を卒業した人に与えられる学位のことです。短期大学士の必要期間は2〜3年が一般的であるため、学士よりも短期間で学位が取得できることがメリットの一つ。短期大学士の学位を取得すると、大学への編入ができるため、進路に幅ができます。
準学士とは
短期大学士は、2005年10月の制度改正で認められるようになった学位です。
それ以前は短期大学を卒業すると「準学士」という称号が得られる仕組みでしたが、2005年から「短期大学士」の学位に変更されました。なお、「準学士」は、高等専門学校を卒業した場合に得られる称号として現在も存在しています。
専門士とは
専門士は学位ではありませんが、文部科学大臣が認めた専門学校を卒業した人に与えられる称号です。短期大学士と同じ扱いになり、大学への編入ができる場合も。文部科学省の「専門士・高度専門士の称号とは」によると、専門士の称号が付与される専門学校の要件として、以下が定められています。
【「専門士」の称号が付与される専門学校の要件】
1.修業年限が2年以上
2.総授業時数が1,700単位時間(62単位)以上
3.試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
高度専門士とは
文部科学大臣が認めた4年以上の専門学校を卒業した人には、高度専門士という称号が与えられます。高度専門士も学位ではありませんが、大学卒業と同じ扱いになり、大学院への入学ができる場合も。大学院へ入学するには、指定されている専修学校の専門課程を修了する必要があります。高度専門士の称号が付与される専門学校の要件は、以下をご覧ください。
【「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件】
1.修業年限が4年以上
2.総授業時数が3,400単位時間(124単位)以上
3.体系的に教育課程が編成されていること
4.試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
専門士、高度専門士ともに学位ではないものの、その後の進路により、学位の取得が可能になります。
専門職学位とは
専門職学位は、専門職大学院や専門職大学、専門職短期大学を修了すると与えられる学位です。例としては、法科大学院を修了した人に与えられる「法務博士(専門職)」や、教職大学院を修了した人に与えられる「教職修士(専門職)」などがあります。
専門職大学・専門職短期大学は2019年にできた制度で、専門職業人材の養成強化が目的です。産業界と連携して実践的な職業教育が行われ、卒業単位の3〜4割以上が実習科目(企業内実習あり)となっています。専門職大学を卒業すると「学士(専門職)」の学位が与えられ、専門職短期大学を卒業すると「短期大学士(専門職)」の学位が与えられるでしょう。
専門職大学院は、高度で専門的な知識とスキルを兼ね備えた高度専門職業人を養成することが目的です。法務博士や教職修士以外の一般専門職大学院を修了すると、「修士(専門職)」の学位が与えられます。
法学士とは?
大学の法学部を卒業すると、かつては法学士と呼ばれていたようです。しかし、現在は「学士(法学)」が正式な学位となっています。
なお、法学部を卒業しただけでは弁護士にはなれず、司法試験に合格する必要があります。
学士・修士・博士の社会的な評価の違いとは
社会的には、「博士>修士>学士」というように、博士号や修士号の難易度が高く認識される傾向にあります。「博士号は大学教授を目指す人が多い」というイメージや「学位の違いが就職後の初任給にも表れる」という実情も理由の一つでしょう。
以下では、学士・修士・博士の社会的な評価の違いを詳しく紹介するので、参考にしてみてください。
初任給の違い
| 学歴 | 20~24歳(高卒は~19歳)の平均賃金 |
|---|
| 大学院 | 28万6,200円 |
|---|
| 大学 | 25万800円 |
|---|
| 高専・短大 | 23万400円 |
|---|
| 専門学校 | 23万1,000円 |
|---|
| 高校 | 19万9,800円 |
|---|
上の表から分かるとおり、博士・修士(大学院卒)と学士(大学卒)では初任給に3万5,000円以上の差があります。1ヶ月の給料としてみると大差がないように思えますが、年収にすると42万円ほどの差です。
このことから、社会的な評価は学士よりも博士・修士のほうが高い傾向であることが分かります。
専門性の違い
学士・修士・博士では専門性のレベルも異なります。修士や博士は、大学院に通ったり研究所や企業に勤めたりしながら自分が専攻する分野の研究を行っていることから、学士に比べさらに専門的知識をもっていると評価されるでしょう。
研究職や開発職、そのほか専門分野に関連する仕事に就きたい場合は、専門性が高いほうがより就活で有利になりやすいといえます。
日本と海外の違い
日本では博士を高く評価するのは研究職に限定される傾向にありますが、海外では社会的に高く評価されるようです。特に、アメリカでは博士号を取得すると給料が高く、昇進にも有利になる場合があるといわれています。
したがって、海外への就職を視野に入れているのであれば、修士以上を取得することで高評価を目指すのも一つの方法です。
学費からみる学士・修士・博士の違い
学位はそれぞれ修了する課程で取得できるものが決まりますが、学位取得までに掛かる学費にも差があることを踏まえて進路を考えることが大切です。下記を参考に、自分が進みたい道は何か考えてみてください。
国公立大学
各国立大学法人は標準額を踏まえ、「一定の範囲内」でそれぞれ定めているようです。国立大学の「標準額」と文部科学省の「国公私立大学の授業料等の推移」を参考に、公立大学の2023年の平均額を紹介します。
| 区分 | 授業料の年額 | 入学料 |
|---|
| 国立大学 | 53万5,800円 | 28万2,000円 |
|---|
| 国立短期大学 | 39万円 | 16万9,200円 |
|---|
| 国立大学院 | 53万5,800円 | 28万2,000円 |
|---|
| 国立法科大学院 | 80万4,000円 | 28万2,000円 |
|---|
| 公立大学 | 53万6,191円 | 37万4,371円 |
|---|
上記の図のなかで最も費用が必要なのは、国立法科大学院です。弁護士、検察官、裁判官を養成するための教育を行う大学院で、先述した「法務博士」の学位だけでなく司法試験の受験資格も得られます。
私立大学
| | 授業料の年額 | 入学料 |
|---|
| 私立大学 | 95万9,205円 | 24万0,806円 |
|---|
| 私立短期大学 | 72万9,069円 | 23万7,122円 |
|---|
授業料の年額と入学料ともに、私立短期大学より私立大学のほうが高いことが分かります。私立短期大学を卒業すると、先述したように「短期大学士」という学位を取得でき、そのあとは4年生大学への編入学や短期大学専攻科入学といった進路に進むことも可能です。
修士・博士の学費
| | 授業料の年額 | 入学料 |
|---|
博士前期課程
(修士課程を含む) | 79万8,465円 | 20万1,752円 |
|---|
| 博士後期課程 | 60万4,592円 | 19万2,686円 |
|---|
| 専門職学位課程 | 106万7,207円 | 19万4,492円 |
|---|
学位による学費の差
国立大学では標準額が決められているため、学位による学費の差はありません。しかし、前述の「私立大学」の表から分かるように、私立大学の学費は、修士・博士よりも高いことが分かります。また、専門性が高い専門職大学院では、より高度な内容になるため、授業料も高くなるようです。
学士・修士・博士の就活での違いとは
就活するにあたって、学士・修士・博士で求められることが変わります。ここでは、それぞれの学位で就きやすい職業などをご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
学士は社会人としての基礎スキルが評価基準
就活で学士に求められるのは、「学生生活での活動を入社後の業務に活かそうとする姿勢」「業務に関する知識やスキルを積極的に習得しようとする意欲」など社会人としての基礎的なスキルです。
就活の面接では、主体的に動ける人材であることをアピールするのがおすすめ。その際、根拠となるエピソードとして学生生活での活動を具体的に挙げられると、説得力をもたせることができます。
修士は専門職への就職に有利になる傾向がある
就活で修士に求められるのは、専門性です。そのため、学士よりも専門性が高い修士は、専門職への就職が有利といえます。研究や開発といった分野、シンクタンク、コンサルティングなどの業務では、修士の専門性を活かせるでしょう。
就活では、学生時代に経験した出来事よりも、研究の実績を伝え、専門分野の知識やスキルをアピールすることをおすすめします。
博士は研究職や教授職で役に立つ
博士号を取得した場合、民間企業への就職ではなく研究職や教授職で有利になりやすい傾向にあります。博士は、博士課程修了後に「ポストドクター(ポスドク)」といって、任期付きの研究員として大学で働くこともあるようです。将来的には、「助教→講師→准教授→教授」というキャリアアップも目指せるでしょう。
学士よりも修士や博士が就活で不利な傾向にある理由
ここでは、学士より修士や博士が就活で不利な傾向にある理由について紹介します。先述したように、社会的には学士よりも博士や修士の地位が高い傾向にあるといえるでしょう。しかし、就活においては、博士や修士よりも学士の方が求人数が多いのが実状です。その理由となるものは何か、以下でご紹介します。
専門分野の求人が少ないため
修士や博士は、専門分野の求人が少ないのが就活で不利といわれる理由の一つ。同じ分野を専攻している人口が多いと競争率は高くなり、同じ分野を専攻している人口が少ないとそもそもの求人数が少なくなってしまうため、専門職は狭き門といわれているのです。
また、専門性が高いゆえに、研究分野と異なる業界・職種に挑戦しにくいことから、学士よりも就活において不利だと感じることがあるでしょう。
人件費が掛かるため
修士や博士の採用には人件費が掛かるため、企業は多くの求人を出さない傾向にあります。先述したように、学士よりも修士や博士の方が初任給が高く設定されているため、ボーナスなども含めると学士よりも人件費の負担が大きいといえるでしょう。
企業側はコストの掛かる修士や博士の採用にはどうしても慎重になるため、就活において不利になってしまうようです。
就活時の年齢が学士より高いため
修士や博士は、就活時の年齢が学士よりも高いことも就活で不利になりやすい理由の一つ。修了までに掛かる年数から、修士課程修了時の年齢はおよそ25歳、博士課程終了時はおよそ30歳であることが考えられます。
若い人材を欲しがる企業のなかには、「専門知識より若さならではのフレッシュさが欲しい」と考え、20代前半の学士の採用に力を入れるところもあるようです。
修士や博士が不利なポイントを払拭するには
大学院へ進む際に、その分野における就職先がどの程度あるかをあらかじめ調べておくことは重要です。そのうえで、修士や博士が学士よりも不利な部分を払拭するには、研究で得たことを入社後に活かせるとアピールすることが大事になります。
人件費にコストがかかっても、それ以上の魅力や採用メリットがあると評価してもらえるよう、戦略を練って選考に挑みましょう。
選考対策に不安がある方は、就職エージェントのハタラクティブにぜひご相談くださいね。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
短大卒・専門学校卒から学士を目指すメリットとは
短大や専門学校で学んだ人が、さらに大学へ編入して学士号を取得することも可能です。学士を目指すことで、キャリアの選択肢が広がったり、さらに専門性が高まったりするメリットもあります。もし、「大学に挑戦してみたかった」という思いがあるなら、学士を目指すのも一つの方法です。
以下では、短大卒・専門学校卒から学士を目指す4つのメリットをご紹介します。
1.最終学歴が大卒だと選択肢が広がる
求人の応募条件を「大卒以上」としている企業もあるため、最終学歴が大卒だと挑戦できる仕事の幅が広がります。特に、企画職・研究職など、分析力や専門的な学問知識が必要とされる仕事では、大卒以上を条件にする企業が少なくありません。
「学歴だけで選択肢が狭まるのはもったいない」と感じる方は、学士を目指すのが望ましいでしょう。
2.専門性が高まりやすい
大学では、自分の興味や関心に応じて学部・学科を選び、専門的な知識を深めることができます。ゼミや卒論研究を行い、課題解決力や論理的思考力を磨くことも可能です。
また、経済学や経営学などを専攻すると、マネジメントに活かせる知識を得られることも。そのため、将来の幹部候補として、大卒以上の応募者を評価する企業もあります。
3.年収アップの可能性がある
前述のとおり、学歴によって賃金に差があるため、短大卒や専門学校卒に比べて大卒のほうが高年収を目指しやすい側面もあります。
もちろん、学歴に関係なく成果に応じて賃金を決める企業もあるため、一概にはいえません。ただし、初任給や昇進・昇給のスピードに学歴が影響する可能性もあることを念頭に置きましょう。
4.人との出会いが増える
大学に入ると、サークル活動や研究室などで人との出会いが増えるでしょう。こうした出会いが、将来の仕事につながる人脈となる場合もあります。
また、人との出会いが増えることで、自分の価値観が広がり、新しい挑戦のきっかけにもなりやすいのもメリットの一つです。
最終学歴を学士にする方法とは
最終学歴を学士にするためには、昼間または夜間の大学に通うか、通信制大学を利用して大学を卒業する方法があります。短大や専門学校を卒業後に学士の学位を得たい場合や、働きながら大学卒業を目指したい場合など、状況に合わせて最適な方法を選んでみてください。
昼間部に通う
一般的な学生と同じく、全日制の大学に通って学士号を取得する方法があります。国家資格の取得を目指す場合、種類によっては昼間部の通学が必須になる可能性もあるでしょう。
昼間部への通学は、学習時間をしっかり確保できるため、専門知識や友人関係を築きやすいのがメリットです。ただし、時間とお金が掛かるため、学費・生活費が課題となるでしょう。
夜間部に通う
働きながら学士を目指したい人には、夜間部がおすすめです。授業は夕方以降に行われるため、仕事をしながら通学できます。
ただし、仕事が終わってから授業を受けるのは、精神的・身体的にハードな側面も。また、授業の開始時間に合わせて退社できる仕事でないと、両立が難しい可能性があります。
通信制大学を選ぶ
通学が難しい人や自分のペースで学びたい人には、通信制大学という選択肢もあります。部分的にスクーリング(登校)が必要な場合もありますが、基本的にはオンラインで学習できるのが魅力です。自己管理力が求められるものの、費用を抑えやすく、社会人には現実的な方法といえるでしょう。
学士の文系・理系別の就活ポイント
就活では、専攻が文系か理系かによって、求められるものが変わります。それぞれ、どのようなアピールが効果的なのか、以下をご覧ください。
文系は教養や社会経済への関心をアピール
文系は、専門分野に関する教養と、社会経済に対する関心の深さをアピールするのがおすすめ。文系は研究の内容がビジネスと結びつきにくい場合、基礎教養や個人の能力が重要視されるためです。
そのため、研究内容そのものより、研究活動から得たスキルや強みをどのように仕事に活かせるかを伝えることがアピールになります。
理系は専門性をアピール
理系は、研究職や技術職としての即戦力が期待されるでしょう。そのため、学生の間にしっかりと専門知識をつけておくことが重要です。
理系の場合、学士であっても卒論研究などで専門性の高い内容を扱う場合があります。就活では研究内容や自身の得意分野をアピールし、ほかの応募者との差別化を図りましょう。
就活を前に学士・修士・博士で迷ったら
就活の時期になり、学士のまま大学を卒業して就職するのか、大学院へ進学するのか迷う人もいるでしょう。迷ったときは将来の目標から逆算して考えるのも一つの方法です。また、どうしても決められないときはプロのアドバイスを受けてみましょう。
キャリアプランを立てる
就活を始める前にキャリアプランを立てると、将来の目標を実現できそうな進路が明らかになるでしょう。
たとえば、特定の研究分野を追及したいなら、修士や博士が向いています。一方、営業職や事務職といった専門職以外の職種を希望する場合は、早めに就職するのが望ましいでしょう。また、専門職のなかでも、宅地建物取引士やファイナンシャルプランナーなど、働きながら資格を取得してスキルを高められる仕事もあります。
「キャリアプランを決められない」「どういう選択肢があるのか分からない」という方は、就職エージェントのキャリアアドバイザーに相談するのもおすすめです。
【体験談をご紹介!】大学院を中退して就職へ
ここでは、「みんなの就職エピソード」から、ハタラクティブを利用して正社員就職に成功した人の体験談を紹介します。
理系の大学院に通っていたものの、修士課程の2年目で中退したT.Tさん。修士1年目には新卒として就活しましたがうまくいかず、学費のことも考えて中退を選んだそうです。
その後、効率的な就活を求めてハタラクティブに相談。紹介された求人のうち3社の選考を受けたそうですが、”実はどれにも興味をもてませんでした。”
大学院時代に希望していたメーカーとは違う業種、また特定派遣という形態にも不安を感じたそうです。
しかし、特定派遣の正社員には”新しい技術や知識を身につけるチャンスがある”刺激的だしやりがいがありそう”と、多くのメーカーに技術職を送り込んでいる会社に就職を決めました。
内定後は、”製造系の技術職として実力をつけたい”という目標ができたようです。
【まとめ】学歴に不安があるなら選考対策に力を入れよう
学歴に不安があり、就職・転職に二の足を踏んでいる方は、選考対策に力を入れましょう。自己PRや志望動機をしっかりと準備することで、学歴以外の強みを伝えられます。面接では、これまでの経験や身につけたスキルをアピールし、ポテンシャルを感じさせるのがポイントです。
「学士をもっていないから就職が不安」「就活の進め方が分からない」とお悩みの方は、ハタラクティブへご相談ください。若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブは、20代のフリーター・既卒・第二新卒に特化した就職支援サービスです。
専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの希望や適性をもとに、マッチしそうな求人をご紹介。ほかにも、自己分析の深掘りから応募書類の作成、面接対策など、内定獲得までの道のりをマンツーマンでサポートします。
また、性格から分かる適職診断を所要時間1分程度で受けることも可能です。サービスの利用はすべて無料なので、「エージェントの利用が初めて」という方もお気軽にお問い合わせください。
学士に関するお悩みQ&A
ここでは、学位の一つである「学士」に関する疑問をQ&A方式で解決します。フリーターからの就職や中退した場合の学位についても回答していますので、ぜひ参考にしてみてください。
短大卒の学位は短期大学士です。学士は大卒の学位なので、短大卒は原則含まれません。学士を取得したい場合は、大学に編入する方法もあります。また、短期大学士として就職をするのも選択肢の一つです。
学士取得後フリーターだった場合、正社員は目指せる?
大学卒業後に就職せずフリーターだった場合も、正社員を目指すことは可能です。正社員就職をするには早めに行動することが重要。第二新卒枠を設けている企業が多いように、中途採用ではポテンシャルのある20代が求められる傾向があるためです。年齢が上がるにつれてよりスキルを求められ、選択肢が狭まる可能性があるので注意しましょう。
学士は学位で、大卒は学歴を指します。どちらも「大学を卒業した」という意味で使われるのが一般的です。ただし、短大や高専を卒業し、さらに通信制大学などで大卒に必要な単位を取得した人が、大学改革支援・学位授与機構の審査を通過すれば学士を得られる場合も。そのため、必ずしも「学士=大卒」ではないといえます。
転職活動において、文系と理系どちらか一方が確実に有利というわけではありません。
しかし、文系であれば営業や事務、理系であれば研究や開発などに向いているでしょう。応募する業界や職種によって求められる人材は異なるため、十分チェックしたうえで自身に合った企業を探しましょう。
ハタラクティブでは、あなたに合った職種をご提案。内定まできめ細やかにサポートするので、ぜひご相談ください。