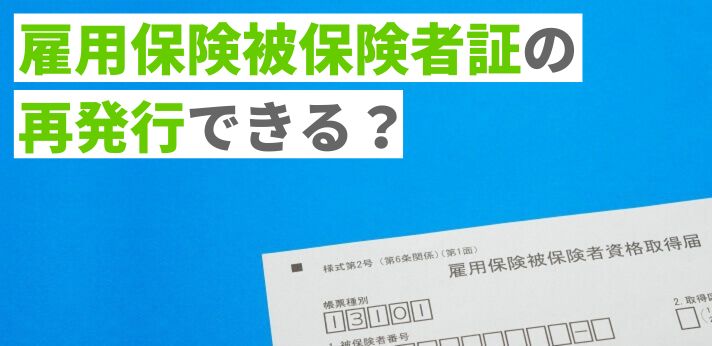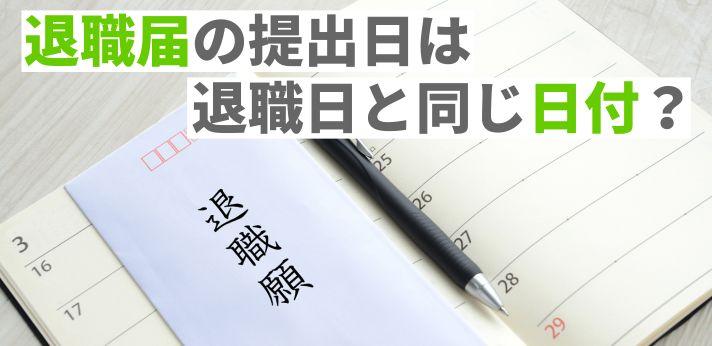失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる?条件や注意点を解説失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる?条件や注意点を解説
更新日
公開日
求職申し込みが済んでいれば、失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる
失業保険を受給している人のなかには、「職業訓練を受けられる?」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。基本的に、職業訓練はハローワークで求職申し込みが済んでいれば受講できます。このコラムでは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットと注意点を解説。残日数が足りないときの対処法をまとめているので、職業訓練への応募を検討している方は参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる?
一定の条件を満たしていれば、失業保険をもらいながら職業訓練を受けられます。新たな技術・知識を身につけたい人や、経験のある分野でスキルアップしたい人、就職後すぐに役立つスキルを習得したい人などにおすすめです。
以下で、「公共職業訓練と求職者支援訓練の違い」についても解説します。
職業訓練とは
職業訓練とは、就職に役立つスキルを無料で受講できる公的サービスです。厚生労働省が運営しており、失業保険を受給している求職者と失業保険を受給できない求職者を対象にサービスの提供を行っています。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
民間の学校に通うと費用が掛かりますが、職業訓練は公的サービスなので費用を掛けずにスキルを習得できるというメリットも。また、ハローワークが主に職業訓練学校の手続きやサポートを行うので、就職活動も安心して行えるためおすすめです。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違い
公共職業訓練とは、失業保険を受給している人が受講する職業訓練を指します。
一方、求職者支援訓練は、失業保険を受給できない人、受給期間が終了した人などを対象とした訓練です。これら2種類の訓練を総称して、「ハロートレーニング」とも呼ばれています。どちらも、就職に活かせる知識や技術を身につけられる公的制度という点では変わりありません。
職業訓練の受講方法
- 1.ハローワークで求職申込み・職業診断
- 2.訓練の申し込み
- 3.面接・筆記試験等を実施
- 4.合格したら受講斡旋
職業訓練にどのようなコースがあるかは、地域によって異なります。居住地が管轄するハローワークで確認し、受講コースを決めましょう。職業訓練の開始日までの間に受給残日数が3分の2以下になる場合、失業保険の受給期間延長ができなくなる可能性があります。
職業訓練の申し込み方法については、「ハローワークの職業訓練を受けるには?具体的な内容や受講給付金制度を解説」のコラムで詳しく紹介しているのでご確認ください。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
職業訓練の給付金額や主な種類
「職業訓練を受けたいけどどうしたら受けられるの?」と気になっている方も多いでしょう。ここでは、職業訓練を受けるための条件や給付金額、訓練の主な種類などを紹介していきます。
職業訓練の受講を考えている人は、自分が条件に当てはまるかを確認しながら見ていきましょう。
職業訓練を受ける条件
- ・ハローワークに求職の申し込みをしていること
- ・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者ではないこと
- ・労働の意思と能力があること
- ・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
職業訓練は離職者の方だけではなく、在職中の方も受講できる場合があります。主に一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方などです。在職者で職業訓練を考えている方は対象者になるのか、一度ハローワークで確認してみましょう。
職業訓練受講給付金を受け取る条件
- ・本人収入が月8万円以下
- ・世帯全体の収入が30万円以下
- ・世帯全体の金融資産が300万円以下
- ・現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していない
- ・訓練実施日すべてに出席する(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合であっても8割以上出席する)
- ・世帯のなかで同時にこの給付金を受給して訓練を受けているものがいない
- ・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
- ・過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
この条件を満たしていると、訓練を受けている期間の1ヶ月ごとに職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当)が支給されます。また、ハローワークで必要性が認められた方のみですが、「寄宿手当」が支給される場合もあります。
職業訓練受講手当は月10万円、通所手当(訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額)は、月に最大42,500円まで、寄宿手当は、月に10,700円と定められています。
主な職業訓練の種類
- ・パソコン、Web関連
- ・情報処理、プログラミング、CAD/NCオペレーション
- ・介護サービス
- ・医療事務
- ・OA事務、簿記、経理
- ・デザイン関連・宅建不動産
- ・電気設備
- ・金属加工、溶接・建築、造園
- ・自動車工学
公共職業訓練は、国、都道府県、民間委託機関が実施し、都道府県立の産業技術専門学院や民間の専門学校や短期大学のような施設で行われます。訓練期間は、コースによりますが、概ね3ヶ月〜2年。
求職者支援訓練は、主に民間の教育訓練機関が実施し、訓練期間は、概ね2ヶ月〜6ヶ月が多いようです。
また、託児サービスを利用できる職業訓練もあるため、お子さんがいる方でも安心して訓練を受講できるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリット5つ
失業保険をもらいながら職業訓練を受けると、「無料でスキルの習得ができる」「失業保険を延長給付できる」などのメリットがあります。以下に、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットについてまとめました。
1.無料でスキルの習得ができる
職業訓練は厚生労働省が運営しているため、無料でスキルの習得ができます。訓練を受けながら職業訓練受講給付金を受け取れるため、金銭の不安も減らせるでしょう。
民間の学校で同じスキルや資格を取ると費用や時間が掛かってしまう恐れがあるので、受講条件をクリアしている方にはおすすめです。
2.失業保険を延長給付できる
失業保険は、年齢や雇用保険に加入していた期間などに応じて、90日・120日・150日・240日のように、受給期間が定められています。しかし、職業訓練を受講している方は、失業保険の延長給付ができる場合があります。
就職活動の際は、身なりを整えたり面接会場への交通費がかかったりなど、何かと出費がかさむもの。失業保険の受給期間が延長できるのは、ハローワークの職業訓練を受けるメリットといえるでしょう。
3.失業認定日の手続きが免除される
失業保険をもらいながら職業訓練を受けている間は、通常毎月行う失業認定日の手続きが免除されます。これは、職業訓練を受けているということは、積極的に就職活動を行っているという証拠とみなされるためです。また、求職活動の実績を証明するための手続きも、同様に免除されます。
4.失業保険を受給できない場合受講手当がもらえる
失業保険を受給していない人が求職者支援訓練を受ける場合、職業訓練受講給付金として「月10万円+通所手当+寄宿手当」を支給してもらえます。病気や仕事以外の理由で訓練を欠席した場合の職業訓練受講給付金は、10万円ではなく日割りの金額で支給されます。
5.自己都合退職の場合給付制限が解除される
自己都合退職者は、待機期間を満了した翌日から失業保険を2〜3ヶ月間は受給できません。しかし、職業訓練を受講した場合は、訓練を開始する前日に給付制限が解除されます。職業訓練を受講した場合は、通常よりも早く失業保険を受給できるようです。
失業保険と職業訓練受講給付金を同時に受給はできない
職業訓練受講給付金は、失業保険の受給資格がない方が、新たなスキルを習得し、再就職を目指すための経済的な支援です。そのため、失業保険と職業訓練受講給付金を同時に受けることはできません。
失業保険をもらいながら職業訓練を受ける3つの注意点
失業保険をもらいながら職業訓練を受ける際は、注意が必要です。
職業訓練を受ける方は、以下で解説する内容を確認してから申し込みをしましょう。
1.応募しても職業訓練を受けられない場合がある
職業訓練はコースごとに定員があり、応募のあとに選考審査が行われるため、希望の職業訓練を必ず受けられるとは限りません。受講希望者が多いコースは倍率が高いので、受けられない可能性が高まります。失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときは、コースを複数検討しておくのがおすすめです。
各コースの応募倍率は、最寄りのハローワークのWebサイトや電話で確認することが可能。また、受講を希望する職業訓練校へ直接電話やメールで問い合わせる、あるいは説明会に参加して質問するという方法もあります。
2.学びたい分野の職業訓練がない可能性もある
職業訓練のコースは地域によって異なるため、最寄りのハローワークに学びたい分野がないという可能性もあります。また、「求職者支援訓練には希望のコースがあるが公的職業訓練にはない」という場合も。
求職者支援訓練は失業保険をもらえない人のための訓練なので、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときは、求職者支援訓練のコースを選択できません。「希望のコースがないけれど、なんでも良いから求職者支援訓練を受けておこう」という気持ちでは、学ぶ意欲が薄れてしまう可能性も。
職業訓練開始から終了まで意欲をもって受講するためには、応募する前に自分が学びたい分野があるかを確認することも大切です。
3.いつから受講開始するか自分で決められない
職業訓練は受講開始日があらかじめ設定されているため、自分の都合では決められません。また、年1回の応募・4月スタートのみといったコースもあるので、タイミングによっては半年以上経つまで応募できない可能性も。
訓練期間は3ヶ月〜1年程度のコースが多く、なかには2年間訓練を行う長期間のコースも。タイミングが合わず、職業訓練の開始時期を待っている間も、失業保険の受給残日数は減っていきます。失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときは、訓練開始時期を考慮したうえで選択する必要があるでしょう。
職業訓練は実務経験として扱わない
職業訓練で行う内容は、スキルを身につけるための「訓練」なので、就職先から実務経験として扱われません。たとえば、パソコン技術を学ぶコースを受講したからといって、その知識を活かせる企業へすぐに就職できるとは限らないのです。
職業訓練によって得た技術や資格は、就活の際のアピールポイントとして有効。面接の際は、職業訓練の経験をどのようにアピールするかを考えることが大切です。
失業保険の残日数が足りないときは訓練を受講できる?
失業保険の残日数が足りなくても、ハローワークが実施する職業訓練プログラムによっては、受講を認める場合があります。ただし、これらのプログラムは、訓練期間中の失業保険の支給が延長されないケースや、定期的にハローワークで失業の認定を受ける必要があるなど、通常の職業訓練とは異なる点がいくつかあるので確認が必要です。
失業保険の残日数が足りない方は、一度最寄りのハローワークへ相談してみると良いでしょう。
失業保険の受給日と待機期間の数え方
離職後はじめて失業保険をもらうときは、ハローワークで求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から7日間の待機期間を経て、振り込まれます。
手続きを行ってその場ですぐに失業手当がもらえるわけではありません。2回目以降は1ヶ月に1度、ハローワークで失業認定日に手続きを行えば、通常5営業日で振り込まれます。ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)をはさむ場合は、振り込まれるまでに時間が掛かる可能性があるので確認しておきましょう。
ハローワークの判断によって給付制限が掛かった場合は、1〜3ヶ月程度の待機期間を要する場合もあるので注意が必要です。
職業訓練のほかにエージェントを利用するのも手
失業保険をもらいながら職業訓練を受けることは、金銭面での不安を軽減しつつスキルアップができるので非常に有効です。しかし、本格的に就職活動をスタートできるのが、職業訓練終了後になってしまうというデメリットも。
職業訓練とあわせて就職・転職エージェントのサポートを受けながら、就職の準備を進めるのも一つの手です。
若年層に特化した就職・転職サービスのハタラクティブでは、求職者一人ひとりに専任のキャリアアドバイザーがつきます。就職活動の進め方や就職先の紹介、面接対策、職業訓練での経験をどのようにアピールするかなど、マンツーマンでアドバイス。
また、就職先へ直接聞きにくいことや就活中のスケジュール管理も、求職者に代わって行います。「未経験の分野に挑戦したい」「自分に向いている仕事が分からない」とお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください。