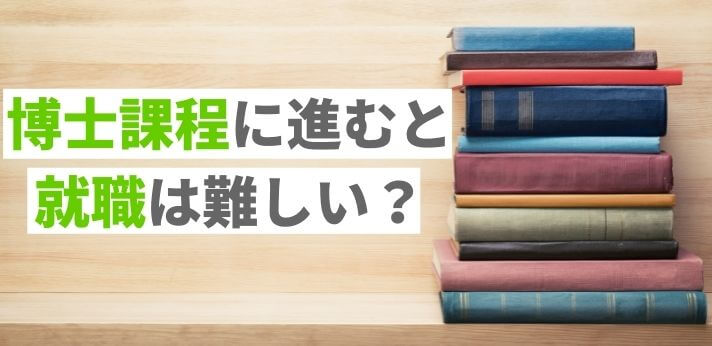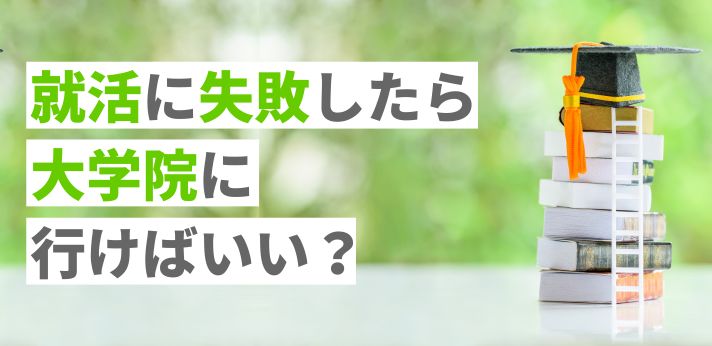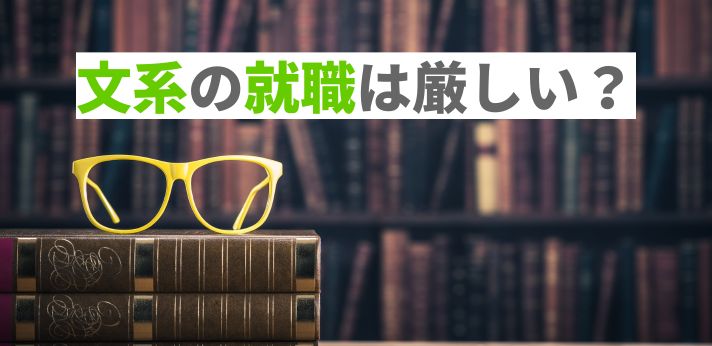大学院卒は就職で不利になる?就活が難しい原因と対策ポイントを解説
更新日
公開日
院卒が就職に不利になる要因は、学部卒と比べて年齢が高いからである
大学院卒は就職で不利?と不安を抱える方もいるでしょう。院卒が就職で不利になる理由は、「学部卒よりも年齢が高い」「研究が忙しい」などが挙げられます。しかし、年齢や研究の忙しさがネックになると言われる一方で、研究活動で培った専門知識や分析力、プレゼン力など、就活でアピールできる点は十分あります。
このコラムでは、院卒者の就職事情や就活で押さえておきたいポイントを解説します。院卒でエージェントを活用するメリットも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
大学院卒は就職できない?不利と言われる3つの理由
「院卒は就職で不利になる?」「大学院卒だと就職は難しいのでは?」と思っている方もいるかもしれませんが、一概に大学院卒の方が就職で不利になりやすいとはいえません。専門知識やスキル、研究を行うにあたって培った論理的な思考力など、院卒者が就活において評価されるポイントは複数存在しているためです。
しかし、「学部卒と比べて年齢が高い」「研究や卒論が忙しく就活に充てる時間が限られる」などの理由から、就職のハードルが高くなる可能性があるのは事実でしょう。以下では、院卒者が就職で不利になりやすい理由として考えられる3つについて詳しく解説していきます。
「院卒が就職で不利になりやすい」と言われるのはなぜか、また実態について教えてください
院卒が就職で不利になりやすい理由として一般的に言われるのは、「学歴が高い一方で、即戦力としての経験不足を懸念される」ことです。特に実務経験を重視する企業では、学術的な研究経験が直接的な業務に役立つかを疑問視する場合があります。また、「院卒者は専門性が高すぎて、柔軟な対応が難しいのでは?」という懸念も抱かれやすいようです。
ただし、実際にはこのような「院卒=不利」という偏見はすべての業界や企業に当てはまるわけではありません。特に研究職や技術職では、専門知識や分析能力が重視されるため、院卒の強みは十分に活かせるでしょう。さらに、大手企業などでは院卒者を歓迎する場合も多く、実際に採用率が高いケースもあります。
重要なのは、自分の強みと企業の求めるスキルを一致させること。柔軟性やチームワークの重要性をアピールし、実務経験が少ない場合は、インターンやプロジェクトでの実績を積むことが有効です。
1.学部卒と比べて年齢が高いから
院卒者は一般的に学部卒と比較して年齢が高いことから、大卒など若手の人材にこだわる企業では不利になる場合があるようです。大学院を修了すると、学部卒と比べて修士課程では2歳以上、博士課程で5歳以上年齢が高くなります。
とはいえ、20代であればポテンシャル採用を期待できる年齢です。年齢以外にもアピールできる知識や技術はあるはずなので、自分の強みを武器に選考に臨みましょう。
2.専攻分野を活かせる求人が少ない可能性があるから
大学院で専攻する研究分野は非常に狭く専門的です。そのため、専攻分野を活かせる求人が少ないケースも考えられます。それに加えて、企業の募集タイミングと院生の求職タイミングが合致しない場合もあるようです。
大学院で培った専門性を評価してくれる企業は、専門的な分野だけとは限りません。就職先を探す際は、視野を広く持って多様な分野から探しましょう。
3.研究や卒論が忙しく就活に充てる時間が限られるから
大学院生は就職活動に充てられる時間が限られているため、就職のハードルが高くなりやすい可能性があります。大学院では研究に加え、修士論文の執筆が必要です。修士論文は執筆量が多く、一般的に一定の基準以上の新しい研究成果が求められることから、実験を行ったり文献を読みこんだりするための時間をより多く取る必要があります。
十分な準備ができないまま就活に挑むことにならないためにも、事前のスケジュール調整や計画的な行動が重要となるでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
大学院卒業後の就職事情
文部科学省が実施した「令和6年度学校基本調査 確定値について(p.6~8、第3~5表)」によると、学部卒業者における就職者の割合が76.5%であるのに対し、修士課程修了者の就職者の割合は78.5%と、学部卒業者の割合を2%上回っていることが分かりました。博士課程修了者になると、就職者の割合は70.0%となっており、学部卒業者・修士課程修了者の割合を下回る結果となっています。
院卒の方の就職者の割合は、大卒者と比べてやや低くなるものの、それほど大きな違いはありません。「大学院卒だから就職は難しいかも…」と考えすぎず、前向きに就活に取り組む姿勢が大事です。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
院卒で就職は不利じゃない!3つのメリット
院卒での就職には、いくつかのメリットが挙げられます。以下で解説しているので、参考にしてみてください。
院卒で就職するメリットは「高い専門性とスキル」です
大学院から就職活動を行う最大のメリットは「専門性の高さ」と「研究で培った実践的なスキル」にあります。研究活動を通じて得た知識や思考力は、企業が注目するポイントです。特に理系の研究職や開発職、技術職などの専門職では、大学院卒が評価される事も少なくありません。
大学院生は研究発表やディスカッションの経験も比較的豊富なので、面接でも自信を持って話せる方が多いのではないでしょうか。また、研究室によっては企業とのつながりが強く、教授の推薦などで就職活動をサポートしてもらえるケースもあります。大学院で学んだからこそ得られた自分の強みを明確にし、それを武器として就職活動に臨む姿勢が大切です。
加えて、「課題解決力や粘り強さ」「情報収集と分析のスキル」など、研究生活を通して養われる能力は、就職活動でも社会人になっても大きな強みになります。こうして得た専門性と高いスキルを企業に評価してもらえるよう、普段から言語化できるように準備しておきましょう。
院卒で就職するメリット
- 専門知識が強みになる
- 研究者として採用されるチャンスがある
- 研究室推薦を受けられる可能性がある
1.専門知識が強みになる
大学院では、大学に比べてより高度な専門知識やスキルを身に付けられます。研究職や開発職、専門職などを希望する場合、大学院で培った専門知識やスキルは、面接のアピールにも就職後の業務にも活かせるでしょう。
また、大学院では研究を進める過程で分析力が会得できます。そのうえ、自分の研究を発表する機会が多いことから、プレゼン能力もおのずと身に付いていくでしょう。これらのスキルは、ビジネススキルとしても非常に有効なため、企業から評価されるポイントとなります。
2.研究者として採用されるチャンスがある
大学院に進学することで、研究者として採用されるチャンスが広がる点はメリットといえるでしょう。大学院では、自分が興味を持つ研究テーマについて深く学び、新たな発見のために研究へ取り組みます。
その研究を学会発表で説明する経験を通して、分かりやすく説明を行う能力を身に付けたり、ほかの研究者と議論することで自分の研究内容についてより理解を深められたりするでしょう。
大学院での研究活動や学会発表で得られる専門知識・スキルは、研究職として採用されるための重要な武器となります。
また、研究者の求人は院卒を応募条件とする場合も多いようです。企業で研究職に就きたいと考えているのであれば、大学院に進むのが望ましいといえるでしょう。
3.研究室推薦を受けられる可能性がある
大学院では、研究室に求人が来たり、選考の際に教授の推薦を受けられたりする場合があります。つてを頼って就活できる可能性がある点は、院卒で就職するメリットの一つといえるでしょう。
しかし、研究室ごとに特定の企業への推薦枠を持ち、応募するパターンが一般的な流れであるため、推薦をもらえる数は限られており、必ずしも推薦を受けられるわけではない点に注意が必要です。
研究室推薦を受けるなら早めの行動が重要
研究室推薦を受けて就職活動を有利に進めたい場合は、早めに教授やキャリア支援担当と相談しておきましょう。推薦枠には限りがあり、推薦の有無や推薦先企業は、教授のつながりや裁量に大きく左右されます。推薦枠を得られれば、専門性を活かせる職場に早期内定が狙えます。ただし、推薦で得た内定は辞退が難しいため、利用には覚悟と計画性が必要です。
院卒で就職する3つのデメリット
院卒で就職する場合、社会人経験がない点を懸念されたり、専攻を活かせる求人が見つかりにくかったりするなどの、デメリットを感じる可能性があります。
1.年齢や社会人経験がない点を懸念される可能性がある
院卒で就職する際のデメリットとして、年齢や社会人経験がない点を懸念される可能性がある点が挙げられます。同年代の学部卒者が社会人として経験を積んでいる一方で、院卒者は一般的に社会人経験がない新卒扱いのため、年齢に対してキャリアスタートが遅れていると見られる場合もあるようです。
そのため、若い人材を求めている企業や実務経験を重視している企業では、評価されにくい可能性があるでしょう。
2.専攻を活かせる求人が見つかりにくい場合がある
大学院では、専門性が高い分野の研究活動を行いますが、専門知識を活かせる求人は限られていています。そのため、専攻に合った企業への就職は非常に狭き門となる可能性があるでしょう。
専攻を活かせる求人が少ない可能性があることに加え、企業の募集タイミングと院生の求職タイミングが合致しない場合もあり、専攻を活かせる求人が見つかりにくい恐れがあるでしょう。そのため、専攻とは関係のない職に就かざるを得ない人もいるようです。
専攻にとらわれすぎない
大学院で学んだ専門性を活かしたいという思いは自然ですが、それだけに固執すると選択肢を狭めてしまう場合もあります。企業が求めるのは「専攻で学ぶ知識知識」だけではなく、「知識を応用して価値を生み出す力」です。物理専攻の学生がエンジニアだけでなく、データ解析やコンサルティング職で活躍するように、専攻で学んだ知識はあくまでキャリアの「出発点」に過ぎません。専攻を活かすための幅に目を向けると、進路の可能性が大きく広がるかもしれません。
3.給与額が学部卒と変わらないこともある
研究職として大学院卒が求められる求人は、学部卒よりも高い給与が設定されていることが一般的といえます。しかし、専攻を活かした求人でない場合は、院卒と学部卒で同様の給与が設定されているパターンもあるようです。給与額に期待して大学院へ進んだ場合、待遇に不満を感じる可能性があるでしょう。
大学院へ進学するか迷ったときの判断基準
大学院へ進学するか迷ったときは、進学する意義を自分なりに見出せるかどうかが大切なポイントとなります。以下では、具体的な判断基準を解説しているので、詳しく見ていきましょう。
大学院を中退した場合には就職にどのような影響がありますか?
大学院を中退した場合も、しっかりと就職活動に向けて準備をすれば影響は少ないです
大学院を中退したからといって、必ずしも就職に不利になるとは限りません。大切なポイントは中退した理由と、その後の行動を自分の言葉でしっかりと説明できるかどうかです。
たとえば「自分にとって今、社会に出て実務経験を積む事が成長につながると判断した」など、前向きな決断である事が企業側に伝われば、マイナス評価にはなりにくいでしょう。実際に、大学院に進学したからこそ気づけた自分の適性や目標があるなら、それは自分の大切な“軸”となり、あなたの強みになり得ます。
大学院の中退という事実に対して、必要以上に引け目を感じる必要はありません。ご自身の選択を見つめ直し、前向きなストーリーとして語れるように準備することが次のステップです。就職活動の成功につながるよう、しっかりと前を向いて取り組んでいきましょう!
大学院でやりたい研究があるか
大学院へ進学するか迷ったときは、大学院でやりたい研究があるかを考えることが大切です。やりたい研究が明確であることは、研究室を選ぶうえでも役に立ちます。大学院は、自分が興味を持つテーマについて深く研究し、新たな発見や課題解決に挑戦する場です。そのため、研究テーマに対する強い興味や目的意識がないと、途中で進路に迷ったり、モチベーションを失ったりする可能性があるでしょう。
また、大学院へ進学するかどうかは、自分の興味と将来を踏まえて判断するのが重要といえます。「就活する際、どのような企業の求人を受けられそうか」や「研究職に必ず就けると限らなくても進学したいのか」など、自分の将来を十分考慮したうえで、後悔しない選択をしましょう。
就活を先延ばしにしようとしていないか
就活がうまくいかず、「就活を先延ばしにしたい」という理由だけで大学院へ進学するのは避けるのが無難です。大学院では大学よりもレベルの高い専門知識や研究能力が求められます。そのため、新卒枠をもう一度狙うことだけを目的としている場合、研究内容に興味が持てず、途中で挫折する恐れがあるでしょう。
また、大学院への進学には多額の学費が掛かります。そのうえ、修士課程修了までに最短でも2年必要となり、その分年齢を重ねることになるため、明確なビジョンがなければ進学を後悔する可能性があるでしょう。
「とりあえず進学」の危険性とは?
「特に就きたい仕事がない」「就職がうまくいかない」といった理由で、「とりあえず大学院に進学する」というのは避けるのが望ましいでしょう。院卒者として就活を行えば学部卒者に比べて最低でも2年の差が生まれます。若い人材を求めている企業も多いため、この2年を埋められるほどのスキルやアピールポイントがないと、就職のハードルが高くなる恐れがあるでしょう。
また、企業は院卒者に対して「学部生では持っていない専門性」「研究などを通して身につけた高い知識」などを求めています。そのため、「就職できなかったから」「周りが進学するから」といった理由で進学し、研究に高い意欲を持てなかった場合、企業が求めるスキルや人材に及ばず就職が難しくなる可能性もあるでしょう。
院卒見込みと学部卒見込みの就職活動の違い
以下では、院卒見込みと学部卒見込みの就職活動の違いについて詳しく解説していきます。就職活動の進め方が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
学部生の場合
学部生の就活は、大学3年生の4~6月頃から始まるのが一般的です。このころから夏のインターンシップのエントリー・選考が始まるため、インターンシップに参加希望の学生は、早めに企業研究や自己分析を行っておく必要があります。
インターンシップはエントリーだけで参加可能のものもありますが、エントリーシートや面接で選考通過しないと参加不可能なものもあるため、事前に志望動機や自己PRを用意しておきましょう。
修士課程の場合
修士課程の就活は、修士課程1年(M1)の5~6月頃からスタートします。5~6月頃にインターンシップのエントリー・選考が始まるため、学部生の場合と同様、早めに企業研究や自己分析を行い、インターンシップの選考突破へ向けて志望動機や自己PRを考えておきましょう。
外資系企業をはじめとする一部企業では、修士課程1年(M1)の10月頃から説明会・エントリーが開始します。一部企業を除いた大多数の企業では、修士課程1年(M1)の3月から説明会・エントリーが始まるのが一般的です。修士課程2年(M2)の6月には面接などの選考が始まり、10月には内定式が行われます。
博士課程の場合
博士課程の就活では、基本的に学部生や修士課程のような「就活ルール」が適応されません。そのため、「3月からエントリー、6月から選考開始」といった定型的なスケジュールよりも早く、エントリーや選考が行われる場合があります。
一般的に博士課程の就活は、博士課程2年(D2)の夏から本格的にスタート。しかし、企業によっては博士課程2年(D2)の6月頃からエントリーが開始されたり、10月には選考が始まったりするパターンもあります。そのため、より早い時期から就活の準備をしておくのがベターといえるでしょう。
院卒の就活のポイント
大学院生が就活を成功させるためのポイントとして、推薦制度を活用することや早い段階から就活を始めることが挙げられます。それぞれ下記で詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
院卒の就活成功のカギは、専門知識を実務にどう活かすかを伝えること
院卒の就活を成功させるためには、まず自分の研究内容や学業で培ったスキルを具体的にアピールできることが重要です。院卒の特徴として、深い専門知識や高度な問題解決能力が挙げられます。選考では、これらをどのように企業の求めるスキルに結びつけるかがポイントです。
私の実体験として、過去に院卒の方が面接で成功した例では、研究テーマを単なる学問としてではなく、実際の業界課題にどう応用できるかを示すことが効果的でした。たとえば、「新しい材料の開発に取り組んだ研究を通じて、製造業の品質改善に貢献できる」といった具合です。
また、院卒の方は自分の専門分野に対する自信だけでなく、柔軟性やチームワークの重要性を伝えるのも大切。特に、就活中は「新しい環境でどう成長できるか」という姿勢をアピールすることが、企業にとって非常に魅力的に映ります。最終的には、業界研究や企業のニーズをしっかり理解し、自分の強みと企業の課題がどれだけ合致するかをしっかりと伝えることが成功へのカギとなるでしょう。
推薦制度を活用する
理系の院生の場合は、推薦制度を積極的に活用するのがおすすめです。推薦制度を活用すると、内定率が高くなる可能性や、一部の選考過程が省略されることがあります。ただし、専攻や研究室によっては推薦枠を設けていない場合もあるため、推薦制度があるか事前に確認しておくことが重要です。
早い段階から就活を始める
就活を成功させるためには、早い段階から情報収集と自己分析を始め、自分の知識が活かせる企業を見つけることが大切です。研究や執筆作業で忙しく、就活の準備に充てる時間が限られてしまう大学院生は、就活の準備が間に合わなくなってしまいかねません。そのため、時間がなくて就職先を妥協することがないよう、早め段階から時間を確保して就活に取り組んでおきましょう。
大学院生も新卒扱いされる?
新卒とは、学校を卒業見込みの就活生を指す言葉です。年齢制限がないため、大学院生も新卒として扱われます。
しかし、企業によっては募集要項に「××年4月1日生まれまで」「△歳未満の方」といった年齢制限を記載しているパターンもあるようなので、応募前に確認しておきましょう。
院卒の就職先の例
文系大学院卒の場合
以下では、文系大学院卒の就職率が高い業種を「人文学部」「社会学部」に分けて紹介していきます。
人文学部
- ・教育、学習支援業(23.0%)
- ・情報通信業(16.6%)
- ・公務(13.8%)
人文学部出身の場合は、その専攻で培った豊かな教養や論理的な思考力を活かし、多岐にわたる分野で活躍しています。教育分野では、研究職や教員としての道に進む人が多く、情報通信業や公務では、複雑な課題を分析し、解決に導く能力が評価されるでしょう。
社会学部
- ・情報通信業(14.9%)
- ・学術研究、専門・技術サービス業(14.1%)
- ・製造業(12.1%)
社会学部を卒業した場合、社会の動向や人間の行動に関する洞察力を活かして専門性の高い職種で評価されています。市場や顧客のニーズを読み解く力が求められ、専門的な知識と調査能力が役立つでしょう。また、社会のニーズを製品開発に反映させる企画職などで活躍する道があります。
理系大学院卒の場合
以下では、理系学部出身者の就職率が高い業種を「理学部」「工学部」「農学部」に分けて紹介していきます。
理学部
- ・製造業(31.2%)
- ・情報通信業(26.2%)
- ・学術研究、専門・技術サービス業(9.8%)
理学部出身の場合は、物理学や数学などの専門知識と、論理的な思考力やデータ分析能力を活かして幅広い分野で活躍しています。データサイエンティストやシステムエンジニアなどで、専門性を生かしたキャリアを築けます。
工学部
- ・製造業(51.0%)
- ・情報通信業(13.6%)
- ・建設業(11.4%)
工学部を卒業した場合、設計や開発といった実践的なスキルを強みとして、多くの企業から高く評価されています。自動車や機械、電子機器などの研究開発や設計に携わったり、システム構築やITインフラの設計、構造物の設計や施工管理といった専門職に就く人が目立ちます。
農学部
- ・製造業(29.3%)
- ・農業、林業、漁業(14.6%)
- ・公務(12.3%)
理系大学院卒の場合、専門知識を学ぶうえで培った、論理性や分析力などのスキルを活かして働ける業種が人気のようです。
農学部を卒業した場合、生命科学や環境科学に関する深い知識を生かし、食品や農業分野をはじめ、幅広い業種で活躍しています。食品や医薬品の研究開発や品質管理、農林水産関連の行政分野などで専門性を発揮できるでしょう。
院卒が就職エージェントを利用するメリット
院卒が就職活動で就職エージェントを利用すると「自分の強みの活かし方を教えてもらえる」「院卒に対して意欲的に採用する企業と出会いやすい」などのメリットがあります。以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。
自分の強みをどう活かすべきかアドバイスがもらえる
就職エージェントの魅力は、最初のカウンセリングで自分の強みをどう活かすべきか、客観的にアドバイスをもらえることです。研究に関連しない仕事に応募する場合でも、大学院の研究活動で培った強みを就活でアピールできれば、企業から魅力的に感じてもらえるチャンスがあります。効果的なアピールの仕方をプロの目線で教えてくれる点は、大きなメリットといえるでしょう。
院卒を意欲的に採用する企業と出会いやすい
就職エージェントを利用することで、院卒を意欲的に採用する企業と出会いやすい点もメリットの一つです。就職エージェントでは、事前に応募者の情報を企業に伝えたうえで選考をセッティングするため、ミスマッチが起きにくく、スムーズに就職活動を進められます。
企業情報を熟知した就活のプロが選考を申し込むため、自分で求人を探すよりも選考通過率が高まる可能性があるでしょう。
論文執筆で忙しいなか就活をサポートしてもらえる
就活を全面的にサポートしてもらえるというのも、就職エージェントの魅力です。大学院で執筆が必要となる修士論文や博士論文は、学部の卒業論文に比べて執筆量が多く、より多くの実験をしたり文献を読みこんだりする必要があります。そのため、院卒からの就活は、ハードなスケジュールになりやすいでしょう。
就職エージェントによって支援サービスの内容は異なりますが、応募先企業とのやり取りの代行や面接のスケジューリング、選考対策をしてもらえる場合があります。忙しいなかでも就活をよりスムーズに進められるでしょう。
院卒での就職活動にお悩みの方は、就職エージェントのハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブでは、経験が少ない若年層の方に向けて、大手企業の求人や人柄・ポテンシャルを重視する企業の求人をご紹介しています。「院卒は就職に不利なのでは…」と不安に感じている方も、専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行い、適性や強みに合ったアドバイスを行うので安心してご利用可能です。
また、適性に合った求人選びや選考対策など就活を全面的にサポートいたします。サービスのご登録、ご利用はすべて無料です。ハタラクティブに相談して、スムーズな就活を叶えましょう。
院卒の就職活動に関するQ&A
ここでは、院卒の就職活動に関してよくある質問と回答をご紹介しています。
一概に院卒が就職活動で不利になるとはいえません。専門知識や分析力、研究発表の経験から得られるプレゼン能力など、院卒者が就活でアピールできるポイントは複数存在しているためです。
院卒の就職活動では、研究で培った専門知識や論理的思考力、プレゼン力などをアピールするのがおすすめです。
進学するか迷ったときは、「大学院でやりたい研究があるか」「就活を先延ばしにしようとしていないか」を確認してみましょう。やりたい研究が明確でないと、研究テーマに迷ったり、モチベーションを失ったりする可能性があります。また、学費がかかるほか、学部卒を選んだ場合に比べて年齢を重ねることになるため、「就活を先延ばしにしたい」という理由だけで進学するのは避けるのが無難でしょう。
就活中の大学院生ですがうまくいかずに困っています…
就活がうまくいかない大学院生の方は、就職支援サービスの利用を検討してみましょう。大学院の修士論文や博士論文を執筆するうえでは、文献を読み込んだり実験したりすることに多くの時間が必要となり、就活との両立は一定の大変さがあります。そのため、就活のプロにサポートしてもらいながら短期間で効率よく就活を進めるのがおすすめです。
就職・転職エージェントのハタラクティブでは若年層向けに就職支援をしていますので、ぜひ一度ご相談ください。