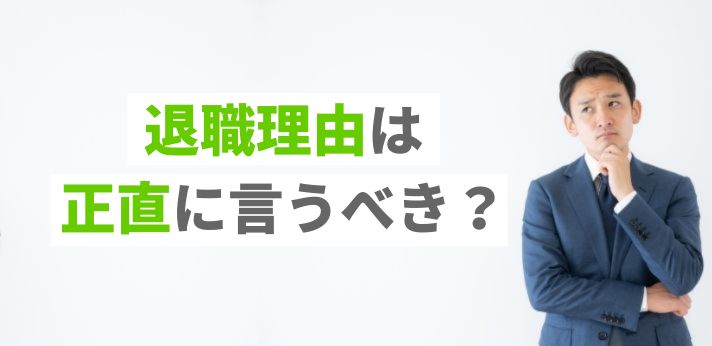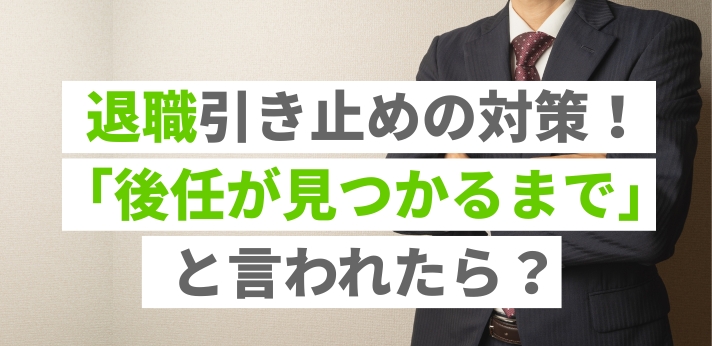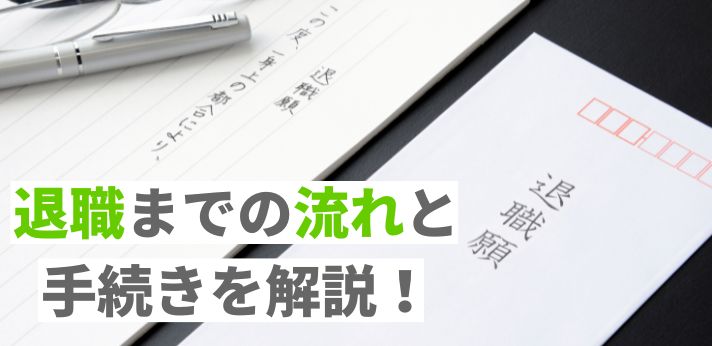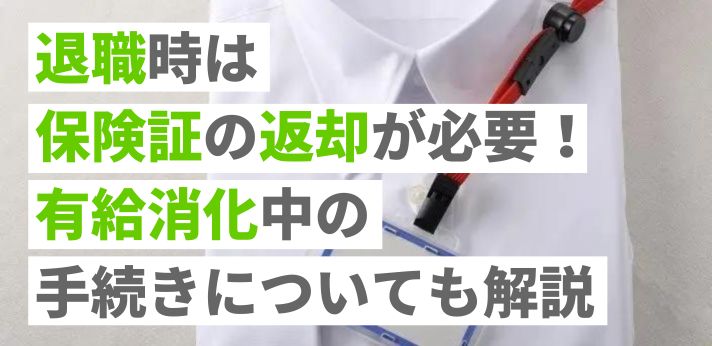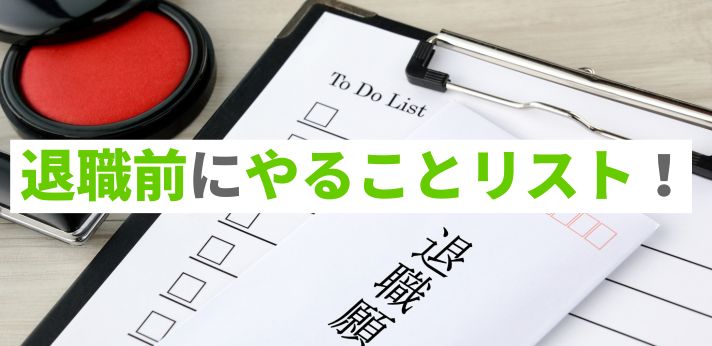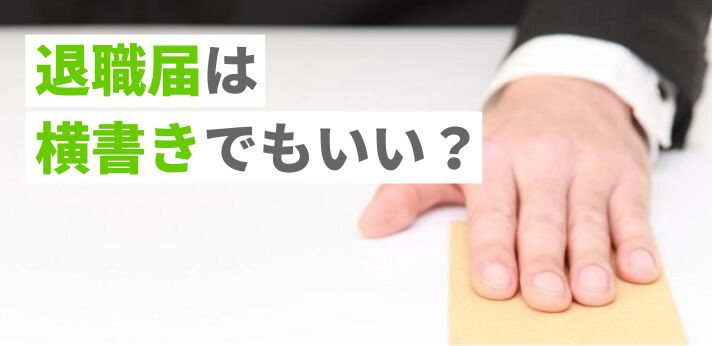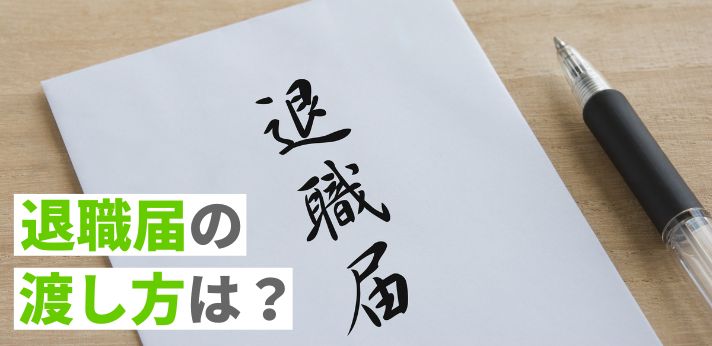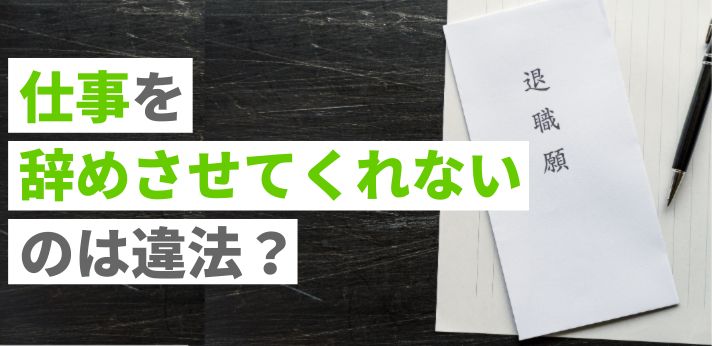退職はいつまでに伝える?退職届を出す時期や必要な手続きを詳しく解説
退職をいつまでに申し出るべきか悩む人もいるでしょう。退職を申し出る時期は、会社の就業規則にもよるものの、一般的には1ヶ月前と言われています。退職を伝える際はトラブルが起きないよう、書類作成や提出時の注意点をしっかりと押さえ、退職までの期間に余裕を持たせることが重要です。
このコラムでは、退職までの流れや伝える方法をご紹介します。退職願や退職届の書き方も解説しているので、参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断

就職でお困りではありませんか?
当てはまるお悩みを1つ選んでください
退職はいつまでに会社へ伝えるべき?
退職をいつまでに申し出るべきかは就業規則に記載があり、職場によって異なります。一般的には、退職日の1ヶ月前までと定めている職場が多いようです。なお、正社員など雇用期間を定めない労働者の場合、いつでも退職の申し入れができます。
また、法律に基づいていえば、民法627条第1項により「雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定されているので、退職の2週間前までに申し出れば認められることになるようです。
しかし、2週間前では引継ぎや退職手続きなどが慌ただしく、職場に迷惑をかけるので、雇用形態にかかわらず1ヶ月前には申し出ると良いでしょう。
参照元
e-GOV法令検索
民法
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
【雇用形態別】退職の旨を伝えるタイミング
退職を雇用主に申し出するタイミングは、雇用形態によって異なります。知識がない状態で退職を申し出て「退職できなかった」とならないよう、事前に確認しておきましょう。
正社員
前述したとおり、雇用期間の定めのない正社員が退職を希望する場合、退職する2週間前に申し出れば退職できます。務めている企業が、退職する申し出の期間に関して就業規則で定めている場合はそれに従いましょう。
正社員は責任のある仕事や重要な仕事を任されている場合が多いため、引継ぎや人員確保に時間がかかる傾向にあります。就業規則にある期日より早めに退職の申し出をすることで、円満に退職ができるでしょう。
契約社員
契約社員は企業と一定期間を定めて労働契約を結んでいることがほとんどのため、基本的には契約期間内で退職はできません。
ただし、病気やケガなどのやむを得ない理由や、労働者と雇用側の両者が合意していれば退職が認められる場合があります。
派遣社員
派遣社員も、契約社員と同様に雇用契約期間中の退職は原則として不可です。やむを得ない理由で退職したい場合は、勤務先(派遣先)ではなく、派遣元企業の担当者に相談します。
パート・アルバイト
パートやアルバイトも基本的には雇用期間の定めがあるため、契約期間中の退職はできません。ただ、上司や雇用者に相談すれば、契約期間中でも退職できるケースが多いようです。
なお、契約期間が1年以上ある場合、1年を経過したあとは契約期間中であっても退職を申し出ることが可能になります。
業務委託
業務委託で働いている人が退職したい場合、契約書の内容にのっとって契約解除の申し出を行う必要があります。一般的には契約書に定められた期間内にクライアントや雇用主に申し出することが求められますが、業務委託契約者の契約解除申し出は、書面で行うことでトラブルを回避できるでしょう。
参照元
厚生労働省
知って役立つ労働法
退職を2か月前や3か月前に申し出るのは非常識?
退職を早く伝えたからといって、非常識と思われるとは限りません。一般的に退職を申し出るのは1ヶ月前ですが、会社によっては退職までの期間を長く設定していることもあるようです。
ただし、退職を申し出るのがあまりにも早すぎると、上司から引き留めに合う可能性も考えられます。退職までの期間について就業規則が定められていない場合、1か月前に伝えるのが無難でしょう。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職までの流れとスケジュールの目安
会社や自分自身の状況にもよりますが、一般的な退職までの流れは以下のとおりです。自分が退職したいと考えている日から、有給消化や引継ぎ期間などを考慮し、あらかじめ退職までのスケジュールを確認しておきましょう。
1.【約1ヶ月~3ヶ月前】直属の上司に退職を伝える
まずは、自分の直属の上司に退職したい旨を申し出ます。ここで注意すべきなのは、退職は必ず直属の上司に最初に言うことです。
同僚やほかの上司などに先に言うと、直属の上司に言う前に、誰かを通じて耳に届いてしまう可能性があります。直属の上司への信頼がないと受け取られ、心象が悪くなる恐れもあるため注意しましょう。
また、退職願を提出する必要があれば、申し出たあとに上司に手渡します。退職願は必ずしも必要ではなく、口頭で申し出れば良い場合もあるので確認しておきましょう。
2.【約1~2ヶ月前】会社の承認が得られ退職日が決定
退職願を上司が受け付けたら、次に社内の承認を得る期間に入ります。担当業務の内容や役職、部署の忙しさによって異なりますが、正社員の場合、承認が得られるまでの期間はおよそ1〜2週間程度のようです。
優秀な人材であったり、部署の人手が足りていなかったりする場合には、引き止めに合うこともあります。会社からの引き止めの内容は、昇進や昇給など待遇アップの打診や、上司との面談などさまざまです。部署の忙しさや引き止めなどにより、社内承認を得られるまでの期間が長くなることもあるので想定しておきましょう。
有給消化のことも考慮しよう
転職活動や引継ぎなどに時間がかかるため、有給休暇の残日数を職場の担当者に確認しておきましょう。自分が把握している残日数と正確な日数に差が生じている場合、新しい職場への入社日や、転職活動に影響が出てしまいます。
一般的に有給消化の期間は1〜2週間、長くても1カ月程度のようです。有給消化を優先して引継ぎが不十分なまま休みに入ると、休暇中や退職後に問い合わせを受ける可能性もあるので注意しましょう。
また、有給消化を取るために入社日を遅らせた場合、転職先からの印象が悪くなる恐れもあります。
3.【約1~2ヶ月前】退職届を提出する
退職日が決まったら、退職届を作成して提出しましょう。提出先は、退職願と同様に直属の上司です。退職届は、職場の規定がある場合それにしたがって書く必要があるため、会社の就業規則を確認しておきましょう。規定がなければ、一般的なフォーマットを使用して大丈夫です。
4.【約1ヶ月前~3日前】業務の引継ぎを行う
引継ぎには思ったより時間がかかる場合が多いので、余裕を持って行いましょう。
最終出勤日まではできるだけ区切りの良いところまで業務を担当し、これまでの業務内容と今後の予定を、新しく入社してきた人や後任者に伝えます。引継ぎ期間に長い時間を割くのは難しいので、後任者に業務を教えながら引継いだり、引継ぎ資料を作成したりしておくことが必要です。
引継ぎ漏れは後々トラブルにつながる可能性もあるため、丁寧に行いましょう。引継ぎに関して、どのように行うかを事前に考えたり、上司に相談したりすることで、スムーズな引継ぎが行えます。
5.【退職当日】挨拶や私物の整理を行う
退職当日は、お世話になった方々への挨拶や私物の整理をします。必要であれば、社外の方へもメールや電話で挨拶をしましょう。
会社の規模や状況にもよりますが、挨拶回りに時間がかかる可能性もあるため、退職当日までにはできるだけほかの仕事を片付けておくのがおすすめです。
有給消化期間が最終出社日後になる場合は、最終出社日が退職当日ではありません。そのため、会社でお世話になった方への挨拶は最終出社日にしておきましょう。
また、事前に職場へ返却するものを確認しておき、退職当日までに用意できるものはすべて返却しましょう。
退職までの期間には余裕を持たせよう
退職までの期間には余裕を持たせましょう。上司からの引き留めや引継ぎが間に合わないなどの理由により、退職までのスケジュールが思うように進まないこともあります。
引継ぎ不足でほかの社員たちへ迷惑をかけてしまったり、円満に退社できなかったりする恐れも。トラブルを防ぐためにも、退職までの期間はできるだけ余裕を持たせると良いでしょう。
退職を申し出る際に揉めないための注意点
退職を申し出る際に、伝える方法や言い方によってはトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。円満に退職するために、退職の意思を伝える場合の注意点を確認しておきましょう。
一番はじめに直属の上司へ直接伝える
前述したように、退職したい旨は、必ず一番はじめに直属の上司に直接伝えます。重要な報告をする際は、対面で自分の口から伝えるのが社会人としてのマナーです。電話やメールなどの使用は控え、リモートワークがメインの場合は、自分の顔が映る状態に設定して退職を伝えましょう。
また、「相談」「お話したいこと」といった曖昧な表現ではなく、「△月△日で退職をしたいと考えています」のように、退職の意思をはっきりと伝えることも重要です。曖昧に伝えてしまうと、上司からの引き留めに合い、退職交渉に時間がかかってしまう可能性があります。
悪口や不満などは言わない
退職理由を聞かれた際にやってはいけないことは、会社に対する不平不満を話し過ぎたり、悪態をついたりすることです。
失礼な態度によって上司を怒らせてしまうことで、退職について穏便に話し合えなくなる恐れも。退職を申し出る際は、これまでお世話になったという気持ちを忘れず、誠意をもって上司に伝えることが大切です。
繁忙期などは避ける
退職の時期を決める際は、繁忙期はできる限り避けるなどの配慮が必要です。
退職する場合、自分の仕事を後任者に引き継ぐ必要がありますが、繁忙期などの忙しい時期は引継ぎができない可能性があります。人手不足の時期に退職するのは大きな迷惑になり、同僚や上司に悪い印象を持たれる恐れも。揉めることのないよう、会社が忙しいときの退職は避けましょう。
また、入社日が決まっているからといって、「一刻も早く退職したい」という自分勝手な振る舞いをするのもトラブルのもとです。円満な退職を望むのであれば、繁忙期なども考慮しながら退職日を考える必要があります。
退職を控えた方が良い場合
「転職したい」といった理由で退職を考えることもあるでしょう。しかし、場合によっては退職をしない方が良いこともあります。以下で詳しく解説します。
ボーナスの支給日が近い
ボーナスの支給日が近い場合は、退職時期を改めるのが賢明です。会社の規定にもよりますが、多くの場合、ボーナス時期に会社に在籍しているかどうかで付与の対象や金額が決まります。
これまで会社で頑張ってきた成果として、ボーナスを受け取ってから退職する方が良いでしょう。また、ボーナスを貰うことで想定年収が高くなり、転職先との給与交渉時に役立つというメリットもあります。
昇進の可能性がある
昇進の可能性がある場合は、退職を控えた方が良いでしょう。昇進することで給与が上がったり、仕事の幅が増えて新たなスキルを身につけられたりすると考えられます。
現状に不満がある場合や、新しいことに挑戦したいという理由で退職を考えている場合は、昇給を待つのも有効でしょう。スキルを身につけてから転職活動をすることで、転職先の幅も広がります。
また、昇進後に転職活動を行えば、年収が上がった状態で転職先の給与を考えることも可能です。
ローンを組む予定がある
退職することでローンを組む際に不利になってしまう可能性があります。そのため、直近でローンを組む予定がある場合は退職を控えましょう。
退職後すぐに転職しても、勤続年数の短かさがローン審査に影響してしまう場合があります。また、転職先の会社が現在よりも小規模の場合、借入金額や金利の条件などが厳しくなる可能性も。結婚やマイホームを検討している場合は、退職についてもう一度考えてみると良いでしょう。
スキルアップの見込みがある
現在の会社がスキルアップや成長する機会を与えてくれている場合、退職は控えたほうが無難です。新しいスキルを身につけることで成長でき、自分のキャリア形成にも良い影響を与えてくれるでしょう。
ただし、ほかにやりたいことがある場合や、別の会社でもスキルアップが見込める場合は、退職後に転職するのも一つの手です。
退職までに必要な手続きとは
退職が決まったあとは、社内と社外でそれぞれ必要な手続きがあります。不足があると手続きが遅れることもあるので、確認しながら着実に進めましょう。
退職の手続きで職場から受け取るもの
退職の際、会社から受け取る書類は以下のとおりです。転職活動や転職先へ入社後に提出するもの、公的な制度を利用するために必要なものなど複数あります。
・退職証明書
・年金手帳
・雇用保険被保険者証
・離職票
・源泉徴収票
退職日に受け取れるものもあれば、退職後郵送されて来るものもあります。不足があったらすぐに気がつけるように、事前に確認しておきましょう。
退職の手続きで会社へ返却するもの
退職の際、会社へ返却しなければならないものは以下のとおりです。
・健康保険証
・社員証など
・名刺
・業務で使用していたデータや書類・制服などの備品
返却し忘れて「また会社へ行かなければならない」「担当者から何度も連絡がきて気まずい」といったことがないよう、しっかりと確認しておきましょう。
保険証はいつまで使える?
勤めていた会社の健康保険証は、退職日まで使用できます。いつまでに返却するかは会社によって異なるので、あらかじめ担当者に確認しておきましょう。
退職後に必要な公的手続き
退職後、すぐに転職する予定がない人は公的手続きが必要です。以下のうちいずれかの手続きを行いましょう。
・国民健康保険に加入する
・退職前の健康保険を任意継続する
・家族の健康保険の扶養に入る
これまでは勤務先で社会保険料を払っていましたが、退職後に一定期間職のない状態になる場合、健康保険や税金、年金の切り替えなどの手続きが必要です。さらに、失業保険の申請にも職場から受け取った書類が必要になります。不備がないように準備し、ハローワークへ向かいましょう。
退職に関する書類の違い!いつまでに提出すれば良い?
退職書類は退職願と退職届、辞表の3種類あり、それぞれ性質と提出時期が異なります。各書類の概要を押さえておきましょう。
退職願・退職届・辞表の違い
退職に関する書類には、退職届以外にも退職願や辞表があります。それぞれの違いについて、以下で詳しくまとめました。
退職願
退職願は、「退職したい」という自分の思いを申し出るときに、直属の上司に提出する書類です。直属の上司から人事部に渡され、人事部の承認が下りると退職が認められます。場合によっては、人事部の承認が下りず会社から退職を却下されたり、希望する退職日が実際の退職日にならないことも。
また、退職願は退職が承認される前であれば、退職願を取り下げや内容の変更が可能な場合もあります。退職願の取り下げや変更を希望する場合は、直属の上司に相談し、会社の規定に従って手続きを行いましょう。
退職届
退職届は「退職します」という強固な意思を表明する書類です。基本的に会社は退職届を拒否できず、一度提出すると撤回ができません。
退職届を提出したあとに後悔する可能性もあるため、退職を「願い出る」意味合いのある退職願を提出する方が安心です。会社と退職について合意したうえで退職届を作成することで、円満退職ができるでしょう。
辞表
辞表は、役員などの役職に就いている人が役職を辞める際に提出する書類です。任用されて働いている公務員の場合も、提出するのは辞表となります。
退職書類を出す時期
それぞれの書類を提出する時期は、以下のとおりです。
退職願
退職願を提出する時期は、最初に直属の上司に話をするときです。退職願は必ずしも必要ではなく、上司に口頭で申し出るだけでも構いません。上司から作成を求められたら対応するというかたちで良いでしょう。
退職届
退職届の提出は、上司に退職を申し出て社内の承認を得たあとです。退職届は、退職の意思を表明する書類で撤回ができないため、退職が本格的に決まったときに提出します。
辞表
辞表は、民間企業の役員や公務員が提出するもので、退職届にあたります。よって、提出するのは退職届と同様に退職を申し出て、社内や団体内の承認を得たあとになるでしょう。
退職願・退職届の書き方
退職願や退職届の書き方は、縦書きと横書きで多少異なります。用紙のサイズや色、使う筆記用具、内容についてはおおよそ決まっているので、以下を参考にしてください。
用紙のサイズと色
退職願や退職届を作成する場合、用紙のサイズはA4便箋やB5便箋、セミB5便箋などを使用します。便箋は過度に装飾された派手なものは避け、白くてシンプルなものを選びます。罫線の有無は問いません。
使用する筆記用具は黒色のボールペンや万年筆が最適です。鉛筆や、インクが消せるボールペンを使用するのは避けましょう。
また、退職願や退職届の作成にPCを使用しても問題はありませんが、手書きで作成するのが一般的です。特別な事情がない場合は、便箋を用意して手書きで作成した方が良いでしょう。
内容
退職願と退職届ともに書く内容はほとんど同じです。本文の内容には退職の意思や退職理由、退職日以外については書きません。退職願や退職届に書く内容の順番は、以下のとおりです。
1.一行目に退職願または退職届と書く
2.二行目に私事または私儀と書く
3.三行目から退職理由と退職の旨を書く
4.提出日を書く
5.所属部署を書く
6.自分の氏名を書く
7.代表者の肩書と氏名を文末に書く
退職理由は自己都合の場合、「一身上の都合により」とするのが一般的です。退職願の場合は「△年△月△日をもちまして退職いたしたく、ここに申し上げます。」と書き、退職届の場合は「△年△月△日をもちまして退職いたします。」と書きます。
書き方のポイントとして、年月日は和暦か西暦のどちらかに統一して書く必要があります。また、所属部署を書く際に役職名を書く必要はありません。自分の氏名を書く際は、下に捺印を押すためのスペースを空けておきます。代表者の氏名には「様」か「殿」の敬称をつけましょう。
縦書きの注意点
- 退職願または退職届は、便箋の中央よりやや上に書く
- 私事または私儀は、便箋の下に書く
- 年月日は漢数字を使う
- 自分の氏名は所属部署名の次行、やや下に書く
- 代表者名は自分の氏名よりも高い位置から書く
横書きの注意点
- 退職願または退職届は、便箋の中央に書く
- 私事または私儀は、便箋の右端書く
- 年月日は算用数字を使う
- 自分の氏名は所属部署名の次行の下または右に書く
退職願や退職届は縦書きが一般的といわれています。特別な理由がなければ、上記のポイントを参考に縦書きで退職願や退職届を作成しましょう。
日付の書き方
先述のとおり、縦書きの場合は漢数字を使い、横書きの場合は算用数字を使うのが基本です。和暦と西暦を統一することも忘れないようにしましょう。
また、日付に間違いがないよう注意しましょう。自分が退職の意思を伝えた日と、退職希望日または会社と決めた退職日の証明になります。退職日に間違いがあると、自分と会社との間にトラブルが発生する恐れも。円満に退職するためにも、日付を書く際はよく確認しましょう。
封筒の書き方と入れ方
封筒の書き方と入れ方のポイント
- 退職願や退職届を三つ折りにして封筒に入れる
- 封筒の表側中央に退職願または退職届と書く
- 封筒の裏側左下に所属部署と自分の氏名を書く
- 手渡しする場合は封を閉じる必要はない
- テープ付きの封筒の場合は封を閉じて〆と書く
封筒は、重要な書類を提出するのにふさわしい、白色で無地の「白封筒」や「二重封筒」で、郵便番号欄がないものを選びます。さまざまな関係者の手に渡り、保管される重要書類のため、必ず封筒に入れて提出しましょう。
【まとめ】退職をいつまでに申し出るか悩んだら
一般的に、退職を申し出るタイミングは退職希望日の1ヶ月前とされています。多くの企業では就業規則にタイミングを定めているので、確認したうえでルールを守りましょう。
また、退職を希望していても、雇用期間の定めがある場合は期間内の退職が難しいこともあります。正社員以外の雇用形態で働いている場合は、こちらも併せて確認しておくのがおすすめです。
退職後の転職活動で悩んだら、エージェントの利用がおすすめです。
就職・転職エージェントは民間企業の運営する転職支援サービスで、会社ごとに扱う業界や支援対象が違うのが特徴です。自分に合うサービスを選ぶことで、希望する条件に近い求人に出会えるのがメリット。
また、就職・転職エージェントの多くは企業の紹介だけでなく、応募書類の添削や面接練習も行っています。会社とのやり取りもキャリアアドバイザーが担当してくれるので、退職手続きで忙しい期間でも転職活動が進めやすくなるでしょう。
就職・転職エージェントのハタラクティブは、若年層の既卒や第二新卒、フリーター、ニートの方の求職活動をサポートします。ハタラクティブでは、求職者一人ひとりに合う就職支援をするために、専任のキャリアアドバイザーが求人紹介や面接対策などを一貫して実施。マンツーマンで行われるカウンセリングを通してプロからアドバイスを受けられ、忙しい中でも効率的に就職活動を進めることが可能です。約1分間で簡単に自分の適性を調べられる適職診断を行えば、ミスマッチを起こしにくい職業を知れるでしょう。
「退職後の転職活動が不安」という方は、お気軽にハタラクティブにお問い合わせください。
退職はいつまでに申し出れば良い?退職に関するFAQ
退職はいつまでに申し出れば良いか迷う方に向け、退職に関する質問と回答をまとめました。
退職日までの期間は気まずくなりませんか?
退職することに後ろめたい、気まずいと思う人も多いでしょう。しかし、残りの出勤日に、しっかり引継ぎを行うことで気まずさは和らいでいくはずです。
突然辞めるわけではなく、就業規則どおりに退職の意思を伝えているので、ある程度割り切ることも重要です。
職場の就業規則では4ヶ月前に申し出るように定められています
一般的には1ヶ月ですが、それ以上長い期間を設定している職場もあるようです。退職をいつまでに言うかは会社の就業規則によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。あまりにも長い期間の場合は退職者に不利益が生じるので、必ずしも就業規則に乗っ取らなくても退職できます。
退職後の転職活動が不安です…
退職後は収入面を不安に思ってしまいますが、退職後の転職活動で再就職先を決めるのは十分に可能です。
退職後に新しく自分の理想の条件に合う会社に入社できるか不安な方は、転職エージェントのハタラクティブをご活用ください。転職活動が不安な方に向け、就活アドバイザーが会社選びから求人紹介、選考対策まであなたの転職活動をしっかりとサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?
マーケティングアシスタント
東京都
年収 315万円~360万円
正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!
ライター・取材担当
東京都
年収 315万円~360万円
未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?
営業
東京都
年収 328万円~374万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆
ルート営業
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…
年収 228万円~365万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「お悩み」についての記事一覧
- 「退職の悩み」についての記事一覧
- 「退職手続き・法律関連」についての記事一覧
- 退職はいつまでに伝える?退職届を出す時期や必要な手続きを詳しく解説