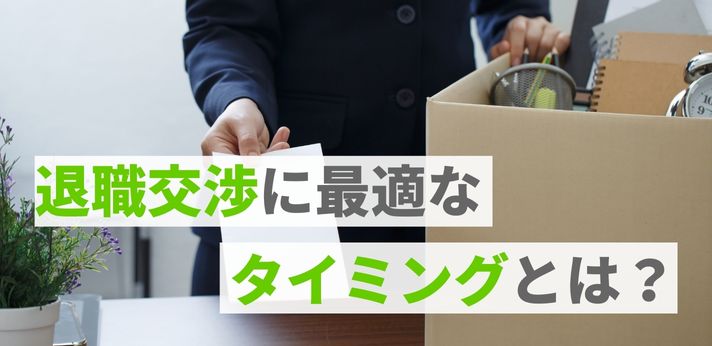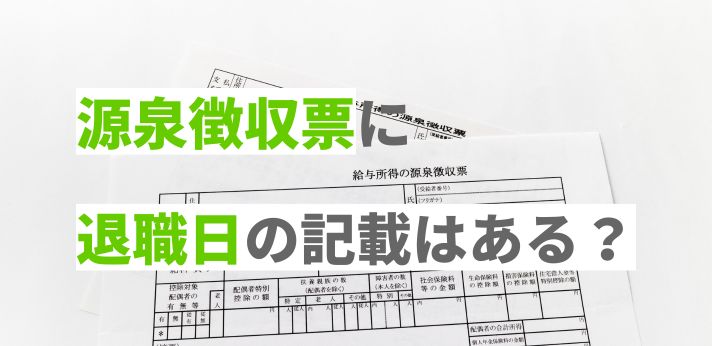退職金にも税金はかかる?計算方法は?手取り額のシミュレーションも紹介
「退職金にも税金はかかるの?」「手取り額はいくらになる?」と気になる方も多いでしょう。退職金には所得税、住民税、復興特別所得税が課税されます。受け取り方でかかる税金の額が変わる場合もあるため、退職金について知っておくことが大切です。このコラムでは、退職金にかかる税金や計算方法、手取り額のシミュレーションを紹介しています。将来の退職金の額を知りたい方や、退職を検討している方は参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断

就職でお困りではありませんか?
当てはまるお悩みを1つ選んでください
退職金に税金はかかる?かからない?
退職金にかかる税金は所得税、住民税、復興特別所得税(2013年1月1日から2037年12月31日まで)の3つです。ただし、退職金は退職後の生活資金としての意味合いが強いことから、税負担が大きくならないよう軽減措置が取られています。
所得税
所得税は個人の所得に対して発生する税金です。収入金額の全てに課税されるわけではなく、1年間の総所得から各種所得控除額を差し引いて計算した「課税所得」に対して適用されます。退職金に関しては、一時金であれば「退職所得控除」、年金形式での受け取りには「公的年金等控除」があります。
復興特別所得税
復興特別所得税は東日本大震災の復興に使用される税金で、2013年から2037年の24年間における各年の所得が対象です。復興特別所得税の税額は、所得税額×2.1%で算出できます。
住民税
住民税は、都道府県民税と市区町村民税を合わせた名称であり、その年の1月1日時点での住所地に納税します。前年の所得金額に応じた「所得割」と所得の額に関わらず定額で課税される「均等割」で成り立っています。
退職金の制度については「退職金は勤続年数によって変わる?計算方法や制度について詳しく解説」のコラムでもご確認いただけます。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職金の受け取り方によって税金の種類や額が変わる
退職金は、一括もしくは分割のいずれかで受け取れます。受け取り方によって税金の算出方法が変わるため、ライフプランと合わせて確認しておきましょう。
退職金を一時金で受け取った場合
退職金は全額一括で受け取ることが可能です。一時金で受け取ると「退職所得」となり、税金の計算時に退職所得控除が適用されます。退職所得控除とは勤続年数に応じた優遇措置で、課税対象になるのは退職所得控除を差し引いた残りの半分です。
年金形式で受け取る
退職金を分割して「年金形式」で受け取ると、公的年金に含まれるため、税法上は「雑所得」として扱われることになります。この場合は「公的年金等控除」の対象です。公的年金等控除は収入や年齢によって異なってきます。国税庁の「公的年金等の課税関係」によれば、65歳以上で年金収入が330万円未満ならば年間110万円、65歳未満で年金収入が130万円未満なら年間60万円が控除の対象に。将来の年金額を確認したうえで、控除内に収まるように受け取り方を工夫すると、税負担を少なくできるでしょう。
受け取り方法は自分に合ったものを選ぼう
退職金を一時金にすると、大きな額を手にできるため住宅ローンなどを完済できる可能性が高まります。ただし、気が大きくなって無駄遣いをする可能性も。分割で受け取ると管理がしやすく、無駄遣いも防ぎやすくなりますが、課税対象期間が長くなるため、一時金に比べて課税額が大きくなることもあるでしょう。退職後の生活についてよく考え、自分に合った受け取り方を選んでください。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
参照元
国税庁
公的年金等の課税関係
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職金に課税される税金の計算方法:一時金
退職金は「長年の勤務に対する報償的給与」と位置づけられるため、一時金として受け取る場合は通常に比べて優遇されるのが特徴です。ここで税金の計算方法について確認しておきましょう。
退職金に対する所得税の計算
課税されるのは、退職金総支給額(額面)ではありません。国税庁の「退職金を受け取ったとき(退職所得)」によれば、支給額から退職所得控除額を引いた残額の1/2(50%)が、「課税退職所得金額」として課税対象になります。計算式は以下のとおりです。
課税退職所得金額=(退職金の総支給額-退職所得控除額)✕50%
また、国税庁「退職金と税」によれば、「課税退職所得金額」を計算するために必要な退職所得控除額は、勤続20年までは年40万円、21年目以降は年70万円ずつです。なお、1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。
退職所得控除額
以下の表は国税庁「退職金と税」による退職所得控除額です。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
引用:国税庁「退職金と税」
表のとおり、勤続年数が20年を超えた場合は、20年目までの控除額「40万円×20=800万円」をベースに21年目以降は年70万円が追加されます。勤続30年で退職金を受け取った場合は、「800万円+70万円×10年=1,500万円」が退職所得控除額です。説明したように、課税対象となる退職金は「(退職金の総支給額-退職所得控除額)✕50%」です。そもそも退職金の額が退職所得控除額の範囲内に収まれば、課税対象となる退職金はないので非課税となります。
一方、支給額が退職所得控除額を超えた場合は、超えた額の50%が課税対象となり、下記の税率に応じた税金を支払います(対象となる額に応じた税率を掛け、控除額を差し引いた額が税額)。
役員の退職金の場合は税金の計算方法が変わることも
退職金に対する所得税の計算では、退職金額から退職所得控除額を引いた残額の50%に課税されますが、適用されない場合もあります。国税庁の「退職金と税」による、1/2を掛けることができないケースは以下のとおりです。
- ・勤続年数5年以下の役員等として勤務した場合の退職金
- ・勤続年数5年以下の役員等以外の人で、退職金額から退職所得控除額を引いた残額の300万円を超える部分
上記は従業員として働いた期間が5年を超えていても、役員の期間が5年以下であれば該当。また、勤続年数が5年以下で役員ではない人の場合、退職所得控除額を差し引いた残額のうち300万円までは1/2が適用され150万円となり、超える部分にはそのまま課税されます。
なお、退職金所得控除の計算における勤続年数の数え方については「勤続年数とは?正しい数え方や転職・失業保険・退職金・有休への影響を解説」のコラムがおすすめです。役員の退職金計算での勤続年数も解説しています。勤続年数は退職金の計算にも関わるため、気になる方はチェックしてみてください。
参照元
国税庁
退職金と税
2024年分の所得税の税額表
以下は、国税庁「退職金と税」による2024年分の所得税の税額表です。(求める税額=A×B-C)
| A課税退職所得金額 | B税率 | C控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁「退職金と税」
上記のとおり、退職所得金額に応じた所得税がかかる仕組みになっています。
参照元
国税庁
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
退職金と税
退職金に対する住民税の計算
「総務省」によれば、住民税は市町村民税6%と都道府県民税4%を合わせた計10%が一律で課税されます。計算式は以下のとおりです。
退職時に支払うべき住民税=課税退職所得金額✕10%
参照元
総務省
個人住民税
退職金に対する復興特別所得税額の計算
国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」によれば、退職金にかかる復興特別所得税の税率は、所得税額の2.1%です。計算式は以下のようになります。
退職時に支払うべき復興特別所得税額=所得税額✕2.1%
参照元
国税庁
個人の方に係る復興特別所得税のあらまし
退職金から税金を引いた手取り額のシミュレーション
先ほどの計算式を使って、実際に退職金の手取り額をシミュレーションしてみましょう。
勤続年数30年で退職金が3,000万円の場合
勤続年数が30年で退職金が3,000万円の場合の手取り額を計算すると、以下のとおりです。
- ・退職所得控除額=800万円+70万円✕10年=1,500万円
- ・課税退職所得金額=(3,000万円-退職所得控除額)✕50%=1,500万円✕50%=750万円
- ・所得税額=課税退職所得金額✕23%-控除額=172万5000円-63万6000円=108万9000円
- ・復興特別所得税額=所得税額✕2.1%=108万9000円✕2.1%=2万2869円
- ・住民税=課税退職所得金額✕10%=750万円✕10%= 75万円
- ・退職金手取り額=3,000万円-(108万9000円+2万2869円+75万円)=2,813万8131円
上記のケースでは、退職金を一時金として受け取ると約2,813万円の手取りになります。
勤続年数24年と3ヶ月で退職金が2,000万円の場合
以下は勤続年数が24年と3ヶ月あり、2,000万円の退職金を受け取る場合の計算式です。
- ・退職所得控除額=800万円+70万円✕5年(勤続年数は端数切り上げ)=1,150万円
- ・課税退職所得金額=(2,000万円-退職所得控除額)✕50%=850万円✕50%=425万円
- ・所得税額=課税退職所得金額✕20%-控除額=85万-42万7500円=42万2500円
- ・復興特別所得税額=所得税額✕2.1%=42万2500円✕2.1%=8,872円(1円以下端数切り捨て)
- ・住民税=課税退職所得金額✕10%=425万円✕10%=42万5000円
- ・退職金手取り額=2,000万円-(42万2500円+8872円+42万5000円)=1914万3628円
端数は切り上げとなるため、勤続年数25年として計算すると手取り額は約1914万円になります。
勤続年数20年で退職金が1,000万円の場合
勤続年数が20年で退職金が1,000万円の場合を手取り額を計算すると、以下のとおりです。
- ・退職所得控除額=40万円✕20年=800万円
- ・課税退職所得金額=(1,000万円-退職所得控除額)✕50%=200万円✕50%=100万円
- ・所得税額=課税退職所得金額✕5%-控除額=5万-0円=5万円
- ・復興特別所得税額=所得税額✕2.1%=5万円✕2.1%=1,050円
- ・住民税=課税退職所得金額✕10%=100万円✕10%=10万円
- ・退職金手取り額=1,000万円-(5万円+1050円+10万円)=984万8,950円
勤続年数が20年以下のため、退職所得控除額の計算式が変わっています。退職金が1,000万円の手取り額は約984万円でした。
退職金に税金がかからない金額は?
一時金で受け取る場合、退職金の額が退職所得控除額より少なければ所得税はかかりません。多い場合は税金がかからない金額を一時金で受け取り、一部を年金形式にする方法も。一時金と年金形式のどちらにも対応している企業であれば、組み合わせることで税金を抑えられる可能性があります。併用のメリット・デメリットについては「退職金のもらい方の種類とは?制度の違いや受け取れる金額の相場を知ろう」のコラムで解説しているので、ぜひご覧ください。
退職金に課税される税金の計算方法:年金
退職金を年金形式で受け取る場合は、基礎年金と同じく雑所得とみなされ、金額に応じた控除額が差し引かれたうえで税額が決まります。なお、公的年金があれば合算します。国税庁「高齢者と税」によれば、「公的年金等に係る雑所得の速算表は」以下のとおりです。65歳未満の方と、65歳以上の方で異なります。
<65歳未満>
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
|---|---|
| 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超130万円未満 | 収入金額-60万円 |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 -27万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 -68万5千円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 -145万5千円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
引用:国税庁「高齢者と税」
次に、65歳以上の方の場合の表は下記のとおりです。
<65歳以上>
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
|---|---|
| 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円未満 | 収入金額-110万円 |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 -27万5千円 |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 -68万5千円 |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 -145万5千円 |
| 1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
引用:国税庁「高齢者と税」
どちらの表においても、「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が1,000万以下の場合となっています。
また、雑所得は年金のほかに給与所得や不動産所得なども合算する「総合課税」です。退職金のほかにも所得があれば、税額はまとめての算出となるので注意しましょう。
参照元
国税庁
高齢者と税
退職金を受け取る際は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しよう
退職の際は「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することで、源泉徴収による納税が可能になります。もし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないと、退職金を対象にした税制上の軽減措置を受けることができず、所得税は一律20%に。軽減措置を受けるためには、税額を再計算してもらうための確定申告が必要になります。
「退職所得の受給に関する申告書」は、税務署で入手または国税庁のWebサイトからのダウンロードが可能です。なお、退職金を年金形式で受け取る場合、「公的年金等の収入金額が400万円以下」かつ「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」だと確定申告は不要です。
退職金の額は会社の「就業規程」で確認しよう
今仕事を辞めたら退職金はいくらもらえるのか、これからのライフプランを考えるうえでも正確な数字を知っておきたいところです。退職金については会社の就業規則で確認することができます。一般的には退職金を算出するための計算方法が記載されているので、その式に勤続年数を当てはめれば退職金額がわかるでしょう。ただし、退職金の支給は企業に義務づけられているわけではありません。もし、就業規則に退職金に関する記載がなければ、退職金は出ない可能性があります。
一方、退職金の記載がある場合、支給額を算出する計算式が企業によって異なることも。勤続年数が同じ人でも、企業によってその額は大きく変わる場合があります。また、会社都合退職か自己都合退職かによっても、退職金額は変わる可能性が高いので、気になる方は確認してみましょう。
もし、将来受け取れる退職金が少ないと感じたら、ぜひハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、20代を中心とした若者向けの就職・転職支援サービス。「収入アップにつながる転職情報が知りたい」「収入アップを目指して未経験分野にチャレンジしたい」など、転職に関するさまざまなお悩みにマンツーマンで対応しています。もちろん、「退職金をもらえるくらい、長期で活躍できる職場を探している」方も大歓迎です。まずは相談料無料のハタラクティブまでお気軽にお問い合わせください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?
マーケティングアシスタント
東京都
年収 315万円~360万円
正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!
ライター・取材担当
東京都
年収 315万円~360万円
未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?
営業
東京都
年収 328万円~374万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆
ルート営業
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…
年収 228万円~365万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「お悩み」についての記事一覧
- 「退職の悩み」についての記事一覧
- 「退職手続き・法律関連」についての記事一覧
- 退職金にも税金はかかる?計算方法は?手取り額のシミュレーションも紹介