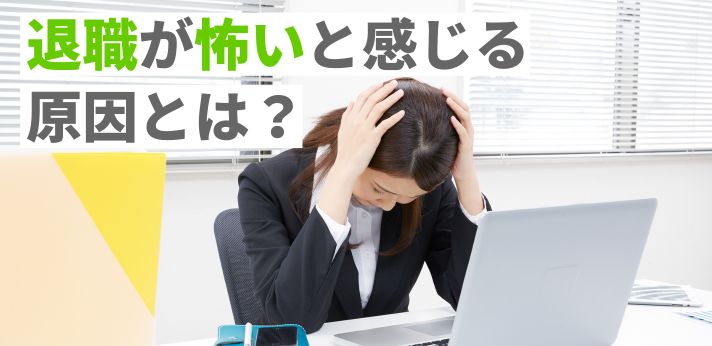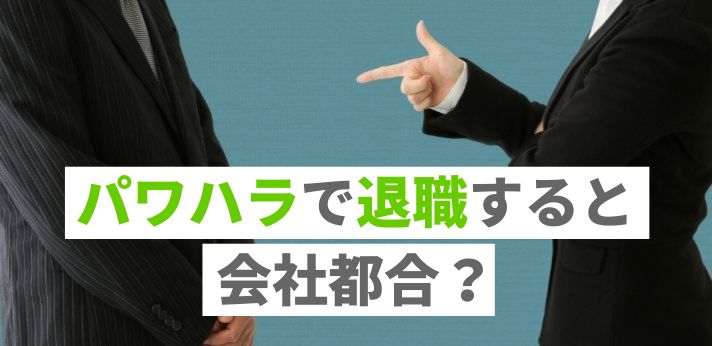引き止められない退職理由はある?病気・転職など状況別の例文を紹介引き止められない退職理由はある?病気・転職など状況別の例文を紹介
更新日
公開日
引き止められにくい退職理由は、病気や転職など会社が関与できない個人的な事情
「引き止められない退職理由はある?」とお悩みの方もいるでしょう。会社に退職の意思を伝える際は、病気や介護、転職など個人的な理由を伝えると引き止められにくくなります。このコラムでは、引き止められにくい退職理由の例文や伝え方をご紹介。また、引き止められたときの対処法や退職が決まったあとの流れについても解説します。円満退職して新しいスタートを切りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
引き止められない退職理由はある?
確実に退職できる理由は「ある」とは言い切れませんが、病気や転職など個人的な事情を伝えると引き止められにくくなります。具体的には、以下のような理由です。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
ここでは、これらの退職理由と、上司に伝える際の例文をご紹介します。正社員やアルバイト(パート)など、雇用形態にかかわらず退職しやすい理由なので、スムーズに会社を辞めたいと考えている方はぜひご一読ください。
なお、仕事のストレスで精神的に負担を感じていることも、退職理由になり得ます。特に、ストレスによって心身に何らかの影響が出ている場合は、無理に仕事を続けていると健康に支障をきたす可能性も。できるだけ早めに上司に相談して、退職を視野に入れて検討するのも一つの方法です。
退職しやすい理由1:病気
退職しやすい理由として挙げられるのが「病気」です。「病気の症状によって仕事に影響が出る」「仕事を続けながらでは治療できない」といったやむを得ない理由の場合は、会社から引き止められにくい傾向があります。そのため、きちんと事情を話せばスムーズに退職しやすいでしょう。
ただし、病気で退職する場合は医師が作成した診断書の提出を求める企業もあります。会社への診断書の提出は義務ではありませんが、就業規則に定められていることがあるので、退職の意思を伝える前に確認しておきましょう。
例文
会社に貢献できるよう頑張ってきましたが、○○月から体調が優れず療養に専念したいため、○○月で退職させていただきたいと考えております。
退職しやすい理由2:結婚・出産
結婚・出産にともない家庭に入ることも、退職しやすい理由の一つです。「専業主婦になる」「子育てに専念する」など、家族と話し合って決めたことを伝えれば、会社に納得してもらいやすくなるでしょう。
例文
○○月に結婚することとなり、退職させていただきたいと考えております。ここまで育てていただいたのに申し訳ありません。家庭を優先したいという気持ちが強いため、家族とも相談し決意いたしました。
退職しやすい理由3:介護
「家族の介護」も退職しやすい理由の一つです。「家族が高齢のため側で支えたい」という前向きな意向を伝えれば、会社から引き止められにくいでしょう。ただし、場合によっては「なぜ介護施設に預けないのか?」「ほかに介護できる人はいないのか?」などと踏み込んだ質問をされる可能性もあるので、回答を用意しておくと安心です。
例文
母が高齢となり、介護に専念したく退職させていただきたいと考えております。仕事を続けるか悩みましたが、自分を育ててくれた親の面倒を自分で見たいという気持ちが強く、このように決断いたしました。
退職しやすい理由4:転居
「遠方に引っ越さなければならない」といった事情も退職しやすい理由として挙げられます。しかし、引っ越し先の近くに支店がある場合や在宅勤務が可能な会社では、異動やリモートワークを提案される可能性があります。その場合は、「引っ越し後は家庭に入る」「環境の変化に伴い新しい仕事に挑戦したい」などと、転居後の計画を交えて述べると退職の交渉が進みやすくなるでしょう。
例文
この度、配偶者が遠方へ転勤することになりました。家庭の事情で大変恐縮ですが、私もついて行きたいと考えております。また、引っ越しを機に新しい環境でやりたかったことにチャレンジしたいと考え、退職を決意いたしました。
退職しやすい理由5:転職
「転職してキャリアアップ(キャリアチェンジ)をしたいから」というのも、退職しやすい理由の一つです。今の職場では携われない仕事に挑戦して、「自分の経験値を上げたい」「長年の夢を実現したい」といった目標を伝えれば、応援してくれる可能性もあります。挑戦したいポジションや業界、磨きたいスキルなどを具体的に伝えると、納得してもらいやすいでしょう。
ただし、現在の会社で実現できそうな目標の場合は、引き止められることもあるので注意してください。
例文
私は、IT技術を駆使した介護用品の販売会社を立ち上げることが夢です。起業の夢を叶えるためには、IT業界で新規事業の立ち上げに携わり、知見を得る必要があると考えています。新しい仕事にチャレンジするため、○○月をもって退職させていただきたく存じます。この会社では多くの経験をさせていただき、大変感謝しております。
上記のように、個人的な理由を伝えると、引き止められにくいでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
会社が退職希望者を引き止める理由
会社が退職希望者を引き止めるのには、上司の負担が増えたり、人手不足になったりするのを防ぎたいといった理由があります。また、上司が退職希望者の将来を心配して引き止める場合もあるでしょう。ここでは、これらの理由について詳しく解説します。会社が引き止める背景を理解することで対処しやすくなるので、ぜひご一読ください。
上司の負担が増えるのを防ぎたい
会社が退職希望者を引き止める理由の一つは、上司の負担が増えるのを防ぐためです。従業員が退職すると、その人が所属していたチームの人数が1人減るため、直属の上司は業務プランの立て直しを求められることも。以前より少ない人数でチームを運営しなければならないため、管理職としての負担が増える可能性もあります。
また、退職者が出ると上司が会社から管理能力を問われる場合もあるでしょう。上司によっては、育ててきた部下が会社を辞めることに、精神的なつらさを感じることも。このような背景から、会社や上司が退職希望者を引き止める場合があります。
人手不足になるのを避けたい
人手不足になるのを避けたいというのも、会社が退職希望者を引き止める理由です。従業員が1人減ると人出が不足し、業務に支障が出たり、新たな人材を採用するために労力・コストがかかったりするのが一般的。また、会社側からすれば、後継者を育てるのも同様にコストがかかります。このような状況を避けるため、引き止めを行う企業もあるでしょう。
退職希望者の将来を心配している
上司が、「会社を辞めると本人が困るのでは」と退職希望者の将来を心配して引き止める場合もあります。特に、親しくしていた上司なら、会社や業務の都合があるなか、退職希望者のことを親身に考えてくれることもあるでしょう。
このような場合は、上司に退職したい具体的な理由を明確に伝えれば、納得して退職の意思を尊重してくれる可能性があります。一方、本心から心配してくれる上司が、理由を聞いたうえで「今の仕事を続けるべき」と言う場合は、相談してみるのも選択肢の一つです。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職を切り出したらどんな方法で引き止められる?
会社が退職を引き止める方法は、「勤務条件の改善を提案する」「感情に訴えて説得する」「退職日を延期するよう打診する」といったものがあります。ここでは、これらの方法について解説しますので、退職を考えている方は参考にしてみてください。
勤務条件の改善を提案される
退職の引き止めとして、給料のアップや昇進といった勤務条件の改善を提案されることがあります。このような提案をされたら即答はせず、「自分はなぜ退職したいと思ったのか」に立ち返って考えることが大切です。
給料のアップや昇進によって退職したいと思った原因が解決する場合は、提案を受け入れることを検討するのも選択肢の一つ。一方、勤務条件の改善が現職への不満の解消やキャリアビジョンの達成につながらないなら、提案に応じて現職を続けても、また辞めたくなる可能性があるでしょう。
感情に訴える言葉で説得される
「あなたが辞めると上司や同僚が困る」といった感情に訴える言葉で引き止められることもあります。そのように説得されると、もう少し今の仕事を続けるべきかと迷うこともあるでしょう。
しかし、労働者には自由に退職する権利があります。退職による会社への影響について、申し訳なく思う必要はありません。
退職を考え直すよう説得されたときは、感情に流されず、冷静に対応することが大切です。
退職日を延期するよう打診される
「退職は認めるが、退職日を3ヶ月後に延期してほしい」といった打診をされる場合もあります。企業によっては、退職日を先延ばしにして、当日までの期間に考え直すよう促されることもあるでしょう。
一方、人手不足で急に退職されると困るという理由で、延期を打診する企業もあります。企業側が本当に困っている場合は、その点を考慮し延期を検討するのも選択肢の一つです。検討の結果、予定どおりの日に退職すると決めたら、業務を引き継ぐスケジュールを明確に伝えると納得してもらいやすいでしょう。
実際に退職した理由ランキング【アンケート調査】
ここでは、ハタラクティブの「若者しごと白書2024」を参考に、会社を辞めた人の退職理由をランキング形式で紹介します。正社員からフリーターになった人を対象に、正社員の仕事を退職した理由を調査したところ、結果は以下のとおりでした。
| 順位 | 男性 | 女性 |
|---|
| 1位 | 労働環境・時間が不満
(25.9%) | 結婚・出産など
(22.3%) |
| 2位 | 人間関係の不満
(18.8%) | 労働環境・時間が不満
(17.5%) |
| 3位 | 健康上の理由
(14.1%) | 人間関係の不満
(13.5%) |
上記の結果から、男女ともに労働環境・労働時間への不満や、人間関係が原因で退職する人が多いことが分かるでしょう。
また、女性は結婚や出産などのライフステージの変化が退職理由の1位に入っているのに対し、男性は同じ理由を挙げた人は少なく、健康上の理由が3位となっています。
引き止められないよう退職理由を考えるときの手順
退職を引き止められないよう退職理由を考える際は、最も大きい理由をポジティブな言葉に変換することが重要です。ここでは引き止められにくい退職理由を考える手順を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.退職理由として思いつくものを書き出す
最初に、退職したい理由として思いつくものを書き出しましょう。理由の大きさや、ポジティブかネガティブかにかかわらず、すべて書くことが大切です。
退職理由の例は、「担当している業務が自分の適性に合わない」「仕事量や労働時間が多く、身体に負担がかかっている」などが挙げられます。退職したい理由を書き出すことで、考えを整理しやすくなるでしょう。また、自分が仕事に求める条件が明確になり、転職活動をする際にも役立ちます。
2.書き出した退職理由のうち最も大きいものを明確にする
次に、書き出した退職理由のうち、最も大きいと思うものを明確にしましょう。
「どの理由が一番大きいか分からない」という場合は、系統が似ている理由がないか考えてみてください。たとえば、「労働環境に関すること」「健康上の問題」など系統が同じ理由が複数あったら、1つのグループにまとめてみましょう。
退職したい理由を整理することで、自分が今の仕事のどの点に何を感じているかが分かりやすくなります。そのうえで、自分にとって最も大きい退職理由を考えてみてください。
3.最も大きな退職理由をポジティブな言葉で言い換える
最も大きいと思う退職理由が明らかになったら、ポジティブな言葉で言い換えてみましょう。退職理由が待遇や仕事内容への不満などのネガティブな場合、会社から改善を提案されて引き止められる可能性があります。
一方、キャリアチェンジのため転職したいといった前向きな理由であれば、会社側が関与しにくくなるため引き止められにくいでしょう。
たとえば、先述した「担当している業務が自分の適性に合わない」という退職理由は、「自分のスキルに合う職種に転職したい」とポジティブに伝えられます。また、「仕事量や労働時間が多く、身体に負担がかかっている」という理由は、「今後は働き方を変えて、自分の健康を優先しながら仕事をしていきたい」と言い換えられるでしょう。
上司に退職を伝える際のポイント
ここでは、上司に退職を伝える際のポイントを紹介します。会社に納得してもらい、円満に退職できるように以下の内容を押さえておきましょう。
上司に退職を伝える際のポイント
- 退職の意思は1ヶ月半~3ヶ月前に伝える
- まず直属の上司に伝える
- 個室を選ぶ
- 個人的な理由をポジティブに伝える
- 退職の意思が固いことを伝える
- 感謝の気持ちを伝える
1.退職の意思は1ヶ月半~3ヶ月前に伝える
スムーズに会社を辞められるよう、退職の意思は1ヶ月半~3ヶ月前には伝えるのがおすすめです。退職時期を決める際は、業務の引き継ぎ期間や有給休暇の取得日などを考慮し、なるべく会社に迷惑をかけないよう配慮しましょう。
繁忙期は避ける
上司に退職の意思を伝える際は、繁忙期を避けましょう。繁忙期に退職を切り出すと、会社や上司に業務が忙しいなか対応してもらうことになり迷惑を掛ける可能性があります。話を聞いてもらえたとしても、「忙しいから続きはまた今度」と話し合いを先延ばしにされることもあるでしょう。退職理由について話すときは、時期やタイミングが大切です。
就業規則も確認しておく
退職の意思を伝える前に、就業規則も確認しておきましょう。会社によっては、「退職の○ヶ月前に申し出る」というように、退職の意思を伝える時期が就業規則で決められている場合もあります。トラブルを防ぐためにも、緊急事態でない限り就業規則に沿って退職理由を伝えましょう。
法律上は最短2週間で退職が可能
法律上は、民法「第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」によって、「無期雇用契約の場合、2週間前に意思表示すれば会社を辞められる」とされています。しかし、2週間前に申し出ると引き継ぎや人員確保などが間に合わず会社に負担がかかる可能性も。やむを得ない理由がない限りは、1ヶ月半~3ヶ月前に退職の意思表示をしましょう。
2.まず直属の上司に伝える
退職の意思は、まず直属の上司に伝えましょう。仲の良い先輩や同僚に話したくなるかもしれませんが、上司に伝える前に辞めるという噂が広まれば、不信感を与える場合があるからです。また、直属の上司がいるにもかかわらず、最初に社長や役員に伝えるのも好ましくありません。「スタッフの管理ができていない」と上司が責められてしまう可能性があります。
3.個室を選ぶ
退職を申し出る際は、個室を選びましょう。事前に上司へメールで「今後のことについてお話があるので、お時間をいただけますでしょうか」と連絡し、日時を設定したうえで直接退職の意思を伝えます。会社や自分自身の将来に関わる大事な話なので、ほかの人がいる場所で話すのは避けましょう。社内の会議室や喫茶店といった静かな場所で話すのがおすすめです。
4.個人的な理由をポジティブに伝える
このコラムの「引き止められない退職理由はある?」でも述べたとおり、個人的な退職理由を伝えるのもポイントです。個人的な理由の場合は会社が関与するのが難しいため、引き止められにくくなるでしょう。また、前述した「引き止められないよう退職理由を考えるときの手順」も参考に、ポジティブな言葉で伝えましょう。
たとえば、「キャリアアップのため」「今の仕事と異なる業界に転職したい」など、個人的な理由を前向きな言葉で話せば、応援したいと思ってもらえる可能性があります。
嘘はつかない
個人的な理由がない場合も、嘘をつくのは避けたほうが無難です。嘘が発覚すると信頼を失い、円満に退職することが難しくなってしまう恐れがあります。
曖昧な表現は避ける
退職を申し出る際は、曖昧な表現は避けましょう。たとえば、「時期は決まっていないが退職したい」「会社を辞めようか悩んでいる」など、退職の意思が伝わりにくい言い回しをすると、引き止められてしまう可能性があるので要注意です。
5.退職の意思が固いことを伝える
退職を申し出る際は、引き止められてもブレないような強い意思があることもあわせて伝えましょう。理由が曖昧だったり、自分のなかで迷いがあったりすると、「交渉の余地があるのでは」と思われる可能性があります。また、引き止められて会社に残ることになったとしても、一度退職したいと伝えたことで居心地が悪いと感じる場合もあるでしょう。
退職時期の延長を求められたらどうする?
就業規則に沿っていたり、時間に余裕を持たせたりしたうえで退職を申し出たにもかかわらず、退職時期の延長を求められた場合は、延長できない旨を伝えましょう。このコラムの「退職日を延期するよう打診される」でも前述したとおり、延長に応じると、そのまま引き止められてしまう可能性があります。
6.感謝の気持ちを伝える
感謝の気持ちを述べることも、退職の意思を伝える際に重要なポイントといえます。仕事上の指導やサポートをしてもらったことに対するお礼を述べ、相手に敬意を払いましょう。あくまで自分の都合で退職することを念頭に置き、謙虚な姿勢で話すのが大切です。
要注意!引き止められやすい退職理由
会社から引き止められるのを避けたいなら、退職理由として待遇面や残業時間、人間関係に関する不満を伝えるのは避けましょう。これらの理由は会社側が改善できる余地があるため、引き止められる可能性があります。
給与や休暇など待遇面に関する不満
会社に引き止められたくない場合は、給与や休暇など待遇面に関する不満を言うのは避けましょう。待遇面の不満は、会社側に改善の余地があるため引き止められやすい理由です。「給料が低い」「土日出勤が多い」といった理由を述べれば、上司から「給料を上げることを検討する」「休みを増やせないか会社と相談する」などと提案される場合があるでしょう。
残業時間や業務内容に関する不満
「残業時間が多い」「業務内容が自分のスキルに合わない」といった不満を退職理由にするのも避けたほうが無難です。会社側から、残業時間を減らしたり、部署を異動させたりすることで解決する問題と認識されてしまい、退職しにくくなる恐れがあります。
人間関係の不満
「人間関係の悩み」もスムーズに退職できる理由を探している方にはおすすめできません。「チームに苦手な人がいて仕事に支障が出ている」「同僚とうまく関係が築けない」といった問題は、会社側が改善に取り組めるからです。人間関係の悩みを話した場合は、別の部署への異動を提案され、引き止められることが予想されます。
退職を認めてもらえない場合の対処法
退職の意思を伝えたものの認めてもらえない場合は、退職届を提出する、別の上司に申し出る、退職代行サービスを利用するといった対処法があります。退職の意思が固まっている方は、以下を参考にしてみてください。
退職届を提出する
退職の意思を伝えても会社側に認めてもらえない場合は、退職届を提出するのも一つの手です。退職の意思を表明する書類には、「退職願」と「退職届」の2種類があります。「退職願」は、退職を願い出る際に会社に提出する書類です。一般的には、口頭で退職の意思を伝え合意を得たあと、退職願を出します。
一方、「退職届」は自分の退職を通告するための書類です。会社側がなかなか辞めさせてくれない場合でも、退職届を提出すれば法的に退職が成立します。
別の上司に退職の意思を伝える
直属の上司に退職の意思を伝えたものの、話し合いに応じてもらえない場合は、別の上司に退職を申し出て対応してもらうのも選択肢の一つです。その際、直属の上司にメールで改めて退職の意思を伝え、辞めたいことを伝えた証拠を残しておきましょう。
退職代行サービスを利用する
退職代行サービスを利用すれば、自分で退職の意思を伝えるよりもスムーズに辞められる可能性があります。労働者は自由に退職する権利があり、会社側は強引に引き止めることはできないからです。また、退職代行サービスを利用すると、退職届の提出や備品の返却をすべて郵送で済ませられます。強引な引き止めにあっていて退職できないという方は、退職代行サービスの利用も検討してみましょう。
退職が決まったあとの流れ
退職について上司から承諾を得たら、退職願を提出し、最終出社日までに業務の引き継ぎや備品の返却などを行います。以下で流れを詳しく見ていきましょう。
退職が決まったあとの流れ
- 退職日を決める
- 退職願を提出する
- 業務の整理や引き継ぎをする
- 必要書類の受け取りと備品の返却を行う
1.退職日を決める
退職することが決まったら、退職日を決定します。退職の意思を伝える際は、自分から退職希望日を申告しましょう。そのうえで、「何日に退職するか」「最終出社日はいつにするか」といった詳細について、上司の意見も踏まえて決めます。
2.退職願を提出する
退職日が決まったら、退職願を作成してください。書類の作成方法はPC、手書きのどちらでも問題ありませんが、会社から指定があれば従いましょう。所定のフォーマットがない場合は、「退職理由」「退職日」「日付(退職願を提出する日)」を記し、「署名」「捺印」をします。
なお、自己都合で退職する際の退職理由は、「一身上の都合により退職いたします」で構いません。退職願は、退職日の約1ヶ月前までに直属の上司に直接手渡ししましょう。
3.業務の整理や引き継ぎをする
最終出社日までに、身の回りの整理整頓や業務の引き継ぎを行います。引き継ぎの漏れがないように、スケジュール表やチェック表などを活用しながら進めましょう。この際、マニュアルを引き渡すだけではなく、後任者に直接教える機会を設けるとベターです。
4.必要書類の受け取りと備品の返却を行う
退職する際は、会社から公的手続きに必要な書類を受け取り、貸与された備品や仕事の書類は必ず返却しましょう。これらの受け取りや返却を忘れてしまうと、スムーズに手続きできなかったり、会社に迷惑をかけたりする恐れがあります。受け取るものと返却するものを事前にチェックしておきましょう。
受け取るもの
- ・離職票
- ・雇用保険被保険者証(会社が保管している場合)
- ・年金手帳(会社が保管している場合)
- ・源泉徴収票
返却するもの
- ・健康保険被保険者証
- ・社員証
- ・自分の名刺
- ・取引先から受け取った名刺
- ・通勤定期
- ・会社のパソコン、文具、書籍
- ・書類やデータ
失業保険の申請に必要な離職票や、転職先で提出が求められる源泉徴収票は、退職後に自宅に送付されるのが一般的です。念のため、いつごろ送ってもらえるのかを確認しておきましょう。仕事で使用した書類やデータは、すべて会社に返却しましょう。
転職活動は在職中に始めるのがおすすめ
退職を決めたら、できるだけ早めに次の仕事を探すことも大切です。現職を続けながら転職活動をするのは時間的に難しいという理由で、退職後に仕事を探そうと考える方もいるでしょう。しかし、収入がない状態で転職活動を行うと、次第に経済的な余裕がなくなり、早く仕事を決めなければと焦ってしまうこともあります。心に余裕を持って就職先を探すためにも、転職活動は在職中に行うのがおすすめです。
働きながら転職活動を行うなら、就職・転職エージェントを利用するのも選択肢の一つです。若年層向けの就職・転職エージェントであるハタラクティブでは、専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行い、希望の職種や条件を丁寧にヒアリング。カウンセリング後は、分からないことや不安なことをLINEで気軽に相談していただけます。
最短2週間と短期間で内定が出るので、仕事と転職活動を両立したい方にもぴったりです。サービスはすべて無料なので、「スムーズに退職したいけど理由が思いつかない」「働きながら転職活動をしたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「引き止められずに退職したい」と考えている人のお悩みQ&A
ここでは、引き止められずに退職したいと考えている方のお悩みをQ&A方式で解決します。
「ある」とは言い切れませんが、退職しやすい理由として「病気の治療」や「結婚・出産」、「遠方への引っ越し」などがあります。これらの理由はやむを得ない事情のため、上司は引き止めにくく、退職しやすいといえるでしょう。詳しくは、このコラムの「引き止められない退職理由はある?」をご覧ください。
退職代行サービスに依頼をすれば、自身で退職を申し出ることなく会社を辞められます。会社から強引な引き止めにあっている方や、心身の状態により自身で意思表示するのが難しい方は、退職代行サービスの利用を検討してみましょう。退職代行サービスについては「退職の申し出を相談せずメールだけで済ますのはアリ?注意点や例文をご紹介」でまとめているので、あわせて参考にしてください。
退職理由がネガティブなものであれば、ポジティブに言い換えることでスムーズに退職できる場合もあります。「残業がきつい」「人間関係が良くない」といった理由で退職したい方もいるでしょう。しかし、これらの本音をそのまま伝えると、改善を提案されて引き止められる可能性があります。本音をうまく言い換えて円満に退職したい方は、このコラムの「引き止められないよう退職理由を考えるときの手順」をご一読ください。
退職届は、一般的に「退職する1~3ヶ月前に提出」と規定している会社が多いようです。ただし、退職届の提出期限は企業によって異なるので、就業規則を確認しましょう。詳しくは、「退職届はいつまでに出す?提出のスケジュールと必要な手続きを紹介」を参考にしてください。
「退職する前に転職先を決めたい」「スムーズに会社を辞めたい」という方は、ハタラクティブへご相談ください。転職支援の経験が豊富なキャリアアドバイザーが、丁寧にアドバイスいたします。