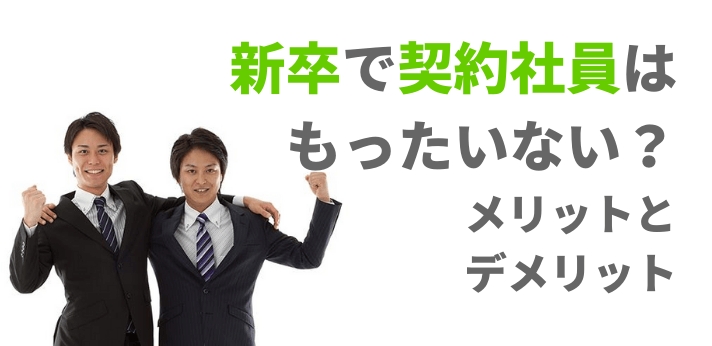契約社員でも退職金は支払われる?正社員との違いと働く際の留意点も紹介契約社員でも退職金は支払われる?正社員との違いと働く際の留意点も紹介
更新日
公開日
「契約社員を辞めたいけれど、退職金はもらえるのか?」と疑問に感じている人は、多いのではないでしょうか。結論からいうと、退職金の有無は会社次第です。ボーナスと同様、法律上の決まりはないため、会社に契約社員に対する退職金制度が用意されているかどうかが基準となります。そのほか、同一労働同一賃金や雇用期間など、契約社員として働くなら知っておきたい知識をまとめているので、参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
契約社員は退職金をもらえる?
結論からいうと、契約社員が退職金を支給されるかどうかは、会社によって異なるものの支給されないのが一般的でしょう。退職金とは、会社を退職するときに支給されるお金のこと。退職金の設置や支給については、法律で定められていません。ボーナスと同様に退職金制度の有無や金額は会社の裁量に任せられているため、会社によっては、正社員として勤めていても退職金が支給されないこともありえます。
また、退職金の支給を行っている企業の多くが勤続年数に応じて金額が変動する方法を採用しており、ほとんどが勤続3年以上が対象。契約社員は1回の雇用契約で最長3年までしか勤務できないため、無期雇用の正社員は対象であっても有期雇用の契約社員を対象外とする企業が多いようです。
しかし、正社員向けの就業規則を契約社員にも適用しているなど、就業規則の内容によっては支払われる可能性もあります。自分が退職金を支給されるか気になったら、就業規則を確認すると良いでしょう。
厚生労働省
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
契約満了も退職金の対象?
退職金というと、定年退職時に支給されるイメージをもつ人も多いですが、実際にはどのようなタイミングの退職でも支給対象となります。契約社員の契約時期満了もあてはまるでしょう。ただし、先述のとおり、退職金制度には法的な決まりはありません。会社の規定によっては退職金支給の対象外となる場合が定められている可能性もあるので、よく確認しましょう。
退職金をもらえたとしても金額が高くない可能性がある
退職金の支給金額は、勤続年数に応じて水準が高くなるように設定されることが一般的です。正社員であっても、勤続年数が短い場合は支給されないこともあります。勤続期間が限定される契約社員は、退職金が支給されたとしても、金額は低いでしょう。
正社員でも退職金がもらえるとは限らない
| 企業規模 | 退職給付制度がある | 退職給付制度がない |
|---|
| 1,000人以上 | 92.3% | 7.7% |
| 300~999人 | 91.8% | 8.2% |
| 100~299人 | 84.9% | 15.1% |
| 30~99人 | 77.6% | 22.4% |
| 調査計 | 80.5% | 19.5% |
企業規模や産業によっても割合は異なるものの。小規模な会社ほど退職金制度を取り入れていない割合が高いようです。正社員に退職金を支給しない会社が契約社員に退職金を支給することは、まずないでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
契約社員も退職金がもらえる?同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは 働き方改革の一環として、正規雇用労働者(正社員)と、契約社員と派遣社員など非正規雇用労働者の間の待遇差の解消を目指すものです。契約社員と正社員に同じ仕事をさせているにも関わらず、「退職金やボーナスが出るのは正社員だけ」といった待遇差をなくすことを目的に、制度が作られました。
非正規労働者は、正社員との間の待遇差について、事業主に説明を求めることができます。
賞与や手当にも適用される
同一労働同一賃金は、雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保するためのルールです。基本給はもちろん、労働者の貢献に対し支払われる賞与であれば、同一の貢献度に対して同一の賞与が支給されなければなりません。昇給やボーナス、各種手当や福利厚生についても当てはまります。
厚生労働省のガイドラインに明記されていないものの、退職金や家族手当などの手当に関しても、不合理な待遇差の是正が求められているようです。この制度により、正社員と同等に働いている契約社員なら、退職金をもらえる可能性が高まるでしょう。「正社員のメリット・デメリットとは?派遣や契約社員についても解説!」でも、同一労働同一賃金について解説しているので、参考にしてください。
無期転換ルールとは?
無期転換ルールとは、有期労働契約者が、一定の条件を満たすことで、無期労働契約に転換できる制度です。同一の雇用者と有期雇用契約の労働者との間で、契約が通算5年を超えたときに、労働者からの申し出があれば、無期労働契約に転換できるようになりました。契約社員もこの制度の対象です。就業規約に「契約社員の場合は5年以上の勤務が対象」など記載があれば、無期雇用に転換することも検討してみましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
契約社員以外に退職金をもらえるのは誰?雇用形態の違い
冒頭でも説明したとおり、正社員と契約社員では、退職金やボーナスにおいて待遇の差があることが多いようです。正社員と契約社員以外にも、臨時社員や準社員、派遣社員、嘱託社員といった雇用形態もあります。ここでは、厚生労働省の定義をもとに、それぞれの雇用形態の特徴と違いを簡単に説明するので、今後のキャリアを考える参考にしてください。
正社員
正社員とは、雇用期間の定めなく、1週間の所定労働時間で働いている常用労働者のことを指します。常用労働者とは、期間を定めず(または1か月以上の期間で)雇われている者のこと。契約社員のように働く期間が定まっておらず、本人が望み、会社が存続していれば、定年まで働き続けることができます。そのほか、一般的にいわれている正社員の特徴は、以下のとおりです。
・雇用期間の定めがない
・フルタイムで働く
・年齢とともに給与が上がることが多い
・社会的信頼度が高くなる
あくまでも一例ですが、仕事量や責任の大きさから、正社員の方が高賃金となることが多いようです。また、福利厚生が手厚かったり雇用が安定していたりする点も、正社員のメリットといえるでしょう。退職金が多くもらえる可能性があることも、正社員の特徴です。
近年では、転勤を伴わない「勤務地限定正社員」や、特定の業務に専念する「職務限定正社員」という制度を取り入れる企業も増えています。契約社員と正社員、派遣社員など働き方で悩んだら、正社員として就職した方が、得られるメリットは大きいでしょう。
契約社員
厚生労働省の定義によると、契約社員とは、あらかじめ雇用期間が定められている労働契約をした労働者のこと。一般的にいわれている契約社員の特徴は、下記のとおりです。
・雇用期間があらかじめ決められている
・昇給や昇格するチャンスが少ない
・ボーナスや退職金が適用されないことが多い
・転勤や異動の対象にならない
・ライフスタイルに合わせた働き方ができる
・雇用が不安定
会社によっては、特定のスキルを持つ人を契約社員として確保したがることもあり、スキルのある人には、得意分野を活かす働き方が可能です。雇用期間が定められているので、雇用が不安定な一方、正社員よりも就業のハードルは低いでしょう。ただし、退職金やボーナス、福利厚生などの面では、正社員に劣る点も多いのが現実です。「契約社員と正社員の違いは?メリットを比較して適した働き方を知ろう」で、契約社員と正社員、それぞれのメリットとデメリットを紹介しているので、参考にしてください。
パートタイム労働者
パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間よりも短い時間の勤務する労働者のことです。契約期間と就業時間、給与や雇用条件を、事前に取り決めします。臨時社員や準社員、アルバイトも、パートタイム労働者の1種です。
準社員
準社員という雇用形態は、法律上で明確に定義されたものではありません。この名称を用いている雇用主によって、給与や待遇が決められています。厚生労働省が挙げている例として、パートは時給制、準社員は日給制といったように、一部のルールが異なる労働者に、便宜上名称をつけているようです。
準社員として労働契約を結ぶ場合は、業務範囲や契約期間、就業時間などを確認しましょう。残業の扱いや賞与、退職金などの扱いが、不合理な場合があります。
派遣社員
派遣社員という雇用形態も世間的に浸透した働き方です。派遣社員とは、人材派遣会社と雇用契約を結んだ労働者が、人材派遣会社から人材を必要とする企業に対して派遣されて働く労働形態。雇用元と勤務先が異なるのが特徴です。詳しくは「派遣社員とは何か?種類や正社員との働き方の違いを解説」のコラムでご確認ください。
嘱託社員
嘱託社員も、法律上で明記された雇用形態ではありません。契約社員の一種で、定年退職者を一定期間再雇用することを嘱託社員と呼ぶことが多いようです。再雇用のため、一度は退職していることになります。そのため、定年までの労働に対する退職金をもらうことができるパターンが多いようです。
退職金だけじゃない!契約社員と正社員の6つの違い
契約社員と正社員では、雇用契約や就業規則などいくつかの違いが挙げられます。それらの違いは
契約前によく確認しておきましょう。ここでは、契約社員と正社員の違いを大きく6点で紹介します。
1.雇用期間
これまで説明してきたように、契約社員は雇用時の契約によって雇用期間が決められます。一回の契約で働ける期間は、最長で3年間。契約終了時の再契約により、それ以降の雇用が延長されます。先述のとおり、2013年4月から労働契約法が改正され、「無期転換ルール」ができました。これにより、通算して5年以上の雇用契約更新をしている有期労働者は、申し込みにより期間契約のない無期労働契約へ転換できます。詳しくは、このコラムの「無期転換ルール」を参照ください。
2.昇進や昇給
一般的に、契約社員の待遇や給与は、契約時から期間満了まで、一定の条件となります。契約期間中に途中で変更されることは、あまりありません。契約更新時に、実績や会社への貢献度を加味して、新たな待遇や給与で契約を結ぶことは可能です。正社員の場合は勤続年数に応じて昇給することがありますが、契約社員は、契約期間が長くなっても給与が上がるとは限りません。
3.賞与
賞与(ボーナス)に関して法律上の規制はありません。正規社員であっても賞与が支給されない会社もあります。過去は賞与があっても、業績によって減額したり、支給がなくなったりすることもあるようです。契約社員の場合には、雇用契約や就業規則に定めがなければ、支払われない場合が多いでしょう。支払われる場合においても、正規社員と契約社員では金額の差があります。ただし、先述の「同一労働同一賃金」制度により、正社員と同等に働いている契約社員なら、賞与をもらえる可能性が高まりました。詳しくは、このコラムの「契約社員も退職金がもらえる?同一労働同一賃金とは」をご確認ください。
4.転勤や異動
契約社員は、契約書に勤務場所や所属部署が明記されているため、基本的に異動や転勤の対象にならないでしょう。就業規則や雇用契約に転勤、異動に従うといった記載がある場合にも、本人の同意なしでの異動や転勤の心配はいらないといえます。一方、正社員では転勤や異動の決定には抗えないこともあるでしょう。
5.解雇予告
契約社員は契約期間を定めて就業しますので、雇用主は「やむを得ない事由」を除いて、契約期間の途中で解雇することはできません。これは、労働契約法の第17条で定められています。
契約社員の場合、契約期間満了により契約を終了するのが一般的です。ただし、3回以上契約が更新されている、もしくは1年を超えて継続勤務している労働者に対して契約更新しない場合は、雇用主は30日前までに解雇を予告する必要があります。
6.福利厚生
健康保険や厚生年金などの社会保険の保険料は、会社によって負担される法定福利厚生です。これは、いずれの雇用形態の社員にも等しく対象となります。それ以外の住宅手当や扶養手当、退職金制度は、法定外の福利厚生です。そのため、正社員には適用されても、契約社員には適用されない場合があるでしょう。
退職金以外に契約社員のデメリットはある?
契約社員として働くには、退職金を支給される可能性が低いこと以外にも、多くのメリットが挙げられます。ここでは、契約社員のメリットとデメリットをいくつか紹介するので、参考にしてください。
契約社員のメリット
契約社員のメリットは、社会保険などの正規社員と同様の福利厚生が保証されることです。会社によっては、退職金も受け取れるでしょう。また、正社員と異なり契約期間が決められるため、将来の留学や起業、結婚・出産など、ライフプランが立てやすい雇用形態です。
基本的に異動・転勤が無く、残業が少なく自身の時間の確保ができるので、プライベートの時間が確保しやすいという面もあります。子育て中の方や資格試験の勉強に時間を取りたい人にとって大きなメリットといえるでしょう。
契約社員のデメリット
契約内容にもよりますが、契約社員は、契約した給与以外の賞与や退職金がない、もしくは少ない傾向があります。契約満了まで契約時の契約内容が継続されるので、昇給や昇格も見込めません。
また、契約が満了になったあとも更新されるとは限らないこと、正社員に比べるとスキルアップの機会が少ないことなどもデメリットとして挙げられます。
契約社員として働く際の3つの留意点
契約社員として働く際は、給与や就業時間だけでなく、退職金や福利厚生といった面も労働契約内容をよく確認しておく必要があります。もし、契約内容に明記されていない内容があれば、雇用主に問い合わせ、確認しておきましょう。
1.契約内容の確認
契約社員にとどまらず、どのような雇用形態であっても、労働契約内容はきちんと確認しておきましょう。業務の内容や就業の場所、始業・終業時刻と休憩時間などは必須事項です。残業の有無や休日と休暇、賃金の締め支払い方法、退職に関する事項も、よく確認しましょう。そのほかにも、退職金制度や賞与の有無など、気になる点は就業前によく確認し、納得したうえで働くようにしてください。
正社員登用制度
正社員登用制度は、契約社員や派遣社員などの非正規社員が正社員雇用に切り替わる制度です。制度があっても正社員に切り替えた実績がない会社もあれば、制度が無くても業績によって正社員に採用された実績がある会社も存在します。契約社員や派遣社員などからいずれ正社員になることを検討しているなら、この点も確認しておきましょう。正社員登用制度により正社員就業を目指す方は、「正社員登用制度とは?読み方や必要な実績・試験について解説!」もご覧ください。
2.内定先の就業規則を確認する
10人以上の労働者がいる事業所では、就業規則の作成が義務です。契約社員やアルバイトなど、個別の就業規則が作成されていない場合には、正社員と同じ就業規則が適用されます。これは、雇用契約書よりも優先される規約です。有期雇用契約書に、「退職金は支払われない」と記載があったとしても、就業規則に退職金を支払う記載があれば、就業規則が優先され、退職金は支払われなければなりません。
3.労働条件通知書の内容を確認する
契約社員に限らず、就業する際には労働条件通知書を取り交わさなくてはなりません。通知書には「絶対的記載事項」と、文書または口頭で通知される「相対的明示事項」があります。
相対的明示事項については、不明な点があれば明確にすることが必要です。「絶対的記載事項」においても、労働期間の満了について、日付まで記載されているかどうか確認しましょう。また、契約更新については記載されていない場合が多いので、更新が有るのかどうか、更新となる条件などを確認します。労働条件通知書は、雇用契約が終了し退職したあとも、3年間は保管しておきましょう。
「契約社員として働いているけれど、退職金がもらえるか不安」「契約社員になることを検討しているけれど、正社員より待遇が悪そう」など、契約社員に関してお悩みの方は、ハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは20代を中心とした、若者向けの就職・転職支援サービスです。正社員経験のない方の転職相談も受け付けています。転職の意志が固まっていない方も、今後のキャリアを考えるお手伝いをいたしますので、お気軽にご相談ください。
契約社員の退職金に関する疑問Q&A
契約社員として活躍する方に向け、退職金に関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。
どうしても退職金がほしい場合は、就業規則・労働条件などをよく確認したうえで契約しましょう。しかし、退職金は契約社員に支給する企業は少ないうえ、法律で支払うことが定められているものではないため、契約社員や派遣社員などの雇用形態を問わず「絶対にもらえる」ものではありません。
退職金の給付方法は「退職一時金」と「企業年金」の2種類が基本です。主に「基本給連動型」「ポイント制」「定額制」「別テーブル制」など4種類の算出方法があり、どれを採用しているかは企業によって異なります。それぞれの退職金算出方法については「退職金は何年目から出る?基礎知識や計算方法を解説!」で解説していますので、ご一読ください。
正社員の退職金は、就業規則の「退職金規定」欄に記載されています。勤続年数や導入している算出方法などによって正確な退職金の金額は変わりますが、大まかな計算はできるでしょう。
退職金にも、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」がかかります。課税額・手取り額などの計算方法は「退職金にも税金はかかる?計算方法と注意点のまとめ」で例を挙げていますので、ご活用ください。退職金を得るなら正社員がおすすめです。契約社員から正社員を目指すなら、ハタラクティブにお任せください。じっくりヒアリングを行い希望に合う企業をご紹介します。