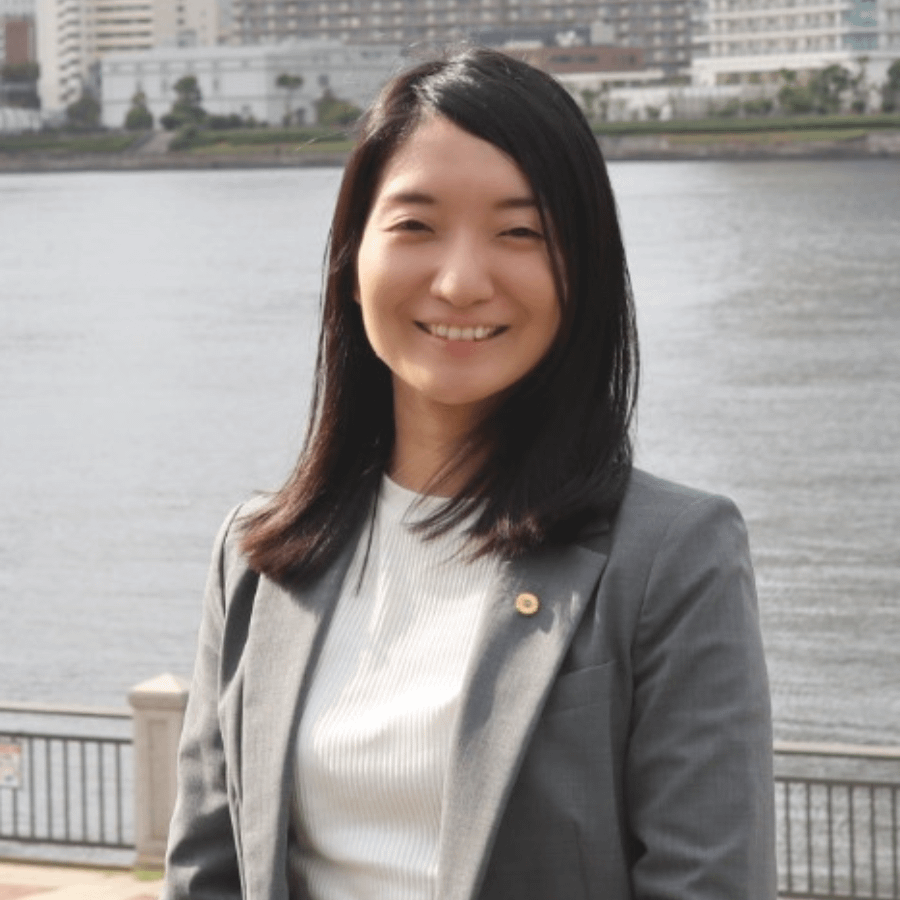- 「ハタラクティブ」トップ
- 記事トップ
- 「お悩み」についての記事一覧
- 「退職の悩み」についての記事一覧
- 「退職手続き・法律関連」についての記事一覧
- 退職後の手続きを順番に解説!期限はいつまで?必要書類の一覧も紹介
退職後の手続きを順番に解説!期限はいつまで?必要書類の一覧も紹介
この記事のまとめ
- 退職後に行う手続きには、「健康保険」「年金」「税金」などがある
- 退職後の手続きに必要な書類だけでなく、パソコンや名刺など会社への返却物も確認しておく
- 転職先が決まっていない場合、退職後に失業保険の受給手続きをする
- 退職後すぐに働けない場合は、失業保険受給延長の手続きが可能
- 退職後の転職活動が不安なら、エージェントのサポートを受けるのも手
あなたにおすすめ!
「退職後の手続きには何がある?」「転職を控えているが、やることや必要書類などが多くて難しい…」と悩んだり「以前退職後の手続きをしたが忘れてしまった」と困っている方もいるのではないでしょうか。
退職後の手続きには、健康保険や年金、税金、雇用保険などがあります。状況によって行うべき手続きの内容や期限が異なるので、事前に把握しておくことが大切です
このコラムでは、退職後に行う手続き一覧に沿って、健康保険・年金・税金・失業保険に関わる手続きの方法を紹介します。期限や流れを知り、退職後の手続きをスムーズに行いましょう。
自分に向いている仕事を
簡単に診断してみましょう
性格でわかる
私の適職診断

就職・転職でお困りではありませんか?
退職後の手続きでやることリスト

退職後に行う手続きは、抜け漏れのないようスムーズに取り組むことが大切です。以下に退職後に行う可能性のある手続きとその期限をリストにまとめました。
退職後の手続きで注意すべきポイントを教えてください
手続きはそれぞれ期限が決まっているので注意!
転職先が決まっている場合は転職先の会社で案内された書類を準備すればよいですが、転職先が決まっていない場合は自分で手続きする必要があり、また、手続きにはそれぞれ期限が決まっていることが注意点です。
転職先がまだ決まっていない場合に具体的に行う手続きは、健康保険や年金、雇用保険、住民税です。
健康保険は、退職後会社の健康保険から脱退します。今まで使っていた健康保険証は返却し、使用することはできません。会社の健康保険に継続することもできますが、退職後20日以内に申請する必要があります。もし国民健康保険に加入するのであれば、14日以内に市区役所に行きます。
また、退職後も年金は支払い続ける必要があります。厚生年金から国民年金に切り替え、同様に市区町村で手続きが必要です。
転職活動を行う際は、ハローワークで失業手当を受け取る手続きもします。退職後にハローワークに行き、必要書類を提出しましょう。
最後に、住民税の納付があります。住んでいる市区役所から届いた納付書を使って、期限までに納付しましょう。
このように、退職後すぐに転職しない場合は、自分で書類を用意し期限を管理して手続きしないといけないことが注意点です。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 【健康保険】家族の扶養 | 速やかに |
| 【健康保険】国民健康保険に加入 | 14日以内 |
| 【健康保険】前職の健康保険を任意継続 | 20日以内 |
| 【健康保険】転職先の健康保険に切り替え | 転職後すぐ |
| 【年金】国民年金への切り替え | 14日以内 |
| 【税金】住民税 | 1~5月と6~12月に退職する場合で異なる |
| 【税金】年末調整 | 再就職した場合、企業が設ける期限内に対応 |
| 【税金】確定申告 | 再就職しなかった場合、翌年の2月~3月に申告 |
| 【雇用保険】失業保険 | 原則として離職日の翌日から1年間 |
上記リストから自身に必要な項目をピックアップし、期限内に手続きを済ませましょう。状況によって期限が異なったり、手続きが不要だったりするので、よく考えてから進める必要があります。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職後の手続きに必要な書類一覧
退職後の手続きには、必要となる書類がいくつかあります。以下の一覧を確認し、該当の手続きを行う際に慌てないよう用意しましょう。
期日までに前職から書類を手に入れられていない場合にはどうしたらいいですか?
書類が揃わない場合は行政の各窓口に相談しましょう
退職後の手続きに必要な書類が遅延する場合があります。転職先が未定、家族の扶養に入らないなど、自分で手続きをする必要がある時は、行政の相談窓口に問い合わせをするとスムーズです。
国民健康保険の手続きは、市区町村の国民健康保険課で相談ができます。国民年金は年金事務所が主な窓口となり、市区町村の国民年金課でも基本的な手続きが可能です。また、「ねんきんダイヤル」での電話相談も受け付けています。
税金については、所得税は税務署、住民税は市区町村の税務課が担当します。確定申告や各種控除の相談は税務署で受け付けており、国税庁のホームページでも情報を確認できます。
雇用保険はハローワークが窓口です。基本手当の手続きや求職活動の相談ができます。
各種手続きには期限があるため注意が必要です。窓口では本人確認書類、マイナンバー、印鑑、給与関係書類などが必要となります。手続きをスムーズに進めるため、事前に電話で必要書類や来所時間を確認することをおすすめします。
会社側からもらう書類
退職後の手続きに必要な書類のなかで、会社からもらうものを下記にまとめました。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 健康保険資格喪失証明書 | ・健康保険の資格を喪失した日や扶養者でなくなったことを証明する書類 ・国民健康保険の切り替えに必要 |
| 退職証明書 | ・勤務した会社を現在は退職していることを証明する書類 ・国民健康保険や国民年金の切り替えに必要 |
| 年金手帳 (基礎年金番号通知書) | ・公的年金制度の加入状況が書かれている書類 ・年金に関する手続きに必要 ※2022年3月31日に年金手帳の新規発行と再発行は廃止 |
| 源泉徴収票 | ・1年間の収入と納付した所得税、控除額などが書かれている書類 ・年末調整や確定申告の手続きに必要 |
| 雇用保険被保険者離職票 | ・離職していることを証明する書類 ・失業保険の申請手続きに必要 |
| 雇用保険被保険者証 | ・雇用保険に加入していることを証明する書類 ・失業保険の申請手続きに必要 |
上記の書類は、仕事を辞める際に会社側から受け取るものです。退職後の手続きの際に必要なため、不足している書類がある場合は、早めに会社に問い合わせましょう。
退職時に会社側からもらう書類は、正社員やパートなどでそこまで違いはありません。詳しくは「退職時にもらう書類はパートと社員で異なる?返却物や必要な手続きも解説」のコラムもあわせて参考にしてみてください。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。適性に合わない仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「性格でわかる私の適職診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職後の手続きに自分で準備するもの
退職の手続きを行う際に自分で用意するものは、下記のとおりです。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 身分証明書 マイナンバーカード | 手続きの際に本人確認を行うために必要 |
| 印鑑 | 各種書類に押印するために必要 |
| 通帳またはキャッシュカード | 失業保険の給付金振込口座を指定する際に必要 |
退職の手続きをする際は、会社から受け取る書類だけでなく、上記もそろえておきましょう。
会社側へ返却するものを確認する
退職時は、返却物の確認も忘れずに行ってください。一般的には以下のようなものがあります。
- ・健康保険被保険者証
- ・社内用携帯電話、パソコン
- ・社員証、名刺
- ・事務用品
- ・社外秘のデータや資料
特に会社の所有物であるパソコンや携帯電話、社外秘データなどは、返却を忘れるとトラブルにつながる恐れがあります。何を返すのかを事前に確認したうえで、退職日までに会社へ返却できるようにしましょう。
「退職前にやることリスト!会社への返却物と受け取る書類や公的手続きを確認」のコラムでは、退職時に会社へ返却するもののチェックリストを掲載しているので、ぜひ活用してみてください。
退職前・退職後・転職後それぞれの手続きを把握しておこう
退職を決意したら、退職前後と転職後、それぞれのタイミングで必要な手続きを確認することが大事です。たとえば、退職前は会社から支給されていた備品や健康保険証など、職場に返却するものがあります。また、退職後に転職活動を行う場合は、人によって失業保険の手続きが必要になることも。手続きに使用する雇用保険被保険者証や離職票を、退職時にもらい忘れることがないようにしましょう。退職後の手続きの詳細は、「失業したらやることは?年金・保険の手続き・失業保険の受給手順も解説」のコラムもあわせてご覧ください。
退職後に行う手続き一覧【順番・期限】
退職後に行う手続きの順番は、仕事が決まっている場合やそうでない場合などによって異なります。すぐに転職しない場合は、下記の順番で覚えておきましょう。
退職後に行う手続きの順番
- 健康保険の手続き【退職後5日以内/14日以内/20日以内】
- 年金の手続き【退職後14日以内】
- 住民税の手続き【時期によって退職後速やかに】
- 所得税の手続き【確定申告は退職後翌年3月15日まで】
「健康保険」「年金」「住民税」「所得税」の手続きにはそれぞれ期限が設けられており、早いものでは退職日から2週間以内に行う必要があります。なお、健康保険と年金の手続きは、順番が前後しても問題はありません。
この項では、「健康保険」「年金」「住民税」「所得税」の4つの手続きについてまとめました。
速やかに転職先や役所などに相談しよう
もし再就職をしているのであれば、速やかに会社の人事部門や総務部門に連絡を取り状況を説明します。半年以上経ってしまったなど極端に期限を過ぎていなければ、期限の延長や再提出を受け付けてもらえると思います。
また、たとえ受付や再提出を認めてもらえても、手続きが遅れることによって給与の支給や社会保険、住民税の手続きに影響が出る場合もあるため、早く対応することが重要です。
再就職していない場合、健康保険の任意継続の手続きは期限を過ぎてしまうと受け付けてもらえないことがあるので、退職日の前からあらかじめ健康保険の任意継続するかしないか決めておくことが大切です。
また、退職後に必要な手続きの中には、ハローワーク、市区役所で直接対応する必要がある場合もあります。そのため、まずはハローワークや市区役所へ電話をして期限を過ぎてしまったことを説明し、案内された必要な書類をそろえて早く手続きしましょう。
1.健康保険の手続き【退職後5日以内/14日以内/20日以内】
退職後に社会保険を抜けて保険証を返却する場合、新たに健康保険へ加入する必要があります。保険証がないと医療費が高額になり、必要なときに病院にかかりづらくなる場合があるため、早めに手続きを行いましょう。
健康保険の主な加入方法は、以下の4種類です。
| 健康保険の手続き | 期限 | 手続き方法 |
|---|---|---|
| 【1】転職先企業の健康保険に切り替える場合 | 転職後すぐ | ・次の転職先が決定している場合、その企業で健康保険に加入できる ・転職先の健康保険への加入手続きは、企業側が行ってくれるのが基本 ・前職から受け取る「健康保険資格喪失証明書」の提出は必要ないが、念のため手元に保管しておくのがおすすめ |
| 【2】家族の扶養に入る場合 | 退職後5日以内 | ・被保険者である家族が勤務先で手続きを進める ・必要な書類や条件は、状況によって異なるため、事前の相談・確認が必要 ・被扶養者になるときは、退職した翌日から認定を受けられる(原則として退職後5日以内に手続きが必要) |
| 【3】国民健康保険に加入する場合 | 退職後14日以内 | ・国民健康保険とは、会社に所属していない方や職場の健康保険に入っていない方が加入する制度・保険料を自分で全額支払う ・対象者は、退職後すぐに転職しない人や個人事業主、フリーランス ・国民健康保険に加入する場合は、居住地を管轄する役所で手続きを行う(退職後14日以内) |
| 【4】前職の健康保険を任意継続する場合 | 退職後20日以内 | ・任意継続とは、会社が半分負担していた保険料を全額自分で支払うことで、退職後も前職の健康保険に加入できる制度 ・退職後は、前職で加入していた健康保険を最長2年の任意継続が可能 ・健康保険を任意継続したい方は、健康保険組合へ申し出る(退職した翌日から20日以内) |
扶養に入る場合の条件が知りたい方は、「扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での『被扶養者』条件の違いも解説」のコラムで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
参照元
日本年金機構
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
国民健康保険は退職後14日過ぎたら加入できない?
国民健康保険は、退職後14日を過ぎても加入が可能です。14日を過ぎて手続きした場合、届出の日付以降が保険給付の対象となります。保険料の全額負担を避けるためにも、退職後14日を過ぎている場合は早急に手続きを済ませることが大事です。
期限を過ぎた際の対応については、「国民健康保険の退職後手続きが14日過ぎたら?行うべき手続きを紹介」のコラムでまとめているので、合わせてお読みください。2.年金の手続き【退職後14日以内】
会社を辞めたら、退職日の翌日には厚生年金の資格を喪失します。すぐに転職先の厚生年金へ加入しない場合は、国民年金へ切り替える手続きが必要です。
国民年金に切り替える際は、退職後14日以内に居住地を管轄する役所で申請をしましょう。手続きの際は、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書といった退職日を証明するための書類が必要です。
| 年金の手続き | 期限 | 手続き方法 |
|---|---|---|
| 【1】すでに転職先が決まっている場合 | ー | ・厚生年金への切り替え手続きが不要 ・転職先に基礎年金番号またはマイナンバーを聞かれる可能性があるので、必要書類を揃えておく必要がある |
| 【2】転職先が未定で厚生年金から国民年金に切り替える場合 | 退職後14日以内 | ・厚生年金の加入資格を失うため、自身で国民年金に切り替える・対象者は、退職後すぐに転職しない人や個人事業主、フリーランス ・住民票のある市区町村役場で手続きを行う(退職後14日以内) ※手続きに必要なもの 「退職日が記載された離職票」 「健康保険資格喪失証明書」 「本人確認書類」 ※保険料の負担が厳しい場合は、免除や猶予制度の申請を検討してみましょう。 |
| 【3】被扶養者になる場合 | 退職後14日以内 | ・国民年金の第3号被保険者に切り替える ・第2号被保険者の扶養に入れば、年金を個別に納める必要なし ・手続きは配偶者の勤務先を通して行うため、書類を受け取ったら、必要事項を記入して提出する(退職後14日以内) ※第3号被保険者になれる条件 ・20歳以上60歳未満 ・第2号被保険者(国民年金と厚生年金・共済組合に加入している)の配偶者に扶養されている ※配偶者を第3号被保険者にしている第2号被保険者が会社を辞めた場合、自身の手続きとともに、配偶者の手続きも必要になるため、夫婦ともに国民年金への切り替え手続きを行う |
参照元
日本年金機構
た行 第3号被保険者
確定拠出年金に加入している場合の退職後の手続きは?
転職先に企業型確定拠出年金があれば、運用資産を移換する手続きを行います。転職先に企業型確定拠出年金の制度がない場合は、個人型確定拠出年金であるiDeCoに移換して運用を継続しましょう。退職後6ヶ月月以内に移換手続きを行わない場合、資産は国民年金基金連合会に自動移換され、運用が停止して手数料のみが引かれる可能性があるため注意が必要です。
iDeCoの場合は退職後もそのまま継続でき、給与所得がない場合は国民年金第1号被保険者として掛金を自分で払い続ける必要があります。また、転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合はiDeCoの資産を移換することも可能です。いずれの場合も、退職時に企業から提供される確定拠出年金に関する書類を基に手続きを進め、移換期限を守るよう心掛けましょう。参照元
厚生労働省
確定拠出年金制度の概要
3.住民税の支払い手続き【退職後速やかに】
住民税の手続きは、転職のタイミングに合わせて、給与から一括天引きまたは普通徴収へ切り替える必要があります。未納状態を避けるためにも、速やかな対応を心掛けましょう。
| 住民税の手続き | 期限 | 手続き方法 |
|---|---|---|
| 【1】退職後1ヶ月以内に転職する場合 | 退職後速やかに | ・新しい職場で住民税を納付するのが一般的 ・給与から住民税を天引きしてもらう手続きを行う ・手続きを行わない場合は、普通徴収として自分で住民税を支払うことになる |
| 【2】1~5月に退職かつ1ヶ月以上の離職期間ができる・独立する場合 | ー | ・該当期間の住民税を一括徴収することになるため、特別な手続きは不要 ・退職時に給与や退職金から住民税が全額一括で差し引かれることが一般的 ※給与や退職金のみでは支払いが不足する場合、差額については自治体から納付書が送られ、普通徴収となる場合がある |
| 【3】6~12月に退職かつ1ヶ月以上の離職期間ができる・独立する場合 | 退職後速やかに | ・普通徴収か一括徴収のどちらかを選択が可能 ・一括徴収を選択する場合は、給与もしくは退職金から一括徴収される ・普通徴収を選択する場合は、納付書に記載された期日までに自分で住民税を納める |
「無職でも住民税は払う?状況別の納付方法や注意ポイントについて解説!」でも住民税について詳細に触れているので、ぜひご確認ください。
自分で住民税を納めるときは?
退職後に普通徴収で住民税を支払うときは、自宅に郵送される納付書の内容に従いましょう。住民税の支払いが難しい場合は、居住地を管轄する自治体に相談するのがおすすめです。特別な事情で住民税の支払いが困難であると認められれば、減額や免除をされることもあるでしょう。
ただし、自己都合退職の場合、納付が免除になる可能性は低いようです。気になる方は、居住地を管轄する自治体に問い合わせてみてください。4.所得税の手続き【確定申告は退職後翌年3月15日まで】
退職後の状況によっては、年末調整や確定申告といった所得税に関する手続きが必要です。以下で詳しく解説します。
| 所得税の手続き | 期限 | 手続き方法 |
|---|---|---|
| 【1】年内に転職した場合の年末調整の手続き | ー | ・新しい職場で年末調整を行う ・転職先で年末調整をしてもらう際は、前職の源泉徴収票を提出する ※年末調整の期日は職場によって異なるので、あらかじめ必要書類を準備しておくこと ※年末調整は12月31日までに在籍している職員を対象としているため、12月末に退職する場合は対象外 |
| 【2】年内に転職しなかった場合は確定申告の手続き | 退職後翌年3月15日まで | ・「確定申告」とは、1年間の所得に掛かった税金を納めるための申告手続き ・退職後、年内に再就職しなかった場合は、「確定申告」で所得税の過不足を精算する ・確定申告は、対象となる年の翌年2月16日〜3月15日までに行う ※提出書類の作成方法「税務署で受け取れる確定申告書に記入する」 「確定申告ソフトを利用する」 「国税庁が提供している確定申告書の作成サービスを使用する」など |
参照元
国税庁
確定申告書等作成コーナー
年内に転職しても時期によっては自分で確定申告が必要な場合がある
年内に転職しても、入社する時期によっては自分で確定申告をする必要があるでしょう。企業によって異なりますが、年末調整の手続きは11月から12月下旬にかけて行われます。企業は年末調整に必要な書類の提出期限を設けているため、期限までに前職の源泉徴収票を出せない場合は自分で確定申告を行いましょう。転職先で年末調整をしてもらいたい場合は、10月中に勤務を開始しておくと安心です。再就職まで1ヶ月以上空くのでれば、健康保険や年金、雇用保険の手続きが必要となります。健康保険や年金、雇用保険は月単位での加入となるからです。
また、雇用保険の受給を希望する場合は失業給付の手続きも必要です。転職先が決まっていない場合は、4週間に1回はハローワークに行き、手続きを忘れないようにしましょう。
退職後すぐに就職しないなら失業保険の申請手続きをしよう

退職後すぐに就職しない場合は、失業保険を受け取れる可能性があります。失業保険を受給する際は、離職日の翌日から1年の間にハローワークで手続きしましょう。
失業保険の受給要件
ハローワークインターネットサービス「受給要件」によると、失業保険の主な受給条件は、以下のとおりです。
- ・離職日以前の2年間で雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある
- ・再就職をする意思がある
- ・ハローワークに登録して就職活動を行っていると判断された
失業保険とは、退職後も生活の心配をせず再就職に向けて求職活動を行えるように支給される手当です。そのため、「再就職できるよう努力している」ことが前提となります。
また、会社都合や労働契約期間の満了により離職した人は、「離職日以前の1年間で雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あること」が受給の要件です。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
ハローワークの手続きに必要な書類と持ち物
失業保険の手続きに必要な持ち物は、以下の内容が挙げられます。ハローワークの手続きがスムーズに進むよう、事前に準備しておきましょう。
- ・雇用保険被保険者証
- ・雇用保険被保険者離職票1、2
- ・写真(縦3センチ×横2.5センチ)×2枚
- ・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- ・印鑑
- ・身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
雇用保険被保険者証は退職時に会社から直接渡され、離職票は郵送されるのが一般的です。「雇用保険被保険者証を渡されていない」もしくは「2週間以上経っても離職票が届かない」ときは、前職に確認しましょう。会社が発行してくれない場合は、ハローワークに相談すれば再発行できるようです。
失業保険の手続きに必要なものは、「ハローワークで失業保険受給の手続きをするには?必要な持ち物や書類とは」のコラムで触れているので、ご参照ください。
失業保険申請の手続きの流れ
失業保険の手続きは、居住地を管轄するハローワークで行います。受給の流れは以下のとおりです。
- ・ハローワークで求職申し込みをして面談を行い、受給資格者として認定される
- ・7日間待機する
- ・雇用保険説明会に出席して雇用保険受給資格者証を受け取る
- ・指定された失業認定日に再び出向く
- ・給付制限期間のあとに失業保険が口座に振り込まれる
退職後に離職票を受け取ったら、なるべく早くハローワークで手続きしましょう。自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の受給までに2ヶ月ほど給付制限が設けられます。手続きが遅れるほど、受給開始日も先に伸びるため注意しましょう。
失業保険の手続き期限を過ぎても遡って申請することが可能
厚生労働省の「雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です」によれば、失業保険の手続き期限を過ぎても、2年以内であれば遡って申請することが可能です。
手続きの際には、期限を過ぎた理由をハローワークに説明し、やむを得ない事情があれば認められる可能性があります。ただし、遡って申請できる期間には限度があるため、早めにハローワークで相談することをおすすめします。
参照元
厚生労働省
雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です
失業保険(正式名称:基本手当)の申請時に気をつけるポイントは「待機期間」と「給付制限期間」を理解することです。自己都合退職の場合、申請から7日間の待機期間に加えて、2ヶ月以上の給付制限期間が設けられます。そのため、退職後できるだけ速やかに手続きを始めることをおすすめします。
また、失業認定日には必ず本人が出向く必要があり、その際には就職活動状況の報告も求められます。
自己都合退職と会社都合退職の支給日の違い
自己都合退職と会社都合退職の支給日について、以下にまとめました。
| 自己都合退職の場合 | 7日間の待期期間と2ヶ月間の給付制限を過ぎたあとに失業手当が支給される |
| 会社都合退職の場合 | 失業日の8日目以降から失業手当が受け取れる |
退職事由によって、失業手当の支給日が異なることを理解しておきましょう。
すぐに働けない場合は受給を延長できる
出産や病気といったやむを得ない事情で退職後すぐに働けない場合は、失業保険の受給資格を延長できます。最大3年間延長できるため、必要に応じて所定の手続きを行いましょう。延長後の受給期間の最終日までであれば、失業保険の手続きが可能です。
なお、妊娠・出産の場合は母子健康手帳、病気の場合は診断書が必要となります。
副業収入がある場合にも、条件により基本手当を受給できます。ただし、申告が必要です
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中でも、一定の条件下で副業することは可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
副業する場合には、必ず失業認定申告書に記載のうえ、申告が必要です。「週の所定労働時間が20時間未満」かつ「31日以上の雇用見込みがない」仕事である必要があります。仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならない場合や、収入額により減額される場合があります。
また、自己都合退職による給付制限期間(2ヶ月間~)中でも副業は可能ですが、収入の有無にかかわらず、必ず失業認定申告書に仕事をしたことを記載する必要があります。もし、申告せずに失業保険を受給した場合には不正受給となります。不明な点がある場合は、必ずハローワークに確認しましょう。
早期に正社員として再就職した場合には、条件により受給できる「再就職手当」という制度もあります。将来に向けて安定した正社員としての再就職を目指す際には、転職エージェントでもキャリア相談ができます。ぜひ、利用を検討してみてください。
退職後の再就職は転職エージェントに相談するのも手

退職後に転職活動を始めるとき、「前職で抱えていた悩みを解消できるか」「希望の転職先から内定をもらえるか」など、不安に思う方もいるでしょう。転職活動を始めるにあたって不安なことがある場合は、転職のプロに相談しながら選考を進めることをおすすめします。
転職エージェントでは、専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行ったうえであなたにぴったりの求人紹介や応募書類の作成サポート、面接対策、スケジュール調整などを行ってくれるのが特徴です。応募先企業の傾向や採用ニーズに沿った選考対策のアドバイスももらえるため、転職活動に不安があったり選考の進め方に悩む方は利用を検討してみましょう。
ハタラクティブ在籍アドバイザーからエージェントを利用する際のアドバイス
転職エージェントでは、非公開求人を取り扱っているところもあります。ヒアリングを通じて相談者にぴったりの求人を提案するので、自分では適性に気づけなかった仕事やスキルを活かせる環境を見つけられるでしょう。
「転職エージェントの使い方を解説!利用時の基本の流れと賢い活用方のコツ」のコラムも参考に、利用方法をチェックしてみてください。ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
「退職後に一人で転職活動を行う自信がない」「手続きが複雑で分からない」とお悩みの方は、ハタラクティブの利用がおすすめです。
若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブでは、相談者の希望条件に合わせた求人をご提案します。実際に企業に足を運んで得た情報を提供するため、情報収集や企業選びにかかる時間を大幅に短縮することが可能です。
応募したい企業が見つかったら、ハタラクティブがあなたの都合に合わせて面接の日程調整を行います。経験豊富なキャリアアドバイザーが、応募から入社後のフォローまでトータルサポートするので、お気軽にご相談ください。
退職後の手続きに関するお悩みQ&A
ここでは、退職後の手続きに関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。退職後の手続きが分からない方は、ぜひ参考にしてみてください。
退職したらやることは何がありますか?
退職したらやることには、「健康保険」「年金」「税金」の手続きなどが挙げられます。退職後すぐに転職しない場合は、失業保険の申請も行いましょう。失業保険は、申請後に待期期間があり、受給できる期間が決まっているため、なるべく早く手続きを済ませるのがポイントです。
詳しくは、「仕事を辞めたらすること5ステップ!退職後の手続きや必要書類を順番に解説」のコラムを参考にしてみてください。
退職後に市役所で必要な手続きは何ですか?
退職後に市区町村の役所で行う手続きは、健康保険と年金の切り替えです。会社の健康保険や厚生年金保険の資格を喪失するため、国民健康保険や国民年金に加入する手続きを行う必要があります。
ただし、退職してすぐに任意継続や転職先で新たに加入する場合、手続きは不要になる場合もあるので、よく確認してから手続きを行いましょう。
退職後フリーランスになったら何の手続きが必要ですか?
退職後にフリーランスとして働く場合は、健康保険や国民年金の切り替え手続き、住民税の支払い方法の確認などが必要です。また、フリーランスの事業を開始した日から1ヶ月以内に、開業届を提出しましょう。開業届は、本格的にフリーランスとして動き出す前に提出しておくと、慌てないで済むので安心です。
参照元
国税庁
個人事業の開業届出・廃業届出等手続
退職後、次の転職先で必要な手続きはありますか?
転職先に社会保険が完備されている場合は、加入手続きを行うことになります。会社の社会保険に加入する場合は、転職先で加入手続きを進めることが一般的です。
扶養家族の申請が必要な場合は、証明書を提出して手続きを行いましょう。また、転職先の年末調整に間に合う場合は、退職時に受け取った源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらってください。
退職後に傷病手当金はもらえますか?
もらえる可能性はあります。ただし、傷病手当金の申請には、主治医が記載する欄があるため、時間や手間が掛かることを理解しておきましょう。
傷病手当金の詳しい申請手順や受給額については、「休職届の書き方や申請方法は?傷病手当や休職中の過ごし方のお悩みを解決」のコラムも参考にしてみてください。
退職後の手続きが終わったら1ヶ月程度休んでも大丈夫ですか?
退職後に心身のリフレッシュ期間を設けるのは問題ありません。ただし、休む期間が長引き過ぎないようにするのがポイント。空白期間が長くなると、企業側から仕事に対する意欲を懸念されやすくなるからです。
「退職後の手続きは何をする?期限や順番、必要書類を分かりやすく解説!」のコラムでは、1ヶ月休む場合の注意点をまとめているので、あわせてご一読ください。退職後の仕事探しが不安な方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。