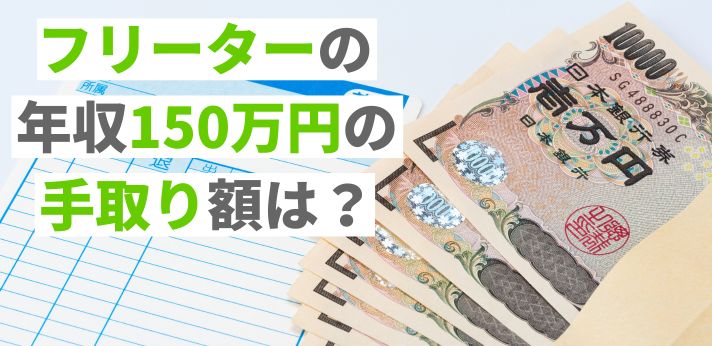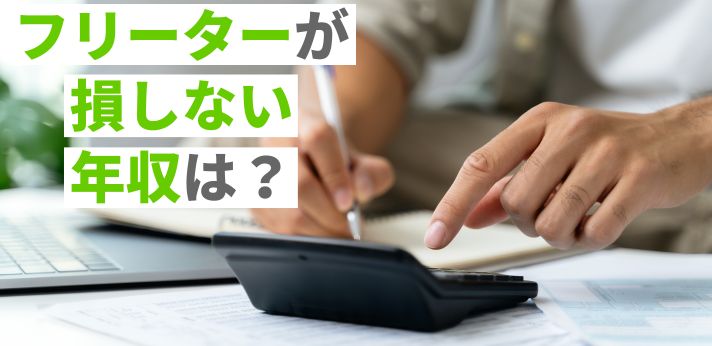150万を超えたら税金はいくら払うの?年収の壁とあわせて詳しく解説
更新日
公開日
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
年収150万円を超えたら税金をいくら払うかは、収入や住んでいる場所によって変わる
フリーターやパートとして働く人のなかには、「年収が150万円を超えたら税金をいくら払うの?」と気になる方もいるでしょう。年収が150万円を超えた場合、支払う税金の額は収入や居住地によって異なります。このコラムでは、年収150万円を超えたときに気になる配偶者特別控除や年収150万円以上稼ぐメリット・デメリットを解説。103万円や130万円などの年収の壁もご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。
※現在は制度変更により、配偶者特別控除の満額基準が「160万円」へ引き上げられています。 制度は随時更新されるため、働き方を決める際は必ず最新の公的情報を確認してください。
年収が150万を超えたら?税金はいくら払うの?
※2025年12月より、配偶者特別控除が満額適用となる年収水準が「160万円」に引き上げられました。これに伴い、控除対象も年収201万5,999円以下(所得133万円以下)へと緩和されています。
160万円までは税負担を抑えて働くことが可能で、それを超えても段階的に控除を受けられる仕組みです。制度は随時更新されるため、働き方を決める際は必ず最新の公的情報を確認してください。
年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が減り始めます。国税庁の「年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき」によると、配偶者の合計所得金額が48万円超え133万円以下(収入が給与所得のみの場合は年収103万円超え201万5,999円以下)の場合、給与所得者(納税者)に配偶者特別控除が適用されることがあるようです。
年収が150万円を超えた場合に支払う税金について教えてください
年収100万円以上で住民税を納める必要があり、年収160万円以上なら所得税も発生する
住民税は前年の所得に基づいて計算されます。年収が100万円を超えると、翌年に住民税が発生し、税率は一律10%です。
所得税については、2025年度から基礎控除と給与所得控除の見直しにより、従来の「103万円の壁」から「160万円の壁」に引き上げられました。つまり、年収160万円以下であれば所得税はかかりません。年収150万円の場合は所得税の心配はありませんが、160万円を超えると所得税が発生します。
税金のほかにも、社会保険料に注意が必要です。社会保険の壁には「106万円の壁」と「130万円の壁」があり、勤務先の従業員数や就業条件に応じて、どちらの壁が適用されるのかが異なります。
年収が150万円を超えるといずれの壁も超えるため、自分自身で社会保険料を納めなければなりません。最終的な手取り額に影響するため、税金だけでなく社会保険料の仕組みも理解することが大切です。
たとえば、パートで働く方が年収103~201万円程度の場合、条件を満たすと配偶者の課税所得が控除されます。それに伴い、配偶者が支払う所得税や住民税の額も抑えられるでしょう。
ただし、配偶者特別控除は、配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が減り、201万5,999円を超えるとなくなる仕組みです。よって、年収が150万円を超えると、配偶者が支払う所得税額や住民税額も高くなるでしょう。
配偶者特別控除とは
国税庁の「配偶者特別控除」によると、配偶者特別控除とは、合計所得が48万円を超える(収入が給与所得のみの場合は年収103万円を超える)配偶者がいる場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。たとえば、夫婦のどちらか一方が正社員、もう一人が年収103万円を超えているパート従業員の場合、条件を満たすとパート従業員の収入に応じて正社員の課税所得が控除されます。
以下では、給与所得者の合計所得金額が900万円以下(給与所得のみの場合は年収1,095万円以下)の場合の配偶者特別控除額を表にまとめました。
| 配偶者の年収 | 控除額 |
|---|
| 103万円超150万円以下 | 38万円 |
| 150万円超155万円以下 | 36万円 |
| 155万円超160万円以下 | 31万円 |
| 160万円超166万7,999円以下 | 26万円 |
| 166万7,999円超175万1,999円以下 | 21万円 |
| 175万1,999円超183万1,999円以下 | 16万円 |
| 183万1,999円超190万3,999円以下 | 11万円 |
| 190万3,999円超197万1,999円以下 | 6万円 |
| 197万1,999円超201万5,999円以下 | 3万円 |
| 201万5,999円超 | 0円 |
配偶者の年収が150万円以下の場合、38万円が給与所得者の課税所得から控除されますが、150万円を超えた場合は収入に応じて控除額が減少していることが分かります。
扶養控除との違いは?
配偶者特別控除と扶養控除の主な違いは、対象者です。国税庁の「扶養控除」によると、扶養控除の対象者には配偶者以外の親族も含まれます。一方、配偶者特別控除の対象は、結婚している夫や妻のみです。
参照元: 国税庁 扶養控除
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
年収150万を超えた場合のメリットとデメリット
年収150万円を超えた場合、税金や手取り額に関してメリットとデメリットがあります。メリット・デメリットを確認し、働き方を考えてみましょう。
年収150万円を超えた場合は、手取り・年金・給付金の増額といったメリットがあります
年収が150万円を超えると、自身の手取りが増えるため世帯収入は増えます。社会保険料も増えるので「働き損になる」ともいわれますが、厚生労働省の試算では、年収150万円くらいから手取りが増えていくとされています。
ほかにも、各種給付の金額も増加します。たとえば、厚生年金に加入していれば将来の年金額を増やすことができます。さらに、私傷病により休職せざるを得なくなったときの所得保障の「傷病手当金」や産休時の所得保障の「出産手当金」、育休・介護休時の所得保障の「育児・介護休業給付金」、失業時の「基本手当」は、過去の給与額に応じて給付額が決定されますから、給与が増えることでこれらの給付も手厚くできるわけです。
世帯収入を上げて、万が一のときの備えを手厚くできるのは、将来を見据えたときに大きなメリットといえるでしょう。
メリット
厚生労働省の「『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?(p.14)」によると、年収が150万円を超えて配偶者特別控除の控除額が減少しても、世帯の手取りは減りません。パートとして働く自分の年収が150万円を超えた場合、夫や妻の税金が増えますが、自身の手取りが増えます。よって、世帯全体でみると損はしないといえるでしょう。
また、収入が増えるぶん、将来受給できる厚生年金の額が上がります。世帯の手取りが増えるうえ、将来にも備えられるのは大きなメリットです。
デメリット
自分の年収が150万円を超えた場合、夫や妻が納める所得税や住民税の額が増える点はデメリットといえるでしょう。しかし、配偶者特別控除の控除額は段階的に減るため、150万円を少し超えた程度であれば、納税額は大きく上がらないといえます。
税金面で見ると、年収100万円を超えた翌年は年間数万円の住民税負担が生じます。ただし、所得税については2025年度より控除額が160万円に引き上げられたため、150万円の段階では発生しません。
親や配偶者の扶養に入っている場合、年収が130万円を超えると扶養に入り続けることはできません(60歳以上または障害者の場合は180万円)。この場合、勤務先が特定適用事業所の場合は勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入し、自分で社会保険料を納めます。
また、勤務先が特定適用事業所でない場合は、国民健康保険と国民年金に加入し、自分で保険料を納めなければなりません。これにより月額2~4万円程度の保険料負担が発生し、実質的な手取り収入が減少してしまうデメリットがあります。
そのほかにも、親や配偶者が受けている扶養控除や配偶者控除が減額または廃止される場合があり、世帯全体の税負担が増加することも。また、勤務先の扶養手当が支給停止になるケースも考えられるでしょう。
なお、収入が増えると、それに伴い自身が納める社会保険料が増える点にも注意が必要です。将来の年金が増額されますが、社会保険料が増額されればデメリットに感じることもあるでしょう。
※現在は制度変更により、配偶者特別控除の満額基準が「160万円」へ引き上げられています。 制度は随時更新されるため、働き方を決める際は必ず最新の公的情報を確認してください。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
150万以外にもある?知っておきたい年収の壁とは
年収の壁とは、税金が課税されたり、社会保険料の支払い義務が発生したりする基準。150万円以外にも、103万円や130万円などさまざまな年収の壁があります。以下では、年収の壁を表にまとめました。
年収の壁には、社会保険と税金に関するものが合計6つあります
年収の壁には、税金に関するものと社会保険に関するものがあります。
税金に関するものは次の4つです。
■100万円の壁……住民税の納税義務発生(金額は自治体による)
■103万円の壁……所得税の納税義務発生
■150万円の壁……配偶者特別控除が段階的に減額
■201万円の壁……配偶者特別控除が対象外
社会保険に関するものは次の2つです。
■106万円の壁……健康保険・厚生年金保険の加入義務発生(その他要件も満たす場合)
■130万円の壁……国民健康保険・国民年金の加入義務発生
ただし、「103万円の壁」は2025年12月から最大「160万円の壁」になり、「106万円の壁」は2028年6月までに撤廃されます。
このように複数の年収の壁があるため、「年収の壁の範囲内で働きたい」との希望を伝えても、どの年収の壁を指しているのかをハッキリさせないと、思ってもいない労働条件を提示される場合がありますので要注意です。
※2025年以降、配偶者特別控除が満額適用となる水準は160万円に引き上げられています
| 年収の目安 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 健康保険・年金 |
|---|
| 年収100万円超 | 必要 | 不要 | 〇 | ✕ | 不要※ |
| 年収103万円超 | 必要 | 必要 | ✕ | 〇 | 不要※ |
| 年収106万円超 | 必要 | 必要 | ✕ | 〇 | 状況により、社会保険の加入対象 |
| 年収130万円超 | 必要 | 必要 | ✕ | 〇 | 加入必須 |
| 年収150万円超 | 必要 | 必要 | ✕ | △ | 加入必須 |
| 年収201万円超 | 必要 | 必要 | ✕ | ✕ | 加入必須 |
※扶養に入っている場合には支払いが不要。年金保険料が不要なのは、配偶者の扶養に入っている場合のみ。
ここからは、年収150万円の壁以外にも理解しておきたい年収の壁について詳しく解説します。収入と税金や保険料の関係について確認したい人は、ぜひ参考にしてみてください。
年収100万の壁
年収100万円の壁とは、住民税の支払いが発生する目安です。自治体によっても異なりますが、年収100万円を超えると住民税が掛かるのが一般的。住民税が課税されると、そのぶん手取り額が減少します。
年収103万の壁
年収103万円の壁は、所得税が課税される基準です。103万円以下の場合は所得税の納税は必要ありませんが、103万円を超えると所得税を支払わなければなりません。
また、年収103万円は配偶者控除の壁でもあります。国税庁の「配偶者控除」によれば、配偶者が年収103万円以下の場合、給与所得者は収入によって13~38万円の控除を受けることが可能。しかし、年収103万円を超えると配偶者控除が適用されず、控除額が1~38万円の配偶者特別控除に変わります。
年収103万の壁については、「年収が103万超えたらどうなる?収入の壁とは」でも詳しくご確認ください。
所得税の算出方法
所得税は「(給与収入ー所得控除)×税率」で算出できます。基本的に、所得控除は基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円。したがって、年収が103万円の場合は所得税が掛かりません。所得税の控除の種類は、「所得税の控除ってなに?仕組みや種類を知ろう」のコラムでも確認してみてください。
住民税の算出方法
住民税は、一定の所得がある場合に定額で負担する「均等割」と昨年の所得をもとに算出される「所得割」で成り立っています。総務省の「個人住民税」によると、自治体によって異なりますが、均等割は基本的に年間4,000円+森林環境税1,000円。所得割は、「(所得金額ー所得控除)×税率ー税額控除額」で算出されます。
なお、住民税の税額は前年の所得を基準に決まるのが特徴です。そのため、今年収入がなくても前年に収入があると納税の必要があります。
年収106万の壁
年収106万円を超えると、社会保険の加入義務が生じる可能性があります。年収106万円以下の場合、被扶養者であれば社会保険料を支払う必要がありません。しかし、年収106万円を超えると社会保険上の扶養から外れ、健康保険料や厚生年金保険料の支払い義務が生まれることがあります。
以下では、厚生労働省の「社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について」をもとに、社会保険加入対象者を表にまとめました。
| 正社員・フルタイム労働者 | 加入必須 |
| 1週間の所定労働日数と1日の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の労働者 | 加入必須 |
| 右のすべての要件を満たす非正規労働者 | ・従業員数が51人以上の事業所で勤務
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生ではない |
社会保険料の加入義務が生まれると手取りが減る恐れがあるので、年収が106万円を超えないように働き方を工夫する人もいるようです。
社会保険に加入するメリットとは
社会保険に加入する場合、保険料が会社と自分の折半になるのがうれしいポイント。また、老後の年金が増えたり、傷病手当金や出産手当金を受け取れたりするのもメリットでしょう。「リスクに備えられる」「休業中も保障を受けられる」などは魅力的ですよね。
社会保険制度の概要や加入のメリットについては、「
社会保険とはどんな制度?アルバイトやパートでも加入対象になる?」でも詳しく確認してみてください。
ハタラクティブキャリアアドバイザー
後藤祐介からのアドバイス
年収130万の壁
年収130万円の壁では、年収106万円の壁で社会保険の加入義務が発生しない人も、社会保険上の扶養から外れます。よって、勤務先の社会保険に加入しない場合は、国民健康保険料や国民年金保険料の支払いが必要です。
保険料のぶん手取りが減るため、労働時間や勤務日を調整し、年収130万円未満にする人もいるでしょう。なお、年収106万円の壁には通勤手当や時間外労働手当、賞与などは含まれません。一方、年収130万円の壁にはこれらが含まれる点に注意が必要です。
「フリーター130万円の壁!超えたらいくら払うのか解説」では、年収130万円の壁や社会保険加入のメリット・デメリットを詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
年収201万の壁
年収201万円の壁は、配偶者特別控除と関係します。「配偶者特別控除とは」の表からも分かるように、配偶者の年収が201万5,999円を超えると、給与所得者は配偶者特別控除を受けられません。よって、自分の年収が201万5,999円を超えた場合、夫や妻の所得税や住民税が上がります。
150万は得?働き損しないにはどうするか
給与額面が増えても手取りが減少する「働き損」をしないためには、働き方について考える必要があるでしょう。以下では、働き損をしない働き方について解説します。
自分の生活に合った働き方をする
働き損をしないためには、自分自身の経済状況を考えて働き方を決めましょう。社会保険の扶養から外れるのを避けたいなら「年収130万円」、手取りを減らしたくないなら「年収150万円以上」が一つの目安です。
社会保険の扶養から外れないなら年収130万
社会保険の扶養から外れない働き方を希望する場合、年収106万円もしくは130万円以上にならないように収入を調整するのがおすすめです。前述のように年収106万円を超えた場合、基準を満たしていると勤務先の社会保険に加入しなければなりません。
また、年収130万円以上になると、年収106万円で社会保険の加入対象でなかった場合も、国民健康保険や国民年金への加入が必須です。そのため、社会保険の扶養から外れたくない方は、自身の状況を踏まえて年収106万円もしくは130万円未満に調整しましょう。
手取り額の減少を避けるなら年収150万以上
社会保険の加入による手取り額の減少を避けたい場合は、年収150万円以上を目安に働くことをおすすめします。たとえば、年収130万円以上になり自分で社会保険に加入すると、保険料の負担が必要。年収129万円で社会保険上の扶養から外れない場合と比べて手取り額が下がり、「働き損」といわれる状態になる恐れがあるでしょう。
一方、年収150~160万円程度になれば、社会保険料を差し引いても手取りが増えます。そのため、手取り額を増やしたい場合は、年収150万円を超えるように働くのがポイントです。
年収の壁を気にしない場合は正社員で働くのも一つの手
年収の壁を気にせずに働きたいなら、正社員になるのも一つの手段でしょう。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によると、平均賃金は非正規社員が233,100円であるのに対し、正社員は348,600円。約11万円の差があります。
安定した収入を得たい場合は、正社員としての就職がおすすめです。
正社員で働くメリットとは
正社員として働くメリットの一つは、時給制のパートやアルバイトとは異なり、一定の収入を得られること。賞与や手当、退職金などが支給されることもあります。また、社会保険への加入が必須で保険料が会社と折半な点もメリットといえるでしょう。 国民健康保険と国民年金を自分で支払う場合と比べ、保険料の負担が抑えられると考えられます。正社員になるメリットは、「
正社員になるメリットとは?働く魅力や特長について解説」でも詳しく解説しているので、ご一読ください。
正社員として就職を考えている場合は、就職・転職エージェントのハタラクティブの利用がおすすめです。ハタラクティブでは、知識豊富なキャリアアドバイザーがマンツーマンで求職者に対応。丁寧なヒアリングをもとに、あなたに合った求人をご紹介します。
未経験歓迎の求人も充実しているので、「正社員としての就職は初めて」という人もご安心ください。求人選びから書類選考や面接の対策までサポートします。
年収が150万を超えそうな場合によくあるQ&A
ここでは、年収が150万円を超えそうな場合によくある疑問をQ&A方式にまとめました。「150万円を超えたらどうなる?」「税金をいくら払うの?」など、疑問がある人は参考にしてみてください。
パートが年収150万を超えたら税金はいくら払うの?
社会保険上の扶養から外れる場合、年収150万円を超えるように働くことをおすすめします。150万円以下では、社会保険の負担によって扶養内で働く場合と比べ、手取り額が減少する恐れがあるためです。150~160万円以上を目安に稼ぐと、手取りが増加し将来の年金も増えるでしょう。
年収130万円と150万円には、それぞれメリットがあります。年収を130万円未満に抑えて社会保険上の扶養を継続するか、年収150万円以上で手取りを増やすか、自分に合った働き方を検討してみましょう。
年収の壁を気にせず、パートから正社員就職したいです
パートから正社員就職を目指すことは可能です。「面接や書類選考に不安がある」「自分に合う求人の選び方が分からない」といった人は、就職・転職エージェントのハタラクティブにぜひご相談ください。