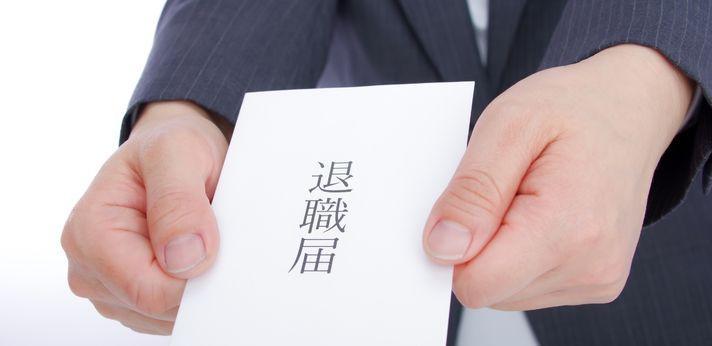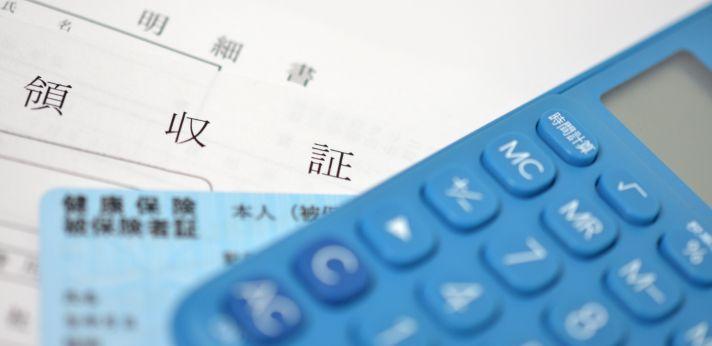退職後に健康保険に入らなくてもいい?加入方法や必要手続きを解説
更新日
公開日
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
退職により前職の社会保険を脱退する場合、国民健康保険に入るのが一般的
「退職後は健康保険に入らなくていい?」とお悩みの方もいるでしょう。しかし、退職して会社の社会保険を脱退するとそれまで使用していた健康保険証が使用できなくなるため、健康保険の切り替え手続きを行う必要があります。
このコラムでは、退職後の健康保険加入に関する選択肢や健康保険に加入しない場合のリスクを解説。国民健康保険へ加入する手順や必要書類も紹介しているので、参考にしてみてください。
退職後に健康保険に入らなくてもいい?
結論から言うと、「健康保険へ入らない」という選択肢はありません。日本に住む人は「国民皆保険制度」により、年齢を問わず健康保険に加入する義務があります。
退職するとこれまで勤めていた会社で加入していた健康保険の被保険者資格がなくなるので、忘れずに健康保険の手続きを行いましょう。
加入が必要な保険
国民が入らなければいけない保険の種類には、社会保険としての「健康保険」と「国民健康保険」があります。以下でそれぞれの詳細を解説しているので、ご一読ください。
健康保険
健康保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合、共済組合が運営している保険です。中小企業では協会けんぽを、大企業では健康保険組合を利用している傾向があるでしょう。
会社勤めの場合、保険料は月々の給与から会社側が天引きされるため、自分で納付手続きをする必要はありません。保険料は、社員本人と会社が折半して支払います。
国民健康保険
国民健康保険とは、原則として社会保険としての健康保険に加入していない国民すべてを対象とした医療保険です。病気や怪我、出産、死亡などの保険事故が発生した場合に必要な給付を行う制度となっています。
国民健康保険は市町村が保険者となって運営を行っており、保険料のすべてを自分で負担しなければなりません。
退職後に健康保険の加入手続きをしなくていい場合もある
退職後すぐに転職する場合は、保険の手続きを自分で行う必要がなくなる可能性があります。被保険者資格を失う退職日翌日からほかの会社の健康保険に加入できる場合は、会社が社会保険の加入手続きを行ってくれるためです。
ただし、退職日から入社日まで期間が空く場合は、数日であっても国民健康保険への加入や前職の健康保険の任意継続、親の健康保険の扶養加入など、何らかの手続きを行う必要があります。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職後に健康保険に入らないリスク
退職後に国民健康保険に入らないと、「医療費が全額自己負担になる」「延滞金が課せられる可能性がある」など、さまざまなリスクがあります。社会保険や国民健康保険に加入していれば、自分で支払う医療費は3割負担ですが、保険に入らないと全額自己負担で支払わなければいけません。医療費が高額になるため、体調不良の際も医療機関に行きにくくなるでしょう。
また、国民健康保険に加入しなくても、退職した翌日から保険料は発生します。国民健康保険料は2年の時効があり、未払いの場合は過去2年分まで遡って請求されるので注意が必要です。先述したように、日本に住む限り国民健康保険への加入は義務のため、市町村によっては加入していないと延滞金が課せられる可能性もあります。
どうしても保険料を支払えない場合は?
退職後にどうしても保険料を支払えない事情がある場合は、すぐに居住地を管轄する市区町村の役場の窓口に相談しましょう。事情によっては減税制度や徴収猶予制度が受けられる可能性があります。ただし、減税や猶予は滞納した分の保険料には適用されないため、注意が必要です。保険料を支払うことが難しい場合は、滞納する前に相談しましょう。
「国民健康保険料は無職だと全額免除される?減免・猶予制度や利用条件を解説」のコラムで減免・猶予ができる制度について解説しているので、あわせてご覧くださいね。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職後に入らないといけない健康保険とは?
退職後に加入する健康保険にはいくつかの選択肢があります。ここでは、退職後に行う健康保険の手続きを紹介するので参考にしてください。
退職後に行う健康保険の手続き
- 国民健康保険に加入する
- 家族の健康保険の扶養に入る
- 勤務していた会社の健康保険の任意継続者になる
1.国民健康保険に加入する
退職後すぐに転職しない場合は、国民健康保険に加入するのが一般的です。保険料は、自治体や前年度の世帯年収、国民健康保険に加入する家族の人数などによって変わります。また、扶養の概念がなく、家族の人数が増える分だけ保険料が高くなる仕組みです。
納付は世帯ごとのため、世帯主に通知が届きます。国民健康保険について詳しく知りたい場合は、お住まいの自治体の健康保険を扱う窓口に問い合わせてみましょう。
国民健康保険のメリットとデメリット
国民健康保険のメリットとして、就業の有無に関わらず誰でも加入できる点が挙げられます。一方で、扶養の概念がないため家族の人数分だけ保険料が高くなる点はデメリットといえるでしょう。傷病手当金や出産手当金などの制度もないため、状況によっては金銭的に厳しくなる可能性があります。
2.家族の健康保険の扶養に入る
退職後の健康保険加入の選択肢として、家族の健康保険の扶養に入ることが挙げられます。家族が社会保険に加入している場合は、扶養に入る選択肢も検討してみてください。
ただし、家族の健康保険の扶養に入るためには年収の要件を満たす必要があります。下記で紹介する要件を確認しておきましょう。
年収制限
家族の健康保険の扶養に入るには、以下の年収要件を満たす必要があります。
- ・被保険者の収入によって生計が維持されている
- ・退職後1年間の見込み収入が130万円未満である(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がいのある方の場合は180万円未満)
- ・被保険者の年間収入の2分の1未満
ただし、「被保険者の年間収入の2分の1未満」の条件を満たしていない場合も、自身の収入が被保険者の収入を上回らなければ扶養に入れる可能性があるようです。詳細は、家族の健康保険事業者に問い合わせてみてください。
被扶養者とみなされる範囲
被扶養者として保険に加入できるのは、三親等以内の親族です。扶養に入りたい人が被保険者の配偶者や子、兄弟姉妹の場合は、同居の有無は問われません。
ただし、別居家族の場合は、前述の年収条件に加え、被保険者からの援助が収入額より少ないことも条件となります。
3.勤務していた会社の健康保険の任意継続者になる
退職後も勤務していた会社の健康保険の被保険者資格を継続できる、「任意継続被保険者制度」という制度があります。制度の概要は、以下のとおりです。
| 任意継続被保険者制度 | 詳細 |
|---|
| 加入要件 | 資格喪失の日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと |
| 任意継続被保険者資格を喪失する理由 | ・任意継続被保険者となってから2年間経ったとき
・被保険者が死亡したとき
・ほかの保険の被保険者になったとき
・期日までに保険料を納付しないとき |
| 保険料 | 全額自己負担 |
任意継続被保険者制度を利用する場合は、原則として退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。正当な理由がなければ、期限を過ぎてから手続きを行うことはできないので、注意が必要です。
任意継続保険のメリットとデメリット
任意継続保険のメリットは、企業に勤めていたときと同じ給付額を受け取れることです。切り替えの書類を特別に提出する必要はないため、国民健康保険と比べて手間も省けるでしょう。
しかし、これまで会社が半分出してくれていた保険料は全額自己負担になります。任意継続できるのは2年間なので、その後は国民健康保険に切り替えるか、再就職先で社会保険に加入する必要があります。
退職後に国民健康保険へ加入する方法と必要書類
勤めていた会社を退職後、転職の予定や任意継続などの予定がない場合は、国民健康保険加入の手続きをできるだけ早めに行いましょう。ここでは、退職後に国民健康保険へ加入する手続きについて順を追って解説します。
1.健康保険証を会社に返却する
会社に勤めていたときに加入していた社会保険の健康保険証は、退職した次の日から使用できなくなるため、速やかに会社に返却してください。退職後に国民健康保険に加入する場合だけでなく、家族の扶養に入る場合も返却は必要です。
誤って退職後に会社の健康保険証を使用した場合、後日健康保険から返還請求を受けることになります。返却ができていなくても、退職後は健康保険証を利用しないよう注意しましょう。
2.会社から健康保険資格喪失証明書を受け取る
一般的に退職後数日から数週間ほどで、会社から「健康保険喪失証明書」が郵送されます。この書類は、国民健康保険に加入する際に職場の健康保険を脱退したことを証明するために必要です。退職日を確認できるものとしては、退職証明書や離職票などの書類でも代用できます。
3.本人確認書類を用意する
退職後に国民健康保険へ加入するには、本人確認書類が必要です。顔写真付きのマイナンバーカードを持っている方は、持参すると手続きがスムーズになります。
マイナンバーカードを持っていない場合は、身分証明書とマイナンバーが分かる書類(個人番号通知カードなど)を用意してください。身分証明書は運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのものが望ましいでしょう。顔写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険資格喪失証明書や年金手帳など、複数の書類が必要です。
すでに国民健康保険の加入者が同一世帯にいる場合は?
国民健康保険は、世帯ごとに保険料が通知される仕組みとなっています。そのため、同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、その保険証も必要になるので忘れないようにしましょう。
4.市区町村の役所で手続きを行う
国民健康保険の加入手続きは、退職後14日以内に行う必要があります。手続きは、居住地を管轄する市区町村役所の健康保険窓口で行ってください。当日は下記の持ち物を忘れずに持参しましょう。
- ・会社の健康保険から脱退した証明書(資格喪失証明書や扶養削除証明書など)
- ・本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
- ・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- ・保険料口座振替用の通帳(キャッシュカードも可)
- ・印鑑
当日に慌てないように、必要なものがすべて揃っているかよく確認しておくのがおすすめです。
手続きを忘れてた…期限を過ぎたらもう間に合わない?
国民健康保険は、加入期限の14日を過ぎても手続きを行うことが可能です。ただし、「退職後、なかなか役所へ出向けず14日を過ぎてしまった」という場合は、保険に入っていない期間分の保険料の納付が必要です。スムーズに加入手続きを行うためにも、早めに手続きを行いましょう。
健康保険や税金、年金などの手続きが一段落したら、転職を考える方もいるでしょう。「ブランクができたけれど転職できるかな…」「1人で転職をするのは不安」という場合は、ハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブは若年層向けの就職・転職エージェントです。マンツーマンのカウンセリングで、現在の悩みや不安、仕事の希望をヒアリングし、一人ひとりの適性に合った求人を紹介します。書類添削や面接対策、1分程度でできる適職診断など、転職活動を全面的にサポートするサービスが無料で利用できるので、お気軽にご利用ください。
社会保険に関するお悩みQ&A
ここでは、社会保険に関する疑問をQ&A方式でまとめました。国民健康保険への未加入がバレるかについてや、健康保険以外の手続きについても解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
社会保険とは、健康保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の総称です。生活を守るために設けられた公的保険で、会社に属し、一定の条件を満たす人が加入できます。保険料を会社と折半できるのが特徴です。厚生年金は被保険者が支払う金額に会社が負担する金額が上乗せされるので、国民年金に比べて将来受け取れる額が高くなります。
詳しくは、「社会保険料の計算はどのようにして行う?正社員とパートとの違いも解説」のコラムもご覧ください。
バレなければ退職後に国民健康保険に入らなくていい?
日本は国民皆保険制度を採用しているため、退職後も健康保険に加入する必要があります。未加入だと病院での自己負担額が増えたり、加入後に過去の保険料を請求されたりするリスクがあるでしょう。
このコラムの「退職後に入らないといけない健康保険とは?」で述べているように、国民健康保険に入らない場合は「家族が加入している健康保険の扶養に入る」「任意継続被保険者制度を利用する」といった選択肢があります。よく確認してから自分に合った制度を検討しましょう。
国民健康保険に、扶養という考え方は存在しません。被扶養者が社会保険から国民健康保険に切り替えれば、それまで扶養に入っていた家族もそれぞれ国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の加入方法については、このコラムの「退職後に国民健康保険へ加入する方法と必要書類」を確認してみてください。
退職後、年内に再就職をしない場合は、税金を納めるための確定申告を忘れずに行いましょう。退職後の税金や健康保険の手続きについては、「仕事を辞めたらすることは?もらえるお金や手続きなど退職後の流れを解説!」のコラムでも確認が可能です。
再就職まで期間が空いてしまうと、保険や税金の手続きが必要になるだけでなく、ブランクができてしまいます。早期の再就職を目指したいという方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。