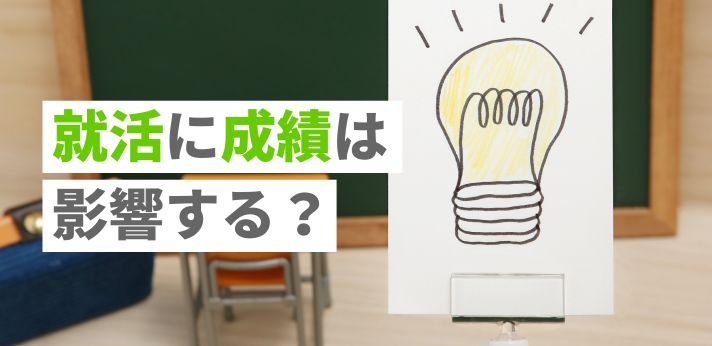グループディスカッションでよく出題されるテーマとは?対策方法もご紹介
グループディスカッションにはさまざまなテーマがあり、どう発言すべきか悩む就活生も多いでしょう。グループディスカッションには4つの形式があり、出題されるテーマの傾向もそれぞれで違います。当コラムでは、グループディスカッションの形式別に、出題されやすいテーマ例や具体的な対策などをまとめています。グループディスカッションに苦手意識がある場合は、このページの内容を参考にしっかり対策しておきましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断

就職でお困りではありませんか?
当てはまるお悩みを1つ選んでください
グループディスカッションとは
グループディスカッションとは、企業が採用試験で用いる選考方法の一種です。概ね4人~8人の参加者を1つのグループとして、テーマに関する意見交換や議論の経過、制限時間内にどんな結論を出すのかなどを観察します。一度に多くの応募者を選考できる、応募者が組織内でどんな考え方や動き方をするのか判断しやすいなどの利点から、大企業を中心に多くの採用試験に導入されているようです。また、就活業界では、頭文字を取ってGDと呼ばれることもあります。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
グループディスカッションの4つの種類と扱うテーマ
グループディスカッションは、種類ごとに違った特徴があり、企業がチェックしているポイントもそれぞれ異なります。
自由討論型
「理想の社会人とは?」など、答えの出ないテーマについて自由に討論させるタイプ。企業側は、社風に合った価値観を持った人物かどうか、議論をコントロールして結論まで導くファシリテーション力などをチェックしているようです。よく出題されるテーマとしては、「働きやすい企業とは?」「救急車が有料化されたらどんな問題が起こるか」「童話『うさぎとかめ』のその後のストーリーを考える」「10年後になくなる職業を考える」などがあります。
自由討論型のディスカッションは、話しやすいテーマが選ばれることが多く、議論が活発化しやすい反面、抽象的な議論に終始して結論に至らないまま終了してしまうケースもあるようです。まずはテーマの定義づけを行い、時間内に結論までたどり着くことが大切になります。自由討論型のグループディスカッションに参加する際は、以下の3点にも注意しましょう。
・採用を勝ち取るには活発な議論が不可欠のため、グループのメンバー全員で合格するという意識で、協力して話し合いを進める
・企業の社風を踏まえて、求められている人物像に適った議論を展開する
・抽象的で散漫な内容のディスカッションにならないよう、具体的な経験に裏打ちされた発言を心がける
ディベート型
「日本にカジノは必要か?」など、賛否のあるテーマについて賛成派と反対派の2グループに分かれて討論するタイプ。企業側は、相手の主張にすぐ反応して反論できる瞬発力や、参加者が相手を納得させられる論理的な主張を展開できているかなどをチェックしているようです。よく出題されるテーマには、「年功主義か成果主義か」「少年法は存続するべきか、廃止するべきか」「国会議員の育児休暇に賛成か、反対か」「旅行に行くなら海外か、国内か」などがあります。
ディベート型のディスカッションでは、全員に発言の機会が回ってくるとは限りません。次々と発言される意見を聞くだけになってしまわないよう、相手方の意見をしっかり聞き、素早く反論を用意する必要があります。また、味方(派閥内)の意見を後押しする、弁護するなどして協力する姿勢もアピールしましょう。ディベート型のディスカッションに参加する際の注意点は以下の3つです。
・相手側の発言を予想し、いつでも反対意見を出せるように準備しておく
・あくまで冷静に、論理的に反論する(喧嘩腰に相手方を攻撃しない)
・ひとりで相手方の意見を論破しようとしない
選択型
「東京に来ている留学生を旅行に連れて行くなら北海道がいいか、京都がいいか」など、提示された複数の選択肢の中から1つを選ぶために討論するタイプ。企業側は、選択のために何を評価し何を切り捨てたのか、参加者の論理的な思考力や判断力、価値観などをチェックしているようです。ほかによく出題されるテーマは、「家族、恋人、仕事、友人、お金に優先順位をつけるとしたら」「このメンバーの中でひとりだけ合格するとしたら誰か」「火星に4人のメンバーと移住することになった。次の中から誰を連れて行くか選べ。医師(男)、弁護士(女)、野球選手(男)、ピアニスト(女)、大学生(男)、料理人(女)、軍人(男)」「オリンピックの開催地を選ぶとしたら次の都市のどこにするか。バンクーバー、大阪、ブエノスアイレス、シカゴ、ニューデリー、アブダビ、ケープタウン」などがあります。
選択型のディスカッションは、選択肢を評価するための基準を設定しておかないとただの水掛け論に終わってしまう可能性もあるので注意しましょう。中身のある議論をするためには、論理的に話し合いを進めるための評価基準が不可欠になります。そのほかの注意点は以下の3つです。
・議論の前提は、なるべく広く定義づけておく
・評価基準が複数ある場合は、評価基準間の優先順位をつけておく
・選択型のディスカッションでは、司会役の力量がもっとも問われる
グループディスカッションのテーマ例
たとえば、「東京に来ている留学生を旅行に連れて行くなら北海道がいいか、京都がいいか」のテーマでグループディスカッションを行う場合、以下のように前提の定義に幅を持たせておけば議論が深まりやすくなります。
・留学生の出身国は特定しない
・北海道や京都の市区町村などエリアは指定せず、全体で考える
・旅の日数は細かく決めず、1週間未満という大雑把な枠だけを決める
さらに、「留学生に喜んでもらえる旅の条件」といった選択のための評価基準を定めます。評価基準が複数ある場合は、どちらの条件をより優先させるかまで決めておきましょう。評価基準を定めておくことで、たとえば「日本文化に親しむ体験ができる」と「東京では味わえない日本の食文化を堪能できる」の2つがあった場合、前者を優先させることができます。また、評価基準に則して選択肢それぞれのメリットとデメリットを洗い出し、それらを根拠に議論を深めることで、参加者全員が納得する結論を導きやすくなるでしょう。
メンバーの価値観によって意見がはっきり分かれる選択型のディスカッションでは、司会役の力量がもっとも問われます。ファシリテーション力をしっかりアピールしておきたいと考えるなら、司会役を引き受けてもいいでしょう。司会役として参加者全員の納得する結論まで導くことができれば、高い評価が期待できます。
課題解決型
「花粉症患者を減らすにはどうすればよいか」など、提示された問題についての解決策を討論し制限時間内に結論を出して発表するタイプ。企業側は、参加者の論理的な思考力、独創性などをチェックしているようです。よく出題されるテーマは、「若者の投票率を上げるにはどうしたらよいか」「ボールペンを10万円で売るにはどうしたらよいか」「下町の商店街を発展させるにはどうしたらよいか」「シャンプーの国内市場を2倍にするにはどうしたらよいか」などがあるようです。
課題解決型のディスカッションでは、結論よりそこまでのプロセスが重視される傾向があります。議論の前提となるテーマの定義をメンバー間で共有することからはじめて、実現可能な結論へと1つずつステップを着実に踏みながら議論を進めましょう。主な注意点は以下の3つです。
・課題を定義付け、現状を把握する
・課題を解決して、最終的に何を目指すのかはっきりさせる
・アイデアを出す段階では実現可能性は考えずに、出せるアイデアはすべて出す
グループディスカッションのテーマ例
たとえば、「花粉症患者を減らすにはどうすればよいか」というテーマでグループディスカッションを行う場合、まずは以下のように共通認識をはっきりさせ、問題点を洗い出しておきましょう。
定義:花粉症患者とは、スギやヒノキの花粉が原因のアレルギー症状に苦しむ人たち
現状:日本人の花粉症の有病率は現在約30%。1998年からほぼ1.5倍に増加している
課題①:戦後盛んに植林されたスギが、活発に花粉を飛散させる時期を迎えている
課題②:花粉の飛散量の増加と大気汚染が相まって、花粉症患者の増加を招いている
課題③:子どもの花粉症患者も成人と変わらない割合で増加している
最終目標:1998年当時の水準まで花粉症患者数を減らす
問題点を洗い出したあとは、目標を実現するためのアイデアを出し合います。このとき、はじめから実現の可能性に縛られていると議論はなかなか深まりません。一見無理と思えるアイデアから良い案が生まれることもあるので、まずは活発に意見を出し合って発想力もアピールしていきましょう。
積極性をアピールするには当事者意識を持つことがポイント
活発に意見を出すためには課題を解決するためのアイデアも大切ですが、当事者意識を持つことで積極性をアピールできるかもしれません。当事者意識とは、「課題を自分が解決する意識を持つこと」です。詳しくは、「当事者意識とは?積極的に仕事に取り組める人材の特徴と主体性の持たせ方」にまとめているので、チェックしてみてください。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
グループディスカッションの基本的な流れ
以下は、すべての型に共通する、ディスカッションの基本的な流れです。
1. 司会、タイムキーパー、書記の役割を分担する
一般のメンバーとしても十分議論に貢献できるので、まだグループディスカッションに慣れないうちは、どのポジションも安易に引き受けない方がいいでしょう。企業によっては、役割に徹しているだけでは評価されないこともあります。役割を果たすことでしっかり議論に貢献できる、役割を果たしながら議論にも参加していけるという自信がつくまで、無理に役割を引き受ける必要はありません。グループディスカッションにおける役割については、「グループディスカッションを行う意味とは?進め方や対策のコツをご紹介」にて詳しくまとめているので、あわせてご覧ください。
2. 時間配分を決める
グループディスカッションでは、発表の有無に関わりなく、まずは結論までたどり着くことが大切になります。テーマの定義づけや意見の出し合い、意見の絞り込み、まとめ、発表準備などの項目ごとに時間配分を決めて、有効に時間を使いましょう。
3. テーマを定義づける
語句の定義や出題の意図、最終目標などをメンバー間で共有することも大切です。
4. 活発な議論を行う
高評価を得るためには、活発な議論を展開することが大前提になります。ディスカッションのメンバーはライバルではなくお互いが協力者だということを忘れず、積極的に話し合いに参加しましょう。
5. 出揃った意見の絞り込みやまとめ、発表の準備をする
グループ内で出し合った意見をまとめ、結論を出します。発表では、結論に至った根拠を具体的に説明することが大切です。企業の採用担当者や社員に伝わりやすいように発表内容をまとめましょう。
グループディスカッションによく出題されるテーマへの対策は必ずしておこう
グループディスカッションによく出題されるテーマについては、自分の意見を整理しておきましょう。事前の準備を重ねれば自信を持ってディスカッションに参加できるうえに、気になるデータなどを調べておくことで説得力のある持論を展開することも可能です。
参加者全員で合格を目指す気持ちで参加しよう
議論を深めるためには参加者がテーマに関する認識を共有することが不可欠です。参加者は敵ではなく、お互いが協力者だという意識で全員での合格を目指しましょう。特に、人の意見を聞かず自分の意見を押し通そうとする、ルールを無視した発言を繰り返すなどの行為は厳禁。ディスカッションの場を壊すクラッシャーとして、評価の対象から外されてしまう可能性があります。話しかけるときは相手の名前を呼ぶ、会話の最中は相手の目を見るなどの基本的なコミュニケーションスキルも大切にしながら、参加者全員での合格を目指す気持ちで参加しましょう。コミュニケーションスキルに自信がない方は、「コミュニケーション能力とは?スキルを鍛える具体的な方法をご紹介!」を参考にしてみてください。
もし、グループディスカッションでの振る舞いに迷ったら、「どうしたら貢献できるか」を考えてみましょう。たとえば、発言の少ない参加者に意見を促す、ずれてしまった論点を修正する、クラッシャーも無視せず全員でディスカッションを進めようとするなどの姿勢は、グループディスカッションへの貢献度から高く評価される傾向にあるようです。グループディスカッションで採用担当者が見ているのは、参加者が討論にどう貢献しているかの1点だといっても過言ではありません。細かな判断に迷ったら、「グループディスカッションに貢献するために今するべきことは何か」を基準に行動しましょう。
グループディスカッションに不安がある方は、ぜひハタラクティブまでご相談ください。ハタラクティブは、20代を中心とした若者向けの就職・転職支援サービス。「グループディスカッションは苦手」、「面接対策がうまく進まない」など、就活生のお悩みにプロの就職アドバイザーがマンツーマンで対応しています。客観的な立場からのアドバイスを受けてみたい、今度こそ面接の壁を突破したいという方、ぜひ一度ハタラクティブまでお気軽にご相談ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?
マーケティングアシスタント
東京都
年収 315万円~360万円
正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!
ライター・取材担当
東京都
年収 315万円~360万円
未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?
営業
東京都
年収 328万円~374万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆
ルート営業
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…
年収 228万円~365万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「選考対策」についての記事一覧
- 「就職・転職のノウハウ」についての記事一覧
- 「就職ノウハウ」についての記事一覧
- グループディスカッションでよく出題されるテーマとは?対策方法もご紹介