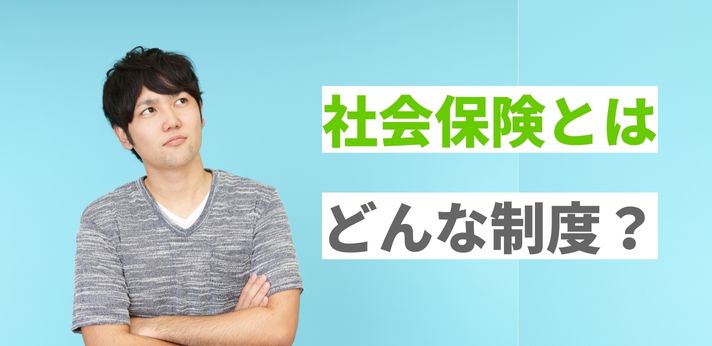有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説
更新日
公開日
有給休暇は条件を満たしたすべての労働者に付与/使用権利がある休暇のこと
労働者の正当な権利である有給休暇ですが、取得しにくいケースも多く、取れない雰囲気がある会社も少なくないようです。有給休暇は義務化されており、取得させないのは違法の可能性があります。このコラムでは、有給休暇の概要と対象のほか、違法に当たる事例や義務化についてもまとめました。有給休暇が取得できないケースに直面した際には、有給休暇が認められない理由や対処法を確認しましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
厚生労働省
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
有給休暇が取れない会社を訴えることはできる?
義務化された有給休暇を使用者である会社の都合で取れないのは違法に当たり、理由によっては訴えることも可能です。しかし、訴えると今後の働き方にも影響が出る可能性が高いため、すぐに訴訟を起こすのではなく会社の管理部門や労働基準監督署など、手順に沿って対応する必要があります。
有給休暇を取らせないのはパワハラなのか
基本的に、有給休暇の申し出を会社側が拒否することは禁じられているため、正当な理由なく認めない・取らせない対応はパワハラに当たる可能性があります。有給休暇の付与と取得は法で定められた労働者の権利であり、企業や経営者の考えで変更できません。
パワハラの被害にあった場合は、証拠を集め弁護士に相談し解決へ導いてもらいましょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
有給休暇とは
有給休暇とは「年次有給休暇」のことであり、休みながらも賃金が支払われるのが特徴です。労働基準法第39条で定められた労働者の権利で、正社員に限らず契約社員やパート・アルバイトなどの非正規社員にも付与が義務づけられています。
勤続年数と付与される有給休暇日数は、以下の表を参考にしてください。
| 勤続年数 | 有給休暇日数 |
|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年以上 | 20日 |
一般労働者(正規社員)は全労働日の8割以上出社しているなど、一定の条件を満たせば入社6ヶ月後から付与されます。
労働基準法の定義
労働基準法第39条の定義では、有給休暇について以下のように示されています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
取得に際しては雇用形態の限定はなく、正社員のほかパートタイマーやアルバイト店員でも適用が可能です。非正規の週間労働日数と勤務期間に応じた有給日数は、以下のとおりです。
| 週間労働日 | 年間労働日 | 勤務期間 |
|---|
| 6ヶ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.6年 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
非正規職員で週の所定労働時間が30時間未満の場合、週の所定労働日数と勤続年数によって有給休暇の日数が変化するので注意しましょう。
有給休暇の買取や繰越は可能?
有給休暇の有効期限は付与から2年間であり、年内に使用しなくても翌年いっぱい繰り越されます。使用時は古い日数分から消化されるので「2020年の付与分から使用され2019年の分は消滅した」といったことは起きません。
なお、有給休暇の買取に関しては原則として労働基準法では認められませんが、以下の条件で実施する企業もあるようです。
- ・会社独自で設定する有給休暇
・時効を迎える有給休暇
・退職で無効になる有給休暇
有給休暇はあくまでも「労働者が休むための制度」なので、最初から買取目的での使用はできません。買取に応じるかどうかは両者の合意が必要であり、買取を拒否されても違法にはならず企業側が一方的に買い取ることも不可能です。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
有給に関して違法に当たる例
会社より当たり前のように有給休暇がないと説明されたり取得を断られたりした場合は、違法に当たる可能性があります。有給休暇は従業員の権利であり、使用者である企業は休暇の申請を受理しなくてはなりません。
労働基準法の違反に当たる例
- 上司から「この会社に有給休暇はない」といわれた
- 有給休暇を取る理由によっては取得させない
- 有給休暇を取得することが人事評価に影響する
例1:上司から「この会社に有給休暇はない」といわれた
有給休暇について定めているのは使用者である会社ではなく労働基準法であり、「有給休暇がない」発言は明らかに違法といえます。上司のみならず企業全体で有給休暇を認めない場合は、外部の労働基準監督署や弁護士に相談すると良いでしょう。
例2:有給休暇を取る理由によっては取得させない
世間話で有給休暇を取る理由を聞くのは問題ありませんが、内容によって取得させない判断を取られるのは問題です。例えば、従業員が「旅行に行くために有給休暇を取りたい」と申請したにも関わらず、業務に支障がないのに取得を許可されないケースは違法行為に当たります。
有給休暇の取得は労働者の権利であり、使用者である企業は従業員からの休暇申請を正当な理由なく拒否してはいけません。もし取得を拒まれた場合は違法行為に当たるため、会社の管理部門や労働基準監督署など信頼できる機関に相談しましょう。
有給の理由や目的を聞くのは違法?
有給休暇の日の過ごし方について、上司や同僚から世間話として尋ねられること自体は問題ありませんが、使用者がその答えを理由にして従業員の有給休暇取得を制限したり、影響を与えたりすることは問題です。有給休暇は従業員の権利であり、取得の理由は問われるべきではありません。もちろん、答えるか否かは従業員の自由です。
例3:有給休暇を取得することが人事評価に影響する
有給休暇の取得日数が多いことを理由に、人事評価で不当な扱いをするのは違法です。先述したように、有給休暇は会社ではなく法律で定められている労働者の権利。付与されている範囲内であれば、いつ・どのように・どのくらい使用するかは労働者の自由です。
そのため、「今年に入って有給を多く使っているから評価を下げる」といった行為は違法に該当するでしょう。有給の使用日を制限したり、取得について圧力をかけるような言動も違法に当たる可能性があります。ただし、「有給を使いすぎて通常業務が滞り成果につながらなかった」など、有給休暇の取得が間接的に評価の要因になった場合は、違法にはなりません。
「取れない」が解消する?「有給休暇の義務化」とは
有給休暇の義務化は「働き方改革関連法案」により2019年4月1日に施行され、企業の規模に関わらずすべての企業が対象となっています。制定された目的は有給休暇の取得率の改善のためであり、年間10日以上の有給休暇を付与されるすべての労働者に対して、年間5日の取得(時期指定)を義務としています。
労働者が自主的に年間5日以上の有給休暇を取得していれば、追加の必要はありません。しかし、自主的な取得が3日の場合は、5日に達するぶん(2日)を会社が労働者の希望に沿った時期指定のうえで取得させる必要があります。
法令で定められているにも関わらず年間5日の有給休暇を認めない場合は、企業に対して労働者1人あたり30万円以下の罰金が命じられます。年間5日以上の有給休暇が取れない労働者が5人いるなら最大で150万円、10人なら最大で300万円の罰金が課せられることに。なお、労働者側に罰則や刑事罰はありません。
有給休暇が取れない理由
有給休暇が取得できない主な理由は、「人手不足」と「忙しさ」の2つです。なかには、周囲に有給休暇を取る人が居なくて取りづらかったり、上司から有給休暇を取得すると評価に影響するといわれたりするケースもあるようです。しかし、いずれの理由も有給休暇を取れない正当な理由にはなりません。
厚生労働省の調査によると、令和4年の有給取得率は62.1%と過去最高の値でした。
令和4年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)をみると、労働者1人平均は17.6日(令和4年調査17.6日)、このうち労働者が取得した日数は10.9日(同10.3日)で、取得率は62.1%(同58.3%)となっており、昭和59年以降過去最高となっています。
労働者1人あたりの有給休暇日数は17.6日で、そのうち10.9日が取得されている状況です。
有給が取りやすい仕事
有給休暇の取りやすさは、企業規模や業界によって状況が異なります。有給休暇の取りやすい企業の特徴や業種の傾向を紹介するので、仕事選びの参考にしてください。
企業規模が大きい
人材が潤っており社内制度が整っている企業ほど、有給休暇の取得率は高くなります。また、有名企業は知名度が高いゆえに、勤務環境や制度がずさんだと悪評が広まる可能性があるため、法令遵守を徹底する企業が多いでしょう。
中小企業は有給休暇を取りにくい傾向
企業規模が大きいほど勤務環境が整備されているため、有給休暇の取得がしやすいといわれています。しかし、その一方で、中小企業では人手不足や業務量の多さから希望日に休みが取れないケースが多くなっています。
| 企業規模 | 有給取得率 |
|---|
| 1,000人以上 | 0.656 |
| 300~999人 | 61.8% |
| 100~299人 | 62.1% |
| 30~99人 | 57.1% |
女性役員がいる
女性が活躍する企業は産休や育休といったライフイベントに合わせた休暇制度が整っている傾向があります。会社でもワークライフバランスを重視している可能性が高く、有給休暇の取得にも積極的と予想できます。
業界の傾向
厚生労働省が令和5年に実施した就労条件調査によると、有給休暇の取得率が高い業界と低い業界の順位は下表のとおりです。有給の取りやすさを確認する目安にしてみてください。
| 業種 | 年間付与日数のうち取得日数 | 取得率 |
|---|
| 複合サービス事業 | 19.3日のうち取得日14.4日 | 74.8% |
| 電気/ガス/熱供給/水道業 | 19.6日のうち取得日14.4日 | 73.7% |
| 製造業 | 18.7日のうち取得日12.3日 | 65.8% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 16.4日のうち取得日10.8日 | 65.4% |
| 情報通信業 | 18.6日のうち取得日11.8日 | 63.5% |
| 業種 | 年間付与日数のうち取得日数 | 取得率 |
|---|
| 宿泊業/飲食サービス業 | 13.6日のうち取得日6.7日 | 49.1% |
| 教育/学習支援業 | 17.9日のうち取得日9.8日 | 54.4% |
| 卸売業/小売業 | 17.5日のうち取得日9.7日 | 55.5% |
| 建設業 | 17.8日のうち取得日10.3日 | 57.5% |
| 生活関連サービス業/娯楽業 | 16.2日のうち取得日10.1日 | 62.3% |
違法ではなくても有給が取れないケースもある?
有給休暇は労働者が求めるタイミングで使用するのが望ましいですが、希望日に取れないケースもあります。そのため、希望のタイミングで取得できないときは予定の調節が必要です。有給休暇が取得できないケースについて確認しておきましょう。
有給休暇を申請しても認められない可能性が高いのは、以下の3つのケースです。
- ・長期休暇を突然申請する
・業務に必須の研修が予定されている
・業務の代替者がいない
有給取得への拒否は原則として認められないため従業員が事前に有給休暇を取得する日を伝えておけば許可されます。ただし、有給休暇を承認すると事業に著しく支障が出るときに限り、企業側は「時季変更権」を主張して取得時期を変更できます。時季変更権は労働基準法に定められており、事業の正常な運営を妨げる場合において使用者側が行使できる権利です。
ただし、時季変更権はあくまでも「変更」を前提とした権利です。「業務が落ち着いたら、そのうち」などの曖昧な回答は有給休暇の拒否と捉えられ、違法となる可能性があります。
有給休暇が取れないときの3つの対処法
有給休暇が認められないときは、まず正当な理由での不認可かを確認します。不当な理由での拒否の可能性があれば、上司に相談しましょう。解決に至らない場合は、転職も選択肢に入ります。
1.正当な理由での不認可かを確認する
有給休暇が取れないときは、労働者の権利であるうえでなぜ認められないのかを確認しましょう。業務上やむを得ず認められない場合、取得できる明確な日程を確認する必要があります。
「人がいない」など、業務への支障を理由にして時季変更権を利用した不認可であれば問題ありませんが、正当な理由のない拒否は法に触れる可能性があるでしょう。納得いかない理由の場合には、上司よりも上の役職や管理部門への相談が必要です。
2.相談する
直属の上司に確認しても納得できる回答が得られなければ、さらに上の管理者に相談することも検討しましょう。相談先は、以下の順番で進めてください。
- 1.会社の労務や総務などの管理部門
2.労働基準監督署
3.労働組合
4.弁護士
まず相談すべきなのは、会社の労務や総務といった管理部門です。使用者として制度が整っていれば、速やかに解決するでしょう。会社で解決しなければ、会社の管轄にある労働基準監督署に相談します。通報内容次第では取締りや訪問・立入検査も実施することが可能です。ただし、対象となるのは「法律に明確に違反している」場合のみで、会社と従業員の個別的トラブルには介入できず、事例によっては対処できない可能性もあります。
労働基準監督署でも解決しなければ、所属する労働組合に相談しましょう。労働組合は労働者の権利・地位を守るための団体です。まずは会社に労働組合があるかを確認し、なければ必要に応じて個人で加入できる外部ユニオンをご活用ください。最終的に解決しない場合は、弁護士への相談が必要です。従業員が訴訟に勝てば、会社に罰金が課せられるだけではなく損害賠償の請求もできます。
3.転職する
労働基準監督署からの指導や労働組合からの要求が入ったにも関わらず、状況が変わらないときは、環境を変えるために転職を考えても良いでしょう。指導が入っても対応を変えない職場では、今後も有給休暇が取れない可能性が高いと考えられます。
退職時に有給休暇を使う方法
良識的な企業であれば、退職前に残っている有給休暇をすべて取得できるよう配慮してくれます。退職時にトラブルなく有給休暇を消化するには、以下の3点に注意しましょう。
・残りの有給日数を正しく把握する
・できるだけ早く伝える
・引き継ぎに影響のないスケジュールを組む
万が一直属の上司が退職時の有給休暇を認めなければ、人事や総務に相談するのがおすすめです。退職時の有給休暇の扱いに関しては「
退職前に有給は消化できる?取得する際のポイントや拒否された場合の対処法」で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
雇用条件や勤務環境を理由に転職をする場合、転職先でも同じトラブルに合わないよう、有給休暇の取り扱いについての確認が大切です。しかし、個人で集められる企業情報は限られており、入社してから気づくことも多いでしょう。
実際の勤務条件や休日休暇の取得状況を知りたいなら、転職エージェントのハタラクティブがおすすめです。ハタラクティブでは、ご紹介する企業に訪問調査を行っており、求人情報と実際の条件・環境に相違がないか確認しています。社内の雰囲気や社員の傾向など「リアルな情報」を把握しているため、あなたの性格や適性に合う求人をご紹介できます。
転職サポートも充実しており、自己分析や企業選びの諸段階から内定まで、専任アドバイザーが親身にお手伝いいたします。円満退職のアドバイスも可能ですので、「在職中で忙しくて転職活動の時間がない、退職の意向を伝えづらい」などのお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。
有給休暇が取れない場合に関するFAQ
有給休暇は労働者に与えられた正当な権利ですが、まだまだ取得しにくい会社もあるのが現状です。有給休暇についてよくある質問を3つ紹介します。
有給休暇を取得することによって不利益な扱いを受けない?
労働基準法により、企業側は有給休暇を取得する従業員に対して不利益な扱いをしてはいけないと定められています。不当な扱いを受けた場合は会社の労務や総務に相談しましょう。個人の力だけでは問題解決が難しいケースでは、弁護士への相談も必要です。弁護士の介入で会社側が要求に応じてくれる可能性は高くなります。
参照元
e-gov法令検索
労働基準法第136条
非正規のアルバイトやパートでも、一定の基準を満たせば有給休暇が付与されます。
非正規職員には付与されないと勘違いしている会社もありますが、有給休暇は法律で定められた労働者の権利です。週の所定労働日数や勤続年数によってもらえる有給休暇数が異なるため、自分が何日付与されるのか確認しましょう。
有給休暇を取得させてくれない場合、訴えることも可能?
不当な理由により有給を取得させてくれない企業は、訴えられます。
有給休暇は法律で決められた権利であり、企業側が取得を拒むことは違法行為です。違法行為が発覚した場合、従業員1人につき30万円の罰金が課せられるうえ、労働者は弁護士を雇い損害賠償の請求もできます。ただし、業務に支障がでるケースでは「時季変更権」により申請が却下される可能性もあるようです。「時季変更権」についてはこのコラムの「違法ではなくても有給が取れないケースもある?」をご確認ください。