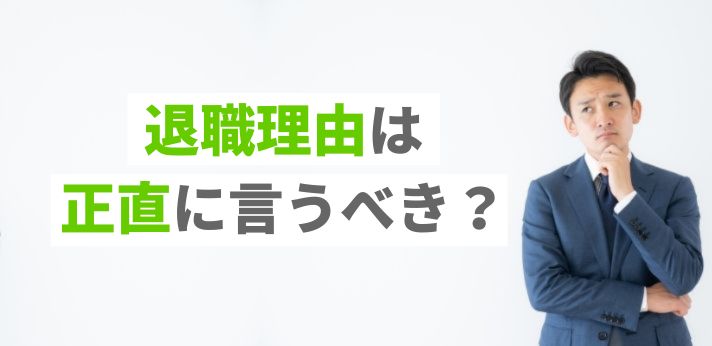退職理由の伝え方は?本音は言わない方がいい?ポイントと注意点を解説退職理由の伝え方は?本音は言わない方がいい?ポイントと注意点を解説
更新日
公開日
退職理由で本音を言わないのも、円満に退職する方法の一つ
「退職理由は本音を言わない方がいい?」と悩む方は多いでしょう。会社や仕事への不満などが退職理由の場合は、本音を言わない方が望ましいケースもあるようです。このコラムでは、本音を隠すのが望ましい退職理由をご紹介。また、本音を隠すメリットとデメリットや、退職理由を伝える際のポイントや注意点についてもまとめました。円満に仕事を辞めたい方は、退職理由を考えるための参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
退職理由は本音を言わなくていい?
「退職理由は本音で伝えなければならない?」と不安に感じている方もいるでしょう。本当の理由で退職するのが難しい場合は、嘘の理由を伝えるのも方法の一つです。退職理由によっては相手に不快感を抱かせてしまったり、本気度が伝わらず引き止められたりする可能性があります。本音を隠して退職の意思を伝えた方が、円満に退職できるケースもあるでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
経験者に聞いた退職の理由
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
また、男性は「思っていた仕事内容と違った」、女性は「結婚・出産などのライフステージの変化」を理由として挙げる方が多く、男女差も見られるようです。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職理由で本音を言わない方が望ましいケース
本音を言わない方が望ましい退職理由とは、どのようなものなのでしょうか。ここでは、本音を隠すべき退職理由を紹介します。自分の状況と照らし合わせ、判断の参考にしてみてください。
会社の待遇や環境に不満がある場合
会社の待遇や環境に不満がある場合は、本音を隠すのが望ましいでしょう。会社への不満の具体例として、以下が挙げられます。
- ・業務量と給与が釣り合っていない
- ・残業が多く身体的な負担が大きい
- ・人間関係が悪く仕事をしづらい
- ・社風や経営方針に馴染めない
- ・会社の将来性に不安を感じる
退職理由として上記のような不満を伝えると「自分も同じ環境で働いているのに無責任だ」と思われる可能性があるようです。周囲の協力を得ながら円満に退職するためには、会社への不満は伝えないのが望ましいでしょう。
仕事内容にやりがいを感じない場合
仕事内容にやりがいを感じない場合も、本音を避けた方が円満に退職できるでしょう。
- ・業務内容に興味を持てずやる気が出ない
- ・ノルマを達成するのが大変でモチベーションが維持できない
- ・仕事が単調で自分の成長につながっていない
上記を退職理由として伝えると「経験を積むことで面白みが分かるはず」と引き止められてしまう可能性があるようです。強く引き止められると退職の意思そのものが揺らぐこともあるため、正直に理由を話さない方が得策といえるでしょう。
競合他社に転職が決まっている場合
転職を退職理由として伝えるのは問題ありませんが、競合他社への転職が決まっている場合は避けるのが望ましいでしょう。退職が認められなかったり、他社への情報漏洩を警戒され気まずくなったりする可能性があります。退職理由を説明する際は、転職先の詳細は伝えないのが無難です。
退職理由で本音を言わないメリット
退職理由で本音を言わないメリットとして「引き止められる可能性が低い」「退職手続きがスムーズに進みやすい」の2点が挙げられます。
引き止められる可能性が低い
嘘の退職理由を述べることで、引き止められる可能性が低くなります。たとえば、結婚や体調不良などの個人的な理由であれば、会社側も引き止めにくいものです。退職理由が引き止められやすい内容の場合は、本音ではなく別の理由を伝えるのも一つの選択肢でしょう。
退職手続きがスムーズに進む
仕事を辞めるために本音を隠した場合、退職手続きがスムーズに進む可能性があります。上司や同僚に納得してもらえると周囲の協力が得やすくなり、書類のやり取りや業務の引き継ぎといった退職手続きを進めやすくなるでしょう。
また、角が立ちにくい退職理由には、退社後も会社と良好な関係を保てるというメリットも。退職後の公的手続きや転職先の入社手続きなどで、前職の会社に書類の発行を依頼する場合もあります。良い雰囲気のまま会社を辞めることで、退職後も気後れすることなくやりとりができる点は大きなメリットでしょう。
退職後の手続きで必要な書類とは?
「雇用保険被保険者証」や「源泉徴収票」「離職票」などは退職後の公的手続きや転職手続きで必要なので、忘れずに受け取りましょう。なお、「源泉徴収票」と「離職票」は退職日以降に発行されるため、郵送で受け取ります。
「
退職後の手続きは何をする?期限や順番、必要書類を分かりやすく解説!」のコラムでは、退職時の手続きや公的手続きの方法や必要書類を紹介しているので参考にしてみてください。
退職理由で本音を言わないデメリット
本音を隠した退職理由のデメリットとして、「つじつまを合わせるのに気を使う」「本当のことをいえずにストレスが溜まる」の2点が挙げられます。以下で解説しているので、退職を切り出す前に確認しておきましょう。
つじつまを合わせるために気を使う必要がある
本音を隠した退職理由の場合、つじつまを合わせるために気を使う必要があります。会社の規定や手続きに要する期間にもよりますが、申し出から実際の退職日までは1ヶ月程度かかるのが一般的です。その場しのぎの嘘をついた結果、途中でバレてしまうと気まずい雰囲気の中で退職手続きを進めなければいけません。
退職するまでは、矛盾を生まないように「全員に同じ理由を話す」「必要以上のことを話さない」などの注意が必要なことを理解しておきましょう。
本音を言えないことにストレスを感じる
退職の際に本音を隠すことで、事実を話せないストレスを感じる人もいるようです。嘘をつき続けることに、罪悪感を抱いてしまう場合も。また、周囲の人や会社への不満を話せず、問題が解決しないまま会社を辞めることに釈然としない人もいるでしょう。円満に退職するためには、ある程度割り切って考えることが大切です。
本音を隠しやすい退職理由と例文
「本当の退職理由は伝えにくいけど、嘘がバレないか不安」という方もいるでしょう。ここでは、退職の際に本音を隠しやすい理由と例文を紹介します。上司や社内の人に納得してもらえる理由を考える際の参考にしてみてください。
結婚するため
結婚は退職理由として挙げる人が多く、円満に退職しやすい理由の一つです。ただし、結婚したあとも同じ会社で勤務し続ける人がいる職場では、「結婚するから」だけでは納得してもらえない可能性もあるでしょう。
説得力をアップさせるためには、「結婚のタイミングで退職する理由」をしっかり説明することが大切です。具体的には、「結婚して遠隔地へ引っ越す」「配偶者の扶養に入るので仕事を辞める」「結婚を機に家業を継ぐ」など。結婚後に仕事を続けられない理由を具体的に伝えるのがおすすめです。
【例文】
△月に結婚が決まり、相手の転勤に伴って転居することとなりました。家庭の事情で大変恐縮ですが、△月で退職させていただきたく存じます。
体調不良のため
「体調不良のため」も、退職する際本音を隠しやすい理由です。会社側が体調の悪化を懸念して、強引な引き止めを行う可能性も低いでしょう。もし休職を提案されたとしても、「仕事から離れて療養に専念したい」とはっきり意思を伝えることが大切です。
【例文】
△月から体調が優れず、業務の継続が困難と判断し静養することにしました。休職も考えましたが、医師からの助言もあり、退職を選択することにしました。
家族の看病や介護のため
「家族の看病や介護のために、自身の生活スタイルを変える必要がある」というのも納得されやすい理由の一つです。自分の意思や会社の意向では解決できない問題のため、引き止められたり事情を詮索されたりすることも少ないと考えられます。
【例文】
母が高齢となり、介護に専念しなければならない状況になりました。急遽のご相談ではありますが、△月に退職させていただきたく存じます。
家業を継ぐため
「家業を引き継ぐため」も、納得されやすい退職理由の一つといえます。「両親が高齢のため」や「実家へ引っ越す必要があるため」などの理由をつけ加えると説得力が増し、引き止められる可能性も低いでしょう。
【例文】
高齢の両親の体調面が心配で、家業を継ぐことを決意しました。家族の健康と幸福を第一に考えたいため、大変勝手なお願いではありますが、△月に退職させていただきたく存じます。
興味のある仕事に挑戦するため
「興味のある仕事に挑戦したい」という退職理由も、本音を隠せる理由です。とはいえ、部署異動や待遇の改善を提案されて、引き止められる可能性もあるでしょう。スムーズに退職するためには、異業種への転職希望を伝えて熱意や向上心をアピールするのが効果的です。「新しい環境でキャリアアップしたい」という従業員の前向きな気持ちを否定してまで引き止める会社は少ないでしょう。
【例文】
以前から興味のあった△△業界への転職を考えております。これまでの経験を活かし、新たな環境でチャレンジしたいため、退職を選択することにしました。
理由が「一身上の都合」のみでも退職できる
退職理由が「一身上の都合」のみでも、基本的に問題はありません。理由の詳細を聞かれたくない場合や嘘をつくことに罪悪感を覚える場合は、会社側に「一身上の都合で退職したい」と伝えましょう。ただし、上司が納得しなかったり、引き止められたりすることもあるため、可能なかぎり退職理由は具体的に準備しておいた方が安心です。
「一身上の都合」の使い方は「
『一身上の都合』とは?使い方や面接で理由を聞かれたときの対策を解説!」のコラムで解説しているので、ご一読ください。
退職理由を伝える際のポイント
「退職理由は考えたけど、どのように伝えたらいいか分からない」という方もいるでしょう。上司に退職を申し出る際は「退職の意向をはっきり伝える」「ネガティブな理由はポジティブに言い換える」「感謝を伝える」といったポイントを意識します。本音で伝える場合も隠す場合も、これらのポイントを理解しておくことで、円満な退職が目指せるでしょう。
退職の意向をはっきり伝える
退職理由を上司に伝える際は、意思をはっきりと伝えることを心掛けましょう。気を使って曖昧な表現にすると、上司や会社から引き止められる可能性があります。スムーズに退職するために、迷いを見せずはっきりと退職理由を伝えるようにしましょう。
ネガティブな理由はポジティブに言い換える
職場環境や人間関係の不満など会社を批判するネガティブな表現は避け、ポジティブな理由に言い換えましょう。たとえば、「スキルアップできない」というネガティブな本音は、「新しい環境で成長したい」と言い換えることで前向きな退職であるという印象を与えられるでしょう。
感謝を伝える
退職の意思を伝える際は、感謝の気持ちも忘れず伝えましょう。どのような職場であっても、社会人としてさまざまな経験が得られる場であったはずです。職場に不満がある場合も、大人な対応を心掛け感謝を伝えることで、円満に退社できるでしょう。
退職理由を伝える際の注意点
退職理由を伝える際には、「一貫性をもたせる」「繁忙期を避けて申告する」「会社を批判しない」などの点に注意する必要があります。以下で解説しているので、参考にしてみてください。
就業規則に従う
就業規則に退職に関する項目がある場合は、必ず確認しておきましょう。会社によっては、退職の意向を上司に伝える期限が決まっている場合があります。また、退職手続きや引き継ぎには時間がかかるものも多く「すぐに辞めたい」は会社にマイナスな印象を与えかねません。退職の意向は、退職希望日の1〜2ヶ月前を目安に伝えるように意識しましょう。
理由には一貫性をもたせる
退職理由で本音を隠す際は、理由に一貫性をもたせましょう。相手によって話す内容が変わったり、当初伝えていた理由とズレたりすると、矛盾を指摘される恐れがあります。嘘の理由と気づかれないために、整合性のある内容を事前に練っておくことが重要です。
辞める意思表示は繁忙期を避ける
退職の申し出は、繁忙期を避けましょう。納得してもらいやすい退職理由を練っても、伝えるタイミングを誤ると「周りのことを考えていない無責任な人」とマイナスな印象を与えてしまう可能性があります。忙しい時期を避ければ上司にゆっくり話を聞いてもらえて、同僚に引き継ぎの協力も仰ぎやすいでしょう。
退職日は会社側の都合も考慮して決めよう
退職日を決めるときは、自分の意思だけでなく会社側の都合も考慮しましょう。後任者の決定や引き継ぎにかかる期間などを考えず一方的に退職日を決めてしまうと、無責任な印象を与えてしまう可能性があります。まずは直属の上司に退職の意思を伝え、仕事を辞めるまでに必要な手続きや業務を確認したうえで日程を決定しましょう。
直属の上司に先に伝える
退職の相談や報告は、まず直属の上司に伝えるようにしましょう。他のメンバーに退職することや転職活動をしていることなどを上司に知らされた場合、「自分には知らされていなかった」とマイナスな印象を与えてしまう可能性があります。直属の上司との関係が悪化すると、スムーズに辞められなくなる可能性もあるので注意が必要です。
会社を批判する表現はしない
退職理由を考えるときは、会社を批判する表現は使わないように注意しましょう。円満に仕事を辞めるためには、会社の責任を問うような表現は避けるのが無難です。職場環境や人間関係に不満がある場合も会社を責めず、「自分に至らなかった点がある」という謙虚な姿勢で退職の意思を伝えましょう。
退職後に転職活動を見据えている方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、既卒や第二新卒などの若年層に特化した転職エージェント。専任のキャリアアドバイザーが希望に沿った求人紹介や選考対策をマンツーマンでサポートします。サービスはすべて無料なので、お気軽にご利用ください。
退職理由に関するFAQ
ここでは、本音を隠し嘘の退職理由を伝えても良いのか疑問に思っている方のお悩みをQ&A方式で解決します。
本音を伝えてしまうと円満退職が難しそうな場合は、嘘の理由を伝えるのも一つの方法でしょう。会社への不満や人間関係、仕事に対するモチベーションの低下などが原因で仕事を辞める場合、納得してもらいやすい別の理由を伝えた方がスムーズに退職できる可能性もあります。
「退職理由は正直に言うべき?上司や面接官への上手な伝え方を紹介」のコラムでは、退職理由の好印象な伝え方を解説しているので、ご一読ください。
「仕事を続ける自信がない」は退職理由として伝えてもいい?
「仕事を続ける自信がない」と正直に伝えると、会社に「努力が足りない」といったマイナスな印象を与えかねません。本音をそのまま伝えるのは避け、「スキルアップ」や「新たなチャレンジ」といったポジティブな表現に言い換えて伝えるのがおすすめです。
結婚や親の介護、体調不良などが理由の場合は、本音を隠して伝える必要はありません。嘘の理由はバレるリスクや嘘をつき続けるストレスなどのデメリットがあります。そのまま伝えても問題のない退職理由は、嘘をつかず本音で伝えましょう。
退職理由を伝えづらいと感じている場合は、転職エージェントを利用するのも手です。エージェントに本音を伝えておくことで、スムーズに退職できる退職理由や企業への伝え方などのアドバイスが得られるでしょう。
退職や転職に関してお悩みの方は、ぜひ一度ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは専任のキャリアアドバイザーが、就職や転職活動に関する悩みをしっかりとサポートします。サービスの登録や利用はすべて無料です。所要時間1分程度で簡単にできる適職診断もあるので、お気軽にご利用ください。