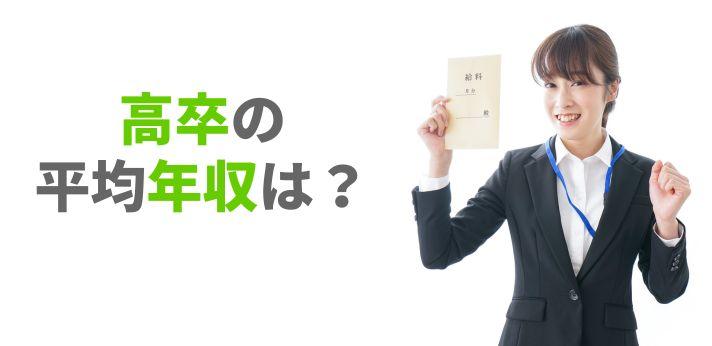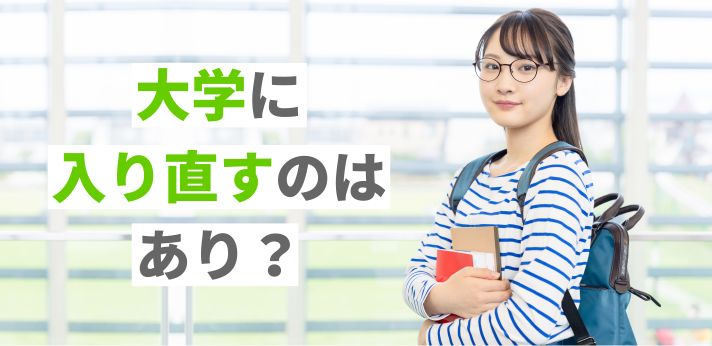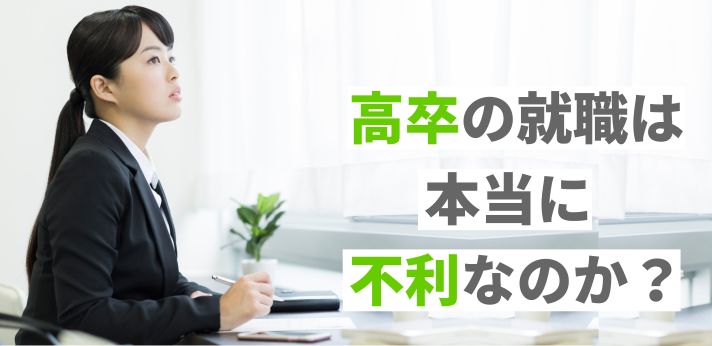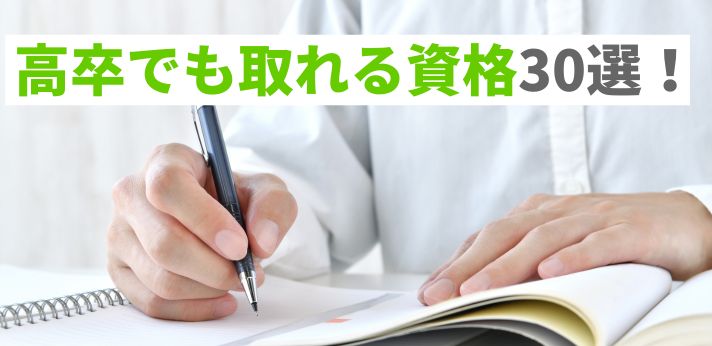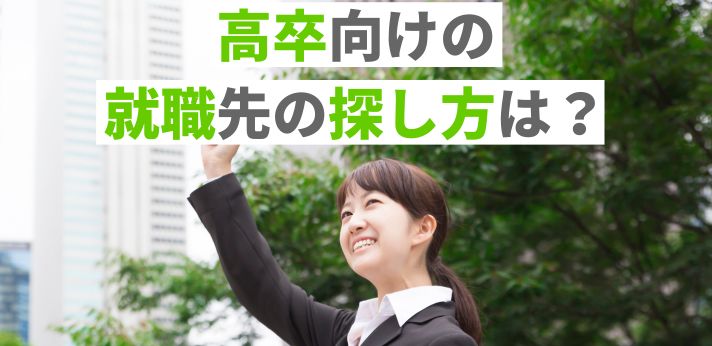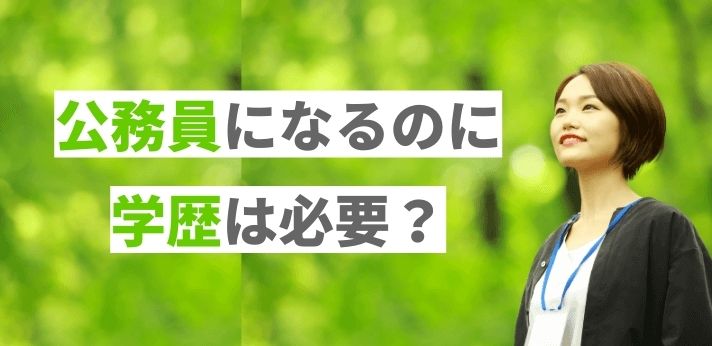大卒と高卒の違いを9個紹介!人間性・考え方や給料・メリット・デメリットも大卒と高卒の違いを9個紹介!人間性・考え方や給料・メリット・デメリットも
更新日
公開日
大卒と高卒では、生涯賃金・平均年収・就職できる仕事などに違いがある
「大卒と高卒の違いは何がある?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。大卒と高卒とでは、生涯賃金や平均年収、就ける仕事・就けない仕事などに違いがあります。医師や獣医などは大卒でないと就職することができません。
このコラムでは、大卒と高卒の違いを9個まとめました。大卒・高卒それぞれのメリット・デメリットも解説しているので、これから就職活動をする方はぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
大卒と高卒の9個の違い
「大卒と高卒の違い」と聞いて、給料の差を思い浮かべる方もいるでしょう。大卒と高卒の違いは給料だけでなく、人数や応募できる求人数、社会人になる早さなど、さまざまな点が挙げられます。
この項では大卒と高卒の違いを9個紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
1.生涯賃金:高卒1億5,000万~2億円、大卒2億~2億5,000万円
大卒と高卒では初任給や平均年収に差があり、当然、生涯賃金も異なります。独立行政法人労働政策研究・研修機構の「ユースフル労働統計労働統計加工集2024」によると、学校を卒業後、60歳までフルタイムの正社員として働いた場合の生涯賃金は以下のとおりです。
| 学歴 | 男性 | 女性 |
|---|
| 高卒 | 2億1,000万円 | 1億5,000万円 |
| 大卒 | 2億5,000万円 | 2億円 |
この結果から、一般的には男女ともに大卒者のほうが生涯賃金が高いことが分かります。しかし、企業によって初任給や昇給の基準、ボーナスの金額などはさまざまです。成果を上げたり役職に就いたりすることで、高卒者が大卒者以上の収入を得られる可能性は十分にあります。
初任給:高卒16万円、大卒21万円
| 学歴 | 初任給 |
|---|
| 高卒 | 16万7,400円 |
| 大卒 | 21万200円 |
上記の結果から、大卒と高卒の初任給の差は約5万円であることが分かります。年齢を重ねるにつれて収入は上がりますが、大卒と高卒の差は縮まらない傾向です。
平均年収:高卒300~440万円、大卒480~670万円
| | 男性 | 女性 |
|---|
| | 高卒 | 大卒 | 高卒 | 大卒 |
|---|
| ~19歳 | 20万3,100円 | ー | 19万3,100円 | ー |
|---|
| 20~24歳 | 22万3,300円 | 25万1,500円 | 20万6,900円 | 25万200円 |
|---|
| 25~29歳 | 25万2,600円 | 29万300円 | 22万3,700円 | 27万6,700円 |
|---|
| 30~34歳 | 28万500円 | 34万500円 | 22万9,300円 | 30万円 |
|---|
| 35~39歳 | 30万2,300円 | 39万2,800円 | 23万5,200円 | 33万1,300円 |
|---|
| 40~44歳 | 32万8,200円 | 43万3,000円 | 24万1,600円 | 33万8,900円 |
|---|
| 45~49歳 | 34万8,200円 | 49万3,300円 | 24万7,000円 | 36万5,700円 |
|---|
| 50~54歳 | 36万2,800円 | 52万1,600円 | 25万5,900円 | 38万1,400円 |
|---|
| 55~59歳 | 36万9,400円 | 54万9,600円 | 25万7,100円 | 40万3,700円 |
|---|
上記の表を見ると、男女ともに50~59歳までは年齢が上がるにつれて賃金は増えていますが、高卒よりも大卒のほうが収入の増え幅が大きいことが分かります。
55〜59歳の賃金に12を掛けて年収に換算すると、男性の場合は高卒が約443万円で大卒が約659万円円、女性の場合は高卒が約308万円で大卒が約484万円です。つまり、大卒と高卒の年収の差は男性で約216万円、女性で約176万円と計算できます。
学歴による年収の違いは、生涯賃金の格差に影響しているといえるでしょう。
業種や職種によっては高卒が大卒の賃金を上回ることもある
一般的に、初任給や平均年収は大卒のほうが高いといわれていますが、場合によっては高卒のほうが生涯賃金が高くなることもあります。たとえば、中小企業の一般事務職として就職した大卒者と、大企業の営業職として就職した高卒者では、後者のほうが生涯賃金が高くなる可能性があるでしょう。
高卒者がより多くの生涯賃金を得るのであれば、企業規模の大きい会社や成果主義の職種へ就職するのがおすすめです。
2.人数
3.最終学歴
応募資格として、「大卒以上」と最終学歴の条件を設けている企業もあります。大卒者は「高卒以上」「大卒以上」のどちらにも応募可能です。
一方、高卒者は基本的に「大卒以上」と記載のある求人には応募できません。そのため、高卒者よりも大卒者のほうが応募できる求人数が多いのです。
4.社会人になる早さ
高卒者は大卒者よりも早く社会に出るため、高卒者のほうが社会人経験が長くなるのが一般的です。なかには、社会人経験を重視する業界や企業もあり、社会人になる早さはキャリア形成において優位に働くこともあるでしょう。
キャリアアップ
技術や実戦的な経験が重要な仕事では、社会人経験がキャリア形成に必要とされやすい傾向にあります。そのため、大卒者よりも先に社会人になった高卒者のほうが、キャリアアップを早く目指せる可能性があるでしょう。
一方で、学歴がキャリアに影響する業界や企業では、あとから入社した大卒者が、経験年数の長い高卒者よりも先に昇進・昇給することも考えられます。学歴による評価を避けたい場合は、企業選びの際によく調べることが大切です。
5.受験費や学費
大学に進学をすると、学費や受験費などの費用がかかります。
しかし、費用を抑えて大学進学を目指すことは可能です。具体的には、私立大学に比べて学費が安い国立大学を目指したり、特待生や奨学金の支援制度を利用して金銭的な負担を減らしたりする方法があります。
※奨学金は全額返済しなければならない場合もあります
6.離職率
7.就職できる仕事
就職できる仕事においても、大卒と高卒で違いがあります。下記で詳しく見ていきましょう。
高卒の割合が多い仕事
大卒の割合が多い仕事
ホワイトカラーと呼ばれる仕事では、大卒者の割合が多いようです。ホワイトカラーの仕事として、医師や教師、研究職などが挙げられます。
研究職や学者など高度な知識を求められる職種では、大卒以上の学歴が必要な場合が多く、医師や教師といった職種では、専門的な知識だけでなく資格が必要です。
たとえば、公認会計士・警察官・消防士の高卒・大卒の割合は下表のようになっています。
| | 高卒 | 大卒 |
|---|
| 公認会計士(ホワイトカラー) | 4.3% | 80.9% |
|---|
| 警察官(ブルーカラーとホワイトカラーの両面をもつ) | 61.7% | 91.5% |
|---|
| 消防士(ブルーカラー) | 60.9% | 67.4% |
|---|
大卒でないと就けない仕事もある
前の項目で解説している仕事は、高卒の割合が少ないものの高卒から目指せないわけではありません。
しかし、世の中には大卒でないと就けない仕事も存在します。たとえば、医師や獣医、薬剤師は大学を卒業しなければ専門資格を得ることができません。
8.待遇
高卒者の初任給を、大卒者よりも低く設定している企業もあります。これは、大卒者のほうがより高い知識や技術をもっていると見なされるからです。一部の企業では、大卒者に比べて高卒者の出世が遅れる可能性もあります。
9.転職市場
転職の際は、一般的にこれまでの実績や経験が重視される傾向にあります。高卒者は大卒者よりも早く就職し社会人経験を積んでいるため、社会人としての基本マナーやスキルを身に付けている・業務経験が十分にあると考えられやすく、転職市場において有利な場面もあるでしょう。
また、転職時は実績があれば学歴を問われないこともあるようです。そのため、高卒から転職する際は社会人経験をうまくアピールすることで、希望する企業への就職成功を叶えられる可能性があります。
しかし、すべての企業で学歴が関係しないとは限りません。転職先によって求められる条件は異なるため、志望する分野の募集要項をしっかりと確認することが重要です。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
大卒と高卒で人間性に違いはない
高卒の方のなかには、「高卒よりも人間性が確立されていそう」「大卒のほうが長く勉強しているから、人間性が違いそう」と思っている方もいるのではないでしょうか。しかし、大卒か高卒かによって人間性に違いはうまれません。
人間性は、その人が生きてきた環境や関わってきた人に影響を受けることが多いため、学歴で違いを区別することは不可能です。
就職率もほとんど同じ
高卒者と大卒者の就職率は0.1%しか変わらないため、新卒においてはどちらも同じくらい就職しやすいといえます。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
高卒で就職するメリット・デメリット
この項では、高卒で就職するメリットとデメリットをご紹介します。就職と進学で迷っている方やこれから就職活動を始める方は、ぜひ参考にしてみてください。
高卒で就職するメリット
高卒で就職する場合、「大学の学費がかからない」「経済的自立が早い」などがメリットです。それぞれについて以下で紹介します。
大学の学費がかからない
大学に進学する場合は受験費や学費などが必要になり、奨学金を借りる場合は将来的に返済する必要があります。一方、高卒であれば大学進学にかかる費用を支払う必要がないため、経済的負担が大幅に軽減されるでしょう。
経済的自立が早い
大学進学の場合、親に学費や生活費を援助してもらうことが一般的ですが、高卒で就職すれば大卒よりも早く経済的に自立できる可能性があります。大卒者よりも早い段階で趣味や生活にお金をかけられるようになるでしょう。
キャリアチェンジがしやすい場合もある
キャリアチェンジをする場合、高卒者は大卒者よりも就活を有利に進められる可能性があります。たとえば、未経験の仕事に挑戦したいと思い社会人3年目に転職すると、大卒の場合は25歳です。
一方で、高校卒業後に3年で離職した場合は21歳となり、大卒者の新卒就職時の年齢より若いです。転職市場では年齢が若いほどポテンシャルを重視されるうえに、3年ではあるものの社会人経験も身に付いているため、転職先の企業によっては大卒よりも有利に進められるでしょう。
高卒で就職するデメリット
高卒で就職するデメリットとして挙げられるのは、「基本給が低い」「大卒者よりも自由な時間が少ない」などです。下記で詳しく紹介します。
基本給が低い
高卒者のデメリットの一つは、一般的に大卒者と比べて基本給が低いことです。企業や職種によって異なるものの、高卒者の基本給を大卒者より低く設定している企業もあります。
大卒者よりも自由な時間が少ない
高校卒業後に就職する場合は、大学生と比べると自由に使える時間が少なくなるでしょう。社会人になると、1日のうちの8~9時間ほどを職場で過ごすことになります。場合によっては、職場の人との付き合いで退勤後に食事をしたり、帰宅後に仕事に必要な勉強をしなければならなかったりすることもあるでしょう。
一方、大学に進学をすると、サークル活動やアルバイト、留学など自由に使える時間ができます。学生なので授業はきちんと受ける必要がありますが、それ以外の時間を充実させやすいのは大学生になるメリットといえるでしょう。
学歴コンプレックスを抱く可能性がある
高卒で就職する場合、学歴コンプレックスを抱く可能性があります。企業によっては、大卒や大学院卒のほうが昇進しやすかったり、初任給が高かったりすることもあるため、不公平と感じる人もいるようです。
また、日本では大学に進学する人が多いため、人によっては高卒であることに自信をもてなくなり、自己評価が低下してしまうケースもあるでしょう。このような学歴コンプレックスを克服するためには、自分の強みやスキルに焦点を当て、自己成長に努めるのがおすすめです。
ハタラクティブキャリアアドバイザー
後藤祐介からのアドバイス
大卒で就職するメリット・デメリット
この項では、大卒で就職するメリットとデメリットを紹介します。
大卒で就職するメリット
大卒で就職するメリットには、「大卒の学歴が役立つことがある」「専門的な知識や経験を得られる」「自由な時間を有効活用できる」などが挙げられます。それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。
大卒の学歴が役立つことがある
大学を卒業することで、大卒以上を応募要件とする企業に挑戦できます。さらに、新しい分野を学びたい場合に、社会人向けの大学院に通いながら仕事をすることも可能です。
一時的に働けない期間があっても、大卒の資格をもっていれば再就職のハードルが下がる可能性もあり、さまざまな状況で役立つでしょう。
専門的な知識や経験を得られる
専門的な知識や経験を得られることも、大学進学のメリットの一つです。特定の教育課程を修了すると取得できる資格もあるため、興味のある分野や就きたい職業が明確な場合におすすめです。
自由な時間を有効活用できる
大学生の主な活動は学業ですが、高卒者と比べると時間的な余裕があります。アルバイトやサークル活動などに加えて、留学や海外旅行など、大学生ならではの経験をする人もいるでしょう。なかには、「海外経験が豊富な人材は自主性が高い」と捉える企業もあるようです。
大卒で就職するデメリット
大卒で就職するデメリットには「高卒よりも学費がかかる」「時間を無駄にする可能性がある」「高卒よりも社会に出るのが遅くなる」などが挙げられます。以下で詳しく紹介するので、チェックしてみてください。
高卒よりも学費がかかる
大学へ進学すると、高卒に比べて受験費や学費がかかります。地元を離れて一人暮らしをする場合は、家賃や食費などの生活費もかかるでしょう。奨学金を借りる場合は、卒業後から返済しなければならず、金銭的に負担がかかる点はデメリットといえます。
時間を無駄にする可能性がある
大学は自由度が高いため、人によっては勉強を怠ったり、無気力になったりしてしまうようです。きちんとした目標がないまま進学をすると、学業や興味のあることに集中できず、結果的に「ただ時間を無駄に過ごした」と後悔する可能性も考えられます。
一方、高卒で就職すると、大学生が学校に通っている期間に働きながらスキルや知識を身につけられるため、高卒者と大卒者の間で経験やスキルの差が生じることもあるようです。
高卒よりも社会に出るのが遅くなる
高卒で就職する場合、10代から社会に出て働きます。大卒の場合は早くて22歳、大学院進学や留年、休学した場合は23〜25歳で社会に出るのが一般的です。
大卒のほうが社会に出るタイミングが遅く、年齢が上がることでキャリアチェンジの際に影響する可能性もあるでしょう。
大卒になる意味とは
学びたいことがある場合や資格が取得できる場合は、大卒になる意味があるといます。専門性の高い医師や看護師、教師などの仕事に就きたい場合は資格が必要であり、試験を受けるためには大学で特定の教育課程を修了しなければなりません。
研究職や学者を目指す場合も、大学や大学院でより専門性の高い知識を身に付ける必要があります。
また、入りたい企業が「大卒以上」を対象にしている場合も、大卒になる意味があるといえるでしょう。
高卒から目指しやすいおすすめの職種
高卒者が未経験の仕事に応募する際は、学歴が重視されない・資格が必要ない・未経験者が活躍しやすい・人手不足といった求人に注目するのがおすすめです。ここでは「飲食店スタッフ」「営業職」「システムエンジニア」「建設作業員」の4つの職種をご紹介します。
飲食店スタッフ
飲食店スタッフの仕事は資格が必要なく、未経験歓迎の求人が多い傾向にあるため、高卒から就職を目指す方におすすめの仕事です。また、高校生のときに飲食店でアルバイトしていた方はその経験を活かして働けるでしょう。
| 仕事内容 | 接客やキッチン業務を通じて、顧客に食事とサービスを提供する |
| 平均年収 | 358.4万円 |
|---|
| 向いている人 | ・コミュニケーション能力の高い人
・おもてなしすることが好きな人
・立ち仕事を長時間続ける体力がある人 |
|---|
| ポイント | ・学歴や資格経験問わず挑戦しやすい
・店長は「防火管理者」「食品衛生責任者」等の資格が必要な場合がある |
|---|
営業職
営業職は、飲食店スタッフと同様に無資格で働くことが可能です。営業職にはいくつか種類がありますが、ここでは新規開拓営業とルート営業(既存営業)について詳しく紹介します。
新規開拓営業
新規開拓営業は、言葉のとおり新規の顧客に対して営業をする仕事です。初対面での営業は警戒されたり門前払いされたりすることもあるため、精神的なストレスに強い人に向いているでしょう。
| 仕事内容 | 未取引の顧客に対して商品やサービスを提案し、新たな取引関係を構築する |
| 向いている人 | ・コミュニケーション力を磨きたい人
・精神的なストレス耐性が高い人
・チャレンジ精神旺盛な人 |
|---|
| ポイント | ・獲得した新規顧客数が多いと、インセンティブがつくことがある
・営業方法は、電話で行ったり直接訪問したりとさまざま
・結果が出るまで粘り強く営業先を回る体力が必要 |
|---|
ルート営業(既存営業)
ルート営業は既存営業とも呼ばれ、既存顧客に対して営業をする仕事です。顧客の課題解決に貢献したいという意欲が強い人に向いているでしょう。
| 仕事内容 | 既存顧客との関係を維持・強化し、継続的な取引を行う |
| 向いている人 | ・長期的な関係構築を得意とする人
・継続的なフォローアップが得意な人
・顧客サービス精神の高い人 |
|---|
| ポイント | ・既存顧客に対する営業が基本で、ノルマがあることは少ない
・長く良好な関係を維持するうえでのプレッシャーを感じることがある
・1人で複数の企業や個人の顧客をもつことが多い |
|---|
システムエンジニア
IT業界は人手不足なので、未経験者も歓迎されやすい傾向にあります。日々変化・進歩するIT技術を学び続けられる自信のある方におすすめです。
| 仕事内容 | Webサービスの設計から開発、保守運用まで一連の工程を担当し、システムを構築する |
| 平均年収 | 574.1万円 |
|---|
| 向いている人 | ・論理的思考力がある人
・新しい技術に興味を持っている人
・細部まで丁寧に取り組める人 |
|---|
| ポイント | ・学歴や資格が必須とされることは少ない
・在宅・リモート勤務、フレックス制で働ける場合が多い
・技術だけでなくコミュニケーション能力も重視される |
|---|
建設作業員
建設業界も、IT業界と同様に人手不足が続いています。形に残る仕事を通じて社会貢献したい方は、視野に入れてみましょう。
| 仕事内容 | 土木工事現場で、機械あるいは人手で、掘削、盛土、コンクリート作業などを行う |
| 平均年収 | 415.1万円 |
|---|
| 向いている人 | ・注意力、集中力のある人
・指示を正確に守れる人
・屋外作業を長時間行う体力がある人 |
|---|
| ポイント | ・機械化の標準化が進行しているが、人力作業は一定の需要が見込まれる
・年末年始やお盆など、長期休暇が多い
・早出、残業、夜勤、休日出勤などの可能性がある |
|---|
高卒者が就職を成功させるコツ
高卒で就活を行う方のなかには、「高卒からの就活がうまくいくか不安…」という方もいるでしょう。高卒の就活を成功させるためには、次の5つのポイントを押さえることが大切です。
高卒者が就職を成功させるコツ
- 資格取得を経て専門知識をアピールする
- 具体的な数字を用いて自己PRを行う
- 求人数が多い業種・企業を狙う
- 就職・転職エージェントを活用する
1.資格取得を経て専門知識をアピールする
専門性や難易度の高い資格を取得し、専門知識をアピールすることで、高卒からの就活が成功しやすくなります。高卒からの取得におすすめな民間資格は以下のとおりです。
- ・秘書技能検定
- ・マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
- ・日商簿記検定
- ・調剤事務管理士技能認定試験
- ・医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)
- ・ネイリスト技能検定試験
- ・NSCA認定パーソナルトレーナー
- ・TOEIC
- ・登録販売者試験
- ・整体師
上記のような資格を取得しておくと、「専門的な知識が身に付いている」というアピールになり、入社後に即戦力として期待されることも。
また、以下のような高卒からも取得可能な国家資格を取得するのもおすすめです。
- ・宅地建物取引士
- ・FP技能士(ファイナンシャル・プランニング技能士)
- ・司法書士
- ・行政書士
- ・弁護士
- ・公認会計士
- ・ITパスポート
- ・基本情報技術者
- ・調理師
- ・製菓衛生師
弁護士や公認会計士といった国家資格の取得には、大学進学をしなければ難しいイメージをもつ方もいるでしょう。しかし、実際には受験資格に学歴要件はなく、高卒者も試験に合格することで国家資格を得られます。
国家資格は社会的信用度が高く、職種や企業によっては採用条件に含まれることもあるため、就活で有利に働きそうな資格がある場合は取得を検討してみましょう。
2.具体的な数字を用いて自己PRを行う
採用面接で自己PRを効果的に行うためには、具体的な数値や実績を示すことがポイントです。アルバイトや部活動での成果を数値やデータで具体的に説明すると、自身の実績がより明確に伝わります。
また、TOEICのスコアが高い場合や、業務で役立つ資格を取得していることなどもアピールにつながりやすいです。
3.求人数が多い業種・企業を狙う
| 業種 | 求人数 |
|---|
| 医療、福祉 | 214,272件 |
|---|
| サービス業(他に分類されないもの) | 109,072件 |
|---|
| 卸売業、小売業 | 98,882件 |
|---|
| 製造業 | 68,998件 |
|---|
| 建設業 | 68,681件 |
|---|
高齢化が進む現代では医療・福祉業界の需要が高まっており、求人数が多くなっています。医療の仕事では資格が求められる場合がありますが、医療事務や福祉関係の仕事などでは学歴不問や未経験の求人もあるようです。
高卒から正社員就職を目指す場合は、求人数が多い企業を狙うのもおすすめです。同資料によると、求人数が多い企業規模は、従業員数が29人以下の企業で約51万件、次いで従業員数が30~99人以下の企業で約17万件です。
| 企業規模 | 求人数 |
|---|
| 29人以下 | 512,847件 |
|---|
| 30~99人 | 177,317件 |
|---|
| 100~299人 | 65,443件 |
|---|
| 300~499人 | 12,944件 |
|---|
| 500~999人 | 9,533件 |
|---|
| 1,000人以上 | 7,934件 |
|---|
上記の結果から、規模が小さい企業ほど求人数が多いことが分かります。仕事探しの際は、大手企業だけでなく中小企業も視野に入れるようにしましょう。
4.就職・転職エージェントを活用する
「希望の企業に就職できるか心配」「学歴に不安がある」という場合は、就職・転職エージェントに相談するのがおすすめです。就職・転職エージェントでは、専任のキャリアアドバイザーがプロ目線で自分の希望に合った求人を紹介してくれます。
また、労働環境や給与の詳細、待遇面、人間関係といった詳細な情報を教えてくれるので、安心して応募することが可能です。
まとめ
大卒と高卒は、初任給や平均年収、就職できる仕事などに違いがあることが分かりました。
しかし、高卒者も業種・職種によっては大卒より高収入を得られます。高卒であることをマイナスに捉えず、自分のスキルや能力を磨き、採用されやすい求人を見極めることが大切です。
ハタラクティブは、高卒や既卒、第二新卒などの若年層を対象とした就職・転職エージェントです。経験豊富なキャリアアドバイザーがカウンセリングで適性を把握し、一人ひとりの希望に合わせて仕事を紹介します。学歴不問や未経験可の求人を多数ご用意しているため、学歴に不安がある方もご安心ください。
また、応募書類の添削や面接対策のほか、面接日時の調整といったサポートもマンツーマン体制で実施しています。適職診断を通して自分に合った仕事を調べることも可能です。
サービスはすべて無料で利用できるので、お気軽にご相談ください。
大卒と高卒の違いに関するQ&A
大卒と高卒の違いについて知りたい方もいるでしょう。ここでは、大卒と高卒の違いに関する疑問にQ&A形式でお答えします。
必ずしも高卒者が就職で不利になるとはいえません。ただし、学歴を重視する企業への就職を目指す場合は、大卒者と比べると不利になる場合もあるようです。
また、基本的に高卒者は「高卒可」の求人にしか応募できないため、申し込める求人数は大卒者のほうが多いといえるでしょう。
業界や企業によって異なるものの、大卒者のほうが給料を高めに設定していることが一般的なようです。また、このコラムの「生涯賃金」で紹介したとおり、高卒者より大卒者のほうが生涯賃金も高くなっています。
公務員試験を受ける場合、大卒と高卒では公務員試験の内容や難易度、受験できる条件に違いがあります。高卒程度の公務員試験を受ける際は、年齢制限をしっかりと確認しましょう。