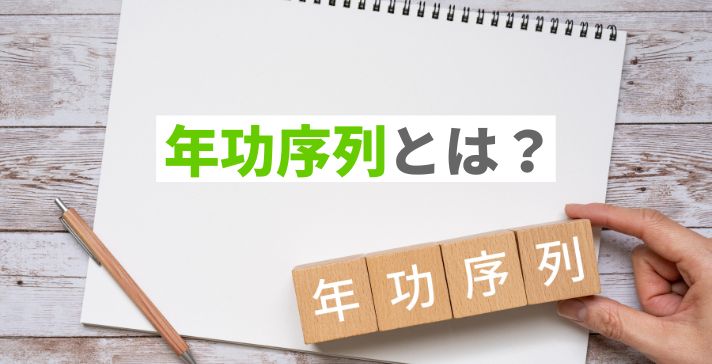平均勤続年数とは?全体の目安は?企業の特徴や転職で役立つポイントを解説平均勤続年数とは?全体の目安は?企業の特徴や転職で役立つポイントを解説
更新日
公開日
平均勤続年数は社員全員の在籍年数の平均値で毎年変動し、就職先選びの目安となる
就活時、企業の平均勤続年数が気になる方も多いでしょう。平均勤続年数は、社員の定着状況を示す指標の一つです。勤めている社員それぞれの勤続年数から算出されるので、働きやすい企業を見極めるのに役立つでしょう。ただし、新入社員や退職者の数によって毎年変動するため、勤続年数のみで企業を選ぶのは注意が必要です。
このコラムでは、平均勤続年数の見方や目安、計算方法などについて解説。ぜひ就活の参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
平均勤続年数とは
「平均勤続年数」とは、勤めている会社の社員全員を対象とした在籍年数の平均値を指します。会社全体を対象とするため、新入社員の数によって左右されたり、定年まで勤め上げた社員が退職したりと、その年の社員の動きによって変化するものです。
「勤めている会社の社員全員」には新入社員も含まれているため、算出時期によっては平均勤続年数が短くなることがあります。そのため、平均勤続年数を就職先選びの参考にする際は、年数のみで判断せず全体を通して確認するようにしましょう。
働きやすい企業の見極め方
平均勤続年数が高めの企業は、「働きやすい会社」という指標にもなります。居心地のよい職場環境を就職先の条件としている求職者にとって、とても大切な項目ともいえるでしょう。
就活時の参考となる平均勤続年数ですが、日本では年功序列による就労形態が多いこともあり、世界的に見ると長めの傾向が見られるようです。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
平均勤続年数の計算方法
平均勤続年数の計算方法は「常勤従業員の勤続年数の合計」÷「常勤従業員の総人数」で求めることが可能です。
まず、すべての常勤従業員の勤続年数の合計を求めます。次に、常勤従業員の総人数を数えましょう。そして、これらの値を式に代入して計算を行った結果が平均勤続年数となります。
男女別の平均値もチェック
男性と女性では、勤続年数の平均値に違いを生じてしまうもの。女性は、結婚や出産によって一人ひとりの勤続年数が変わってきます。この先、結婚をして出産もして…と考えている人は、転職するときの目安として男女別の平均値も参考にしてみてください。家庭に入って子育てをしつつも「長く働ける」環境が整っているのかどうかを知る手がかりになるはずです。
男女別の平均値では、男性の方が長い傾向が見られますが、企業によっては、男性よりも女性の平均勤続年数の方が長いという結果も出ています。就活するときには、復職支援制度や出産・育児休暇制度など、長く在籍できる環境が整っているのかどうかなどもチェックしておくとよいでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
企業の平均勤続年数の目安
国税庁が公表した「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、企業全体の平均勤続年数は12.7年となっています。男性の平均勤続年数は14.3年、女性の平均勤続年数は10.4年です。
また、同様の資料で平成26年度から令和4年度までをみても、約11~13年の間で推移していることから、平均勤続年数の大きな変動はないといえるでしょう。
平均勤続年数からみる企業の特徴
企業の平均勤続年数は、その企業の特性を理解するうえで重要な指標です。短い場合と長い場合、それぞれに特徴があります。
以下では、平均勤続年数の長さから見えてくる企業の特徴をまとめました。
平均勤続年数が短い場合
平均勤続年数が短い理由には、以下のようなものがあります。
新入社員増加による勤続年数の減少
先述したように、新入社員の割合が増えると、必然的に全社員の平均勤続年数が短くなります。これは、若い人材を積極的に採用し、企業の成長や新規事業の拡大を図っている証拠でもあるでしょう。
このような企業は、若手に多くの成長機会を提供し、早期にキャリアアップを図ることができる環境が整っていることが多い傾向があります。
吸収・合併に伴う従業員転籍によるリセット
吸収や合併によって従業員が転籍する場合、その企業の勤続年数はリセットされることが一般的です。これにより、勤続年数の計算が新たに始まり、結果として平均勤続年数が短くなることがあります。
吸収・合併は企業の成長戦略の一環として行われることが多く、新しい体制での事業拡大やシナジー効果を目指すポジティブな動きと捉えられるでしょう。従業員にとっても、新しい環境でのキャリア構築やスキルアップの機会が増える可能性があります。
転職者が多い可能性がある
転職者が多い企業では、平均勤続年数が短くなる傾向があります。転職理由には、労働条件や働く環境が合わないなどがあるものの、必ずしもネガティブな要因だけではありません。
たとえば、2〜3年で転職する人が多い企業では、「キャリアや経験を積み、次のステップへ進むために転職する」といったポジティブな理由で退職する場合も多く見受けられるようです。
平均勤続年数が短い=ブラック企業というわけではない
人材業界やIT業界などは業界柄、転職してキャリアアップしたり起業したりする場合も多く、平均勤続年数が短くなる傾向があります。また、企業側が起業・独立を推奨しているパターンもあるため、「平均勤続年数が短い=ブラック企業」と一概には言えません。平均勤続年数は目安として、業界や会社の特徴をよく確認しましょう。
平均勤続年数が長い場合
ブラック企業の見極めも重要ですが、平均勤続年数は業績不振の企業をチェックする指標にもなります。たとえば、新卒採用をしていない企業では、自然に平均勤続年数が長くなるため、その長さに違和感を抱くことが重要です。
業績が長期間で安定している
平均勤続年数が長い企業の特徴は、業績が長期間にわたって安定していることです。業績が安定している企業はリストラを行わずに雇用を守る傾向が強く、その結果、平均勤続年数が長くなります。このような企業では、万が一不景気に陥ってもリストラのリスクが低いため、自ら退職する社員も少なくなるでしょう。
特に電気やガスといったインフラ関係の企業は、生活に欠かせないサービスを提供しているため、業績が安定していることが多いようです。これにより、雇用を削減する必要が少なく、結果として平均勤続年数が長くなります。
安定した職業とはどのようなものがあるか、詳しく知りたい方は「安定した職業12選!仕事選びのコツやおすすめの資格をご紹介」こちらも参考にしてください。
新卒の採用を見送っている
新卒採用を行わない企業では、既存の社員が長期間にわたって勤務し続けるため、平均勤続年数が自然と長くなります。このような企業では、新しい人材の採用よりも、現在の社員を大切にし、育成し続ける方針をとっている場合が多いようです。長年働いている社員が多いため、職場の安定性や社員同士の結束力が強いことが期待されます。
しかし、場合によっては新しい刺激や学びの機会が少ないと感じられることもあるでしょう。
年功序列が厳しく出世が難しい
年功序列が厳しい場合、組織の安定性や秩序が保たれることが重視されます。一方で、新人や若手社員がスピーディーに成長や貢献を認められる環境ではないため、モチベーションの維持やキャリアプランの実現が難しく感じられることもあるでしょう。
組織の文化や働き方に合った企業選びが重要であり、個々のキャリア目標や志向に合った環境を見極めることが必要です。
福利厚生や研修制度が整っている
福利厚生や研修制度が整っている企業は、社員の働きやすさや成長を重視しています。充実した福利厚生は、社員が安心して仕事に取り組める環境を提供し、生活面での不安を軽減するものです。
また、研修制度の充実は、社員の能力向上やキャリアの発展を支援。定期的な研修や教育プログラム、キャリアカウンセリングなどが提供され、社員が専門知識やスキルを磨き、成長する機会を得ることができるでしょう。
さらに、長期間同じ職場で働くことで退職金や医療保険、教育支援などの各種サポートを受けられることが期待され社員の満足度が高まり、結果として勤続年数が長くなるといえます。
企業を見極める指標をもっと詳しく知りたい方は「ホワイト企業の見分け方とは?働きやすい環境に転職しよう」も参考にしてください。
平均勤続年数とあわせて転職時の参考になるポイント
平均勤続年数のほかにも、企業を選ぶ際に役立つデータがあります。以下のデータと併せて分析することで、より精度の高い情報を取得しましょう。
ここでは平均勤続年数と組み合わせて考慮すべきポイントをご紹介します。
採用人数
平均勤続年数だけでなく、採用人数も重要なポイントです。企業が新卒や中途採用をどれだけ行っているかは、社員の入れ替わりや定着率に直結します。
採用人数が多い場合、業績が良く事業を拡大している可能性が高く、採用人数が少ない場合は業績が停滞している可能性も考えられるでしょう。そのため、平均勤続年数と同様に、近年の採用人数や業績などを確認して、企業の将来性を判断することが重要です。
企業が設立した年
設立年を把握することで、平均勤続年数の背景や企業の成長状況をより理解し、転職時の判断材料とすることができます。
企業の設立年は、その年数によって平均勤続年数の意味が大きく異なるものです。たとえば、創業10年で平均勤続年数が6年の企業と、創業50年で平均勤続年数が7年の企業を比較すると、前者の方が社員の定着率が高いと考えられるでしょう。
設立して間もない企業では、平均勤続年数が短くなる傾向が強いため、単純に比較しても、社員の定着率を正確に判断することは難しいといえます。企業の設立年は、企業の公式HPや資料などで確認できるので、事前にチェックしておきましょう。
新卒者の3年以内の離職率
新卒者の3年以内の離職率は、新入社員の定着率を把握するために重要です。平均勤続年数が長かったとしても、新入社員が定着しているとは限らない可能性があります。
企業は基本的に新卒以外の社員が大半を占めるため、新卒の離職が平均勤続年数に大きな影響がありません。そのため、明確な離職率を知りたいなら、就職情報サイトや就職四季報などに3年以内の離職率が掲載されている場合があるので、一度調べてみましょう。
平均勤続年数を含め広い視点から転職活動を進めよう
平均勤続年数は転職活動において参考になるデータですが、それだけでは企業の良し悪しは分かりません。平均勤続年数が高いからといって、ホワイト企業だと安心して決めるのは早計といえるでしょう。
入社後は業務内容や勤務地、給与など多くの要素が影響します。そのため、長期的に見据えた総合的な判断が重要。転職が一般的になる現代においては、自分の人生設計と合致するかどうかを考えながら慎重に企業選びを進めましょう。
自分に合った仕事を見つけたい方には、転職エージェントの利用もおすすめです。転職エージェントでは企業に訪問調査を行うので、信頼できる求人を取り扱っています。
就職・転職支援のハタラクティブは、専任のキャリアアドバイザーが、求職者の理想の給与形態・給与水準・働き方などについてカウンセリングを実施。保有する優良企業の中からスキルや適性にマッチした求人のご紹介を行っています。
また、応募書類の添削や面接対策、基本的なビジネスマナーの指導などのバックアップ体制が充実しているのも特徴です。
サービスの主な利用者は、高卒や既卒、第二新卒やフリーターといった若年層の方が中心。未経験OKの正社員求人を取り揃えていますので、初めて就職する方にも幅広い選択肢をご提供できます。サービスの登録・利用料はすべて無料です。気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。