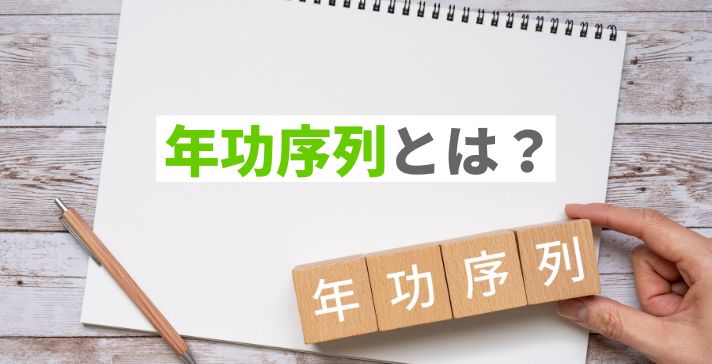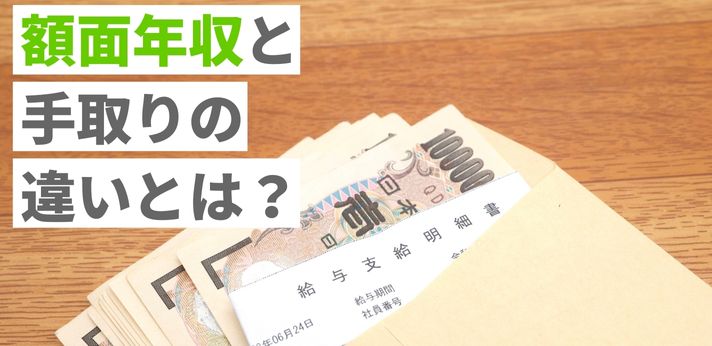勤続年数とは?正しい数え方や転職・失業保険・退職金・有休への影響を解説
「勤続年数とはどういう意味?」「正しい数え方は?」と疑問に思っている方は多いでしょう。勤続年数とは、一般的に「一つの会社で入社~退社まで続けて勤務した年数」を指しますが、捉え方は企業によって異なります。このコラムでは、勤続年数の正しい数え方や転職・有給休暇・失業保険・退職金への影響を紹介。休職・退職した場合の勤続年数の数え方も解説します。勤続年数への理解を深め、職業生活や転職活動で役立てましょう。

強みをかんたんに発見してみましょう!(所要時間:30秒)
就職でお困りではありませんか?
当てはまるお悩みを1つ選んでください
勤続年数とは
勤続年数とは「一つの会社において、入社〜退社まで継続して勤務した年数」のこと。入社した日から退社する日までの期間を合計して計算します。たとえば、4月1日に入社し、翌年の4月以降も続けて勤務している場合、勤続年数の数え方は「勤続2年目」です。
国税庁の「タックスアンサー(よくある税の質問)『No.2732 退職手当等に対する源泉徴収』」では「勤続年数は、原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間の年数」と定義されています。勤続年数の数え方が知りたい方は、後述する「勤続年数の数え方」をご覧ください。
参照元
国税庁
国税庁トップページ
勤続年数における「満」の使い方は?
勤続年数につく「満」は、満年齢と同じで「ちょうどその期間に達した」ことを意味します。しかし、勤続年数においては「満」をつけなくても問題はありません。たとえば、勤続年数が「満5年」の場合は、ちょうど5年を経過したことを指します。一方で「勤続5年」と表記しても同じ意味として扱われることが一般的です。「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
平均勤続年数との違い
平均勤続年数とは「現在会社に勤務している社員の勤続年数を平均した値」を指します。勤続年数との大きな違いは算出の対象です。勤続年数は個人で算出する値であるのに対して、平均勤続年数は会社の社員全員を対象にして算定します。
現在会社に勤務している社員には新入社員も含まれるため、算出するタイミングによっては平均勤続年数が短くなるでしょう。新入社員の割合が高い会社においても、平均勤続年数が短くなりやすいといえます。「平均勤続年数が短くても離職率が高いわけではない」と頭に入れておけば、求人を探す際の視野が広がるはずです。
平均勤続年数については「平均勤続年数とは?全体の目安は?企業の特徴や転職で役立つポイントを解説」のコラムでも触れていています。ぜひ参考にしてみてください。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
勤続年数の数え方
勤続年数は、基本的に入社日から退社日までの期間を合計して算出します。勤続年数を計算する際は、端数を切り上げるのが基本。たとえば、10月1日に入社した人の場合、翌年9月30日に退職すれば「勤続1年」、翌年10月1日に退職すると「勤続2年」とするのが一般的です。
ただし、勤続年数の考え方や数え方は、記載する書面や会社の制度によって異なる場合があります。手続きする署名や会社の規定をよく確認して算出しましょう。基本的な算出方法を踏まえ、勤続年数の数え方をいくつかのケースごとに解説します。
休職・退職に係る勤続年数の数え方
勤続年数の数え方は、雇用保険の適用条件や退職金などにも大きく関わってきます。休職・退職をしたときの勤続年数の数え方について、しっかり確認しておきましょう。
休職した場合における勤続年数の数え方
一般的に、病気やケガなどによる休職の期間は、勤続年数に含みません。ただし、具体的な取り扱いは、会社の規定や労働契約内容によって異なります。たとえば、会社都合による休業で休職した場合や休職期間が1年未満の場合、勤続年数に含むケースもあるでしょう。勤続年数に含む場合でも、長期の休職後に職場復帰した際、昇給の算定などに影響を与えることもあるのでよく確認しましょう。
休職期間を勤続年数に含めるのは、基本的に年次有給休暇を取得したときのみです。年次有給休暇について詳しく知りたい方は「有給休暇とは?付与の目的・日数・取得義務などについて解説」もあわせてご覧ください。
産休・育休における勤続年数の数え方
年次有給休暇の付与基準となる勤続年数を算出する場合、産休・育休期間は勤続年数に含めます。ほかにも以下の期間においては、勤続年数に含めて計算されることが多いでしょう。
- ・非正規雇用で勤務していた期間
- ・出向していた期間
- ・護休業の期間
- ・試用期間
ただし、「労働基準法」で勤続年数について触れられているのは「第39条 年次有給休暇」の項目のみです。年次有給休暇の付与要件以外では、産休・育休をはじめとする上記の期間を勤続年数に含むかどうかは記されていません。
退職金や雇用保険などに係る勤続年数の数え方において、産休・育休期間を勤続年数に通算するかどうかは、就業規則や会社の判断に委ねられます。退職金の算定基礎となる必要勤続年数では、産休・育休の期間は除き、休業前と復帰後の期間のみ勤続年数に含めるケースも珍しくありません。企業によって条件が異なるため、就業規則などで事前の確認が必須です。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
退職時における勤続年数の数え方
退職時における勤続年数の数え方は、入社日から退社日までの期間を合計して求めます。計算するときは、端数を切り上げましょう。なお、退職後に雇用保険制度において失業保険の給付を受ける場合、勤続年数の数え方が重要です。雇用保険を受給するには「離職をした⽇以前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上」である必要があります。
出戻りした場合の勤続年数の数え方
雇用において、いわゆる「出戻り」をしたときの勤続年数の数え方は、企業の規定や制度によって異なります。一度退職してから再入社した場合、再入社した日から勤続年数をカウントするのが一般的です。ただし、定年退職後すぐ再雇用されるなど、実質的に雇用関係が継続しているケースでは、通算勤続年数として扱われることがあります。
退職金の計算に係る勤続年数の数え方
勤続年数の数え方は、退職金の算出時にも大きな関わりがあります。一般的な社員として勤務した期間の数え方と、役員としての勤務期間における数え方について確認しましょう。
退職所得控除(退職金控除)計算での勤続年数の数え方
退職所得控除額(退職金控除)に係る勤続年数は、退職金を支払う企業のもとで退職日まで勤務した期間を基に計算します。勤続年数が1年未満の場合、端数は1年に切り上げて計算するのが一般的な数え方です。
転職に伴い転籍した際、転籍時に退職金が支払われていなければ、転籍前と転籍後の会社における勤続年数を合算できる場合があります。ただし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職所得控除が適用されないため注意が必要です。
役員の退職金計算における勤続年数の数え方
役員退職金の計算時における勤続年数の数え方は、役員勤務期間の年数で計算します。端数が1年未満の場合、1年に端数を切り上げるのは同じです。たとえば、役員等としての勤続年数が4年11ヶ月の場合は5年として扱われます。4年1ヶ月や4年11ヶ月といった4年以上5年未満の期間は、すべて5年とするのが正しい数え方です。
職種・雇用形態ごとの勤続年数の数え方
勤続年数の数え方は、職種や雇用形態によっても異なります。公務員や教員、パートなどの非正規雇用における勤続年数の数え方を確認しましょう。
公務員・公立学校教員の勤続年数の数え方
公務員や公立学校の教員の場合、勤続年数は在職している期間を月単位で計算します。公務員となった月から退職する月までの期間で計算し、月の途中で採用された場合は1月分とするのが基本です。在職して1年経過していない場合の数え方は、6ヶ月未満なら切り捨て、6ヶ月以上なら切り上げます。なお、子どもが1歳を迎えるまでの育休期間は勤続年数から1/3が除算。1歳を過ぎた翌月からは、休業期間の1/2が除算されます。
教育職員検定における教員の勤続年数の数え方
教育職員検定を受ける場合における教員の勤続年数の数え方は、辞令に記載された採用日を基準に年単位で計算します。併任や兼務の場合は、本務の職による計算が原則です。通常、休職期間は勤続年数に含まれません。在職年数に算入できない期間がある場合は除き、1年未満の期間は切り捨てると覚えておきましょう。
パートの勤続年数の数え方
パートの勤続年数の数え方は、パートとして雇用された日から通算して計算します。フルタイム勤務ではないケースでも、計算の仕方は同じです。継続して働いていれば、雇用契約を交わした最初の日を勤続年数の起算日として勤務期間を基準にカウントします。ただし、勤続年数の考え方や数え方は、契約内容や就業規則によって異なるので、勤め先の規定をよく確認しましょう。
勤続年数が影響を及ぼすことはある?
勤続年数は、転職や有給休暇の付与、失業保険の受給、退職金の額などに影響する場合があります。以下で一つずつポイントを解説しているので、参考にしてください。
勤続年数が与える影響
- 勤続年数が短いと転職が不利になる可能性がある
- 勤続年数の長さで有給休暇の付与日数が変わる
- 一定の勤続年数がないと失業保険が受給できない
- 勤続年数によって退職金の額が異なる
勤続年数が短いと転職が不利になる可能性がある
前職の勤続年数が短いと、転職で不利になる場合があります。前職の勤続年数が短いと早期離脱を懸念され、採用面接の際にネガティブに受け取られる可能性があるためです。勤続年数が短いと「業務に必要な知識やスキルが十分備わっていない」と判断され、採用に不利に働く恐れもあるでしょう。
勤続年数の長さで有給休暇の付与日数が変わる
年次有給休暇の付与日数は、勤続年数の長さによって変わります。厚生労働省の「労働基準法に関するQ&A『年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか』」によると、有給休暇は勤続年数が1年伸びるごとに付与日数も1~2日増加すると定められています。有給休暇の取得において、正社員・パートタイム労働者などの区分はありません。
ただし、有給休暇が付与されるには、規定の要件を満たす必要があります。雇入れの日から6ヶ月継続して勤務しており、その期間の全労働日の8割以上出勤していることが条件です。有給休暇の取得条件については「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」で詳細を確認してください。
参照元
厚生労働省
労働基準法に関するQ&A
一定の勤続年数がないと失業保険を受給できない
勤続年数は、失業保険の受給にも影響します。失業保険受給の条件は、原則として「離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月あること」です。勤続年数が短く十分な被保険者期間がない場合は、失業保険を受給できません。なお、離職理由が会社の倒産や解雇の場合は、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月必要です。
失業保険の受給条件を詳しく知りたい方は「失業保険の受給条件は?給付日数やもらい方などもあわせて紹介!」をご覧ください。
勤続年数によって退職金の額が異なる
勤続年数によって退職金の額が変化します。基本的には、勤続年数が長くなるにつれて退職金の額も増えることが多いでしょう。ただし、退職金の額は、勤続年数だけではなく、企業の規定や退職理由などによっても変化します。勤続年数の長さを気にし過ぎる必要はありませんが、少なからず影響があることは認識しておきましょう。
就職・転職活動を行う際は、平均勤続年数も含め、各企業の情報を入念に調べることが大切です。就職後に「もっとしっかりと調べておけば良かった」「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、企業研究は丁寧に行いましょう。
「就職・転職活動は初めて」「情報収集に不安がある」という方は就職エージェントを活用するのがおすすめです。就職・転職エージェントのハタラクティブは、既卒・フリーター・第二新卒など、若年層の就職・転職に特化しています。経験豊富なアドバイザーが丁寧にカウンセリングを行い、一人ひとりにぴったりの求人をご紹介。マンツーマン体制で書類作成や面接対策などをサポートします。サービスの利用はすべて無料のため、就職や転職活動に不安がある方はお気軽にご相談ください!
勤続年数の数え方に関するFAQ
勤続年数の数え方に関してよくある質問にQ&A方式で回答します。
新卒入社した新入社員の勤続年数の数え方は?
新卒で入社した場合の勤続年数は、入社日の翌日から計算し、退職する日までの期間を通算して算出します。たとえば、4月1日に入社した場合、翌年の3月31日に退職すると「勤続1年」、4月2日以降だと「勤続2年」です。入社して1年が経過する前に退職した場合は「勤続1年」と数えます。
複数の会社に勤めた場合の勤続年数の数え方は?
複数の会社に勤めた場合は、会社ごとに勤続年数を計算するのが基本です。ただし、転職時に退職金が未支給であるなど特定条件を満たせば、前職の期間が考慮され、退職金や福利厚生で勤続年数を通算するケースもあります。
パートから正社員になった場合の勤続年数の数え方は?
基本的には、パートやアルバイトとしての勤務期間も含めて勤続年数を計算するのが一般的です。雇用形態が変わっても契約が継続していると判断されます。ただし、勤続年数の取扱いは会社によってさまざまです。退職金や昇給の計算において、雇用形態ごとに勤続年数を区別する場合もあります。雇用形態を変えて勤務を続ける場合は、契約内容や会社の就業規則を確認しておきましょう。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?
マーケティングアシスタント
東京都
年収 315万円~360万円
正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!
ライター・取材担当
東京都
年収 315万円~360万円
未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?
営業
東京都
年収 328万円~374万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆
ルート営業
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…
年収 228万円~365万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「お役立ち情報」についての記事一覧
- 「ビジネス用語」についての記事一覧
- 勤続年数とは?正しい数え方や転職・失業保険・退職金・有休への影響を解説