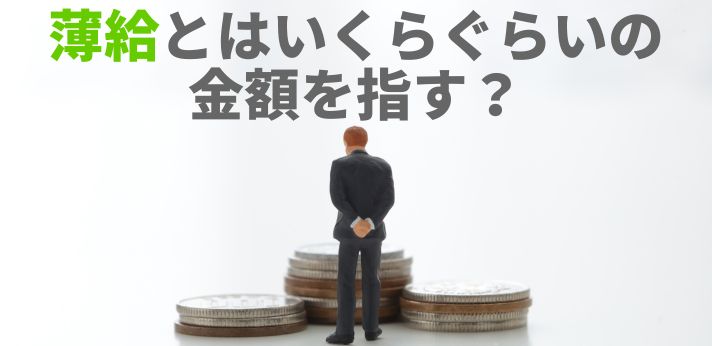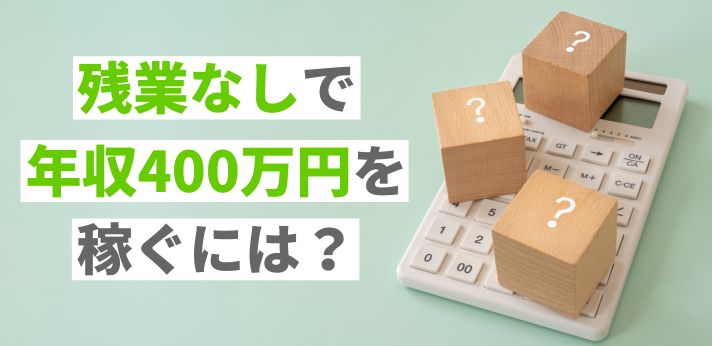貯金額の平均はどのくらい?おすすめの貯金方法を紹介貯金額の平均はどのくらい?おすすめの貯金方法を紹介
更新日
公開日
「20代の平均貯金額はどのくらい?」と気になる方もいるでしょう。20代の平均貯金額は、約110万円と公表されています。ただし、毎月貯金できる金額は人によって異なるため、いくら貯めるかよりもコツコツと継続をすることが大切です。
このコラムでは、貯金額の平均のデータや貯蓄を増やす方法などをご紹介しています。将来のために貯金額を増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
年齢別の貯金額の平均
しかし、40代で保有率が減少していることから、資産形成の方法やライフイベントによる支出があると考えられるでしょう。
| 年代 | 金融資産を保有している | 金融資産を保有していない | 総数(預貯金残高保有世帯) | 現在保有している預貯金残高合計(万円)※ |
|---|
| 20代 | 56.1% | 43.9% | 145 | 110 |
| 30代 | 66.0% | 34.0% | 68 | 183 |
| 40代 | 59.6% | 40.4% | 86 | 266 |
(※)金融資産非保有世帯のうち、問2(a)1(預貯金の合計残高)で回答があった世帯の平均値。
高校卒業後、仮に貯金額が0円とすると、20代の最後である29歳までに110万円を貯金するには年間で約10〜11万円、1ヶ月で9千円〜1万円程度貯めるのが理想といえます。
下表は、金融広報中央委員会の「金融資産保有額」に関するデータを年代別にまとめたものです。
| 年代 | 100万円未満 | 100~200万円未満 | 200~300万円未満 | 300~400万円未満 | 400~500万円未満 | 500~700万円未満 | 平均 | 中央値 |
|---|
| 20代 | 40.9% | 19.5% | 9.4% | 8.8% | 4.5% | 7.1% | 219万円 | 103万円 |
| 30代 | 22.0% | 9.3% | 11.2% | 9.3% | 6.1% | 8.4% | 912万円 | 300万円 |
| 40代 | 18.7% | 8.8% | 6.7% | 6.2% | 4.1% | 7.8% | 964万円 | 500万円 |
平均値とは
平均値は、すべてのデータを合計し、そのデータ数で割ることで算出されます。データ全体の傾向を把握しやすいという利点があります。
たとえば、5人の貯金額が10万円、20万円、30万円、40万円、50万円だった場合、合計は150万円です。これを5で割ると、平均値は30万円になります。このように、平均値はデータ全体の傾向を一つの数値で表すために便利です。
ただし、極端に高い数値や低い数値が含まれると、実際の状況とは異なる印象を与えることがあるため注意が必要です。
中央値とは
中央値とは、データを小さい順や大きい順に並べたときに、ちょうど中央に位置する値のことです。
たとえば、5人の貯金額が10万円、20万円、30万円、40万円、50万円だった場合、30万円が中央値になります。もし、データの数が偶数で中央に位置する値が2つある場合は、その2つの平均値を取ったものが中央値です。
中央値は極端に大きい値や小さい値の影響を受けにくく、データの真ん中にある典型的な値を知れるメリットがあります。
しかし、極端なデータの影響を受けない一方で、データ全体のばらつきや傾向を把握しにくいというデメリットもあります。データ全体の傾向を把握するには、平均値と併せて見るのが効果的です。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
20~30代は「先取り積立」で貯める習慣を身につけよう
20~30代は、収入が増える前に「先取り積立」を習慣化しましょう。将来に備えるためには、若いうちから投資や貯金をしておくのがポイントです。以下で詳しく解説していきます。
緊急時や近い将来に必要なお金を貯める
緊急資金として、病気やケガで働けなくなったときのために、最低3ヶ月分の生活費を用意しておくと安心といわれています。緊急時や近い将来に必要なお金を貯めることは、生活の安定に欠かせないでしょう。
また、住宅購入や子どもの教育費など、10年以内に使うお金も計画的に貯める必要があります。少しずつでも、コツコツと貯めることが大切です。
将来に備えるためのお金を貯める
10年以上使う予定がないのであれば、貯蓄だけでなく投資を検討するのも一つの方法です。まとまったお金がなくても、毎月少額からの積立投資で無理なく始められます。
たとえば、投資信託の積立なら、毎月1万円や3万円など一定額をコツコツと投資でき、計画的に資産を増やすことが可能です。将来のために少しずつでもお金を増やす方法として、投資を活用してみましょう。
高卒が貯金するのは難しい?
高卒の社会人1年目や2年目など仕事を始めて間もないころの月収では、すぐに高額な貯金をするのは難しいでしょう。厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、20~24歳の大卒の平均月収が23万9,700円なのに対し、高卒は21万6,200円と少し低めです。
| 年齢階級 | 高卒 | 大卒 |
|---|
| 20~24歳 | 21万6,200円 | 23万9,700円 |
| 25~29歳 | 24万700円 | 27万2,600円 |
| 30~34歳 | 25万8,500円 | 30万9,000円 |
| 35~39歳 | 27万6,800円 | 35万4,100円 |
| 40~44歳 | 29万3,400円 | 39万4,700円 |
引用:厚生労働省「第3表 学歴、性、年齢階級別賃金及び対前年増減率」
しかし、無理に大きな金額を貯めることが重要なのではありません。少額でも毎月コツコツと貯金を続けることを習慣化すれば、将来的に必要な資産を築けるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
貯金額を増やすために意識したい6つのポイント
すぐに高額な貯蓄をするのは難しいですが、工夫次第で貯金額を増やすことは可能です。以下では、貯金を増やすために意識したいポイントを紹介します。
- 家賃を抑える
- 水道光熱費を節約する
- 収入と支出を見直して管理する
- クレジットカードは慎重に使う
- 目標貯金額を決める
- 口座を目的別に分ける
1.家賃を抑える
一人暮らしを始める際は、譲れない条件と妥協できる条件を整理して部屋探しを行いましょう。毎月の生活費の中で、特に大きな負担となるのが家賃です。要望をすべて満たそうとすれば当然家賃は高くなり、貯金が難しくなるだけではなく、生活費の余裕もなくなります。
2.水道光熱費を節約する
普段から意識的に電気・ガス・水道の使い方に気をつければ、水道光熱費を減らすことが可能です。外出時に電気のコンセントを抜くだけでも節電効果があります。
また、今よりも基本料金が安い電力会社やガス会社に切り替えるのもおすすめです。
3.収入と支出を見直して管理する
毎月の収入と支出を見直せば、年間の貯金額を増やせるでしょう。毎月の赤字分をボーナスでカバーする方法より、1ヶ月分の生活費を月収内で抑えれば貯金を大幅に増やせます。
また、1ヶ月の予算を設定するのではなく、平日や1週間ごとに使える金額を決めることで、支出をより細かく管理できます。さらに、外出時に持ち歩く現金を少なくして、無駄遣いを防ぐ工夫も効果的です。
4.クレジットカードは慎重に使う
水道光熱費やスマートフォン代などの固定費はクレジットカードを利用してポイントを貯め、普段はカードを持ち歩かないのもおすすめです。
また、クレジットカードの利用が多過ぎる場合は、カード会社に相談して利用限度額を引き下げることも一つの手です。自分の収入に見合った使い方を心掛けることで、無駄な出費を抑え、貯金を着実に増やしていけるでしょう。
5.目標貯金額を決める
「年間で○○円を貯金する」といったように、明確な目標貯金額を設定することも大切です。アバウトな金額設定をするよりも、具体的な金額を決めたほうがモチベーションが高まり、達成に向けた計画を立てやすくなります。
また、目標が明確であれば、毎月の貯金額や支出の見直しなど、日常の行動にも意識が向きやすくなるでしょう。最終的に「これだけ貯めたい」というゴールを持つことで、貯金の習慣がより確立されやすくなります。
6.口座を目的別に分ける
貯金がなかなか増えないと感じる方には、口座を目的別に分ける方法がおすすめです。給与が振り込まれる口座とは別に、貯金専用の口座を用意することで、使うお金と貯めるお金を明確に分けられます。
さらに、毎月一定額を貯金専用口座に自動的に振り込む設定にすることで、手間なく計画的に貯金を増やせます。この方法を取り入れることで、日常の支出管理がしやすくなり、自然と貯蓄の習慣を身につけられるでしょう。
ポイント:毎月の貯金額の目安
毎月の貯金額の目安は、収入の10~20%を目指すと良いでしょう。たとえば、手取りが20万円なら2~4万円、30万円なら3~6万円が適切です。
貯金額を増やすことは可能ですが、無理な節約は避け、長期的に続けられる金額を設定しましょう。
おすすめな4つの貯金方法
おすすめな貯金方法として、「先取り貯金」「財形貯蓄制度」「貯蓄型保険」「つみたてNISAやiDeCo」の4つが挙げられます。貯金額を増やしたい高卒の方はぜひ参考にしてみてください。
- 先取り貯金
- 財形貯蓄制度
- 貯蓄型保険
- つみたてNISAやiDeCo
1.先取り貯金
貯金額を増やしたい方は、先取り貯金をしてみましょう。先取り貯金とは、毎月の収入から一定の金額を先に貯蓄へ回す方法です。毎月決まった金額を先に貯金することで、残ったお金で生活費やそのほかの支出をやりくりする習慣がつき、無駄遣いを防げます。
また、貯金専用の口座を作り自動的に振り込む設定にすると、無意識のうちにお金を貯められるのでおすすめです。少しずつでもコツコツと続けることで、将来的にまとまった貯金ができるでしょう。
2.財形貯蓄制度
財形貯蓄制度は、会社が導入している場合に利用できる貯蓄方法で、毎月の給与から一定額を天引きし、自動的に提携銀行へ送金して貯金する仕組みです。この制度を使うと、手元にお金が残らず無駄遣いを防げるため、計画的に貯金を進められるでしょう。
また、自分で貯金口座に移す手間がかからないこともメリットとして挙げられます。応募する企業に財形貯蓄制度が導入されているか事前に確認しておくと、効果的な貯金習慣を築く手助けになるでしょう。
3.貯蓄型保険
貯蓄型保険は、万一のときのリスクに備えながら貯蓄ができる制度です。毎月の保険料が、「満期保険金」や解約時の「解約返戻金」として返金されることが特徴です。
ただし、通常の掛け捨て型保険よりも毎月の保険料が割高なので、生活が苦しくならないようにバランスを考慮する必要があります。
4.つみたてNISAやiDeCo
つみたてNISAやiDeCoは、投資しながら貯蓄できる方法です。
2024年より、新NISAがスタートしました。新NISAでは年間投資枠が大幅に拡大しています。つみたて投資枠は40万円から120万円に、成長投資枠は120万円から240万円に増えました。これにより、非課税で得られる利益も増えるため、資産運用がより効率的に進められます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は自分で掛金を運用する年金制度で、掛金の全額が所得控除の対象となり、運用益も非課税です。ただし、60歳まで引き出せない点に注意が必要です。
どちらも、将来に備えた賢い貯蓄方法としておすすめです。
貯金額はライフプランによって変わる
貯金額は、住宅購入や教育費、退職後の生活資金など、人生におけるライフイベントに合わせて計画しましょう。以下では、主なライフイベントごとの一般的な費用を解説します。
子どもの教育に必要な資金
子どもの教育資金は、進学先によって大きく異なります。国公立か私立かでも費用が変わるため、早めに資金計画を立てておきましょう。
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校(全日制) |
|---|
| 公立 | 16万5,126円 | 35万2,566円 | 53万8,799円 | 51万2,971円 |
| 私立 | 30万8,909円 | 166万6,949円 | 143万6,353円 | 105万4,444円 |
公立に比べて、私立のほうが高額な費用がかかると分かります。
| 区分 | 入学料(入学年度のみ) | 授業料 |
|---|
| 私立大学 | 24万5,951円 | 93万943円 |
| 私立短期大学 | 23万7,615円 | 72万3,368円 |
| 私立高等専門学校 | 24万6,753円 | 62万7,065円 |
| 国立大学 | 28万2,000円 | 53万5,800円 |
| 公立大学 | 39万1,305円 | 53万6,363円 |
たとえば、高校・大学が私立、大学のみ私立、すべて国公立のパターンで教育費を比較すると以下のとおりです。
・高校、大学が私立:1,113万9,226円
・大学のみ私立:973万5,807円
・すべて公立、大学は国立:819万1,284円
上記のパターンでは、どのケースでも大学卒業までに1,000万円前後の費用がかかることが分かります。
ただし、公立校であれば高校までにかかる費用は比較的少ないため、この期間に貯蓄を増やすのが賢明でしょう。大学費用を中心に資金計画を立て、私立大学に進学する可能性を考慮すると、400〜500万円程度を目標に貯金しておくと安心です。
また、大学進学時に一人暮らしをさせる場合は、生活費の仕送りが発生する可能性があるため、追加の資金が必要になります。これも含めて余裕を持った資金計画を立てておきましょう。
マイホーム取得のための資金
マイホームといえども、「戸建住宅」「マンション」「中古住宅」などさまざまな選択肢があり、それぞれの物件タイプや地域によって価格が異なるため、自分に合った選択を見つけましょう。
マイホーム取得のための資金は、物件の広さや地域によっても価格に差があるため一概にはいえませんが、住宅金融支援機構が実施している「フラット35利用者調査(2022年度)」のデータを参考にするのがおすすめです。
| 種別 | 金額 |
|---|
| 土地付注文住宅 | 4,694万円 |
| 建売住宅 | 3,719万円 |
| マンション | 4,848万円 |
| 中古戸建 | 2,704万円 |
| 中古マンション | 3,157万円 |
全国平均の購入価格は、土地付注文住宅が約4,694万円、建売住宅が約3,719万円、マンションが約4,848万円、中古戸建が約2,704万円、中古マンションが約3,157万円となっています。このように、マイホームの価格は選択するタイプによって大きく異なります。
また、購入資金を準備する際には、頭金や諸費用も考慮に入れた計画が必要です。一般的に、頭金は物件価格の20%を目安にすると良いとされています。さらに、登記費用や仲介手数料など、諸費用も物件価格の5~10%程度かかることを念頭に置きましょう。
住宅ローンを組む場合は、無理のない返済計画を立てることが大切です。マイホームの取得は人生の大きな決断ですが、しっかりとした資金計画を立てれば、安心して夢を実現できるでしょう。
老後のための生活資金
退職後の生活では、主な収入源が年金となるため、年金で賄えない支出は貯蓄などから補うことが必要になります。そのため、年金収入と支出の差額を埋めるための資金をどれだけ準備するかが重要になるでしょう。
総務省の「家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)における平均的な収入は24万4,580円、消費支出は25万959円であることから、月額の不足分は6,379円です。退職後の生活を30年と仮定すると、約230万円が不足する計算になります。
しかし、このデータはあくまで平均的な生活費に基づいており、今後の物価の高騰や光熱費の値上がりなどによっては、さらに支出が増える可能性があります。ゆとりある生活や趣味、旅行などの充実した生活を送るには、早めの準備を心掛けましょう。
物価上昇が進むと「お金の価値」が下がるリスクがある
貯金は大切ですが、インフレによって物価が上がると、お金の価値が目減りしてしまうリスクがあります。
たとえば、現在の1,000万円が、毎年2%のインフレが30年続くと仮定した場合、30年後には552万円相当の価値しかなくなってしまうと考えられます。貯金だけでは将来の生活を支えられない可能性があるため、インフレに備えた対策が必要になるでしょう。
その対策の例として、株式や投資信託などの資産運用があります。投資信託は少額から始められ、運用のプロが資産を管理してくれるため、初心者も取り組みやすい方法です。お金の価値の目減りを補う効果が期待できるため、検討してみるのも良いでしょう。
上手に貯金するコツ
貯蓄が苦手な人や、なかなかお金が貯まらなくて困っている方は、貯金の目的や毎月の使える金額を決めてみましょう。以下では、上手に貯蓄するコツを解説します。
貯金の目的や目標額を決める
貯蓄の目的と目標額、そして「いつまでにいくら貯めたいのか」を明確に決めましょう。「毎月の収入の△%を貯金する」といった具体的な目標を設定するのも効果的です。
また、目標を設定するだけでなく、定期的にどれくらい達成できているのかを確認しましょう。その際、目的別に口座を分けておくとどれだけ貯まっているかが一目で分かり、管理がしやすくなります。
毎月の使える金額を決める
「食費」「交通費」「日用品費」など、支出の項目ごとに毎月の予算をあらかじめ決めておくことも、効率的に貯蓄するためのポイントです。予算を設定することで、収入を超える支出を防げるでしょう。
収入に応じた割合で各項目の予算を決めておけば、毎月の予算振り分けが簡単になります。迷わず計画的にお金を使えるため、必要な支出をカバーしつつ貯金も確保できるでしょう。予算を守ることで貯蓄の意識が高まり、将来的な目標に近づけます。
キャッシュレス決済を使う
キャッシュレス決済を利用すると、ポイント還元やキャッシュバックといった特典が得られ、現金での支払いよりもお得に買い物を楽しめます。
また、アプリを通じて利用明細を確認でき、日々の支出管理もスムーズになります。便利さゆえに使い過ぎる心配がある場合は、事前にチャージが必要なプリペイド型の決済サービスを選ぶのも良いでしょう。予算内での支払いが可能になり、無駄遣いを防げます。
貯金額が少ないと感じたときは転職するのもアリ
貯金額が平均と比べて少ないと感じたときは、転職を視野に入れても良いでしょう。転職をすれば、給与が上がったりボーナスが増えたりする可能性があります。
また、先述した「財形貯蓄制度」を導入している会社で働くのもおすすめです。
給与アップの転職を考えている方は、転職エージェントに相談するのも一つの方法です。エージェントとの面談では希望の給与を伝えられるので、「思っていたよりも給与が低かった…」といったミスマッチを防ぎやすいでしょう。
また、転職エージェントは事前に企業へ取材している場合もあり、職場のリアルな情報が手に入りやすいのもメリットです。
就職・転職エージェントのハタラクティブは、若年層を対象にした就活全般のフォローを行っています。経験豊富なキャリアアドバイザーがカウンセリングを行い、一人ひとりに合った求人をご紹介。書類添削や面接対策など、マンツーマンで手厚いバックアップを行っています。
「毎月十分な貯金をするために、今よりも給与の高い企業へ転職したい」「ライフプランに合わせた資金を用意したい」などの相談にもお答えしますので、就職・転職活動が不安な方も安心です。
サービスの登録・利用料はすべて無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
平均はどのくらい?貯金額に関するQ&A
「正直みんなはどのくらい貯金があるの?」と気になる方のために、貯金額に関する疑問をQ&A方式で解決します。
金融広報中央委員会のデータでは、110万円と発表されています。また、20代の金融資産の保有額は、100万円未満が40.9%、100〜200万円未満が19.5%という結果に。このことから、20代の約半数は金融資産保有額が200万円未満と分かっています。
詳しくは、このコラム内の「年齢別の貯金額の平均」をご一読ください。
参照元
金融広報中央委員会
各種分類別データ(令和5年)
月収の1〜3割を目安に貯金すると良いでしょう。
ただし、毎月貯金できる金額は人によって異なるため、大切なのは金額の大きさよりも継続をすることです。20代のうちから自分のライフスタイルと給与のバランスを考え、無理のない貯金をしましょう。「フリーターが貯金できないときの対処法は?毎月の貯金額を増やす方法を解説」では貯金のポイントをご紹介しているので、気になる方はご参照ください。
固定費を節約したり、クレジットカードの使い方を考えたりすることが大切です。クレジットカードをつい使い過ぎてしまう方は、固定費の支払いのみをカードで済ませ、持ち歩かないようにするのが効果的でしょう。
また、貯金専用の口座と給与が振り込まれる口座を分けるのもおすすめです。
貯金額を増やしたい方は、このコラム内の「貯金額を増やすために意識したい6つのポイント」をチェックしてみてください。
思い切って転職をするのも選択肢の一つです。給与アップが目的の転職であれば、モチベーションも維持しやすいでしょう。
なお、給与を重視して転職するなら、転職エージェントに相談するのがおすすめです。
若年層に特化した就職・転職エージェントのハタラクティブは一人ひとりの悩みに寄り添い、転職活動を全面的にサポートします。求人の紹介や面接対策だけでなく内定後のフォローも行うので、最後まで安心です。ご登録・ご利用はすべて無料です。一人で転職について悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。