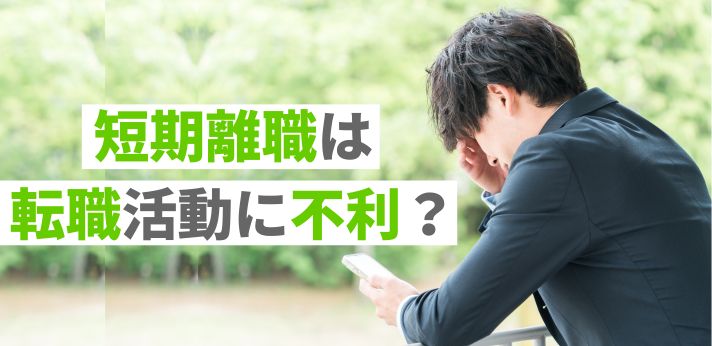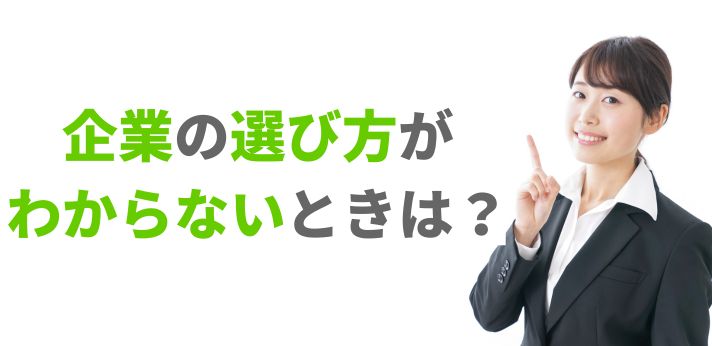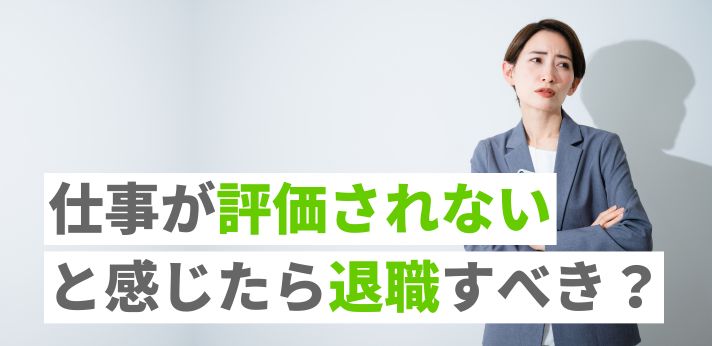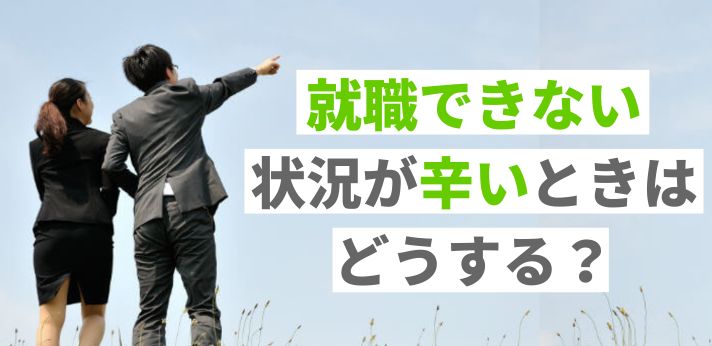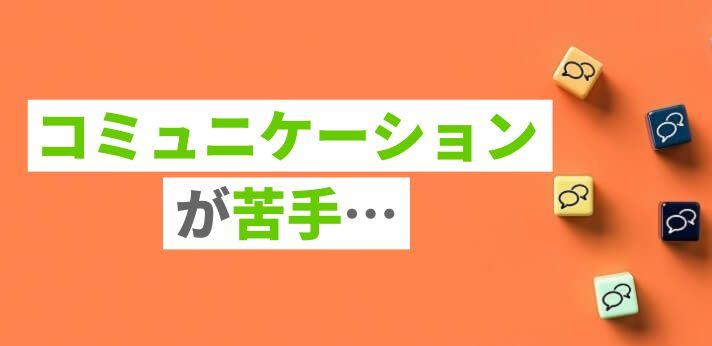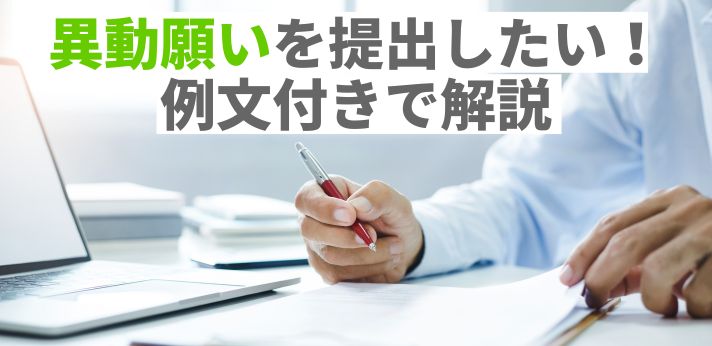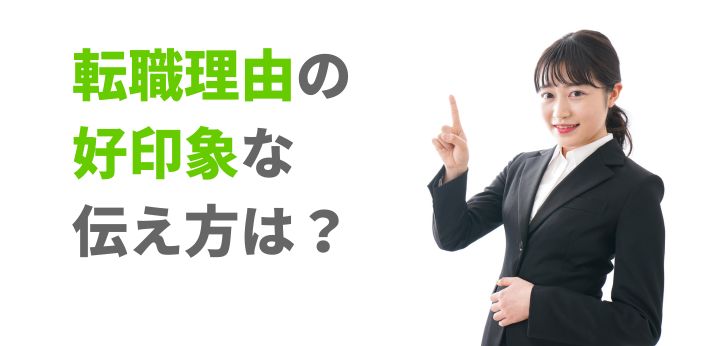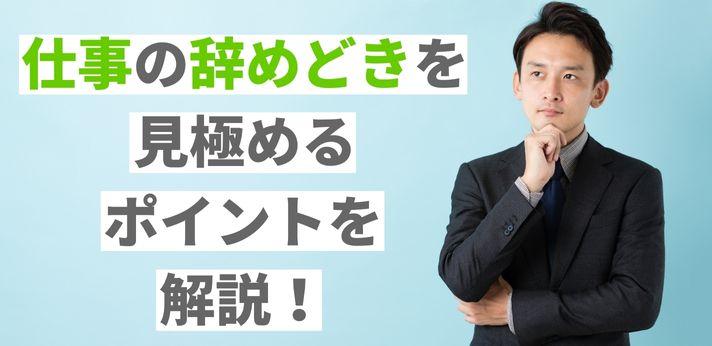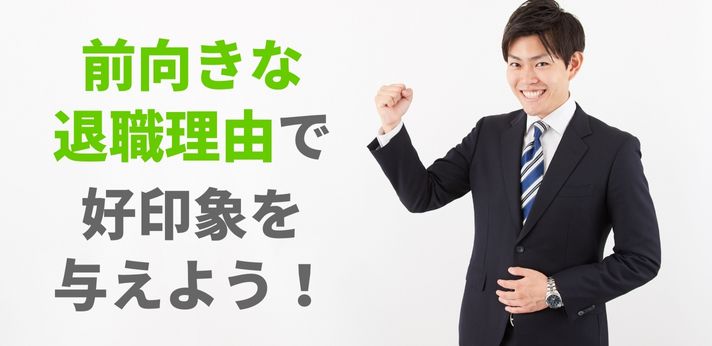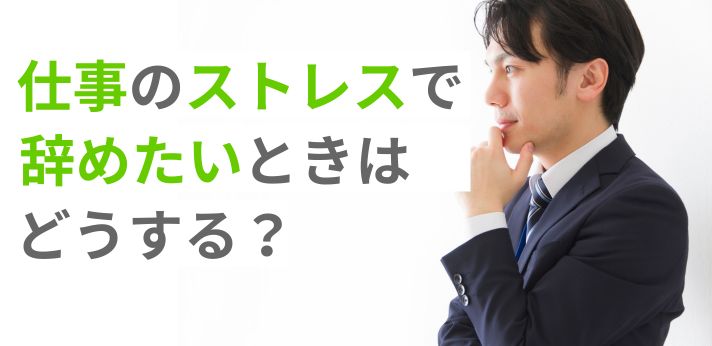「社風が合わない」を転職理由にできる?退職を検討すべき状況や注意点を解説「社風が合わない」を転職理由にできる?退職を検討すべき状況や注意点を解説
更新日
公開日
社風が合わないことで転職を考える際は、慎重に検討する必要がある
「社風が合わないから転職したい…」とお考えの方もいるのではないでしょうか。「社風」は、会社が自分に合っているか判断する材料の一つ。「社風が合わない」と感じたら、本当に社風だけが原因なのかを熟考してから転職を決断することが大切です。
このコラムでは、「社風が合わない」と感じたときの転職活動のポイントや退職の判断基準を解説します。また、職場を転職する前にできる対処法や注意点もご紹介するので、参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
「社風が合わない」を理由に転職しても良い?
「社風が合わない」という理由で転職しても問題はありません。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
しかし、一時的なトラブルや些細な理由で退職しても、転職先で同じ理由や悩みが起こる可能性は十分にあります。また、「社風が合わない」と感じるたびに辞めてしまうと、短期間での転職を繰り返す恐れがあるでしょう。
転職を考えているなら「社風が合わない」と感じる根本的な理由を探り、解決策も検討しましょう。
合わない会社をさっさと辞めるのはアリ?
自分の置かれている状況や退職したい理由によっては、さっさと辞めるのも一つの選択肢といえるでしょう。合わない会社で無理やり働き続けると、心身に不調をきたす恐れがあります。また、仕事に対するモチベーションが下がり、経験やスキルを得られず、転職市場での価値が下がってしまう可能性もあるようです。
経験やスキルを得られずストレスだけが蓄積していくような場合は、転職するほうが自分のキャリアのために良いと判断できることもあります。ただし、さっさと辞めるのがベストな判断かは慎重に検討する必要があるでしょう。
今の会社をすぐに辞めるべきか判断が難しい場合は、転職エージェントに相談するのも手です。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
「社風が合わない」が理由で転職を検討すべき状況
社風が合わないことが理由で「長期的な活躍を見込めない」「ストレスで心身に影響が出ている」などの状況に陥っている場合は、転職を検討するのが望ましい場合があります。以下でそれぞれを説明しているので、転職を検討している方は参考にしてみてください。
長期的な活躍を見込めない
今の会社で働き続けた将来を考えたとき、自分の成長が見込めなかったり、理想の働き方が叶わなかったりする可能性が高いなら、転職するのが望ましい場合があります。
転職して自分に合った環境に身を置くことで、スキルを発揮しやすく、より充実したキャリアを築ける可能性があるでしょう。
社風が合わないストレスで心身に影響が出ている
あまりにも社風が合わず心身に影響が出ている場合も、転職を考えるタイミングといえます。社風が合わないことでストレスが溜まり、業務に支障をきたしていたり精神的に追い詰められていたりする場合は、転職をして働く環境を変えることで改善する可能性があるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
よくある「社風が合わない」の例
一口に「社風」といっても、社内の雰囲気や仕事に対する考え方、会社の経営方針など、定義が明確に決まっているわけではありません。
以下で「社風が合わない」と感じる場合の例を具体的に紹介します。自分が「社風が合わない」と感じる理由を知りたい方は、参考にしてみてください。
よくある「社風が合わない」の例
- 社内の雰囲気と合わない
- 仕事に対する考え方や取り組み方が合わない
- 企業理念や経営方針が合わない
- 人事評価制度が合わない
社内の雰囲気と合わない
社内の雰囲気や企業文化に馴染めず、自分とは合わないと感じることがあります。
「上司の威圧的な態度や強い上下関係がある」「業務時間外の不要な連絡が多い」といった風土に苦手意識をもつ人もいるでしょう。会社に昔ながらの習慣や慣例が多かったり、トップの意見が絶対だったりする場合も、人によっては「合わない」と感じることがあります。
人間関係は「社風」ではない
上司や同僚など、社員一人が会社の社風そのものではありません。たとえば、上司が大雑把で仕事を細かく見てくれないことに不満を感じていても、「企業自体が大雑把な社風である」とは限らないでしょう。
退職を希望する理由が、社風なのか人間関係なのかは、対処法や自分に合った会社を探すためにしっかり見極める必要があります。もし、人間関係が原因であれば、人事や相談できる上司に掛け合うのも手です。
仕事に対する考え方や取り組み方が合わない
周りの上司や同僚たちの仕事に対する価値観や向き合い方が自分と異なり、「社風が合わない」と感じる場合もあるでしょう。
たとえば、「自分は時間を掛けてキャリアアップしたいのに、経験が少ないうちから管理職を任される」といった場合が該当します。自分の仕事のスタイルと合わないと感じて、転職を検討する人もいるでしょう。
企業理念や経営方針が合わない
企業理念や経営方針が自分の価値観や希望と異なり、「社風が合わない」と感じる場合もあるようです。
経営方針は経営者の意図が反映され、社員の働き方や考え方など組織の雰囲気を左右します。そのため、企業が重視していることと自分の価値観に相違があり、やりがいをもって働けない場合もあるようです。「職場の人と考え方が合わない」「自分らしい働き方ができない」といった懸念から、転職を考える人もいます。
人事評価制度が合わない
人事評価制度の評価基準に納得がいかないと、「社風が合わない」と感じることもあるでしょう。
会社の評価基準が曖昧だったり、そもそも評価の仕組みがなかったりすると、仕事のモチベーションが低下してしまうこともあります。「評価してもらえる職場で働きたい」と考えて、転職を検討する人もいるでしょう。
社風が合わない会社に入社してしまう理由
社風が合わない会社に入社してしまう原因として、「企業研究・自己分析が不十分」「焦って就職活動を進めた」などが考えられます。転職先で同じ悩みを抱えないためには、社風が合わないと感じる会社に入社してしまう理由を知っておくことが肝心です。
ここでは、会社とのミスマッチが起こる理由を詳しく解説するので、転職前にぜひご確認ください。
企業研究・自己分析が不十分
入社時の自己分析や企業研究が不十分だったために、自分と合わない会社に入社してしまう場合があるでしょう。
企業研究を十分に行わずに、会社のイメージや知名度、扱う商品・サービスだけを見て入社を決めてしまうと、働き方に目が向かず、ミスマッチを起こしやすい傾向があります。また、自己分析が不十分だと、自分の適性や強み・弱みが明確にならず、自分に合う社風を見極めるのは難しいかもしれません。
結果的に、入社してから違和感を覚え、不満や悩みにつながることがあります。
就職に焦って入社を決めた
焦って入社を決めた場合も、会社とのミスマッチを起こしやすいといえます。卒業間近なのに内定がもらえていなかったり、なかなか転職先が決まらなかったりした場合、焦りや危機感が先立ってしまい、よく検討せず内定が出た会社に入社してしまう人もいるでしょう。就職や転職することに焦っていると、求人情報に記載されている内容で会社を選んでしまい、自分に合った社風かどうか確認するのが後回しになりがちです。
自分に合った社風か確認するためにも、求人情報だけでなく会社説明会に参加したり、OB・OG訪問をしたりして、企業に関する情報を多く得るのが望ましいでしょう。
社風が合わない職場を転職する前にできる4つの対処法
社風が合わないからといってすぐに転職を決断するのではなく、退職をせずに解決できる方法を検討してみることが大切です。
ここでは、「社風が合わない」と感じる職場を転職する前にできる対処法を4つ紹介します。以下を参考に、転職前に対策をとってみてください。
社風が合わない職場を転職する前にできる対処法
- 信頼できる人に相談する
- コミュニケーションのとり方を意識する
- 時間によって解決するかを考えてみる
- 異動を依頼する
1.信頼できる人に相談する
社風が合わない企業を退職する前に、信頼できる人に相談してみてください。信頼できる上司や同僚に相談することで、職場環境の改善をしてもらえたり、対処法を一緒に考えてもらえたりするでしょう。また、客観的な意見をもらえることで、自分一人だと思い浮かばなかった解決策が見つかる可能性もあります。一人で悩まず、周囲の力に頼るのも一つの手です。
2.コミュニケーションのとり方を意識する
上司や同僚と「仕事に対する価値観が合わない」と感じている方は、コミュニケーションのとり方を見直すのも手です。
たとえば、相手のことを理解する意識をもって話を聞いたり、相手の立場になって考えたりすることで、その人なりの仕事に対する姿勢や考え方が見えてくるでしょう。
また、「コミュニケーションのとり方を意識しているのに合わない」という方は、無理に積極的なコミュニケーションをとるより、業務に必要な会話で留めるのも手です。仕事と割り切って社内の人と関わることで、気持ちが楽になる可能性があります。
3.時間によって解決するかを考えてみる
「社風が合わない」と感じる原因が、職場を変える必要があるものなのか、時間が解決できるものなのか考えてみるのもおすすめです。
たとえば、「入社後間もない」「異動してきたばかり」など、環境の変化によって「社風が合わない」と感じることもあるでしょう。しかしその場合は、時間が経って新しい環境に慣れることで、職場の雰囲気に馴染んだり、コミュニケーションがとりやすくなったりすることもあります。「合わない」と感じた原因に対処するのに転職が必要なのか、今一度見つめ直すことも大切です。
4.異動を依頼する
所属している部署やチームの雰囲気が合わないと感じる場合は、異動をすることで状況が改善される場合があります。異動をすることで、同じ会社にいながら新しい人間関係を築けるでしょう。
異動であれば会社を変える必要がないため、心身や経済的な負担を押さえて職場環境を変えることができます。転職を決める前に、上司や人事部に異動を申し出るのも一つの手です。
仕事とプライベートのメリハリをつけるのも有効
「社風が合わない」と悩む場合は、ストレスを溜めないためにも、仕事とプライベートのメリハリをつけることが大切です。退勤後や休日は自分の時間を楽しみ、リフレッシュする時間を確保することで、心にゆとりをもって仕事に向き合える可能性があります。
また、メリハリをつけて仕事と向き合うことで、「今の社風が仕事に支障をきたすのか」「転職するべきなのか」などを見直すきっかけになり得るでしょう。
一時的な感情に流されず、冷静に転職をすべきかを検討することを心掛けてくださいね。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
社風が合わないと感じて転職するときの注意点
冒頭でも述べたとおり、社風が合わないと感じて転職するのは悪いことではありません。しかし、「本当に転職を決めて良いのか」「感情だけで決めていないか」今一度考えてみましょう。
以下では、社風が合わないと感じて転職するときの注意点を詳しく説明しています。
「社風が合わない」と感じる原因を特定する
なぜ社風が合わないと感じるのか、原因を特定することで、転職時の会社選びに役立つでしょう。
原因を特定せずに転職活動に踏み切ると、入社後に同じ状況に陥り早期退職につながる恐れがあります。「合わない」と感じた場面を思い返し、具体的な原因を特定することで、社風が合わない会社を避けられるでしょう。
「社風が合わない」と言い訳にしていないか考える
本当はなんとなく転職したいだけなのに、「社風が合わないから」を言い訳にしていないか考えましょう。自分にとって都合の悪い内容を「社風が合わないから」という言い訳で片付けていては、転職は成功しません。
社風が合わないと感じる原因を深掘りし、転職を希望する理由を明確にすることが、転職成功への第一歩です。「仕事に対する考え方や価値観が異なる」「休みの日も業務連絡が来る風土に馴染めない」など、具体的な理由を探り出しましょう。
「社風が合わない」を理由に転職する際のポイント5つ
ここでは「社風が合わない」と感じて、転職する際のポイントを解説します。転職先で「社風が合わない」と感じて転職を繰り返すことを避けるためにも、以下を確認してみてください。
「社風が合わない」を理由に転職する際のポイント
- 自己分析を行って自分の価値観を明確にする
- 企業研究をして経営方針や社風を把握する
- 職場見学をする
- 面接で社風について質問する
- 転職理由はポジティブなものにする
1.自己分析で自分の価値観を明確にする
社風が合わないと感じて転職する場合、自己分析を通じて自分の価値観を確認するのがポイントです。自分に合った社風の会社を見つけるために、客観的に自分を観察し、「どのような人間関係を望んでいるのか」「どのように業務を進めたいのか」など、自分の価値観を丁寧に分析しましょう。
自己分析で自分の価値観が明確になったら、社風の面で企業に求める条件を洗い出し、優先順位をつけることが大切です。求める条件がいくつもあると、自分の理想に完璧に当てはまる企業を探すのが難しくなってしまいます。
譲れない条件を2~3つ考えておくことで、幅広く自分に合う企業を探せるでしょう。
2.企業研究で経営方針を把握する
企業研究を行い、会社の社風を知ることもポイントの一つに挙げられます。
会社の社風を知るのに効果的なのが、会社のWebサイトです。会社のWebサイトには、経営者の紹介や考え方が掲載されている傾向にあるでしょう。経営者の考え方は会社全体に社風として反映されることがあるので、社風を見極める一つの要素となります。
SNSや口コミの情報を参考にする
会社が発信しているSNSをチェックすれば、職場がどのような雰囲気なのか、どのような人たちが働いているのか確認できる可能性があります。また、元社員が会社について口コミを投稿しているWebサイトの情報では、実際に会社で勤務経験がある人の意見を知ることができるでしょう。
ただし、口コミサイトは誰でも記載でき、情報の信憑性が低いため、あくまでも参考程度に捉えるのがおすすめ。不自然な高評価や低評価には注意し、複数の口コミを総合して判断するようにしましょう。
3.職場見学をする
実際に職場を見学することで、会社情報から読み取れなかった職場の雰囲気を、自分の目で確かめられるでしょう。また、可能であれば、自分が希望する部署で働く社員と話す機会を設けてもらうのもおすすめです。仕事で関わる可能性がある社員がどのような人か知ることで、入社後のイメージが湧きやすいでしょう。
4.面接で社風について聞く
面接の逆質問で実際に社風について聞いてみるのも、具体的な社内の雰囲気を知るのに役立つでしょう。質問をする際には、求人情報や会社のWebサイト上で得られる情報をよく確認し、それを深掘りした質問をするのがコツです。
たとえば、「御社のWebサイトで、○○を大切にする社風があると拝見したのですが、実際にどのようなことに取り組まれていますか?」「御社ではどのような方が活躍されていますか?」など、具体的に社内の様子が分かる質問が望ましいでしょう。
5.転職理由はポジティブなものに言い換える
どのような事情があっても、転職理由はポジティブに言い換えるように心掛けましょう。社風が合わないことだけを転職の理由にすると、「社風だけで選んだのか」「社風が良ければどこでも良いのか」といった印象を与えてしまう可能性もあります。
そのため、社風が合わないと感じた原因を具体的に探り、「キャリアアップのため」「新しい環境でチャレンジするため」など、前向きな理由に転換して伝えることが大切です。
社風が合わないことで転職する際の面接のコツ
面接で「社風が合わなかった」とだけ回答してしまうと、採用担当者にきちんと理解してもらえない可能性があります。面接では、前職のどのような面で社風の合わなさを感じたのかを具体的に説明するのがポイントです。
前述したように、ポジティブな動機であることを強調し、退職理由の回答でも自分の魅力を伝えられるように心掛けてください。
社風が合わない場合の退職理由例文
では、面接で実際にどのように転職理由を伝えれば良いのか、例文をご紹介します。「成績だけを重視する社風があり、自分の努力を認めてもらう機会が少なかった」という理由で転職する場合の例文は以下のとおりです。
前職は個人の成績を重視する社風だったため、自分の業務パフォーマンスを最大限発揮することを心掛けていました。しかし、働くなかで個人のスキルを自分だけでなく、チームで活かす仕事がしたいと感じるようになりました。
そのため、社内全体で大きな事業を創り上げていくことを目指す会社に魅力を感じ、退職する運びとなりました。
上記のように、前職の不満は述べずに入社後に取り組みたいことを前向きに伝えるようにしましょう。
【まとめ】社風の合う会社探しはエージェントを活用しよう
社内の雰囲気や働く人の傾向は、会社のWebサイトやパンフレットなどである程度は確認できるものの、実際の雰囲気は入社してみないと分からないものです。転職してみたら「思っていた社風と違った」とミスマッチを感じることもあるでしょう。
このようなミスマッチを防ぐには、転職エージェントの活用がおすすめです。転職エージェントは掲載会社の社風や労働環境を確認しているので、自分に合う社風の会社を見つけやすくなります。企業研究を行ってもいまいち社風が掴めない場合は、利用してみるのも手です。
「自分に合った社風が分からない」「ミスマッチを減らして転職したい」という方は、ハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブは若年層に特化した就職・転職エージェントです。扱う会社や求人はスタッフが事前に訪問調査を実施しています。社風や社内の雰囲気、働く社員の傾向、実際の勤務環境など、求人情報だけでは分からないことをお伝えできるのが強みです。カウンセリングから内定まで専任のキャリアアドバイザーがサポートするので、まずはお気軽にご相談ください。
「社風が合わないから転職したい」と悩む方向けのFAQ
ここでは、「社風が合わないから転職したい」と悩む場合に抱えがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。
社風が合わないからといってすぐに仕事を辞めてしまうと、次の転職先でも同じ理由で早期離職してしまう恐れがあります。「本当に転職すべきかどうか」「転職せずに解決できないか」を考えてみることが大切です。具体的に何が合わなかったのかを分析し、次の転職先探しに活かしましょう。
ポジティブな内容に言い換えることを心掛けましょう。「社風が合わなかったから」とそのまま伝えてしまうと、「自社に転職しても同じ理由で退職してしまうのでは」と懸念を抱かれてしまう恐れがあります。「社風が合わない」と感じた原因を特定し、前向きな理由に変換するようにしましょう。
「社風が合わない」と感じたまま働くことでストレスが蓄積し、やがて「業務が楽しくない」「働きたくない」とモチベーションが低下してしまう恐れがあります。長く働ける職場を見つけるためにも、社風をチェックしてから応募することが大切です。
企業のWebサイトやパンフレットなどにある経営者からのコメントや、社内イベントの詳細で確認するのがおすすめです。また、社員インタビューのページもヒントになるでしょう。より具体的に知りたい場合は、企業訪問をする方法もあります。
会社選びの時点で自己分析や企業研究を徹底するのがおすすめです。もし、一人での会社選びに不安がある方は、転職エージェントに頼ることも検討しましょう。
「自分に合った社風の会社を探したい」という方は、ハタラクティブにご相談ください。ご相談いただいた方一人ひとりが、のびのびと働けるような会社を厳選してご紹介し、内定獲得に向けてサポートします。