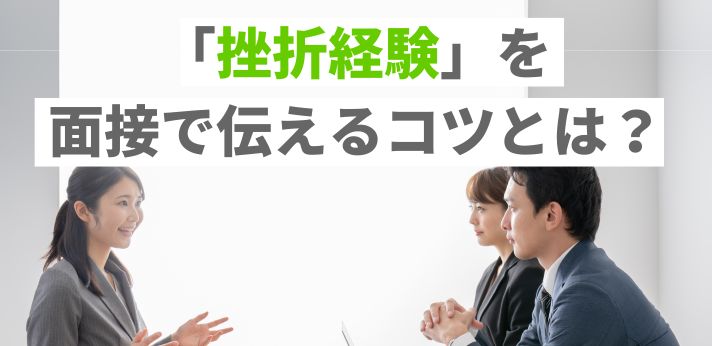転職理由をスキルアップにする際のコツとは?面接で評価される例文も紹介
更新日
公開日
転職をしてスキルアップを目指す決意をしたものの、「転職理由はスキルアップでいい?」と悩むこともあるでしょう。スキルアップを転職理由にする際は、志望動機につなげたり、志望企業を選んだ理由を踏まえて伝えるのがおすすめです。
このコラムでは、転職理由でスキルアップを伝える際のポイントや回答例をご紹介します。転職理由の内容に自信がない方や、思いつかない方は、ぜひ参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
転職理由は「スキルアップ」にしてもいい?
転職理由を「スキルアップ」にすることは可能です。「スキルアップしたい」という転職理由は、企業から「成長意欲がある」と思われ、高評価につながる可能性があります。
スキルアップ以外によくある転職理由とは?
スキルアップ以外によくある転職理由は以下のとおりです。
- ・職場環境を変えたい
・年収を増やしたい
・評価制度が整っている環境で働きたい
・将来性のある企業で働きたい
・違う業種や職種に挑戦したい
「スキルアップしたい」という理由以外で転職を考える理由には、職場の人間関係や年収や評価制度に不満を感じていることが挙げられるでしょう。また、「将来性のある企業で長く勤めたい」「未経験の業界や職種にチャレンジしたい」と、今後のキャリアを考えた転職理由も多い傾向にあります。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
転職理由の「スキルアップ」を企業側が見るポイントは?
ここではスキルアップを転職理由にした際に、企業が評価するポイントを紹介します。
以下では、転職理由を聞いて企業が判断することを「磨きたいスキルが自社で身につく場合」と「転職しなくてもスキルアップできる場合」に分けて説明しているので、自分の状況と照らし合わせてみてください。
磨きたいスキルが自社で身につく場合
磨きたいスキルが志望企業で身につく場合、企業は応募者がスキルアップして、どのように自社に貢献してくれるか確かめる傾向にあります。
そのため、「スキルアップしたい」という自分の目的だけでなく、「身につけたスキルを活かして業績を向上させたい」など、企業側にメリットがあることを伝えるのがおすすめです。「スキルアップしたい」という目的に焦点を当ててしまうと、「自分の成長のためだけなのでは」と懸念を抱かれる恐れがあるので注意しましょう。
転職しなくてもスキルアップできる場合
転職をしなくても、現在勤めている企業でスキルアップが望める場合は、「なぜ自社でスキルアップしたいと思ったのか」を疑問に思うでしょう。そのため、「前職でスキルアップできなかったのか」「志望企業でなくてはいけない理由」を明確にすることが大切です。
また、面接でも「現職での異動や別の事業に参加することで、転職せずスキルアップが可能でないか」などと指摘されることを想定して回答を考えておくことが望ましいでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
企業側が転職理由で確かめていること
企業側は応募者の転職理由で、「転職理由に一貫性があるか」「長く働いてくれるか」「自社の社風や求める人物像とマッチしているか」を確かめているでしょう。以下でそれぞれを詳しく解説します。
転職理由に一貫性があるか
企業側は応募者の転職理由に一貫性があるか判断しています。
転職理由の「スキルアップしたい」に対して、「仕事内容が合わなかった」「職場環境を変えたい」など、ほかの理由に焦点を当ててしまうと、面接官に「転職理由に一貫性がない」という印象をもたれる恐れがあります。
スキルアップしたいと思った経緯や、スキルアップした後の展望を中心に話し、伝える内容に一貫性をもたせるようにしましょう。
長く働いてくれるか
企業側は応募者が自社で長く勤めてくれるかどうか、転職理由で判断しているでしょう。企業側は採用活動にコストや時間を掛けていたり、長く勤めて組織を活性化してもらいたいと考えたりすることから、なるべく定着してくれる人材を求めています。
そのため、スキルアップを転職理由にする場合は、「スキルアップした後に辞めてしまうのではないか」という懸念を払拭するために、志望企業で携わりたい業務や目指したいポジションなどをあわせて伝えるのがおすすめです。
自社の社風や求める人物像とマッチしているか
企業は転職理由を通して、応募者の仕事に向き合う姿勢が自社の社風や求める人物像に合っているか確認しているでしょう。
企業にとって、社風や求める人物像とマッチしているかどうかは「応募者が無理なく働けるか」「応募条件を満たしているか」を判断する基準になります。
そのため、事前に企業のホームページや求人情報で、企業の社風や求める人物像を確認しておくことが大切です。
スキルアップを転職理由にするときの書き方のコツ
スキルアップを転職理由にするときは、「スキルアップを志望動機につなげる」「転職先でなければスキルアップできないことを伝える」など、書き方にポイントがあります。以下で書き方をチェックしておきましょう。
スキルアップを志望動機につなげる
転職理由をスキルアップにするなら、志望動機も関連付けた内容にしましょう。「スキルアップがしたい」という転職理由なのに、志望動機が「働きやすそうな環境だから」といったような内容では、「自社でスキルアップする気がないのか?」と面接官に疑問視されてしまいます。
転職理由としてスキルアップを伝えるなら、志望動機も「御社の○○の仕事では、△△な経験ができ、スキルアップができると考え志望しました」というように、スキルアップできそうな根拠を述べるのがおすすめです。
転職先でなければスキルアップできないことを伝える
スキルアップを転職理由にする際は、「職場を変えることで、どのようにスキルアップできるか」を主張するのがおすすめです。加えて、「そのスキルが企業にどう活かせるか」も伝えると、面接官は応募者が自社で活躍するイメージがしやすくなります。
ただし、「企業の教育制度を利用してスキルアップしたい」という内容では、面接官から「スキルアップを企業任せにしている」と思われてしまう恐れがあるので注意しましょう。
スキルは転職先で必要となるものを選ぶ
習得したいスキルが転職先の業務に関係ないものだと、企業に「自社でないほうがいいのでは?」と疑問を抱かれてしまう恐れがあります。
そのため、志望企業が行っている事業や、就きたい職種に必要なスキルを選択し、伝えるようにしましょう。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
習得したいものだけでなく既存のスキルもアピールする
スキルアップを転職理由にするなら、今あるスキルのアピールも忘れないようにしましょう。前職で身につけたスキルをアピールしないと、面接官から「前職でスキルアップできることはなかったのか」と不安視されてしまうでしょう。
また、中途採用の場合は、前職での経験やスキルが選考で重視されやすく、ある程度の即戦力が求められる傾向にあります。
今あるスキルで入社後も活かせるものがないか、前職での経験を深掘りしてみてください。
スキルアップを転職理由にするときの注意点
スキルアップを転職理由にする際に注意したいことには、「前職を批判する内容は避ける」「嘘やいい加減なことを言わないようにする」が挙げられます。以下で詳しく紹介するので、参考にしてみてください。
前職を批判する内容は避ける
転職理由を前職を批判するような内容にしてしまうと、志望企業にマイナスイメージを与える恐れがあるため避けましょう。
たとえば、「上司が○○なせいでスキルアップが叶わなかった」というような転職理由は、「責任転嫁している」という印象を与えかねません。スキルアップは自身の努力で成し遂げるもの。身に付かなかった理由を他人のせいにすると、面接官から「スキルアップの意思が弱い」とマイナスに思われるリスクがあります。
嘘やいい加減なことを言わないようにする
スキルアップを転職理由にするときは、嘘やいい加減なことを言わないように注意しましょう。たとえば、「印象が良さそうだから」という理由で転職理由をスキルアップにすると、面接官からの質問に答えていくうちに矛盾が生じて、嘘が発覚してしまうリスクがあります。面接官に「この応募者は嘘をついているかも」と思われると、信頼性が失われる恐れがあるため注意が必要です。
スキルアップを転職理由として伝える際の4ステップ
ここでは、スキルアップを転職理由として伝える際の4ステップを紹介します。スキルアップのために転職したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
1.スキルアップの目的を明らかにする
まずは、なぜスキルアップしたいのか目的を明らかにしましょう。スキルアップしたい目的という結論を述べることで、面接官に内容が伝わりやすくなります。
「仕事の幅を広げたい」「○○のスキルを身につけたい」「○○のスキルをさらに伸ばして企業に貢献したい」など、スキルアップの目的を簡潔に述べましょう。
2.スキルアップしたい理由を前向きに表現する
スキルアップしたいと思った理由を述べる際は、ネガティブな理由であっても、ポジティブに変換することが大切です。
転職理由が「企業の評価制度が整っていなかったから」「企業に将来性がなかったから」などの場合、そのまま伝えてしまうと企業にマイナスイメージをもたれる恐れがあります。
「スキルアップして新しい事業に挑戦したい」「自分のスキルがさらに活かせる環境で働きたい」など、前向きな表現を意識しましょう。
3.応募企業でスキルアップしたい理由を述べる
数ある企業のなかで、なぜ応募する企業でスキルアップしたいと思ったのか述べましょう。
たとえば、「自分のスキルを御社ならではの○○の事業で活かしたいと思った」「さらに高いスキルを習得するための制度が整っている点が魅力的だった」など、志望企業の魅力に思った点を伝えるのがポイントです。
上記のように企業が行う事業やスキルアップのための制度など、志望企業ならではの特徴を踏まえて述べることで、入社意欲も伝わりやすい可能性があります。
4.スキルアップ後に達成したいビジョンを伝える
最後に「スキルアップをし、○○職としてさらに成果を出したい」「将来○○の仕事に携わりたい」など、入社後のキャリアプランを具体的に述べましょう。
「スキルアップしたあと自社でどのように活躍してくれるのか」は企業側が応募者に期待するポイントの一つです。そのため、入社後の展望を具体的に伝えるようにしましょう。
スキルアップを転職理由にする際の例文
ここでは、転職理由がスキルアップの場合の例文をご紹介します。以下にご紹介するので参考にしてみてください。
営業職を希望する場合の例文
私は、「実践的な提案力を身につけたい」と思い、転職を決意しました。
現職では、営業職として取引先へ定期発注のやり取りを主に行っており、働くなかで、自分が提案した新商品・サービスをお客さまに売り込む仕事がしたいと思うようになりました。
御社の新規顧客へのアプローチを強みにしている点に魅力を感じました。これまで営業職で培ったコミュニケーション能力を活かしつつ、新規顧客とのやり取りで提案力を身につけてスキルアップし、御社に貢献したいと考えています。
事務職を希望する場合の例文
私は、WordやExcelを利用したデータ管理スキルを活用できる業務にチャレンジしたく、転職を決意いたしました。
現職では、事務職として書類の作成や整理、顧客管理を務めております。WordやExcelを使用して作成した書類が社内で評価されたことがきっかけで、より高いパソコンスキルが必要になる業務に携わりたいと思うようになりました。
御社ではAccessやICTツールを活用した新規事業に取り組んでいると存じております。新しい事務業務に携わることで、自身のスキルアップにつながるだけでなく、前職で培ったパソコンスキルを活かせる環境に身を置くことで業務の効率化にも貢献できると考えております。
入社後は、事務職のスペシャリストとして新規事業を支えていけるよう取り組んでまいります。
企画職を希望する場合の例文
私は、現職で培った市場ニーズを把握するスキルを活かして、新商品の企画に携わりたいと思い、転職を決意しました。
現職では、食品メーカーの企画職として売上向上を図るために既存商品の改良に携わっております。業務を行うなかで、新商品を一から企画し、業績を上げる仕事がしたいと思うようになりました。
御社は、新商品の開発が活発で、若手のスキルアップを推進する社風に魅力を感じました。
私も御社の一員として、これまでの経験を活かしながら新商品の企画に携わりたいです。
経理職を希望する場合の例文
私は、経理の経験を活かし、経営を支える財務の仕事で企業に貢献したいと思い転職を決意しました。
現職では、伝票入力や決算書作成など、幅広い経理業務に携わっております。事業活動を支える経理の仕事はやりがいがありますが、企業の事業展開に携わる財務の仕事にチャレンジしたいと思うようになりました。
御社は、資金調達や運用、財務状況の分析にもチャレンジできる環境であることが魅力に感じました。これまでの経験を活かし、企業全体を支える存在になりたいです。
「スキルアップできる転職先を見つけるには?」「一人で転職活動をするのが不安」という方は、ハタラクティブをご活用ください。
ハタラクティブは、転職未経験や第二新卒の方をはじめとする若年層に特化した、就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが丁寧なカウンセリングを実施し、一人ひとりに合った求人をご紹介します。
面接の日程調整もアドバイザーが行うので、スケジュール管理が苦手な方も安心です。サービスはすべて無料なので、ぜひお気軽にご登録ください。
スキルアップが転職理由の場合によくあるお悩みQ&A
ここでは、スキルアップを転職理由にする場合のお悩みをQ&A方式で解決します。
「前職ではスキルが身につかないから転職したい」とそのまま伝えるのは避けましょう。
転職理由が前職への不満として伝わると、面接官にマイナスなイメージを与える恐れがあります。転職理由では、入社後に志望企業で取り組みたいことや、キャリアプランを前向きに話すことで、入社意欲や仕事に対して前向きであることがアピールできるでしょう。
面接で話すキャリアプランを作るコツは「面接向けのキャリアプランを作るコツと答え方は?新卒・転職者の例文を紹介」で紹介しているので、あわせてご一読ください。
「キャリアアップが望めない」「企業の将来性がない」などの理由で転職する場合は、前職を否定せず、ポジティブな理由に変換するようにしましょう。
前職を否定してしまうと、「自社でも同じ不満が生まれるのではないか」と、面接官に懸念を抱かれてしまう恐れがあります。
そのため、転職理由では「○○のポジションを目指したい」「新たな業務に積極的にチャレンジできる環境で働きたい」など、キャリアアップしたい気持ちを前向きに伝えるのがおすすめです。
転職でキャリアアップを目指したい方は、「転職してキャリアアップを目指すのは難しい?成功のコツとできる人の特徴」のコラムも参考にしてみてください。
第二新卒の転職理由も「スキルアップしたい」は可能?
第二新卒の方が転職理由をスキルアップにすることは可能です。第二新卒の方のなかには、「以前からやりたかったことに挑戦する」「専門性を高めたい」など、ポジティブな理由で転職する方もいます。
転職理由を話す際は、前職で経験したことや学んだこと、スキルアップしたいと思ったきっかけなどを伝えると熱意や成長意欲が伝わるでしょう。
第二新卒の方の転職理由については、「第二新卒の転職理由はどう伝える?ネガティブな印象を与えない例文も紹介」のコラムで解説しているので、あわせてご一読ください。