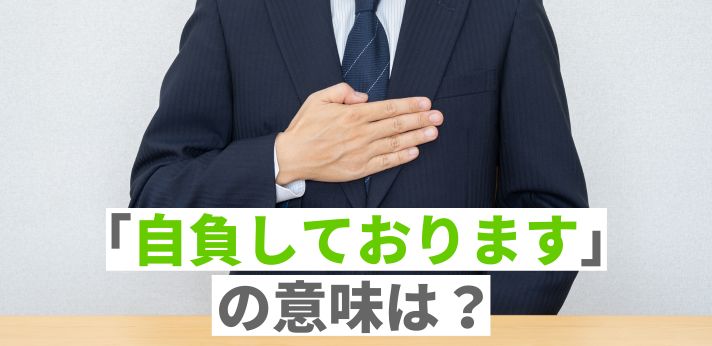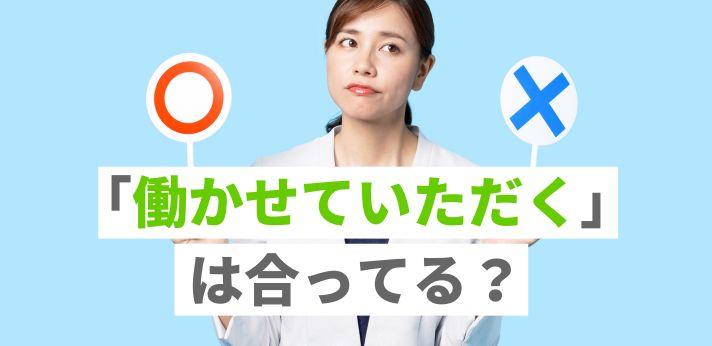リモートワークとは?テレワークと違う?メリット・デメリットも詳しく解説リモートワークとは?テレワークと違う?メリット・デメリットも詳しく解説
更新日
公開日
リモートワークとは、会社以外の場所で仕事をする働き方のこと
「リモートワークってどんな仕事のこと?」と思う方もいるでしょう。リモートワークとは、会社以外の場所で仕事をする働き方であり、テレワークと大差はありません。
このコラムでは、リモートワークの定義や働き方、メリット・デメリットなどを解説します。また、テレワークとの違いや、快適にリモートワークができる企業の特徴もまとめたので、自分に合った働き方が可能な求人を探すための参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
リモートワークとはどんな仕事のこと?
リモートワークとは、オフィス以外の場所で働くことを意味します。英語で「remote work」、遠隔で働くという意味で、自宅やサテライトオフィス、カフェなど会社とは離れた場所で仕事を行う勤務形態です。
リモートワークの働き方については、後述する「リモートワークの主な働き方」で詳しく紹介します。
リモートワークとテレワークの違い
在宅での仕事を「リモートワーク」ではなく「テレワーク」と呼ぶことがあるものの、両者には大きな違いはないといえます。
テレワークとは、英語のtele(遠い)work(仕事)を合わせた言葉で、「離れた場所での業務」という意味です。総務省の「テレワークの推進」では、「テレワークとは、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義づけられています。前述したリモートワークの定義と重なるため、テレワークとリモートワークは同一であるととらえて問題ないでしょう。
「雇用型」と「自営型」がある
リモートワークには、「雇用型」「自営型」という雇用形態があります。
「雇用型」とは、企業に所属して仕事をする働き方のことであり、「自営型」とは、企業に所属せず、個人事業主として働くことです。雇用型の場合、会社全体で同じチャットツールや勤怠管理システムなどを使用することになるでしょう。
一方、自営型では自営業のほかに、IT系エンジニア職やデザイナー、コールセンターなど、業務委託としての求人もあります。ただし、自営型の場合は企業による社会保障はなく、収入も不安定なのがデメリット。急に仕事を失うリスクもあるので注意が必要です。
フルリモートワークとは
フルリモートワークとは、出社することなく、常にオフィス以外の場所で仕事をする働き方のことです。リモートワークもオフィス以外の場所で働くことを意味しますが、「フル」が付いていない場合、出社が必要なときがある可能性も。出社の可能性があるかどうかが、リモートワークとフルリモートワークの違いとして挙げられるといえます。
「フルフレックスとは?メリット・デメリットとフルリモートとの違い」のコラムでは、フルリモートワークのメリット・デメリットを紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
リモートワークの主な働き方
ここでは、仕事の場所を自由に選べるリモートワークの具体的な働き方について解説します。ただし、「在宅のみ」「自宅またはサテライトオフィス」と場所を限定する企業もあるので、すべてのリモートワークで以下の働き方が認められるわけではない点に注意が必要です。
在宅勤務
在宅勤務とは、会社へ出社せず自宅で働く勤務形態です。原則自宅にいることが前提のため、会社とは電話やメール、チャットなど、さまざまなツールやシステムを活用して連絡をとります。在宅勤務は、自宅で落ち着いて仕事に取り組みたい人や、長時間家を空けられない人に向いている働き方といえるでしょう。
モバイルワーク
モバイルワークとは、外出先や移動中に仕事をすることです。スマートフォンやノートパソコンなどを使用し、カフェやホテル、新幹線などで業務を行います。
時間を有効活用できるのが魅力ですが、端末の紛失やデータの抜き取りなどセキュリティリスクが高い点に注意が必要です。そのため、企業側は暗号化ツール・システムの導入やルールの徹底といった対策に力を入れています。
サテライトオフィス勤務
サテライトオフィスとは、本社や支店から離れた場所に設置されたオフィスです。従業員がスムーズに業務を行えるよう、通信設備や働きやすい環境などが整っています。
また、企業専用のサテライトオフィスを設ければ社内用回線が引けるので、情報漏洩も防げるでしょう。近年では、個人で気軽に利用できるコワーキングスペースも増えています。
ノマドワーク(ノマドワーカー)
ノマドワーク(ノマドワーカー)とは、英語のnomad(遊牧民)とwork(働く)を組み合わせた言葉で、会社以外の場所で仕事をすることを指す言葉です。近年、リモートワークやフリーランスの増加に伴い普及しつつある働き方といわれています。
リモートワークと意味の違いはないものの、ノマドワークは企業に雇われている場合と個人事業主として働く場合、どちらも当てはまるのが特徴です。
クラウドソーシングはリモートワークの働き方に含まれる?
クラウドソーシングとは、インターネットを通じて複数の人々にタスクやプロジェクトを分担して仕事をしてもらう仕組みのことです。クラウドソーシングは仕事の発注形態を意味する言葉のため、オフィス以外の場所で働くリモートワークとは直接的な関係はありません。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
リモートワークで働くメリット・デメリット
リモートワークで働くうえで、「通勤や出社のストレスが減る」「時間が有効に使える」といった点はメリットです。しかし、コミュニケーションの取りにくさや、仕事とプライベートの切り替えの難しさといったデメリットも存在します。そのため、働き方を選ぶ際は、メリットとデメリットを把握したうえで判断することが大切です。
以下で、リモートワークで働くメリット・デメリットを紹介するので参考にしてみてください。
メリット
リモートワークによって働き方の選択肢が増えるのは、従業員に大きなメリットをもたらします。リモートワークなら「自分のペースで仕事に取り組みたい」「家族と過ごす時間を増やしたい」といった希望を叶えやすくなるため、ストレスの軽減やモチベーションの向上も期待できるでしょう。
リモートワークで働くメリット
- ストレスが減る
- 育児や介護との両立が図れる
- 時間の有効活用ができる
- 住む場所の選択肢が広がる
- 生産性が上がる
1.ストレスが減る
リモートワークで働くメリットとしてまず考えられるのが、人間関係のストレスが減ることです。出社する機会が減ることで、直接オフィス内の人と関わる機会も少なくなります。人間関係にストレスを感じやすい場合、リモートワークであれば心の負担を軽くして業務を進められるため、仕事の効率を上げる効果も期待できるでしょう。
また、リモートワークで働けるようになると、通勤によるストレスが減る可能性が高いこともメリットといえます。長時間の移動や満員電車での通勤を負担に感じている場合、通勤がなくなることで体力的・精神的な負担が減るため、生産性の向上に期待できるでしょう。
2.育児や介護との両立が図れる
リモートワークで働けば、介護や育児との両立が図れるのもメリットの一つです。働く意思があっても、時間の制約からやむを得ず退職を選ぶ方も少なくありません。しかし、リモートワークなら自宅で働けて時間にも余裕ができるため、プライベートと仕事を両立しやすいでしょう。
3.時間の有効活用ができる
前述のとおり、リモートワークでは通勤の必要がありません。そのため、通勤にかかっていた時間で家事を進めたり趣味の充実を図ったりするなど、有効活用できるでしょう。リモートワークで時間に余裕が生まれることで、ワークライフバランスを保ちやすくなるといえます。
また、副業が認められている企業であれば、時間がなくてできていなかったサイドビジネスやボランティアなどにも挑戦が可能です。新たな知見や人脈が増えれば、本業の業務に活かせる可能性もあるでしょう。
4.住む場所の選択肢が広がる
リモートワークの場合、出社することは少ないため、会社から離れた場所に住むことも可能です。家賃の安い郊外や実家に近い場所などを選べるのはメリットといえるでしょう。
また、将来パートナーの転勤に付いていくことになったり、家族の介護が必要で実家に帰らなくてはならなくなったりすることも考えられます。自己都合で遠方に引っ越さなければならなくなった際に、リモートワークであれば会社を辞めずに済む可能性がある点もメリットです。
5.生産性が上がる
リモートワークを行うことにより、生産性の向上が期待できることもメリットの一つ。厚生労働省の「テレワークを巡る現状について」によると、企業側が感じたテレワークの効果は以下のとおりです。
| 順位 | 回答 | 割合 |
|---|
| 1位 | 働き方改革が進んだ(時間外労働の削減) | 50.1% |
| 2位 | 業務プロセスの見直しができた | 42.3% |
| 3位 | 定型的業務の生産性が上がった | 17.0% |
「テレワークを取り入れたことで生産性が上がった」と答えている企業が一定数いることから、リモートワークは生産性の向上に一定の効果があると考えられます。
働く人のなかには、自宅から会社までの距離が遠く通勤だけで疲れてしまったり、周りに人がいると集中できなかったりする方もいるでしょう。その場合、リモートワークになることで、疲れや注意力の散漫による業務への影響が解消されるため、生産性の向上に期待できるでしょう。
デメリット
メリットが多いリモートワークですが、コミュニケーションが取りにくかったりプライベートとの切り替えが難しかったりとデメリットを感じることも。ここでは、従業員が感じやすいリモートワークのデメリットについて解説します。
リモートワークで働くデメリット
- ほかの社員とのコミュニケーションが取りにくい
- プライベートとの切り替えが難しい
- 運動不足になりやすい
- やりがいや達成感を得にくい
1.ほかの社員とのコミュニケーションが取りにくい
リモートワークでよくあるデメリットには、コミュニケーションの取りにくさが挙げられます。出社の必要がなくなることから従業員同士が対面で接する機会が減るため、挨拶やちょっとした世間話などができず、仕事の息抜きが難しくなる懸念があるでしょう。
また、リモートワークでは気軽に声を掛けにくく、コミュニケーション不足によるトラブルの芽を摘めなくなることも。気づかないうちに問題が大きくなるのを避けるためには、オンラインツールやシステムを活用し、従業員同士で積極的にコミュニケーションを取るのが大切です。
2.プライベートとの切り替えが難しい
リモートワークでは、プライベートとの線引きが難しくなる恐れがあります。在宅のほうが集中できる人がいる一方、自宅で業務を行うことで仕事が私生活と地続きになってしまい、気持ちの切り替えができないと感じる方もいるようです。「集中できない」「そのまま残業してしまう」といったことにならないよう、メリハリのある働き方を意識する必要があるでしょう。
3.運動不足になりやすい
リモートワークをすることで、出社していたときよりも運動不足になる可能性があるのもデメリットの一つです。通勤がなくなることで、長時間同じ姿勢が続いたり、屋外を歩いたりする機会が減ったりと健康に悪影響が生じる恐れもあるでしょう。
オフィスよりも座りっぱなしの時間が増えてしまうぶん、「1時間おきに立つ」「空いた時間に体操をする」など、積極的に身体を動かすように意識することが大切です。
4.やりがいや達成感を得にくい
リモートワークの場合、周囲にほかの社員がいない状態で仕事を進めていくことになります。そのため、作業中に励まし合ったり業務を終えたときに賞賛し合ったりする機会が少なく、やりがいや達成感を得にくいと感じることもあるようです。
また、リモートワークは基本的に一人で業務を進めていくため、「自分が働くことで会社の役に立っている実感が湧かない」「上司からどう評価されているのか分からない」というように、仕事へのモチベーションが下がってしまうことも。
このようなデメリットを回避するためには、企業調べや選考時にコミュニケーションを取るための仕組みや評価制度が整えられているかどうかを確認しておくことが大切です。
快適な作業環境を整備しよう
リモートワークをする際は、快適な作業環境を整備しましょう。スムーズな通信環境だけでなく、作業しやすい椅子や机、照明などにも気を配り、オフィス以外でも仕事が捗る環境を整えるのが大切です。
リモートワークを導入する企業側のメリット・デメリット
リモートワークは、人材確保や経費削減など、企業にとってもメリットが豊富です。多様な働き方を認めることで企業イメージも向上し、消費者へのアピールになる可能性もあります。一方で、リモートワークを取り入れるにあたって、仕組みや制度などを整えるのが難しいというデメリットもあるようです。
以下で、リモートワークを導入する企業側のメリットとデメリットを紹介するので、仕事選びの参考にしてみてください。
メリット
ここでは、リモートワークを導入する企業側のメリットについて解説します。
リモートワークを導入する企業側のメリット
- 優秀な人材を確保しやすくなる
- 経費を削減できる
- 業務効率化につながる
- 災害対策にもなる
- 世間からの評価が向上する可能性がある
1.優秀な人材を確保しやすくなる
リモートワークを導入することで、優秀な人材を全国から確保できる可能性が高まります。たとえば、「遠方に住んでいる」「家庭の事情で通勤ができない」といった人も採用の対象となるので、求人の応募者数が増えるでしょう。
また、ライフステージの変化や家庭の都合などによる従業員の離職も防ぎやすくなり、定着率が上がる可能性もあります。
2.経費を削減できる
リモートワークの導入によって、固定費を削減できるのもメリットの一つです。出社人数が減るためオフィスを縮小でき、家賃や光熱費、通勤手当などを削減できます。
また、都心部にオフィスを設ける必要もなくなるので、賃料の安い地方へ移転したり、支店をなくしたりする選択肢も。そのほか、デジタル化による用紙代・印刷代の削減、備品購入額の減少などもメリットといえます。
3.業務効率化につながる
リモートワークによって業務プロセスの見直しが進み、効率が上がる可能性もあります。たとえば、これまで対面で行っていた「契約書へのサイン」「上長の捺印」「稟議書の回覧」といった署名・押印対応をオンライン化することで、仕事のスピードが上がるでしょう。
そのほか、タスク管理ツール・システムによって従業員の進捗管理がしやすくなったり、クラウド上の情報共有が進み、属人的な仕事が減ったりするなどのメリットがあります。
4.災害対策にもなる
仕事をするうえで、リモートワークは災害対策になる点もメリットです。たとえば、地震や大雨など突発的な災害が起こった場合、自宅まで歩いて帰らなくてはいけなかったり、オフィスに寝泊りしたりしなければならない恐れも。一方、リモートであれば自宅で仕事ができるため、その心配がありません。
また、災害の影響が長期に及ぶ場合も、自宅や自分自身が無事であればリモートワークで働くことも可能です。オフィス以外で業務を進められる環境が整備されていないと仕事が止まってしまい、経営状況が悪化する恐れもあるでしょう。平時からリモートワークに慣れていれば、災害時に取引先やお客さまへの影響を最小限に抑え、経営を安定させやすい点もメリットといえます。
5.世間からの評価が向上する可能性がある
リモートワークを導入していることで、世間から「従業員のワークライフバランスを大事にしている」といった印象を持たれやすくなるでしょう。また、先述したように災害対策にもつながることから、取引先や求職者などに「万が一のときの対応がしっかりしていて安心できる」とプラスなイメージを与えられる可能性も。リモートワークを導入することで、結果的に企業のイメージアップにつながる可能性があるのはメリットといえます。
デメリット
次に、リモートワークを導入する企業側のデメリットについて解説します。
リモートワークを導入する企業側のデメリット
- コミュニケーション不足で一体感が低下する
- 生産性管理のマネジメントが必要になる
- セキュリティリスクが高まる
- ICTツール導入のコストがかかる
- 署名や押印をする業務が不便になる
1.コミュニケーション不足で一体感が低下する
リモートワークは対面でのやり取りが減るため、組織全体の一体感が低下する恐れがあります。社内メンバーとの意思疎通ができないとトラブルも起きやすく、生産性に影響を及ぼす場合もあるでしょう。
そのため、定期的に出社日を設けたりチャットツールを利用したりと、コミュニケーションの機会を増やす工夫が重要です。
2.生産性管理のマネジメントが必要になる
リモートワークでは、従業員の自己管理能力やスキルによって生産性が大きく左右されます。時間を有効活用して生産性を高める従業員がいる一方、周囲の目がないからといってサボる人や、効率性が落ちて残業が増えてしまう人も出てくるでしょう。
リモートワークの導入を検討している企業は、「始業・終業時にはチャットで連絡をする」「勤怠システムを導入する」などの労務管理の体制も整える必要があります。
3.セキュリティリスクが高まる
リモートワークには、徹底したセキュリティ対策が必須です。会社以外での業務は、資料や端末の紛失リスクが高まります。また、公共の場で利用できるネットワークはセキュリティ保護が十分にされていないことが多いので、情報漏洩の心配もあるでしょう。
リモートワークを導入する際は、従業員へのセキュリティ研修やVPNの使用といった対策を取る必要があります。
4.ICTツール導入のコストがかかる
リモートワークは環境設備の導入コストがかかることもデメリットの一つ。たとえば、業種に関わらず必要となるツールには以下のようなものがあります。
- ・クラウド上のファイル管理ツール
- ・Web会議ツール
- ・チャットツール
- ・勤怠管理ツール
リモートワークは、オフィスの維持費や交通費といった固定費関連のコストは削減できるものの、初期投資が必要になるのは企業にとって懸念点といえるでしょう。
5.署名や押印をする業務が不便になる
リモートワークを行うことで、直接書類に署名や押印をする業務が不便になる場合があります。デジタル署名や電子印鑑などの活用で、リモート環境でも効率的に文書の署名や承認を行うことが可能ですが、これらのツールが普及していない企業もあるでしょう。
リモートワークが普及した背景
近年リモートワークが普及した背景には、働き方改革や感染症の流行など、社会動向と関連した理由があります。とくに感染症の流行は、業種・職種を問わずリモートワークを拡充させるのに大きな影響があったといえるでしょう。
以下で、リモートワークの普及に関連があると考えられる社会動向をご紹介します。
働き方改革によるワークライフバランスの向上推進
リモートワークが普及した理由には、働き方改革の推進によってワークライフバランスの向上が重視されるようになったことが関係しています。リモートワーク・テレワークと働き方改革の相関関係は厚生労働省の調査「テレワークを巡る現状について(6p)」でも明らかにされており、企業側がリモートワーク・テレワーク導入で感じている効果の第1位は「働き方改革が進んだ(50.1%)」です。
さらに、従業員がリモートワーク・テレワークを継続したい理由にも「自由に使える時間が増える(30.1%)」「家事と仕事の両立がしやすくなる(16.7%)」が挙げられています。リモートワーク・テレワークによって通勤時間をなくし、プライベートな時間を充実させることで、業務にもポジティブな効果が生まれるでしょう。
少子高齢化による労働人口の減少
少子高齢化で労働人口が減少するなか、多様な働き方を可能にして労働力を増やすことが社会的に求められているようです。家庭の事情で出社が難しい人も、自宅にいながら仕事ができれば働く機会を増やせるでしょう。
働く人を増やして、日本の生産性向上や人手不足の解消を目指す動きが強まったことも、リモートワークが普及した理由といえます。
感染予防対策
感染症への予防・拡大対策の一環として、リモートワークを導入し始めた企業が増えたのも理由の一つ。感染拡大防止のためにリモートワークを導入し、根本的な働き方や業務の進め方について見直しを検討した企業は多いでしょう。これをきっかけに、感染症や災害への備えとしてリモートワークを続けている企業もあるようです。
環境負荷やコストの軽減推進
前述のように、リモートワークの場合はオフィスまで通勤する必要がなく、CO2排出量や交通費支給額の軽減が見込めます。また、出社する社員の人数が減れば、オフィスを縮小して賃料の軽減も図れるでしょう。
このように、環境負荷やコストを軽減するためにリモートワークを導入する企業もあります。
リモートワークの普及率は?
総務省の「令和5年通信利用動向調査の結果」をみると、2023年にテレワークを導入している企業は約49.9%でした。また、「今後導入予定がある」と回答した企業も含めると52.9%であり、テレワークやリモートワークはある程度普及しているといえるでしょう。
快適にリモートワークを行える企業の特徴
長距離の通勤や家庭と仕事の両立に負担を感じている場合、リモートワークという働き方に魅力を感じる方もいるでしょう。
ここでは、快適にリモートワークを行える企業の特徴をご紹介します。どのような企業なら快適なリモートワークができるか、以下で確認してみてください。
経営層がリモートワーク・テレワークを勧めている
経営層が積極的にリモートワーク・テレワークを勧めている企業であれば、快適に働ける可能性があります。そのような企業では、制度導入の目的や重要性が社内に浸透しているので、従業員一人ひとりがリモートワーク・テレワークを前向きにとらえている傾向があるためです。
また、細かいルールが整備されており、「自宅の通信費は経費になる?」「休日に少しだけ仕事をした場合は?」といったモヤモヤを抱えなくて済むでしょう。
コミュニケーションを取るための仕組みがある
コミュニケーション不足を解消するための仕組みがある職場では、孤独を感じずにリモートワークができるといえます。以下は、コミュニケーションを取るための仕組みの一例です。
- ・チャットツールやバーチャルオフィス、オンライン会議システムなどの導入
- ・画面モニタリングシステムの導入
- ・サテライトオフィスの設置
- ・相談やフォローアップ制度の導入
- ・コワーキングスペースの利用補助
前述の通り、リモートワークはちょっとした相談や雑談がしにくい点がデメリットといえます。しかし、バーチャルオフィスに雑談部屋があったり、定例でオンラインランチをしたりする仕組みがあれば、従業員同士のコミュニケーション活発化が可能です。オンライン上でのコミュニケーションが難なくできれば、業務もスムーズに進められるでしょう。
課題解決のためのツールやシステムが導入されている
課題解決のためのツールやシステムを積極的に導入している企業ほど、リモートワークに取り組みやすい傾向があります。たとえば、勤怠管理システムと連携できる人事管理システムの導入によって一人ひとりの生産性が可視化されるため、適切な評価を受けやすくなるでしょう。
「一般社団法人日本テレワーク協会」によると、リモートワーク・テレワークの導入を進める企業に対して、国や自治体から補助金や助成金を支給する仕組みもあるようです。このような助成や補助を活用している企業ほど、リモートワーク・テレワークの導入に積極的であるという見方もできるでしょう。
書類作業のデジタル化が進んでいる
書類作業のデジタル化が進んでいる企業も、リモートワークを快適に行える可能性が高いといえます。反対に、オンライン契約やデジタル押印が認められていない企業の場合、署名や印鑑をもらうために出社しなければならないことも。リモートワークのしやすさは、オンライン化の進み具合に左右される側面があります。
セキュリティ対策がしっかりしている
従業員への研修や業務管理ツールやシステムの導入など、セキュリティ対策を徹底している企業では、リモートワークで働きやすいでしょう。対策が不十分な企業では、従業員がリスクを負うことになってしまう可能性もあります。
企業側の対策がないまま、情報漏洩やマルウェア感染を起こしてしまい、処分を受けるのは避けたいもの。また、セキュリティ管理にかかるコストを従業員が負担するのは厳しいため、企業による環境整備が重要です。
生産性管理や評価制度が整っている
先述したように、リモートワークでは業務を管理しにくかったり、評価されている実感が湧かなかったりするデメリットがあります。しかし、生産性管理や評価制度が整っている企業であれば、そのような心配は少なくなるため、快適に働きやすいといえるでしょう。
たとえば、勤怠管理システムやバーチャルオフィスの導入がされていれば、出退勤の時間が明確になるため、残業代や休出手当などが抜けてしまうといった事態を回避できます。また、評価基準が細かく決められており、定期的に評価の場が設けられている企業であれば、モチベーションを高く保ちながら働けるでしょう。
リモートワークOKの求人はどう探す?
リモートワークが可能な求人は、転職サイトや就職・転職エージェントで探せます。転職サイトで探す場合は「リモートワーク」「テレワーク」のほか、「フルリモート」「在宅勤務」「在宅ワーク」といったキーワードでも探してみましょう。「テレワーク可」という求人では、リモートワークはできるものの、基本はオフィス勤務となる場合もあります。探し方に不安がある方は、就職・転職エージェントに相談するのがおすすめです。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
リモートワークがしやすい職種
リモートワークがしやすい職種として、営業職やバックオフィス業務に携わる職種などが挙げられます。営業職は客先に出向くことが多いため、オフィスに出社しなくても仕事は可能です。ただし、営業職の業務を完全在宅で行うことは難しい側面もあるので、モバイルワーク中心と考えておきましょう。
また、バックオフィス業務に携わる職種も、リモートワークに向いているものの一つ。バックオフィス業務とは、顧客と直接やり取りをすることがない業務を指し、関連する職種としては事務職や経理職などが挙げられます。事務職や経理職のデータ入力や書類作成、経費精算などはリモートワークに適しているといえるでしょう。
リモートワーク可能な企業への就職を検討している方は、ハタラクティブへお問い合わせください。若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブでは、専任のキャリアアドバイザーによるマンツーマンのサポートであなたに合う求人をご紹介します。企業情報も事前に確認できるので、リモートワークの実態も把握したうえでの応募が可能です。1分程度でできる適職診断を行えば、自分に合う仕事からリモートワークの仕事を探すこともできるでしょう。
求人紹介のほか、応募書類の作成や面接対策なども実施しており、就職・転職活動をスムーズに進められる環境が整っています。サービスの登録・利用料はすべて無料なので、お気軽にご相談ください。
リモートワークに関するFAQ
リモートワークに関するいろいろな疑問について、Q&A方式で解決していきます。
リモートワークとは、オフィス以外の場所で働くことを意味します。働く場所は企業によって決められている場合もありますが、自宅やサテライトオフィス、カフェなどが一般的です。
リモートワークについては、このコラムの「リモートワークとはどんな仕事のこと?」で詳しく解説しています。
リモートワークのやり方は、働き方や企業によって異なります。在宅勤務であれば自宅で作業を進め、モバイルワークの場合は電車やタクシーなどで移動中に仕事をする場合が多くなるようです。また、サテライトオフィス勤務では、本社や支店への出社はないものの、自宅付近に設置されたオフィスで業務を行います。リモートワークのやり方については、応募前や面接時によく確認しておきましょう。
リモートワークの働き方については、このコラムの「リモートワークの主な働き方」で紹介しています。
労働契約を結ぶ際に就業場所などを書面で伝えるのが原則であり、リモートワークは一般的に自宅を指定する企業が多いようです。また、オフィス出社とリモートワークで勤務時間が異なる場合や、通信費の一部を従業員負担とする際は就業規則に明記されます。これから就職・転職する方は、労働契約の内容をよく確認し、疑問があれば契約締結前に確認しましょう。
労働契約については「労働条件通知書兼雇用契約書とは?入社前の書類について詳しく解説!」のコラムで詳しく解説していますので、ご一読ください。
リモートワークで働く際は、業務効率化の考え方を身につけたり、ツールを活用したりするのがおすすめです。「効率が悪い」という悩みがある場合は、業務の優先順位がつけられていなかったり、完璧主義だったりする可能性も。改善策として、業務の重要度や作業にかかる時間を考えるようにしてみましょう。また、情報管理ツールやタスク管理ツールなど、アプリやシステムにサポートしてもらうのも効果的です。
「仕事ができるようになるには?うまくいく人の特徴や意識するポイントを解説」のコラムで仕事を進めるコツを紹介していますので、参考にしてみてください。
経験職種への転職や、異業界でも類似の業務経験が活かせる仕事を選ぶのがおすすめです。
未経験者は業務の進め方やツールの活用が不十分な恐れがあるため、リモートワークを不安視される場合も。ただし、一定の研修を受ければリモートワークできる仕事もあります。「未経験からリモートワークに挑戦できる?正社員を狙いやすい職種とは」のコラムで、未経験からリモートワークを目指しやすい職種を紹介していますのでご確認ください。
ハタラクティブでは、希望の働き方ができる求人探しをサポートします。お気軽にご相談ください。