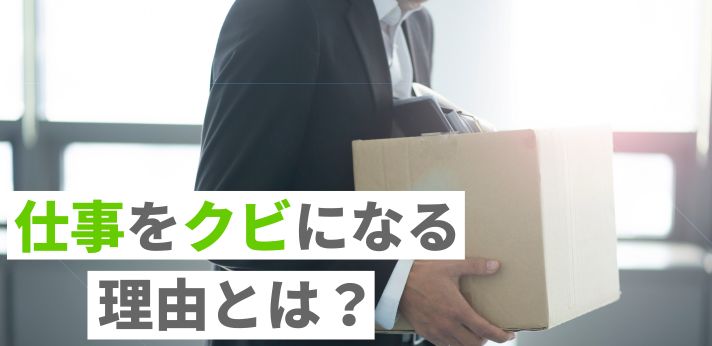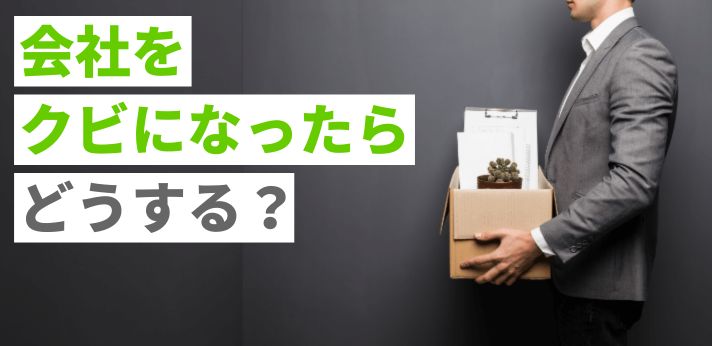国民健康保険の退職後手続きが14日過ぎたら?行うべき手続きを紹介国民健康保険の退職後手続きが14日過ぎたら?行うべき手続きを紹介
更新日
公開日
退職後の国民健康保険加入手続きは14日を過ぎても手続き可能
退職後手続きで国民健康保険へ加入するのが14日過ぎたらどうすればよいのか悩んでいる方もいるでしょう。期限内に手続きをしていないと、医療費が全額負担になるため要注意です。退職後、忘れずに行うべきなのは、「健康保険」「年金」「失業保険」の3つの手続き。このコラムでは、忘れてはいけない退職後の手続きの進め方や期限、相談先などを紹介します。退職後の手続きをもれなく進めるための参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
退職手続きを忘れることなく着実に行いたいとお考えの方は、ハタラクティブに相談してみましょう。ハタラクティブは、若年層に特化した就職・転職エージェントです。求人紹介から内定獲得後のケアまで、専任のキャリアアドバイザーが一貫したサポートを行っています。退職する際や求職中の手続き、転職前後の書類の準備などに関するさまざまなお悩みも相談可能です。プロのサポートを受けながら退職や転職を進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
もし退職後手続きから14日過ぎたらどうなる?
もし、退職から14日を過ぎた場合でも国民健康保険への加入手続きは可能です。しかし、資格取得は事由発生日にさかのぼって適用され、保険料も資格取得日に遡及して支払う必要があります。手続きを忘れたからといっていくらか保険料が免除される、ということはありません。退職後の活動スケジュールをしっかりと立てておきましょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
忘れてはいけない退職後の手続きとは
忘れてはいけない退職後の手続きは、「健康保険種別を選ぶ」「年金の切り替え」「失業保険の申請」の3つです。退職後に会社に再就職しない人や転職まで間が空く人は、安心して次の活動を行うためにも確実に手続きを行いましょう。以下でそれぞれの手続きの方法を解説しているので、参考にしてみてください。
忘れてはいけない退職後の手続き
- 健康保険種別を選ぶ
- 年金の切り替え
- 失業保険の申請
1.健康保険種別を選ぶ手続き
退職したら健康保険を選び、変更の手続きを忘れずに行います。「国民健康保険」「任意継続被保険者制度」「扶養に入る」の3つのなかから選びましょう。
国民健康保険に加入する
国民健康保険は、自治体が運営する健康保険制度です。企業を退職後、自営業者やフリーランスとして活動を始める方や企業に所属しない方は、居住地の市・区役所で国民健康保険への加入手続きを行います。
国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から原則14日以内に行う必要があります。また、転職先で新しい健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きを行いましょう。新しい健康保険証と国民健康保険の保険証を持参し、速やかに手続きを済ませることが大切です。
任意継続被保険者制度を利用する
任意継続被保険者制度とは、企業を通じて加入していた健康保険に最長2年間継続して利用できる制度です。
加入の条件は、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること。条件に当てはまる人は、退職日の翌日から20日以内に所属していた企業の健康保険組合に相談し、手続きを行う必要があります。
企業の健康保険組合に加入していた場合、退職後に必要な書類が送付されるケースが多いため、指示に従って手続きを進めましょう。一方、協会けんぽに加入していた場合は、居住地を管轄する年金事務所で手続きを行う必要があります。
また、任意継続被保険者制度では、退職前に企業が負担していた健康保険料の一部を含め、全額を被保険者自身が負担することに。退職前は、給料から天引きされていた保険料も自身で納付する必要があります。
扶養家族になる
社会保険に加入している家族の扶養に入れば、自身で保険料を納める必要はありません。扶養家族の範囲は配偶者や子、孫および兄弟姉妹などの直系尊属と、同居している3親等以内の親族です。
また、「年間収入が130万円未満であること」という要件もあります。
要件に該当する人は、退職後すぐに扶養者の会社に必要な証明書類である退職証明書や収入証明書などを提出し、申請手続きを忘れずに行いましょう。扶養家族については、「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」で詳しくまとめています。
2.年金の切り替え手続き
年金の切り替え手続きの方法は、国民年金に加入するか家族の扶養に入るかの2つです。企業に属さず国民年金に加入する場合は、退職日の翌日から原則14日以内に居住地域の役所で手続きを行いましょう。もし、14日を過ぎてしまっても、自宅に届いた国民年金未納分納付案内書の期日内に納付しましょう。
また、過去の雇用履歴や退職日を証明する離職票がなくても焦る必要はありません。退職日が分かる退職証明書もしくは健康保険資格喪失証明書など、退職日を証明する書類があれば手続きは可能です。
扶養に入る場合は、健康保険と同様に扶養者の会社へ申請します。手続き忘れがないように、退職後にどのような活動をするかスケジュールを組んでおきましょう。
国民年金の保険料は支払い忘れに注意
国民年金の保険料を支払い忘れると老後の年金額が減るだけでなく、万が一の障害や遺族のための年金を受け取れなくなる可能性があります。厚生年金に加入していると、保険料は会社と折半され、給与から自動的に控除されますが、退職後は国民年金へ切り替わり、自分で保険料を納めなければなりません。
もし経済的な理由で支払いが難しい場合は、「免除」や「納付猶予」の制度を活用できる可能性があります。これらの制度を利用すれば、一定の条件のもとで支払いを延期したり、一部または全額の負担を免除してもらったりできるでしょう。手続きを行えば、将来的に未納分をさかのぼって支払うことも可能です。年金の受給額を減らさないためにも、早めに役所の窓口で相談しましょう。
3.失業保険の申請手続き
失業保険の申請手続きは、企業を退職したあとの活動としてすぐにハローワークで行います。ハローワークで申請を行なってから受給資格が決定したら、7日間の待期期間を経て説明会へ参加しましょう。自己都合退職の場合は、受給資格が決まってからさらに2ヶ月間の給付制限期間があります。
手続きを忘れると給付開始の時期が遅くなり、次への活動も制限されてしまうため、離職票などの証明書類がそろったら速やかに申請を行いましょう。
住民税の支払い手続きにも気をつけよう
退職後、住民税の支払い手続きも忘れないように気をつけましょう。1~5月に退職した場合、住民税は最後の会社の給与から特別徴収として天引きされますが、不足があれば直接納付への切り替えが必要です。また、6~12月に退職した場合は自動的に直接納付に切り替わるため、納税通知書を使って自分で住民税を納めます。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職後の手続きを忘れたらどうなる?
退職後に健康保険や年金の切り替え手続きを忘れると、医療費の負担額が増えたり年金受給額が減ったりする恐れがあります。以下では退職後に手続きを忘れた場合のリスクと対処法を解説しているので、参考にしてみてください。
退職後の手続きを忘れたらどうなる?
- 医療費が全額自己負担になる恐れがある
- 空白期間の健康保険料はあとから徴収されることも
- 将来の年金受給額が減る可能性がある
医療費が全額自己負担になる恐れがある
健康保険の切り替え手続きを忘れたままだと医療費が全額自己負担になる恐れがあります。退職後、加入していた企業の健康保険を抜けると、7割の医療費軽減を受けられなくなるからです。また、手続きを忘れていた期間に支払った医療費は健康保険に加入したあとも払い戻しはされません。
企業を退職した後の活動をスムーズにするためにも、退職日の翌日から14日以内に、退職証明書などの必要な証明書類を準備して確実に切り替え手続きを完了させましょう。
空白期間の健康保険料はあとから徴収されることも
転職までに期間が空く場合、健康保険の手続きを怠るとあとから保険料を請求されるケースがあります。健康保険は未加入のまま放置しても、自動的に免除されるわけではありません。最長で2年前まで遡り、保険料を支払わなければならないケースもあります。
また、遡って保険料を支払ったとしても、その期間にかかった医療費には保険が適用されず、全額自己負担となる点にも注意が必要です。退職後は速やかに健康保険の手続きを行い、未加入期間が生じないようにしましょう。
将来の年金受給額が減る可能性がある
年金の切り替え手続きを忘れて未納のままにしておくと、将来の年金受給額が減ってしまう可能性があります。健康保険と同様に、退職から14日以内に必要な証明書類を準備して手続きを行いましょう。
国民年金は期限から2年以内なら納付できる
手続きを忘れてしまっても、国民年金は納付期限から2年以内ならあとからさかのぼって納めることも可能です。
退職後に切り替え手続きをしていない場合、国民年金保険料の納付書が後日送られてきます。将来年金を満額で受給するためにも、納付書に記載されている期限から2年以内に納めるようにしましょう。
不明点は役所の国民年金課や最寄りの年金事務所に相談してみてください。
年金保険料を納付できない場合は猶予制度を利用しよう
退職後に年金保険料を納付できない場合、猶予制度を利用する手もあります。本人や配偶者の前年所得が一定額を下回る場合は保険料の納付が猶予され、猶予期間分は年金額の計算に含まれません。また、本人や世帯主、配偶者の前年所得を考慮して保険料の納付が免除される制度もあります。
免除や猶予されたぶんの保険料は10年以内であれば追納できるので、納付が困難な場合は役所の国民年金課で相談してみましょう。
退職後の手続きを忘れないために気をつけるべきこと
退職後の手続きを忘れないためには、「期限を意識する」「余裕をもって証明書類を用意する」の2点に気をつけることが大切です。以下の内容を、手続き忘れを回避するための参考にしてみてください。
手続きの期限を意識して行動する
退職後は手続きの期限を意識して行動しましょう。前述したように、国民健康保険や国民年金の切り替えは退職日から14日以内で、任意継続被保険者制度への変更は20日以内。手続きの種類や切り替え先によって定められている期限は異なります。自分が行うべき手続きを忘れないためには、期限を把握したうえで計画的に準備することが大切です。
余裕をもって必要な書類を用意する
退職後の活動に必要な書類は余裕をもって用意しておきましょう。
失業保険を申請する際に必要な離職票や転職先に提出する退職証明書などを発行してもらう場合、退職者からの申請が必須の会社もあるようです。申請を忘れたままだと、提出期限に間に合わない恐れも考えられます。
申請から発行までにかかる日数を考慮したうえで、退職手続きで必要な書類は前もって手元にそろえておきましょう。
チェックリストを活用して手続き忘れを防ごう
チェックリストの活用は、退職後の手続き忘れの防止に効果的です。必要な手続きがひと目で分かるチェックリストと自身の行動を照らし合わせて、忘れていることがないか確認しましょう。転職に関する手続きのチェックリストは「
退職前にやることリスト!会社への返却物と受け取る書類や公的手続きを確認」でまとめられているので、あわせてご一読ください。
退職後の手続きに関するQ&A
仕事を辞めた後は、健康保険や年金、税金の手続きが必要です。しかし、何をいつまでに済ませるべきか分からず、不安を感じる人も多いでしょう。ここでは、退職後に必要な手続きを分かりやすくQ&A形式で解説します。退職後のトラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
健康保険証は、退職日までに会社へ返却しなくてはなりません。退職すると、それまで使用していた健康保険証は無効となり、使用できなくなります。
もし返却を忘れた場合は、速やかに郵送などで会社に送り返しましょう。失効した保険証を誤って使うと、後日、健康保険組合や協会けんぽから医療費の返還を求められる可能性があるため注意が必要です。
「健康保険は仕事を辞めたら手続きが必要?切り替えの方法や注意点を解説!」では、退職後の健康保険の手続きについて詳しく紹介しているため、あわせてご覧ください。
国民健康保険の保険証が発行される前に通院する場合は?
国民健康保険の加入手続きを行っても、保険証の発行までには一定の時間がかかります。そのため、手続き後すぐに医療機関を受診する予定がある場合は、役所の窓口で事情を説明しましょう。場合によっては、保険証が手元に届くまでの間に使用できる「資格証明書」などを発行してもらえることがあります。
退職後の健康保険について詳しく紹介している「退職後に健康保険に入らなくてもいい?加入方法や必要手続きを解説」もぜひご参照ください。
退職後すぐに新しい会社へ転職する場合、多くの手続きは新しい勤務先が代行してくれるため、市役所での手続きはほとんど必要ありません。しかし、しばらくの間無職の状態が続く場合は、自分で行うべき手続きがいくつかあります。
まず、健康保険に関しては、国民健康保険への加入手続きが必要です。また、住民税は会社を通じた給与天引きがなくなるため、市役所から送られる納付書を基に自分で支払う必要があります。その他にも、国民年金への切り替え手続きも必要になるため、退職後は速やかに市役所に確認し、適切な手続きを進めましょう。「退職後に市役所の手続きでやることは?必要書類や持ち物も解説」のコラムで退職後の市役所での手続きを紹介しているため、あわせて参考にしてください。