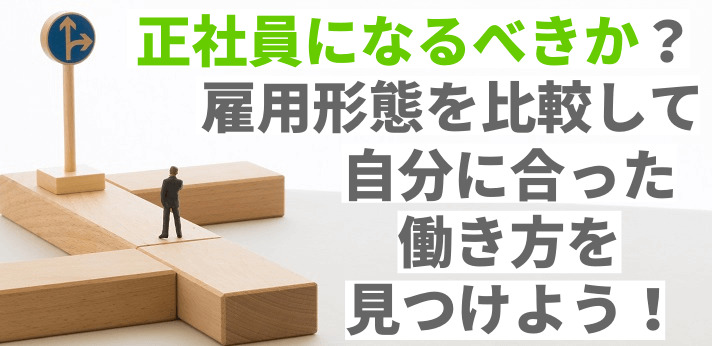委託社員とは?働くメリット・デメリットやほかの雇用形態との違いも紹介
「委託社員」が、どのような働き方を指すのか分からないという方も多いでしょう。委託社員とは、業務を行うことのみを契約し、企業と労働契約を結ばない働き方のことです。契約社員や派遣社員、嘱託社員といった働き方と混同しやすいですが、企業との雇用関係がない点が大きな違いといえます。
このコラムでは委託社員の特徴やメリット・デメリットなどを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断

就職・再就職でお困りではありませんか?
当てはまるお悩みを1つ選んでください
委託社員とは?

委託社員とは、「特定の仕事を業務委託という形で引き受ける契約を結んだ人」を指します。委託社員として働くことを英語では「outsourcing(アウトソーシング)」といい、いわゆる外注と考えれば分かりやすいでしょう。
委託社員は企業との間に雇用関係はなく、労働契約を結ぶわけではありません。つまり、「社員」という言葉を使用していてもその企業の社員ではないといえます。企業に雇用されている社員ではないため、業務委託契約を結んだ企業の管理下に置かれないことが特徴。仕事の結果に応じて契約企業から報酬を得られますが、基本的に個人事業主となるため、労働基準法の規制や社会保険の対象にはなれません。
委託社員の特徴をまとめると、以下の通りです。
- ・委託社員には派遣会社のような仲介となる会社がない
- ・企業と立場は対等であり、指揮命令や労務管理は受けない
- ・委託社員は委託元とは独立し、業務を行う権利がある
- ・内容によっては在宅勤務も可能
- ・働く期間は、委託契約内容の仕事が完了するまで
- ・自身の得意分野の仕事を専門として活躍することもでき、成果が直接収入につながる
- ・業務内容が達成できなかったときには責任を問われるケースもある
- ・委任された行為を行うことが契約内容となっている
委託社員は、業務内容や労働時間などの裁量が大きく、自由な働き方が可能。一方、会社に属する労働者ではないため、社会保険や有給休暇、育休といった制度を活用できないというデメリットもあります。委託社員のデメリットについて詳しくは、後述する「委託社員のデメリット」の項をご覧ください。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
委託社員とほかの雇用形態の違い
労働形態には、委託社員以外にも嘱託社員や契約社員などさまざまなものがあります。
ここでは、正社員や嘱託社員、契約社員などとの違いを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
委託社員と正社員の違い
正社員と委託社員は、会社との契約内容が異なります。正社員は会社と直接労働契約を結び、雇用主と従業員という関係です。
一方、委託社員は企業と直接雇用の関係にありません。業務の遂行だけを請け負うため、会社とは対等な関係となります。
委託社員と嘱託社員の違い
嘱託社員とは、嘱託制度を利用して正社員とは異なる働き方をしている社員のことです。会社によっては、契約社員や定年退職後の再雇用者の呼称として「嘱託社員」という言葉を利用することもあります。
期限のある働き方という意味では委託社員と似ていますが、嘱託社員も正社員と同様に会社と労働契約を結んでいる労働者です。
委託社員と契約社員の違い
委託社員と契約社員との違いは、企業との雇用関係の有無です。契約社員は雇用期間に期限があるものの、正社員と同様に会社と労働契約を結んでいます。ただし、昇進・昇給や賞与の額は正社員と差があるケースが多く、仕事の範囲も狭い場合があるようです。
雇用に期限があるという意味では委託社員と似ていますが、契約上は正社員に近いといえるでしょう。
委託社員と派遣社員の違い
委託社員はどこにも雇用されませんが、派遣社員は派遣会社が雇用主である点が両者の違いです。
派遣社員は派遣会社と労働契約を結び、派遣会社に仲介された企業で就業します。そのほか、派遣社員の特徴は下記のとおりです。
- ・派遣先の正社員と同じような業務、もしくは補助的な業務を任せられる
- ・指揮命令は派遣先に準ずる
- ・雇用期間は契約時に定められた満了期間まで(更新あり)
派遣会社は、就業先の企業と労働者派遣契約を結んで契約内容を定めます。また、派遣社員には労働者派遣法が適用され、「同じ事業所での派遣期間は原則3年まで」「日雇い派遣は原則禁止」などのルールがあるのも、委託社員との違いです。
委託社員とフリーランスの違い
委託社員は開業届を提出して個人事業種として働いている人のことを指し、フリーランスは企業や団体に所属せずに個人で仕事をする働き方のことを指す言葉です。フリーランスは個人で働くスタイルの大枠を指すため、委託社員もフリーランスの一つに含まれます。そのため、フリーランスで働いている人が仕事を獲得する手段の一つとして委託社員を選択することもあるのです。
後述の「委託社員としての仕事の始め方と探し方」で、フリーランスとして委託社員の仕事を始める方法を紹介しているので、参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
委託社員の契約と該当する職種

委託社員の契約には、大きく2種類あります。請負契約と委任契約です。さらに、委任契約には準委任契約という契約形態もあります。
| 委託社員の種類 | 報酬の目的 | 成果物の完成義務 | 例 |
|---|---|---|---|
| 請負契約 | 成果物 | あり | デザイナー ライター プログラマー など |
| 委任契約 | 業務遂行 (法律行為) | なし | 税理士 医師 弁護士 など |
| 準委任契約 | 業務遂行 (法律行為なし) | なし | 美容師 エステティシャン 受付 など |
この項では、委託社員の契約形態について解説するので、実際に契約を結ぶ際、報酬の対象などを確認するための参考にしてみてください。
請負契約
請負契約は、成果物の納品に対して報酬が支払われます。働いた時間やプロセスは考慮せず、完成品が問題なく納品されるかどうかが問われるでしょう。納期までに完成できなかった、あるいは契約通りの成果を出せなかった場合、報酬は受け取れないのが原則です。
請負契約は、主に以下のような職種で用いられます。
- ・デザイナー
- ・ライター
- ・プログラマー
- ・営業
- ・警備員
警備員は警備した場所の安全、営業は売上が成果として見なされるため、請負契約が用いられるようです。
委任契約
委任契約では、業務を行うこと自体を契約します。請負契約と異なり、業務を行えば報酬が発生する仕組みです。
さらに、委任契約には狭義の委任契約と準委任契約の2種類があります。弁護士のような法律にまつわる委任契約を狭義の委任契約、それ以外の契約を準委任契約と呼ぶのが特徴です。
委任契約は、主に以下のような職種で用いられます。
- ・弁護士
- ・医師
- ・美容師
- ・エステティシャン
先述したように、弁護士以外の職種は準委任契約です。
委託社員の3つの特徴
ここまででご紹介したとおり、委託社員とは契約どおりに仕事を完成させることによって報酬を得る働き方です。派遣社員と違って会社との雇用関係を結ぶわけではないため、あくまで対等な立場で仕事を行います。
ここでは委託社員の特徴を紹介しますので、どのような働き方やお金の管理方法があるのかチェックしてみてください。
1.委託社員は事業主扱い
業務委託契約を結んで仕事を行う人は、個人事業主として開業届を出しているケースが多いようです。
これまで説明したように、委託社員として仕事をする場合は正社員や契約社員のように企業と雇用関係を結ぶことはありません。独立した事業主として、あくまで対等な立場で仕事を受けることになります。
業務委託を社員扱いすると違法になる?
個人事業主である委託社員に対し、企業側が指揮命令を出すと労働法に触れる場合があります。
本来、業務委託は企業から指揮命令を受けることはないため、仕事のプロセスはすべて本人の決定が必要です。そのため、依頼主である企業が委託社員の勤務時間を管理したり、業務に対して細かい指示を出したりすると、偽装請負と見なされる場合も。業務委託には福利厚生や社会保険が適用されないため、人材コストを削減しながら労働力を得た疑いがあるためです。
ただし、企業側も意図せず偽装請負のような形になってしまったというケースもあります。仕事をしていて疑問に感じることがあれば、依頼主とよく相談して良好な関係を築きましょう。
2.就業期間は契約によって決められる
委託社員の場合は仕事の期間も契約ごとに決まります。委任契約の場合は、あらかじめ決まっている期間で業務を請け負うのが一般的です。請負契約の場合は、成果物を完成させることによって報酬が発生するため、期日までの労働時間の使い方は自由であることが多いでしょう。
3.業務範囲は契約によって決められる
委託社員の場合、業務内容は契約によってその都度決まるため、業務範囲についても毎回変わります。たとえば、請負契約の場合は成果物を納品することによって報酬が発生する契約となっているため、納品済みの成果物に問題があった場合には修正が求められるケースも少なくありません。
しかし、過度な修正や当初の依頼とは異なる内容を求められた場合、修正費用の有無でトラブルとなることも。契約の時点で、業務・責任の範囲をしっかり確認しておくことが大切です。
委託社員として働く3つのメリット
委託社員は企業に所属しないため、仕事内容や働き方を自分で選べるといったメリットがあります。
ここでは委託社員のメリットを紹介するので、就職先に求める条件とマッチしているか確認してみてください。
1.働き方の自由度が大きい
前述したように、委託社員は契約を結んだ会社と対等な立場であり、業務の遂行によって報酬を貰う働き方のため、会社から指示を受けることはありません。
また、契約内容によっては在宅勤務も可能です。委託社員の働き方は自由度が大きく、時間や場所に縛られずに好きな働き方ができるというメリットがあります。
委託社員は複業もできる
業務委託であれば、複数の仕事を請け負うこともできるのがメリットの一つ。複業とは、パラレルキャリアとも呼ばれる働き方で「副業」と異なり、いずれの仕事も本業とする考え方です。複業のメリットは、収入アップやリスク分散といわれています。委託社員は急に仕事がなくなる恐れもあるため、いくつかの企業と委託契約を結び、収入が途絶えないように複業する人が多いようです。
2.得意分野に特化できる
委託社員は自分で業務を選べるため、自分の得意分野・好きな分野の業務のみを行える点がメリットです。正社員や派遣社員として働く場合は、自分の得意な分野でなかったとしても、会社の方針にしたがって業務を行う必要があります。委託社員は得意な業務だけに専念できるため、仕事のストレスが少ないでしょう。
3.人付き合いのストレスが軽減できる
委託社員は、職場での人間関係に悩まされることが少なく、正社員や契約社員に比べて人付き合いのストレスを軽減できるというメリットがあります。委託社員は、必ずしも出社して仕事をする必要はありません。業務に差し支えなければ、企業側と合意のうえ在宅可能な委託契約を結ぶことも可能です。
打ち合わせから納品まで、すべての業務をオンラインで完結することもできるでしょう。必ずしも直接会ってコミュニケーションをとらなければいけないわけではないため、対人関係のストレスは少なくなると考えられます。
委託社員として働くデメリット
委託社員は自由な働き方ができる反面、有給休暇や福利厚生がなく、社会保障の面で正社員に比べて手薄な点がデメリットです。また、労働基準法は適用されず、仕事の責任も個人で負わなければならないリスクもあります。
1.社会保険制度に加入できない
委託社員は企業の社会保険には加入できないのがデメリットの一つです。企業と雇用関係がないので、厚生年金や雇用保険の対象外となります。また、企業が加入している健康保険にも入れないため、国民健康保険への加入が必要です。
正社員や契約社員は企業の社会保険に加入でき、保険料も折半になるなど自己負担が少なくてすみますが、委託社員は全額を自分で支払う点にも注意しましょう。
2.有給や育休制度が適用されない
委託社員は福利厚生の対象外なため、有給休暇や育休といった制度が適用されません。産休・育休期間、けがや病気の療養など長期的な休みが必要な場合、収入が保証されないのが委託社員のデメリットです。
正社員や派遣社員の場合、有給を使って収入を減らさずに仕事を休めます。しかし、委託社員は仕事を休めば収入が減り、生活が不安定になる恐れも。また、雇用保険や労災保険にも加入できないため、何かあったときの保障が基本的にありません。
委託社員として働くなら、いざというときの備えも自分で考えておく必要があるでしょう。
3.労働基準法が適用されない
労働基準法が適用されないのも、委託社員のデメリットの一つです。厚生労働省の労働条件に関する総合情報サイト内の「Q&A」によると、委託社員は個人事業主になるため、労働基準法における労働者に該当せず、適用対象になりません。そのため、成果に対して十分な報酬が支払われない、労働時間が長すぎるといったことが起きるリスクもあります。
ただし、労働者に該当するかどうかは実態をもとにした判断となるため、「委託者から指示命令を出された」「細かい社内ルールを適用された」などがあった場合は、労働者と見なされる可能性があることを念頭に置きましょう。
参照元
厚生労働省
労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件
企業が委託社員と契約する理由は?

企業が委託社員と契約する主な理由としては、適切な人材の確保やコスト削減などのメリットがあるからです。ただし、企業側としてもメリットだけでなく、デメリットもあるため注意が必要。
ここでは、企業から見た委託社員のメリットとデメリットを解説します。
委託社員と契約する企業側のメリット
委託社員と契約する企業側のメリットは、専門スキルのある人材を適切なタイミングで確保できる点です。たとえば、大型案件に即戦力が必要な場合や、既存社員にない専門知識を活用したい場合に効果的といえるでしょう。
また、必要なスキルを持った人材を一時的に確保することで、研修や採用にかかるコストの削減にもつながっているようです。企業が社員を雇用する場合、採用や研修のコスト、社会保険の支払い、業務に必要な設備・備品の購入・整備などさまざまなシーンで費用と時間を膨大に要します。委託社員であれば、すでにスキルがある人材を必要な期間だけ確保できるため、コストと手間の負担が軽減すると考えられるでしょう。
委託社員と契約する企業側のデメリット
企業が委託社員を活用する際、業務の進行に指示を出しにくい、自社の情報を外部に渡すことから情報漏洩のリスクがあるなどをデメリットに感じているようです。また、委託社員を利用していると社内の人材が直接業務を行うわけではなくなるため、社内にノウハウが蓄積しません。
すでに社内にノウハウ自体はあり、繁忙期のために委託社員を利用して増員を図っている場合は問題ないでしょう。しかし、自社内にノウハウを蓄積させたい場合は、プロジェクトを委託社員に丸投げせず、社内の人材と一緒に進めることが大切です。
委託社員としての仕事の始め方と探し方
ここでは、委託社員として仕事を始める際の流れと求人の探し方を紹介します。委託社員として働きたいと考えている方は、参考にしてみてください。
委託社員として仕事を始める流れ
委託社員として仕事を始める流れは以下のとおりです。それぞれ、副業とフリーランスに分けて紹介します。
副業でスタートする場合
委託社員としての仕事を副業でスタートしたい場合は、まず現在勤めている会社が副業を認めているか、就業規則を確認してみましょう。認められている場合は、会社に申請を行います。ただし、副業をすることで勤務先が不利益を被る可能性がある場合は制限がかかるため、注意が必要です。始めようとしている副業が会社と競合にならないか、事前に確認しておきましょう。
また、副業としてスタートした場合の収入は基本的に「雑所得」として扱われるため、開業届を提出する必要はありません。ただし、副業で20万円以上の利益を得た場合は確定申告を行う必要があります。
退職してフリーランスとしてスタートする場合
退職してフリーランスとして委託社員の仕事を始める場合、会社の社会保険から外れるため、健康保険や年金の手続きを自分で行う必要があります。また、個人事業主としてスタートすることを考えている方は、独立から1ヵ月以内に開業届を提出しましょう。
開業届を提出すれば制度上のメリットを受けられる
開業届を提出すれば、青色申告ができるようになる、経費として申告できる範囲が広がる、赤字の繰り越しができるといったメリットがあります。
青色申告ができるようになると、所得金額から一定の金額を控除する青色申告特別控除を受けることが可能です。また、経費の範囲が広がれば、家族とともに働いて給料を支払っている場合も経費に含められます。
さらに開業届を提出することで、事業で赤字を出してしまった際も3年間繰り越しできるため、万が一の場合も安心です。
委託社員の仕事の探し方
委託社員の仕事を探す場合は、業務委託や副業の仲介を行うマッチングサイトやエージェントなどのサービスを利用するのがおすすめです。Webデザインやライティングなど、特定の分野の案件を扱っているサイトもあるため、自分が希望する分野に沿ったサービスを利用しましょう。
また、SNSでプロフィールや仕事の実績を公開して宣伝活動をする、現在の勤務先であらかじめ人脈を広げて仕事の依頼を受けやすい土台を作っておくといった方法もあります。
委託社員は履歴書が必要?書き方は?
委託社員であっても、書類選考や面接を行い、経歴やスキルをチェックしたいと考える企業は多いため、求められれば履歴書の提出が必要です。ただし、履歴書が必ず求められるわけではありません。デザイナーといった専門職の場合、履歴書ではなく成果物となるポートフォリオの提出が求められる場合があります。
なお、委託社員の履歴書の書き方は、基本的にほかの雇用形態で作成する際と同じであると考えましょう。志望動機や自己PRに力をいれるとともに、個人事業主やフリーランスになった理由を聞かれる可能性があるため、事前に回答を準備しておくのがおすすめです。
委託社員として働く際の注意点
委託社員として仕事を始める場合は自分で責任を持って行動する必要があるため、契約書の内容や成果物の権利の帰属先、情報漏洩など、さまざまなことに注意を払わなければいけません。
ここでは、委託社員として働く際の注意点を詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
1.業務委託契約書の内容をよく確認する
委託社員として働く場合、まず業務委託契約書の内容をよく確認しましょう。業務委託契約書には、業務を任される範囲や報酬についてなど、重要なことが明記されています。
後々のトラブルを回避するためにも、双方で合意した内容と契約書に明記されている内容に食い違いがないか、事前にチェックしておきましょう。
2.成果物の権利の帰属先をすり合わせておく
ライターやデザイナーなど、成果物が形として残る仕事の場合は、権利の帰属先が企業と自分のどちらにあるのかすり合わせを行いましょう。成果物の権利先を明確にしておかないと、意図しない使われ方をする、企業が成果物を利用することを意図ぜず制限してしまうなど、さまざまなトラブルが考えられます。
そのため、成果物の権利がどちらにあるのかを決定し、契約書に明記しておくことが大切です。
3.情報漏洩に注意する
委託社員として仕事を受ける場合は、情報漏洩にも注意しましょう。仕事を通して知り得た情報は、慎重に扱う必要があります。身近な家族や知り合い、あるいはSNSで仕事の話をしてしまうと、その経緯で重要な情報が漏洩する恐れも。情報漏洩した場合は相手企業に損害を与え、賠償責任が発生する可能性があるので、仕事に関する情報は外部に持ち出さないようにしましょう。
4.契約解除の条件や賠償責任の有無を確認しておく
委託社員で働く場合は、契約を解除する条件や、その際の賠償責任の有無も確認しておきましょう。契約書に解除に至る事由が明記されているので、該当した際は双方で契約を解除することが可能になります。また、契約を解除した際に賠償責任が発生するかどうかも確認しておくことが大切です。
5.すべての責任を自分で負う必要がある
委託社員は自ら営業して仕事を獲得し、見積書・請求書の作成や確定申告などもすべて自分で行わなければなりません。また、請負契約の場合、成果物に問題があれば無償で補修することもあります。
ほかにも、前述したように個人情報の漏洩など、依頼主に損害を与えてしまった場合は賠償責任を問われることも。委託社員にはこういった厳しい側面もあるため、「自由な生活がしたい」と安易に選ぶのは避けたほうが良いでしょう。
安定した働き方を望むなら正社員がおすすめ
「安定した収入を得たい」「将来のためにも社会保険に加入したい」と考えるなら、委託社員より正社員がおすすめです。正社員は毎月の収入が安定するだけでなく、昇給もある程度の見通しができます。また、有給休暇や産休・育休のほか、ボーナスや退職金制度など、メリットが豊富です。働き方の自由度は少ないものの、企業によっては在宅勤務やフレックスタイムを認めている場合もあります。「正社員とは?メリット・デメリットやほかの雇用形態との働き方の違いを紹介」のコラムでは、正社員の特徴を詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
これから就職活動または転職活動を考えている方は、企業の社風や業務内容だけでなく、正社員や派遣社員、委託社員といった「雇用形態」にも注目してみると良いでしょう。応募する企業が希望の職種や社風とマッチしていたとしても、雇用形態によっては自分の目指す働き方ができない場合もあります。就職・転職先を探す際には、「自分に合った働き方ができるかどうか」をしっかりと考えることが大切です。
どの働き方が自分に合っているのか分からない方は、就職サポートサービスのハタラクティブへご相談ください。第二新卒や既卒、フリーターなどの若年層を対象に、就職や転職についての相談を提供しています。専任の就活アドバイザーが、分かりにくい雇用形態についても丁寧にアドバイス。求人の紹介や応募書類の添削、面接対策などにより、就職活動をサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。
委託社員に関するQ&A
ここでは、委託社員に関するよくある疑問をまとめています。給料や委託社員から正社員に転職する方法についても解説していますので、ぜひご一読ください。
委託社員と業務委託の違いは?
どちらも同じ意味で使われます。
委託社員とは、業務委託契約を結んで働く人のことです。企業に雇用されず、個人で仕事を請け負う働き方をいいます。ビジネスシーンでは委託社員のことを「業務委託」と呼ぶ人も多く、どちらを使っても問題ありません。また、求人サイトでは雇用形態の欄に「業務委託」と記載されるのが一般的です。
「委託社員で働くのはやめたほうがいい」と聞きました
委託社員のメリット・デメリットについてよく考え、自分に合う働き方なのかを見極める必要があります。「委託社員の3つの特徴」でも述べたように、会社の制度や社会保障を利用できないリスクは押さえておきましょう。入職後どのような生活スタイルになるかを検討してから、求人に応募するのがおすすめです。
委託社員の給料はどのくらいですか?
会社や職種、案件の難易度によって異なります。
たとえば、ライターが業務を委託された場合は「1文字当たり○円」「1記事当たり○円」「文字や記事数の指定なしで月○円」というように、案件によって細かく規定が違う場合もあるようです。委託で受けることを決めてから後悔しないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。
在宅で業務委託をするにはパソコンを買わないとダメ?
在宅勤務のために、パソコンとWi-Fiの設置を最低限の条件をしている企業は多くあります。
一方、会社からパソコンを支給してもらえることもあるため、委託契約を結ぶ前に確認しましょう。
委託社員から転職して正社員になる方法は?
委託社員として身につけたスキルや経験は、転職市場で評価の対象になります。書類や面接で実績をうまくアピールすれば、正社員になれる可能性は十分にあるでしょう。
どのように転職活動を進めれば良いのか分からない方は、転職サービスに登録し、プロのアドバイザーから支援を受けるのがおすすめです。委託社員から正社員の就職に興味がある方は、ぜひ若年層の就職・転職の支援に特化したエージェントのハタラクティブにご相談ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
語学力を活かしたい方必見!外資系・グローバル系企業の事務職を募集◎
貿易事務
埼玉県/千葉県/東京都/神奈川…
年収 258万円~295万円
正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!
ライター・取材担当
東京都
年収 315万円~360万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?
マーケティングアシスタント
東京都
年収 315万円~360万円
土日休み★私服OK◎事務作業も行うCADオペレーターを募集!
一般事務+CADオペレーター
福岡県
年収 246万円~379万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「経歴別」の記事一覧
- 「正社員・契約社員・派遣社員」についての記事一覧
- 「正社員の就職」についての記事一覧
- 委託社員とは?働くメリット・デメリットやほかの雇用形態との違いも紹介