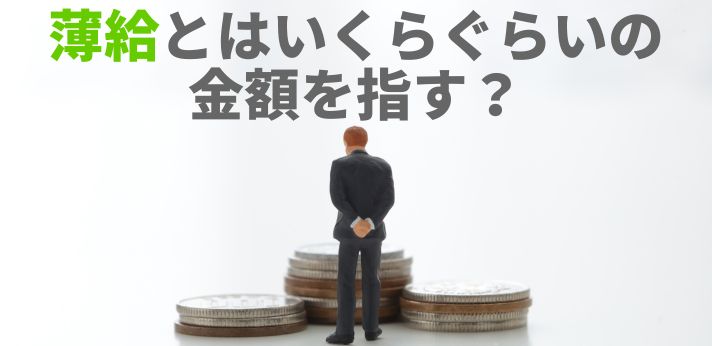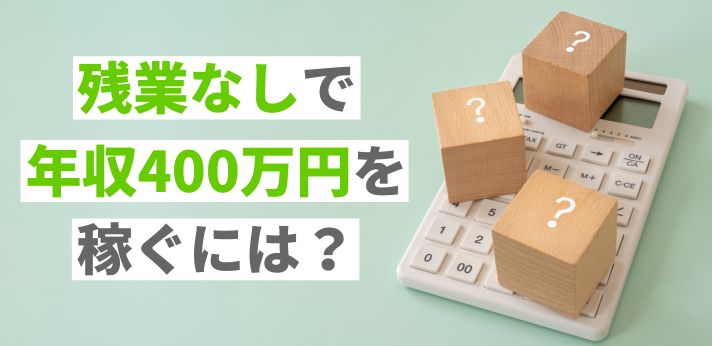年収には交通費を含む?扶養内で働く条件やふるさと納税についても解説
更新日
公開日
年収とは1年間の総収入のことであり、税金や保険料が引かれる前の金額を表す
年収の申告や計算を行う場合に、交通費(通勤手当)を含むべきか悩んでいる方もいるでしょう。「扶養の範囲内で働きたい」「ふるさと納税の控除限度額を計算したい」など、年収が必要なケースはさまざまです。年収を申告する目的によって交通費を含むかどうかは異なるので、各制度を正しく理解しておく必要があるでしょう。
このコラムでは、年収の壁や制度ごとの交通費の取り扱いについて解説します。ぜひ参考にしてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
参照元
全国健康保険協会
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
年収と交通費
年収を計算する際に交通費を含めるのかを考える前に、まず「年収」と「交通費」それぞれの言葉の意味や基本知識を知っておきましょう。
年収とは
「年収」とは1年間の総収入のことであり、給与の「総支給額」を指します。給料をもらう際、税金や保険料などが差し引かれますが、なにも引かれていない状態の給与の1年分の合計金額が「年収」です。手取り金額ではなく、会社が従業員に支払った総支給額を表していることを知っておきましょう。
交通費とは
交通費とは、「仕事や業務を遂行するうえで発生する交通に関する費用」のことを指します。たとえば、出張費用や取引先へ訪問した際にかかる電車代や飛行機代、タクシー代などが交通費に含まれます。
なお、交通費と似たものに「通勤手当」がありますが、通勤手当とは「職場へ通勤するためにかかった費用」のことです。業務中の出張や外出などで発生する移動費は、一般的に通勤手当には含まれません。ただし、会社によっては通勤手当のことを交通費と表示しているケースもあるようです。
会社側に交通費を支払う義務はない
労働基準法には交通費や通勤手当についての定めがないため、会社に支払い義務はありません。そのため、交通費や通勤手当が支給されている場合は、従業員の働きやすさを考慮した会社側の好意だといえます。
また、交通費や通勤手当の支給額は企業によってさまざまです。全額支給する会社もあれば、一部支給としているケースもあります。自宅から職場が離れていると、電車代やガソリン代、バス代などは結構な出費になるでしょう。希望の会社が遠方の場合は、求人情報をしっかり確認しておくことをおすすめします。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
年収の計算に交通費は含まれるのか?
おおまかな年収を求められているときには、状況に応じて交通費を含むか含まないかを判断して問題ないでしょう。しかし、税金や社会保険に関連した内容では、年収に交通費を含むべきかどうかが制度上明確に決まっているケースもあります。
年収に交通費を含むかどうかは場合によって異なる
年収に交通費を含めるかどうかは、どういった目的で年収が必要なのかによって異なります。
たとえば、社会保険上の扶養条件に該当していることを確認するために年収を申告する際は、交通費を含みます。しかし、「税金」を計算する場合は、交通費が非課税であれば年収に含みません。国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げ」によると、1ヶ月の通勤手当が15万円以下であれば非課税とされています。一方、月15万円を超える部分については課税対象となるため、年収に含める必要があるでしょう。なお、交通費が給料に含まれているなど、給料と通勤手当の区別がない労働契約を結んでいるケースでは全額課税対象となります。
参照元
国税庁
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
源泉徴収票の年収に交通費は含まれていない
源泉徴収票の「支払金額」という項目では、1年間の収入の合計金額が確認できます。ただし、税金の計算を行ううえで必要な項目を記載している源泉徴収票の性質上、交通費(通勤手当)が非課税限度額の月15万円以内に収まっていれば「支払金額」に含まれません。
年収の額面(総支給額)を確認する際に源泉徴収票が用いられることは一般的ですが、交通費や通常必要と認められる旅費など、非課税扱いとされる手当は含まれていないことを知っておきましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
「年収の壁」によっても交通費を含めるかどうかは異なる
扶養の範囲内で仕事をしたい場合、年収が103万円・106万円・130万円に収まるかどうかは重要なポイントです。これを「年収の壁」といいます。「年収の壁」を超えていると、税金の優遇を受けられなかったり社会保険上の扶養から外れてしまったりする恐れがあるので、年収の壁ごとの交通費の取り扱いについてしっかり把握しておきましょう。
※以下で解説する内容は、2025年3月時点の税制によるものです。
年収103万円の壁
「年収103万円の壁」には二つの意味合いがあります。一つ目が、所得税の課税対象となる年収の基準です。給与所得者の年収が103万円を超えなければ、所得税が非課税とされますが、超えた部分に対しては所得税の支払いが発生します。
二つ目が、扶養控除が受けられる被扶養者の年収の上限です。扶養されている方(主に学生やフリーターなど)の給与所得が年間103万円を超えると、税制上の扶養から外れます。税制上の扶養から外れると、扶養者(親など)は所得控除が受けられなくなるため、住民税や所得税の支払いが増えてしまうのです。
年収103万円の壁は、税制上の優遇が受けられるかどうかのボーダーラインであり、年収の計算に交通費は含まないことを覚えておきましょう。ただし、前述のとおり、交通費が月15万円を超えると超えた部分を課税対象として年収に含む必要があります。
年収103万円の壁について詳しくは、「年収103万を超えたら税金はいくら払う?働き損にならない方法を解説!」のコラムをご参照ください。
参照元
国税庁
トップページ
150万円の壁とは?
150万円の壁とは、「配偶者特別控除」が満額で受けられる配偶者の年収のボーダーラインです。納税者に配偶者がいる場合、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの所得控除が受けられるケースがあります。
まず、配偶者の給与所得が年間103万円以内であれば「配偶者控除」の対象です。103万円を超えた場合は、配偶者の収入に応じて「配偶者特別控除」が利用できます。配偶者特別控除の控除額は、配偶者の年収が増えると段階的に減少していく仕組みであり、満額の控除が受けられる配偶者の年収の上限が150万円です。また、年収150万円の壁についても、年収に交通費は含みません。
配偶者控除、および配偶者特別控除の金額や条件について詳しくは「
配偶者控除とは?計算方法や対象条件などについて紹介!」をご参照ください。
年収106万円の壁
106万円の壁においても、年収の計算に交通費は含みません。
「年収106万円の壁」は、社会保険への加入義務が発生する年収の目安です。厚生労働省の「社会保険加入のメリット」には、社会保険の加入条件について以下のように記載されています。
- ・週20時間以上の労働をしている(残業時間は含まない)
- ・1ヶ月の賃金が8.8万円以上(年収にして106万円程度)
- ・2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
- ・学生ではない
- ・従業員数が51人を超える会社で働いている
また、1ヶ月の賃金8.8万円以上の条件に関しては、残業代や賞与、通勤手当、臨時の手当は原則含まないとも記載されています。そのため、年収106万円の壁を考えるうえで、年収に交通費は含みません。
年収130万円の壁
130万円の壁における年収は、交通費を含めて計算します。
「年収130万円の壁」とは、社会保険上の扶養に入りながら働ける年収の上限のことです。年収130万円を超えると、社会保険の扶養から外れるため自分で国民健康保険や国民年金の保険料を支払う必要があります。
130万円の壁を考えるうえでは、会社から支払われた総収入額の合計が年収130万円以内に収まっているかがポイントです。毎月の給料はもちろん、交通費や各種手当、ボーナスなど、すべての金額を合わせて年収130万円以下である必要があります。なお、会社から定期券を現物で支給されている場合も、金額に換算して年収に含めましょう。
なぜ年収に交通費が含まれるのか
130万円の壁における年収に交通費を含む理由としては、社会保険料を計算するうえで「標準報酬月額」が基準とされることが挙げられるでしょう。
全国健康保険協会の「標準報酬月額・標準賞与額とは?」によると、標準報酬月額の報酬の範囲について「労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるもの」と記されており、基本給のほかに以下のような手当も該当します。
- ・役付手当
・勤務地手当
・家族手当
・通勤手当
・住宅手当
・残業手当など
よって、年収130万円の壁を考える際は、年収に交通費を含んで計算します。
ふるさと納税の限度額計算も年収に交通費は含めない
ふるさと納税の控除限度額を計算する際は、年収に交通費を含みません。なぜならふるさと納税は、各自治体への寄付により税金の控除や払い戻しなどが受けられる制度であり、課税対象となる収入をもとに年収を考える必要があるからです。
ただし、交通費(通勤手当)が非課税限度額の月15万円を超える場合は、超えた部分を年収に含める必要があります。
前述のとおり、交通費の支給は法律で定められているものではありません。アルバイトやパートでは交通費が支給されないケースも珍しくないでしょう。もし、「現在の勤め先での待遇に満足できない」と悩んでいるのなら、転職を視野に入れてみることもおすすめです。
若年層の就職・転職支援を行うハタラクティブでは、キャリアアドバイザーが求職者の仕事に関する悩みをマンツーマンでしっかりサポートします。希望や適性に合った求人の紹介はもちろん、応募企業に合わせた書類作成や面接対策なども実施。すべてのサービスは無料で利用できるので、ぜひお気軽にご相談ください。
年収や交通費に関するよくある質問
最後に年収や交通費に関するよくある質問を紹介します。
扶養控除や配偶者(特別)控除の年収に交通費は入る?
扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除を考えるうえでは、年収に交通費を含めないことが基本です。税制上の年収は、課税対象とされる収入のみで計算されるからです。交通費が月15万円を超えると、超えた部分は年収に含む必要があることを覚えておきましょう。
通勤手当の非課税限度額については、このコラムの「年収に交通費を含むかどうかは場合によって異なる」をご参照ください。