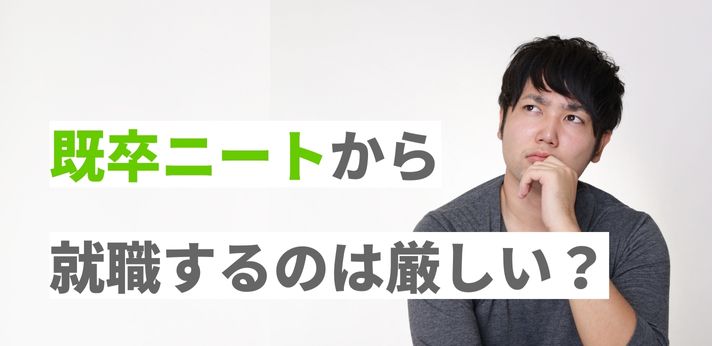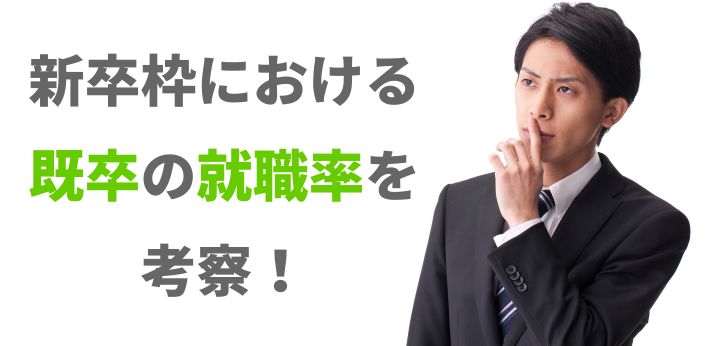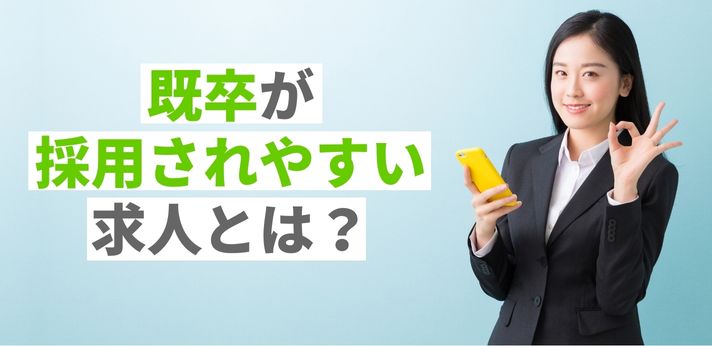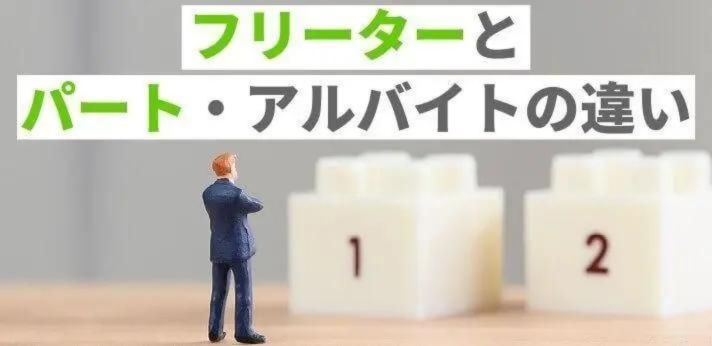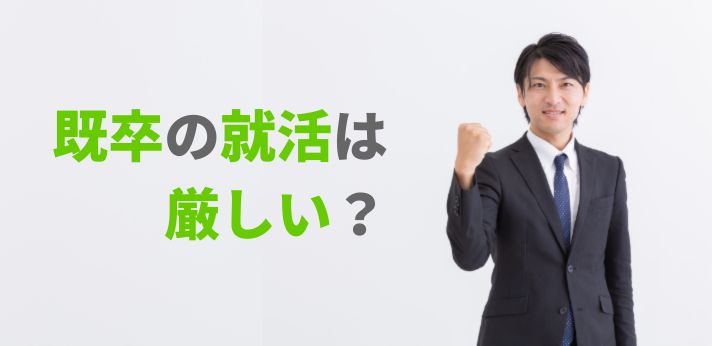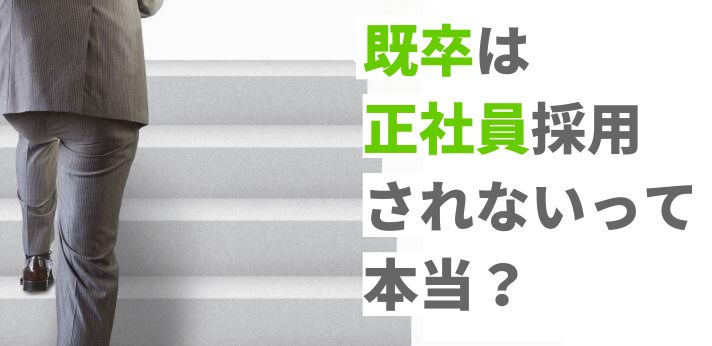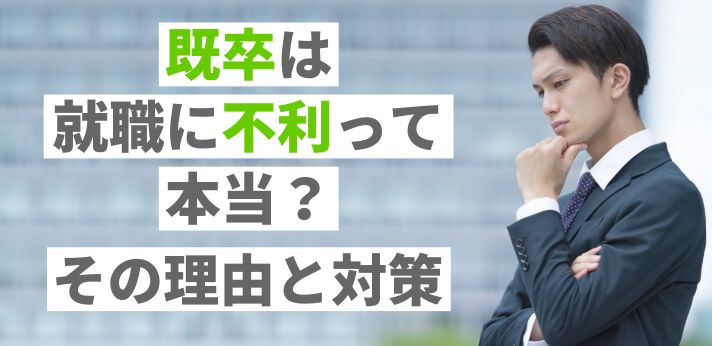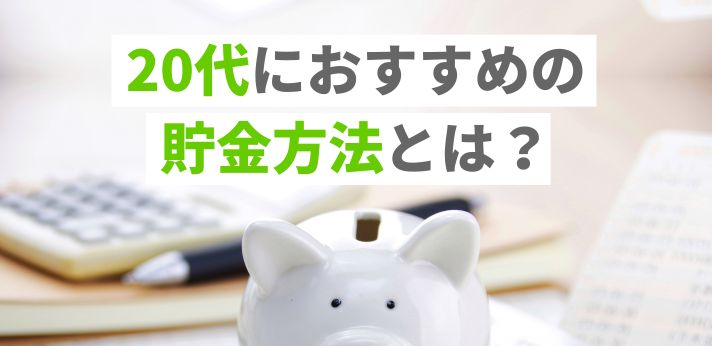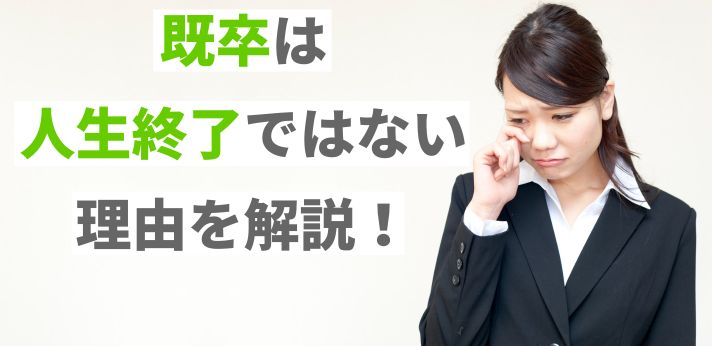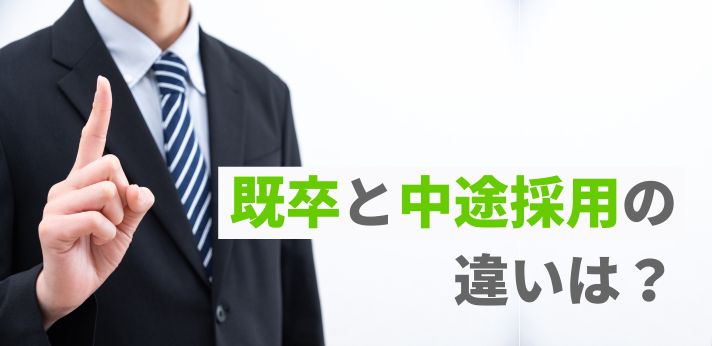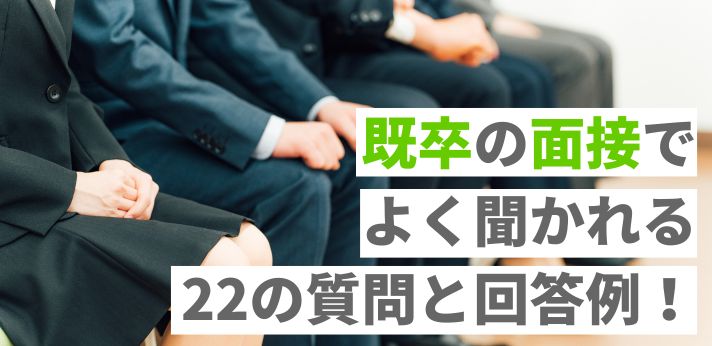既卒の就活方法は?職歴の書き方やおすすめの支援サービスをご紹介!既卒の就活方法は?職歴の書き方やおすすめの支援サービスをご紹介!
更新日
公開日
既卒就活の良い方法は、未経験歓迎の求人を探しつつ少しでも多くの企業を受けること
「既卒就活の方法を知りたい」「効率の良い就活方法が分からない」という方もいるでしょう。既卒就活は、応募時期を考慮して積極的に行動すれば、効率良く取り組むことが可能です。なかには、既卒としての応募が可能な新卒枠を設けている企業もあります。
このコラムでは、既卒の就活のコツや進め方、選考対策をご紹介。既卒の就職活動のポイントを押さえ、内定を獲得しましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
【既卒の就活方法】何から始めるのが良い?
既卒の就活では、本格的に動き出すため事前に準備すべきことがあります。ここでは、「どのような仕事があるか知る」「適性検査を受ける」というように、就職のために何から取り掛かれば良いかを詳しく解説します。
既卒ですが就活を始めたいです、どのようなステップで進めるといいでしょうか
就活は大まかに以下のようなステップで進みます。
①業界研究・自己分析
②履歴書・職務経歴書またはエントリーシートの作成
③適性検査
④面接
⑤内定
⑥入社
就活は業界や職種・企業研究など「相手を知る」ことと、自分のやりたいことや強みなど「自分を知る」ことから始めます。
数ある求人からどんな仕事が世の中にあるのかを幅広く見てみましょう。仕事を調べてみるという点では就活サイトがおすすめです。就活サイトや就活エージェントには自己分析ツールが用意されている場合もあるので、利用してみましょう。厚生労働省の職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tagもおすすめです。
業界研究と自己分析をおろそかにすると、その後の書類作成や企業の選び方、面接のPRにまで影響を与えかねません。①~⑥のステップを一人ですべて行うことに不安を感じたら、就活エージェントを利用してみてください。自分の希望や適性を把握したうえで自分に合った企業を紹介してくれます。また、悩んだときには専任アドバイザーが相談に乗ってくれてアドバイスもしてくれます。
どのような仕事があるか調べてみる
就職活動を始める前に「自分の強みを活かせることはなにか」「どのようなことに興味がもてそうか」という視点で、自分が知らない仕事を探してみましょう。世の中には多くの仕事があり、「現在の自分が知っている仕事はほんの一部だけ」という可能性もあります。Webサイトを活用したり周囲の人がどのような仕事をしているのかを聞いたりして、気になった仕事をいくつか書き出してみてください。
それらの共通点から「自分が仕事に求めているもの」を見出せれば、就職活動の軸が定まるでしょう。既卒は新卒よりも応募できる求人が少ないため、「就職先を決めたい」という焦りから、妥協して自分に合わない求人に応募したり、内定を承諾したりしてしまうことも。就職活動の軸が決まれば、そのようなズレを防ぎやすくなります。
世の中にどのような仕事があるのか知りたい方は、ハタラクティブの「職種図鑑」も参考にしてみてください。
Webサイトを利用して適性検査を受ける
自己分析の参考として、就職支援サイトの適性検査を受けるのもおすすめです。適性検査とは、Webサイト上で質問に回答することで自分の強みや向いている仕事が結果として表示されるサービスのこと。
自分では気づかなかった長所や短所、適性が分かり、自己分析が深まるでしょう。Web上で受けられる適性検査は確実に適性を判断する方法ではありませんが、自分を客観視する助けになるはずです。
自己分析で仕事の適性を見つける
就職活動において、自分の適性を知る方法の一つである「自己分析」を行うことも重要です。既卒は卒業後の空白期間があることから、企業からマイナスイメージを抱かれたり、「即戦力にならない」と思われたりする場合もあるので、選考で効果的なアピールが求められます。
自己分析をすれば、就職活動において以下のようなポイントを掴むことが可能です。
- ・自分の強みや弱み
・卒業後に身につけたスキル
・将来実現したいこと
既卒の場合は転職者と違って業務経験がないため、求人を選ぶ前に自己分析を行い、企業との適性を見極める必要があります。
自己分析のやり方
自己分析を行う際は過去の経験を振り返り、人から感謝された出来事や、やりがいを感じた瞬間を書き出します。書き出した内容の共通点を整理すると、自分が「できること」や「やりたいこと」が明確になるでしょう。
また、過去に取り組んだ活動があれば、興味をもった理由や課題に対する向き合い方を振り返ることで、行動・思考パターンが浮き彫りになります。自分の行動・思考パターンを理解するのは、仕事への適性を把握する有効な方法です。「どのような場面でモチベーションが上がるか」を振り返ったり、小さなころの夢や憧れを思い出してみたりするのも、自己分析のヒントになるでしょう。
第三者に意見を求めるのも就活に有効
自分で適性を判断するのが難しいと感じる既卒は、家族や友人といった第三者に意見を求めるのもおすすめです。第三者の意見を聞くことで、自分では気づけなかった長所や短所を指摘してもらえる可能性があります。
「家族や友人に相談するのが難しい」「的確なアドバイスを受けたい」とお考えの方は、既卒の転職をサポートしているハタラクティブへお気軽にご相談ください。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
既卒とは?
既卒とは、「内定がないまま学校を卒業し、その後正社員として就職をしていない人」を指します。働いていないニートや、アルバイトで生計を立てているフリーターも、既卒に該当します。
既卒になる理由は、「卒業までに内定がもらえなかった」「内定をもらった企業に納得できなかった」という理由があるようです。また、休学したり、公務員試験に落ちてしまったりして既卒になる場合も見られます。
| 区分 | 就職希望率 | 就職内定率 |
|---|
| 大学 | 76.6% | 91.6% |
| 短期大学 | 80.6% | 85.7% |
| 高等専門学校 | 58% | 98.7% |
大卒の場合、就職を希望する約8割のうち9割弱が内定をもらえているようです。しかし、就職を希望したものの内定が獲得できず、既卒となる場合も一定数あることが分かります。
卒業後3年以内が目安
既卒の枠は、卒業後およそ3年以内が目安といわれています。とはいえ、どこまでを既卒として扱うかは企業によって方針が異なるようです。
卒業後は就職せずフリーターとして働いていた場合も、卒業後およそ3年以内であれば既卒としての就職になります。
新卒との違い
新卒は、「大学・短期大学・高等専門学校などをその年に卒業する人」「3月の卒業後、4月に入社できるよう在学中に就活をする人」を指す言葉です。新卒の場合は中途採用枠ではなく、新卒枠で就職活動を進めることになります。
第二新卒との違い
第二新卒は、「新卒で入社した会社に就職後3年以内に離職した人」を指す言葉です。社会人経験があるため、第二新卒が就活する際は既卒と異なり、中途採用枠に応募することになります。
ただし、企業によっては、第二新卒枠を設けていたり、新卒として選考を受け付けていたりする場合もあるようです。
フリーターとの違い
フリーターは、学校を卒業後に正社員として就職せず、パートやアルバイトで働く人を指す言葉です。フリーターは就業する時間や曜日を選択しやすく、比較的自由な働き方を叶えられる特徴があります。
学校を卒業後3年以内であれば、既卒とフリーターは両立するものといえるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
既卒の就活は難しい?実際の状況
既卒の就活は新卒に比べると厳しい傾向にありますが、就職が不可能というわけではありません。就活に向けた準備を整え、ほかの既卒者と差をつければ、内定を獲得することは十分可能といえるでしょう。
既卒応募可の企業は全体の約72%
厚生労働省の「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」によると、令和4年度の新卒募集の際に「既卒応募可」とした企業は全体の約72%に上ります。
以下の表では、既卒を応募可能とした割合の高い産業をまとめました。
新卒の採用枠で正社員を応募した際の既卒者の応募可否(令和4年度新規学卒者)
| 産業 | 応募可能 | 応募不可 |
|---|
| 調査産業計 | 72% | 27% |
| 建設業 | 78% | 21% |
| 情報通信業 | 85% | 15% |
| 金融業・保険業 | 61% | 37% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 73% | 27% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 71% | 24% |
| 医療・福祉 | 85% | 14% |
すべての企業で既卒を新卒枠で応募可能としているわけではありませんが、高い割合で既卒者を歓迎していることがわかります。
既卒を採用した企業は全体の約40%
既卒を応募可能としていた企業割合のうち、採用に至ったのは約40%でした。産業別に見てみると、医療・福祉分野では56%、情報通信業では43%と、高い割合を示しています。
新卒の採用枠で正社員を応募した際の既卒者の採用状況(令和4年度新規学卒者)
| 産業 | 採用した | 採用しなかった |
|---|
| 調査産業計 | 40% | 60% |
| 建設業 | 24% | 76% |
| 情報通信業 | 43% | 57% |
| 金融業・保険業 | 41% | 59% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 39% | 61% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 34% | 66% |
| 医療・福祉 | 56% | 44% |
上記の表を見てみると、新卒枠での既卒の採用に多くの企業が積極的であることが分かるでしょう。
既卒者だからこそ得た「他人と異なる経験」に価値がある
上記のデータを見てもわかるとおり、既卒者の応募を可能としている企業は約70%にのぼります。その理由としては、若手の人材確保に苦戦している企業が多いことが挙げられるでしょう。
長く企業を成長・維持させるためにも、今後を担う若手は欠かせません。既卒のように一度も正社員として会社勤めしていない人材は、経験不足であったとしても、他社の色に染まっておらず、研修・仕事内容や会社の方針などを純粋な気持ちで吸収してくれるという魅力があります。
また、アルバイト経験や留学経験、苦労した経験など、既卒だからこそ得た他人と異なる経験が、入社後の仕事に活かせると考える企業も少なくないでしょう。ポテンシャル採用という言葉のとおり、やる気や元気、若手ならではの発想や吸収力に価値を見出し、期待をかける企業が存在します。
既卒がチャンスを掴むにはどのような就活方法がある?
既卒からの就活は、新卒時と同じように応募できる企業を探しましょう。企業によっては、既卒も新卒枠として応募できるほか、積極的に採用を行っている場合もあります。
また、条件を絞り過ぎず幅広く応募することや、既卒歓迎の求人を探すのも有効的な就活方法です。以下で詳細を説明するので、ぜひ確認ください。
既卒の就活は難しいと聞きました。就活を成功させるためにはどのような進め方をしたらいいでしょうか?
新卒の就活を経験した方は、経験やスキルを求められる既卒の就活を難しく感じるかもしれません。既卒の就活を成功させるために最も重要なことは、自分を良く知り、強みをアピールすることです。
まずは、アピールできるポイントを整理しましょう。アルバイトやインターン、学業やボランティアなど、これまでの経験で身についたスキルやエピソードを深掘りします。
次に、既卒者を採用している企業を探します。求人に「既卒歓迎」「未経験OK」と記載されている企業に応募するのがおすすめです。
あなたが応募したいと思った企業が求めているスキルに対して、自分のスキルが達していない場合は、応募する職種や業種に近いアルバイトをするなど、職務経験を積むことで、早い段階で戦力になれることをアピールしましょう。
まずは興味のある分野をじっくりと探し、焦らずに就職活動を進めていくことをおすすめします。
新卒枠で応募できる企業を探す
「既卒3年以内は応募可能」の記載がある求人を見つけよう
既卒が新卒枠で応募したい場合は、「既卒3年以内は応募可能」と記載されている求人を就活サイトで探してみてください。また、就活を進めるうえで選考を受けたい求人があれば、既卒も受けられるかどうか、個別に問い合わせるのも良い方法です。
既卒者が応募できる求人を効率的に探すなら、就職・転職エージェントに相談する手段もあります。既卒向けの求人を多数取り扱っているエージェントなら、自分の特徴に適した求人の提案を受けることが可能です。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
「既卒歓迎」や「未経験者歓迎」の求人を探す
既卒の就活は、Webサイトに「既卒歓迎」や「未経験者歓迎」と記載している求人を探すのも方法の一つ。既卒歓迎の求人なら、既卒について言及がない求人に応募するよりも採用されやすい可能性があります。
また、「未経験者歓迎」の記載がある求人は、知識や経験よりポテンシャルを重視している傾向にあるでしょう。未経験者を歓迎する企業は、人材を一から教育する姿勢で採用活動をしている場合が多いので、既卒者も受け入れられやすいといえます。
複数の求人に応募する
内定を獲得する確率を上げるためにも、既卒の就活では複数の求人に申し込むようにしましょう。最初から条件を絞りすぎず、就活サイトやハローワークといったサービスも活用しながら、視野を広げてできるだけ多くの企業に目を向けてみてください。
また、複数の選考を受けることで、次第に履歴書作成や面接に慣れ、リラックスした状態で選考に臨めるようになります。
就活をする前に把握すべき既卒のメリット
既卒で就活する際は、「挫折を経験している」「すぐに入社して業務経験を積める」といった要素が強みになる場合があります。既卒になった理由がネガティブなものであっても、それを乗り越えて就活をする経験は、新卒にない要素といえるでしょう。
ここでは、選考の場における既卒のニーズと、アピールする方法をご紹介します。
既卒者が就活成功に向けてアピールすべき3つのポイント
POINT【1】ポジティブに志望動機を伝える
既卒から正社員になりたい理由を明確に伝えましょう。新卒の就活時に採用されなかった、夢を追ってチャレンジしていたなど、既卒には様々な理由があります。社会人未経験だからこそ、「成長して企業に貢献したい」など、ポジティブにアピールしましょう。
POINT【2】これまでのスキルや経験
大学卒業後に得た経験やスキルは、なるべく具体的にアピールしましょう。アルバイトで責任ある立場になって取り組んだ経験や仕事で重ねた工夫は、エピソードや数字を用いて示すのがポイントです。また、既卒の期間に取得した資格は身につけた知識とともに、成長意欲があるという点でアピールポイントになります。
POINT【3】職場への適応力
環境の変化に適応してきたことをプラスに捉え、社員として採用された後も新しい環境に適応できるスキルがあることをアピールするのがポイント。未経験の職種や業界であっても、適応力を活かして積極的に学んでいく意欲を伝えましょう。
1.若い人材は企業側のニーズが高い
少子高齢化の影響もあり、企業によっては若い人材を十分に確保できていない可能性もあります。新卒採用時に思うように人材を集められなかった企業では、既卒者を積極的に歓迎している場合も。
若い人材は、物事を覚えるのが早かったり、柔軟に動けたりと、企業にとって重宝されやすい特徴があります。また、年齢を重ねている人よりも体力のあることを期待できるため、身体的な負担の大きい職種で採用されやすいようです。
2.挫折経験が強みになる
既卒の就活は、挫折を経験していることが強みとなり得ます。「新卒時に内定がもらえなかった」「休学のため就活できなかった」というように、挫折を経験している既卒者もいるでしょう。挫折を乗り越えて前向きに就活している姿勢は、「仕事でも失敗を乗り越えられる」「失敗を反省する素直さがある」といった強みをアピールできます。
3.空白期間の経験が仕事に活きることもある
空白期間があると、就職活動で不利になりやすいのは事実です。しかし、空白期間での経験が応募先企業の仕事に活かせることを説明できれば、プラス評価につながるでしょう。たとえば、アルバイトでのリーダー経験や、趣味を活かしたECサイトの立ち上げ経験があれば、「リーダーシップ」「行動力」「専門性」などをアピールできます。
4.すぐに入社して業務経験を積める
既卒から採用が決まれば、すぐに入社して業務経験を積めるのがメリットの一つです。新卒は、採用が決まってから入社までに数ヶ月〜1年程度掛かるのに対し、既卒は内定後すぐに入社することが可能です。そのため、人手不足の企業では、新卒より既卒を採用して人材を確保する方法を選ぶこともあります。すぐに入社して早くスキルを身につけられることは、企業にとっての大きなメリットです。
就活方法を知る前に把握すべき既卒のデメリット
既卒は、新卒や転職者に比べて就活におけるデメリットが多いといわれています。既卒に対してマイナスイメージがあったり、一括採用ではないため求人数が少なかったりするのが原因です。
1.新卒の就活で努力しなかったと思われる
採用担当者のなかには、既卒就活に対してマイナスイメージをもつ人もいます。「就職への意欲が低いのではないか」「内定をもらえない理由が何かあるのでは」というように、本人に問題があるという懸念を抱く場合もあるからです。そのため、就職活動では既卒になった理由をどのように説明するかが採用に影響するといえます。
2.新卒に比べて求人数が少ない
新卒の一括採用に比べると、既卒の求人数は少ないのが実態です。新卒採用で人材が確保できれば中途採用をしない企業もあるため、既卒が応募できる求人数が常にあるとはいえません。また、定着率の高い企業では、新卒採用時でしか応募できないという可能性もあります。
3.即戦力では転職者が選ばれる可能性が高い
既卒から中途採用枠に応募して内定を得るのは、難易度が高い傾向にあります。自分よりもスキルや経験が豊富な中途の転職者がいれば、就活の選考で不利になることが考えられるでしょう。
人手不足の企業では即戦力を求めるため、実務経験のない既卒として採用されるのは難しいといえます。即戦力を求める企業に応募するのは、既卒の就活方法として避けるのが無難でしょう。
既卒の就活に必要な対策方法とは?6つの進め方
既卒の就活方法では、志望動機や面接、一般常識を問う試験などに対して、新卒とは違う対策が必要です。以下では、それぞれのポイントをご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
既卒の就職活動では、客観的なプロの意見を大事にすることをオススメします。理由として、既卒の方には「空白期間をどう説明すれば良いのか分からない」という方が多いためです。意欲は見せられても、ブランク期間の説明が出来ず、お見送りが続いてしまう方も多くいらっしゃいます。
そこで大事にしてほしいのが、「就活のプロ(=キャリアアドバイザーやキャリアコンサルタント)」に伴走してもらうことです。社会人経験がない中でも活かせる経験やアピールポイントは間違いなくあります。面接で語れる「言語化」を行うため、学生時代の経験を一緒に振り返り軸を再整理し、市場の中で自身が活かすべきスキルを定めてもらうことを大事にしましょう。
また、時に厳しい言葉をもらうこともあるかもしれませんが、素直に受け入れ「まずはやってみる」という気持ちで就職活動を行ってみましょう!
1.業界・企業研究を念入りに行う
既卒の就職活動では、業界・企業研究をしっかりと行う必要があります。応募したい企業のWebサイトを見るだけでは、就活を進めるうえでの情報が不足するので注意が必要です。
「専門誌で業界の立ち位置をチェックする」「他社では行っていない取り組みや社会貢献活動を調べる」というように、多角的な視点で業界・企業研究をしましょう。就活で求める人材と合っていないと判断されたり、入社後のミスマッチで早期退職になったりしないためにも、自分の強みと企業の特徴を照らし合わせることが重要です。
2.履歴書の「職歴」の対策を徹底する
既卒者には職歴がありませんが、履歴書や職務経歴書の職歴欄を空欄のまま提出すると、「卒業後何もしていなかったのだろうか」と疑問をもたれる可能性があります。そのため、アルバイト経験のある既卒の方は、職歴欄にその経験を書くのがおすすめです。
アルバイト経験は、職歴として認められていないのが一般的。しかし、正社員の経験がない既卒者にとって、アルバイトの経験・実績は選考でのアピールに有効といえます。
在学中の部活動やサークル活動をアピールする方法もありますが、アルバイト経験のほうが仕事内容に直結しているので、イメージしてもらいやすいでしょう。特に、リーダー経験や売上実績があれば、採用担当者に評価される可能性があります。
3.志望動機では説得力をもたせる
志望動機では、「なぜ応募先企業でなくてはいけないのか」を説明することが重要です。他社でも使い回せる志望動機は、企業側に「どこでも良いから入社したいのでは」という印象を与えてしまいます。応募先企業だからこそ自分が活躍できる点、やりたいことが実現できる点を盛り込み、採用担当者が納得する根拠を示すことが大切です。
既卒者は転職者ほどスキルや経験が豊富ではないため、就職活動では熱意や意欲を示すのがポイント。入社意欲や入社後のキャリアプランを具体的に伝え、長期的に活躍できる姿勢をアピールしましょう。
4.筆記試験への対策をする
企業によっては、書類選考や採用面接のほかに、筆記試験を実施する場合もあります。筆記試験の予定がある場合は、事前に試験対策をしておくことが重要です。
就職活動で行われる筆記試験は、学力や一般常識を測る「能力検査」と、仕事への適性や人柄、価値観を測る「性格診断」の2種類があります。筆記試験によく利用される主流なテスト形式には「SPI」と「玉手箱」があり、どちらも能力検査と性格検査がセットになった試験です。以下でそれぞれの対策方法について解説します。
能力検査
能力検査は、国語的思考を問う言語分野と、数学的思考を問う非言語分野で構成。仕事で必要となる基礎的な能力が評価される傾向があります。能力検査の対策は、SPIや玉手箱の問題集を確認してみてください。既卒の就活であっても、試験に慣れるため過去問に取り組んでおきましょう。
「苦手な分野を重点的に練習する」「本番と同様に時間を意識して問題を解く」の2点を押さえることが、試験対策として効果的です。
性格診断
性格検査は人柄や適性、企業との相性などを調べるもので、数百の質問を通して結果を導きます。新卒や既卒の就活だけでなく、中途採用で利用されることも。性格検査には、表現を変えた似たような設問が紛れており、嘘をつくと回答を進めるうちに矛盾が生じるので注意が必要です。
性格診断で自分を偽って入社しても、企業との相性が悪ければ、早期離職につながってしまいます。一貫性のある回答ができるよう、性格検査は正直に答えましょう。
5.面接でよくある質問の回答を用意する
既卒者が就活を行うときは、「既卒になった理由は何か」や「卒業してからの空白期間に何をしていたか」のように、よくある質問に対する回答を用意しましょう。
回答に詰まってしまうと、面接の準備不足なのではと思われたり、志望度が低いのではと判断されたりする可能性があります。反対に、自分の状況を理解したうえで質問内容に沿った回答をスムーズにできると、好印象を与えることが可能です。
既卒になった理由
既卒の就活では、企業側から「既卒になった理由」について聞かれます。この質問に対する回答ポイントは、「嘘をつかないこと」です。新卒の就活でうまくいかなかった場合は、その事実を受け止めつつも、前向きに就職活動をしていることを示しましょう。
空白期間にしていたこと
空白期間の経験は、どのようなアピールにつなげたいかを考えながら説明を組み立てるのがコツ。アルバイトや資格の勉強など、空白期間にしていた経験に重きを置いて話すことがポイントです。応募先企業で仕事をしたいという熱意につなげられれば、回答に説得力をもたせられます。
就職を希望する理由
企業側は、なぜ既卒のタイミングで就職活動をするのか、その理由を知りたいと考えている場合もあります。夢を追いかけていたり、なんとなく就職に目が向かなかったりしていた場合は、学校を卒業後に「考えが変わったきっかけ」を添えると、採用担当者が納得しやすくなるでしょう。既卒者が正社員就職を目指すときは、できるだけネガティブなイメージを払拭できる回答を用意するのがおすすめです。
学生時代にしていたこと
企業によっては、既卒の応募者に対して学生時代にしていたことを質問する場合もあります。回答時のポイントは、「応募先の仕事に活かせるかどうか」です。
学業やサークル活動、ボランティア活動など、自分なりに力を入れていた経験を具体的に伝えましょう。周囲と協力したり、自分の提案で物事が進展したりしたエピソードがあれば、積極的に取り入れると、より好印象を残せます。
挫折に打ち勝った方法
採用面接で挫折経験について質問されたら、新卒の就活時に思うような結果を残せなかったことを伝えるのも手です。困難な状況を乗り越えた方法を知れば、応募者の人柄を理解しやすくなります。
「どのような挫折をし、どのように打ち勝ったのか」「挫折や失敗から学んだことは何か」をまとめられると、仕事でも同じように行動してくれるのではと感じてもらえるでしょう。
6.業界や職種に関連する資格を取得する
「応募先に役立つスキルがなく自信がない」「新卒の応募者と少しでも差をつけたい」と感じる方は、資格取得もおすすめです。就職を検討している業界や職種に関する専門資格を有していれば、仕事に対する熱意を汲み取ってもらえたり、早めに戦力として活躍できると見込んでもらえたりします。
ただし、資格の種類によっては、取得までに多大な時間がかかり、空白期間が延びてしまうことも。就活を進めるべきか、資格取得を優先すべきかをよく考え、最適な行動を選択することが大事です。
既卒向け!就活方法の注意点
既卒が就活方法で注意すべき点は、費用面やスケジュール面、マナーなどが挙げられます。それぞれの詳細を以下で解説しますので、事前に確認しておきましょう。
就活に掛かる費用を用意する
既卒が就活を始める前には、就活に掛かる費用を用意しておきましょう。具体的に就活に掛かる費用は以下のとおりです。
- ・交通費
- ・通信費
- ・証明写真
- ・履歴書
- ・スーツ、鞄、靴
就活が長期化した場合には就活期間中の生活費も必要になるので、費用を多めに見積もって用意しておくことをおすすめします。
選考に要する時間とスケジュールを管理する
既卒から就活を始める際は、選考に掛かる期間を把握しておきましょう。
企業に応募してから採用されるまでには、早くても1~2ヶ月程度掛かるのが一般的。選考に要する時間を事前に把握しておき、逆算して就活準備を進めていくことが大切です。
ただし、複数の企業に応募するときは同時進行で選考に進むため、スケジュールが過密になったり、活動自体が長引いたりする可能性もあります。就活をする際は対策や情報収集にも時間をかけ、どれくらいの時間が必要になるのかを把握しておくことが重要です。
就活は早めに取り組むのがポイント
やむを得ない事情や資格取得を優先している場合を除き、既卒の就活は早めに取り組んだほうが得策でしょう。「3年目までは新卒として見てもらえる」と安心するのではなく、空白期間を短くするための姿勢が大事です。就職の場では人材の年齢が若いほど企業によるニーズが高いため、1日でも早く行動するのがおすすめといえます。
履歴書や職務履歴書は使い回さないようにする
既卒の就活に限らずですが、履歴書や職務経歴書は使い回さないのが基本です。提出する書類は応募先ごとに用意し、書き損じが生じたらはじめから作成するようにしましょう。提出期限間近に慌てないためにも、余裕をもって応募書類を用意しておくことが大切です。
受ける企業をある程度増やしておく
既卒の就活では、応募する企業を絞り過ぎないようにしましょう。ほかの日程と被らないように1社ずつ選考を受けると、かなり時間が掛かります。だからといって闇雲に応募数を増やすと、準備に時間を要し、就活が長引く可能性も。応募する企業数は、多くて20社、少なくて5社以上を目安にしましょう。
面接ではネガティブな受け答えを避ける
既卒の就活では、前向きな回答で好印象を与えることが大事です。既卒であることを気にしてしまい、面接での受け答えがネガティブな内容になる人もいます。選考で謙虚さを全面に出してしまうと、自信のなさの表れだと判断されてしまうことも。「自分にできること」を胸を張って説明できれば、企業で働く姿をイメージしてもらいやすくなります。
既卒の就活で大手企業への就職は可能?
ここでは、既卒就活で大手企業への就職が可能かを詳しく解説します。大手企業への就職を考えている既卒の方は、以下をチェックしてみましょう。
大手企業への就職は難易度が高め
既卒から大手企業への就職難易度は、高めといえます。独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「調査シリーズNo.179 企業の多様な採用に関する調査 Ⅱ.調査結果の概要」によると、「新規学卒採用に重点を置いている」と回答した企業は約33.2%。「中途採用に重点を置いている」と回答した企業は約27.4%、「ほぼ同じ程度に重点を置いている」と回答した企業は約32.0%という調査結果になっています。
| 新規学卒採用に重点を置いている | 中途採用に重点を置いている | ほぼ同じ程度に重点を置いている |
|---|
| 100人未満 | 22% | 38.4% | 29.8% |
| 100~299人 | 32% | 27.1% | 34.4% |
| 300~999人 | 43% | 16.4% | 35.5% |
| 1000人以上 | 58% | 7.4% | 31% |
| 合計 | 33.2% | 27.4% | 32% |
上記の調査結果から分かるように、規模の大きい企業ほど新規学卒採用に重点を置いている傾向があります。既卒が大手企業で内定を獲得するには、新卒者以上に選考対策を行う必要があるでしょう。
大手企業で活かせるスキルを磨こう
既卒者が就活で大手企業に就職するには、自分が目指す業界や企業に求められるスキルを磨くのがおすすめです。たとえば、資格取得に向けて勉強するのも一つの手。スキルを磨くために取り組んでいる姿勢を評価される可能性もあるでしょう。
長期的なキャリアプランを考えよう
既卒から大手企業を目指すなら、長期的なキャリアプランを考えることが大事です。すぐに大手企業に就職しなくても、一度中小企業に就職し、経験を積んでから大手企業を目指す選択肢もあります。
既卒でも大手企業への就職は可能でしょうか?大手企業に就職するためのポイントはありますか?
大手企業も既卒者を積極的に採用しているケースがあります!
既卒でも大手企業への就職は可能です。ただし、新卒採用に比べて狭き門となることは覚悟しておきましょう。大手企業は「若手をゼロから育てられる」「一斉教育でコストや管理面でメリットがある」といった理由から、新卒採用に力を入れている場合が多いからです。
しかし、だからといって諦める必要はありません。大手企業であっても、事業拡大や専門性の高い分野での人材不足などにより、すぐに入社可能な既卒者を積極的に採用するケースも増えているからです。
そこで重要になってくるのが、「大手企業が求める人物像」と「あなたが持つ経験・スキル」を結びつけ、他の応募者と差別化を図ることです。
大手企業に就職するためのポイント
・空白期間の説明が明確にできる
・自己分析が出来ており自分の軸が整理出来ている
・徹底的な企業研究
・学生時代の強みをアピール
・熱意を伝える
ただ、人によって「良い会社」は異なります。大手企業だけに選択肢を狭めず、自分に合った転職先を広い視野で見つけることを大切にしてみてくださいね。
既卒の就活を成功させるには時期も関係する?
既卒の場合は基本的に通年採用のため、すぐに就活を始めるのがおすすめです。とはいえ、求人数や内定のもらいやすさは、時期によって違いがあるともいわれています。
就活方法について検討する際に、採用されやすい時期を意識してスケジュール調整するのも良いかもしれません。この項では、時期別の就職成功ポイントを解説します。
1月~3月は求人が増加するタイミング
一般的に、1月から3月にかけて求人が多くなるといわれています。そのため、既卒者はこの時期に集中して就職活動を行うのも手です。特に、年度末の3月は転勤や異動で人材が減りやすい時期。新年度を前に、「3月までに内定者を確保したい」と考える企業も多いので、1月には就活を始め、3月には内定をもらえるようスケジュールを立てるのも手でしょう。
4月~6月は求人が少なめ
4月~6月は、新卒者をはじめ、新年度から働く人材の教育がスタートするため、掲載される求人が少なめの時期です。就活に慣れていない人の場合、自分の希望条件に適した求人を見つけづらいことも考えられます。求人探しに苦戦する場合は、就職エージェントといったプロの手を借りることも検討してみましょう。
早期離職者が出てしまった企業では、再び人材の募集をかける可能性もあるので、タイミングによっては志望する分野の求人に応募できるかもしれません。また、在職者は異動による引き継ぎや担当者の変更で慌ただしい時期のため、競争相手を減らせるといったポイントもあります。
7月~9月は中途採用枠が増える
7月から9月にかけては、年度初めの業務や教育が一段落し、中途採用枠の求人が展開されやすくなります。幅広い業界・職種の求人が出される可能性があるので、このタイミングに合わせて就活の準備を進めておくのも一つの方法です。ただし、企業によっては選考中にお盆休みを挟むため、連絡が遅かったり選考が長引いたりする可能性もあることを理解しておきましょう。
10月~12月は既卒の就活に狙い目
1年で求人が多くなるのは、10〜12月ともいわれています。その理由は、夏のボーナス支給後に退職者が出ることにより、企業がその補充として10月頃に人材募集を開始するからです。中途採用枠のため経験者を募集する求人も含まれますが、なかには未経験で応募可能な仕事もあるので狙い目といえます。
就活の日程がこの時期に重なりそうであれば、万全の状態で自信をもって選考に臨めるよう、3ヶ月前の7月には準備を始めるのがおすすめ。また、確実に内定を得るために、4月ごろから早めにスタートを切るのも手しょう。
既卒におすすめな5つの就活方法
既卒の就活方法には、企業の採用ページの確認や紹介制度の利用、就職支援サービスの活用などが挙げられます。下記では、既卒の就活におすすめな方法を5つご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1.企業のWebサイトから採用ページを確認する
気になる企業や働いてみたい業界があれば、該当する企業のWebサイトを調べ、採用ページがあるかどうかをチェックしましょう。現在人材を募集中なら、そこから直接申し込むことにより、就活サイトを経由する手間を省けます。
企業のWebサイトから応募すれば、志望度が高いと判断してもらえるメリットも。ただし、採用ページに掲載されている情報は、労働条件が明確に記載されていないこともあります。不明点や疑問点があれば、選考を通じて自身で確認することが必要です。
2.友人や知人による紹介制度を利用する
企業によっては、友人や知人による紹介制度を設けているところもあります。友人や知人が実際に勤めている環境なら、「実際の人間関係」「働くうえでのメリット・デメリット」「自分に向いているかどうか」などを教えてもらえるので、詳細を掴んだうえで総合的な判断が可能です。
とはいえ、友人や知人が働きやすさを感じていても、自分が同じ気持ちになれるかは別です。選考に進んだあとにミスマッチを感じると、辞退をしづらいというポイントも理解しておきましょう。
3.既卒向けだけでなく複数の就活サイトに登録する
就活サイトには、新卒向けや中途・転職者向けなどがあり、それぞれ特徴が異なります。既卒の就職活動では、既卒を対象にしている就活サイトはもちろん、新卒向けや中途・転職者向けの就活サイトにも登録しておくのがおすすめです。
就活サイトは、空き時間を使って手軽に利用できますが、自分で企業とのやり取りを行うので、人によっては手間を感じる可能性があります。しかし、未経験者歓迎の求人を見つけやすく、ポテンシャル重視で採用したいという企業に出会える確率が高いでしょう。
新卒向けや中途・転職者向けの就活サイトも、既卒応募可の求人が含まれていることがあります。既卒向け以外の就活サイトもチェックすることで、自分に合った就職先に出会える可能性を高められるでしょう。
4.ハローワークで中途採用の求人を探す
ハローワークは、厚生労働省が管轄する公的な就職支援サービスです。厚生労働省の「ハローワーク」によると、全国500ヶ所以上に所在しています。ハローワークの特徴は、求人数の多さと管轄地域の求人に強いという点です。
ハローワークはアルバイトやパートの求人も多く、正社員以外の働き方をしたい方にもおすすめ。幅広い層に向けて就職支援を行っているため中途採用向けの求人も多く、「既卒応募可」の求人も見つけやすいでしょう。また、ハローワークでは履歴書の書き方や面接を突破するためのセミナーを無料で行っているので、就活方法でお困りの場合は利用してみてください。
5.既卒を対象にした就職エージェントを選ぶ
就職エージェントは、民間企業が運営する就職支援サービスです。就職エージェントの特徴は、企業ごとに、対象者や扱う業界と職種が異なること。大手エージェントは幅広い業界・職種を総合的に扱う傾向がある一方、中小エージェントは特定の分野に特化している傾向があります。就職エージェントを利用すれば必ずしも就職できるとは限りませんが、就職成功率は上がりやすいでしょう。
既卒の就活方法としては、若手が対象の「未経験可」「ポテンシャル重視」などの求人を中心に扱うエージェントを選ぶのがおすすめです。「既卒向け」と銘打っているエージェントなら、既卒者の就職を成功させるノウハウが豊富なため、効果的な就活方法を教えてもらえるでしょう。
ハタラクティブ在籍アドバイザーからエージェント利用に向けたアドバイス
就職エージェントを利用すれば、一人ひとりに担当の就活アドバイザーがつき、求人選びから選考対策、内定獲得まで全面的なサポートを受けられるのも大きな特徴です。一人で就活を進めなくてはならない既卒者にとって、就職エージェントの利用はおすすめの方法といえます。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
「既卒の就活方法が分からない」とお悩みの方は、若年層向けの就職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、既卒や第二新卒、フリーターなどに向けた求人紹介を積極的に行っているのが特徴。扱っている求人は、人柄や若さといったポテンシャルを重視する企業が多いため、経歴に自信のない方でも安心してご応募いただけます。
履歴書・職務経歴書の書き方や、既卒である理由を面接で説明する方法について、プロのキャリアアドバイザーが個別にアドバイス。1分程度で行える適職診断も含め、サービスのご利用はすべて無料なので、お気軽にご登録ください。
既卒の就活方法に関するお悩みQ&A
既卒の就活方法で悩んでいる方もいるでしょう。ここでは、想定される既卒の就活に関するお悩みをQ&A方式で解決します。
求人サイトでは、はじめに希望条件を登録します。
最初から多くの条件を設定すると該当する求人が少なくなってしまうので、自分の希望条件に優先順位をつけるのがおすすめです。既卒の場合は「未経験者歓迎」や「既卒応募可」の条件も設定しましょう。
中途の就活では、仕事に活かせそうな経験やスキルをアピールするのがコツです。
中途採用枠では転職者がライバルになるため、職歴がない既卒者は就活で不利になりがち。営業職に応募するならアルバイトでの接客経験、事務職を目指すなら簿記資格というように、職種ごとに効果的なアピールをしましょう。
模擬面接を繰り返し行うのがおすすめです。
企業側が重視するのは、「既卒になったことをどう考えているのか」「就職への意欲はあるか」など。就活前にしっかりと練習しておけば、思ったことを堂々と答えられるようになります。
事前の準備を徹底していれば、既卒の就活を成功させることが可能です。
就活を成功させるには、自己分析や企業研究、面接対策などを行うことがポイントといえます。1人での就活に不安を感じている場合は、プロの手を借りるのも有効的な方法の一つ。20代の若者に特化した就職エージェントのハタラクティブなら、既卒になった理由の説明方法もアドバイス可能です。性格から分かる所要時間1分程度の適職診断もありますので、既卒就活を成功させたい方は、ぜひご相談ください。