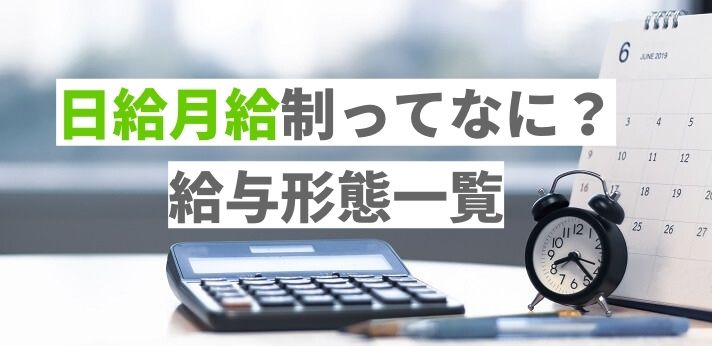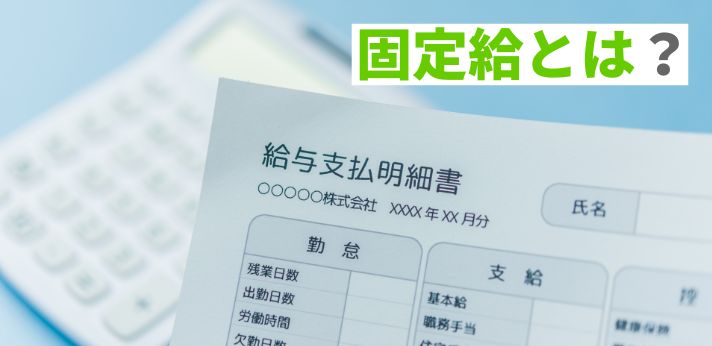住宅手当がないと一人暮らしはきつい?支給する企業の割合を確認しよう
このコラムでは、住宅手当を支給する企業の割合や支給額についてまとめました。また、住宅手当の平均相場や一人暮らしに必要な金額も解説。住宅手当の制度やメリットを知り、就職や転職の際の参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断

就職・再就職でお困りではありませんか?
当てはまるお悩みを1つ選んでください
住宅手当がないと一人暮らしはきつい?

住宅手当がないと一人暮らしがきついかどうかは、居住環境や収入によって異なるので一概にはいえません。家賃の安い地域や物件を選んだり収入が多かったりすれば、住宅手当がなくても一人暮らしは十分に可能でしょう。
一人暮らしに必要な金額
総務省が実施した「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果 6 借家の家賃・間代(p.10)」では、専用住宅の1ヶ月あたりの家賃平均は5万9,656円という結果が出ています。
また、総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要」によると、項目別消費支出は以下のとおりです。
| 費目 | 月平均額 |
|---|---|
| 食費 | 4万6,391円 |
| 光熱・水道 | 1万3,045円 |
| 家具・家事用品 | 5,955円 |
| 被服及び履物 | 4,712円 |
| 保健医療 | 7,426円 |
| 交通・通信 | 2万1,796円 |
| 教育 | 2円 |
| 教養娯楽 | 1万9,425円 |
| その他の消費支出 | 2万5,051円 |
※単身世帯データの住居費を除く
参照:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要 Ⅱ 総世帯及び単身世帯の家計収支 表Ⅱ-1-2 消費支出の費目別対前年実質増減率 -2023 年-(p.15)」
家賃が6万円と仮定すると、上記の費目を合わせた支出は約20万円。毎月20万円を手取りで確保するには、給料の総支給額が25万円ほど必要になります。給料の支給額や家賃の金額、毎月の消費支出によっては、住宅手当がないと一人暮らしがきつく感じる恐れも。
より詳しい一人暮らしに必要な金額の目安を知りたい方には、「手取り20万は額面や年収でいくら?一人暮らしはきつい?家賃や貯金も解説」のコラムも参考になるでしょう。
参照元
総務省統計局
令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果
家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
住宅手当とは?

住宅手当とは、住宅の一部費用を企業が補助する福利厚生のことです。住宅手当の具体的な定義は企業によって異なるため、毎月の家賃補助を社員に支給する会社もあれば、住宅ローンの費用を一部補助する会社も。法定外の手当のため、住宅手当の支給額や条件も企業が自由に決められます。
また、雇用形態や扶養している家族の人数によって、支給額を設定している企業もあるようです。
住宅手当と社宅手当の違い
住宅手当は給与の一部と考えられるため、社会保険や住民税、所得税などの税金の課税対象になります。住宅手当を支給されることで家賃の負担は減りますが、支払う税金の額が増えてしまうことを理解しておきましょう。
一方、社宅手当は企業が用意した社宅や借り上げ社宅の利用に対して支給される手当で、企業が直接家賃を負担する場合もあるようです。企業契約の社宅であれば、一定条件のもと非課税になる可能性もあるでしょう。
「借り上げ社宅とはどんな制度?メリットやデメリットと家賃相場を解説」のコラムでは借り上げ社宅のメリットとデメリットを解説しているため、あわせて参考にしてみてください。住宅手当を支給している会社の割合
厚生労働省が実施している就労条件総合調査を参考に、2020年と2014年、2009年に住宅手当を支給している会社の割合を以下にまとめました。
| 年度 | 住宅手当を支給している会社の割合 |
|---|---|
| 2020年 | 47.2% |
| 2014年 | 45.8% |
| 2009年 | 41.2% |
上記によると、住宅手当を支給している会社の割合は2020年が47.2%、2014年が45.8%、2009年が41.2%という結果が出ています。このことから、住宅手当を支給する企業は年々増加傾向にあることが分かるでしょう。
また、以下は企業規模別の住宅手当の支給割合を抜粋して表にしたものです。
| 企業規模 | 支給割合 |
|---|---|
| 2020年調査計 | 47.2% |
| 1,000人以上 | 61.7% |
| 300~999人 | 60.9% |
| 100~299人 | 54.1% |
| 30~99人 | 43.0% |
企業規模別にみてみると、規模が大きくなるほど住宅手当が支給される割合も高くなっていることが読み取れるでしょう。
住宅手当をもらうには?
住宅手当の制度がある企業であっても、住宅手当を受けられない場合もあります。たとえば、住宅手当を支給するのは「正社員のみ」「社宅のみ」「転勤者または遠方からの入職者のみ」など企業によってさまざまです。会社の従業員だからといって住宅手当をもらえるとは限らないため、会社の就業規則を確認しておきましょう。厚生労働省
結果の概要
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
住宅手当の平均相場
ここでは、住宅手当の平均支給額や、法定外福利厚生費における住宅関連の手当の割合を紹介します。
厚生労働省の「令和2年 就労条件総合調査の概況」を参考に、住宅手当の平均支給額をまとめました。
| 企業規模 | 住宅手当の平均支給額 |
|---|---|
| 2020年調査計 | 1万7,800円 |
| 1,000人以上 | 2万1,300円 |
| 300~999人 | 1万7,000円 |
| 100~299人 | 1万6,400円 |
| 30~99人 | 1万4,200円 |
上記によると、住宅手当の平均支給額は1万7,800円です。企業規模1,000人以上で2万1,300円、300~999人だと1万7,000円。企業規模100~299人で1万6,400円、30~99人だと1万4,200円と、大手企業であるほど従業員に支給される住宅手当の割合が高い傾向があります。
なお、厚生労働省が実施した「平成27年 就労条件総合調査の概況 第18表 諸手当の種類別支給された労働者1人平均支給額(平成26年11月分)(p.21)」の調査結果では、産業別にみた住宅手当の平均支給額は、情報通信業が2万5,312円と最も高額でした。会社によって規定は異なりますが、「住宅ローンの3割を負担」「一律2万円を負担」など、支給額はさまざまです。
参照元
厚生労働省
結果の概要
住宅手当が支給される基準は企業によって異なる
住宅手当が支給される条件は主に、「正規雇用かどうか」「一人暮らしかどうか」です。住宅手当は企業独自の福利厚生制度なので、支給する基準や条件は会社内で自由に決められます。ここでは、住宅手当支給の条件をそれぞれ詳しく解説しますので、確認してみましょう。
雇用形態
住宅手当を支給される際に、正規雇用の社員かどうかが基準とされる可能性があります。転勤が発生すると引越し費用や転勤先の居住などの確保が必要になるため、社員の雇用継続のために企業が費用を負担するのが目的です。
なお、一般的には非正規の派遣社員やアルバイトには住宅手当がないことが多く、労働条件によって支給されるかが変わります。
大手企業だから住宅手当がもらえるとは限らない
住宅手当は大手企業だからといって支給されるとは限りません。企業ごとに福利厚生の方針は異なり、住宅手当を設けていない場合や支給条件が厳しく設定されている場合もあるようです。
たとえば、従業員の雇用形態や勤続年数によって支給対象が限定されることも。そのため、住宅手当を期待する場合は、企業の福利厚生制度を事前に確認しましょう。同居人の有無
一人暮らしか家族と同居しているかを住宅手当の支給基準にしている企業もあるようです。特に単身者向けの住宅手当は、支給額が低めに設定されていることが多く、家族と同居する場合や扶養家族がいる場合には手当の額が増えることが一般的。家族がいる場合は、一人暮らしよりも大きな住居が必要だったり、家賃も高かったりする可能性が考えられるからです。
また、親と同居している場合や、実家から通勤している場合は、支給対象外となる場合も考えられます。実家住まいの場合、同居している家族に食費や光熱費を毎月支払っていたとしても、契約上の家賃は発生していないからです。
住宅補助の支給条件について詳しく知りたい方は「一人暮らしでも家賃補助の対象になる?支給条件や自治体の制度も解説」を参照ください。
住宅手当のメリット

住宅手当には、企業側と労働者側のそれぞれにメリットがあります。以下で詳しく解説しますので、ぜひチェックしてみてください。
企業側のメリット
住宅手当を支給する会社のメリットとして、生活安定をサポートし、従業員を職場に定着させる効果があります。また、住宅手当は基本給の引き上げよりも社会保険や賞与の計算に影響しにくいため、コストを抑えながら従業員の待遇を改善する手段として有効です。
さらに、住宅手当を充実させることで、遠方からの人材確保やUターン・Iターン転職を促進する効果も期待できるでしょう。
労働者側のメリット
住宅手当をもらうことのメリットは、ローンや毎月の家賃支払いの負担が軽くなり、生活に余裕が生まれやすい点です。特に都市部のように家賃が比較的高い地域では、大きな助けとなり得るでしょう。また、住宅手当があることで希望する勤務地に住みやすくなり、通勤時間の短縮につながることもメリットです。
就職・転職前に企業の福利厚生や手当を確認しよう
新卒の就活時や転職活動時には、福利厚生をしっかりと確認するのがおすすめ。住宅手当に限らず、引越し手当や家族手当、赴任手当などの補助の有無も含めてチェックしておくと良いでしょう。
自分に合った働き方をするためにも、どのような手当が従業員に支給されるかだけでなく、支給条件や金額などを細かく調べておくことが大切です。福利厚生と手当の有無や金額を確認することで、実際の生活費の負担がどの程度軽減されるかを把握しやすくなります。特に転職の場合は、前職と比較してどのようなメリット・デメリットがあるかを事前に確認し、総合的に判断しましょう。
福利厚生について詳しく知りたい方は「福利厚生とはどんな制度?目的や適用条件を分かりやすく解説します!」をご一読ください。
「住宅手当や家族手当など、福利厚生が充実している企業はどこだろう?」「自分に合う会社や仕事はどのようなもの?」など、就職・転職活動に関する悩みがある場合は、20代のフリーター、第二新卒、既卒向け就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブでは、専属のキャリアアドバイザーがマンツーマンで若年層の就活を徹底サポート。履歴書添削や面接の練習、企業紹介などを一貫して行っています。企業とのやり取りもキャリアアドバイザーが行ううえ、サービスはすべて無料で利用できますので、ぜひこの機会にご連絡ください。
住宅手当に関する疑問を解消!よくあるお悩みQ&A
住宅手当に関する疑問やお悩みをQ&A形式で解消いたします。「そもそも住宅手当って何?」「支給には条件があるの?」など、よくある質問をまとめました。
住宅手当ってどういう制度ですか?
住宅手当とは、社員の住宅費を企業が補助する制度です。 賃貸であれば家賃の一部を会社が負担したり、持ち家の場合はローン返済を補助したりと、企業によって形式は異なります。
なぜ会社によって住宅手当の有無が異なるのですか?
住宅手当制度の導入は義務ではなく、会社が任意で決めるものだからです。住宅手当だけでなく、法定外福利厚生の細かい内容は企業によって異なります。
詳しくは、このコラムの「住宅手当とは?」で解説していますので、興味がある方はぜひ参考にしてみてください。
住宅手当の支給金額はどれぐらいですか?
企業によって支給額は異なります。「一律△△円」「基本給の×%」のように定めている企業もあれば、同じ会社内であっても、雇用形態や扶養家族の有無、勤務地や役職などによって金額が変わる企業もあるようです。
「家賃補助は会社からいくらもらえる?支給条件やメリットを解説!」のコラムもあわせて参考にしてみてください。
住宅手当のある会社に就職したいです
選考に応募する前に、求人の福利厚生欄をチェックしておきましょう。「住宅手当が支給されるか」「住宅手当が支給される条件」を事前に把握できます。また、より詳細な企業情報を手に入れたい方は、就職・転職エージェントの利用がおすすめです。
若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブでは、企業に事前調査を行っていますので、就職前に就業条件や福利厚生を確認できます。住宅手当の有無を確実にチェックしたい方は、ぜひこの機会にご利用ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?
マーケティングアシスタント
東京都
年収 315万円~360万円
正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!
ライター・取材担当
東京都
年収 315万円~360万円
未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?
営業
東京都
年収 328万円~374万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆
ルート営業
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…
年収 228万円~365万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「お悩み」についての記事一覧
- 「仕事の悩み」についての記事一覧
- 「給料の悩み」についての記事一覧
- 住宅手当がないと一人暮らしはきつい?支給する企業の割合を確認しよう