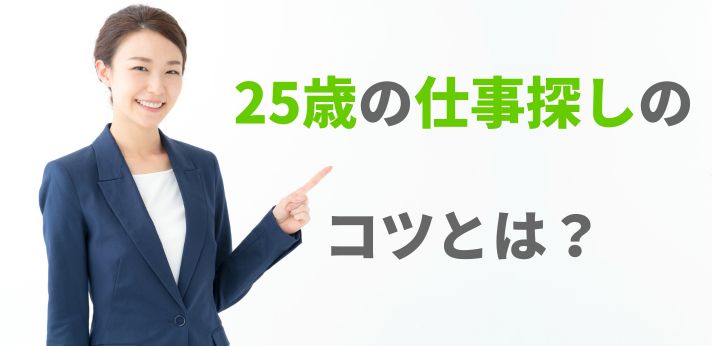30歳の平均貯金額はいくら?大きな出費に備える貯金のコツも紹介30歳の平均貯金額はいくら?大きな出費に備える貯金のコツも紹介
更新日
公開日
30歳を含む30~39歳の平均貯金額は、一世帯あたり約718万円
30歳ではどのくらい貯金額があれば、結婚・出産・教育・住宅購入などのライフイベントを安心して過ごせるのか知りたい方も多いでしょう。。このコラムでは、30代の平均貯金額や支出の無駄を見直す節約のポイントなどを解説。貯金は自分の収入やライフスタイルに合った方法で行うことが大切です。将来の安心のために無理のない貯金生活を始めましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
30歳の平均貯金額はいくら?
2022年の厚生労働省の調査「II 各種世帯の所得等の状況」によると、30歳を含む30〜39歳の一世帯あたりの平均貯金額は約718万円です。年代別だと、40代は約926万円、50代は約1,248万円と年齢が上がるにつれて高くなっています。
| 年齢 | 平均貯金額 |
|---|
| 29歳以下 | 245.1万円 |
| 30~39歳 |
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
しかしながら、正規雇用と非正規雇用ではそもそもの収入差が大きく、職種や勤め先によっても年収は異なるもの。特に30代だと、実家暮らしか一人暮らしか、結婚しているか独身か、子供がいるかいないかなどの条件の違いで支出状況に大きな差が出ます。平均貯金額に関してはあくまで目安として捉え、自分の収入に合った分の金額を貯金していきましょう。
一人暮らしを始めるならどれくらいの貯金が必要?
一人暮らしを始める際の理想的な貯金額は、家賃の5~7ヶ月分程度です。もし、家賃5万円の物件にするなら、引越し費用や日用品、家具の購入なども含め、30万円程度は用意しておきたいところ。詳しい内訳を知りたい方は、一人暮らしに必要なお金について解説している「フリーターの一人暮らしはきつい?入居審査や家賃など気になる疑問を解決」もあわせてご覧ください。
単身世帯の平均貯金額
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
30歳以降の大きな出費を補うためにも貯金は大切
ここでは、ライフイベントにともなった30歳以降にかかる主な費用について解説します。結婚や出産など、人生のタイミングは人によってさまざまです。しかし、いざ必要になったときに困らないよう、知識として頭に入れておきましょう。
結婚費用
結婚にかかる費用は、およそ数百万円にもなることが多いようです。挙式・披露宴の式場費用をはじめ、衣装や装飾、招待人数に合わせた料理や引き出物など、さまざまな出費が生じます。規模や人数によって変動はあるものの、結婚式をする際にはある程度の貯金が必要になるでしょう。「フリーターは結婚できる?できない?後悔しないためのポイントを紹介」では、結婚後に想定されるいろいろな費用について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
出産費用
厚生労働省「出産費用の見える化等について」によると、令和4年度における全施設の平均出産費用は約48万円でした。また、年間を通じて約1%程度上昇していることが分かります。
| 年度 | 出産費用 |
|---|
| 平成24年度 | 41.7万円 |
| 平成25年度 | 42.1万円 |
| 平成26年度 | 43.0万円 |
| 平成27年度 | 44.0万円 |
| 平成28年度 | 44.5万円 |
| 平成29年度 | 44.8万円 |
| 平成30年度 | 45.4万円 |
| 令和元年度 | 46.0万円 |
| 令和2年度 | 46.7万円 |
| 令和3年度 | 47.3万円 |
| 令和4年度 | 48.2万円 |
この出産費用に含まれるのは、入院料や分娩料、手当料などがあります。また、出産前には事前準備としておむつやベビーベッド、ミルクなどを用意する必要があるため、まとまったお金がかかるものです。出産時には、健康保険から50万円を受給できる出産育児一時金制度もありますが、賄えきれなかったときのためにも、余裕をもって貯金をしておくのが賢明といえるでしょう。
子どもの教育費用
子どもの教育費用は、公立・私立によって大幅に異なります。文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高等学校まですべて公立に通った場合、卒業するまでの15年間にかかる平均学習費は、約597万円です。幼稚園から高等学校まですべて私立にすると1,900万円を超えます。
| | 公立 | 私立 |
|---|
| 幼稚園 | 18万4,646円 | 34万7,338円 |
| 小学校 | 33万3,265円 | 182万8,112円 |
| 中学校 | 54万2,475円 | 156万359円 |
| 高等学校 | 59万7,752円 | 103万283円 |
また、子どもの希望や年齢によっては、習い事や塾に通うこともあるでしょう。そのため、家族をもつと決めたら早めに貯金を始めるのがおすすめです。
住宅購入資金
住宅の購入には多くの場合、住宅ローンを利用しますが、物件価格やローンの条件によって必要な資金は大きく異なります。都市部と郊外では価格差があり、設備や広さによっても費用は変動しますが、一般的に数千万円規模の出費となるでしょう。また、住宅ローンを利用する場合でも、頭金として自己資金を準備するのが一般的です。頭金の割合を高くすると、ローンの返済負担を軽減できますが、そのためには計画的な貯金が欠かせません。
結婚や子育てといったライフイベントと重なることもあるため、将来の支出を見据えて資金計画を立てることが重要です。住宅市場の動向や物件の相場を把握しながら、無理のない資金準備を進めましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
30歳は毎月いくら貯金すれば良い?
毎月の貯金額は収入やライフスタイルによっても異なりますが、たとえ少しずつでも「続けること」が大切です。以下を参考に、30歳から無理のない貯金を実現していけるようにしましょう。
貯金額は年収によって異なる
毎月の貯金額は月収の約10~15%が目安といわれています。貯金できる額は、その人の年収や家庭の有無などによって変わりますが、30歳で独身の場合は月収の約20%以上を目標にしてください。ただし、貯金のためだけに無理をする必要はありません。自分の収入やライフスタイルに合った金額の貯金が継続できるよう努めましょう。
老後・緊急時の資金を準備しておくことも重要
緊急予備資金
緊急予備資金とは、病気になったり、会社が倒産したりと急に働けなくなったときのために備えておくもの。緊急予備資金は毎月の生活費の約3~6ヶ月分が目安とされているため、貯金を始める際は現在の固定費や支出がどれくらいなのかを把握しておくことがポイントです。
老後資金
金融庁「高齢社会における資産形成・管理」によると、95歳まで生きた場合、公的年金のみでは資金が足りず、貯金から約2,000万円の取り崩しが必要になるといわれています。また、夫65歳以上・妻60歳以上の夫婦が年金収入のみの生活をすると、毎月5万円ほどの赤字になるようです。公的年金は収入によっても受給金額が異なるので、安心した老後を迎えるためにも、30歳前後からは堅実な貯金を始めるのが良いでしょう。
30歳が貯金するための具体的な方法
ここでは、具体的な貯金の方法について解説します。以下を参考に、まずは自分ができるところから始めてみましょう。
節約する
貯金に回すだけのお金がない場合は、日頃から節約を意識するのが大切です。特に、家計簿をつけていない場合や支出の項目を意識していない場合は、思わぬところで無駄遣いをしていることも。以下に節約のポイントを挙げたので、無駄な出費がないかを振り返ってみましょう。
- ・固定費が高過ぎないか見直す(住居費、光熱費、通信費など)
- ・高い消耗品を使わない
- ・コンビニでいらない物を買わない
- ・服や化粧品などを必要以上に買わない
- ・飲み物は持参しペットボトルは買わない
- ・外食を減らす
- ・ATMで手数料を払わない
- ・スーパーでは予算を決めて買い物をする
- ・水道をこまめに止めるなど節水を意識する
- ・冬は厚着をしてエアコン代を節約する
貯金にストレスは厳禁!
貯金のため「あれもこれも我慢しなければ!」という節約は長く続きません。たまには外食で贅沢する、決めた範囲で趣味にお金をかけるなど、ストレスなく貯金を続けられる工夫を考えましょう。また、漠然と貯金をするのではなく、「結婚資金として△歳までに×円貯める」「△円貯めて海外留学する」など、貯金の具体的な目的を意識するのも大切です。
家計簿アプリで収支を管理する
家計簿アプリを活用すると、日々の支出を簡単に記録でき、無駄遣いを可視化しやすくなります。貯金を増やすためには、まず自分の収支を把握することが重要です。レシートを撮影すると自動でデータ化されたり、銀行口座やクレジットカードと連携して取引履歴を記録できたりするアプリもあります。毎月の支出を分析することで、節約できるポイントを見つけやすくなるでしょう。
貯金専用の口座を開設する
貯金を確実に増やすためには、普段使いの口座とは別に「貯金専用口座」を作るのが効果的です。給与が振り込まれたら、一定額を先に貯金用口座へ移し、残った分で生活する習慣をつけると、計画的に貯金を増やしやすくなります。将来のマイホーム購入や子どもの教育費など、大きな支出に備えて、無理なく積み立てを続けていきましょう。
クレジットカードを有効活用する
クレジットカードを上手に使えば、お得にポイントを貯めて支出を抑えることも可能です。多くのカードでは、利用金額に応じてポイントが還元され、貯めたポイントは商品券やマイル、電子マネーなどに交換できます。日常の買い物や光熱費、通信費などの固定費をクレジットカード払いにすることで、無理なくポイントを貯められるでしょう。
ただし、使いすぎには注意が必要です。計画的に利用し、リボ払いや分割払いを多用せず、一括払いを基本にすることで、無駄な利息を発生させずに賢く活用しましょう。
財形貯蓄をする
貯金が苦手という方は、財形貯蓄の利用がおすすめです。財形貯蓄とは、勤め先の企業が金融機関と連携し、給与やボーナスから天引きで貯金をしてくれる制度。もし会社が制度を導入していれば、申し込みを検討してみましょう。
積立預金をする
積立預金とは、預金口座から定期預金口座へ毎月自動でお金が積み立てられるもの。時間や手間がかからず、コツコツとしっかりお金を貯めることができます。目標金額にあわせて積み立て金額を設定できるので、貯金が苦手だったり難しいと感じたりする方におすすめです。
投資投資をする
貯金を効率的に増やす方法として、投資を取り入れるのも有効です。特に積立投資は、定期的に一定額を投資することで、リスクを分散しながら資産を増やせる手法として人気があります。長期的な視点でコツコツと運用を続けることで、安定した資産形成につながるでしょう。
NISA
NISAは、投資で得た利益が非課税となる制度で、資産運用を始める際の大きなメリットとなります。2024年の制度改正により、年間最大360万円まで投資可能となり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を組み合わせて利用可能です。つみたて投資枠では、長期運用に適した投資信託のみが対象で、少額から投資できます。
iDeCo
iDeCoは、老後資金を自分で積み立てる私的年金制度です。定期預金や投資信託などから運用商品を選び、毎月決まった金額を積み立てていきます。掛金は全額所得控除の対象となり、受取時も税制優遇があるため、節税しながら老後資金の準備が可能です。ただし、60歳まで原則引き出せないため、長期的な資産形成を考えて活用しましょう。
金銭信託をする
金銭信託とは、信託銀行に資金を預け、専門家が運用を行う金融商品です。銀行預金と異なり、信託銀行が資産運用を行い、その運用益が利用者に分配される仕組みとなっています。短期的な市場の変動に左右されにくく、比較的安定した運用が期待できる点が特徴です。
また、一般的な預貯金よりも高い利回りが見込めるため、堅実に資産を増やしたい30代の貯蓄方法として適しています。ただし、元本保証はなく、解約時期によっては元本割れのリスクもあるため、利用する際は慎重に検討しましょう。
30歳で貯金を増やすには、節約で支出を減らすだけではなく、そもそもの収入をアップさせるという方法があります。今の職場の給与が低いと感じている方、自分の力に合った給与がもらえていないと感じている方は、転職を検討するのも一つの手。将来の生活を視野に入れながら、今よりも年収アップが図れる仕事を探してみましょう。
若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブでは、アドバイザーがご希望や条件をお聞きしたうえでその方に合った求人提案を実施。「給与アップしたい」「初めてだけど正社員になりたい」というご相談に対応しています。相談のみのご利用も歓迎しておりますので、ぜひお気軽にご登録ください。
30歳の貯金に関するQ&A
30歳になると、「周りの人はどれくらい貯金しているのか」「今の貯金額で将来は大丈夫なのか」といった疑問や不安を抱えることも少なくありません。ここでは、30歳の貯金に関するよくある質問とその答えをまとめました。貯金がゼロの場合の対策や、一人暮らしを始める際の目安、収入が低くても貯金を増やす方法など、さまざまなケースについて解説します。
30代で貯金がない場合でも、今から計画的に貯蓄を始めることで将来に備えることが可能です。まずは毎月の収支を見直し、無理のない範囲で定期的な貯金を始めることをおすすめします。「貯金がない人はどれくらいいる?年代別の貯蓄額や効果的な節約術」のコラムでは、無理なく節約して貯金するためのコツも紹介しているため、あわせて参考にしてください。
現在30歳のフリーターですが収入が低く貯金ができません
フリーターとして働いていると、収入が不安定で貯金が思うように進まないことがあります。そのため、安定した収入を確保する手段として、正社員を目指すのも一つの選択肢です。すぐに正社員になるのが難しい場合は、まずはアルバイトや派遣社員として働きながら、正社員登用のある職場を探してみるのもよいでしょう。「フリーターの貯金額はいくら?正社員との差は?お金を貯めるコツを紹介」のコラムでは、フリーターと正社員の貯金額について触れています。正社員就職に迷っている方はぜひご参照ください。
30歳で貯金が10万円ほどですが一人暮らしはできる?
30歳で貯金が10万円ほどの場合、一人暮らしを始めるのは慎重に考えた方がよいでしょう。一人暮らしを始めるなら、家賃の5~7ヶ月分程度の貯金が貯まったころがおすすめです。余裕をもった備えがないと、急な病気や失業時に生活が厳しくなる可能性があります。「一人暮らしにかかる費用とは?フリーターの年収でも可能?」では一人暮らしにかかる費用を紹介していますので、事前に貯めておいたほうがよい金額の目安として参考にしてください。