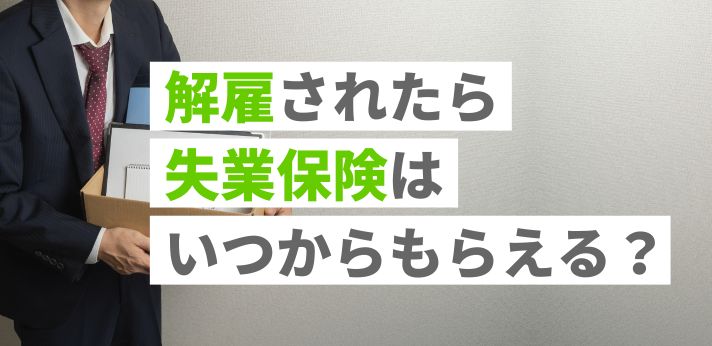退職を1ヶ月前に伝えるのは遅い?非常識だと思われないポイントを紹介
更新日
公開日
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
退職予定の1ヶ月前に意思を伝えても問題ないかは、会社の状況によって異なる
退職の1ヶ月前に意思を伝えることは、非常識なのか疑問に感じる方もいるでしょう。日本の法律では、申告から最短2週間で退職できるとされています。しかし、実際には業務の引き継ぎの時間が必要で、2週間前では会社に迷惑を掛けてしまう恐れがあるでしょう。
このコラムでは、退職までに必要なステップや円満に退職するためのマナーも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
退職の1ヶ月前に意思を伝えるのは遅い?
退職予定の1ヶ月前に意思を伝えても問題ないかは、会社の状況によって異なります。退職の意思を伝えるタイミングは、そのときの会社の状況や自分の業務内容などによって変わるため、一概に「1ヶ月前では遅い」とはいえないでしょう。
たとえば、社内に業務を引き継ぐ人物がいて、業務の引き継ぎが2〜3週間ほどでスムーズに終わるのであれば、申告が1ヶ月前でも遅くはありません。
しかし、小規模の会社や人手不足の部署などでは、後任者を新しく採用しなくてはいけない場合も。そのため、「1ヶ月前の申告では遅い」と思われる可能性もあるでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職を申告する適切なタイミング
特別な理由がないのであれば、2〜3ヶ月前までに退職の意思を伝えるのが理想的です。後任者の有無や引き継ぎの量にかかわらず、退職意思を固めたのであれば余裕をもって申告しましょう。
退職決定後は、仕事の引き継ぎや取引先への挨拶回り、有給消化など普段の業務のほかに時間をとられることが増えるため、思っていたより忙しく感じることも。退職日までに十分な日にちがあれば、各種手続きや引き継ぎ作業を焦らずに進められるだけでなく、残っている有給休暇も計画的に消化できるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職の申告をする際の4つのポイント
法律では、退職の2週間前までに意思表示が必要とされています。しかし、企業の就業規則には「1ヶ月前まで」や「2ヶ月前まで」の記載があることも。また、勤務形態によって退職日の設定で注意しなければならないポイントがあります。
ここでは、法律や就業規則に基づいた退職までに必要な期間を解説するので、自分に当てはまるものを確認しておきましょう。
退職の申告をする際のポイント
- 法律上は退職2週間前までに意思表示が必要
- 就業規則より法律が優先される
- 退職日の設定は土日祝日を含んだ2週間後と考える
- 退職日の設定には注意が必要
1.法律上は退職2週間前までに意思表示が必要
法律上では、退職日から起算して2週間前までに退職の意思表示をすれば問題ありません。民法第627条の第1項において、退職の自由を原則とし、退職の申告から2週間が経過した時点で雇用主との労働契約は解約されると定められています。
申告から2週間あれば退職できると定められてはいるものの、会社の状況や業務の引き継ぎに掛かる日数などを加味し、なるべく早めに上司へ意思を伝えるのがおすすめです。
2.就業規則より法律が優先される
退職日の設定については、就業規則上の規定よりも法律の定めが優先されます。例を挙げると、就業規則に「退職希望日の1ヶ月前までに退職の意思を伝えること」という記載があったとしても、申告を2週間前までに済ませていれば退職は可能です。
就業規則は、あくまで各企業がそれぞれに定めた会社独自の決まりごと。社会全体で見れば法律のほうが効力が強く、民法における2週間前申告のルールが優先されます。
しかし、企業に所属している以上、できるだけ就業規則に準じた申告をしたほうが、円満退職につながるでしょう。
3.退職日の設定は土日祝日を含んだ2週間後と考える
退職日の設定は「土日祝日を含めた2週間後」と考えるのが一般的です。たとえば、12月2日に退職の意思を伝えた場合、2週間後の12月16日が退職日となります。こうした計算の際に誤解が生じないよう、カレンダーを確認しながら余裕をもったスケジュールを設定することが大切です。
4.退職日の設定には注意が必要
勤務形態や給与形態によって、退職するまでの期間は異なります。年俸制や完全月給制の人は、給与の締め日や民法の規定によって退職までに通常の倍以上の日数が掛かる場合も。退職を申し出る前に、自身の勤務形態や給与形態を確認しましょう。
年俸制で働いている場合
年俸制で働いている場合、申告してから実際に退職するまでに3ヶ月の期間が必要です。民法第627条第3項によると、6ヶ月以上の期間に対して給与を決定した場合、労働契約を解約するためには3ヶ月前に申し入れなければならないと定められています。
つまり、退職申告日が7月1日ならば、退職が認められるのは10月1日です。例外として、就業規則に3ヶ月よりも短い期間が設定されている際にはそちらに従っても構いません。
完全月給制で働いている場合
完全月給制の場合、給与の締め日が退職日の決定に影響します。民法第627条第2項において、期間に対して給与を定めた場合、次期以降の解約の申し入れが可能です。ただし、その申し入れは当期の前半に行う必要があると定められています。
給与の締め日が15日の場合、当月16日〜翌月15日までの1ヶ月間が一つの期、すなわち当期とされ、当月16〜30日が期の前半、翌月1〜15日が期の後半と呼ばれます。期の前半で退職の意思を伝えれば、該当期の終わりである翌月15日に退職が可能。期の後半に申告した場合は、退職可能日が翌々月となります。
完全月給制で働く場合は、期の前半と後半がいつからいつまでにあたるのかを事前に把握しておきましょう。
契約社員・パート・アルバイトとして働いている場合
契約社員・パート・アルバイトで働いている方が退職する場合、雇用期間終了日を確認する必要があります。民法628条によると、病気やけがなどやむを得ない理由でない限り、雇用期間中に退職できないと定められています。「やむを得ない理由」とは、「労働条件が実際と異なる」「妊娠・出産」「自身の病気」「家族の介護」などが該当するようです。退職を考えている場合は、自身の雇用契約の内容を一度確認してみましょう。
ただし、労働基準法第137条によって、1年以上3年未満の雇用契約を結んでいれば、1年を経過した日以降に退職できると定められているため、契約締結日から1年以上経過している場合は、退職の申し入れが可能です。
退職するまでに必要な4つのステップ
仕事を辞める決意をしてから実際に退職するまでには、「退職意思の申告」「退職の許可を得る交渉」「有給消化」「退職届の準備」という、4つのステップがあります。各ステップで具体的に何をるのか把握し、スムーズな退職ができるよう事前にイメージしておきましょう。
退職するまでに必要なステップ
- 退職意思の申告
- 退職を許可してもらうための交渉
- 退職日や有給消化の調整
- 退職届の提出
1.退職意思の申告
退職希望日の2〜3ヶ月前を目安に、上司へ退職の意思を伝えます。先述したように、特別な理由がない限り、余裕をもった申告を行うことが円満退職へのカギといえるでしょう。
また、就業規則に目を通し、退職の際に特別な規定がないかを改めて確認しておくと、会社側とのトラブルを未然に防げる可能性があります。
2.退職を許可してもらうための交渉
会社から退職を引き止められた場合には、辞めるための交渉が必要です。企業によっては、現状より高いポジションへの異動や、給与面での待遇アップなどを打診をされることもあるでしょう。企業からの提案が自分の求めるものと合致しているのであれば、そのまま会社に残るという選択も検討してみましょう。
しかし、「今の会社ではできない仕事に挑戦したい」という気持ちで転職を決意したのに対し、「高額の給与を提示されたから」という理由で残留しようとするのであれば、根本的解決に至りません。好条件に目がいき、一時の感情で退職を取りやめた場合、またすぐ退職したい気持ちに駆られる恐れがあります。
3.退職日や有給消化の調整
会社側が退職を受け入れてくれたら、具体的な退職日や有給消化のスケジュール調整を行いましょう。法律上、退職までに2週間以上の日数があれば、会社側は希望する退職日を受け入れなければなりません。しかし、円満退職を希望するのであれば、会社側の希望を聞くことも必要です。「繁忙期が終わるまでは退職を待ってほしい」といったように企業側からお願いされた場合は、できる範囲で協力する姿勢でいたほうがお互いに気持ちの良い関係性を保てるでしょう。
有給消化についても同様です。一方的にこちらの希望を通すのではなく、「△日までには一通りの引き継ぎが終了するので、△日から有給をとってもよろしいでしょうか?」と、状況に鑑みた申請を行うと会社側も申し出を受け入れやすくなります。
4.退職届の提出
退職について会社側からの合意を得られれば、上司に退職届を提出しましょう。会社で決められた書式がないのであれば、自分で用意した便箋に手書きし、上司に直接手渡します。縦書きと横書きは、どちらも記載する内容は同じですが、日付や氏名など記載する順番が異なるので注意が必要です。
提出する際は封筒に入れ、表面に「退職届」、裏面に「氏名と部署名」を記入するのを忘れないようにしましょう。
退職願の提出は必要?
退職するにあたって、「退職願は提出する必要があるの?」と悩む方もいるようですが、退職願の提出は必須ではありません。退職願とは、労働契約の解除を会社にお願いするための書面です。
しかし、退職を願い出る際には必ず書面が必要というわけではなく、口頭での意思表示だけでも問題はないとされています。ここでは、退職願と退職届の違いについて解説するので、確認しておきましょう。
退職届と退職願の違い
退職届と退職願の違いは、前者が「撤回できない」のに対し、後者は「撤回できる」というところ。それぞれの書面がもつ役割については、次のとおりです。
退職届
退職届は、会社側に自分が退職することを宣言するために提出する書面。会社から退職を認められたあとに提出することが一般的です。事前の相談なしに提出する場合、労働者から会社に対し一方的な労働契約の解除を突きつける形にもなるため、基本的には提出後に撤回できない傾向があります。
退職願
退職願は、退職を会社に願い出るために提出する書面です。退職願を提出する時点では、まだ会社側から退職についての合意を得られていません。そのため、上司が引き止めたり、自分から退職願を撤回したりすることが可能です。
円満に退職するための注意点
円満退職のためには、引き止められた際の対応やスムーズな引き継ぎがポイントになります。勤続年数にかかわらず、お世話になった会社はできるだけ円満に退職したいものです。
ここでは、退職の際にどのような点に気をつけるのかを解説します。
円満に退職するための注意点
- 退職の意思を固める
- 退職理由は個人的なものにする
- 引き継ぎリストを作成する
- 無断退職はしない
1.退職の意思を固める
会社から引き止められたとしても気持ちが揺らぐことのないように、退職の意思を固めましょう。
上司に退職の意思を伝えると、引き止められることがあります。一度引き止めに応じてしまうと、そのあとに撤回するのはなかなか難しいものです。退職の意思を示す際には、強い引き止めにあっても気持ちが変わることがないかを再確認しましょう。
また、退職後に必ずしも希望通りの転職先が見つかるとは限りません。転職が上手くいかないと、退職したことを後悔してしまう恐れも。本当に今が退職のタイミングなのか、自身のキャリアプランを基にもう一度考えてみましょう。
2.退職理由は個人的なものにする
上司から退職理由について尋ねられた際には、個人的かつポジティブな理由を伝えるのがおすすめです。退職の意思を伝えると、上司から退職理由について聞かれることもあるでしょう。たとえ会社に対する不満があった場合も、ネガティブな内容を伝えるのは避けるのが無難です。「不満に感じる部分を改善するから残ってほしい」と引き止められたり、会社に残る人の心象を悪くしてしまったりする可能性があります。
退職理由を告げるときは、「将来的にやりたいことができた」「異業種に挑戦したい」など、個人的かつポジティブな内容にすることで、会社側に受け入れてもらいやすくなるでしょう。
3.引き継ぎリストを作成する
計画的かつスムーズに引き継ぎを行うためには、引き継ぎリストを準備するのがおすすめです。自分が今まで担当していた業務をリストアップし、誰にどの業務を引き継ぐのかまとめることで、引き継ぎ漏れを防げるでしょう。
また、業務ごとにマニュアルを作成して後任者がスムーズに仕事に移れるように丁寧に対応することも必要です。「後任者になるべく負担を掛けないように、十分な引き継ぎを行ってから退職します」という誠意が伝われば、会社側も快く送り出してくれるでしょう。
4.無断退職はしない
無断退職するとさまざまなリスクがあります。たとえば、会社の重要なプロジェクトを担当していて、無断退職したことで会社に損害が生じてしまうとなれば損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。
また、次に転職する場合、応募先企業が前職に「本当に働いていたか」を確認することがあるため、転職活動で不利になる可能性もあります。
退職の1ヶ月前に伝えて辞めさせてくれない場合の対処法
会社から退職を認めてもらえなかったとしても、強い意思をもって話し合いを続けましょう。いくら真摯に願い出ても会社から許可が下りない場合には、内容証明で退職届を提出し、労働者側から一方的に労働契約の解約を申し出るという手段もあります。
しかし、できるならばこの手段は使いたくないもの。一方的に退職届を提出することにどのようなリスクがあるのかについても、事前に把握しておく必要があります。
退職の1ヶ月前に伝えて辞めさせてくれない場合の対処法
- 退職に対して揺るがない意思をもつ
- 退職届が受理されないときは内容証明で郵送する
- 退職代行サービスの利用も視野に入れる
- 労働基準監督署や弁護士など専門家に相談する
退職に対して揺るがない意思をもつ
上司から引き止められた場合も、退職に対して揺るがない意思をもつことが大切です。会社によっては引き止めるために、好条件を提示される場合もあります。条件を受け入れることにより、自分にとってプラスになる可能性もあるでしょう。
しかし、引き止められて退職を諦めることには、リスクが伴う場合も。たとえば、「退職を希望したことが周りに知られ、社内での居心地が悪くなる」「提示された条件をなかったことにされた」「不満が解消されなかった場合に、再度退職を言い出しにくくなる」などが挙げられます。マイナスの結果を招かないためにも、退職に対して揺るがない意思をもっておきましょう。
退職届が受理されないときは内容証明で郵送する
いくらお願いしても取り合ってもらえない場合、内容証明を利用して会社に退職届を郵送すれば、2週間後には自動的に雇用契約が解約され退職が可能です。ただし、「退職届と退職願の違い」でも説明したように、基本的に退職届は提出後の撤回が認められていません。一度提出してしまえば、退職を取りやめることは困難です。
また、労働者側からの一方的な申し出のため、会社側との関係が悪化する恐れがあるでしょう。円満退社を望むのであれば、避けるのが無難といえます。内容証明はあくまでも、「これ以上交渉の余地がない場合の最後の手段」という認識をもっておきましょう。
退職代行サービスの利用も視野に入れる
退職を認めてもらえない場合は、退職代行サービスを利用するのも一つの手です。退職代行サービスは、本人の代わりに退職の交渉をしてくれるサービス。主に民間業者・労働組合・弁護士事務所の3種類があります。それぞれ費用や得意分野が異なるので、自分に合ったサービスを選びましょう。
労働基準監督署や弁護士など専門家に相談する
退職の申し入れがトラブルにつながる恐れがある場合は、労働基準監督署や弁護士といった専門家に相談する方法もあります。退職にまつわるトラブルが不明瞭なまま話を進めていくと、会社側のペースで話が進んでしまい、トラブルに発展する可能性も。自分1人での対応が困難だと感じる方は、第三者に相談し助言をもらいましょう。
1ヶ月前には退職の意思を伝えよう
先述のとおり、法律上は2週間前までに退職の意思表示をすれば問題ありません。ただし、就業規則や業務の状況との兼ね合いを踏まえると、1ヶ月前に意思を伝えることで円満に退職しやすくなるでしょう。
「退職のタイミングがつかめない」「会社から退職を引き止められた」といった悩みを抱えている方は、転職エージェントに相談してみるのも一つの手です。
若年層の就職・転職活動に特化したハタラクティブでは、プロのキャリアアドバイザーが一人ひとりに寄り添い、適性に合う求人を紹介します。また、退職届の書き方や退職後の仕事探し、転職準備など幅広いサポートを実施。転職成功後も定期的に連絡を取り合い、企業との間にミスマッチが起きていないかをフォローしています。退職を考えている方や転職したいと思っている方は、ハタラクティブにご相談ください。
退職を考えている方へ向けたQ&A
ここでは、退職を検討する方によくある質問をまとめました。Q&A形式で回答するので、ぜひチェックしてみてください。
それぞれ役割が異なります。辞表は、役職に就いている社員や公務員が退職の際に提出するものです。対して退職願は、辞めることを会社にお願いする際に作成し、撤回が可能です。
一般的な会社員で退職の意思が固まっている場合は、取り下げができない退職届を使用します。
同業種への転職を検討しているなら、3〜5年の経験を積んでから退職することをおすすめします。転職先でアピールできる実績やスキルを身につけてから退職することで、より好条件で転職できる可能性があるからです。
一方、未経験業種への転職は、若いほど有利とされています。スキルよりも意欲が重視される傾向にあるため、未経験業種への転職を考えている方は、なるべく早めに退職を検討しましょう。
詳しくは「転職する時期は何月が良い?おすすめや避けるべきタイミングを解説」でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
挨拶や引き継ぎなどをこなし、退職までやるべきことに集中して過ごすのがおすすめです。退職理由は前向きに簡潔に伝え、業務の引き継ぎを丁寧に行いましょう。普段と同じ態度で責任をもって働き、周囲との会話も自然体を心掛けることで、気まずさを軽減できる可能性があります。
転職活動の時期は、在職中と退職後のどちらにもメリットがあります。在職中に転職活動をするメリットは、収入を得ながら活動できるため金銭的に余裕がもてること。退職後の転職活動では、時間の調整がしやすく集中して準備できることがメリットです。
「働きながら転職活動するのは無理?メリット・デメリットや成功のコツを紹介」にもあるとおり、転職活動の時期は自分の希望にあわせて慎重に決めましょう。「働きながら転職活動できるか不安」「不安で転職活動にやる気が出ない」などの悩みがある方は、ハタラクティブにご相談ください。