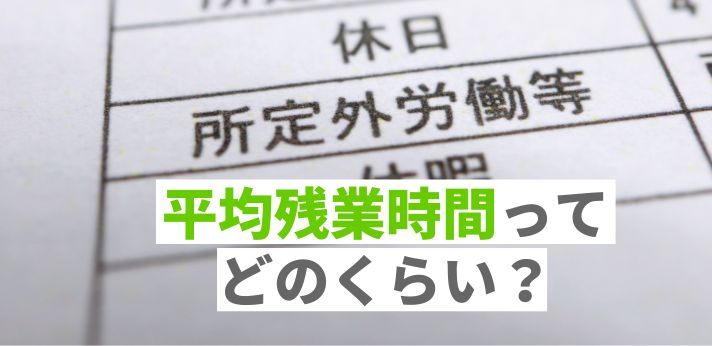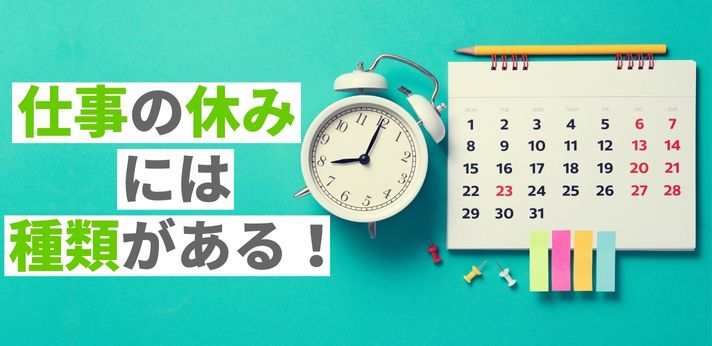休職届の書き方や申請方法は?傷病手当や休職中の過ごし方のお悩みを解決休職届の書き方や申請方法は?傷病手当や休職中の過ごし方のお悩みを解決
更新日
公開日
休職届の書き方が分からず悩んでいる方はいるでしょう。企業によって休職に関する規定は異なるため、就業規則に沿って提出する必要があります。この記事では、休職届の書き方や申請方法、休職するメリットを紹介。また、休職中に受け取れる傷病手当金についてや、申請方法や受給期間なども解説しています。休職を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
休職届の書き方と必要な項目
休職を希望する際、手続きをスムーズに進めるためにも適切な書類作成が欠かせません。企業によって休職の規定は異なるため、就業規則に沿った休職届を提出することが大切です。ここでは、休職届の一般的な書き方や記載すべき項目やポイントについて解説します。
タイトルは「休職届」
書類の冒頭に大きく「休職届」と記載しましょう。提出先に意図が正確に伝わるよう、分かりやすいタイトルをつけることが基本です。企業によっては「休職願」という表現を使う場合もありますが、一般的には「休職届」が正式な書類として扱われます。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
休職届の提出日
書類を作成した日付を明記しましょう。提出日と作成日が異なる場合は、提出日を優先して記載してください。提出日が会社の記録として残るため、必ず正しい日付を記入しましょう。
提出先の所属と役職
提出する相手の所属部署と役職を明記します。多くの場合、直属の上司や人事部長、総務部長が提出先です。不明な場合は、事前に総務や人事担当者に確認しましょう。
自分の所属部署・氏名・押印
自分の所属部署、氏名を記載します。押印が求められる場合もあるため、印鑑を忘れずに用意しておきましょう。
休職を伝える一文
休職の申し出を簡潔に伝える文章を記載します。たとえば、「△△の理由により、休職させていただきたく存じます」といった表現が一般的です。休職の理由について詳しく書く必要はありませんが、企業の規定に従って記入するようにしましょう。
休職する期間
具体的な休職期間を記載します。就業規則を確認し、企業が定める上限期間に基づいて記載してください。終了予定日が未定の場合は仮の日付を記載し、必要に応じて延長手続きを取るのが一般的です。
そのほか必要な添付書類
診断書やそのほか証明書が必要な場合、その書類名を記載してあわせて提出します。特に傷病による休職では診断書が求められる場合が多いため、事前に確認して準備しましょう。介護や育児などの理由の場合も、必要書類の提出を求められることがあるため、事前に人事部に確認しておくと安心です。
休職中の連絡先
休職中に連絡が取れる住所や電話番号、メールアドレスを記載します。仮に自宅以外に滞在する場合も、確実に連絡が取れる先を記載しましょう。
備考
上記項目以外で必要な情報があれば記載します。たとえば、休職中の業務引き継ぎに関する補足情報や、復職の予定について事前に分かっている場合は、「○月○日より復職予定」と記載しておくと、会社側の対応がスムーズです。また、会社に対する特別な要望(リモートワークの希望など)がある場合も、簡潔に伝えると良いでしょう。
手書きかパソコン作成かは企業のルールに従う
休職届の書き方について、手書きにするかパソコンで作成するかは企業のルールに従うのが基本です。就業規則や人事担当者からの指示を事前に確認しましょう。
手書きの場合は、誤字脱字を避け、丁寧な字で書く意識をもつことが大切です。パソコン作成は文書が整って読みやすく、修正も簡単なため、認める企業が増えています。どちらの場合でも、提出前には内容や記載漏れを必ず確認しましょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
休職の申請方法
休職の申請方法は勤務先によって異なりますが、多くの場合の手続きは、医師の診断書を添えて「本人からの申請」を必要としています。なお、勤務先によっては、明らかに体調不良であるにもかかわらず、休職することを拒否する従業員に対して、会社側から休職命令を出せる会社もあるようです。一般的な流れは次のとおりです。
休職の申請方法
- 申請前に職場の就業規則を確認する
- 医師から診断書を受け取る
- 申請に必要な書類を職場に提出する
1.申請前に職場の就業規則を確認する
最初に、職場の就業規則で休職制度の有無を確認し、休職制度がある場合は、申請に必要な書類や手続きの方法、休職できる期間と期間延長の可否などについて確認しましょう。なお、勤務先の会社に休職制度がない場合は、有給休暇を使って仕事を休むという可能性が大きくなります。
ただし、この場合は長期にわたって休むことが難しいといえるでしょう。体調不良のため働くことが困難となったものの勤務先に休職制度がない場合は、まず上司や人事担当者に相談します。
2.医師から診断書を受け取る
休職制度があると確認できたら医師と相談をし、診断書を作成してもらいましょう。かかりつけ医や勤務先の産業医に依頼するのが一般的。
なお、どの診療科であっても、診断書を受け取るまでには、初診から数週間〜数ヶ月かかるとされています。休職開始に向けてのスケジュールも含めて「いつまでに診断書が必要なのか」などを医師に相談しておくと良いでしょう。
3.申請に必要な書類を職場に提出する
診断書が取得できたら、会社で規定されている申請書類とともに職場に提出します。申請書類として「休職申請書」「休職願」「休職届」などの様式が用意されている企業もあるので確認しましょう。
また、提出後に人事部門との面談が行われるケースがあります。面談で「怪我や体調に影響のない業務なら担当できるか」「在宅や部署異動なら勤務可能か」などを聞かれることも予想されるため、自分の意向、体調に合った回答をしましょう。
休職期間は延長できる?
休職期間の延長が可能かどうかは、勤務先の制度や就業規則によって異なります。前述のとおり休職制度は会社が独自に制定しているため、休職期間などの詳細は就業規則を参照しましょう。
たとえば、就業規則に「休職期間は1年半を限度とする」と規定されている会社であれば、1年の休職を申請したとしても、さらに半年間の延長が可能と思われます。ただし、休職制度は、復職できる見込みがあることを前提としているもの。休職期間が延長できたとしても上限期間までに復帰できなければ、退職や解雇になる可能性もあります。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
そもそも休職とは?主な種類も紹介
休職とは、言葉のとおり「職を休むこと」。具体的には、従業員の自己都合で長期的に仕事に就けないときに使用され、勤務先の就業規則に則って人事や労務部門への申請が必要となります。休職の理由として一般論的に挙げられるものは、次のとおりです。
| 休職の種類 | 休職の理由 |
|---|
| 疾病休職(私傷病休職) | 業務を原因としない病気やケガで心身に不調をきたし、療養したい場合。
(うつ病などメンタルの病気を発症した、交通事故により負傷したなど) |
| 自己都合休職 | ボランティア活動などに参加したい、留学したい場合。
(災害復興支援や、社会福祉施設での奉仕活動、キャリアアップのための留学など) |
| 事故欠勤休職 | 疾病や自己都合以外の事由により一定期間休職する場合。交通事故との関係性はない。
(容疑がかけられ、逮捕・勾留されたなど) |
| 起訴休職 | 刑事事件の被告人として起訴された場合。
※従業員が起訴されたことを受け、会社が「就労は不適切」と判断した場合に適用される。 |
| 公職就任休職 | 公職に就任し、多忙になった場合。
(都道府県知事や市町村長、議員に就任した など) |
なお、上記の中で多いのは「疾病休職(私傷病休職)」と言われているようです。
また、休職制度は法律に定められているものではないため、勤務先の就業規則に休職制度がない場合は休職が認められず、年次有給休暇での対応となる可能性もあります。
休職の申請方法と合わせて注意しておきたいポイント
休職の申請方法の確認と合わせて、申請前に確認しておきたいのは、休職時の給料や社会保険料の扱い。また、休職中の連絡方法を決めておくことも大切です。
休職時の給料事情を把握しておく
会社側は、休職している従業員に対して給料を支払う義務は法的にもなく、ノーワークノーペイの原則に則って賃金を支払わないことが一般的のようです。
しかし、なかには「休職中の給料は△割減で支給する」など、給料が支払われるところもあります。自身の職場では休職期間中の給料はどのように扱われるのかを就業規則などで確認しておきましょう。
休職中の社会保険料について確認する
休職中も給料の支払いがある場合は、通常どおり社会保険料は給料から天引きされるため注意が必要です。しかし、無給となる場合は天引きできないため会社側がいったん立て替えて負担し、後日まとめて会社側に支払うといった対応が一般的だといわれています。どちらの場合も、休職中も社会保険料における自己負担金は免除されないことに注意しましょう。
休職中でも自己負担金が必要となるのは、「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」と「住民税」です。
休職中の連絡方法を決めておく
休職中も勤務先との雇用関係は続いているため、定期的な連絡が必要です。休職前に、連絡する相手や連絡の頻度、連絡方法などを決めておきましょう。直属の上司との人間関係が原因で休職を申請する場合は、人事部や産業医などを連絡先とすることも一つの方法です。
休職時は傷病手当金を申請できる
病気やケガなどが理由で休職し、療養のため労務に就けない場合に、傷病手当金を申請できます。以下で解説するので、チェックしてみてください。
支給条件
傷病手当金を申請するためには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- ・業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること
- ・仕事に就けないこと
- ・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- ・休業した期間について給与の支払いがないこと
支給条件として会社を休んだ日が連続して3日間必要です。3日間の中で1日でも出勤した日があれば条件が満たされないので注意しましょう。また、「休業した期間について給与の支払いがないこと」に関しては給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は差額を受け取れます。
申請方法
傷病手当金の支給を申請するときは、「健康保険傷病手当金支給申請書」を提出しましょう。申請書は4枚1組になっており、本人のほか、療養担当者(医師)と事業主(会社)が記載する欄があります。それぞれ期間に余裕をもって依頼し、添付書類が必要な場合は一緒に提出できるよう、準備しておきましょう。
受給期間
傷病手当金は、説明したとおり療養のため連続して3日間仕事を休んだうえで、その次の日(つまり4日目)以降の仕事に就けなかった期間について受給できます。
また、同一の疾病または負傷が理由で休職した場合においては、令和4年1月より、最長1年6ヶ月間と定められていた給付期間について「支給開始日から通算1年6ヶ月間」との改正がなされました。
たとえば、傷病手当を6ヶ月間受給し、その後復職して6ヶ月間働いたとします。再び同じ理由で休職することになったとしても、残り1年間(通算1年6ヶ月間-受給済みの6ヶ月間)受給可能です。
受給できる金額の計算方法
受給できる傷病手当金の1日あたりの金額は、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2」で計算されます。
なお、支給開始日以前の保険加入期間が12ヶ月未満の場合は、「12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を「支給開始日の属する月以前の直近の継続した標準報酬月額の平均値と、全被保険者の標準報酬月額の平均値のいずれか低い方の額」として計算するのが基本です。自身の標準報酬月額が分からない場合は、会社に確認してみましょう。
休職をする3つのメリット
休職することで、仕事や職場のことを忘れてゆっくり休めます。また、自分自身と向き合う時間ができるため今後のキャリアや人生に向けて勉強する時間が取れることもあるでしょう。
1.仕事や職場のことを忘れてゆっくり休める
休職することで、仕事や職場から離れてゆっくりと休め、療養に専念できることは大きなメリットです。特に、仕事で大きなストレスを感じていたり、心身ともに疲れてしまったりしているときは、疲れを癒せる時間をにもなることでしょう。
心の疲れは身体的にも悪影響を及ぼしかねません。そうなる前に、休職をして仕事や職場と距離を置いてみましょう。
2.自分自身と向き合う時間ができる
休職すれば、自分自身と向き合う時間ができます。毎日仕事をしていると、日々の忙しさから自分が本当にやりたいことや、人生の目標を見失ってしまう方もいるでしょう。休職することで、自分自身と深く向き合う時間ができ、今まで抱えていた悩みや問題の本質を理解する機会になるかもしれません。
また、時間や余裕があるとポジティブな思考も生まれやすくなります。休職期間を通じて自分自身と深く向き合ってみるのも良いでしょう。
3.今後のキャリアや人生に向けて勉強する時間が取れる
休職をすることで、今後のキャリアや人生に向けて勉強する時間が取れます。毎日働いていると、資格の勉強をする時間は週末だけという方もいるはず。このため、休職期間を昇格や転職に必要な資格勉強として活用することも良いでしょう。
休職中の過ごし方
休職してずっと自宅にいると、気が滅入ってしまったり、周囲に対して罪悪感を覚えたりすることもあるでしょう。また、早起きの必要がなくなるため、次第に昼夜逆転生活になる可能性も出てきます。復職の際に支障をきたす恐れもあるので、休職中は次のような過ごし方を心掛けると良いでしょう。
療養中は仕事のことを考えない
休職中は心身を休め、療養に専念しましょう。仕事のことは考えず、ゆっくり過ごすことが一番です。「自分がいない間に仕事の方はどうなっているだろう」と気になるかもしれませんが、体調の回復を優先してみましょう。
休職する前の生活リズムを維持する
休職しても、従来の生活リズムを崩さないように心掛けましょう。仕事に行かないからといって生活リズムを崩すと、気分が優れなくなったり病気やケガの治りが遅くなったりしてしまう場合もあります。
一方、休職する前の方が睡眠不足だった、不規則な生活をしていたという場合は、この機会に早寝早起きの習慣を身につけると良いでしょう。
外の空気に触れて気分転換を図る
病気やケガの症状によっては、ずっと家にいることで憂鬱になってしまう場合も考えられます。外出できる状態であれば近場を散歩したり出かけたりするなど、ときどき気分転換を図ることも大切です。
外出ができない状態でも、部屋の窓を開けて日光を浴びたり、外の空気を感じたりすると気分が変わってくるでしょう。
復職や転職に対して焦らない
休職すると、次第に「働いていない自分はダメな人間だ」などとネガティブに感じ、職場への復帰や転職を焦ってしまう可能性もあります。しかし、休職中は、「休むことも仕事のうち」と捉え、復職や転職を焦らないようにしましょう。休むことで心身の早い回復や、自分自身の役割が見つかるかもしれません。
落ち着いたら復職を視野に入れる
しっかり休めたら、復職を視野に入れましょう。その際は、医師や家族などに自身の状況を話して客観的な意見を求めてみることが大切です。そのうえで無理なく働けるよう、会社側と配置転換を相談してみることも良いでしょう。
また、転職の思いがあるなら、復職前に転職エージェントなどを利用し、新しい環境での再スタートを検討することも一つの方法だといえます。
休職をしても解決しなければ転職を検討しよう
休職後、業務量が調節されたり部署の異動が行われたりする場合があります。それでも根本的な悩みが解決しない場合は、転職するのも一つの方法です。休職しても、期間が終われば復職する必要があります。「復職しても前と同じように働けない気がする」「休職の理由が人間関係だから復職したくない」など、復職をためらう場合は、転職も検討してみましょう。
自分に合った転職先をお探しなら、多くの転職希望者をサポートするハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーによるカウンセリングで、あなたの適性や強みを明確化し、希望に沿う条件の求人をご紹介いたします。
取り扱う求人はキャリアアドバイザーが実際に訪問してチェックを行った信頼できる企業のみ。会社の雰囲気や勤務環境など、求人サイトでは分からない情報もお伝えしています。履歴書や職務経歴書といった書類の添削も実施しているので、「前職での休職理由をどう伝えたら良いか分からない」という方もぜひご利用ください。
休職を検討中の方が抱えるお悩みに答えるQ&A
ここでは、休職を検討している方が悩みがちな疑問にQ&A方式でお答えしていきます。
休職のメリットは、療養に専念できることや期間内に回復すれば復帰が可能なことなどです。一方、デメリットには、収入が減ることや昇進のスピードが遅くなることなどが考えられます。休職を検討する前は、メリットとデメリットの両方を知っておくことが大切です。
詳しくは「休職期間中に収入はある?休業との違いやメリット・デメリットを解説」でも解説しているのでチェックしてみましょう。
仕事そのものがストレスになっていた場合は、復帰せず、携わる業界や職種を変更するなど、転職を検討することも選択肢の一つです。ハタラクティブでは、自己分析のアドバイスも行っており、あなたの適性に合った仕事をご紹介できます。退職理由の書き方についてもサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。