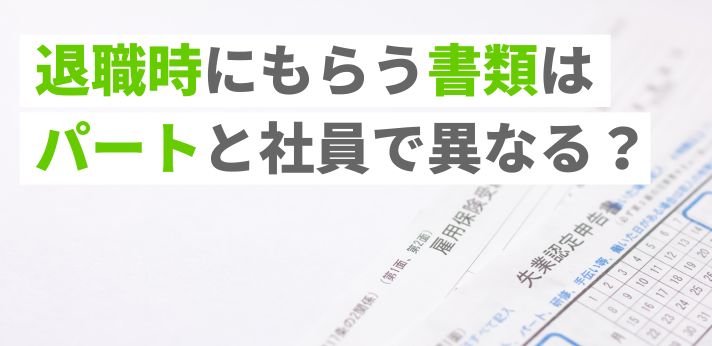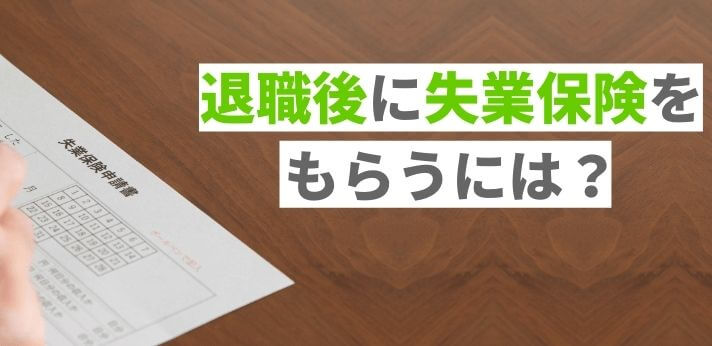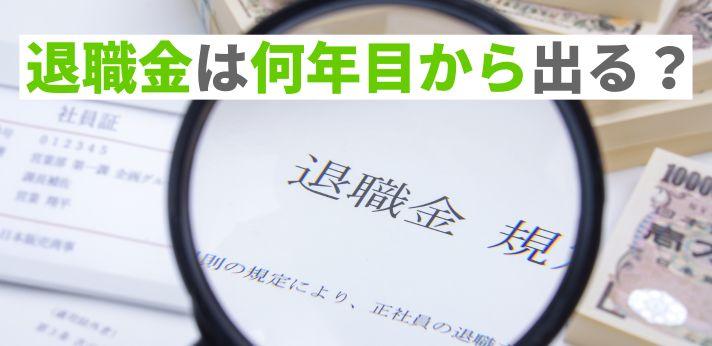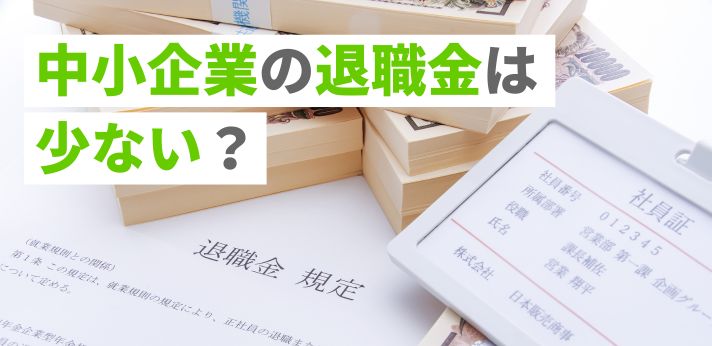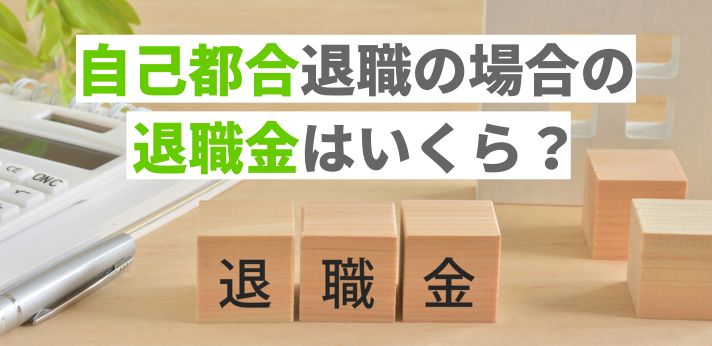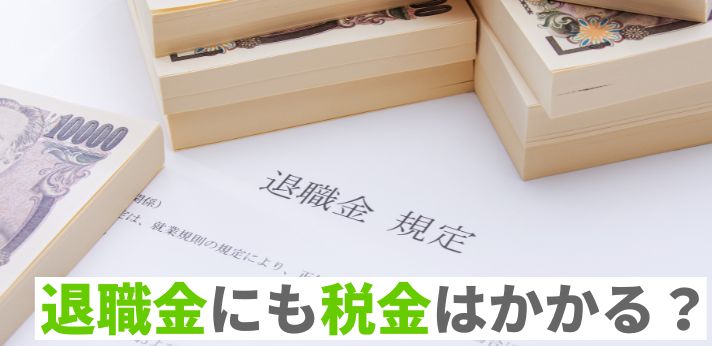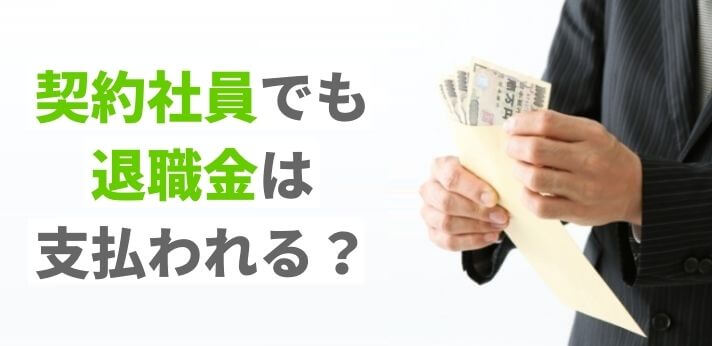退職金をもらえる条件とは?受け取れる金額の相場やいつもらえるかも解説退職金をもらえる条件とは?受け取れる金額の相場やいつもらえるかも解説
更新日
公開日
退職金をもらえる条件は会社によって異なり、就業規則に勤続年数や雇用形態などの規定があるのが一般的
「退職金をもらえる条件は?」「自分の条件で受け取れる?」と疑問に思っている方もいるでしょう。退職金をもらえるかどうかは会社によって異なり、勤続年数や雇用形態など支給条件は独自に決められています。そのため、まずは勤務先の条件を知り、自分が支給対象かどうかを確認する必要があるでしょう。
このコラムでは、退職金をもらえる条件や主なもらい方、相場などをご紹介します。また、退職金をもらえない場合の対処法も解説。自分が退職金をもらえるかどうか確認し、疑問を解消したうえで転職活動に取り組みましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
退職金をもらえる条件とは?どうやって調べる?
退職金制度に導入義務はないため、もらえるかどうかは企業の方針によって異なります。ここでは、退職金制度を導入している企業の割合や自分が支給対象かどうか確認する方法を紹介しているので、参考にしてみてください。
所属する会社で退職金がもらえる条件を確認する方法
所属する会社で退職金がもらえる条件を確認したい場合は、所属する会社の就業規則に目を通しましょう。退職金を受け取る条件や計算方法は企業が独自に決められるもので、退職金制度がある場合は就業規則に載っているのが一般的です。
「会社の就業規則を見てもよく分からない…」という場合は、人事や総務に確認してみるのがおすすめ。「勤続何年目からもらえる?」「適用される雇用形態は?」などの疑問にも回答してくれるでしょう。
退職金制度を導入している企業は約7割
企業規模別の退職金制度の導入割合
同調査によると、企業規模別の退職金制度の導入割合は以下のとおりです。
| 企業規模 | 退職金制度の導入割合 |
|---|
| 1,000人以上 | 90.1% |
| 300~999人 | 88.8% |
| 100~299人 | 84.7% |
| 30~99人 | 70.1% |
上記の表によると、企業規模が1,000人以上の企業では90.1%が退職金制度を導入しているのに対して、従業員数が100人未満の企業の導入割合は70.1%にとどまっていることが分かります。企業規模が大きいほど、退職金制度の導入割合が高い傾向があるようです。
中小企業は「中退共制度」がある場合も
中小企業のなかには、「中退共制度」を導入している場合もあります。
厚生労働省の「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」によると、中退共制度とは「自社だけでは退職金制度を設けることが難しい中小企業が、相互共済と国の援助により退職金制度を設けるための制度」のこと。中小企業が毎月、中退共へ掛金の積立を行い、従業員が退職する際に中退共から退職金が支払われます。
中小企業も自社の従業員に支払う退職金を確保しやすくなるのが、中退共制度を活用するメリットです。自分の会社が中退共制度に加入しているのか気になる方は、退職前に確認しておきましょう。
産業別の退職金制度の導入割合(一部抜粋)
産業によっても、退職金制度の導入率は異なる傾向があります。ここでは、同調査のデータからいくつかの産業を抜き出し、退職金制度の導入割合が高い順にまとめました。
| 産業 | 退職金制度の導入割合 |
|---|
| 電気、ガス、熱供給、水道業 | 96.4% |
| 金融業、保険業 | 92.8% |
| 教育、学習支援業 | 87.3% |
| 製造業 | 85.6% |
| 建設業 | 82.9% |
| 卸売業、小売業 | 77.4% |
| 医療・福祉 | 75.5% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 74.7% |
| 情報通信業 | 74.6% |
| 運輸業、郵便業 | 69.9% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 68.5% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 42.2% |
「電気、ガス、熱供給、水道業」や「金融業、保険業」のように、90%以上の企業が退職金制度を導入している産業もあります。一方で、「生活関連サービス、娯楽業」では68.5%、「宿泊業、飲食サービス業」では42.2%と、数値があまり高くない産業も見受けられました。
上記から、退職金がもらえるかどうかは業界の傾向や会社の方針によるといえるでしょう。
退職金が支給されるタイミング
退職金の支払いには明確な規定がないため、受け取れるタイミングは企業次第といえます。一般的には、退職日から1〜2ヶ月後に支払われる傾向にあるようです。
企業によっては退職手続きに時間が掛かり、退職金の支払いが遅くなることも。結婚や住宅の購入など、ライフイベントが発生するタイミングに備えてまとまったお金が欲しい場合は、「退職金前払い制度」を利用する手もあります。退職金前払い制度とは、在職期間中の月給や賞与へ退職金相当額を加算する方法です。
ただし、企業によっては前払い制度を導入していないことも。また、退職金前払い制度を利用すると退職するときに支給されるお金が減るため、よく検討したうえで利用しましょう。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職金は実際にどれくらいもらえる?条件別に相場を紹介
ここでは、退職金の相場を勤続年数別や企業規模別で紹介します。自分がどのくらいの退職金をもらえるのかおおよその額を知りたい方は、参考にしてみてください。
勤続年数別の退職金の相場
退職金の相場は、勤続年数によって異なります。政府統計の総合窓口e-Statの「令和5年賃金事情等総合調査」をもとに、自己都合で退職した人の学歴別・勤続年数別の退職金の平均金額をまとめました。
| 勤続年数 | 大卒 | 高卒 |
|---|
| 勤続3年 | 34万1,000円 | 23万4,000円 |
|---|
| 勤続5年 | 63万1,000円 | 44万4,000円 |
|---|
| 勤続10年 | 182万8,000円 | 133万6,000円 |
|---|
| 勤続20年 | 761万9,000円 | 522万3,000円 |
|---|
| 勤続30年 | 1,771万8,000円 | 1,316万4,000円 |
|---|
定年退職まで働いた場合
※大卒は勤続38年、高卒は勤続42年 | 2,380万8,000円 | 1,952万8,000円 |
|---|
参照:政府統計の総合窓口e-Stat「産業、学歴、労働者の種類、コース、退職事由、勤続年数別モデル退職金総額及び月収換算月数(第13- 2表)(第13-10表)」
上記のデータによると、勤続年数が増すほど退職金の額も上がっていることが分かるでしょう。また、高卒者よりも大卒者のほうが退職金を多くもらえる傾向があります。
企業規模別の退職金の相場
退職金の平均相場は、企業規模によっても異なります。令和5年就労条件総合調査によると、従業員数別の退職金(管理・事務・技術職として35年以上勤めた場合)の支給金額は、以下のとおりでした。
| 従業員数 | 大卒 | 高卒 |
|---|
| 30~99人 | 1,785万円 | 1,092万円 |
|---|
| 100~299人 | 1,543万円 | 1,373万円 |
|---|
| 300~999人 | 1,742万円 | 1,602万円 |
|---|
| 1,000人以上 | 2,242万円 | 2,189万円 |
|---|
高卒者も大卒者も、従業員数が30~99人の企業と1,000人以上の企業では、退職金額に大きな差があることが分かります。同じ年数や同じ学歴であっても、企業規模が大きくなるほど退職金の額は多くなる傾向があるでしょう。
「中小企業の退職金が少なすぎる」といわれるのはなぜ?
「中小企業の退職金が少なすぎる」という意見を耳にしたことのある方もいるでしょう。中小企業の退職金が大企業と比べて少ない傾向があるのは、「経営資金が大企業ほど潤沢ではないこと」「そもそも退職金制度は任意であること」などが理由として挙げられます。
また、退職金の支給額は一般的に、勤続年数や企業への貢献度、役職などによって決められるものです。そのため、20代の若いうちや勤続年数が短いうちに中小企業から転職する場合、「思ったより退職金をもらえなかった」「少なすぎる」と感じることも考えられます。
「今の会社でできるだけ多く退職金をもらいたい」という場合、条件を満たすまで働き続ける選択肢もあるでしょう。
しかし、今の仕事に不満があるなら、転職を考えるのも手です。できるだけ早く仕事内容や待遇、働き方が自分に合っている会社に転職することで、自分の適性や能力を活かして長く働きやすくなります。結果として勤続年数や貢献度が評価され、将来もらえる退職金が増える可能性もあるでしょう。
業種別の退職金の平均相場
ただし、この統計は東京都にある中小企業を対象としています。全国の平均値ではないため、あくまでも参考としてご覧ください。
| 業種 | 大卒 | 高卒 |
|---|
| 建設業 | 929万6,000円 | 991万4,000円 |
|---|
| 製造業 | 1,107万6,000円 | 1,027万2,000円 |
|---|
| 運輸業、郵便業 | 938万3,000円 | 866万1,000円 |
|---|
| 卸売業、小売業 | 1,239万円 | 880万7,000円 |
|---|
| 金融業、保険業 | 1,940万4,000円 | 1,497万円 |
|---|
| 生活関連サービス、娯楽業 | 1,054万4,000円 | - |
|---|
| サービス業(他に分類されないもの) | 969万1,000円 | 1,213万2,000円 |
|---|
「製造業」「金融業、保険業」は、高卒・大卒どちらも平均の退職金支給額が1,000万円を超えているという結果に。ほかの業界の平均支給額も、800万円台後半から1,000万円台であることが分かります。
なお、職種や労働条件といった幅広い要素によっても、退職金の額は異なります。相場はあくまで目安と捉え、自分が勤務している会社の計算方法にもとづいて退職金のシミュレーションを行いましょう。
自己都合か会社都合かで金額が変わる場合もある
退職金の額は、退職理由が自己都合か会社都合かで変わる場合もあるようです。一般的に、自己都合退職の場合は退職金が満額支給されません。定年前に会社を辞めることになるため、勤続年数が短くなるぶん、退職金は減額されます。
自己都合退職の場合の退職金の減額率は会社によって異なるため、詳細を知りたい方は就業規則を確認しましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職金としてもらえる金額の計算方法
ここでは、退職金の計算方法を「基本給連動型」「定額制」「ポイント制」の3つに分けて解説します。退職時にもらえる退職金の額が気になる方は、それぞれの計算方法や会社の就業規則を確認したうえで、シミュレーションしてみましょう。
基本給連動型
基本給連動型とは、勤続年数や退職時の基本給の額、退職理由などを加味して退職金額を決定する計算方法のこと。計算式は、以下のとおりです。
退職時の賃金(基本給)×支給係数(勤続年数)×退職理由による係数=退職金
この計算方法では、退職時の賃金に、勤続年数や退職理由による係数を掛けます。勤続10年の場合は10、自己都合による退職ならば0.8というように係数は会社が独自に設定しているため、就業規則で詳細を確認しておくのが確実でしょう。
定額制の計算方法
入社から退職までの勤続年数によって支給される金額が決まるのが「定額制」です。たとえば、勤続年数が10年なら退職金は100万円、20年なら250万のように、勤めた年数に応じた金額があらかじめ設定されています。勤続年数ごとの支払い金額は会社によって異なるので、就業規則で確認しましょう。
ポイント制の計算方法
ポイント制は、企業から付与されるポイントをもとに退職金を計算する方法です。ポイントは勤続年数・職能級・担当職務・役職などに応じて決まり、「1ポイントあたり1万円」のように単価が設定されます。ポイント制の計算式は以下のとおりです。
累計ポイント×ポイント単価×退職理由による係数=退職金
基本給連動型と同様に、「退職理由による係数」は、定年・会社都合・自己都合など、理由によって異なります。たとえば、定年退職の係数は1.0、自己都合による退職の場合は係数0.5というように設定されているようです。
退職金のもらい方
退職金の主なもらい方は「退職一時金として受け取る」「退職年金として受け取る」「退職一時金と退職年金を併用する」の3種類で、会社によって異なります。
以下では、それぞれのもらい方のメリットとデメリットを解説しているので、参考にしてみてください。
1.退職一時金として受け取る
退職一時金とは、会社を辞めるときに一括して受け取れる退職金のこと。勤続年数や退職前の給与額などにもとづいて、会社側が退職金の額を決定します。
メリット
退職金を退職一時金として受け取るメリットは、税法上の優遇措置があること。一時金として受け取った額から退職所得控除を引いた残額の半分が「退職所得」とみなされ、課税対象となります。
(退職一時金の総支給額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
なお、勤続年数によって退職所得控除額の計算方法は異なります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合は、80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
上記の方法で計算された退職所得が、所得税と住民税の課税対象となります。ただし、退職一時金が退職所得控除額よりも少なければ、税金は発生しません。
日本では、所得が多くなるほどそれに課される税額も上がる累進課税制度が一般的ですが、退職一時金の場合、控除を受けられるだけでなく課税の対象額は残額の半分のため、掛かる税金を抑えやすいのがメリットです。
デメリット
退職一時金のデメリットは、退職年金よりも受け取る総額が少なくなることです。退職一時金は退職時に一括で受け取る方法のため、運用しながら分割で支給される退職年金と比べると、もらえる金額が少なくなる傾向にあります。
2.退職年金として受け取る
退職年金とは、退職後に分割で退職金を受け取る制度のこと。別名「企業年金」ともいわれ、毎月あるいは数ヶ月に一度の頻度で、決まった額が支給されます。
メリット
前述したように、退職年金は受け取れる総額が一時金よりも多くなるメリットがあります。退職年金の場合、まだ受け取っていないぶんの退職金を金融機関が運用し、その運用益が上乗せされるためです。
また、退職一時金とは違って分割で受け取るため、使い過ぎを防止しやすいことをメリットに感じる方もいるでしょう。一定期間決まった額の収入があるので、退職してから厚生年金の受け取り開始年齢まで期間が空く場合、退職年金によって経済的な安心感を得られる側面もあります。
デメリット
退職年金のデメリットは、税負担が高くなる恐れがある点です。退職年金には、退職一時金のような税制上の優遇措置は設けられていません。
退職年金は公的年金や副業による収入などが該当する「雑所得」として扱われます。退職年金として得ている収入を厚生年金などと合算すると雑所得の金額が大きくなり、それに掛かる税額も増える場合があるでしょう。
雑所得は公的年金控除の対象
雑所得には公的年金も含まれるため、公的年金控除の対象となります。
日本年金機構の「所得金額の計算方法」によると、所得が年金のみで65歳以上の方の場合、受け取る年金額が330万円以下なら公的年金控除は110万円です。また、65歳未満の方の場合も、受け取る年金額が130万円以下であれば60万円の控除を受けられます。
退職年金として受け取る金額が上限を超えないように調整することで、税負担を軽減できる可能性があるでしょう。
参照元
日本年金機構
トップページ
3.退職一時金と退職年金を併用する
退職一時金と退職年金の双方に対応している企業なら、それぞれの制度を併用できる場合があります。退職金の一部を一括で受け取り、残りは年金として分割でもらう方法です。
メリット
退職一時金と退職年金を併用すれば、退職時にまとまった金額を受け取ったうえで、退職後も定期的な収入を得られるメリットがあります。たとえ退職所得控除額よりも退職金額が多くても、一部を退職年金での受け取りにすることで控除額を下回り、税金を抑えられる可能性もあるでしょう。
デメリット
退職一時金と退職年金を併用する場合、「退職年金のみ」の場合よりも受給総額が減るというデメリットが考えられます。退職金の一部を退職時に受け取ることで年金に回す額が減り、フルで退職年金を利用する場合よりも運用益が下がるためです。
退職金のもらい方に悩んだときは?
退職金のもらい方に悩んだときは、「退職後の生活に合うのはどの方法か」を考えてみるのがおすすめ。また、公的年金の受給時期の繰り下げを検討してみるのも一つの手です。以下で悩んだときの考え方を解説しているので、自分に合う退職金のもらい方を選ぶためにお役立てください。
退職後の生活から考える
想定している退職後の生活から、退職金のもらい方を決める方法があります。
たとえば、退職後に再就職せずに過ごすのであれば、退職金を一度に受け取るよりも、退職年金として定期的な収入があるほうが安心という場合もあるでしょう。退職後に働かなければ退職金を退職年金で受け取ったとしても所得はそれほど増えないため、税負担も軽くて済むメリットもあります。
一方で、「再就職して働く」「退職後は自営業として働く」という場合は、退職一時金としてもらうのがおすすめです。退職年金を選択すると、分割で受け取ったぶんが毎年の年間所得に上乗せされて、税金や社会保険料の負担額が大きくなる可能性があるためです。
退職金のもらい方に悩んだときは、自分が退職後にどのように過ごす予定なのかを考えてみましょう。
公的年金の繰り下げ受給も同時に検討してみる
退職年金を受け取る場合、公的年金の繰り下げ受給を同時に検討してみるのも手です。
日本年金機構によると、年金の繰り下げ受給とは、通常65歳からの公的年金受給のタイミングを66歳~75歳の間にずらす方法のこと。退職年金をもらえる期間はあえて公的年金を受給しないことで雑所得が減り、税負担の軽減が望めるでしょう。
退職金をもらえない場合の対処法
退職金をもらえる条件を満たしているのに支給されないときは、労働基準監督署へ相談するのが有効な手段です。一方、会社に退職金制度自体がない場合は、iDeCoやNISA・個人年金保険に加入する方法が挙げられます。
以下で詳しく紹介するので、自分に合った対処法を確認してみてください。
労働基準監督署へ相談する
職場に退職金制度があり、もらえる条件を満たしているのに退職金をもらえない場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。労働基準監督署とは、管轄する地域の事業所が法令を遵守しているかを監督する機関のこと。労働基準監督署が企業に対し、就業規則に従って退職金を支払うよう交渉してくれる可能性があります。
iDeCoやNISA・個人年金保険に加入する
職場に退職金制度がなかったり、受け取れる金額が少なく将来を不安に感じたりする方は、「iDeCo」や「NISA」「個人年金保険」などに加入するのも一つの手。iDeCoやNISAは、少額で長期間の投資を非課税で行える金融商品です。節税しながら資産形成ができるため、退職金の代わりになるお金を自分で貯蓄できるでしょう。
個人年金保険とは、任意で加入する私的年金のこと。積み立てた保険金は、契約時に決めた年齢以降に「一括受け取り」や「年金形式」などの方法で受け取ることが可能です。退職金がもらえる見込みがなく、将来が不安な方は加入を検討してみるのもおすすめといえます。
会社が倒産しても退職金はもらえる?
会社が倒産しても退職金を受け取れる可能性はあります。会社の資産や債務などを整理して退職金を支払える余裕ができれば、従業員へ分配されることになるでしょう。
しかし、会社が所有する資産が少ない場合は、退職金がもらえないことも。会社が倒産しても退職金を受け取る権利は消えないものの、実際に受給できるかどうかは会社の支払い能力に左右されるといえます。
【まとめ】退職金をもらえる条件を確認して転職に備えよう
転職を考えている方は、退職金のもらい方や受給金額などを、事前によく確認しておきましょう。本格的に転職活動や退職手続きが進み始めると、退職金について自社の規定を調べるのに十分な時間を確保できない場合があります。時間に余裕があるうちに、就業規則に目を通しておくのがおすすめです。
「転職活動と退職手続きを両立させたい」とお考えの方は、転職エージェントに相談する方法もあります。転職エージェントとは、仕事探しや選考対策などの転職活動を専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれるサービスのこと。企業とのやり取りもキャリアアドバイザーが代行してくれるため、在職中の転職活動もスムーズに進めやすいでしょう。
転職をお考えの方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは、若年層の転職を手厚くサポートしています。専任のキャリアアドバイザーがヒアリングを行い、一人ひとりの適性や希望に合った求人をご紹介。また、退職金のもらい方や退職手続きなどに関する疑問に対しても丁寧に対応するので、初めて転職する方も安心です。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご登録ください。
退職金はもらえる?と思ったときによくある質問
ここでは、退職金に関するお悩みをQ&A形式でご紹介します。
退職金がもらえるタイミングは、退職日ではなく退職後1〜2ヶ月後が一般的です。退職金をもらうための手続きに必要な書類が揃わなければ、それ以上掛かることもあります。退職金をきちんともらうために、会社任せにするのではなく書類に不備がないか自主的に確認を行いましょう。
一時金で受け取る際は、退職時に会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、基本的に確定申告をする必要がありません。また、年金方式で受け取る場合は、その年の雑所得が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
派遣社員や契約社員、パートも退職金はもらえますか?
派遣社員や契約社員、パートなど非正規社員の場合、退職金がもらえるかどうかは会社の規定によって異なります。正社員向けには退職金制度があるものの、非正規社員は対象外としている企業もあるようです。また、非正規社員に退職金を支払う企業でも、正社員と比べると支給額は少ない可能性があります。
退職金は勤続10年以上経たないともらえないって本当ですか?
退職金をもらえる条件は会社によって異なるものの、勤続3年以上で支給することが一般的なようです。ただし、退職金は勤続年数やスキル、役職などによって金額が増えていくもの。勤続10年以内では、「思ったより少ない」と感じる可能性もあるでしょう。
退職金をもらったあとに自分に合った仕事に転職したいという方は、ハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望に合う仕事をご紹介します。