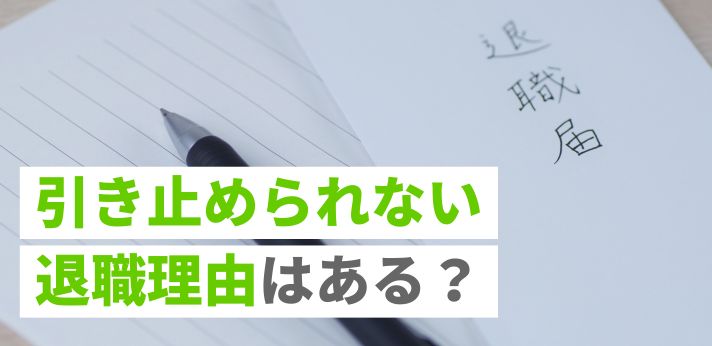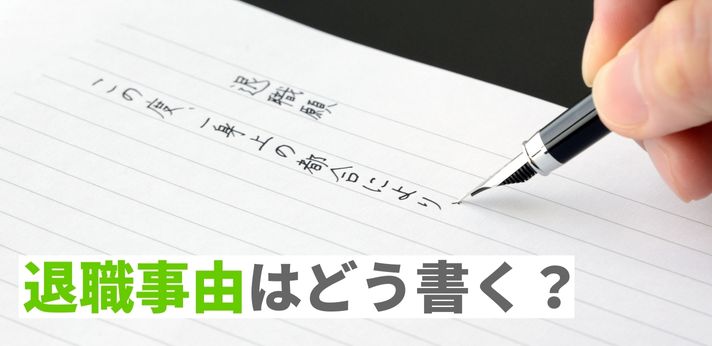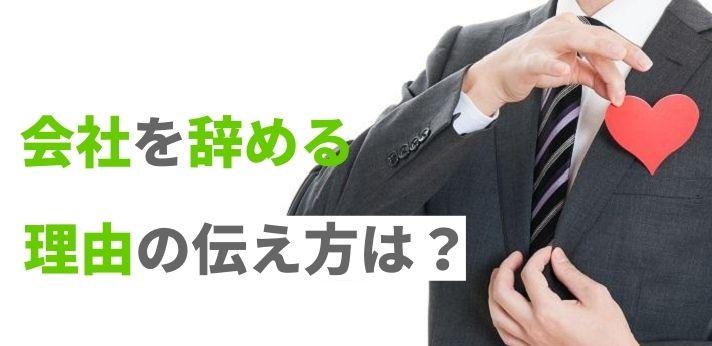退職の切り出し方は?メールでアポを取る際のポイントや例文をご紹介!退職の切り出し方は?メールでアポを取る際のポイントや例文をご紹介!
更新日
公開日
上司へ退職を相談する際の切り出し方として、メールでアポを取っても問題ない
退職相談の切り出し方として、上司へメールでアポを取っても問題ないのか気になっている方もいるでしょう。一般的なマナーとしては口頭で伝えるのが望ましいですが、法律上はメールでも問題ありません。
このコラムでは、退職相談の切り出し方やメールでアポを取る際の例文を紹介します。退職の意思をメールで伝える際の注意点や、社内・社外に向けた退職挨拶メールのポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
上司への退職の切り出し方に決まりはある?
上司に退職を切り出す方法について、明確な決まりはありません。一般的には口頭で伝えるのがマナーとされていますが、就業規則で定めがなかったりやむを得ない理由があったりする場合は、メールで伝えるのも一つの手段です。
口頭で伝えるのがマナーだが法律上メールでも問題ない
退職の相談は、必ずしも口頭で伝えることにこだわり過ぎる必要はありません。民法第627条において、雇用期間に定めのない労働契約を結んでいる場合は「いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」とされています。退職の切り出し方については明記されていないため、メールで相談したり、意思を伝えたりすることも可能です。
とはいえ、退職相談をメールだけで済ませると「マナーがない」と捉えられる恐れがあります。メールを利用する際は、口頭で伝えることが難しいやむを得ない理由をあわせて記載しておきましょう。なお、勤務先の就業規則に退職の切り出し方について定められている場合もあるので、事前に確認しておくのがおすすめです。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職相談の切り出し方はメールでのアポ取りから始める
退職を決めたら、直属の上司にメールで面談のアポイントメントを取ります。メールの内容はできるだけ簡潔にし、「辞める」という文言は入れないのが無難です。以下で、退職相談の詳しい流れを見ていきましょう。
退職相談の切り出し方
- 退職の意思は遅くても希望日の1ヶ月前までには伝える
- 直属の上司と面談のアポイントメントを取る
- アポ取りのメールの内容は簡潔にする
- 「辞める」という言葉の使用は控える
1.退職の意思は遅くても希望日の1ヶ月前までには伝える
退職する旨を切り出す際は、遅くても希望する日の1ヶ月前までには申し出るのが望ましいといえます。法律上、雇用期間の定めがない場合は2週間前までに退職を願い出れば問題ありませんが、円満退職のためにも余裕をもった行動がおすすめです。
退職までの期間が短いと、引継ぎが十分にできなかったり、社内体制が整わなかったりして、会社や同僚に迷惑がかかってしまう可能性があります。退職の意向を早めに伝えることは、社会人として大切なマナーであると認識しておきましょう。
退職を申し出る時期は会社の就業規則によって異なる
退職は、遅くても希望日の1ヶ月前までには申し出るのが望ましいと述べましたが、厳密には各企業の就業規則によって異なります。企業の就業規則に「△ヶ月までに申し出ること」と明記されている場合は、その内容に従いましょう。一般的には「退職希望日の1ヶ月前まで」と定めている会社が多いようです。
なお、「今日限りで辞めます」と突然退職するのは社会人としてマナー違反なうえ、トラブルの原因にもなり得るので避けましょう。円満に退職するためにも、勤務先の就業規則を事前によく確認してみてください。
2.直属の上司と面談のアポイントメントを取る
就業規則をもとに退職希望日を設定したら、直属の上司と退職に関する面談をするためにアポを取ります。退職の内諾をもらうためだけでなく、希望日をもとに実際の退職日をすり合わせたり、引継ぎのスケジュールを考慮したりする必要があるからです。重要な面談なので、個別に話す時間を設けてもらいましょう。
上司が多忙で面談ができない場合
上司が多忙で直接会う機会がなかったり、出張続きだったりする場合は、メールで面談のアポを取る方法があります。退職の意思を伝えたいにもかかわらず面談ができないと、希望する退職時期が先延ばしになってしまう恐れがあるでしょう。
それでも面談をする時間が取れなかったり、タイミングが合わなかったりするときは、社内の人事部やほかの管理職に相談してみてください。
在宅勤務をしている場合
在宅勤務をしている場合は、メールやチャットで面談のアポを取り、直接対面して退職の意思を伝えるのが望ましいでしょう。完全リモートワークで勤務していたり、会社の所在地が遠く対面が難しい状況にあったりするならば、ビデオ通話で面談を行えるか尋ねるのがおすすめです。
休職している場合
休職している状態から退職を申し出る場合、メールですべて完結させることを理解してもらえる可能性があります。休職期間中の体調や自身の現状について説明し、職場復帰の見通しが立たない旨や治療に専念したい旨を伝えましょう。
状況に応じて、医師からの診断書を郵送やメールで提出することで、休職者の状態を企業側が客観的に判断しやすくなります。
3.アポ取りのメールの内容は簡潔にする
退職の意向を伝えるためにメールで面談を依頼するときは、なるべく簡潔な文章を心掛けましょう。あくまで辞める意思は直接伝えるのが基本なので、メールに面談内容の詳細を書く必要はありません。「面談の機会が欲しい」という要点のみを伝える内容にし、上司から返信がきたら、自分のスケジュールと照らし合わせて日程を決めます。
上司が忙しい場合もあるので、候補日を挙げる場合は選択肢を多めに提示しておきましょう。会議室のような他人に聞かれない場所を指定したうえで、30分ほど時間をもらうのがおすすめです。
4.「辞める」という言葉の使用は控える
アポ取りのメールでは、「仕事を辞める」「退職を検討している」などの言葉は使わないようにしましょう。退職相談に関する面談であることを事前に知られてしまうと、面談までの間に待遇や働き方の改善といった対策を取られる可能性もあります。
また、メール上でのやり取りで退職を引き止められたり、わざと面談の機会を作ってもらえなかったりと、スムーズに退職へ進めなくなる恐れも。メールでは「面談をしたい」と伝えるだけに留め、退職の意思は直接会ったときに伝えるようにしましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
上司に退職を切り出す際に送るメールの例文
ここでは、退職を切り出す際に上司に送るメールの例文を紹介します。状況別にまとめているので、どのような書き方をすべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
面談のアポを取りたいときの例文
件名:面談のお伺い
本文:
△△課長
お疲れ様です。△△(氏名)です。
今後について、折り入ってご相談したいことがございます。
△△課長のご都合がよろしいときに、30分ほどお時間をいただくことは可能でしょうか。
会議室等で、個別にお話しできましたら幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
(署名)
先述したように、アポを取る際は退職について切り出さないほうが無難です。やり取りを短縮したい場合は、自分の都合の良い日時をいくつか提示したうえでメールを送っても構いません。
仕事を辞めたい旨を事前に伝える際の例文
件名:退職面談のお願い
本文:
△△課長
お疲れ様です。△△(氏名)です。
突然で申し訳ありませんが、△月末日をもって退職させていただきたく、ご連絡差し上げました。
つきましては、退職に関する個別の面談をお願いしたいのですが、△月△〜△日の期間で、30分ほどお時間が取れる日時を教えていただくことは可能でしょうか。
詳細に関しましては、面談時にお話しできればと考えております。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
(署名)
メールで事前に退職を切り出す場合は、退職を希望する日を記載したうえで面談のアポを取りましょう。ただし、「『辞める』という言葉の使用は控える」で述べたような対策を取られるリスクを理解したうえで、事前に退職の旨を伝える必要があります。
メールで退職願を提出する場合の例文
件名:退職願提出(氏名)
本文:
△△課長
お疲れ様です。△△(氏名)です。
退職願を以下のとおり送付いたしますので、お手数ですがご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
退職願
令和△年△月△日
△△株式会社
代表取締役社長 △△△△様
△△部△△課 △△△△(自分の所属と氏名) 印
私儀、
この度一身上の都合により、令和△年△月△△日をもって退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます。
以上
退職届は退職が正式に決まったあとに会社に届け出る書類なのに対し、退職願は会社を辞めることのお伺いを立てる書類です。そのため、文末は「退職いたしたくお願い申し上げます」という形にしましょう。
退職願に記載する項目
- ・退職願
- ・提出年月日
- ・会社名、代表取締役社長の名前
- ・自身の所属部署、氏名、認印
- ・私議
- ・退職理由、退職希望日
会社名や所属部署は正式名称で記入するのがマナーです。また、退職希望日をはっきりと伝える必要があるため、退職の意思が固まってから作成するようにしましょう。
緊急性が高いと判断されれば即日退職できる可能性も
「急な病気で働けなくなった」「家族が体調を崩して介護を必要としている」など、退職理由の緊急性が高いと判断されれば即日退職できる可能性があります。
法律上は、原則として退職希望日の2週間前までにその意思を伝えなければなりません。しかし、すぐにでも仕事を辞めなければならない事情がある場合、会社の合意を得られれば即日退職できるため、悩んでいる方は上司や人事部に相談してみましょう。
退職をメールで切り出す際の6つの注意点
やむを得ず退職をメールで切り出す際は、仕事を辞める意思が固いことを示し、相手に対して礼儀やマナーを心掛ける姿勢が大切です。以下で解説する注意点を参考に、円満な退職を目指しましょう。
退職をメールで切り出す際の注意点
- 仕事を辞める意思が固いことを伝える
- 退職理由と退職希望日を明確にする
- 繁忙期や異動の時期を避けるなどタイミングを考える
- メールのみで退職の連絡をする場合は理由も添える
- 相手に対して礼儀やマナーを心掛ける
- 退職日までに引継ぎを終えられるような計画を立てる
1.仕事を辞める意思が固いことを伝える
退職を切り出すメールでは、仕事を辞める意思が固いことを明確に伝えるのがポイントです。退職を迷っているような内容だと、上司に「引き止めれば気持ちが変わるかもしれない」と思われ、強く説得される可能性があります。
「退職を検討している」「退職を考えている」といった表現ではなく、「退職させていただきたいと思います」と言い切り、説得の余地をなくすとスムーズです。ただし、上司に失礼のないようクッション言葉を適切に使うようにしましょう。
2.退職理由と退職希望日を明確にする
上司にメールで退職を伝える際は、退職理由と退職希望日もあわせて記載します。「退職します」だけでは上司も納得できず、理由を尋ねられる可能性があるでしょう。「一身上の都合」と書いても問題ありませんが、具体的な理由を伝えられる場合は正直に記載するのが望ましいといえます。
また、おおよその退職希望日が分かると、会社側も業務の引継ぎや後任の選定といった手続きがしやすくなるでしょう。会社に残る人になるべく迷惑がかからないよう、退職時期に余裕をもった連絡が重要です。
3.繁忙期や異動の時期を避けるなどタイミングを考える
退職を切り出すタイミングとしては、繁忙期や異動の時期は避けるのが無難です。忙しい時期に退職を申し出ると周囲に迷惑をかけるだけでなく、「社会人として無責任だ」というマイナスな印象を与える恐れがあります。
また、人事異動の時期は会社全体で配置の調整を行っているため、辞令が出てから退職を伝えると、再度人員配置を考えなければならず、手間をかけさせてしまうでしょう。
退職を切り出す際は、繁忙期直後や異動がない時期を選ぶなど、できるだけ会社に迷惑がかかりにくいタイミングを考えるのがおすすめです。
4.メールのみで退職の連絡をする場合は理由も添える
メールのみで退職の意向を伝える場合は、会って直接話をできない理由も記載しておきましょう。たとえば、「体調不良が続き対面での面談が難しい」「遠距離やアクセスの悪さから会社に出向くことが困難」のような説得力のある理由であれば、相手からの納得を得やすい可能性があります。
5.相手に対して礼儀やマナーを心掛ける
相手を不快にさせない表現や文章を心掛けるのも、メールで退職連絡をする際に重要なポイントの一つです。本来、退職の意思は口頭で直接伝えるのがマナーとされています。そのため、上司のなかにはメールで退職の意思を伝えられた時点で、「失礼だ」「マナーがなっていない」と感じる人もいるでしょう。
上司に会う機会が取れなかったり、どうしても出社できなかったりと、やむを得ずメールという手段を用いる場合は、相手に対して礼を尽くす姿勢が大切です。メールを送る前に「自分勝手な表現になっていないか」「礼儀を欠いた文章になっていないか」といった部分を見返しましょう。
また、誤字・脱字が多いメールも「適当に送っているのではないか」とネガティブなイメージを与える可能性があるので、事前の見直しが重要です。
6.退職日までに引継ぎを終えられるような計画を立てる
退職の意思を切り出す際は、あらかじめ退職日までに引継ぎを終えられるような計画を立てておきましょう。退職が決まったら、仕事を辞める日までに自分の業務を引き継ぐ作業が発生します。退職後に上司や同僚が困らないよう、業務の流れや注意点を円滑かつ確実に引継げるスケジュールを組んでおくことが大切です。
退職理由の切り出し方や言い方も工夫しよう
退職理由の切り出し方や言い方によっては、会社や上司との関係が険悪になる場合もあるため、工夫して伝えるよう心掛けましょう。たとえば、面談では時間を取ってくれた上司へ感謝を示しつつ、退職することに申し訳ないと思っている姿勢を表すと、角が立ちにくい可能性があります。
「残業が多い」といったネガティブな退職理由はストレートに伝えず、「資格取得に向けた勉強のためにワーク・ライフ・バランスを整えたい」のようにポジティブな内容に変換すると、上司からの納得も得やすいでしょう。
また、退職面談ではあくまで「相談」という形を崩さず、自分勝手に話を進めないのもポイントです。とはいえ、あいまいな態度では引き止められてしまったり、退職を先延ばしにされたりする恐れがあるため、「退職の意思は変わらないので、退職日について相談したい」としっかり意思表示をしましょう。
退職が決まったあとの挨拶メールの書き方
ここでは、退職が決まったあとの挨拶メールの書き方について解説します。例文も紹介しているので、上司や社内・社外に向けたメールを作成する際の参考にしてみてください。
上司向けの例文
件名:退職のご挨拶(△△部△△課 氏名)
本文:
△△部 部長 △△さん
お疲れ様です。△△部△△課の△△(氏名)です。
この度、一身上の都合により本日をもちまして退職することとなりました。
本来であれば、直接お伺いすべきところ、メールでのご挨拶となり申し訳ございません。
△△部長には、入社時よりさまざまなプロジェクトをとおして多くの学ぶ機会をいただき、心より感謝しております。
在籍中、至らぬ点も多かったと思いますが、温かいアドバイスや激励のお言葉をいただき、人としても社会人としても成長できました。今後も△△部長に教わったことを糧に、新たな活動に励んでまいりたいと存じます。
なお、退職後の連絡先は下記となります。何かございましたらご連絡をいただけますと幸いです。
メールアドレス:
電話番号:
最後になりましたが、△△部長の一層のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(署名)
上司への挨拶メールでは、愚痴や批判的な言葉は避けたポジティブな内容を重視しましょう。具体的な仕事のエピソードや思い出、学びがあればそれを伝えるのがおすすめです。
また、上司や社内向けの場合は、必要に応じて私用の連絡先を書いても問題ありません。
社内向けの例文
件名:退職のご挨拶(△△部△△課 氏名)
本文:
△△事業部(△△課)の皆様、お疲れ様です。△△(氏名)です。
私事ですが、この度、一身上の都合により△月末で会社を退職することとなり、本日が最終出社日となりました。
本来ならば直接ご挨拶をすべきところですが、メールにて失礼いたします。
これまで△△事業部の皆様には大変お世話になりましたこと、心よりお礼申し上げます。
業務をとおしてさまざまな方と交流し、多くの経験を積ませていただきました。
今後も、この会社で学んだことを活かして、日々励んでまいりたいと思います。
なお、退職後の連絡先は下記となります。何かございましたらご連絡をいただけますと幸いです。
メールアドレス:
電話番号:
最後になりましたが、皆様のさらなるご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
これまでお力添えいただき、ありがとうございました。
(署名)
社内向けにもメールを送ることで、退職前に全員に直接挨拶ができなかったとしても、漏れなく感謝の気持ちを伝えられます。読み飛ばしを防ぐために、メールは「退職のご挨拶【氏名】」といった分かりやすい件名で送りましょう。ビジネスマナーとして、退職理由は「一身上の都合」に留めておくのが無難です。
社外向けの例文
件名:退職のご挨拶【株式会社△△ 氏名】
本文:
株式会社△△ △△部
△△様
平素よりお世話になっております。株式会社△△の△△(氏名)です。
私事で大変恐縮ですが、この度、△月△△日をもって株式会社△△を退職することとなりました。最終出社日は、△月△△日の予定です。
△△様には、何かとお力添えをいただき、大変感謝しております。誠にありがとうございました。
後任は、同じ部署の△△が担当させていただきます。引継ぎは退職までにしっかりと行いますので、ご安心ください。
つきましては、△日にお伺いする際に、後任の△△ともどもご挨拶に伺えればと存じます。
残りわずかとなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
まずは、退職のご挨拶まで申し上げます。
(署名)
社外へのメールは、「自分が退職してからの仕事はどうなるのか」を明確にするのがポイントです。後日、取引先を訪問する・しないにかかわらず、後任者を紹介して先方の不安を払拭しましょう。「取引先から自分宛に連絡が来たが、もう退職したあとだった」というすれ違いが起きないよう、いつまで出社するのかを伝えるのも重要です。
なお、社外の人とは会社をとおしての付き合いなので、転職先や私用の連絡先を書くのは控えます。#後任者との訪問を予定している場合
退職までに先方を訪問する予定があり、その際に後任者を紹介できる場合は、前述の例文のとおり事前にその旨をメールで送っておくと安心感を与えられるでしょう。
ただし、取引先が時間の都合で紹介に対応できなかったり、急なスケジュール変更で後任者と一緒に訪問できなくなったりする可能性もあるため、臨機応変に対応できるよう余裕をもった引継ぎがおすすめです。
退職まで訪問予定がない場合
退職までに取引先を訪問する予定がない場合も、メールで退職の挨拶と後任者の紹介をしておくと、引継ぎ後もスムーズに対応してもらえるでしょう。具体的には、直接挨拶できないことへのお詫びと、後日改めて後任者が挨拶に伺う旨を記載します。先方にとって、引継ぎ後の不安が生じにくい文面を意識することが大切です。
退職の挨拶メールを送る際の6つのポイント
ここでは、退職の挨拶メールを送る際のポイントを解説します。退職を控えている方は、ぜひお役立てください。
1.退職の挨拶はシンプルな文面でもOK
退職の挨拶メールは、感謝の気持ちとお礼が伝わるならばシンプルな文面でも構いません。
社員数が多かったり、周囲と関わる機会が少ない業務だったりすると、全員と密接な関係とはいえない部分もあるでしょう。退職の挨拶は、退職する旨とこれまでの感謝の気持ちを表すもののため、それらが伝わるならば、ある程度シンプルな文面でも支障はないでしょう。
2.メールは一斉送信しても問題ない
退職の挨拶メールは一斉送信しても問題ありません。一斉送信する場合は、受信者同士にほかの人のアドレスが開示されないよう注意しましょう。
To(宛先)に自分のアドレスを入力し、Bccに送信したい連絡先を追加する方法ならば、プライバシーに配慮しつつ一斉にメールを送れます。
お世話になった上司や同僚には個別に送るのがおすすめ
業務上関わる機会が多かった上司やお世話になった同僚へは、一斉送信のメールとは別に個別で挨拶メールを送るのがおすすめです。仕事で印象深かった経験や、当人同士だからこそ分かり合えるエピソードなどを付け加えると、感謝の気持ちがより深く伝わるでしょう。
3.退職理由は「一身上の都合」と記載するのが無難
退職の挨拶メールには、詳細な退職理由を記載する必要はありません。社内・社外向けどちらにしても、「一身上の都合」と記載するのが無難です。特に給与や勤務体制などのネガティブな退職理由の場合、詳細に書くことで自身の信用を損ねてしまう恐れがあります。
結婚や出産といった祝い事での退職であれば、その旨を書いても構いませんが、判断に迷う場合は「一身上の都合」とするのが望ましいでしょう。
4.社内向けには出勤最終日に送る
社内向けの退職の挨拶メールは、最終出勤日に送るのが一般的です。ただし、企業の規則や退職時のガイドラインに「定時終了後に送る」「△日前に送る」などの決まりがあれば、それに従った対応をしましょう。
退職日まで通常業務や引継ぎで忙しい可能性があるため、最終日に慌てなくて済むよう余裕をもって準備しておくことが大切です。
5.社外向けには退職日の2~3週間前に送る
社外向けの退職の挨拶メールは、退職日の2~3週間前に送りましょう。退職までの期間によって、先方の業務の優先順位が変わってくることがあります。事前に退職を知らせるメールを送り、引継ぎの後任者と一緒に挨拶に行くなど、早めの行動を心掛けましょう。
6.転職先が決まっていても企業名は伝えない
退職後の転職先が決まっていても、周囲に企業名を伝える必要はありません。具体的な企業名を教えると、引き止めるために真偽不明の噂話を聞かされたり、同業他社ならば退職まで気まずい思いをしたりする可能性があるでしょう。
しつこく聞き出そうとしてくる相手には、業種や職種だけ答えたり、「転職後の仕事が落ち着いたら改めてご連絡します」とかわしたりするのが望ましいといえます。
円満退職をして次の転職をスムーズに進めよう
退職後の転職活動や新しい活動をスムーズに進めるには、現在の会社から円満に退職することが重要です。メールで退職を申し出たり相談したりする際は、引継ぎや退職手続きを滞りなく行うためにも、退職の切り出し方・アポの取り方をしっかり把握してから臨みましょう。
会社や上司に対する感謝の気持ちをもち、退職日まで自分の業務への責任を果たそうとする姿勢も効果的です。円満退職を叶え、次のステップや転職活動をスムーズに進めましょう。
退職を引き止められてしまったら?
退職を切り出して引き止められたとしても、「自分の意思は変わらない」とはっきり伝えることが大切です。「退職して本当にやりたいことは何か」「転職先でしか実現できないことは何か」が明確になっていると、引き止めにあっても断れるでしょう。
それでもしつこく残るよう説得されたり、悪質な引き止めをされたりしたら、直属の上司より上の立場の人や人事部に相談するのがおすすめです。
「退職が決まったけれど、まだ転職活動中」「在職中は忙しく、転職活動が思うように進められなかった」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
若年層の就職・転職支援に特化したハタラクティブでは、経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたの適性・経歴・希望条件に合った仕事を厳選してご紹介します。取り扱っている求人は、すべて事前に企業への取材を行っているので、求人情報だけでは分からないリアルな企業の様子を知ることも可能です。
応募書類の添削や面接対策、応募先企業への連絡、選考スケジュールの調整など、キャリアアドバイザーが総合的にサポート。忙しい方も効率よく就職・転職活動に臨めます。所要時間1分程度で受けられる適職診断を含め、サービスのご利用はすべて無料です。就職・転職に関するご相談も受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。