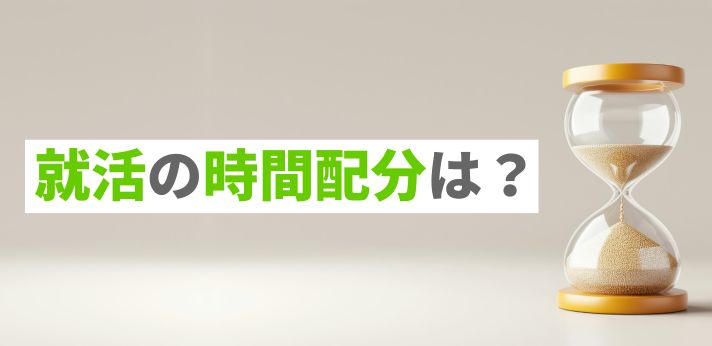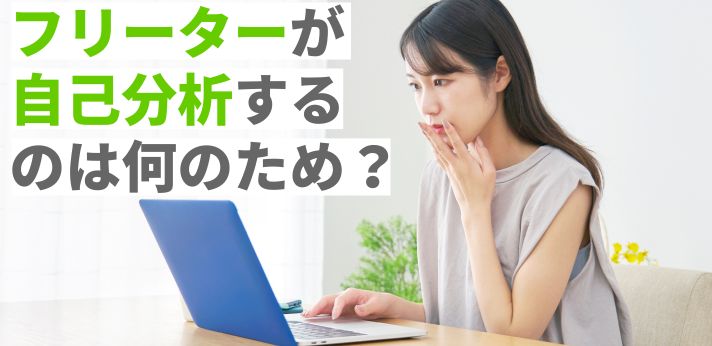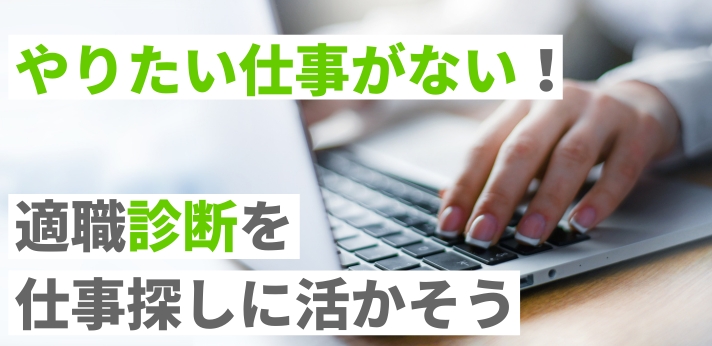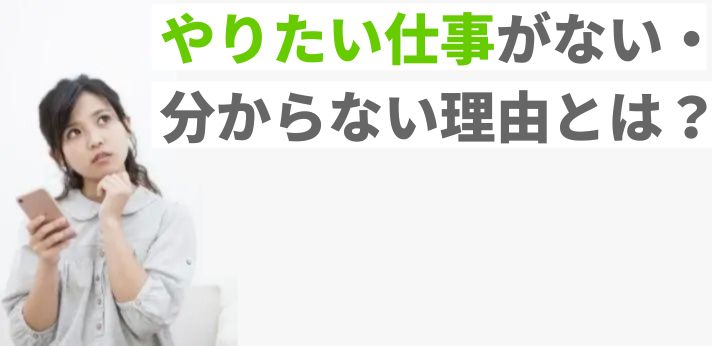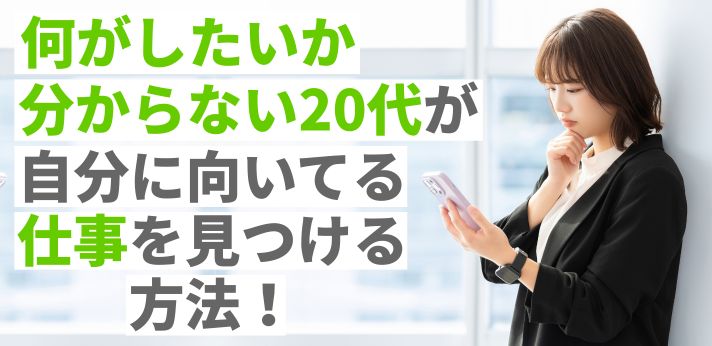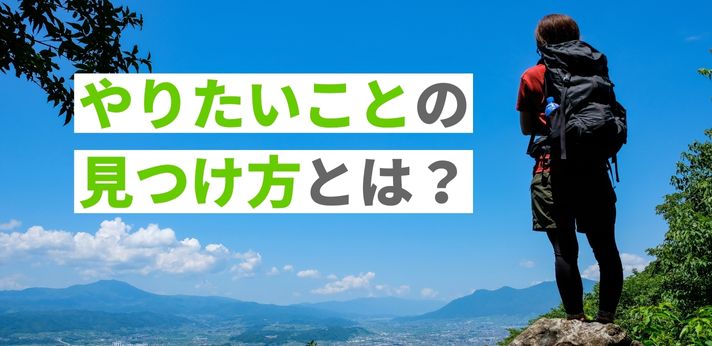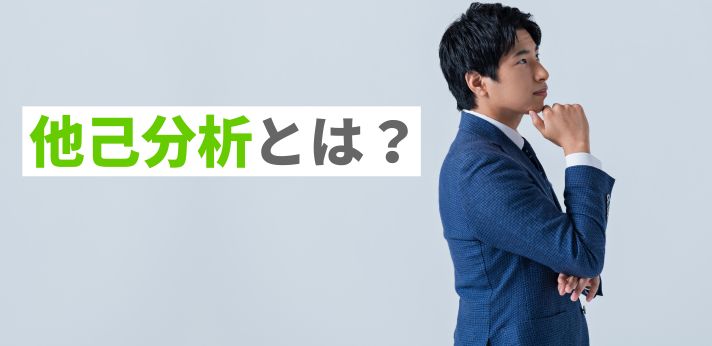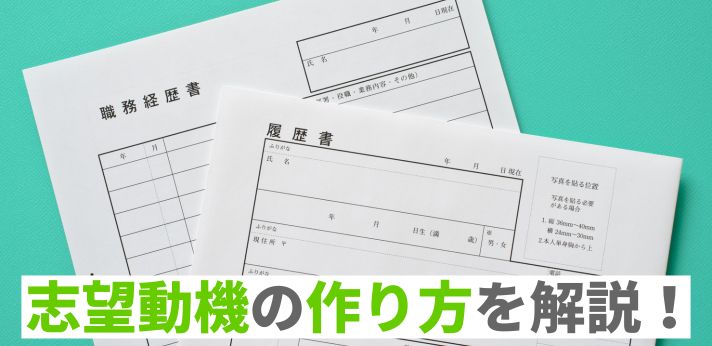自己分析のやり方12選!就活での必要性や志望動機に活かす方法もご紹介! 更新日 2025.08.27
公開日 2017.03.07
こんな人におすすめ
経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方 ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。レバレジーズ株式会社 に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
自己分析とは、自分自身を分析し価値観や適性の理解を深めるもの
「自己分析とはそもそも何?」「どんなやり方があるの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。自己分析とは、自分自身を分析し、価値観や適性の理解を深めるための方法です。
自己分析とは? 自己分析とは、自分の経験や思考から「長所・短所」「得意・不得意」「価値観」などを客観的に分析し、自分自身を深く把握するための作業です 。就職や転職といった求職活動の一環として行われるのが一般的です。自己分析の結果は、向いている業界・仕事を分析するときや、志望動機や自己PRを考えるときに役立ちます。
就職・転職活動で自己分析が必要とされる理由 就職・転職活動の際に自己分析が必要とされる理由として、「客観的に自分を理解するため」「就職活動(転職活動)の軸を定めるため」の2つが挙げられます。自己分析をしないまま就職・転職活動を進めると、効果的な自己アピールができなかったり、仕事や企業とのミスマッチを起こしたりする恐れも。以下で自己分析の必要性について詳しくご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。
客観的に自分を理解するため 自己分析をすることによって、自分の「長所・短所」「得意・不得意」「価値観」といった特徴を客観的に理解できます。
面接では、「自分を客観視できているか」といった自己分析力が評価の対象になることも。また、企業への志望動機を明確にしたり、オリジナリティのある自己PRを考えたりするためにも、自分を客観視する作業が大切 です。
就職活動(転職活動)の軸を定めるため 自己分析は、就職・転職活動の軸を定めるために欠かせません。「就職活動の軸」とは、求人探しや面接対策をする際の方向性や譲れないものを定めるものです。自己分析は、その軸を定めるために必要な「強み」や「価値観」を明確にしやすくなります。
自己分析をしないと求職活動の方向性を見失い、「自分の強みが分からなくなる」「回答がぶれてしまう」「企業のニーズに合わないアピールをしてしまう」などの失敗につながることもあるでしょう。
自己分析を行うメリット ここでは自己分析を行うメリットを4つご紹介します。「自己分析には意味がある?」と疑問に思う方は以下を参考にしてみてください。
自己分析を行うメリット
自分のやりたいことがはっきりする
自己PRや志望動機を考えやすくなる
回答内容に説得力を持たせられる
仕事や企業とのミスマッチを防げる
1.自分のやりたいことがはっきりする 自己分析を行うことで、自分の本当に好きなことや大切にしている価値観が分かり、自分のやりたいことが明確化できるメリットがあります 。やりたいことが明確化されることで、就職や転職活動の軸を決めやすくなり、仕事を選ぶ際に役立つでしょう。
2.自己PRや志望動機を考えやすくなる 自己分析を行い、自分の性格や過去の経験を深掘りしていくと、長所といったアピールポイントが見えてくるため、自己PRや志望動機を考えやすくなります 。また、単に自分の強みや長所を見つけられるだけでなく、説得力を持たせるために必要な具体的なエピソードも同時に見つけ出せる のもメリットの一つです。
面接では、強みだけではなく、その根拠となるエピソードを具体的に示す必要があります。
「自分の強みはもう知っている」という人でも、それを示す根拠はすぐに思い出せない場合があるでしょう。自己分析を行い、自分を客観視し、強みだけでなくその根拠を明確にしておくことが大切です。
3.回答内容に説得力を持たせられる 自己分析をしっかりと行うことで回答内容に一貫性を持たせることができ、説得力をアップできるのもメリットといえます 。自己分析が不十分だと、志望動機と自己PRの内容がずれてしまい、「本当のことをいっているのか」と疑われる恐れもあるので注意が必要です。
面接では発言の整合性が確かめられるので、自己分析によって自分自身を十分理解しておきましょう。
4.仕事や企業とのミスマッチを防げる 自己分析を徹底しておくことで、入社後に自分がやりたい仕事とのミスマッチを起こすリスクを減らせるでしょう 。せっかく入社できても、「思っていた仕事内容と違った」と早期離職してしまう人もいます。自己分析を行うことで、自分の強みや価値観と企業が求めるものを照らし合わせ、相性を確かめやすいでしょう。
また、自己分析に加えて企業研究を行うことで、自身のやりたいことや強みと企業のビジョンをマッチさせやすく、より自身が理想とする企業に就職しやすい 可能性があります。企業研究の方法については、以下のコラムをご一読ください。
自己分析はいつまでにやるべき?
自己分析は、いつまでにやっておかなければいけないという明確な基準はありませんが、就職・転職活動を始める前までに済ませておくのが効果的です。自己分析では、就職・転職活動で活かせるアピールポイントを知れるだけでなく、自分の適性も分かるため適職を見つける際にも役に立つでしょう。
また、就職・転職活動では、企業研究を行うことも大切です。企業研究を行うことで、より自分に合った企業や仕事を見つけやすくなります。スムーズに就職・転職活動を進めるためにも、自己分析と合わせて企業研究も行ってみてください。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介 からのアドバイス
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ 」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
向いている仕事あるのかな? 自分と同じような人はどうしてる? 資格は取るべき? 実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
求職活動における自己分析の基本的な流れ ここでは自己分析を行う際の基本的な流れをご紹介します。1〜6つのステップに分けてご紹介するので、自己分析を行う際の参考にしてみてください。
求職活動における自己分析の基本的な流れ
過去の自分を振り返る
エピソードを深く掘り下げる
分析内容を整理して強みや価値観を見つける
「現在の自分」と「理想の自分」を明確にする
「理想の自分」になるために足らない要素を考える
自分の強みと理想を踏まえて求職活動の方向性を決める
1.過去の自分を振り返る まずは自分の過去を振り返り、出来事を箇条書きで書き出します 。新卒の場合は「学業」や「部活」「アルバイト」など、転職者の場合は前職で印象に残っていることを、時系列で一覧にするのがポイントです。
「好きなこと」「得意なこと」「苦手なこと」「継続したこと」「嬉しかったこと」など、さまざまな視点で思い出してみましょう。時系列にするときは、「中学時代」「高校時代」「大学時代」のように区切って書き出しておくと、整理しやすくなります 。
なお、書き出す出来事は、困難やトラブルといったネガティブな体験談でも問題ありません。長所や短所、自己PRなどを考えるときに役立つ可能性があるので、思いつく限り書き出しておきましょう。
2.エピソードを深く掘り下げる 過去の出来事を振り返ったら、書き出したエピソード一つひとつを掘り下げていきます 。エピソード一つにつき、次のような内容を考えてみましょう。
・取り組んだ内容と経緯
・具体的な印象深いエピソード
・良かったこと
・困難に感じたこと
・困難の場合は解決に向けて工夫した点
・出来事から得た学び
深堀りするコツは、「なぜ?」「どうして?」を繰り返すことがポイントです 。「なぜその活動に取り組んだのか」「なぜ続けられたのか」「どうしてそう感じたのか」と、自問自答を繰り返しましょう。
また、困難やトラブルに関する内容は、「採用の場にふさわしくない」と捉えがちですが、そのようなことはありません。「解決するために工夫した点」や「経験から得られた学び」があれば、有効なアピール材料になります。どのようなエピソードでも採用の場でアピールにつなげられる可能性があるため、漏れなく書き出しておきましょう。
3.分析内容を整理して強みや価値観を見つける これまで洗い出してきたエピソードのなかで共通していることを探し出し、自分の強みや価値観を見つけます 。「内容は違うけど解決に向けた動き方は一緒」「同じようなことを困難として感じやすい」など、さまざまな角度から自分の傾向を分析してみましょう。その結果が自分の強みや価値観を見つけるヒントとなります。
強みは、特別なものである必要はありません。「ほかの候補者よりも良く見せたい」という思いで、嘘の強みを考えるのはやめましょう。嘘やごまかしは、入社後にバレてしまう恐れがあります。
面接官に「一緒に働きたい」「うちに来て欲しい」と思ってもらえるような強みを選んで、自己PRや志望動機などに活かしましょう 。
強みが分からないときはどうする?
過去の出来事や具体的なエピソードを洗い出しても自分の強みや価値観が分からない場合は、家族や友人など、自分のことを理解してくれている人に他己分析を頼んでみましょう。他己分析を頼むことで、客観的な視点で自分の強みや価値観を把握できるでしょう。
身近に他己分析を頼める人がいない場合は、自己分析に活かせるツールやエージェントの利用を検討してみるのも手です。MBTI診断やストレングスファインダーなどの診断ツールで自分の性格を分析することで、強みや価値観を見つけやすくなる可能性も。また、エージェントに相談して自己分析をサポートしてもえば、プロの視点から就職・転職で活かせるアピールポイントを効率的に見つけだすこともできるでしょう。
4.「現在の自分」と「理想の自分」を明確にする 自分の強みや価値観を踏まえたうえで、「現在の自分」と「理想の自分」について考えてみましょう 。今の自分のスキルや性格、経験を洗い出し、客観的な視点で「現在の自分」を見つめ直します。そのあとに、将来なりたい自分の姿や希望する働き方を具体的に書き出し、「理想の自分」を明確にしましょう。「現在の自分」と「理想の自分」を把握することで目標やゴールが明確になり、業界・職種選びや企業選びがしやすくなります 。
5.「理想の自分」になるために足らない要素を考える 「現在の自分」と「理想の自分」を比較し、足りないスキルや経験を洗い出してみましょう 。「理想の自分」になるために必要なものを考えることで、自分の課題や今後の目標が浮き彫りになります。就職・転職活動を成功させるためには、今後の目標を立てることが大切です。自分の成長に必要な課題が明確になれば前向きに進めます。
6.自分の強みと理想を踏まえて求職活動の方向性を決める ここまででに見つけた強みや価値観、理想像をもとに「就職活動(転職活動)の軸」を定め、どのような業界・職種や企業を選ぶべきかを決めましょう 。求職活動の方向性をひとりで決めるのが難しいと感じる場合は、より深く掘り下げて「現在の自分」と「理想の自分」を考えてみたり、就職支援サービスの利用を検討してみたりするのが有効です。
自分に合った仕事や職場環境を選ぶことで就職・転職活動を進めやすくなるのはもちろん、「やりがいを持って働ける」「長期的なキャリアを築ける」といったメリットもあります 。自己分析は就職・転職を成功させるために欠かせないプロセスなので、悩んだときは一人で抱え込まず身近な人やプロに相談してみましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ 」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
自分に合った仕事を探す方法がわからない 無理なく続けられる仕事を探したい 何から始めれば良いかわからない 自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断 」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
簡単にできる自己分析のやり方12選 自己分析には、「自分史」や「モチベーショングラフ」「ライフラインチャート」などさまざまな種類があり、それぞれ分析方法が異なります。以下の表に、簡単にできる自己分析のやり方と、どんなことを調べる際に役立つのかをまとめました。
やり方 調べられること 自分史 過去の出来事を時系列で整理する 成長のきっかけ モチベーショングラフ 感情の浮き沈みをグラフにして可視化する モチベーションが上がる要因 ライフラインチャート これまでの成功・失敗・影響を受けた出来事を線でつなぐ 好調・不調の傾向や転機 マインドマップ 自分に関する情報を図式化する 自分の特性や興味関心のあること ジョハリの窓 他人の視点で自分を客観視する 盲点や思い込みによって気づけなかったこと 自己分析に活かせるツールを使う Webサイトにある診断ツールを使う 自分では気づきにくい傾向や思考パターン、職業適性など WILL・CAN・MUSTフレーム 「やりたい・できる・求められる」のバランスを整理する キャリアの方向性 SWOT分析 「自分の強み・弱み・機会・脅威」を整理する 自分の立ち位置や戦略 ロジックツリー 「なぜ?」を繰り返して思考を深掘りする 行動や選択の背景(自分の価値観) STARメゾット エピソードを「状況・課題・行動・結果」に分けて整理する 自分の行動特性や成果 キャリアアンカー 仕事をするうえで大切にしている価値観を明確にする 仕事に求める価値観 他己分析 他人に自分の印象や強みを聞く 客観的に見た自分
以下で、それぞれの具体的なやり方や、その手法で調べられることについて詳しく解説するので、自己分析を行う際の参考にしてみてください。
簡単にできる自己分析のやり方
自分史
モチベーショングラフ
ライフラインチャート
マインドマップ
ジョハリの窓
自己分析に活かせるツールを使う
WILL・CAN・MUSTフレーム
SWOT分析
ロジックツリー
STARメゾット
キャリアアンカー
他己分析
1.自分史 自分史とは、自分の過去の体験や感情、行動を時系列で振り返るための方法 のことです。自分史を作成することで、自分自身の「価値観」「性格」「強み・弱み」「人生の傾向」などの理解を深められる ので、自己分析に役立てられます。
自分史を作る際は以下のステップで作成すると効果的です。
時期で分ける 出来事や感情を書く 共通点や傾向を探す 特徴や価値観をまとめる
内容 1.時期で分ける 人生を「幼少期」「学生(小中高大)」「社会人」などに分けて考える 2.出来事や感情を書く 各時期で印象に残っている経験や感情を思い出す 3.共通点や傾向を探す 振り返った出来事から、自分の行動パターンや特徴を見つける 4.特徴や価値観をまとめる 見つけた傾向から「自分らしさ」を言語化する
自分史を書くときは、「ネガティブな体験」も避けずに書くことが大切です。つらい経験や失敗のなかに、自分の価値観や成長のきっかけが隠れていることもあります。
また、他人と比較しないことも重要なポイントです。自分史とはあくまでも自分自身の過去と向き合う作業のため、他人と比べて優劣を測るのはやめましょう。
2.モチベーショングラフ モチベーショングラフとは、自分のやる気(モチベーション)の上下をグラフで可視化する自己分析方法です 。
時間の流れ(年齢や学年)を横軸に、モチベーションの高さを縦軸にして、気持ちの浮き沈みを線でつなぎながら、自分の感情や価値観、行動パターンを見える化します。
モチベーショングラフを作成するときは、以下のポイントに注意して作成してみてください。
モチベーショングラフの作り方
横軸に「年齢」や「学年」を書く(例:小学生~現在まで)
縦軸に「モチベーションの高さ」を書く(下がやる気なし・上がやる気があり)
各年代の出来事と当時のモチベーションを思い出し、横軸と縦軸が交わるところに点を記入する
点と点を線でつなぎ合わせる
モチベーションが上がった理由と下がった理由をグラフ内に書く
モチベーショングラフが完成したら、各年代の出来事と感情の上下を見比べて、「何がやる気の源か」「どんなときに落ち込むか」などを分析してみましょう。モチベーショングラフを作成することで、自分の人生におけるやる気や気分の浮き沈みパターンや、その背景にある価値観や行動傾向を客観的に把握できます 。
また、過去の成功体験や挫折体験を振り返ることで、「自分がどのような状況で力を発揮できるのか」「何が自分にとってストレスになるのか」といった人生の傾向や特徴も見えてきます。
このような気づきは、自己理解を深めるだけでなく、進路選択やキャリア設計、自己PRの材料としても役に立つので、就職・転職の際はぜひモチベーショングラフを作ってみてください。
3.ライフラインチャート ライフラインチャートとは、自分の人生を時系列で振り返りながら、「感情」や「満足度」「充実度」の浮き沈みをグラフで表す自己分析の手法です 。
モチベーショングラフに似ていますが、ライフラインチャートのほうが「人生の流れ」や「人生の満足度の変化」をより広い意味で把握できます。
ライフラインチャートの作り方
横軸に年齢・時期を設定する(例:「10歳~30歳」「幼少期・学生・社会人」など)
縦軸に「感情」や「満足度」を設定する(上はポジティブ、下はネガティブ)
各時期の出来事と当時の感情・満足度を思い出し、横軸と縦軸が交わるところに点を記入する
点と点を線でつなぎ合わせる
「なぜその時期が長かったのか」「悪かったのか」など、背景や理由を記録する
ライフラインチャートを作ることで、人生における満足度の高い時期と低い時期のパターンが見えてきます。それにより、どのような環境や出来事が自分にとってプラスに働くのか、逆にどのような状況がストレスや不満につながるのかを客観的に理解できる でしょう。
また、自分にとっての人生の転機や価値観が変わったタイミングも明らかになり、これからのキャリア選択や目標設定のヒントにもなります。
4.マインドマップ 自己分析におけるマインドマップとは、あるテーマを中心に置き、そこから関連するキーワードやアイディアを枝状に広げていく方法です 。思考を整理したり、アイディアを可視化したりするのに非常に役に立ちます。
自己分析では、「自分」というテーマから連想される「経験」や「感情」「価値観」「強み」などを広げていくことで、自分の特徴や考え方を視覚的に整理・理解できる でしょう。
マインドマップの作り方
ノートや紙の真ん中に「自分」と書く
「自分」から太い枝(線)をいくつか書く
それぞれの太い枝の上にメインテーマを書く(性格・経験・価値観・得意・不得意など)
太い枝から細い枝をいくつか書く
太い枝のテーマに合わせて思いつくことを自由に書く(キーワードやイラストを使うのがポイント)
必要に応じて細い枝をさらに細かく分け、深掘りする)
自分 太い枝 細い枝 細い枝をさらに細分化 性格 ・ポジティブ ・ポジティブ→明るい 好きなもの・好きなこと ・読書 ・読書→推理、恋愛 得意なこと ・料理 ・料理→日本食、お菓子 不得意なこと ・動物と触れ合う ・動物と触れ合う→怖い、アレルギー
マインドマップを書くときのポイントは、思いついたことを自由に書き出すことです。正解や形式にとらわれず、自分の頭のなかにあることをそのまま広げていくことで、新たな気づきにつながります。
また、できるだけ単語で書くように書くようにすると、全体が見やすくなり、思考の流れもつかみやすくなるでしょう。さらに、マインドマップの枝の内容は途中で変わっても構いません。
最初に出てきたアイディアが、ほかのテーマとつながったり、自分でも意外な方向に進展したりする場合もあるでしょう。そのため、書きながら気づいたことを追加・修正する柔軟さが大切です。
5.ジョハリの窓 ジョハリの窓とは、自己理解と他者理解を深めるための心理学モデルのこと 。アメリカの心理学者ジョセフ・ルフトとハリ・インガムが提唱しました。人間関係のなかで、自分がどう見られているか、どこまで自分を理解しているかを4つの領域に分けて整理することで、「本当の自分」や「他人との関わり方」への気づきが得られます 。
開放の窓 盲点の窓 秘密の窓 未知の窓
ジョハリの窓を活用するためには、まず自己分析を行い、「自分の性格」や「行動傾向」「価値観」などについて整理します。次に家族や友人、同僚など信頼できる他者からフィードバックを受け取ることで、自分では気づかなかった一面を知れるでしょう。
また、自分の考えや気持ちを意識的に他者に伝える自己開示を行うことで、他者との間にある情報のギャップを減らし、信頼関係を築きやすくなります。このようにして、自分も他人も知っている領域(開放の窓)が広がっていくといえるでしょう。
6.自己分析に活かせるツールを使う 先述した方法で自分について理解を深めることが難しいと感じる場合や、「もっと手軽に自己分析をしたい」と考えている方もいるでしょう。インターネットで検索すると、無料で簡単に自分の性格や適職を調べられるツールが見つかるので、自己分析に役立てるのも一つの手です。
ここでは、自己分析に活かせるツールを6つご紹介します。自己分析にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。
自己分析に活かせるツール6選
職業情報提供サイトjob tagの「自己診断ツール」
MBTI診断
ストレングスファインダー
エニアグラム
V-CAP診断
適職診断
職業情報提供サイトjob tagの「自己診断ツール」 厚生労働省が公開している「職業情報提供サイトjob tag 」の「自己診断ツール」では、自己分析に活かせる6つの検査を無料で行えます 。以下に、実際に利用できる検査の情報をまとめました。
職業興味検査 自分の仕事に対する興味から適職を探索できる 仕事価値観検査 自分の仕事に対する「価値観」から適職を探索できる 職業適性テスト(Gテスト) 自分の「能力面の特徴」から適職を探索できる しごと能力プロフィール検索 自分のスキルや知識などから「しごと能力プロフィール」を作成して適職を探索できる ポータブルスキル見える化ツール 自分の「ポータブルスキル(※)」からそれを活かせる職務・職位を探索できる 結果を組み合わせて適職を検索 自分の検査結果を組み合わせて職業を検索できる
上記の検査を受けることで、自分の性格やスキルに合う適職を調べられるため、就職・転職活動の仕事選びがスムーズになる でしょう。
MBTI診断 MBTI診断とは、Myers-Briggs Type Indicator(マイヤーズ=ブリッグス・タイプ指標)の略で、アメリカの心理学者マイヤーズとブリッグスが開発した、性格タイプを16通りに分類する性格診断ツールです。MBTI診断を行うことで、自分の「物の見方・考え方・判断の仕方」の傾向が明らかになるため、自分らしい行動のパターンや人との違いを理解する際に役立ちます 。
MBTIは「外向(E)・内向(I)」「感覚(S)・直観(N)」「思考(T)・感情(F)」「判断(J)・知覚(P)」の4つの性格指標の組み合わせによって、16タイプに分けられます。自己分析でMBTI診断を活用すれば、自分がどのように物事を考え、感じ、行動する傾向があるのかを知ることが可能です。これにより、自分の強みやコミュニケーションのスタイル、そして他人との違いを客観的に理解できるようになります。
また、自分に合った働き方や職場環境、人との関わり方が見えてくるため、キャリア選択や人間関係の改善にも役に立つ でしょう。
以下のコラムで、MBTIの16タイプそれぞれの向いている仕事や性格タイプなどを詳しく解説しているので、ぜひ自己分析にお役立てください。
ストレングスファインダー ストレングスファインダーとは、アメリカの世論調査会社「ギャラップ社」が開発した、「自分の強み(才能)」を見つけるための診断ツールです 。ストレングスファインダーは、自分の強みを客観的に理解したり、強みを活かして仕事や人間関係、人生全体をより良くしたりする目的があります。
また、苦手なことを克服するよりも、得意なことを伸ばすことに重きを置いている診断ツールです 。
ストレングスファインダーの特徴としては、177問の質問に答えることで、34の資質(才能)のなかから自分がより得意な上位5つが分かります。たとえば、「達成欲」や「共感性」「戦略性」など。これらの特徴を理解することで、自己理解を深め、自身の強みを活かした行動やキャリア形成に役立てられるでしょう。
エニアグラム 日本エニアグラム学会が提供している「エニアグラム」は、いくつかの質問に答えることで、9つの性格タイプの中から自分の性格を診断できるツールです 。エニアグラムを行うことで、自分の根本的な性格傾向や行動パターン、価値観などを客観的に把握できます 。
自己分析にエニアグラムを取り入れると自分の内面をより深く把握できるので、自分とマッチする仕事や企業を見つけやすくなったり、志望動機や自己PRに説得力を持たせられたりするでしょう。
V-CAP診断 V-CAP診断は、心理学の理論をもとに作られた診断ツールで、自分の適職や職業傾向を分析する際に役立ちます 。「価値(Value)」「コミュニケーション(Communication)」「方法(Approach)」「過程(Process)」の要素からV-CAP診断は成り立っており、これらの要素を診断することで行動特性を16タイプに分類し、診断結果から以下を知ることが可能です。
・どんな価値観や動機で仕事を選ぶ傾向があるか
・向いている業界・職種は何か
・どんな職場環境が合うか
・自分のもつスキルや強みは何か
V-CAP診断を活用して上記が見えてくることで、「自分の強みを仕事にどう活かせるか」を具体的に説明しやすくなる ため、説得力のある自己PRにつなげられるでしょう。
適職診断 適職診断は、自分の性格や強みをもとに職業の適性を調べるツールのことです 。インターネット上で検索すると、無料でできるものや就職・転職サイトが提供するものなど、さまざまな適職診断が見つかるため、自己分析に取り入れやすいでしょう。
適職診断では、自分に向いている職業だけでなく、自分の強みや長所・短所、マッチする働き方や職場環境などが分かるものもあります。これらを把握することで、応募書類の作成や面接での自己アピールに活用できるのでおすすめです。
このコラムにも、いくつかの質問に答えるだけで自分の性格や強み、向いている仕事を無料で簡単に調べられる適職診断をご用意しています。ぜひ自己分析にお役立てください。
7.WILL・CAN・MUSTフレーム 「WILL・CAN・MUSTフレーム」とは、自己分析やキャリア設計に使われる思考整理のフレームワークのことです。WILL・CAN・MUSTフレームでは、自分の理想と現実のギャップや今後伸ばしていきたいスキルなどを明確にできます 。
「WILL(やりたいこと」「CAN(できること)」「MUST(求められること)」の3つの要素を掛け合わせ、「自分にとって本当にやるべきこと=理想のキャリア・目標」を見つけるのが、WILL・CAN・MUSTフレームの使い方です。
要素 意味 キーワードの例 WILL ・自分が心から望んでいること 夢、熱意、価値観、目標 CAN ・自分ができること 経験、能力、強み、成果 MUST ・社会や周囲、組織から求められていること 役割、責任、市場のニーズ
自分にとっての「WILL(やりたいこと」「CAN(できること)」「MUST(求められること)」を順番に考えて、可視化できるように紙に書き出します。最後に書いた内容を見比べて、重なりを探したり、ギャップを見つけたりして、就職・転職活動に活かしましょう。
8.SWOT分析 SWOT分析は、「強み (Strengths)」「弱み (Weaknesses)」「機会 (Opportunities)」「脅威 (Threats)」の4つの観点に沿って物事を整理するフレームワークのことです。自己分析でSWOT分析を活用する際は、「活かせる自分の強みは何か」「克服すべき弱みは何か」「市場での需要や懸念点はあるか」といった流れで自分を深掘りしていきます 。
SWOT分析を活用して自己分析を行い、自分自身の能力(強み・弱み)と転職市場における自分自身の評価(需要・懸念点)を把握することで、就職・転職先の選択がしやすくなったり、効果的な選考対策につながったりする でしょう。
9.ロジックツリー ロジックツリーは、複雑な問題をツリー状に分解して論理的に整理する思考法のことです 。「なぜ〇〇なのか?」といった問題・テーマに対して、根本的な原因や具体的な解決策を探るのに役立ちます 。
たとえば、転職活動の際にロジックツリーを用いて自己分析をする場合、「転職したい」という漠然とした考えから、「なぜ転職したいのか」「現職の何が不満なのか」と繰り返し問いかけていきます。問いに対する答えを明らかにしていくことで「転職の軸」が固まり、仕事や企業選びの基準がはっきりするでしょう。
「○○業界で働きたい」と考えている場合は、「なぜ○○業界がいいのか」「どんな仕事をしたいのか」と問いかけながら理由を明らかにしていくことで、就職・転職の方向性が固まったり、希望している業界以外の選択肢を見つけられたりする可能性も考えられます。
客観的な視点で自分の強みや適職を把握するためは、論理的に自己分析を行うことが大切です。「論理的に考えるのが難しい」と感じる方は、ぜひロジックツリーを活用して自己分析を行ってみてください。
10.STARメソッド STARメソッドは、過去の具体的な経験を分かりやすく説明するためのフレームワークです 。以下の4つの要素に沿って話すことで、説得力のある回答ができます。
STARメソッドの流れ
Situation(状況):どのような状況だったか
Task(課題):その状況でどんな課題や目標があったか
Action(行動):課題の解決や目標達成に向けて、何を考えどんな風に行動したか
Result(結果):行動した結果、どのような成果や学びを得たか
自己分析でSTARメソッドを使うことで、過去の経験から学んだことや身につけたスキルがはっきりする ため、仕事選びや自己アピールの役に立つでしょう。また、「状況」「課題」「行動」「結果」と順序だてて伝えることで、論理的思考力のアピールにもつながります。
11.キャリアアンカー キャリアアンカーとは、仕事において「自分が大切にしていること」を指します 。「専門性を高めたい」「安定した企業で働きたい」「社会に貢献できる仕事をしたい」など、キャリアアンカーは人それぞれ。自己分析でキャリアアンカーについて考え、仕事をするうえで譲れない価値観や欲求などを知ることで、仕事選びや職場選びに活かせます 。
以下は、心理学者エドガー・H・シャインが提唱したキャリアアンカー8つです。
1.特定の分野の専門家としてスキルを極めたい
「どんな仕事がしたいのか」「どんな働き方がいいのか」などがはっきりしていない場合は、上記を参考にしながら自分のキャリアアンカーを探してみてください。
12.他己分析 他己分析は、客観的な視点で自分を把握するために、他者に「自分はどんな人間か」を分析してもらう方法です 。家族や友人、職場の人など、自分を理解してくれている人に他己分析を頼むことで、自分では気づかなかった強みや弱みを見つけられる可能性があります 。自己分析だけでは主観的になりがちですが、他己分析を組み合わせることでより多角的に自分を理解できるため、自分に合う仕事や職場を選びやすくなるでしょう。
就職支援サービスに頼るのも手
ここまで紹介してきた方法で自己分析をしたものの、「うまくできない」「本当にこれであっているだろうか」と不安に思う場合は、就職支援サービスに頼るのも手です。エージェントによっては、自己分析をサポートしてくれる場合があります。スムーズに自己分析を進めたい方は、エージェントの利用を検討してみましょう。
また、ハローワークやエージェントといった就職支援サービスでは、自分の性格やスキル、希望する条件をヒアリングしたうえで求人を紹介してくれるので、仕事や企業とのミスマッチを回避できます。自己分析に自信がなくても自分に合う仕事や企業を見つけやすいのでおすすめです。
自己分析をする際に意識すること 自己分析をする際に意識することとしては、「キャリアプランを立てる際に役立てる」や「自己分析の結果を言語化する」などが挙げられます。以下で、詳しい内容を解説するので、自己分析を行う際の参考にしてみてください。
キャリアプランを立てる際に役立てる 自己分析をするときに意識することの一つに、キャリアプランを立てる際に役立てることが挙げられます。自己分析では、自分の内面と向き合い、「何が得意か」「何を大切にしているのか」「どんな働き方が合っているのか」を明確にできるため、より理想に近いキャリア形成を行うことが可能 でしょう。
また、自己分析を通してキャリアプランを立てておくことで、志望動機や面接の際の説得力も高まる のでおすすめです。長期的なキャリアプランを立てておきたいという方は、ライフプランも同時に考えながら自己分析を行うと効果的でしょう。
自己分析の結果を言語化する 自己分析を行う際は、結果が出て満足するのではなく、分かったことを就職・転職活動で活かせるように言語化しましょう 。自己分析の内容を言語化することで、頭のなかの曖昧な感覚を明確にでき、より説得力のある志望動機や自己PRを作成できます。
具体的な言語化の方法としては、人と話すのが好きな人であれば、「なぜ話すのが好きなのか」「それをどう仕事に活かしたいのか・活かせるのか」を自問自答し、「エピソード・理由・強み」をセットでまとめることが重要です。
自己分析を言語化することで、自分自身への理解が深まるだけでなく、他者に伝える力にもつながるので、面接対策にもなる でしょう。
自己分析をもとに志望動機を作る方法 自己分析を終えたら、分かった結果をもとに志望動機を作りましょう。自己分析をもとに志望動機を作る際は、「自分の価値観や強み」と「企業や職種の特徴」をつなげて一貫性のある理由を伝えることが大切 です。自分と企業や職種との接点を示すことで、「なぜその企業に就職したいのか」が明確に伝わるでしょう。
以下で志望動機の例を紹介するので、参考にしてみてください。
志望動機の例 自己分析で分かった、「相手の立場に立って考えられる力」「粘り強く目標に向かう姿勢」の強みを活かした志望動機例は以下のとおりです。
「私は、貴社の個人のキャリアに寄り添い、長期的な成長を支援する姿勢に魅力を感じ志望しました。私は、人の成長に関わることに大きなやりがいを感じており、それを軸に企業を選んでいます。大学時代は学習塾で講師として働き、生徒一人ひとりの性格や理解度に合わせた指導を工夫するなかで目標達成に向けて伴走する喜びを実感しました。
自分の強みでもある『相手の立場に立って考える力』や『粘り強く目標に向かう姿勢』を活かし、求職者一人ひとりに向き合いながら、より良いキャリア支援を実現したいと考えています。将来的には、個人だけでなく企業側の課題解決にも深く関わり、社会全体の成長に貢献していきたいと思っています」
志望動機の基礎的な作り方に関しては、以下のコラムでも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
1人で自己分析をするのが難しいときの3つの対処法 1人で自己分析をするのが難しいと感じたら、次の方法を試してみましょう。
1人で自己分析をするのが難しいときの対処法
自己分析シートを活用する
他己分析をする
就職のプロに相談する
1.自己分析ツールを活用する 自己分析ツールを活用することもおすすめ です。たとえば、「自己分析シート」を使えば、自己分析を簡単に行えます。自己分析シートは、あらかじめ考えるべき項目が記載されたフォーマットです。次のような問いに対し、一つひとつ空欄を埋めていく形で自己分析を行えます。
・過去の活動内容(エピソード)
・なぜその活動に取り組んだのか
・なぜその活動を続けたのか
・なぜ頑張れたのか
・どのような困難に直面したか
・どのように工夫して解決したか
・なぜその対処法を選んだのか
・その活動で学んだことは何か
自己分析シートによって、内容や方法は異なります。Webサイトからダウンロードできるものも多く存在しているので、自分が取り組みやすそうなシートを探してみてください。
2.他己分析をする 「自分で自己分析をするのが難しい」という人は、家族や知人に「他己分析」を頼んでみましょう 。あらかじめ質問シートを用意し、「家族」や「友人」「先輩」など身近な人に他己分析を頼むことで、自分では気づけなかった強みや弱みなどを知れる可能性があります。
・私の第一印象は?
・私の長所とその理由は?
・印象に残っているエピソードは?
・私の性格はどう思う?
・尊敬できる点はどんなところ?
・どんな仕事が向いていると思う?
・将来どんな人になると思う?
質問するときは、答えだけでなく理由も詳しく述べてもらうと、より深く知れるためおすすめです。自分では気づいていない新たな一面を知るきっかけになることもあるでしょう。
3.就職・転職エージェントに相談する 「自己分析をやってみたけどこれで良いか不安」という人は、プロに相談してみるのがおすすめです 。新卒なら大学のキャリアセンターや就職支援サービスへ相談したり、自己分析に特化した就活セミナーへ参加したりすれば、プロの意見を聞くことが可能です。
既卒や転職者の場合は、民間の就職・転職支援サービスのアドバイザーへ相談してみましょう。
就職・転職支援サービスでは求人紹介や求職相談がメインですが、サービスの一環として、自己分析のアドバイスをしてくれることもあります。
多くの求職者を見たアドバイザーならではのノウハウを教えてもらえる可能性があるため、利用してみるのもおすすめです。
【まとめ】自己分析は就職・転職を成功させる鍵! 就職・転職を成功させるためには、自分の強みや弱み、保有スキル、キャリアビジョンなどをはっきりとさせたうえで、仕事や企業を選ぶ必要があります。自分自身への理解を深めるためには、自己分析を入念に行うことが大切です。このコラムで紹介した方法を参考に自己分析を行い、就職・転職成功を目指しましょう。
「自己分析でつまずいてしまった」「自分に合う仕事や企業を見つけてほしい」という方は、
就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、若年層の求職活動を無料でサポートします。
経験豊富なキャリアアドバイザーが、自己分析のやり方や就職・転職に関する悩みにプロの視点でアドバイス。「こんなところは強みになる?」などのちょっとしたお悩みにも丁寧に回答いたします。就職・転職をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
自己分析のに関するQ&A 最後に、自己分析を行うメリットに関して抱かれがちな疑問や質問にお答えします。「自己分析のメリットが分からないためいまいちやる気が起きない」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
自己分析とは簡単にいうと、自分自身を客観視して「自分はどんな人間か」を知ることです。具体的には、自分自身の過去の経験や出来事を振り返り、自分の特徴や行動傾向、価値観などを整理することをいいます。
自己分析は自分の強みや弱みを理解し、就職・転職活動を有利に進めるために行います。自己分析をすることで自分自身を客観的に理解でき、面接や書類選考を有利に進められるでしょう。
社会人が自己分析を行うことで、キャリアプランが明確になります。新卒者が就活時に行う自己分析と比べて、社会人が行う自己分析では働いた経験がプラスされます。
自己分析のやり方が分からない方は、一人で悩まず就職や転職のプロに相談するのも一つの手です。相談することで、自己分析のサポートをしてもらえたり、客観的な意見をもらえるでしょう。一人での就職活動や転職活動に不安がある方は、就職・転職エージェントのハタラクティブ にご相談ください。
自己分析のやり方12選!就活での必要性や志望動機に活かす方法もご紹介!