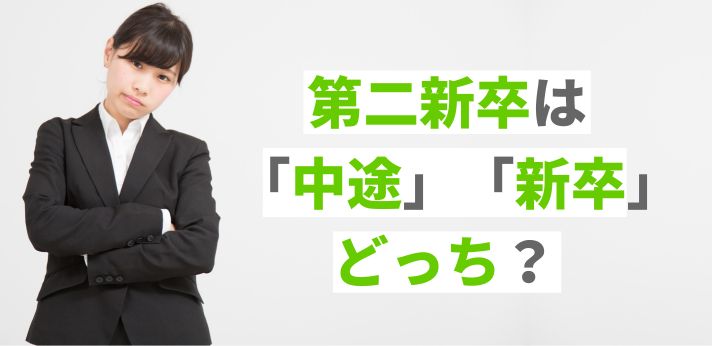院卒が第二新卒で転職できるのはいつまで?タイミングや成功のコツを解説院卒が第二新卒で転職できるのはいつまで?タイミングや成功のコツを解説
更新日
公開日
大学院卒も、退職時が卒業から3年以内なら第二新卒として扱ってもらえる
大学院卒は「第二新卒」として転職できるのか知りたい方もいるでしょう。なかには、新卒で入社したものの、「思っていたのと違った」などの理由から転職を考えている方も。結論からいうと、大学院を卒業して3年以内であれば第二新卒扱いとなるのが一般的です。
このコラムでは、大学院卒が第二新卒として転職活動する際のタイミングや、経歴を活かせるアピール方法などを解説します。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
大学院卒は「第二新卒」として扱ってもらえる?
結論からいうと、大学院卒も新卒として入社した企業を離職したときに卒業してから3年以内なら、一般的に第二新卒として扱われます。新卒後に入社した企業での在籍期間が短く、社会人としての経験やスキル面で自信がない場合は、若さやポテンシャルが評価される「第二新卒」枠での転職がおすすめです。
しかし、希望する企業が提示する条件を満たしているなら、第二新卒にこだわらず即戦力を重視した「中途採用」枠として転職活動するほうが良いことも。
大学院卒が第二新卒枠で転職を成功させるためには、自分の市場価値をしっかり理解したうえで転職活動を進めましょう。第二新卒については、「『新卒』に高卒も含まれる?採用ルールや年収における大卒との違いを解説!」でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
第二新卒の定義
第二新卒とは、「学校を卒業後、正社員として就職してから数年以内に退職した者」を指します。一般的には3年以内とされているため、「大学院卒から3年以内の求職者」も第二新卒となるでしょう。
しかし、この定義は確定しておらず、企業ごとに認識が異なるケースもあるため、企業によっては卒業後3年以内でも第二新卒に含まれない可能性があります。
大学院卒から就職した場合の年齢は?
現役で大学に進学し、留年や休学することなく大学を卒業・就職をする場合の年齢は22歳。修士課程を修了すると24歳、博士課程だと27歳です。休学期間がある場合や博士課程を継続した場合は、同じ年数分、入社時の年齢に追加されます。
先述した「大学院卒から3年以内の求職者」を第二新卒とする場合、一般的に大学院卒で第二新卒が適応される年齢は、およそ27~30歳と認識しておくと良いでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
大学院卒が「第二新卒」として転職する有利点
社会人経験が少ない第二新卒は「企業の色」に染まっておらず、柔軟な対応が期待できます。また、正社員として勤務した経験があるので、基本的なビジネスマナーやスキルが身についている点に魅力を感じている企業もあるようです。
卒就職活動時の企業選びの失敗理由は納得してもらいやすい
大学院卒で就職活動した方は、卒論や研究の時間を確保するために、学部生のように多数のインターンシップに参加し、長い時間をかけて幅広い業界研修やOB訪問をすることなく就職活動を終えた方が少なくありません。理系の場合、研究室経由での推薦という選択肢もあり「一社だけ受けてそこで内定が出て就活が終わった」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
第二新卒でも経験者採用でも、面接では「なぜ転職をしようと考えるようになったのですか」という質問はつきものです。しかし、上記のような長年の「慣習」できちんと企業選びに取り組むきっかけがないまま、本当にやりたいことは何か実際に就職してからでないと気がつけなかった、という失敗理由は共感してもらいやすいといえます。
第二新卒であれば、中途採用ではなかなか求人を見つけるのが難しい大手企業の研究職への応募にもトライできます。あらためて「自分の知識を活かして本当に貢献したいこと」についてよく検討してみましょう。
基本的なビジネススキルをアピールできる
院卒者が第二新卒として転職する有利点の一つは、基本的なビジネススキルがあることです。すでに会社勤務経験があるため、メールの送り方や電話の取り方など業務に必要なスキルは身についているでしょう。企業は教育するコストを削減できるため、メリットと捉えられることがあります。
将来性を評価される
働く熱意や伸びしろを評価してもらえる「ポテンシャル採用」にも期待できるでしょう。特に人材不足といわれている企業では、入社後の育成にも注力しているため、未経験の業界や職種に応募しても採用される可能性があります。
柔軟性が高い
院卒者が第二新卒として転職する有利点の二つ目は、柔軟性が高いところです。社会人経験が長い中途採用の場合、今までの社会経験から形成された価値観を持っていることが多く、企業理念や方針の切り替えに時間がかかる場合があります。
しかし、第二新卒は社会経験が短いため、自社の企業理念や社風などを受け入れやすい傾向があるようです。自社に合った価値観の人材になる期待感は大きいでしょう。
企業の採用タイミングに合わせられる
企業の採用タイミングに合わせられる点も、第二新卒の有利点として挙げられます。
新卒の場合、会社が人材を確保したいタイミングがあっても教育機関で決められている日程があるため、希望のタイミングでの人材確保ができません。
しかし、第二新卒の場合は転職となるので企業のタイミングで採用することが可能です。また採用までの期間も早いため、スムーズに人材を確保できるでしょう。近年では第二新卒の求人を出す企業も増えているようです。
ミスマッチを起こしにくい
会社とのミスマッチが起こりにくいのも第二新卒の利点です。
第二新卒は新卒入社した企業でミスマッチを経験しているため、転職先ではミスマッチが起こらないよう慎重に転職先を選ぶ傾向にあります。そのため、企業側は退職するリスクが比較的低いことから安心して採用できます。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
大学院卒の第二新卒が転職で不利だと感じる4つの理由
大学院卒の第二新卒は、その経験や知識によって「扱いづらい」と判断されてしまい、転職が不利になることもあるようです。ここでは、主な理由について4つ解説します。
第二新卒の大学院卒が転職活動で不利になりやすい理由と回避策
大学院卒の方が第二新卒として転職を考える場合、いくつかのデメリットが生じる場合があります。
まず、多くの企業では新卒採用と中途採用を明確に分けています。第二新卒は「中途採用」として扱われることが多く、応募可能な業界や職種の選択肢が新卒採用と比べて狭まる場合があります。
また、大学院卒という学歴は一般的に高学歴です。企業や採用担当者によっては「当社に活躍できる場があるのか」「給与やキャリアアップに対する期待が高すぎるのでは」と、ネガティブなイメージを抱く場合もあります。
大学院での専門的な研究経験が、応募先企業の業種や職種と結びつきがない場合は、第二新卒のなかでは年齢が高いため採用のハードルが高くなることも考えられるでしょう。
短期間で転職する際には「忍耐力がない」「キャリアの方向性が定まっていない」とイメージを持たれないように、自身の強みをどう活かせるかを明確に伝える準備がポイントです。
1.年齢を重ねると扱いづらいと思われてしまう
企業側からみると第二新卒は人材育成がしやすいといった魅力がありますが、院卒者は学部卒より年齢を重ねているぶん、やや厳しい見方をされることもあるようです。
年齢を重ねると、これまでの経験から偏った見方をしたり、やり慣れた方法を使ったりしてしまうことがあります。また、年齢の割に社会経験が乏しく、「扱いづらい」と判断される可能性もあるでしょう。
2.専門性のある知識がマイナスに捉えられることがある
大学院卒は、専門性の高い知識がある一方で、「柔軟性がない」「自尊心が強い」「協調性がない」といったマイナスの印象をもたれていることがあるようです。
この場合、大学院卒という学歴は関係なく、個々の性格が影響している可能性があります。しかし、企業側や採用担当者によっては、このように誤解される可能性があることも理解しておく必要があるでしょう。
3.中途採用者との年齢が近い
大学院卒の第二新卒は、即戦力としての活躍が期待される中途採用者と年齢が近くなりがちです。中途採用者と院卒第二新卒の求職者とを天秤にかけた際、院卒第二新卒者を教育して戦力として独り立ちさせるまでの時間とコストを危惧して、大学院卒の第二新卒の採用を躊躇する企業もあるでしょう。入社後に活躍できるイメージを持ってもらえるように、大学院卒ならではの強みやスキルをしっかりとアピールすることが大切です。
4.大学院卒に対する企業側の期待値が高い
前項では、「大学院卒がマイナスに捉えられる」と解説しましたが、大学院卒だからこそ「的確に仕事がこなせる」「何事も完璧に対応できる」といった期待を抱く企業も存在します。
大学院卒の第二新卒として期待値を高くもたれてしまったことで、実際に面接をすると「想像していた人と違った」と思われる恐れも。印象だけで判断されないよう、面接で伝えるべきことは具体的に話すようにしましょう。
大学院卒が第二新卒として転職するきっかけ
大学院卒が第二新卒として転職しようとする際、「職場でスキルが活かせない」「同期入社の大学卒と給与などの待遇が同等」などが理由でしょう。
大学院卒業後、転職を検討するきっかけとして、よくあるパターンを紹介します。
スキルが活かせない場合
大学院で培ったスキルが活かせないと感じることが、転職を検討するきっかけとなることがあります。大学院で培った専門知識やスキルを活かせる職場を求め、よりやりがいのある仕事に挑戦したいと考えるのは自然なことかもしれません。
同期入社の大学卒と給与などの待遇が同等の場合
同期入社の大学卒と給与といった待遇が変わらない場合も、転職を検討する理由の一つとして挙げられます。大学院での専門的な学びを踏まえ、自身の貢献度に見合った評価や待遇を求めて転職を検討するようです。
大学院卒が第二新卒で転職活動をする際に注意したいこと
一般的な学卒より年齢が高い第二新卒は、失敗した際のリスクが高くなるため、転職活動をする際に注意することがあります。下記の注意点を意識して転職活動を行いましょう。
大学院卒が第二新卒として転職する際の注意点を教えてください
修士での専門性から異業種・異職種に方向転換する場合は理由や考えをしっかり述べよう
「新卒の時の就活では、毎年OBが入社している会社に研究職として入社した。実は、学生時代から本当に研究に取り組み続けることが自分に向いているのだろうかと悩むことがあった。実際に研究室での専門分野に近いラボで毎日を過ごしてみたら、自分にやりたいことはやっぱりこれではないと思った」
上記の先輩のように、残念ながら新卒で入った会社の仕事に対して「得意だけれども、やりたいことではなかった」と感じてしまう大学院卒生の方もいらっしゃいます。このような専門性の高いキャリアステップを歩んできた方が異業種・異職種に第二新卒としてチャレンジする場合、面接官に「こんなにしっかりした経歴なのに、ウチに来たらもったいない」と思われてしまう場合もあるでしょう。
面接官の懸念を払拭するには、なぜ異業種・異職種にチャレンジしようと思ったのか、キャリアがリセットされることについてはどのように考えているか、書類選考の段階から自由記入欄や志望動機などを通じてしっかり記載するのがおすすめです。エージェントを利用するなら、担当者にも伝えておきましょう。
就職先によって院卒者の人材が少ない可能性がある
在籍している社員のなかに院卒者が少ない企業は、院卒者に対し大きな期待を寄せているケースがあります。
期待に応えられなかった場合、院卒としての経験や知識が正当に評価されず、ストレスから転職のミスマッチにつながる恐れも。このようなことが起こらないために、企業に院卒者が多く在籍しているか事前に確認しておきましょう。
研究内容が活かせる就職先を求め過ぎない
大学院での研究内容を活かすことを求めて転職活動するのは、あまり賢明ではありません。
理由として、研究内容と関連のある就職先は研究職や専門職に限られてしまい、うまく転職できない可能性が高くなるためです。
大切なのは汎用性の高いスキルを活かすこと
院卒の場合、専門的な研究に深く関わってきた経験を持っています。しかし、企業で研究内容をそのまま活かせる仕事は、必ずしも多くはありません。
大切なのは、研究を通して身に付けた「論理的な思考力」や「問題解決能力」といったスキルです。これらのスキルは、研究分野だけでなく、さまざまな職種で活かすことができます。転職活動では、研究内容そのものよりも、これらのスキルをどのように活かしたいのかを明確にすることが大切です。
大学院卒が第二新卒で転職活動を成功させる5つのポイント
大学院卒が第二新卒で転職活動をする場合、3年未満で現職を退職することになるため、企業へマイナスの印象を与えてしまうことも少なくありません。第一印象のみで失敗しないためにも、転職活動を成功させるためのポイントを5つまとめました。
大学院卒が第二新卒として転職する際に成功させるポイントを教えてください
研究で得たスキルをビジネスに応用できることを伝えよう
第二新卒の大学院卒の人が転職を成功させるには、「専門性」と「ポータブルスキル」を明確に伝えることがポイントです。大学院で培った研究経験や専門知識を、企業の課題解決にどのように活かせるのか具体的に示しましょう。
研究活動で養った論理的思考力、問題解決力、プロジェクトマネジメント、プレゼンテーション能力など、ビジネスの現場で応用可能なスキルを強調することが大切です。
また、第二新卒は「ポテンシャル採用」として見られるため、転職理由とキャリアの一貫性を意識しましょう。前職を短期間で離れる理由はポジティブに伝えることを意識し、次の職場でどのような価値を提供できるのかを明確に説明すると採用担当者に好印象を与えられます。大学院卒は「研究職向き」と見なされがちなので、ビジネス環境への適応力やチームでの協働経験をアピールするのがポイントです。
転職を検討する際には、応募企業や業界の選定を慎重に行い、自身のスキルや研究内容と関連性がある職種を選ぶと転職の成功率が高まります。コンサルティング、データ分析、R&D、ITエンジニアといった職種は、大学院での経験を活かしやすい分野です。
可能ならばOB・OG訪問や転職エージェントを活用し、企業が求めるスキルや適性を把握しながら、万全な面接対策を行うこともポイントといえます。
1.大学院で得た実績とスキルをアピールする
就活を成功させるには、大学院卒には学部卒とは違う強みがあることを企業側に知ってもらう必要があります。具体的にどのようなことをアピールできるのか下記の説明を参考にしてみてください。
目標を達成する「実現能力」がある
大学院を修了したということは、高い目標があり、それに向かっていける「勤勉さ」や目標を達成できる「実現能力」があるということ。今後も学び続けていく意欲があることをアピールできれば、「成長する見込みがある人物」と評価される可能性が高いでしょう。
専門的なスキルがある
大学院卒として、研究時に用いたやり方や考え方などをスキルとしてアピールしましょう。
大学院での研究は、「さまざまな意見を取り入れ、新たな可能性にチャレンジしてきた」「1つの事象について理解を深めてきた」という、仕事に十分活かせる能力を培ってきたといえます。仕事にひたむきに向き合い、効率や生産性を意識しながら取り組める能力があることを、自信をもってアピールしていきましょう。
文系院卒の場合は、語学力のアピールがおすすめです。特に学会で英語による研究発表を行った経験がある場合は大きな経験値となります。応募先企業が外資系といった英語を使う仕事なら、十分なアピール要素として活かせるでしょう。
理系院卒では、あらゆる実験やデータ解析などの経験から、論理的な考え方や分析するスキルなどをアピールできるでしょう。もし応募先企業が研究職なら、大学院時代の研究結果や論文なども提示すると、より高評価に期待できます。
2.大学院卒をプラスに捉える
「第二新卒であるかどうか」や、正社員経験を気にするより、自身のやってきたことに誇りをもちましょう。大学院卒はどうしても学部新卒に比べて年齢による差が生まれてしまうもの。しかし、多角的な視点からのアプローチができたり、1つのことに対してひたむきに取り組めたりなど、年齢差を補うほどの力があるはずです。
3.第二新卒として転職する理由を明確にする
面接時には、明確な転職理由を伝えましょう。第二新卒として転職する人のなかには、採用担当者から「なぜ退職したのか」と質問されます。退職理由は、企業側にとっても自社とのミスマッチを防ぐポイントになるため、慎重な回答が必要です。
4.社会人経験があることをアピールする
前職での社会人経験をアピールしましょう。第二新卒の強みは、社会人として働いた経験があることです。そのため、企業側からも「基本的なビジネスマナーが備わっている人」と認識されています。
これまでの経験を伝えるためにも、丁寧な自己分析を行っておくのがおすすめ。具体的にどのようなことを経験してきたのか、何を仕事に活かせるのかが伝われば、採用担当者への好印象にもつながります。
5.転職エージェントを利用する
大学院卒から第二新卒として転職を考えているなら、転職エージェントを利用するのもおすすめです。就活市場を把握しているキャリアアドバイザーが、利用者とカウンセリングを通じて一人ひとりに合った求人を紹介します。数ある転職エージェントのなかでも、第二新卒向けのエージェントを利用することで、転職活動がスムーズに進められるでしょう。
転職エージェントは、あなたの強みやキャリアを客観的に評価し、最適な仕事を一緒に見つけてくれます。また、転職エージェントのなかには、業界や職種に特化した専門的な知識を持っているところもあり、より自分に合った仕事を見つけられるでしょう。まずは、自分に合った転職エージェントを探し、相談してみることをおすすめします。
「大学院卒から転職したい」「第二新卒からの就活方法が分からない…」とお悩みの方は、ぜひハタラクティブをご利用ください!
若年層向け転職エージェントのハタラクティブでは、大学院卒で第二新卒の方へのアドバイスも行っています。専任のキャリアアドバイザーによる丁寧なカウンセリングによって、希望に合った募集求人をご紹介。非公開の求人も取り扱っており、ほかの求職者がアクセスできない転職情報を得られるのもメリットです。
書類添削や面接対策も行っていますので、安心して転職活動ができます。サービスの登録・利用料はすべて無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
こんなときどうする?大学院卒業後の転職に関するQ&A
大学院卒業後すぐに退職した人は、第二新卒としての転職に悩むこともあるでしょう。ここでは、想定される大学院卒業後の転職に関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。
大学院卒だからといって転職が不利になるということはありません。
ただし、早期離職を繰り返している場合や30代を過ぎて未経験業界へチャレンジする場合などは、転職活動に一定の難しさを感じるでしょう。また、入社してすぐの転職は、新卒時の就職活動を振り返っておくのがおすすめです。
大学院卒の就活の特徴については、「院卒は就職で不利になる?院卒の就職事情や就活のポイントを解説」をご覧ください。
大学院卒業後に就職し、数ヶ月程度で仕事を辞めた場合は「第二新卒」として転職活動をする可能性が高くなるでしょう。ただし、志望企業が提示する条件を満たしているのなら、「中途採用」枠で転職活動をしたほうが成功しやすいこともあります。
大学院卒が第二新卒として適用されるかどうかについては、「大学院卒は「第二新卒」として扱ってもらえる?」を参考にしてみてください。
第二新卒に明確な基準はありませんが、一般的には「新卒入社後3年以内」なので、大卒ならおよそ25歳前後の人を指します。
企業によっては学歴を問わず29歳を上限にするところもあるようです。また、第二新卒である条件に当てはまっていたとしても、一度でも転職経験がある方は第二新卒に該当しないのが一般的。第二新卒についての詳しい解説は、「第二新卒歓迎とは?企業が若手を求める理由と転職でアピールするポイント」でもご覧いただけます。
大学院卒の方が転職を成功させるには、できるだけ年齢が若いうちに行動することが大切です。
20代のうちは、若さと柔軟な思考が評価されやすく、新しいことに挑戦しやすい環境が得られることもあるでしょう。しかし、年齢を重ねるにつれ、新卒や若手との競争が激しくなり、転職が難しくなる可能性もあります。なるべく早く転職活動を始めることで、自分に合う仕事を見つけられるでしょう。
ハタラクティブでは、大学院卒の方の転職活動を経験豊富なキャリアアドバイザーが全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。