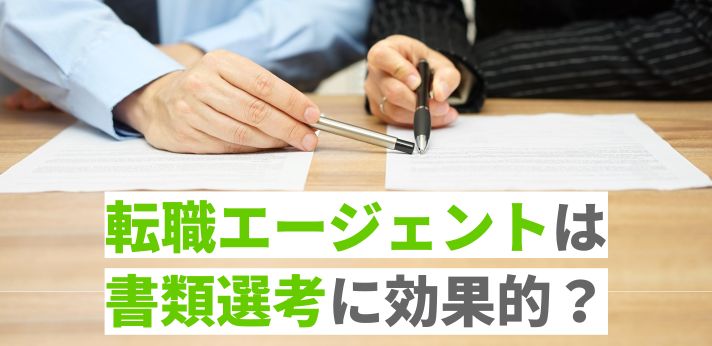転職に必要な手続きとは?住民税・健康保険・雇用保険などやることリスト転職に必要な手続きとは?住民税・健康保険・雇用保険などやることリスト
更新日
公開日
転職が決まったあと、どんな手続きをすべきか分からない方もいるでしょう。退職までは、今の会社に退職の意思を伝えたり、返却物や必要書類などを提出したりと、いくつかの手続きを踏むのが一般的です。なお、再就職までに期間が空く場合は、住民税・健康保険・雇用保険などの切り替えの手続きを行います。
このコラムでは、転職時に必要な手続きや退職までのステップ、会社への返却物などをまとめました。スムーズに転職するためにも、必要な手続きについて事前に知っておきましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
退職から転職までの一般的なステップ
ここでは、退職から転職までを一般的にどのように進めるべきか解説します。退職の意思は早めに伝える・退職届を提出するなど押さえておきたいことがあるため、これから退職をする方はぜひ参考にしてください。
退職から転職までの一般的なステップ
- 1~2ヵ月前:退職の意思を伝える
- 1ヵ月前:退職願を提出する・業務の引き継ぎを行う
- 2週間前:退職届を提出する
- 退職当日:必要書類を受け取る・社内外へのあいさつをする
1~2ヵ月前:退職の意思を伝える
。「辞めるなんて言いづらい…」と感じる方もいるかもしれませんが、前もってきちんと相談をしておかないと、今後も会社にいる前提で仕事を振られてしまう可能性があります。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
退職する1~2ヵ月前に、退職の意思を直属の上司に伝えます
人員補充の時間的余裕がなくなったり、退職希望日を超えて取り組み続けないといけないプロジェクトに参加することになったりして会社側に迷惑を掛けないためにも、退職の意思は早めに伝えましょう。
1ヵ月前:退職願を提出する・業務の引き継ぎを行う
退職意思を上司に伝え、退職予定日が決まったら、「退職願」を提出します。「退職願」と似た言葉の「退職届」は退職日が完全に確定してから出す書類なので、間違えないように気を付けてください。
会社によっては退職願の提出が不要な場合もあります。提出が必要かどうかは就業規則で確認しましょう。
しかし、退職願は「退職すると言った・言わない」というトラブルを防ぐことにもつながるため、念のため提出しておくのが安心です。
退職願が受理された後、業務の引き継ぎを行います。最終出社日から逆算して、後任者の状況を考慮しながら、引き継ぎのスケジュールを作成しましょう。
業務の引き継ぎについては、「退職時の引き継ぎのポイント」で解説しています。詳しく知りたい方は併せてご覧ください。
2週間前まで:退職届を提出する
退職日の2週間前には退職届を提出しましょう。「民法第627条」では、期間に定めのない場合、退職届は2週間前に出せば問題ないと定められているからです。
しかし、多くの会社では就業規則で「退職の際は1~2ヵ月前までには退職届を提出すること」と定められており、業務の引き継ぎも含め、退職までには一定の期間が必要です。就業規則を踏まえたうえで、退職日から必要な期間を逆算し、いつまでに退職の意思を伝えるかを決めておくとスムーズに手続きが行えるでしょう。
退職当日:必要書類を受け取る・社内外へのあいさつをする
退職当日は、会社の備品を返却したり、転職先に提出すべき書類を受け取ったりします。詳しくはこれから解説していきます。
また、社内外の関係者へのあいさつもしましょう。午前中や休憩後すぐなどの比較的忙しい時間帯を避けるため、退勤時間の2~3時間前からまわるのがおすすめです。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職するときに会社に返すもの・受け取るもの
退職をするときは、会社に返すもの・受け取るものがいくつかあります。あらためて会社に連絡したり返却しに行ったりする手間を防ぐためにも、内容をきちんと確認しておきましょう。
| 会社に返すもの | 会社から受け取るもの |
|---|
・名刺
・社員証
・カードキー
・通勤定期券(または定期代の残額)
・健康保険証
・書類データやPCなどの会社の備品 | ・離職票
・源泉徴収票
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・雇用保険被保険者証 |
|---|
会社に返すもの
1.名刺
会社で作った名刺は返却します。会社によっては、取引先などから受け取った名刺を返却する場合もあるようです。
2.社員証
社員証はその会社の社員であることを証明するものなので、退職時には必ず返しましょう。
3.通勤定期券
電車やバスなどの通勤定期券を支給されている場合は、返却します。
4.健康保険証
退職時はこれまで加入していた健康保険組合を抜けるため、健康保険証の返却が求められます。ただし、マイナンバーカードを保険証として利用している場合は、保険の切り替え手続きは必要であるもののカード自体は退職後も使用できるため、返却する必要はありません。
5.書類データや会社の備品など
業務内で作成した資料や顧客リストも自分の手元に残らないようにします。また、会社のパソコンやタブレット、スマホなどの備品も忘れずに返しましょう。
会社から受け取るもの
1.離職票
離職票は前の会社を離職した証明になるため、転職先で提出を求められる場合があります。再就職まで期間が空く場合は、雇用保険の受給手続きの際にも必要になります。
2.源泉徴収票
源泉徴収票には、会社から支払われた1年間分の総支給額(給与や賞与など)、所得税額、社会保険料の控除額などが記載されています。転職先の会社で年末調整を行ってもらうためには、源泉徴収票が必要です。
3.年金手帳または基礎年金番号通知書
年金手帳または基礎年金番号通知書は、厚生年金の加入手続きの際に必要になります。ただし、基礎年金番号もしくはマイナンバーが分かれば手続きができるため、年金手帳や基礎年金番号通知書の提出を不要とする会社もあるようです。
4.雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類です。退職時は雇用保険被保険者証を忘れずに受け取り、転職先の会社に提出しましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
転職先に提出する書類
退職するときに会社に返すもの・受け取るものを把握できたら、次は転職先の入社手続きに必要な書類をチェックしましょう。
入社承諾書や内定誓約書のほか、先述した雇用保険被保険者証や源泉徴収票、年金手帳は基本的に提出が求められます。また、税金や社会保険の手続きなどに扶養控除等申告書が必要になるので、必要事項を記入して提出します。
会社によっては健康診断書の提出を求める場合もあるため、その際は指定された病院で健康診断を受けましょう。ほかには、大学の卒業証明書や保有している資格・免許の証明書などが求められるケースもあるようです。
| 多くの会社で提出する書類 | 場合によっては提出を求められる書類 |
|---|
・年金手帳
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・扶養控除等申告書
・健康保険被扶養者異動届
・給与振込届出書 | ・健康診断書
・身元保証書
・住民票記載事項証明書
・入社誓約書(入社承諾書) |
|---|
多くの会社で提出する書類
1.年金手帳
日本年金機構が運営する公的年金制度の加入者一人ひとりに交付される手帳のことです。
2.雇用保険被保険者証
会社を辞める際に雇用保険被保険者証を受け取り、転職先の会社で忘れずに提出しましょう。
3.源泉徴収票
源泉徴収票も雇用保険被保険者証と同様に会社を辞める際に受け取り、転職先の会社に提出します。
4.扶養控除等申告書
扶養控除等申告書は、扶養している家族の有無を会社に申告する書類で、個人の事情に合わせて税金の軽減を受けるために必要です。会社から給与をもらっている場合は提出する義務があるので、たとえ扶養家族がいなくても「いない」という旨を記入して提出する必要があります。
転職先の会社から申告書を渡されるので、記入して提出しましょう。
5.健康保険被扶養者異動届
健康保険の被保険者の家族(被扶養者)に変更があった際は、転職先の会社に健康保険被扶養者異動届を提出します。ただし、扶養家族がいない場合は提出不要です。
6.給与振込届出書
給与振込届出書は、給与の振込みに使う口座を届け出るための書類です。転職先の会社で専用の用紙を渡されるので、記入・捺印して提出しましょう。
場合によっては提出を求められる書類
1.健康診断書
会社が指定する医療機関の健康診断を受け、健康診断書を提出することを義務付けている会社もあります。
2.身元保証書
身元保証書とは、従業員が会社に損害を与えた場合に、従業員本人だけでなく身元保証人も連帯して賠償責任を負うことを契約する書類です。提出が義務付けられているわけではありませんが、会社によっては提出が必要になります。
3.住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書とは、住民票の記載事項のうち、記載してほしいと要望のあった事項のみを記載して証明する書類です。
提出を求められた場合は、住んでいる市区町村の役所で発行してもらいましょう。自治体によってはコンビニエンスストアで発行できる場合もあります。
4.入社誓約書(入社承諾書)
入社誓約書(入社承諾書)は、会社が定めるルールや規則を遵守することを誓約するための書類です。渡された場合は、内容をよく確認したうえで記入・捺印をして提出します。
【退職後の手続き】やることリスト
離職後に転職活動をする場合や、再就職まで期間が空く場合は、国民年金や健康保険、雇用保険などの手続きを行う必要があります。ここでは、退職後にやるべき手続きについてまとめました。
【退職後の手続き】やることリスト
- 国民年金の切り替え
- 国民健康保険の切り替え
- 雇用保険の基本手当の受け取り
- 住民税の支払い
1.国民年金への切り替え
在職中は会社で厚生年金に加入していますが、離職後は自分で国民年金に加入し直す必要があります。失業時には、納付免除や猶予が受けられる可能性があるため、収入が少ない場合も必ず相談に行きましょう。
手続き期間:離職後14日以内
手続き場所:お住まいの市町村の役所
2.国民健康保険への切り替え
国民健康保険も、国民年金と同様に自分で加入し直す必要があります。国民健康保険は、これまでに加入していた保険の任意継続という選択肢もあるので、どちらが良いかを確認して早めに手続きを行いましょう。
ただし、マイナンバーカードの健康保険証等利用登録が完了している場合は、退職や転職などの変更に伴う再登録は必要ありません。
手続き期間:離職後14日以内
手続き場所:お住まいの市町村の役所
3.雇用保険の基本手当の受け取り
一般的に「失業保険」と呼ばれるのは、雇用保険の基本手当のことを指します。自動的に受給できるわけではなく、ハローワークでの手続きが必要です。
- ・離職日からさかのぼって2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入している
- ・働く意思と能力があり、求職活動を行っている
ただし例外もあるため、まずはハローワークに相談してみましょう。
手続き期間:定めなし(ただし、受給期間は原則1年間なので早めに手続きを行う)
手続き場所:お住まいの住所を管轄するハローワーク
4.住民税の支払い
住民税の支払い手続きは、退職した月によって変わります。
6~12月に退職した場合は退職月分までの住民税が給与から天引きされ、その後は徴収票に従って自分で納付。
一方、1~5月に退職した場合は、最終月に5月までの住民税を一度に天引きされます。たとえば3月に退職した場合は、3月分の給与から3~5月分の住民税が天引きされるということです。
手続き期間:納付書に定められた期間まで
手続き場所:お住まいの市町村の役所
転職の手続きに関するまとめ
退職をする際は、会社のルールに則って上司へ報告をしたり退職届を提出したりして、気持ち良く転職先に移れるようにしましょう。次の仕事に就くまで期間が空く場合は、住民税・健康保険・雇用保険などの手続きをしっかりと行ってください。
転職時にはやるべき手続きが多くあります。なかには、初めてのことで不安を抱える方もいるのではないでしょうか。
退職後の手続きで忙しく、転職の準備まで手が回らないという方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが、就職・転職に関するあらゆる相談に応じています。面接の日程調整や入社日の相談など、企業とのやりとりはハタラクティブがすべて代行。転職先が決まったあともフォローを行うので、転職に不安を抱えている方はぜひお問い合わせください。