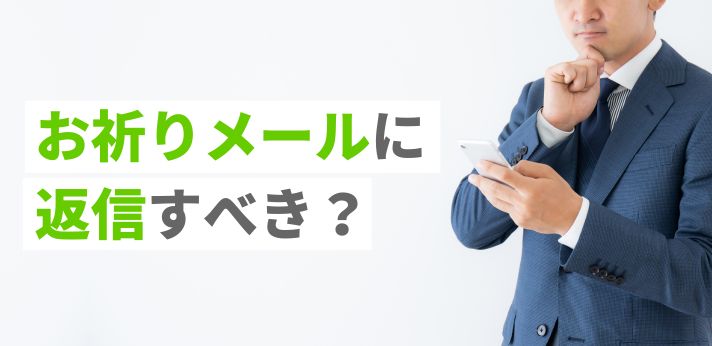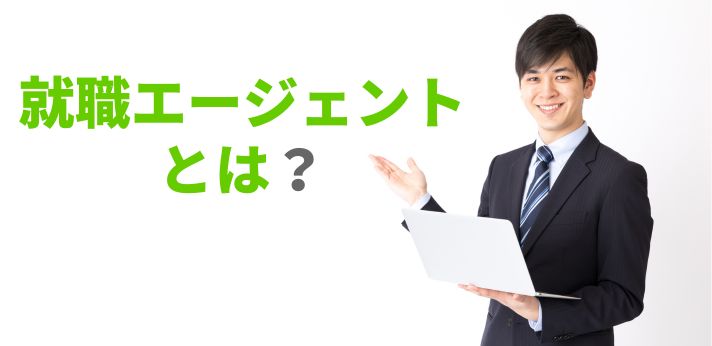離職率とは?高い会社に特徴はある?計算方法や業界別の調べ方を解説
更新日
公開日
離職率とは、ある期間において離職した社員の割合を示すもの
「離職率は何を指しているの?」「計算方法は?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。離職率とは一定期間に離職した割合を示す数値のことで、就職・転職活動の際に確認しておきたい項目の一つです。このコラムでは、離職率の計算方法や調べ方、業界や新卒など条件別での離職率をご紹介します。また、離職率が高い企業に見られる特徴もまとめました。離職率について正しく理解し、企業研究や業界研究に活用しましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
離職率とは
離職率とは、ある期間において離職した従業員の割合を示すものです。一般的に年初の従業員数を分母とし、当年内に離職した従業員数を分子として算出されます。期間の設定はデータの目的によって自由に決められるため、「新卒入社の人が3年以内に退職する割合」や「中途採用の人が1年以内に辞める割合」などが求められる場合もあるでしょう。
離職率と退職率の違い
離職率は自己都合や会社都合などの理由を問わず、会社を辞めた従業員の割合を示すものです。一方、退職率とは自己都合や定年退職といった理由で、労働契約を解消した従業員を分子として求めます。会社都合退職は含まれません。
離職率と退職率は、求める理由や知りたいデータによって使い分けることが可能です。たとえば、離職率はどのような理由も数値に含まれるため、「辞めた人の数」を確認するのに活用します。また、退職率は企業が今後の退職者数をシミュレーションするために求める場合があるでしょう。
離職率と定着率の違い
離職率と対になる指標が定着率です。定着率は「一定期間会社に勤め続けている従業員の割合」を指しており、高いほど離職者数は少ないといえます。離職率と定着率は、それぞれ「離職者数」「勤続者数」を「一定期間の在籍者数」で割って算出するものです。そのため、2つの指標の割合を足すと100%になります。
離職率を把握することは就職や転職にどう活用できる?
離職率は就職・転職活動で応募企業を検討する際に活用できる可能性があります。離職率を調べることで、その会社内での人材の流動性が分かるでしょう。離職を選ぶ社員が多い理由や、反対に定着している社員が多い理由や背景を知れば「転職や起業などでキャリアアップを図る社員が多い」「社員定着のために働き方改革を進めている」など、企業の社風や取り組みへの理解を深められる可能性も。企業研究に役立ち、企業選びの判断材料の参考になるでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
離職率の計算方法とは
離職率=離職者数÷1月1日現在の常用労働者数×100
※常用労働者とは「期間を定めずに雇われている者」「1ヶ月以上の期間を定めて雇われている者」のいずれかに該当する労働者を指す
企業や統計によって、期間や対象となる労働者の範囲は自由に設定可能です。以下では、この式を用いて「年間離職率」「新卒入社3年以内の離職率」をそれぞれ算出します。
年間離職率の計算例
ここでは、期初に100人が在籍し、期末までに9人が離職した会社を例に、年間の離職率を求めます。年間の離職率を求める場合、計算式は以下のとおりです。
年間離職率=期末までの1年間の離職者数÷期初の時点で在籍していた従業員数×100(%)
これに、期初での従業員数と期末までの離職者を当てはめてみましょう。
新卒入社3年以内の離職率の計算例
新卒入社した社員の数とそのうち3年以内の離職者数が分かれば、新入社員の3年以内の離職率が求められます。以下は、新卒社員が50人で、そのうち5人が3年以内に辞めた場合の計算式です。
新卒入社3年以内の離職率=新卒入社の従業員のうち、3年以内に離職した人数÷入社日時点での新卒入社の従業員数×100(%)
=5÷50×100
=10(%)
上記より、この会社での新卒社員の3年以内離職率は10%と分かります。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
日本企業における2023年の平均離職率は15.4%
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、日本企業における2023年の平均離職率は15.4%でした。男女別では男性が13.8%、女性が17.3%という結果になっています。雇用形態別に見ると、一般労働者が12.1%、パートタイム労働者は23.8%でした。
以下は、2022年と2023年の離職率をまとめたものです。
| | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 計 | 15.4% | 15% |
|---|
| 男性 | 13.8% | 13.3% |
|---|
| 女性 | 17.3% | 16.9% |
|---|
| 一般労働者 | 12.1% | 11.9% |
|---|
| パートタイム労働者 | 23.8% | 23.1% |
|---|
雇用形態や性別によって若干のばらつきはあるものの、おおよそ10〜20%の範囲内で離職率が推移していることが分かるでしょう。
条件別の平均離職率
ここでは、「産業」や「新卒入社後3年以内」など条件別の平均離職率をご紹介します。目指している業界や企業、働き方などによって数値は変動するため、気になる会社がある方はぜひ照らし合わせてみましょう。
産業別の離職率
| 産業分類 | 離職率 |
|---|
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 28.1% |
|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 26.6% |
|---|
| サービス業(他に分類されないもの) | 23.1% |
|---|
| 不動産業・物品賃貸業 | 16.3% |
|---|
| 教育・学習支援業 | 14.8% |
|---|
| 医療・福祉 | 14.6% |
|---|
| 卸売業・小売業 | 14.1% |
|---|
| 情報通信業 | 12.8% |
|---|
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 11.5% |
|---|
| 金融業・保険業 | 10.5% |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10.4% |
|---|
| 運輸業・郵便業 | 10.3% |
|---|
| 建設業 | 10.1% |
|---|
| 製造業 | 9.7% |
|---|
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 9.2% |
|---|
| 複合サービス事業 | 0.078 |
|---|
離職率が最も高いのは「生活関連サービス業・娯楽業(28.1%)」でした。2位以下は、「宿泊業・飲食サービス業(26.6%)」「サービス業(他に分類されないもの)(23.1%)」と続きます。一方、最も離職率が低いのは複合サービス事業で7.8%でした。
看護師や美容師など気になる仕事の離職率を知るには?
厚生労働省による上記データは業界別ですが、職種ごとの離職率の目安になるでしょう。看護師や保育士などが含まれる「医療・福祉」の離職率は14.6%です。また、美容師は離職率が28.1%と高い「生活関連サービス業・娯楽業」に含まれます。「離職率の平均は?新卒者や業界別のデータを参考に早期退職を防ごう」では業界別の離職率を職種の例を挙げながら解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
新卒入社後3年以内の離職率
| | 1年目離職率 | 2年目離職率 | 3年目離職率 | 3年以内離職率 |
|---|
| 大学卒 | 12.3% | 12.3% | 10.3% | 34.9% |
|---|
| 短大等卒 | 18.5% | 14.1% | 12% | 44.6% |
|---|
| 高校卒 | 16.7% | 12.2% | 9.4% | 38.4% |
|---|
| 中学卒 | 31.4% | 11.1% | 8% | 50.5% |
|---|
上記より学歴に関わらず、2年目・3年目離職率よりも1年目離職率が高い傾向があることが分かります。また、3年以内離職率の合計も30~50%という結果に。先述した日本企業全体の平均離職率が15.4%だったことを踏まえると、全体的に新入社員の3年以内離職率は高い傾向があるといえるでしょう。
離職率の高い・低いを判断する目安はある?
離職率の高い・低いを、単純に数値だけで判断することは難しいといえます。離職率を調べる際は、対象期間や対象者、業界などから慎重に判断する必要があるでしょう。
業界を例に挙げると「生活関連サービス業・娯楽業」が約28%であるのに対し、「複合サービス事業」は約8%と大きな幅があります。同じ離職率15%でも、生活関連サービス業・娯楽業の企業であれば平均と比較して低い、複合サービス事業を展開する企業であれば高いと判断できるでしょう。
そのため、就職・転職活動では離職率にとらわれずに、会社ごとの取り組みや社風、自分との相性などを判断することが重要です。このコラムの後半では離職率を踏まえたうえでの就職・転職活動のコツを解説しているので、ぜひ読み進めてみてください。
離職率の主な調べ方
離職率の調べ方にはさまざまな方法があります。ここでは代表的な方法を6つ紹介するので、離職率を調べる際の参考にしてみましょう。
なお、離職率は公開義務がありません。そのため、企業によっては調べても見つからない場合がある点に注意が必要です。
離職率の調べ方
- ハローワーク
- 就職四季報
- 就職・転職エージェント
- 口コミサイト
- 企業に直接質問する
- 自分で離職率を計算する
離職率の調べ方1:ハローワーク
ハローワークの求人票で、離職率の確認ができます。求人票には過去3年間の応募者数や採用者数、離職者数などが記載されている場合があるため、掲載情報から離職率の計算が可能です。ただし、先述したように離職率を公開していない企業もあります。
離職率の調べ方2:就職四季報
「就職四季報」とは、東洋経済新報社から年に1回発行される雑誌です。各企業の3年後離職率が掲載されており、気になる企業の離職率を素早く調べることが可能です。また、離職率以外に「平均勤続年数」「平均残業時間」「有給休暇の取得実績」なども記載されています。
ただし、企業によっては離職率を非公開にしていたり、そもそも四季報に掲載されていなかったりするため、必ずしも自分の欲しい情報が手に入るとは限りません。
離職率の調べ方3:就職・転職エージェント
就職や転職でエージェントを活用している場合は、担当者に気になる企業の離職率を尋ねてみるのもおすすめです。就職・転職エージェントは民間の就職支援機関で、企業に人材を斡旋して報酬をもらう仕組みで運営されています。そのため、紹介した人材がすぐに離職してしまうと、報酬の一部を返金しなければならない場合も。紹介後の離職を防ぐには、求職者と企業の双方にとって満足度の高いマッチングを行う必要があるため、エージェントは企業の情報に詳しい傾向にあるようです。離職率以外にも、社内の雰囲気や事業についてなど、エージェントでしか聞けない情報を入手できる場合があるでしょう。
離職率の調べ方4:口コミサイト
大まかな離職率を手軽に調べる方法として、口コミサイトの活用があります。口コミサイトでは、従業員や元従業員が会社の体制について投稿が可能です。離職率自体が掲載されていなくても、会社を辞めた理由や年代が分かるサービスもあります。また、仕事内容や働いて感じたことなどが投稿されているため、会社のリアルな雰囲気を把握しやすい調査方法といえるでしょう。ただし、匿名であるぶん信ぴょう性に欠ける情報がまぎれている可能性があります。
離職率の調べ方5:企業に直接質問する
「企業に直接質問したら離職率が分かるのでは」と考える方もいるでしょう。企業によっては、離職率を一切公表していない場合もあります。しかし、離職率が知りたいからといって企業に直接質問するのは、避けたほうが無難です。直接質問することで、採用担当者が「離職率を知ってどうする気なのか」「自社の労働環境や働き方について不安や疑問があるのか」とマイナスな印象を抱くリスクも考えられます。先述した就職・転職エージェントに聞いてみたり、口コミサイトで大まかな離職理由や人数を推測したりする程度にして、直接の質問は避けるようにしましょう。
離職率の調べ方6:自分で離職率を計算する
会社の離職者数と在籍している従業員数が分かれば、離職率を自分で計算することが可能です。3年目以内離職者数は就活サイトの企業情報に載っている場合があるほか、従業員数は企業ホームページの「会社紹介」「概要」ページなどから調べられます。
会社の経営状況を知れるデータもあわせて活用してみよう
会社の経営状況を知れるデータをあわせて活用することで、離職率だけでなく会社の事業内容や業績が分かります。離職率だけでは確認できない会社の安定性や事業の方向性を確認できるため、企業研究に役立つでしょう。
活用できるデータとして、「有価証券報告書」や民間企業が運営している企業データベースサービスなどが挙げられます。「有価証券報告書」とは、会社の概況や財務諸表などの情報を掲載した株主や投資家向けの報告書です。売り上げや事業内容だけでなく、従業員数の推移や平均勤続年数も調べられます。また、企業データベースサービスでは、「業績」「資本構成」「企業規模」「損益」「経営者情報」「企業活力」などが確認可能です。
ただし、有価証券報告書の提出義務があるのは、一定の条件を満たした会社のみとなっています。また、民間のデータベースサービスが行う調査に会社側が協力する義務はありません。そのため、すべての会社のデータを調べられるわけではない点に注意が必要です。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
社員の離職率が高い会社によくある特徴とは?
社員の離職率が高い会社には「仕事内容と給与が見合っていない」「会社の方向性が分かりにくい」などの特徴があります。働きやすい環境が整っていないと社員のモチベーションや帰属意識につながりにくく、離職率が高くなりやすいでしょう。ここでは、離職率が高い会社にみられる特徴を紹介します。
仕事内容と給与が見合っていない
仕事内容と給与が見合っていないと、離職を考える社員が増える可能性があります。給与は仕事での満足感やモチベーションに直結しやすいためです。自分の適性に合っている仕事や、やりがいのある仕事を任されていたとしても、給与が仕事に見合っていないと「頑張る意味がない」と感じてしまう場合も。給与が低いことで日々の生活にゆとりをもちにくく、貯金や将来のライフイベントの計画も立てにくくなるでしょう。趣味やプライベートに使えるお金を増やしたり将来に備えたりと、待遇改善を目的に転職する社員がいる可能性があります。
会社の展望が不明確で分かりにくい
離職率が高い会社にみられやすい特徴として、「会社の展望が不明確」という点が挙げられます。
会社全体としての方向性や長期的なビジョンが見えないと、社員は進むべき方向性が分からなくなってしまうことも。そのため、「何を目指して働けば良いのか分からない」「具体的にやりたいことがない」と感じ、より良い環境を求めて離職してしまう可能性があります。また、会社の展望が社員にとって魅力的でない場合も、離職率に影響するでしょう。会社が目指している展望が自分のキャリアの方向性と異なれば、業務に対する成長意欲やモチベーションは向上せず、離職につながる可能性があります。
明確な評価基準がない
明確な評価基準がなく、個人の成果や能力を公平に評価していない会社も、離職率が高い可能性があります。「頑張りを評価してもらいたい」「成果に応じた報酬をもらいたい」など上昇志向が強い方の場合、評価基準が明確でない環境ではモチベーションを維持しにくいでしょう。「能力を正しく評価してもらいたい」という思いが強まり、実力主義や歩合制など成果が反映されやすい企業へ転職するために、離職する人が増えている可能性があります。
社員研修や社員教育などの体制が整っていない
会社の社員研修や教育の制度が整っていないことが、離職率が上がる一因になることもあります。入社時に仕事内容やビジネスマナーなどの研修や教育が十分でないと、人によっては「何をすれば良いか分からない」という不安を感じることも。会社への不信感や仕事のやり方が分からないストレスから、離職を考える社員がいる可能性があります。
柔軟な働き方に対応していない
柔軟な働き方ができない会社では、離職率が高くなりやすいでしょう。会社の求める働き方に順応できず離職したり、より良い環境を求めて転職を考えたりする社員がいると考えられるためです。たとえば、家庭の事情で働き方を変える必要が生じても、「リモートワーク」や「時短勤務」といった制度がないため仕事を続けられない場合があります。また、「満員電車を避けて通勤したい」「朝から働いて帰宅を早くしたい」と考え、フレックスタイムを導入した会社に転職する場合もあるでしょう。
労働環境の改善やハラスメント対策がされていない
労働環境の改善やハラスメント対策を行っていないことも、離職率が高い企業の特徴です。深夜や休日に及ぶ長時間労働やハラスメントが横行していると、疲労やストレスから心身の調子が崩れたり働きにくさを感じたりし、離職を考える社員が増える可能性があります。のびのびと仕事に取り組めないと、仕事へのモチベーションや働くことへの充実感を得にくいでしょう。そのため、「もっと良い会社があるはず」「ワークライフバランスを整えたい」という思いが強まり、離職する社員が増える可能性があります。
面談やコミュニケーションの機会が少ない
離職率の高い企業の特徴として、会社内でのコミュニケーションの機会が不十分なことも挙げられます。働き方や労働環境に関する定期的な面談やヒアリングがない会社の場合、社員の意見や要望が会社側にうまく伝わらないことも。社員の不満が溜まることで、離職率も高くなるでしょう。また、コミュニケーションが少なく風通しの良くない環境では、思っていることやアイディアを共有しにくくなります。そのため、新しい考えや解決策が生まれにくいほか、社員同士の信頼関係や仲間意識も育ちません。コミュニケーションが足りないと社員同士の結束や会社への愛着が芽生えず、そのぶん離職を決断しやすいといえます。
離職率の高い職場は人間関係のストレスも感じやすい
社員同士のコミュニケーション不足により、職場での人間関係にストレスを感じてしまうことも。上司からの暴言やパワハラが多い職場だったり、社内でいじめが起こっていたりする場合もあるでしょう。そのため、人間関係や雰囲気に問題がある職場も離職率が高くなる可能性があります。人間関係が原因の離職については「人間関係で仕事を辞めるのはあり?ストレスになる理由や対処法などを解説」のコラムも参考にしてください。
福利厚生が充実していない
離職率が高い会社について調べる場合は、福利厚生も重要です。会社が独自に設定できる「法定外福利厚生」が充実していないと、離職率が高くなる可能性があります。法定外福利厚生の例としては、「通勤手当」「住宅手当」「人間ドックの費用補助」「リフレッシュ休暇」「社員旅行の実施・補助」などが。会社によって内容は異なるものの、自分にとって「助かる」「役に立つ」と思える制度が多いほど、会社に対する満足度も向上しやすいでしょう。
有給休暇を取得しにくい
有給休暇を取得しにくい会社は、離職率が高くなりやすい可能性があります。有給休暇を習得することは、要件を満たした労働者全員に与えられた権利です。本来は自由に消化できるものですが、有給休暇を取得しにくい企業もなかには存在しています。「有給休暇を使うなといわれた」「理由をしつこく確認される」といった会社では、社員の満足度は低くなりやすいでしょう。そのため、より良い環境の会社を求めて離職する社員が一定数いる可能性があります。
社員のキャリア形成に対する支援が十分でない
社員のキャリア形成に対する支援が十分でない会社では、離職率が高くなる傾向があるようです。たとえば、社員の希望に合わせた挑戦やキャリアアップを後押しし、実現に向けサポートする環境が整っている会社では、社員が自分のキャリアビジョンを具体的に描きやすいでしょう。一方、それらの支援がないと今の会社でのビジョンを描きにくく、「この会社で成長したい」というモチベーションを維持するのが難しいといえます。また、育児や介護といったライフステージの変化に対応しているかどうかも重要です。育休制度や復帰後のキャリア支援がない会社では、継続したキャリアを築きにくいでしょう。ブランクがあっても復帰しやすい環境や制度が整っていないため、キャリアを諦めて離職したり、制度の充実した会社へ転職したりすることが考えられます。
社員の定着率が高い企業に見られる特徴は?
定着率が高い企業では、社員の満足度を上げるために以下のような取り組みをしている可能性があります。
・社員のワークライフバランスを重視した労働環境の整備
・社員同士でのコミュニケーションが取りやすい場の提供
・明確な評価基準の設定や周知
・教育体制やキャリア支援制度の整備
働きやすい環境が整っていると社員の満足度やモチベーションが上がり、離職率が下がりやすいようです。「働きやすい会社の特徴とは?職場環境の良さを感じるポイントを紹介!」のコラムでは、働きやすい職場環境の例をより詳細にご紹介しています。企業研究をする際のチェック項目として、ぜひ参考にしてみてください。
離職率の高い・低いはどのように捉えればいい?
なかには、「離職率が高い会社は絶対に避けよう」と考えている方もいるでしょう。しかし、離職率だけでその会社のすべてが分かるわけではありません。ここでは、離職率をどのように捉え、就職・転職活動に活かすかを解説します。
離職率はあくまで参考として考える
就職・転職活動では離職率の高い・低いだけで、企業が自分に合うか合わないかを判断しないようにしましょう。離職率はあくまで一定期間の離職者数を示した値であり、その背景や会社の状況は確認できません。たとえば、「自社の職場環境に不満はないが、自己成長のために次の挑戦をしたい」「自社で身につけたスキルを活かしてキャリアアップしたい」といった前向きな転職が多い可能性も考えられます。上昇志向の社員が多かったり、社員の挑戦を後押しする雰囲気が整っていたりすることもあるでしょう。「離職率が高い=労働環境が悪い」という認識でいると、上記のような会社を見逃してしまう恐れも。離職率はあくまで参考としてとらえておくことが大切です。
働きやすい会社かどうかは離職率だけでは判断できない
離職率だけでは、自分にとって働きやすい会社かどうかを判断できません。重要なのは離職率の高さよりも、企業風土や働き方が自分に合っているかどうかです。たとえば、ベンチャー企業は平均年齢が若く、「今の会社でスキルを身につけて転職したい」という人材や、積極的にキャリアアップを目指す人材が一定数いるため離職率が高くなりやすいといえます。しかし、「裁量をもって働きたい」「この会社の技術でイノベーションを起こしたい」といった希望やビジョンがあるのであれば、離職率に関わらず満足度の高い就職・転職を実現できるでしょう。
ただし、あまりにも離職率が高いと、在籍している社員の負担が重くなっている可能性も考えられます。企業研究ではエージェントに企業の雰囲気を聞いたり社員のインタビューを確認したりし、現場の働き方や一人ひとりの業務量をよく確認しましょう。そのうえで、自分の理想とする働き方に近いかどうかを判断することが大切です。
就職・転職活動では多角的に企業研究を行うことが大切
就職・転職活動を成功させるためには、多角的に企業研究を行うことが大切です。離職率のほかにも、企業研究で調べておきたい内容はたくさんあります。企業研究を深く行うほど入社後のギャップが生じにくくなるため、できるだけ丁寧に進めましょう。
企業研究のポイントは、自分が希望する働き方や会社に求めるものを分析して、社風や会社の取り組みと照らし合わせていくことです。たとえば、「スキルを身につけてキャリアアップしたい」と考えているなら、研修制度の充実度や資格取得支援制度の有無などを調べてみてください。「育児と仕事を両立したい」と考えているなら、育休の取得率や復帰後の支援制度を確認しましょう。
離職率にとらわれずに自分に合った仕事を探そう
自分に合った働きやすい職場を探すには、離職率にとらわれずに自分が職場に求める優先順位を明確にすることが大切です。「収入」や「人間関係」、「ワークライフバランス」など、自分にとって譲れない条件を洗い出してみましょう。
何をもって働きやすいと感じるかは、一人ひとり異なります。求人情報だけでなく企業のホームページやリクルートサイトを確認したり、企業説明会や口コミサイトで社員の生の声を聞いたりして、労働条件や社風、仕事内容などさまざまな側面から自分に合った仕事かどうか調べましょう。
「後悔しない就職がしたい」「長く働ける会社に転職したい」と考えている方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブは、若年層に特化した就職・転職支援サービスを展開しています。専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを行い、一人ひとりの適性に合った求人を厳選してご紹介します。すべての企業に取材を行っているので、職場の雰囲気を細かくお伝えすることが可能です。
また、選考対策や面接の日程調整なども行い、就職・転職活動をトータルサポート。1分程度で簡単に行える適職診断もご用意しています。サービスの登録・利用料はすべて無料のため、ぜひお気軽にご相談ください。
離職率についてのお悩みQ&A
ここでは、離職率についてよくある質問にQ&A形式でお答えしています。就職・転職活動をしていて離職率が気になる方は、参考にしてみてください。
離職率が高い職場に転職するのは避けたほうが良いの?
「離職率が高い=避けるべき会社」と一概にはいえません。離職率の高さが気になる場合は、その理由を調べてみましょう。「若者が多く人材の流動性が高い」「上昇志向が強く転職者が多い」など、労働環境や会社の制度に問題がなくても離職率が高い場合もあります。離職率に惑わされずに自分に合った仕事を探すには、業務内容や適性を踏まえて企業との相性を確認することが重要です。適性に合う仕事の探し方が分からない場合は「自分の適性に合う仕事の探し方とは?」を参考にしてみてください。
必ずしもそうであるとは限りません。離職率が低いのは定着率が高いことを示しているため、長く働ける職場と考えられる場合もあります。一方、長く働いている従業員が多いと保守的な傾向が強まったり、中途社員が人間関係を構築するのが難しいと感じたりする可能性もゼロとはいえません。
自分に合う働きやすい職場を見つけるためには、企業理念や社風、仕事内容への適性などにも着目してみましょう。