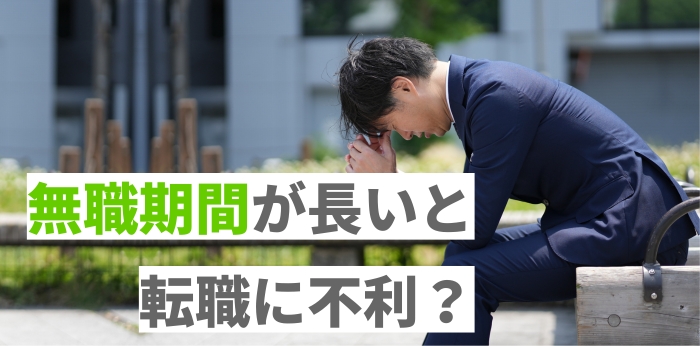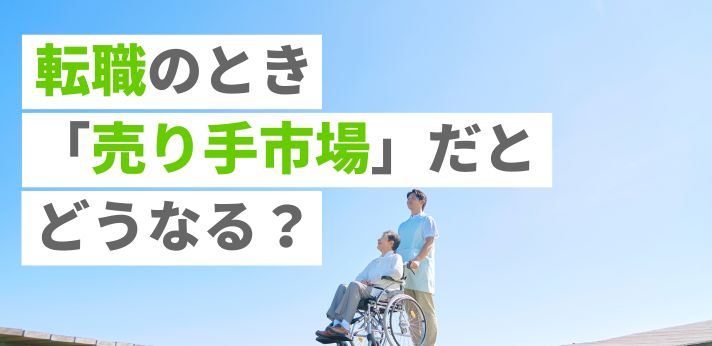転職したら税金や社会保険はどうなる?退職後の流れを詳しく解説転職したら税金や社会保険はどうなる?退職後の流れを詳しく解説
更新日
公開日
給与から差し引かれる税金は、所得税と地方税の2つがある
「転職したら、税金や社会保険はどうなるのだろう」と疑問に思っている方もいるでしょう。会社勤めのときは、所得税や住民税といった税金はもちろん、医療保険や年金保険などの社会保険もすべて給与から天引きされていましたが、仕事を辞めたら自分で行うことになります。コラムでは、税金や社会保険の内容を詳しく解説。転職先が決まっている場合と決まっていない場合、それぞれの手続き方法についてもお伝えしています。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
転職先が決まっている場合の税金・社会保険の手続き
退職後に日を空けることなく転職する場合は、書類を提出することで、旧会社から新会社へ事務手続きを引き継いでもらえます。特に、健康保険や年金は無職の期間がなければ転職先の企業で継続して加入できるのがポイント。自分で行う作業はそれほど多くないため、悩まずスムーズに移行できるでしょう。
-
- 源泉徴収票
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)
手続きに必要な書類のほとんどは、退職した会社に用意してもらう必要があります。転職先が決まっている場合は、できるだけ早く用意してもらえるように依頼しておくと安心です。「」のコラムも参考にしてください。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
転職先が決まっていない場合の税金・社会保険の手続き
転職先が決まっていない場合は、税金・社会保険ともに自分で手続きを行う必要があります。特に健康保険と国民年金は期限が設けられているため、あらかじめ準備をしておきましょう。
所得税
退職直後は転職先が決まっていなくても、年内に再就職する場合は、新しい会社が手続きを行うため自身での手続きはありません。
しかし、年内に再就職できなかった場合や年内に再就職したものの新しい会社の年末調整に間に合わなかった時は、翌年の確定申告の時期に税務署にて自身で手続きを行う必要があります。
手続きの際には、確定申告書や前の会社の源泉徴収票、各種控除証明書、印鑑を準備しておきましょう。
住民税
住民税は退職した時期によって手続き方法が異なります。6月から12月までの間に退職した場合は、退職時に一括で払うか分割で払うかを選択し、退職する会社へ伝えます。1月から5月に退職した場合は、退職時に一括で支払うのが一般的のようです。
失業保険
退職後、無収入になる期間の生活を支援してくれるものです。受給されるまでに時間を要しますので、なるべく早めに手続きを行うようにします。手続きの際には、雇用保険被保険者離職票(1)、雇用保険被保険者離職票(2)、印鑑、写真2枚、普通預金通帳、マイナンバー確認証明書、本人確認証明書が必要です。ハローワークにて申請を行いましょう。失業保険の受給条件やもらうまでの流れについては、「ハローワークで失業保険受給の手続きをするには?必要な持ち物や書類とは」のコラムをご確認ください。
国民年金
日本では20歳以上60歳未満であれば年金への加入が義務付けられているため、退職後は国民年金への種別変更手続きを行う必要があります。市区町村の役所や役場にて手続きを行うために、年金手帳や印鑑と、退職日を確認できるもの(離職票や退職証明書)を準備しておきましょう。
なお、厚生年金は会社側と折半した金額を支払っていましたが、国民年金は全額自己負担。状況によっては負担が増えることを理解しておきましょう。
健康保険
健康保険も、「国民皆保険制度」のため加入が必要です。
退職すると会社で加入していた保険証は利用できなくなるため、手元にある健康保険証を退職する会社へ返却し、健康保険資格喪失証明書を受け取ります。その後、新たに加入する健康保険の手続きを進めます。
急な病気やケガで病院を受診した際、保険証がないと全額負担となる可能性もあるので、できるだけ速やかに手続きを行うことが大切です。健康保険の選択肢としては、「家族の社会保険の扶養に入る」「任意継続」「市区町村運営の国民健康保険組合に入る」といったパターンがあります。自身の条件に合うものを確認し、加入してください。
仕事を辞めたあと無職になっても税金の支払いは必要?
仕事を辞めて無職になっても、税金の支払いは必要です。住民税は「前年の収入」に基づいて課税されるため、前年に収入があれば納付義務があります。もし収入がなくてすぐに支払えない場合は、放置せずに自治体へ相談しましょう。分割払いや免除制度が使えることもあります。無視すると延滞金や差し押さえのリスクもあるので、早めの対応が大切です。状況別の納付方法や注意ポイントをもっと詳しく知りたい方は「
無職でも住民税は払う?状況別の納付方法や注意ポイントについて解説!」も合わせてご一読ください。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
転職前に知っておきたい税金のこと
税金は、社会保障や水道・道路といったインフラの整備、教育をはじめとする公的サービスを運営していくために必要な費用を賄うためにあります。納税は国民の義務であり、会社員は所得税と住民税が給与から天引きされるのが一般的です。
所得税(国税)
所得税は、その年に得た個人の収入に対し課される税金です。金額は1年分をあらかじめ想定し算出。12分割された金額が毎月の給料から天引きされます。
年の途中で退職した場合は、自分で確定申告を行う必要があります。ただし、年内に再就職した場合は新しい会社で手続きを行ってもらえる可能性が高いです。
なお、新しい会社で手続きをしてもらうためには、生命保険や医療費の控除証明書、旧会社の源泉徴収票といった書類が必要になります。
住民税(地方税)
住民税とは、都道府県民税と区市町村民税の総称です。金額は1年間の所得に対し算出されます。納付のタイミングは、翌年6月から翌々年5月までの後払いです。
納税方法は退職時期によって異なります。1月から5月に退職した場合、住民税は最終月の給与から一括で天引きされます。6月から12月に退職した場合の納付方法は、退職月から翌年5月までの住民税を給与天引きにしてもらう方法と、市町村から送られてくる納付書を使って納める方法の2通りです。
転職前に知っておきたい社会保険のこと
給与から天引きされているのは、税金だけではありません。社会保険も給与から差し引かれています。社会保険には、医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険の5種類があります。詳しくみていきましょう。
医療保険
病気やケガなどで病院を受診した際、かかった治療費の一部を負担してくれる保険のことです。
年金保険
老後の暮らしや、働けない状態になったときの支えとなるのが年金保険です。年金保険は以下のとおりに区分されます。
第1号被保険者
国民年金のみに加入している方を指します。20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス、農業者、漁業者、学生、無職の方などが該当する区分です。
第2号被保険者
70歳未満の会社員や公務員など、厚生年金の加入者を指します。厚生年金に加えて、国民年金の加入者にもなります。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方を指します。保険料は第2号被保険者全体で負担をするため、自身では保険料を納めずに年金の受給資格を得ることが可能です。
雇用保険
失業した際の生活支援や再就職支援、介護や育児などで休業した際の生活を支援してくれる保険です。
労災保険
事故や災害に見舞われ、病気になったりケガをしたりした際に、治療費や生活を支援してくれる保険のこと。仕事中または通勤時のときに発生したケースのみ対象です。
介護保険
その名のとおり、介護を必要とする人が必要なサービスを受けられるための保険です。40歳になった月から支払いが発生します。
基本的には、上記に挙げた保険が給与から差し引かれています。会社に雇用されているあいだは手続きのすべてを会社が行ってくれますが、退職後は自身で対応することになります。
退職金にも税金はかかる?
退職金にも税金はかかります。ただし、退職後の生活を支える資金という側面があるため、通常の給与所得よりも税制上の優遇措置が設けられています。
具体的には、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されますが、「退職所得控除」を差し引いた額の50%だけが課税対象になる仕組みです。
また、税制優遇を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。受け取り方次第で税額も変わるため、事前に確認しておきましょう。退職金の計算方法や注意点についてもっと詳しく知りたい方は、「
退職金にも税金はかかる?課税の種類・計算方法・注意点について解説」もご一読ください。
転職したいけど、転職後の税金や社会保険の手続きが不安で一歩を踏み出せないという方は、転職エージェントを利用してみるのも一つの方法です。
ハタラクティブでは、プロのアドバイザーが求職者の不安や悩みに寄り添い、安心して転職活動を進められるようサポートしています。退職後の流れに対する疑問点も、お気軽にご相談ください。そのほかにも、ハタラクティブではあなたのニーズや適性に合った求人の紹介や、書類の作成方法、面接日の日程調整など、さまざまなサービスを提供しています。サービスはすべて無料です。ご登録をお待ちしております。
転職時の税金に関するFAQ
ここでは、転職した際の税金や社会保険に関するよくある質問と回答についてまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
転職しても基本的に税金(住民税)が二重払いになることはありません。ただ、退職時に前職で住民税を一括徴収された場合、その後に納付書が届くことで「二重払いでは?」と感じてしまう方もいます。万が一、実際に二重に支払ってしまったとしても、払いすぎた税金は自治体から返金されるのでご安心ください。転職の際の住民税についてもっと詳しく知りたい方は、「転職したら住民税が二重払いになる?納付書が届く理由や手続きについて解説」もご一読ください。
税金が高いから払えない場合はどうしたらいいでしょうか?
税金が高くて支払いが難しいと感じたら、無視せず、できるだけ早く市区町村の税務課や税務署に相談しましょう。事情をきちんと伝えれば、「納税の猶予」や「分割払い」などの制度を利用できる可能性があります。また、収入が一定の基準を下回っている場合は、減免制度が適用されることも。延滞を放っておくと差し押さえなどのリスクが出てくるため、困ったときや不安があれば、遠慮なく役所へ相談しましょう。
転職して年収が下がる場合、所得税などの税金は変わりますか?
転職で年収が減ると、それに伴って税金の負担も変わってきます。特に所得税は、収入が多いほど税率が高くなる仕組み(累進課税)なので、年収が下がればかかる税金も少なくなるでしょう。これに対して住民税は、計算の元になるのが去年の所得です。そのため、たとえ今年の年収が下がっても、すぐに税額は減らず、影響が出るのは翌年になります。転職してすぐの頃は、この住民税の金額が変わらないため、手取りが以前より減ったと感じやすいかもしれません。社会保険料についても、いずれ収入に見合った金額に下がっていくでしょう。
税金や社会保険の手続きが不安な方や、転職活動がうまくいかずにお悩みの方は、一度、ハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーがあなたの相談にのり、数多くの求人情報の中からあなたにピッタリの仕事を紹介します。