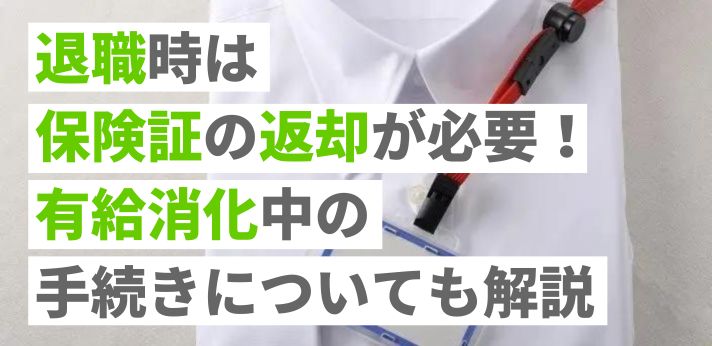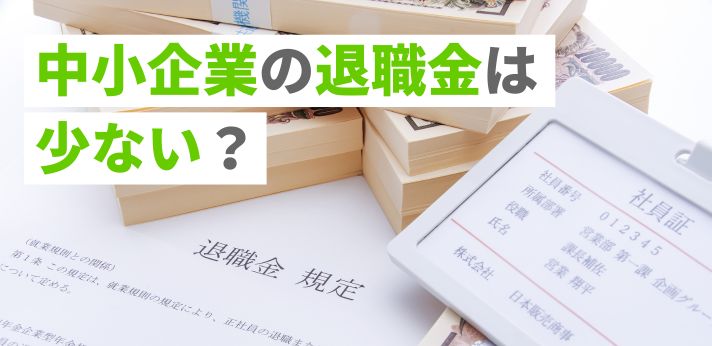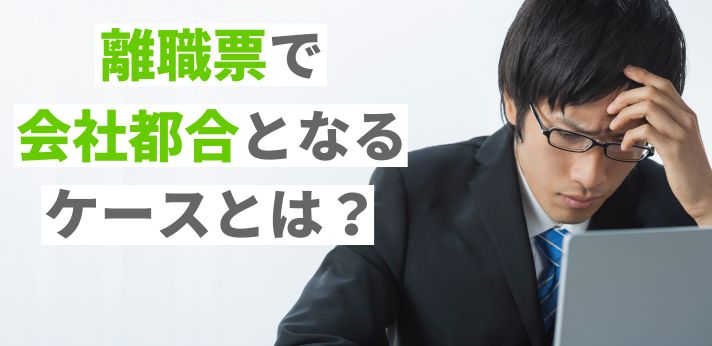退職届はいつ出す?提出の流れも解説更新日
公開日
退職届をいつ出すかは、上司に退職の意思を伝えてから
「退職届はいつ出す?」と悩む方もいるのではないでしょうか。退職届の提出期限は、基本的に就業規則で定められていることが一般的なため、まずは就業規則を確認してみましょう。それから、直属の上司へ退職を伝えるのがベターです。
このコラムでは、退職届を出すタイミングや基本的な退職の流れなどを解説します。円満退職のためにも、ぜひチェックしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
退職届はいつ出すのが最適?
退職届を出すタイミングは、退職の1ヶ月前が一般的です。
しかし、上司に相談もなしに突然退職届を提出するのはマナー違反と思われ、受理されない可能性があります。そのため、退職届を提出する前に上司に申し出ることが望ましいでしょう。また、企業によっては、退職届の前に退職願の提出を求めるところもあります。
退職届の提出は就業規則で定められていることが一般的
一般的に1ヶ月前といわれていますが、多くの企業は就業規則で退職届の提出タイミングを定めています。これは、退職にあたって業務の引き継ぎや後任者の選定、必要に応じて人材の異動などが必要になるためです。就業規則を守った期間に提出することで、職場とのトラブルを防ぎ、円満退職を成功させることにつながるでしょう。
法律では2週間前の提出で問題ない
民法第627条第1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。
つまり、雇用期間が定められていない従業員は、2週間前に退職を申し出たら受理されるのです。万が一のトラブル防止のため、法的根拠による退職届提出のタイミングも覚えておきましょう。
退職を伝える時期は繁忙期以外が望ましい
企業側に退職を伝えるのは繁忙期以外のタイミングが望ましいでしょう。繁忙期は、上司の都合がつきにくく二人で話す時間がなかなか作れない場合があるためです。
また、大きなプロジェクトの途中や人事異動をしてすぐなどは、引き継ぎも難しいでしょう。
退職を告げるのは、できるだけ引き継ぎのしやすいプロジェクトの終了直後や、人事異動の内示直後がおすすめです。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職までの一般的な流れ
ここでは、退職を決意してから実際に対処するまでの流れを8つのステップで紹介します。一般的な流れを知っておきましょう。
1.退職を決める
最初に、退職の意思を固めましょう。転職や結婚、家族の介護、体調不良など、退職を考える理由は人によってさまざまです。自分の気持ちや現在の状況などをじっくり考えたうえで、退職するか決めましょう。
退職を決めたら、それまでの経緯を文書にしておくことをおすすめします。会社に提出するものではなく、退職を申し出る際に退職理由をスムーズに説明するための資料として残しておく目的です
2.就業規則を確認する
退職届提出のタイミングや提出先などを把握するため、就業規則を確認しましょう。就業規則に記載されている内容に従うことで、退職に関するトラブルを防止できる可能性があります。退職に関する規則は、「退職届の前に退職願を出す」「会社独自のフォーマットで提出する」など、企業によって違いがみられる場合があるため事前確認は大切です。
3.直属の上司へ退職を申し出る
退職を決めたら、2ヶ月から3ヶ月ほど前に直属の上司に、口頭で退職意思を伝えます。
順番を飛ばして人事部や社長などに直接退職の意思を伝えることは、トラブルにつながる恐れがあるため避けましょう。
また、退職の理由を述べる場合も注意が必要です。会社に対する不平不満や人間関係のもつれ、仕事に対する難癖など、何らかの不満を理由にするのはあまり好ましくありません。
4.退職届を提出する
退職日が決まったら、退職届を提出します。会議室などほかに人がいない場所で、直属の上司へ手渡しすることが一般的です。できるだけ人目につかないように渡すのが望ましいでしょう。内ポケットに忍ばせておき、上司の席の前で取り出して渡したり、人のいない別室で渡すなどの方法をとるのがおすすめです。
上司が離席中に机の上に置いておくことや、人の目の多いタイミングで渡すのは避けましょう。
5.引き継ぎや退職準備を行う
退職が決まったら、自分が担当していた業務を後任者へ引き継ぎます。後任者に分かりやすいよう、業務マニュアルを作成したうえで、口頭での説明も行うのが望ましいでしょう。
また、担当していた取引先にも退職挨拶と後任者紹介を行います。退職日の1~2週間前を目安に行いましょう。仕事で使用していた備品や制服、書籍、業務用のパソコンやスマホなどの返却も忘れずに行ってください。
6.必要な手続きを行う
退職時に必要な手続きとして、雇用保険や健康保険の手続きなどが挙げられます。人事担当者からの指示があれば、それに従って行いましょう。
また、離職票と健康保険資格喪失証明書を受け取った際は、転職先への提出が求められたり失業保険を受給する際にハローワークに提出したりするため、大切に保管するようにしてください。
7.有休を消化する
有休取得のタイミングは、「退職日前に取得して、退職時に最終出社する」と、「最終出社日後に取得してそのまま退職する」の2パターンです。
ただし、退職前の有休消化は労働者の権利ですが、基本的に引き継ぎが終了していることを前提としています。上司と相談して決めるのが望ましいでしょう。
8.上司や同僚に挨拶する
最終出社日には、今までの感謝の気持ちを込めて社内の人に挨拶しましょう。仕事の邪魔にならないように、職場の雰囲気が比較的落ち着いているときにそっと動き出すのがおすすめです。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職理由・退職意思の伝え方
退職理由・退職意思の伝え方には、「ネガティブな理由は避けて個人都合を伝える」「退職への固い意志表明をする」といったポイントがあります。ここではこれらのポイントを詳しく解説するので、確認してみてください。
ネガティブな理由は避けて伝える
退職理由を聞かれても、ネガティブな理由は伝えないようにしましょう。会社への不満を伝えると、上司の気分を害したり、引き止めの口実になってしまったりする恐れがあります。たとえば「○○の分野に興味があり、チャレンジしたいため」といった前向きな内容に変換しましょう。
退職への固い意志表明をする
退職を伝える際は、引き止められないよう固い意志表明をするのが大切です。
しかし「もう辞めると決めているんで」「○月○日までには必ず会社を辞めます」といったように、一方的な言い方はトラブルを招く恐れがあるため避けましょう。
自分の気持ちを一方的に伝えるだけだと上司からの心証が悪くなり、円満退社が難しくなる可能性があります。
上司への退職理由の伝え方は「退職理由は正直に言うべき?上司や面接官への上手な伝え方を紹介」でも紹介しているので、興味のある方はこちらも参考にしてみてください。
退職を伝えた際の反応別の対応例
退職を伝えた際、引き止められたり話を聞いてもらえなかったりといった反応に困る人もいるようです。ここでは、そうした状況でどのように対応するのが良いか、想定できる反応別に紹介します。
事前に知っておけば、いざここで紹介するような反応をされたときも冷静に対処しやすくなるため、目を通しておきましょう。
話を聞いてもらえなかった場合
直属の上司に退職理由・退職意思を伝えようとしたにも関わらず、話を聞いてもらえなかった場合は、さらに上の上司に持ち掛けます。それでも話を聞いてもらえなかったり、退職を受け入れてもらえなかったりした場合は、人事部に相談してみましょう。
前述のように、民法第627条第1項では、「当事者が雇用の期間を定められていない場合、いつでも解約を申入れられる。また、解約の申入れから2週間経過した雇用を終了できる」とされています。つまり、法的には企業側は従業員の退職を拒否できないのです。
上司の上司や人事部に掛け合っても解決しない場合、労働基準監督署に相談することで、対応を一緒に考えてもらえるでしょう。
参照元
e-gov法令検索
民法
競合へ転職する場合
会社を辞めたいと伝えると、「転職先は決まっているのか」と聞かれることがあります。転職先を伝えるかどうかに明確な決まりはありませんが、競合に転職する場合は明言を避けるのが無難です。
競合他社に転職するとなると、現在の会社での機密事項や知的財産が流出しないかと懸念される可能性があります。不安要素を作らず円満退社するためにも、可能であれば明言は避けるのが良いでしょう。
あっさり受け入れられた場合
引き止められることもなく、あっさり退職を受け入れられる場合もあります。寂しい気持ちになるかもしれませんが「揉めることなく余計な時間や気苦労をせずに辞められる」とポジティブに考えましょう。
引き止められた場合
引き止められた場合「自分は会社に必要とされているんだ」と、期待に応えたい気持ちになってしまう人もいるでしょう。しかし、次の転職先が決まっている場合、応えるわけにはいきません。
もし、次の就職先が決まっていなかったとしても、退職しようと思った理由があったはずです。改めてその理由を思い出してみましょう。
引き止めに応じない場合、まずは「身に余るお言葉、ありがとうございます」などと感謝の気持ちを伝えます。そのうえで、「しかし、自分なりに検討を重ねた結論ですので、ご理解ください」といったように毅然とした態度で退職の意思を伝えましょう。
退職届の書き方
退職届を書く際は、まずは会社の指定のフォーマットがないか確認しましょう。特に決まりがないようであれば、白地のA4またはB5サイズの用紙に縦書きで手書きするか、パソコンで作成します。
- ・退職届(タイトル)
- ・1行目の下部に「私儀」
- ・退職理由(自己都合なら「一身上の都合」)と退職日
- ・提出日
- ・所属部署と氏名
- ・捺印
- ・所属企業名と代表者の役職名と氏名
手書きの際は、消しゴムで消せない筆記具で書きます。修正テープでの修正は不可なので、書き損じた場合は一から書き直しましょう。
退職届と退職願や辞表の違いとは?
退職届は退職することを届け出る書類で、一度提出すると撤回できないものです。これに対して退職願は、退職を願い出る書類のこと。人事管理者の決定前であれば、撤回できるといわれています。また、辞表は、役職者や公務員がその職を辞するときに提出する書類です。
退職届は正しいタイミングで提出して円満退職を目指そう
円満退職を叶えるには、「退職することが上司よりも先に職場の人にバレないように気をつける」「繁忙期は避ける」「会社や職場の人の悪口、文句、不満は言わない」などを守る必要があります。
会社に迷惑を掛けない辞め方が、社会人としては理想的です。退職するその日まで、しっかりと会社の一社員として貢献することが大切だといえます。
円満退職のコツを知りたい、期間を空けずに転職したいけど時間がないといったお悩みなら、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブでは若年層に特化した就職・転職支援を行っており、就業中からご利用が可能です。
専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの適性に合った求人の紹介や、応募先企業の特徴や社風の共有、応募先企業に合ったアピールのコツなどで転職成功をサポートします。また、在職中に気になる面接スケジュール調整も代行して実施。
サービスはすべて無料で利用できるので、ぜひお気軽にご相談ください。
退職届に関するFAQ
退職届について、提出のタイミング以外にもさまざまな疑問を持つ方もいるでしょう。ここでは、退職届に関する4つの質問にお答えしているので、ぜひ参考にしてみてください。
書き出しを「私儀」として、退職理由、退職日を含めた本文を記載します。書類の提出年月日を記載し、所属部署と氏名を書いて捺印をしたら、最後に宛名を記載します。社長など、最高執行責任者が一般的です。退職届も退職願も会社指定のフォーマットがあれば、それに準じます。
退職願の書き方について詳しくは「退職届の提出日は退職日と同じ?日付や書かない場合についても解説!」でも紹介しているで、こちらもあわせてご覧ください。
退職届を書かなくても、退職の意思を明確に示せていれば退職できます。ただし、退職を「伝えた」「伝えられていない」といったトラブルを避けるためにも、退職届を正しく記載して提出するのが望ましいでしょう。
なかには会社によっては紙の退職届は不要で、電子申請書が設けられている場合もあります。退職の際の手続きは、就業規則を確認のうえ上司や人事に確認しておきしょう。
なお、会社都合の退職で退職届は不要です。退職届を提出してしまうと、自己都合退職として処理される恐れもあるため注意しましょう。会社都合の場合の退職届に関しては「会社都合のときに退職届は必要?自己都合退職との違いや書き方・例文も解説」で解説しています。
会社都合の場合は退職理由をどのように書くと良いでしょうか?
「業績不振に伴う事業の事業所廃止につき」「雇用契約終了のため」「早期退職のため」などの書き方が一般的です。なお、会社都合退職の場合、退職届を提出する必要がないとされています。
退職届の記載方法について第三者に相談したい方は、転職エージェントを利用するのがおすすめ。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、専任のキャリアアドバイザーがあなたの疑問にしっかりとお答えします。