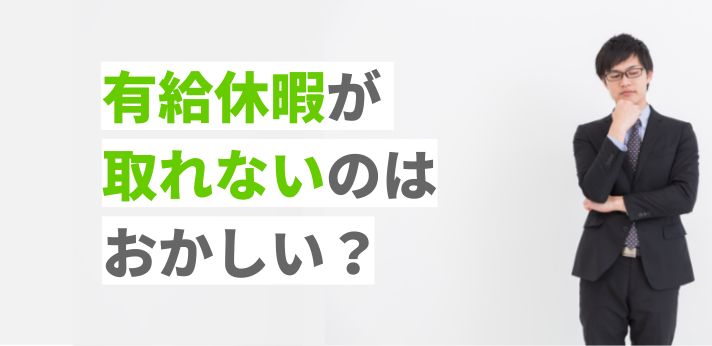休みが少ない仕事の目安は?きつい場合の対処法や転職先の探し方を解説休みが少ない仕事の目安は?きつい場合の対処法や転職先の探し方を解説
更新日
公開日
休みが少ない会社の年間休日数は、法律上の最低ラインである105日
「休みが少ない会社を辞めたい…」このように悩んでいる方もいらっしゃることでしょう。
このコラムでは、「休みが少なくてきつい」と感じたときの対処法や、業界によって異なる休日数などを解説します。休みが少ない会社にもメリットはあり、辞めないほうが良いこともあります。一方、健康面に支障がある場合には転職を検討したほうが良いでしょう。
転職活動のポイントも紹介しているので、休みが少なくてお悩みの方はご一読ください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
休みが少ないのは何日以下?年間休日の平均と最低ライン

「休みが少ない」と感じる休日数は人によって異なりますが、年間休日の最低ラインは法律で定められています。この項では、法律上の最低ラインをもとに、休みが少ないとは具体的に何日以下のことを指すのかを解説します。「今の会社は休みが少ないのかも…」とお悩みの方は参考にしてみてください。
厚生労働省
ハタラクティブ
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
105日は法律上の最低ライン
年間休日の最低ラインは105日です。「労働基準法」の「使用者は労働者に最低でも1週間に1日の休みを付与する」「1週間について40時間を超えて労働させてはならない」という定めに従うと、年間休日の最低ラインは105日の計算になります。
105日は平均的な休日数に比べると少ない
厚生労働省の「令和5年度就労条件総合調査」によると、1企業の平均年間休日総数は110.7日でした。労働者に与えられるべき最低限の休日数と平均年間休日総数の差は、5.7日です。
年間休日総数が105日ということは、年末年始や夏季休暇、大型連休といった休みはないことになります。お正月やお盆にまとまった休みが取れる会社が多いなか、年間休日数が105日の会社は「休みが少ない」といえるでしょう。
年間休日の平均
厚生労働省の同調査によると、労働者1人の平均年間休日総数は115.6日でした。
なお、従業員数が1,000人以上の大企業は平均年間休日総数が119.3日、300~999人の会社では117.3日、100~299人の会社は113.1日となっています。企業規模が大きいほど休日数が多い傾向にあるようです。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
休みが少ない仕事は何?業界ごとの年間休日数
年間の休日数が何日かは業界や会社、職種によって異なり、どのような職場でも同じ日数というわけではありません。ここでは、休みが多い仕事と休みが少ない仕事をそれぞれ紹介します。
平均よりも休みが多い業界
| 業界・業種 | 労働者1人平均年間休日総数 |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 122.5日 |
| 情報通信業 | 122.3日 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 121.6日 |
| 金融業、保険業 | 121.1日 |
インフラ業(電気、ガス、熱供給、水道業)
インフラ業に休みが多いのは、インフラを事業とする会社に大企業が多いのが要因の一つです。「年間休日の平均@」で解説したように、大企業は休みが多い傾向があります。
また、労働組合のある会社が多く、社員側が働きやすい環境を作れる風土も要因の一つといえるでしょう。取引先も大企業であることが多く、相手側に合わせて休みを取りやすいといった事情もあります。トラブル発生時には休日出勤になる場合もありますが、代休として平日にまとまった休みを取れる会社が多いようです。
情報通信業
情報通信業にはBtoB企業が多いといわれています。BtoBとは、企業を相手にした取引をする会社のことです。休みが少ないといわれるBtoC(個人を相手にした取引)の仕事に比べて、取引先に合わせて休みを取りやすい傾向にあります。
また、行政や公共事業に関わる大企業が多いのも年間休日数が多い理由の一つです。
学術研究、専門技術サービス業
学術研究、専門技術サービス業には企業や大学の研究職、弁護士のほか、経営コンサルタントやデザイナーなどが含まれています。研究職は、カレンダーどおりに休みが取れるのが一般的です。そのほかの職種は顧客に合わせて休めることから、年間休日数が多くなっているようです。
金融業、保険業
金融業、保険業はカレンダーどおりに休むのが一般的です。土日祝日や年末年始は、よほどのことがない限り休めることから年間休日数が多くなっています。
平均よりも休みが少ない業界
| 業界・業種 | 労働者1人平均年間休日総数 |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | 104.7日 |
| 運輸業、郵便業 | 107.8日 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 108.2日 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 111.8日 |
宿泊業、飲食サービス業
ホテルや飲食店は土日祝日や大型連休が繁忙期となるため、カレンダーどおりに休める職場は少ないのが実情です。そのため、宿泊業、飲食サービス業全体で年間休日数が少なくなっています。
また、自身のシフトが休みでも、職場に急な欠員が出たときに出勤をお願いされることもあります。本来休みの日に出勤をすることがあれば、必然的に休みが少なくなるでしょう。
運輸業、郵便業
運輸業は人手不足の影響で年間の労働時間が多くなっており、休日出勤も多いといわれています。また、年間を通して繁忙期が多いのも特徴です。
特に、トラックドライバーは、母の日やクリスマス、年末商戦といったインターネット通販の注文が増える機会が頻繁にあるため、まとまった休みが少ない傾向にあります。郵便業も年末年始は繁忙期でカレンダーどおりには休めないため、年間休日数が少ないようです。
生活関連サービス業、娯楽業
生活関連サービス業とは、クリーニングや家事代行などのことです。娯楽業は映画館や遊園地、理美容院などを指します。宿泊業と同様カレンダーどおりに休みにくいため、年間休日数が少なくなるようです。
鉱業、採石業、砂利採取業
鉱業、採石業、砂利採取業の主な職種は、現場作業員や重機オペレーター、営業や現場管理などです。人手不足のうえ工期が短い現場が多いことから休みが少ない仕事といわれています。
また、非正規雇用者においては日給制の場合が多く、出勤日数が多いほど収入アップになるため、休みを取らずに仕事をしたいと思っている人もいるようです。
休みが少なくても有給休暇を取得しやすい仕事もある
年間休日数は平均程度でも、有給休暇をきちんと取得させてくれる業界もあります。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況(6p)」によると、有給休暇の取得率が高かったのは複合サービス業(信用事業、保険事業、郵便局、農業協同組合など)74.8%、電気・ガス・熱供給・水道業73.7%、製造業65.8%でした。
一方で、有給休暇の取得率が低かったのは卸売業・小売業55.5%、教育・学習支援業54.4%、宿泊業・飲食サービス業49.1%です。飲食業は、年間休日のみならず有給休暇の取得率も低いために休みが少ない職業であると分かります。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
休みが少ない会社で働くデメリット
以下では、休みが少ない会社で働くデメリットを解説します。
有給休暇を取得しにくい場合がある
会社で定められた休みが少ない場合、有給休暇も取得しにくい傾向があるようです。たとえば3~4日程度の連続した休暇を取りたい場合、土日祝日が休みの会社では1~2日の有給休暇で済みますが、休みが少ない会社では3~4日ほど有給休暇を取得しなければならない可能性もあります。
そのような職場では、やむを得ない理由がない限り長期の連休を取りたいとは言い出しづらいでしょう。余暇を楽しむ時間が少なくリフレッシュできないことが、会社を続けにくくしている側面もあります。
疲れたりイライラしやすくなったりする
休みが少ないとイライラしやすくなったり、疲労が蓄積して「疲れやすくなった」と感じたりすることがあります。疲れた体のままで仕事をしていては集中力も持続せず、仕事の効率が落ちてしまうでしょう。
また、休みが少ないために疲労が蓄積すると、健康面にも支障をきたすことが考えられます。年齢を重ねるごとに体力ももたなくなり、過労となってしまう可能性もあるでしょう。
プライベートの時間が持てない
休みが少ないと、友人に会ったり趣味を楽しんだりする時間も減ってしまうでしょう。そうなると、休日は人と会ったり出かけたりするより、体力回復のために寝ていたいと思ってしまいます。翌日のことを考えて休息するのが優先になってしまい、貴重な休みも仕事のために費やすことが増えてしまうようです。
また、カレンダーどおりに休めない仕事の方は、家族や友人と休みが合わないことも多いでしょう。休みが少ないうえに土日祝日や年末年始が繁忙期になる場合、家族や友人とスケジュールを合わせられず徐々に疎遠になってしまう恐れがあります。
プライベートの時間を大切にしたい人は多い
ハタラクティブの調査「
若者しごと白書2024」によると、「仕事で一番大切にしている価値観」の回答で最も多いのは、「プライベートを大切に働けること」でした。正社員は37.7%、フリーターは41.3%の人が、プライベートを大切にしながら働きたいと考えているようです。この結果から、「仕事をするうえでプライベートの時間も大事にしたい」と考えている人が多くいることが分かるでしょう。
休みが少ない会社にはメリットもある
休みが少ない=デメリットと考えがちですが、休みが少ない会社にもメリットはあります。以下のメリットが今の仕事に当てはまるかどうか、考えてみましょう。
収入アップにつながる可能性がある
休みが少ない仕事は、時給制や日給制で働く人にとっては収入アップにつながる可能性があります。自身が休日でも会社は営業しているため、希望すれば出勤できることもあるでしょう。
また、歩合やインセンティブがある仕事なら、働く時間を増やすことで成績アップを実現できる可能性もあります。「休むよりも稼ぎたい」という人にとっては、休みが少ないのはメリットとなるようです。
早期のスキルアップにつながる可能性もある
休みが少ない仕事では、勤務日数が人よりも多くなる分多くの仕事に携わるチャンスに恵まれたり、仕事と向き合う時間が長くなったりするため、早期のスキルアップにつながる可能性があります。働きながらスキルアップを目指したいという方にとっては、休みが少ないことがチャンスになる場合もあるでしょう。
計画的に仕事ができる
休みが少ない業界は残業が発生しにくく、計画的に仕事をしやすい側面があります。宿泊業や運輸業のように繁忙期があらかじめ分かっている仕事は、忙しくなるのを見越して仕事を進められるでしょう。
突発的な残業にストレスを感じる方は、休みが多く残業が発生しやすい仕事よりも、今の職場のほうが合っている可能性があります。
休みが少ない会社できついと感じたときの対処法
最低限の休みだけでは体がもたない、仕事がきついと感じ始めたら、早めの対策が必要です。ここでは、休みが少ない会社できついと感じたときの対処法をご紹介します。
休みが少ない会社できついと感じたときの対処法
- 勤務時間を調整してもらう
- 会社に待遇改善を相談する
- 閑散期に休暇を取得する
- 年間休日120日以上の会社に転職する
勤務時間を調整してもらう
休みが少ないことで心身に不調をきたしている場合は、勤務時間を調整してもらえるよう上司に相談しましょう。仕事量や勤務時間の影響で心身の不調があることを伝えれば、体に負担がかからないようある程度調整してもらえる可能性があります。残業が多い場合は、業務量を見直して残業を減らせないか検討をお願いしましょう。
会社に待遇改善を相談する
直属の上司に言いにくい、または相談しても勤務時間が調整できない場合は、人事部に相談するのも一つの方法です。人事部への相談は人間関係やハラスメントの問題だけでなく、休日や勤務時間に関する相談も受け付けています。
また、会社の休日日数が最低ラインの105日を下回っていて明らかな違法性がある場合は、労働基準監督署へ相談するのも手です。ただし、労働基準監督署に相談する場合、対応までにある程度時間がかかる点に注意しましょう。
閑散期に休暇を取得する
閑散期のタイミングを狙って有給休暇を使い、リフレッシュするのもおすすめです。有給休暇を取得する理由は「私用のため」として、旅行や趣味に使っても良いとされています。「仕事がきつい」という状態のまま働き続けるより、有給休暇を取得して気持ちを切り替えたほうが仕事を続けやすくなるでしょう。
年間休日120日以上の会社に転職する
一般的に休みが多いといわれる会社は、年間休日数が120日以上あります。休みが120日あると、土日祝日のほか夏季休暇や年末年始の休みもあり、ゆとりを持って働けるでしょう。さらに有給休暇も加えると、旅行や趣味にも時間が使えることになります。
休みが少ないために「きつい」と感じているなら、このような優良企業へ転職するのも対処法の一つです。
なぜ休みが少ない会社が存在するのか
会社の休みが少ないことの原因には、人手不足が常態化している、昔ながらの風習を守っているといったことが挙げられます。また、社員よりもアルバイトが多い会社では、アルバイトの急な欠勤やトラブルの対処などに呼ばれやすく、休日出勤を余儀なくされて結果的に休みが少なくなってしまうことがあるでしょう。
休みが少なくても辞めないほうが良いケースもある
休みが少ない会社でも、やりたい仕事をやれる環境だったり、待遇が良かったりする場合は、今すぐ辞めないほうが良い可能性があります。休みが少ないのを理由に転職活動を始める前に、本当に今の会社を辞めたほうが良いのか検討しましょう。
仕事内容には満足している
「子どものころからの夢が叶った」「キャリアプランに合った仕事ができている」と仕事内容に満足している人は、休みが少ない会社でもすぐには辞めないほうが良いでしょう。転職してやりたい仕事ができなくなった場合に、「やっぱり前の仕事のほうが良かった」と後悔する恐れがあるからです。
休みが少ないことがどうしてもストレスに感じるなら、「3年は続ける」「資格が取れたら辞める」など、転職のタイミングを決めておくと良いでしょう。
給料や福利厚生が充実している
「休みが少ない=給料が安い」とは限りません。休みが少ない会社でも給料が良く、福利厚生も充実しているケースもあります。その場合は、今すぐに辞めるのは控えたほうが良いでしょう。転職によって年収が下がる可能性があるからです。
住宅手当や扶養手当で生活費をまかなっている人は、引っ越しせざるを得なくなったり、食費を節約しなければならなかったりすることも考えられるでしょう。特に、結婚や住宅購入を考えている場合は、条件の良い転職先が見つかるまで今の会社を辞めないのがおすすめです。
良好な人間関係を築いている
今の職場で良好な人間関係を築けている方も、すぐに辞めないほうが良いでしょう。ハタラクティブの「若者しごと白書2024」によると、正社員が転職活動を始めたきっかけの第3位に「人間関係」が挙げられています。
人間関係が良好であることは、仕事を続けるうえで重要なポイントといえるでしょう。転職先の人間関係が自分に合わなかった場合、早期離職となる恐れもあります。休みが少ない会社でも仲間と仕事をするのが楽しいと思えるなら、辞めないほうが良い可能性もあることを念頭に置きましょう。
休みが多い仕事に就こう!転職活動の5つのポイント
休みが少ない会社を辞めて転職する場合、転職理由の明確化や業界の選び方など、いくつかのポイントがあります。この項では主な5つのポイントを紹介するので、転職活動の参考にしてみてください。
転職活動のポイント
- 「週休2日制」と「完全週休2日制」に注意する
- 休みを増やしたい理由を明確にする
- 休みが多い業界や職種を選ぶ
- 今の仕事を辞める前に転職活動を始める
- 転職エージェントを活用する
1.「週休2日制」と「完全週休2日制」に注意する
求人情報サイトで企業の休日数を確認するとき、「週休2日制」と「完全週休2日制」の違いに注目しましょう。一見するとどちらの企業にも週に2回の休みがあるように思えますが、意味は全く異なります。
完全週休2日制は毎週必ず2日以上の休みがあるのに対し、週休2日制は「1ヵ月間に週2日の休みが最低1回はある」という意味です。そのため、週休2日制と記載されている求人は休みが少ない会社である可能性があります。
年間休日数を条件に入れて検索しよう
求人サイトで休みが多い会社を探す場合は、職種や勤務地だけでなく「年間休日数」を条件に入れましょう。休みが多い会社を選ぶ場合は「年間休日120日以上」「完全週休2日制」と書かれている会社を選ぶのがおすすめです。
2.休みを増やしたい理由を明確にする
休みが少ない会社を辞めて転職する際は、「なぜ休みを増やしたいのか」を明確にする必要があります。面接で「休みが少ないこと」だけを転職理由に挙げたとしても、選考を突破するのは難しいでしょう。「休みが多い会社ならどこでも良いのでは」と思われかねません。
「自己研鑽の時間が欲しい」「仕事もプライベートも大事にしたい」など理由を明確にして目的意識を持つことで、自分に合った転職先を見つけやすくなります。
3.休みが多い業界や職種を選ぶ
「平均よりも休みが多い業界@」で解説したとおり、休みが多い業界にはインフラ業や情報通信業、金融業などがあります。休みが少ない会社から転職するなら、これらの業界を選ぶのが良いでしょう。
ただし、転職成功のためには今までの職歴やスキルを活かすのも大事です。休みが少ない業界で働いている場合、休みが多い業界に必要なスキルが身についていない可能性もあるでしょう。
そのような場合は、経験のある職種を選んで異業界への転職を試みるのがおすすめです。たとえば、営業や経理といった職種はどのような業界でも存在するため、異業界でも転職しやすいといえます。
4.今の仕事を辞める前に転職活動を始める
「休みが少ないから辞めたい」と思っても、勢いで辞めるのは避けたほうが無難です。休みが多い転職先がすぐに見つかるとは限らないので、今の仕事を辞める前に転職活動を始めるのが良いでしょう。
先に会社を辞めた場合、転職活動が長引いたときに焦って結局休みが少ない会社に就職してしまう恐れもあります。後悔しない転職をするためには、今の仕事と転職活動を両立させるのがおすすめです。
5.転職エージェントを活用する
「効率的に転職活動を進めたい」という人には、転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは求人探しや面接の日程調整などを代行してくれるため、今の仕事を続けながら転職活動も進められます。
休みの多い企業をどのように探せば良いか分からないとお悩みの方は、就職・転職エージェントのハタラクティブをご利用ください。あなたの希望に合わせて年間休日数が多めの会社や、休みが多いといわれる業界の求人をお探します。さらに、転職理由の答え方や志望動機の書き方などを、専任のアドバイザーがマンツーマンでサポート。プロのサポートを受けることで、今の仕事が忙しくても効率的に転職活動を進められます。サービスはすべて無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
休みが少ないと感じている人のお悩みを解消するQ&A
ここでは、「休みが少ない仕事を辞めたい」といったお悩みをQ&A方式で解消します。
退職理由を「休みが少ない」とする場合の例文を知りたいです
面接では、「前職では毎月80時間以上の残業が常態化していて、スキルアップのための勉強時間の確保が困難だった」というように、具体的な労働時間や環境を変えたい必然性を伝えるのがコツです。退職理由を「休みが少ないから」と伝えると、「労働意識が低い」とマイナスイメージを持たれる可能性があるので注意しましょう。
詳しくは、「転職理由別の例文紹介!好印象を与えるためのポイントをおさえよう」のコラムを参考にしてみてください。
休日数が法律の基準を満たしていない場合の対処法を知りたいです
制度上は法律で定められた休日数があっても、実際には休日出勤が多く年間休日数が105日に満たないことが続くなら、労働基準監督署に相談するのも方法の一つです。休日数が最低ラインを満たしていない場合、法律に違反したブラック企業の可能性があります。
「仕事を休めないのはおかしい?休みがとれない原因や対処法を紹介」で労働基準法について解説していますので、参考にしてください。
休みが少なくて疲れた…休日の多い大企業に転職すべき?
休みが多いのは大企業ばかりではありません。休みが多い会社に大企業が多いのは事実ですが、中小企業のなかにも休みが多い会社はあります。「休みが少ない仕事は何?業界ごとの年間休日数@」で紹介したとおり、インフラ業や情報通信業といった業界を選べば、会社の規模が小さくても休みが多い可能性があるでしょう。
「休みが多い会社へ転職したい」とお考えなら、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。就活のプロであるキャリアアドバイザーが、あなたの悩みに寄り添いながら内定獲得に向けてサポートいたします。