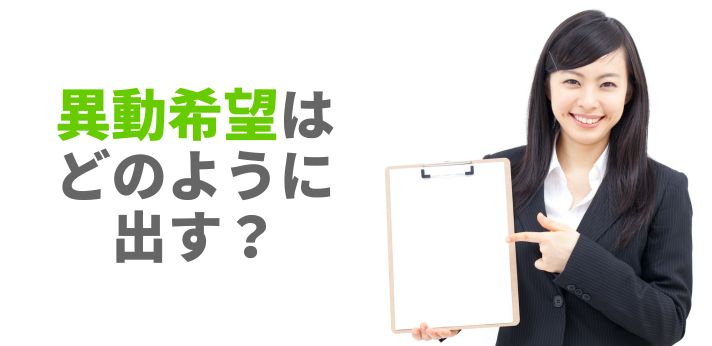なぜ副業禁止の企業があるの?具体的な理由と法律的な側面を解説なぜ副業禁止の企業があるの?具体的な理由と法律的な側面を解説
更新日
公開日
「なぜ副業禁止なのか」という理由には、長時間労働や情報漏えいリスクの回避にある
「収入を増やしたい」「本当にやりたい仕事をしたい」といった理由で副業に携わる人がいるなかで、副業禁止とする企業もあるのが実情です。なぜ副業を禁止するのかは、企業の方針によって異なります。このコラムでは、企業が副業を禁止する理由や、労働者が副業をするメリットをご紹介。副業禁止に関連する現状を掴みながら、今後の働き方を見つめ直してみましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
なぜ副業は禁止される?4つの理由
副業禁止とする企業は、副業を行うことで社員の長時間労働につながったり、本業に影響が出たりすることを懸念しています。また、副業によって企業機密などの情報が漏洩する可能性があるのも、禁止とする理由といえるでしょう。
副業禁止の理由
- 社員の労働時間を把握できないから
- 生産性に支障をきたすおそれがあるから
- 情報漏洩などのリスクがあるから
- 転職や独立による人材流出を防げるから
1.社員の労働時間を把握できないから
副業は、本業を終えたあとや休みの日に行うことになります。副業をする社員は、本業とは別に働いている時間が増えるのが現状です。
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」によると、「労働時間は異なる事業場であっても通算する」と記載されています。本業の「1日8時間、1週間40時間」に加えて副業の時間が発生すると、実際は長時間労働になるといえるでしょう。しかし、副業について詳細に申告する社員は少なく、労働時間の管理や把握が困難なため、禁止している企業もあるようです。
2.生産性に支障をきたすおそれがあるから
副業により労働時間や体力、精神的な負担が増加することで、本業の生産性が低下するおそれがあります。特に副業が長時間に及ぶ場合、睡眠不足や疲労が蓄積し、本業の効率が悪くなってミスが増えたり仕事の質が低下したりする可能性は高いでしょう。
また、副業がストレスの原因となり、職場でのコミュニケーションやモチベーションに悪影響を及ぼし、結果としてチーム全体の生産性に支障をきたすことを懸念する企業もあるようです。
3.情報漏洩などのリスクがあるから
本業で身につけた知識やスキル、顧客情報などを副業で利用されると、情報漏洩のリスクが生じます。また、意図的でなくても副業をカフェや図書館などの場で行うと、パソコンの画面を見られ知らないうちに情報が漏れていることも。情報漏洩は企業にとって大きなダメージとなりかねません。
4.転職や独立による人材流出を防げるから
企業にとって人材は重要な資産であり、これらの人材がほかの職場に移ったり独立したりすることは、損失となります。
副業を通じて社員が新たなスキルや知識を得ることで、転職や独立のために辞めてしまう可能性も。たとえば、副業で成功体験を得たり、新しい分野での専門知識を習得したりすると、「現在の職場を離れてより魅力的な職場に転職したい」という意欲が湧くこともあるでしょう。これにより、企業は優秀な人材を失うリスクに直面します。
契約社員は副業してもいい?
契約社員が副業をしても良いかどうかは、会社の就業規則によって異なります。契約社員も正社員と雇用形態は異なるものの、就業時間の減少や情報漏洩など懸念し、副業を禁止している企業もあるようです。「契約社員は副業できる?」と疑問に思う方は「
契約社員は副業しても大丈夫?注意点や雇用形態の定義などを解説」をご一読ください。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
禁止は違法?日本国憲法と労働基準法から見る副業
日本では職業選択の自由が保障されており、副業についても職業選択の自由と捉えられます。また、「仕事を複数もつこと」も、法律上は禁止されていません。そのため、副業を行うことは、憲法で保障された職業選択の自由の一部といえるでしょう。
日本国憲法の「第二十二条」によると、「公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」とあります。なお、労働基準法においても、副業の禁止を明確に規定している条文はありません。
したがって、副業に関する制約は、基本的には企業の就業規則や契約に依存することになります。しかし、就業規則が法律によって保障されている基本的な権利を侵害する場合、その正当性を問われる可能性もあるでしょう。
副業解禁された公務員に禁止されていることとは?
国家公務員の場合は、国家公務員法の「
第百三条」によって、営利企業(一般企業)の役員や社員、企業を経営することは禁止されています。
地方公務員の場合は、知事や市区町村長といった任命権者の許可が下りれば、営利企業の関係者として副業が可能なようです。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
近年では副業禁止ではなく解禁の姿勢も見られている
近年では、副業を許可する会社も増えている傾向にあります。これは、2018年に改定された「モデル就業規則」が影響しているためです。「モデル就業規則」とは国が定める就業規則の基本のようなもので、時代背景などを踏まえて改定されます。
国が推し進める働き方改革や多様な働き方の影響から、2018年の改定でこれまで「副業禁止」だった内容が「副業OK」に変わったため、多くの企業もこれに倣って変更したと考えられるでしょう。
正社員が副業をする3つのメリット
副業をすることで収入が増えます。また、本業では身につけられないスキルや経験を得たり、本当にやりたい仕事ができるという満足感を得たりできるのも、副業のメリットといえるでしょう。
1.収入の増加
頻度や内容にもよりますが、働くことに変わりないため副業を行うほうが収入を増やせるでしょう。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の「副業者の就労に関する調査」によると、副業をする目的で最も多かったのは「収入を増やしたいから」で、割合は33.7%でした。
| 副業を行う理由 | 割合(単一回答) |
|---|
| 収入を増やしたいから | 33.7% |
| 1つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができないから | 26.2% |
| 自分が活躍できる場を広げたいから | 6.2% |
| 時間のゆとりがあるから | 4.8% |
| 副業のほうが本当に好きな仕事だから | 4.3% |
また、「1つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができないから」といった回答も26.2%と割合が高く、副業をする方の半数以上が収入アップを目的にしていることが分かります。
参照元
独立行政法人労働政策研究・研修機構
記者発表
2.スキルアップ
もともともっている専門的スキルの向上ができたり、本業とは全く異なる仕事内容でスキルアップが叶ったりと、副業が自己研鑽につながることもあるでしょう。
また、仕事を複数担当することで、タイムマネジメントや問題分析、コミュニケーション、マルチタスクといった汎用的なスキルの向上につながる可能性もあります。
3.生活満足度の向上
副業で本当にやりたいことや好きなことを仕事にできると、生活満足度が向上する可能性も考えられるでしょう。また、「本業で万が一が起きても副業がある」という安心感やリスクヘッジも、副業を行うメリットになります。
副業禁止の規則に違反したらどうなる?
副業について許可されていない企業で副業を行っても、就業規則に副業および違反した場合の規定がなければ処分を受けることはありません。口頭で注意を受ける程度で終わることもあるようです。
就業規則違反の場合は状況によって処分が異なる
就業規則に違反した場合の規定や処分についての記載がある場合は、処分が課されることが一般的です。処分の内容は「戒告・けん責」から「懲戒解雇」まであり、違反内容によって処分が決定されます。
ただし、解雇にならないとしても、会社内での信用を失えば安心して仕事をまかせられないと思われ、本業の仕事に支障をきたす可能性があるでしょう。
副業が会社にバレる原因
ここでは、副業が会社にバレる原因について解説します。トラブルを避けるためにも、なぜ副業が発覚してしまうのかを知っておきましょう。
税金の増加
企業に黙って副業を行っても、税金の額からバレる可能性があるでしょう。特に、副業収入が「給与所得」の場合は、給与所得の合算額で計算する住民税などから発覚します。
副業の利益が20万円以下の場合はバレない?
副業の利益が20万円以下の場合も、会社に隠し通すのは難しいでしょう。住民税は給与から天引きされるため、副業の収入があると住民税が増え、会社に気づかれる可能性があります。住民税を「普通徴収」に変更しても、申請手続きが必要なため完全に隠せる保証はありません。そのため、副業禁止の会社で黙って副業をすることはリスクが高く、完全に隠し通すのは困難です。
ハタラクティブキャリアアドバイザー
後藤祐介からのアドバイス
このような事例は副業に該当する?
副業とは、本業とは別に収入を得るために行う仕事のことを指します。これは、主な収入源を補完するために行われるものであり、具体的な法律や定義は存在しません。この項では、副業に該当する可能性があるかどうかを事例別に解説します。
フリマアプリやオークションへの出品
フリマアプリやオークションへの出品は、副業に該当する場合があります。定期的に売買を行い、その収入が一定の額を超える場合には、副業と見なされることがあるようです。
ただし、一度きりの出品や不用品の処分程度であれば、副業とは見なされないこともあるでしょう。収入の規模や頻度に応じて、副業かどうかが判断されます。
文筆業
文筆業は、副業に該当することもあるようです。「本業の勤務時間外に執筆活動を行い、その対価として報酬を得る」「継続的に記事や本を執筆し収入が一定額を超える」といった場合は、副業と見なされます。給与所得者の場合は、文筆業から得た年間所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
ただし、具体的な状況によって副業に該当するかどうか異なるため、税務署や専門家に相談することが望ましいでしょう。
制作物の販売
製作物の販売も、文筆業と同様に副業と見なされることがあります。たとえば、手作りのアクセサリーや雑貨などをオンラインで販売するケースが該当。給与所得者の場合は、年間の製作物販売による所得が20万円を超えると確定申告が必要になる点も文筆業と同様です。
不動産や株式への投資
不動産や株式への投資は、一般的には副業に該当しません。しかし、特定の条件下では副業と見なされることもあるようです。たとえば、不動産投資として、複数の物件を所有し賃貸業として継続的に運営したり、賃貸管理に時間を割いて実質的に事業として行ったりしている場合は、副業と見なされる可能性があります。
また、株式投資として、「株式の売買を頻繁に行いデイトレードのように日常的に活動している」「投資による収入が主な収入源となり安定的に高額である」といった場合も、副業と見なされることがあるので注意しましょう。
副業をしたいときはどうする?
副業を検討するなら、まず会社が定める就業規則をチェックする必要があります。会社と労働者のルールを定めるのが就業規則で、互いにそのルールを守ることで、雇用主と労働者のトラブルを防ぐことにつながるでしょう。副業について「許可制と書かれている」「特に何も規定がない」といった場合は、上司や人事に相談するのが無難です。
副業をしたいときはどうする?
- 就業規則をよく確認する
- 健康状態と勤務時間の管理に
- 確定申告の必要性を理解する
就業規則をよく確認する
副業を始める際には、企業の就業規則をよく確認しましょう。一般的には、企業や組織は従業員に対して副業に関する特定の規定を設けているからです。就業規則には、副業に関する禁止や制限、申請手続き、競業禁止条項、機密保持に関する規定などが含まれる場合があります。
競業禁止条項は、自身の副業が会社の業務や競合他社の業務に干渉する可能性がある場合に問題となることがあるようです。また、機密情報や知的財産権の保護についても就業規則で明確にされていることがあります。
健康状態と勤務時間の管理に気を配る
副業を始める際には、健康状態と勤務時間の管理に気を配ることが重要です。副業を行うと収入やスキルを向上させられる一方、身体的・精神的な負担が増える可能性があります。過労やストレスを避けるために定期的に体調をチェックし、適度に休息を取るようにしましょう。また、効率的に時間を管理し、無理のないスケジュールを立ててバランスを保つことも大切です。
確定申告の必要性を理解する
副業を始める際には、確定申告の必要性を理解しておきましょう。給与所得者の場合、副業で得た年間所得が20万円を超えると確定申告が必要です。確定申告を行うことで、適切に税金を納め、税務署からの指摘やペナルティを避けられます。心配な場合は、税理士や公認会計士などに相談すると良いでしょう。
副業を始める際に注意すべきことを知りたい方は、「副業をする会社員が注意したいこと」のコラムもご一読ください。副業のメリットや始める際の注意点、副業が会社に見つかる理由をご紹介します。
副業以外の方法も!収入アップを目指すなら
収入アップが目的の場合は、副業を許可する企業に転職するほか、収入アップが狙える企業に転職するのもおすすめです。
副業OKの企業に転職する
「本業にするのは難しいけど、やりたい仕事がある」という場合は、副業OKの企業に転職しましょう。前述のとおり、副業禁止の会社で隠れて副業を行っても、税金通知からバレる可能性があります。就業規則違反になれば処分対象となるため、「どうしても副業をしたい」という場合は、許可されている企業で働くのがおすすめです。
副業を就活の軸とするのは避けよう
副業をしたいことは決して悪いことではありません。しかし、副業を就職・転職活動の軸にして入社しても、仕事内容や社風などが自分の価値観と合わず早期離職すると、その後の転職活動に影響が出る可能性もあります。
そのため、副収入を稼ぐことよりも、本業として収入を上げることが重要です。就職・転職活動の軸を定め、そのうえで副業が許可されている企業を探しましょう。
納得のいく収入を得られる会社に転職する
副業を許可している会社を探すほかに、自分が満足できる収入を得られる企業に転職する方法もあります。1つの会社で懸命に働き、満足できる収入を得ることで、やりがいにつながるといえるでしょう。プライベートと仕事のバランスがとりやすいといったメリットも魅力です。
「初めての転職活動で何から始めて良いのか分からない」「なかなか内定が獲得できない」といった悩みを抱えている場合は、転職活動のプロに相談しながら転職を進めるのがおすすめ。
就職・転職エージェントのハタラクティブは、若年層に特化した転職支援サービスです。キャリアアドバイザーが、一人ひとりの希望や状況に沿った求人をご提案します。志望動機の書き方や面接対策などもアドバイスするので、初めて転職する方も安心です。サービスはすべて無料なので、転職をお考えの方はぜひご相談ください。
副業禁止に関するQ&A
ここでは、副業禁止に関する質問にQ&A方式でお答えするので、ぜひ参考にしてみてください。
企業が就業規則に「副業禁止」の条項を設けることは違法ではありません。就業規則は各企業が独自に定める社内ルールであり、法的規制を直接受けるものではないからです。また、法律上「就業規則で副業を禁止してはならない」という規定も存在しません。
「正社員の副業は法律違反?」「副業禁止の会社でバレるとどうなるの?」と疑問に思う方は、「正社員は副業してOK?働く際の注意点と確定申告の基礎知識」のコラムもチェックしてみてください。会社が正社員の副業を禁止する理由や、バレるとどうなるかをご紹介します。
企業が副業を禁止することで、従業員は本業に集中しやすくなり、生産性が向上します。また、過重労働や副業による機密情報の漏えいリスクが低下し、労務管理もしやすくなるでしょう。詳しくは、本コラムの「なぜ副業が禁止される?4つの理由」を参考にしてみてください。
「従業員の不満やモチベーション低下」「優秀な人材の流出」が挙げられます。副業を許可しないことで、従業員の自己成長や満足度が損なわれ、企業にとって有益な人材が退職する可能性も考えられるでしょう。従業員が副業で得たスキルは、本業で発揮できる場合も考えられるので、副業を禁止しない企業も増えているようです。
転職サイトで「副業OK」の求人を探したり、転職エージェントで副業可能な求人の紹介を受けたりすると、効率的な仕事探しができます。転職エージェントを利用を検討している方は、若年層に特化したハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブでは、プロのアドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを行い、あなたに合った求人をご提案します。