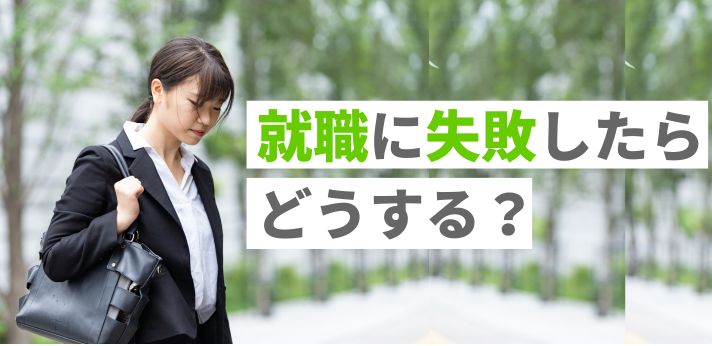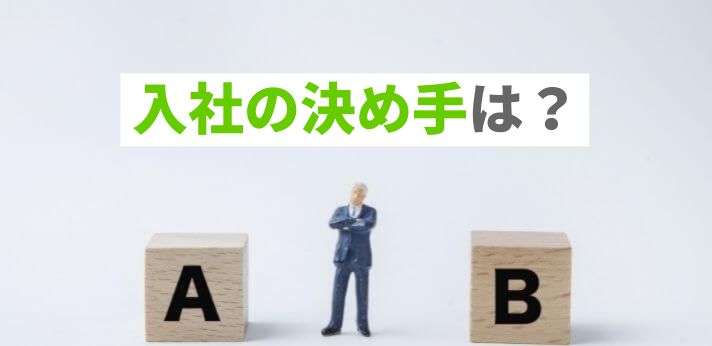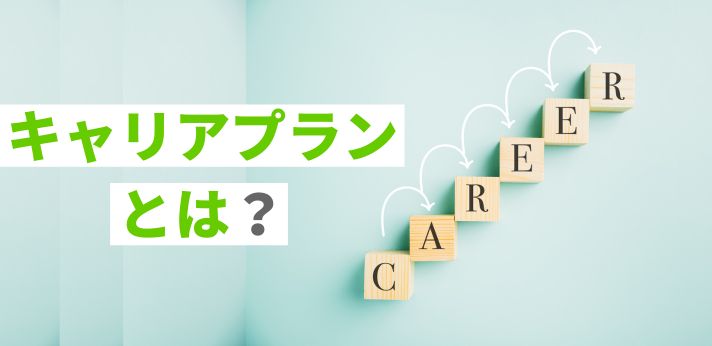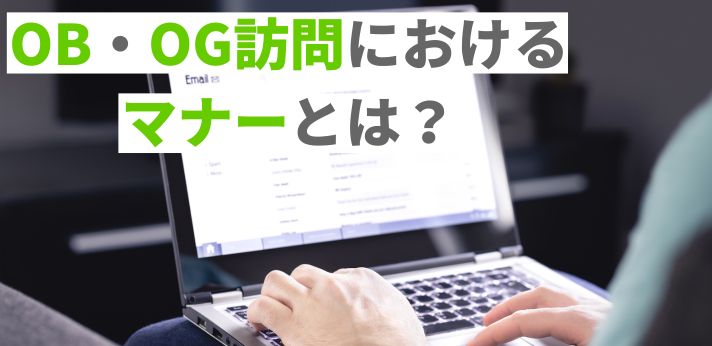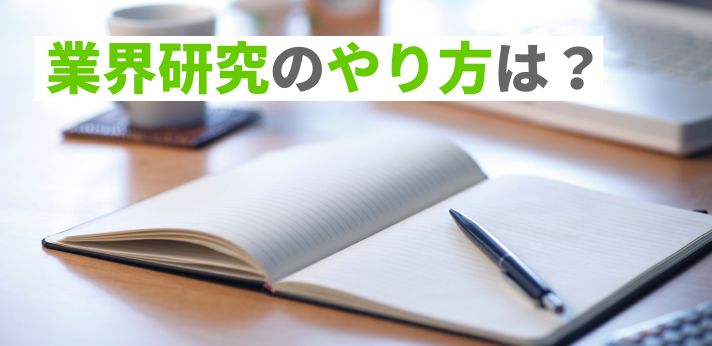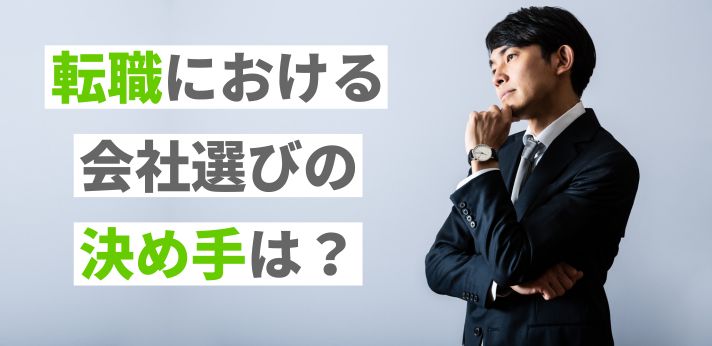就職先が決められないときはどうする?企業の選び方や注意点を紹介!
更新日
公開日
就職先が決められないときは、原因を明確にして対策をとるのがおすすめ
「就職先が決められない…」と悩んでいる方もいるでしょう。決められない理由には、希望条件が絞られないことや、複数内定によって承諾に迷うことなどがあります。いずれにしても、原因を明確にし、自己分析や企業研究などの対策を練るのが大切です。
このコラムでは、就職先が決められない理由の一例や迷ったときの対処法を紹介します。また、仕事を決めるときの注意点も解説するので、就職先選びの参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
就職先が決められない人の状況
就職先が決められないと悩んでいる人の状況は、大きく2種類に分けられます。一つは、応募する企業が決められないエントリー前の段階、もう一方は内定を獲得したものの承諾に迷っている状態です。
以下では、就職先が決められない人の状況について詳しく解説するので、自分に当てはまるかどうか確認してみてください。
就職先が決められない人の状況
- 就活前にエントリー先が決められない
- 複数内定をもらい承諾が決められない
就活前にエントリー先が決められない
いざ就活を始めようと思っても、「どうやってエントリー先を選ぶべきか分からない」という人もいるでしょう。求人サイトには多数の業界や職種の募集があり、どれが自分に合いそうかを見極めるのは大変です。
このような場合は、自己分析をしっかりと行う必要があります。自分の価値観や得意なことを明確にすれば、就職先を選ぶ基準が分かるでしょう。
複数内定をもらい承諾が決められない
就活が順調に進み、内定をもらった段階で迷う場合もあります。特に、複数の企業から内定が出た場合、選ぶのに苦心することもあるでしょう。
どの企業も志望度が高いと、一つに絞るのが難しくなってしまいます。逆に、「内定が複数出ているけど、第一志望の会社に落ちてしまった」「内定が出た会社に魅力を感じられず就職先を決められない…」という場合も。就職は人生の大きな決断なので、「本当にこの会社で良いのだろうか」と迷うのも当然でしょう。
こうした迷いを解消するためには、まず自分の価値観や働き方の優先順位を整理することが大切です。さらに、企業の情報を改めて確認し、社風や成長性、実際の業務内容を再評価してみてください。
第三者の意見も参考にしてみよう
内定の承諾に迷ったときは、家族や友人に意見を聞いてみるのもおすすめです。第一志望の企業の内定を得られても、いざ承諾を目の前にすると、冷静な判断が難しいこともあるでしょう。家族や友人が指摘してくれることで、本来の目的や優先順位を思い出す場合もあります。そのうえで、最終的には自分で決めることが大切です。
一人で決断するのが難しい場合は、ハローワークや就職エージェントに相談してプロの意見を聞くのもおすすめ。不安な方はハタラクティブにぜひご相談くださいね。
ハタラクティブキャリアアドバイザー
後藤祐介からのアドバイス
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
就職先を決められない原因
就職先が決められないときは、まずは自分自身の企業選びを見直してみましょう。志望業界や志望企業が定まらないまま、やみくもに選考を受けたせいで就職先を決められなくなっている可能性があります。また、自分自身で志望度が分からなくなり、どの企業で働きたいのか決められないという場合もあるでしょう。
そのようなときは、なぜ就職先を決められないのかを考えてみるのがおすすめです。原因が分かれば、今何をすべきかが明確になります。
以下では、就職先が決められない理由の一例を紹介するので、参考にしてみてください。
就職先を決められない原因
- 仕事の選び方を理解できていない
- 希望条件が明確になっていない
仕事の選び方を理解できていない
世の中には数多くの仕事が存在するので、選び方が分からないと就職先が決まらない場合があります。
選択肢が豊富なぶん、仕事選びの基準を明確にもっていないと、自分に合う就職先を選ぶのは困難になる恐れがあります。
希望条件が明確になっていない
希望条件をいくつか挙げていたものの、優先順位があいまいだと就職先が決められない場合があります。求人サイトを見ても、「A社は給料が良いけれど、仕事内容はB社が良い」というように、決められなくなることも。
複数社から1社を選ぶ必要がある場合は、「最も優先したい希望条件は何か」を明確にすることで、入社後のミスマッチを防げる可能性があります。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
就職先が決められない原因別の対処法
ここでは、就職先が決まらない原因別に、それぞれの対処法を紹介します。以下を参考に、自分に合った対処法を選んでみてください。
仕事の選び方が分からない場合
仕事の選び方が分からず就職先が決められない場合は、自己分析をしたり希望条件を明確にしたりすることが大切です。
自己分析をする
自己分析とは、自分の人生や経験を振り返り、長所や短所、得意なこと・苦手なことなどを明確にする作業です。自己分析によって自分の強みが分かれば、向いている仕事や自分に合う就職先を見つけやすくなります。
自己分析が難しいと感じている人は、適職診断ツールや就職支援サービスを利用するのもおすすめです。
希望条件を明確にする
仕事の選び方が分からないときは、希望条件を明確にしてみましょう。就職先に求める条件がはっきりすれば、仕事を選びやすくなります。希望条件の決め方が分からない場合は、ハタラクティブの「若者しごと白書2025」に掲載されているデータを参考にしてみてください。
以下の表は、「仕事選びで最も重視していること」を尋ねたアンケート結果をまとめたものです。
上位5位までを抜粋
※回答者数:フリーター1,000人、正社員1,000人
| | フリーター | 正社員 |
|---|
| 1位 | 希望する仕事内容かどうか(31.6%) | 希望する仕事内容かどうか(31.9%) |
|---|
| 2位 | 理想的な勤務時間(固定勤務制やシフト制)や
休日数か(12.7%) | 希望する収入が得られるか
(20.0%) |
|---|
| 3位 | 希望の労働時間で働けるか(12.3%) | 理想的な勤務時間(固定勤務制やシフト制)や
休日数か(7.7%) |
|---|
| 4位 | 社風や職場の雰囲気が合うか(11.7%) | 希望の労働時間で働けるか(7.3%) |
|---|
| 5位 | 希望する収入が得られるか(10.6%) | 社風や職場の雰囲気が合うか(6.3%) |
|---|
上記のデータを見ると、フリーター・正社員ともに、仕事を選ぶときは仕事内容を重視する人が多いようです。そのほか、労働時間や休日数、収入などを大切にしている人も多くいます。
就職先が決められない高校生や大学生はどうする?
社会人経験のない学生の場合、就職先が決められないのも無理はありません。なかにはアルバイト経験のない人もいるので、仕事のイメージを掴みにくいこともあるでしょう。
まずは、興味のあることを書き出したり、将来どんな人になりたいかを考えてみたりすることから始めてみてください。また、高校生なら担任の先生、大学生は学校の就職課に相談して、アドバイスを受けるのもおすすめです。
どの会社にも良いところがある場合
どの会社にも良いところがあって就職先が決められない場合は、企業研究を深めたり、キャリアプランを明確にしたりしましょう。
企業ごとの長所・短所を書き出す
2社以上の企業から内定をもらったものの、それぞれに良い部分があって「どっちが良いか選べない」という場合は、改めて企業研究をしてみましょう。Webサイトを比較したり、面接で受けた印象をまとめたりするなど、企業ごとの長所と短所を整理し直すと、自分が本当に行きたい会社が明確になる可能性があります。
キャリアプランを明確にする
どの企業にも良いところがある場合は、キャリアプランを明確にすることも大切です。自分が5年後10年後にどうなっていたいのかを考えれば、「どの会社であれば夢の実現につながるのか」という視点で就職先を選ぶことができます。
どの会社にも入社への熱意をもてない場合
どの企業に対しても決定打がない場合は、原因と向き合い、改めて検討するのがおすすめです。なんとなくで決めてしまうと、入社後に後悔する可能性もあります。早期離職は次の転職にも響くので、納得のいくまで検討を重ねるのが望ましいでしょう。
不安の原因を分析する
「自分にできる仕事なのか自信がない」「人間関係が悪かったらどうしよう」などの理由で就職先を決められない場合は、不安の原因を分析しましょう。
たとえば、営業職に対して「ノルマが厳しい」というイメージがあり、自分にできるのか不安になっているとします。その場合、不安の原因は応募先企業や営業職にあるのではなく、ノルマにあるということが分かるでしょう。
不安の原因が分かれば、就職先を決める基準が「ノルマのないルート営業」というように絞れます。漠然とした不安をそのままにせず、細分化してみてください。
就活を続けるのも選択肢の一つ
どの会社にも入社への強い熱意をもてず就職先が決められない場合は、妥協して選ぶのではなく、就職活動を継続するのも選択肢の一つです。「仕事内容には興味があるけど、離職率の高さが気になる」「仕事内容や労働条件は問題ないけど、面接時の会社の雰囲気があまり良くなかった」などの懸念があるまま無理やり就職先を選ぶと、早期離職につながる恐れがあります。
「なぜ入社への熱意をもてなかったのか」を次の仕事選びに活かし、より自分の理想に合う就職先を見つけましょう。
就職先が決められないときの企業研究のやり方
就職先が決められないため企業研究を行う場合は、複数の方法でできるだけ多くの情報を集め、企業への理解を深めてみてください。また、業界や職種について詳しく調べるのも、応募先企業について深く理解するために役立ちます。
特に、社風・雰囲気はWebサイトや広報誌だけでは分からないため、会社説明会やインターンシップなどに参加して理解を深める必要があります。人事担当者や先輩社員と接するなかで、「自分に合いそう」と感じられるか、または「ちょっと合わないかも」と違和感を覚えるかは、実際に交流してみないと分からない部分です。こうした印象も、就職先を決めるうえでの大切な判断材料になります。
以下では、就職先が決められないときの企業研究のやり方を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
就職先が決められないときの企業研究のやり方
- 企業サイトの情報を確認する
- 会社説明会で直接話を聞く
- インターンシップに参加する
- OB・OG訪問で社員に質問する
- 競合他社と比べてみる
- 業界や職種の情報も調べる
企業サイトの情報を確認する
就職先が決められないときには、企業サイトをチェックしてみましょう。企業のWebサイトには、企業規模や事業内容といった基本的な情報のほか、理念や職場風土も紹介されている場合があります。
特に、採用ページには先輩社員の経歴や仕事の体験談なども紹介されていることがあるので、確認してみましょう。また、求めている人物像やキャリアパスなどが紹介されている場合には、しっかりと読み込んで自分の強みやキャリアプランとの一致度を確かめることが大切です。
会社説明会で直接話を聞く
就職先が決められないときは、会社説明会へ参加してみるのもおすすめです。会社説明会に参加すると、採用担当者や管理職クラスの人の話が直接聞ける可能性があります。直接話を聞くことは、社風を理解するのにも役立つでしょう。
Webサイトで紹介されている仕事内容についてさらに詳しく聞けたり、働き方や制度について教えてもらえたりもします。企業の担当者に直接質問する機会も得やすいので、不明点がある場合に説明会へ参加するのも一つの手です。
インターンシップに参加する
就職先を決めるために、インターンシップに参加するのも選択肢といえます。インターンシップに参加すると、就職後の自分を具体的にイメージできるのがメリットです。一定期間を職場で過ごすため、会社説明会よりもさらに理解が深まるでしょう。
また、実務を体験し、先輩社員とコミュニケーションを取ることで、企業とのマッチ度も明確になります。インターンシップはミスマッチ回避にも効果的です。
OB・OG訪問で社員に質問する
OB・OG訪問を行うことで、就職先を決められる可能性もあります。OB・OG訪問は、マンツーマンでじっくり話を聞けるのが魅力です。会社説明会では質問しにくい、企業の改善点や苦労話なども聞ける可能性があるでしょう。
また、先輩社員が就職先をどうやって決めたのかを聞いてみるのもおすすめ。今の会社に入社した決め手や重視したポイント、入社前に抱いていた不安や期待とのギャップなどを聞くことで、自分にとってその会社が合っているかどうかを判断する材料になります。
競合他社と比べてみる
競合他社との比較で、応募先企業の理解を深める方法もあります。同じ業界・職種でも企業によって特色があり、働き方や身につくスキルに違いがあるでしょう。複数の企業を比較検討すると、応募先企業が自分の求める条件を満たす会社なのか、あるいは他社のほうが合いそうなのかが判断できます。
業界や職種の情報も調べる
就職先を決めるうえでは、業界全体や職種についても調べる必要があります。幅広い情報を得ることで、より客観的な判断ができるようになるためです。
業界研究を行う
業界研究を行うと、業界の将来性や市場のトレンドが分かり、就職先を決めやすくなります。また、同じ業界内でも企業ごとに特徴があると分かり、就職先選びの基準も明確になるでしょう。
業界研究のやり方としては、まずはニュースや本で業界の全体像を把握します。さらに、専門誌や業界団体のWebサイトで知識を深めてみてください。
職種の特徴を理解する
就職先が決められないときは、職種から選ぶのも一つの方法です。世の中にはどのような職種があるのかを調べて、興味を感じた仕事を選んでみましょう。
たとえば、事務職といっても、経理事務や営業事務、医療事務などさまざまな種類があります。どの事務職に就きたいかを考えると、業界・業種が絞られていくでしょう。
就職先を決めるときの4つの注意点
就職先を決めるときは、焦りや周囲の意見、表面的なメリットなどに注意する必要があります。就職先を決められないと悩むあまり、労働条件をよく確認せずに決めたり、給料や企業規模だけで判断したりすると、入社してから後悔する可能性もあります。
以下で紹介する注意点を念頭に置き、納得感のある判断をすることが大切です。
就職先を決めるときの注意点
- 焦って判断しない
- 周囲の意見に流されない
- 労働条件だけで決めない
- 大企業や有名企業であることを判断軸にしない
- 採用担当者との相性だけで判断しない
1.焦って判断しない
就職先が決まらないからといって、焦って判断をするのは避けましょう。たとえば、労働条件をよく確認せずに応募したり、妥協して就職先を選んだりすると、就職後にミスマッチが生じる可能性があります。
ミスマッチが早期離職につながると、就職先が決まらない状態に逆戻りすることになるので注意が必要です。
2.周りの意見に左右されない
就職先が決まらないときは、周囲の意見に流され過ぎないことも大切です。他人軸で就職先を決めると判断に責任が伴わず、ちょっとしたことで挫折してしまう可能性があります。「親に言われたから」「アドバイザーに勧められたから」ではなく、「自分がどうしたいか」を大切にしてみてください。
3.労働条件だけで決めない
労働条件だけで仕事を選ぶのも避けるべきです。賃金や労働時間などの雇用条件のみを就職先選びの軸にすると、入社後に労働条件が変わった場合にモチベーションを維持できない可能性があります。労働条件だけでなく、事業内容や業務内容など、複数の点を考慮したうえで就職先を選んでみてください。
以下では、就職先選びで注意すべき労働条件についてまとめました。
福利厚生
福利厚生には「法定福利」と「法定外福利」があります。「法定福利」とは、雇用保険や厚生年金といった法律で決められた福利厚生のため、就職先による差はありません。
一方、「法定外福利」は企業が独自で決めるもので、住宅手当や短時間勤務制度などが該当します。
特に手当は毎月の収入に影響するため、就職先選びの条件として「法定外福利」を重視する人もいるでしょう。
「法定外福利」の内容は変わる可能性もあり、当てにしていた手当が廃止になることも考えられます。就職先を決められないで悩んでいるとしても、福利厚生は補足的な条件と考えましょう。
固定給や賞与
固定給や賞与は就職先を決めるうえで重要なポイントです。しかし、給与だけを基準にすると、仕事のやりがいや働き方においてミスマッチとなる恐れがあります。どれだけ収入が高くても、長時間労働や厳しいノルマが続くと仕事を続けるのが難しくなるでしょう。就職先を決める際は、仕事内容や企業の価値観を重視するのも忘れないことが大切です。
ただし、固定給が低過ぎるのも問題なので、業界の平均月給などから適切な範囲なのかを確認してみてください。
休日数や有給休暇取得率
就職先を決めるうえで、私生活との両立を重視する人もいるでしょう。年間休日数や有給休暇取得率をチェックするのは大切ですが、「休みが多い=働きやすい」とは限らないため注意が必要です。
たとえば、休日数は多いものの残業も多いという場合は、結果的にハードワークとなってしまいます。また、有給休暇取得率が高いのは短時間勤務やリモートワークが認められておらず、有給休暇を使うしかないという可能性もあるでしょう。
数字上の休日数や有給休暇取得率だけで判断せず、希望の働き方に照らし合わせて実態を把握することが重要です。
4.大企業や有名企業であることを判断軸にしない
就職先が決められないと悩んだときに、企業規模や知名度のみを判断軸にするのはやめましょう。大企業では大きな仕事を経験できる可能性があり、福利厚生の充実や給料の高さなど魅力が多い側面もあります。しかし、組織が大きいために意思決定が遅かったり、希望の仕事に就くのに数年かかったりするといったデメリットもあるでしょう。
新しいことに挑戦したい人や、自分の裁量で物事を決めたい人の場合は中小企業のほうが合っている可能性もあります。自分に合った就職先を決めるには、キャリアプランを叶えられる職場かどうかをしっかりと見極めることが大切です。
5.採用担当者との相性だけで判断しない
採用担当者と「話が合う」「感じが良い」というだけで、就職先を決めるのはやめましょう。採用担当者はあくまで企業の一員であり、実際に一緒に働く上司や同僚とは異なる場合があります。採用担当者との相性の良さは参考程度にとどめ、仕事内容や待遇、社風など総合的に判断することが大切です。
就職先が決められないときは支援機関の利用も検討しよう
就職先が決まらないときは、就職支援サービスの利用も検討してみてください。就職のプロであるキャリアアドバイザーに相談することで、自分の希望が明確になる場合もあります。
経験者も就職支援サービスを利用している
ハタラクティブの「若者しごと白書2025」によると、現在就職・転職中、もしくは過去に就職・転職活動をしたことがある人の、 企業探しの手段や利用サービスは以下のとおりです。
上位3位までを抜粋
※回答者数:フリーター567人、正社員519人
| | フリーター | 正社員 |
|---|
| 1位 | 求人サイトや就職・転職情報サイト(65.1%) | 求人サイトや就職・転職情報サイト(45.7%) |
|---|
| 2位 | ハローワーク(15.0%) | 就職・転職エージェント(20.0%) |
|---|
| 3位 | 就職・転職エージェント(8.3%) | ハローワーク(16.2%) |
|---|
フリーター、正社員ともに求人・転職サイトを利用して就職活動を行う人が多いようです。そのほか、ハローワークや就職・転職エージェントを利用して求職活動を行う人も多い傾向にあります。
キャリアアドバイザーの意見を参考にするのも手
就職先が決められないことを、ハローワークや就職・転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談するのもおすすめです。就職事情に詳しい専門家の意見を取り入れることで、マッチ度の高い就職先を選びやすくなるでしょう。
また、キャリアアドバイザーと一緒に自己分析やキャリアプランの作成をすることで、将来の目標や実現に向けてやるべきことが明確になる可能性もあります。
ただし、前述のとおり人の意見に流されると希望に合わない就職先を選んでしまう恐れもあるので、最終的な判断は自分で行うのが重要です。
【まとめ】自分に合った職場を選んで就職を成功させよう
就職先が決められない原因は、業界・職種についての知識不足や、自分の長所・短所が分析できていないことなど、人によってさまざまです。まずは、自分が迷っている原因を明らかにして、適切な対策をとりましょう。
また、ハローワークや就職エージェントのカウンセリングを利用するのもおすすめ。キャリアアドバイザーと面談するなかで、自分の希望が明確になる場合もあります。最終的に判断するのは自分ですが、悩んでいるときは一人で抱え込まないのも大切です。
「就職先が決まらないから焦っている」「自己分析や自分に合った求人の探し方が分からない」という方は、ハタラクティブにご相談ください。就職・転職エージェントのハタラクティブは、求職者とマンツーマンのカウンセリングを行ったうえで、一人ひとりの適性に合った求人を紹介しています。
また、応募先企業に合わせた選考対策も実施。就活中だけでなく、就職後の悩みも無料で相談できるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
就職先が決められないときに抱えやすい悩みに関するFAQ
以下では、「就職先が決められない人の特徴は?」「おすすめの支援サービスは?」など、就職先が決まらないときに抱きがちな疑問とその回答をQ&A形式で紹介します。
まずは自己分析をしっかりと行うことが大切です。新卒採用では、企業説明会や職場見学などのイベントが多く、インターンシップのチャンスも豊富にあります。こうした機会を積極的に活用しながら、自分の強みや価値観に合った業界・職種を見極めるのが大学生の就職先の決め方です。
就職先が決まらない主な理由は、「応募書類の内容に不備がある」「面接対策が不十分」「志望動機や自己PRが弱い」「就活の軸が定まっていない」などです。そのほか、ビジネスマナーに問題があったり、理想が高過ぎたりすることも就職先が決まらない要因として挙げられます。
どの企業を選ぶか迷っている場合は、内定保留という方法もあります。転職活動の場合、他社の結果を待ちたいときもあるでしょう。保留の理由と入社意思を伝えれば、採用担当者も承諾してくれる可能性があります。
就職先が決まらないときは、フリーターになるのも一つの選択肢です。フリーターは勤務時間や勤務日数を調整しやすく、プライベートの時間を充実させやすいのが特徴。その一方で、正社員より雇用や収入が不安定だったり、社会的信用が得にくかったりするといったデメリットがあるのも事実です。
就職先が決められない人におすすめの支援サービスは?
就職先が決められないときは、就職エージェントを活用するのがおすすめです。就職エージェントでは、キャリアアドバイザーが一人ひとりの適性に合う求人を紹介してくれたり、応募企業に合った選考対策をしてくれたりします。
就職・転職エージェントのハタラクティブは、自己分析から選考後のフォローまで丁寧にサポートしますので、ぜひ利用を検討してみてください。