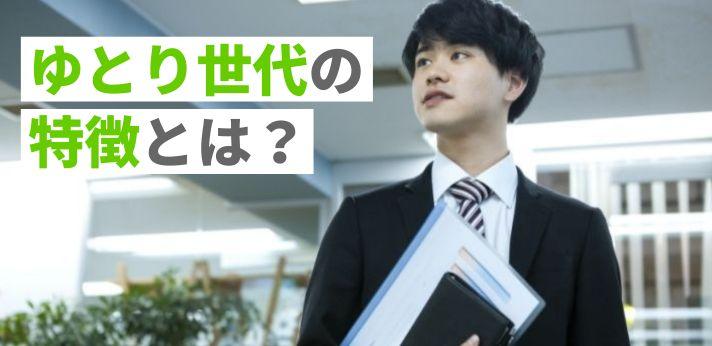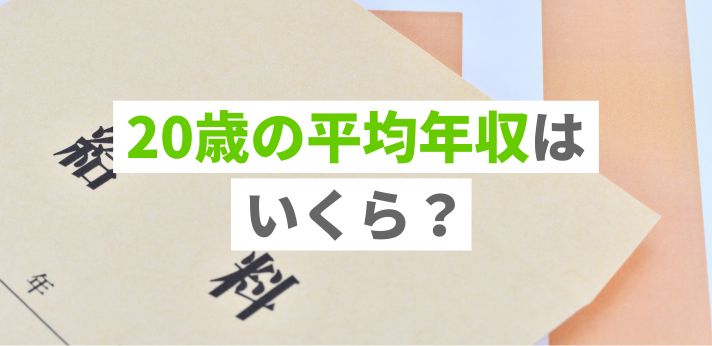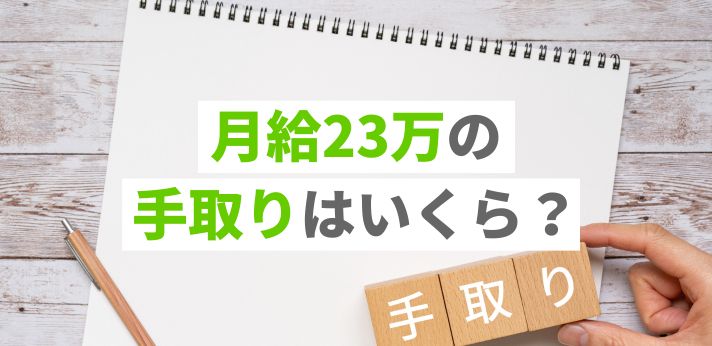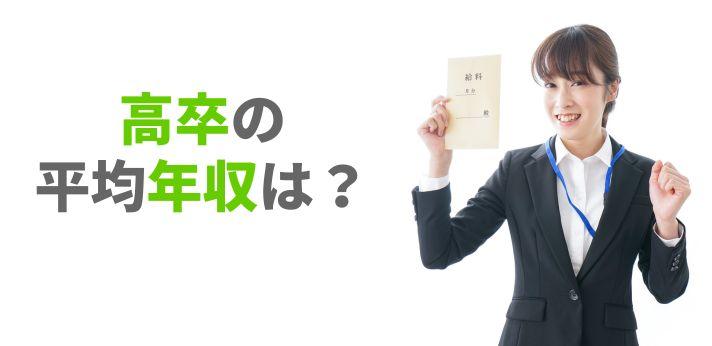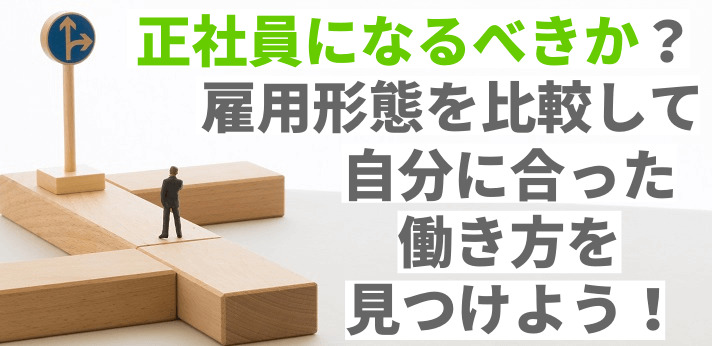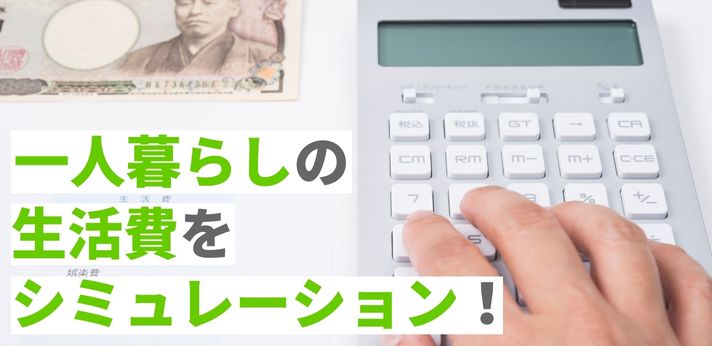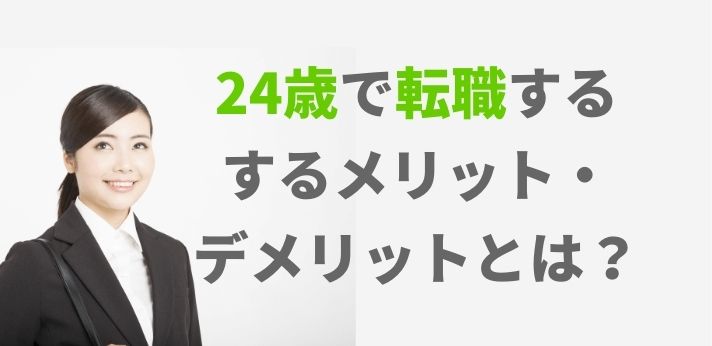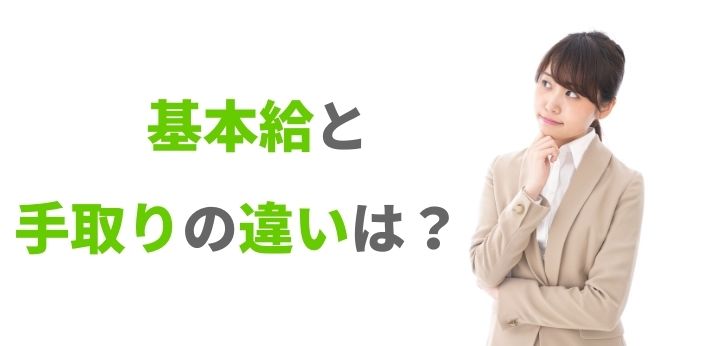24歳の平均年収は?ボーナス込みの額や収入アップを目指す方法を解説24歳の平均年収は?ボーナス込みの額や収入アップを目指す方法を解説
更新日
公開日
24歳を含む20代前半の平均年収はボーナス込みだと約277万円
「24歳の平均年収はいくらなんだろう」「自分の年収って低いのかな」と疑問をもつ方もいるでしょう。24歳を含む20代前半の平均年収はボーナス込みで約277万円です。同年代と比べて自分の年収が低いと焦りを感じる方もいるかもしれませんが、24歳であれば将来的に年収を上げられる可能性が十分にあるでしょう。
このコラムでは、24歳の平均年収について企業規模別や学歴別など幅広く解説します。収入アップを目指す方法も紹介しますので、ぜひご覧ください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
参照元
国税庁
厚生労働省
参照元
政府統計の総合窓口(e-Stat)
総務省統計局
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
24歳の平均年収はボーナス込みで約277万円
国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-」によれば、24歳を含む20代前半の平均年収はボーナス込みで約277万円です。性別で見ると、男性が約295万円、女性が約258万円となっています。
以下の表では、20代前半に加えて、24歳と年齢が近い20代後半や全年齢のデータを抜粋しました。自分の年収とそれぞれの平均年収を照らし合わせてみましょう。
| 年齢 | 男女計 | 男性 | 女性 |
|---|
| 20~24歳 | 約277万円 | 約295万円 | 約258万円 |
| 25~29歳 | 約407万円 | 約438万円 | 約370万円 |
| 全年齢 | 約478万円 | 約587万円 | 約333万円 |
上の表から分かるように、24歳を含む20代前半の平均年収は、20代後半よりも低い結果でした。全年齢と比較しても約201万円の差があります。
24歳は長いキャリア人生の下積み期間ともいえる年齢のため、それほど平均年収は高くないのが一般的です。20代後半・30代・40代と経験を積むことで、年収が上がっていく傾向にあるでしょう。
24歳の平均年収の中央値は約271万円
国税庁の前出資料のデータを使うと、24歳を含む20代前半の平均年収の中央値は約271万円になります。
中央値とは、数値を低い順に並べた際に真ん中にくる値のこと。平均値と異なり極端な数値の影響を受けにくいのが特徴です。中央値と平均値の差が大きいときは、データに極端な数値が含まれている可能性が考えられます。
ここでは、以下表の20~24歳における事業所規模ごとの平均年収で中央値を出しました。
| 事業所規模 | 20~24歳の平均年収(男女計)
※並びは上から低い順 |
|---|
| 5,000人以上 | 約240万円 |
| 10人以上 | 約247万円 |
| 5~9人 | 約258万円 |
| 1~4人 | 約259万円 |
| 30人以上 | 約282万円 |
| 1,000人以上 | 約290万円 |
| 100人以上 | 約306万円 |
| 500人以上 | 約308万円 |
データが偶数個ある場合の中央値は、数値を低い順に並べたときの真ん中の数値2つの平均です。上の表でいえば、約259万円と約282万円の平均である「約271万円」が中央値になります。
各事業所規模の平均年収を平均すると約274万円で、中央値の約271万円と大きな差はありません。冒頭で示した20~24歳(男女計・事業所規模合計)の約277万円と比べても同様のため、20代前半では年収差が開きにくいと推測できるでしょう。
24歳の月平均手取り額は約19万円
「手取り」とは、額面給与(給与の総支給額)から社会保険料や税金などが控除され、実際に手元に入ってくるお金です。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によれば、20~24歳の月の平均賃金は23万2,500円でした。給与の控除額は15~25%程度が一般的です。仮に23万2,500円から15%を差し引いた場合、月の平均手取り額は約19万円になります。
| 年齢 | 月の平均賃金 | 月の平均手取り額
※控除額15~25%で算出 |
|---|
| 20~24歳(男女計) | 23万2,500円 | 約19万7,625~17万4,375円 |
給与の手取り額は、総支給額の75~85%ほどが目安ともいわれています。そのため、額面給与に0.75~0.85を掛けても大まかな手取り額を出せるでしょう。
「自分の手取りで一人暮らしできる?」と心配な方は、後述の「24歳の手取り約19万円で考えられる1ヶ月の生活」で一般的な生活費の例をチェックしてみてください。また、以下のコラムでも、手取りの計算方法を詳しく解説しています。
平均年収は女性より男性のほうが高い傾向にある
既出の国税庁「
令和6年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-(p.170)」を見ると、24歳を含む20代前半の平均年収は男性が約295万円、女性が約258万円で、男性のほうが約37万円高くなっています。さらに20代後半では、男性が約438万円、女性が約370万円と差が開いてしまう結果でした。
男性と比べて女性の平均年収が低い傾向にある原因の一つには、結婚や出産などで離職する人の割合が多いことが挙げられます。離職後にキャリア構築が難しくなったり、パートやアルバイトで働いたりすると収入が上がりにくいでしょう。
しかし、厚生労働省の「男女間の賃金差異解消に向けて」にあるとおり、昨今は男女間の賃金差をなくす働きかけが活発化しています。女性の職域拡大や管理職割合の上昇などの傾向も見られるため、年収アップを目指せるチャンスは増えているようです。
以下のコラムでは、女性が高年収を目指しやすい職種や年収を上げる方法をまとめています。気になる方はぜひチェックしてみてください。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
大企業・中小企業別で見る24歳の平均年収
企業規模が異なると平均年収に差が生じる傾向にあります。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によれば、20~24歳における大企業・中企業・小企業それぞれの平均年収は以下のとおりです。
なお、ここでの平均年収は「月の平均賃金×12ヶ月」で算出し、ボーナスを含みません。
| 企業規模 | 男女計(20~24歳) | 男性(20~24歳) | 女性(20~24歳) |
|---|
大企業
(常用労働者1,000人以上) | 293万6,400円 | 293万8,800円 | 293万5,200円 |
中企業
(常用労働者100~999人) | 272万7,600円 | 276万1,200円 | 269万2,800円 |
小企業
(常用労働者10~99人) | 266万1,600円 | 269万7,600円 | 262万2,200円 |
上の表を見ると、「小企業→中企業→大企業」と企業規模が大きくなるにつれて平均年収が高くなっています。大企業と小企業間の平均年収の差は、男性で約24万円、女性で約31万円です。これは、おおよそ1ヶ月分の賃金に相当するので小さくない金額といえるでしょう。
「同年代の平均年収以上を稼ぎたい」「できるだけ年収を上げたい」と思う場合は、今よりも規模の大きい企業に転職するのも一つの手です。ただし、どのような労働環境が合っているかは人によって異なるため、以下のコラムで両者の特徴を把握しておきましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
高卒・大卒別で見る24歳の平均年収
24歳の平均年収は学歴によっても変わる可能性があるでしょう。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」を見ると、20~24歳における高卒と大卒の平均年収は以下のとおりです。
なお、ここでの平均年収は「月の平均賃金×12ヶ月」で算出し、ボーナスを含みません。
| 学歴 | 男女計(20~24歳) | 男性(20~24歳) | 女性(20~24歳) |
|---|
| 高卒 | 260万7,600円 | 267万9,600円 | 248万2,800円 |
| 大卒 | 300万9,600円 | 301万8,000円 | 300万2,400円 |
20~24歳の男女あわせた平均年収は、高卒者が約260万円、大卒者が約300万円で、その差は約40万円です。
給与水準が高い仕事では、高度な知識や技術が求められるのが一般的。大卒者は大学で専門的な知識や技能を学ぶため、高卒者よりも給与水準が高い仕事に就きやすい傾向にあります。そのぶん平均年収も高くなるでしょう。
高卒と大卒では、生涯賃金にも差が生じやすいようです。また、高卒の方で「今の年収に満足できない」「もっと高収入を得たい」と考える場合は、収入アップが期待できる職種に就いたり、資格を取得したりするのが有効です。
雇用形態別で見る24歳の平均年収
ここでは、雇用形態別に24歳の平均年収を見ていきましょう。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によると、20~24歳における正社員と正社員以外の平均年収は以下のとおりです。
なお、ここでの平均年収は「月の平均賃金×12ヶ月」で算出し、ボーナスを含みません。
| 雇用形態 | 男女計(20~24歳) | 男性(20~24歳) | 女性(20~24歳) |
|---|
| 正社員・正職員 | 284万4,000円 | 285万8,400円 | 282万8,400円 |
| 正社員・正職員以外 | 236万7,600円 | 238万8,000円 | 234万9,600円 |
20~24歳の男女あわせた正社員の平均年収が約284万円であるのに対し、正社員以外の平均年収は約236万円。両者の差は約48万円で、前述した企業規模別や学歴別の平均年収差よりも大きい結果でした。
正社員は無期雇用契約のため、企業側も長い付き合いを想定して待遇を手厚くする傾向にあります。パートやアルバイトなどの非正規社員と比べれば、正社員のほうが基本給の設定が高めだったり、昇給・昇進の機会が多かったりするのが一般的でしょう。
現在パートやアルバイトなどの非正規雇用で働いており、「今より平均年収を上げたい」と考えている方は正社員就職するのも一つの選択肢です。
また、就職を検討している24歳の方には、若年層向けの就職・転職エージェントの活用がおすすめです。若年層向けのエージェントは「未経験OK・歓迎」の求人が充実しているのがメリット。「仕事の経験やスキルに自信がない」「就職活動のやり方が分からない」などの悩みも相談できるので、安心して正社員を目指せるでしょう。
24歳の手取り約19万円で考えられる1ヶ月の生活
24歳は大卒新卒者なら社会人2年目、高卒新卒者なら社会人6年目になる年齢です。一定の社会人経験を積み仕事にも慣れてきて、「そろそろ一人暮らししたいな」と考える方もいるのではないでしょうか。場当たり的に一人暮らしを始めると生活に困るリスクがあるため、事前に自分の収入をもとにした生活のシミュレーションを行っておくと安心です。
ここでは、前述した24歳の月平均手取り額の約19万円を基準に、生活費の大まかな目安を解説します。「今の年収で一人暮らしできる?」「もっと収入を増やしたほうがいい?」と悩んでいる場合は、自身の将来プランを考える際の参考にしてみてください。
※以下で紹介する内容はあくまでも一例です。人や状況によって内容は変わるため、すべての方に当てはまるわけではありません。
家賃の相場は手取りの約30%
家賃の相場は、手取りの約30%が目安といわれています。24歳の平均手取り額19万円をもとに計算すると、家賃の目安は5万7,000円です。
一般的な6畳ワンルームを5万7,000円で探す場合、都心だと見つけるのに苦労することも。物件探しに難航したときは、郊外や地方などにもエリアを広げると、希望の物件に出会う可能性が高まるでしょう。また、周辺環境や室内設備などの条件を緩めるのもおすすめです。家賃の目安額を上げる選択肢もありますが、そのぶん別で節約が必要でしょう。
家賃は固定費のため、収入に占める割合が高過ぎると家計を圧迫しかねません。ただし、住居に難点が多ければ生活の満足度が下がる場合も。物件選びは自分の中での妥協点を探りながら、納得いくまで検討することが大切です。
食費の目安は手取りの約20%
食費は手取りの約20%に抑えるのが目安とされているため、24歳の平均手取りを19万円で考えると3万8,000円になります。
政府統計総合窓口e-Statで、総務省統計局の「家計調査 家計収支編/単身世帯/詳細結果表/年次(男女、年齢階級別)」を見ると、34歳以下の単身・勤労者(男女計)が食費にかけた月平均額は4万305円。食費の目安額3万8,000円と大きな差はないものの2,000円ほど多いことから、食費を目安額に収めないと生活が厳しくなる恐れがあるでしょう。
先の家計調査データの対象には、24歳より収入が高い傾向にある20代後半や30代前半が含まれているため、24歳に限った場合は食費額が下がる可能性も考えられます。また、実際に生活を始めれば外食や昨今の物価高などにより想定以上に食費が掛かることも。普段から月の収支を把握しておき、必要があれば節約も検討するのが望ましいでしょう。
水道光熱費・通信費の目安は手取りの約4~5%
水道光熱費と通信費の目安は、それぞれ手取りの約4~5%が一般的とされています。24歳の平均手取り19万円をもとに計算した場合、両者とも7,600~9,500円程度が目安になるでしょう。
政府統計総合窓口e-Statの既出資料によれば、34歳以下の単身・勤労者(男女計)における水道光熱費の平均額は9,005円、通信費の平均額は5,730円でした。水道光熱費と通信費の目安額を5%の9,500円で考えれば、どちらも収まる想定です。しかし、目安額を4%の7,600円で見たときは水道光熱費がオーバーしてしまうため、場合によっては一定の節約が必要になる可能性があります。
水道光熱費で節約したい方は、自身の生活スタイルに合ったプランを検討したり、日々の生活で節水・節電を心掛けたりするなど工夫しましょう。通信費を減らしたい場合も同様、自分に合った料金プランやオプションの見直しがおすすめ。格安SIMを利用するのも一つの手です。
貯金する場合は手取りの約10~20%
貯金をする場合は、手取りの約10~20%が理想とされているようです。24歳の平均手取りを19万円と仮定すれば、約1万9,000~3万8,000円を貯金に回す計算になります。
日ごろから貯金をしておくと緊急時に困らなかったり、結婚や出産などのライフイベントに対応しやすかったりするのがメリットです。ただし、手取りを毎月住居費と生活費だけで使い切ってしまえば、貯金ができません。一人暮らしをしながら貯金もしていきたい場合は、自身の将来プランを明確にし、それに合わせた貯金の計画を立てるのがポイントです。
まずは結婚資産や老後資金など「何にどれくらいのお金が必要か」を考え、貯金の目的や目標金額を定めましょう。そのうえで、いつまでにいくら貯めたいか、目標達成に必要な月々の貯金額はいくらかを具体化してみてください。
貯金方法には、銀行の積立預金や先取り貯金などがあります。また、NISAやiDeCoを活用して資産形成を目指すのも一つの手です。もし貯金に回すお金がない・十分でない場合は、生活費の支出を見直しましょう。
配偶者や子どもがいると生活水準を維持するのが難しいことも
配偶者や子どもがいると、月の平均手取り19万円では生活水準の維持が難しい場合があるでしょう。総務省統計局の「
家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要(p.15)」によれば、総世帯のうち二人以上の世帯は、単身世帯よりも食費や水道光熱費が高くなっています。月の平均消費支出額も二人以上の世帯は30万243円で、単身世帯の16万9,547円と比べて13万696円多い結果でした。
一緒に暮らす家族が増えるぶん、食費や水道光熱費も上がるもの。子どもがいれば養育費や教育費も掛かります。誰かと生計をともにしたい場合は、世帯年収を増やすことも検討する必要があるでしょう。結婚前に考えておくべきお金については、以下のコラムでも詳しく解説しています。
24歳で平均年収アップを目指す方法
24歳で平均年収を上げるには、手当の対象資格を取得したり、今の職場で昇給・昇進を目指したりする方法があります。状況によっては、今より高い給与がもらえる職場に転職するのも一つの選択肢といえるでしょう。
ここでは、24歳で平均年収アップを目指す方法を紹介しますので、「平均年収を上げたい」と思っている方は参考にしてみてください。
24歳で平均年収アップを目指す方法
- 業務に活かせる資格を取得して手当をもらう
- 今の仕事で成果をあげて昇給・昇進する
- より給与が高い職場に転職する
業務に活かせる資格を取得して手当をもらう
24歳で平均年収を上げたいときは、業務に活かせる資格の取得がおすすめです。手当が付く資格だと、月に数千円~数万円ほど手取りが上がる可能性があるでしょう。また、資格により専門的な職種や役職に就けば、基本給アップも見込めます。
資格の取得を目指す場合は、今の仕事でキャリアアップしてスペシャリストになりたいのか、全く別の業界・職種に挑戦したいのかなどを考えましょう。せっかく資格を取っても、業務に活かせないと年収アップにつながりにくいことも。自分のキャリアビジョンを踏まえたうえで、仕事に関連した資格の取得を検討することが重要です。
企業の中には資格取得支援制度を設けて、社員のスキルアップやキャリアアップをサポートしているところもあります。資格取得にともなう費用の援助が受けられるため、勤め先や転職志望先の制度を確認してみましょう。
今の仕事で成果をあげて昇給・昇進する
今の仕事で成果をあげて昇給・昇進することも、平均年収アップを目指す方法の一つです。先述したように、新卒就職した場合の24歳は一定の社会人経験を積んで仕事にも慣れてくる年齢。上司や先輩からステップアップを求められやすい時期ともいえます。
入社時と比べて仕事の裁量が徐々に増えているのであれば、積極的に仕事を引き受けてみましょう。やや難易度が高い仕事にも臆せず挑み、上司や周囲に意欲をアピールするのがおすすめです。任された仕事を責任感とスピード感をもって進め、関係スタッフとの連携も忘れなければ、周囲からの評価が上がる可能性があるでしょう。
ただし、会社によって評価基準やキャリアパス制度は異なります。アピールの方向性が会社の求めていることから逸れていると、「努力を全然認めてもらえない」「成果が給与に反映されない」などの状況に陥る場合も。昇給や昇進を目指すのであれば、勤め先の評価制度やキャリアパスをよく把握しておくことが大切です
より給与が高い職場に転職する
今の会社で平均年収を上げるのが難しいときは、より給与が高い職場に転職するのも一つの選択肢といえます。ハタラクティブの独自調査「若者しごと白書2025(p.47)」でも、正社員が転職したい理由の1位は「今より多くの収入を得たいため(63.4%)」でした。
20代前半はポテンシャル採用されやすく、求人の選択肢も多い傾向。24歳であれば希望の転職を実現しやすい可能性があるため、平均年収アップを目指し転職するなら早めの行動が肝心です。ただし、転職で年収が下がるケースもあるので注意しましょう。
空いた時間に副業をするのも手
前述した資格取得や昇進を目指す場合、目標達成には一定の時間が掛かるでしょう。すぐにでも平均年収を上げたいときは、空いた時間に副業をするのも手です。たとえば、単発のアルバイトをする、クラウドソーシングで委託業務を引き受けるなどの方法があります。
ただし、副業を禁止している会社もあるため、勤め先の就業規則は事前に確認しておきましょう。
24歳で年収を上げるために転職するメリット
24歳で年収を上げるために転職するときは、ポテンシャル採用が見込めたり求人の選択肢が多かったりするのがメリットです。また、若年層を対象とした就職支援サービスが使えるので、より自分に合ったサポートを受けながら転職を目指せるでしょう。
24歳で年収を上げるために転職するメリット
- 20代はポテンシャルを重視してもらいやすい
- 応募できる求人数が多い傾向にある
- 若年層向けの就職支援サービスを利用できる
20代はポテンシャルを重視してもらいやすい
20代は年齢が若く、企業にとって今後の成長や活躍を期待できる人材のため、転職活動でポテンシャルを重視してもらいやすいのがメリット。仕事の経験やスキルが十分でなくても、将来性を買われれば採用される可能性があるでしょう。
24歳の方は「経験が浅いから」「スキルが足りないから」と思わず、興味のある業界・職種があれば積極的に挑戦してみるのがおすすめです。転職活動では自身の意欲や「強み」といえる長所をしっかりとアピールし、採用担当者の関心を高めましょう。
応募できる求人数が多い傾向にある
24歳で平均年収アップを目指して転職するメリットには、応募できる求人数が多い傾向にあることも挙げられます。
たとえば、大卒新卒で就職した24歳の場合、「第二新卒枠」での転職が可能です。第二新卒とは、一般的に新卒入社後3年程度で転職する人のこと。転職市場で第二新卒は社会人経験をもつ若い働き手として、企業からの需要が見込める存在といえます。
また、前述したとおり、20代はポテンシャル採用されやすく、30代や40代と比べて経験が浅い状態から挑戦できる求人が多いでしょう。そのため、転職先の選択肢の幅が広いのが利点です。
若年層向けの就職支援サービスを利用できる
若年層向けの就職支援サービスを利用できることも、24歳で転職するメリットの一つです。若年層向けの就職支援サービスでは、若い世代が就職・転職で抱えやすい悩みを解消するためのサポート体制が整っている傾向にあります。初めて転職活動する場合も相談しやすかったり、要望にマッチした求人を見つけやすかったりするでしょう。
若年層向けの主な就職支援サービスは、「わかものハローワーク」「ジョブカフェ」「就職・転職エージェント」など。それぞれのサービスについて以下で詳しく解説しますので、自分に合ったサービスを探す際の参考にしてみてください。
わかものハローワーク
わかものハローワークは、おおむね35歳未満の正社員を目指す人を対象とした国の就職支援サービスのため、24歳の方も利用可能です。厚生労働省の「わかものハローワーク」によると、主に以下のようなサービスが受けられます。
- ・担当者制による職業相談
- ・就職活動に役立つセミナー
- ・職業訓練(ハロートレーニング)
- ・応募書類の作成支援や面接対策
- ・全国の求人情報の検索や閲覧
わかものハローワークでは、「就職支援ナビゲーター」にマンツーマンでサポートしてもらえるのが特徴。また、就職・転職活動に役立つ各種セミナーが充実していたり、ハローワークが有する全国の求人から仕事を探せたりします。無料で利用できるため、24歳で転職を検討している場合は一度利用してみるのがおすすめです。
ジョブカフェ
ジョブカフェとは、都道府県主体の若年層向け就職支援サービスで、「若年者のためのワンストップサービスセンター」が正式名称です。厚生労働省の「ジョブカフェにおける支援」によると、主に以下のようなサービスが受けられます。
- ・就職セミナーや職場体験
- ・企業説明会
- ・職業相談や職業紹介
- ・キャリアカウンセリング
ジョブカフェは、各地域の特色を生かした就職セミナーや職場体験、地元企業の説明会など地域に根差したサービスが魅力です。現在、香川県以外の46都道府県にあり、ハローワークに併設していることも。その名のとおり、カフェ気分で立ち寄れる施設を目指しているようです。「地元の仕事に就いて平均年収を上げたい」「気軽に就活相談できる場所が欲しい」と考える24歳の方に向いているでしょう。
就職・転職エージェント
就職・転職エージェントとは、民間企業が提供する就職支援サービスです。エージェントでは、プロのキャリアアドバイザーから就職・転職活動を包括的にサポートしてもらえます。「どんな仕事なら平均年収を上げられるのか知りたい」「自分に向いている仕事が分からない」など、就職・転職に関するさまざまな相談が可能です。
以下では、一般的にエージェントで受けられる主なサービスを挙げました。
- ・キャリアアドバイザーによる個別カウンセリング
- ・自分に合った求人や非公開求人の紹介
- ・面接対策や履歴書添削
- ・企業とのやり取り代行
- ・内定後のフォロー
エージェントと一口にいっても、サービスの内容や対象者は異なるため、自分の状況やニーズに合ったエージェントを選ぶのがポイントです。24歳の方であれば、若年層向けのエージェントがおすすめ。また、幅広い求人を探したいなら業界・職種を問わない総合型エージェント、特定の業界・職種を志望しているなら該当分野に強い特化型エージェントを選ぶ方法もあります。
「年収を上げるために転職すべきか迷っている」「転職したいけど自分に合う仕事が分からない」と悩んでいる方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにぜひご相談ください。
ハタラクティブは、20代を中心とした就職・転職支援サービスです。若年層の転職に強く、正社員経験がない・浅い方向けの求人も多く取り扱っています。自分のアピールポイントに悩む場合も、経験豊富なキャリアアドバイザーがマンツーマンで付き、強みを引き出す自己分析を一緒に行うのでご安心ください。また、企業とのやり取りは担当アドバイザーが代行いたします。サービスはすべて無料のため、転職を検討している方はお気軽にご利用ください。
24歳の年収に関するよくある質問
ここでは、24歳の年収に関してよくある質問にQ&A形式で回答していきます。自身の年収に不安や疑問をもっている方は参考にしてみてください。
国税庁の調査データから計算すると、24歳女性の平均年収の手取り額は約193~219万円です。
国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-(p.170)」によれば、20~24歳女性の平均年収はボーナス込みで約257万9,000円。一般的に手取り額の目安は額面給与の約75~85%なので、額面給与に0.75~0.85を掛けると約193~219万円になります。
額面給与から差し引かれる項目や手取りの計算方法については、以下のコラムをご参照ください。
参照元
国税庁
令和6年分 民間給与実態統計調査
厚生労働省の調査データをもとに計算した場合、東京都における24歳の平均年収はボーナス抜きなら約331万円、ボーナス込みなら約367万円でした。
政府統計総合窓口e-Statで、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者/都道府県別(東京・神奈川)」を見ると、東京都(産業計・企業規模計・男女計)の20~24歳の平均賃金は月27万6,100円。これを12ヶ月分で単純計算すれば、ボーナス抜きの平均年収は約331万3,200円になります。
同資料の「年間賞与その他特別給与額」は36万1,800円のため、この金額を上記約331万3,200円に足すと、東京都における24歳のボーナスを含めた平均年収は約367万5,000円です。
参照元
政府統計の総合窓口(e-Stat)
「賃金構造基本統計調査(令和6年賃金構造基本統計調査/都道府県別)」(厚生労働省)
職種や働き方によっては、24歳で年収400万円以上を目指せるでしょう。
たとえば、「給与水準が高い業界に就職・転職する」「成果主義や実力主義の仕事に就く」「副業をする」などの方法が考えられます。
年収を上げるために転職を検討している場合は、就職・転職エージェントの利用がおすすめです。ハタラクティブでは、プロのキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングのもと、一人ひとりに合った求人を紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。